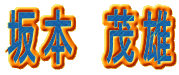




![]()
![]()
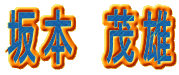




ようこそご訪問下さいました
2025年12月20日更新
|
| プロフィール | 議事録 | 県政かわら版バックナンバー |
![]()
| 月 | 日 | 曜 | 予 定 | 25年9月定例会質疑 県政かわら版77号 |
| 12 | 20 | 土 | 神戸大学オープンゼミナール | |
| 下知地区減災連絡会講演会 | ||||
| 22 | 月 | 県立施設運営活性化懇談会 | ||
| 全国防災関係人口ミートアップ | ||||
| 23 | 火 | JICA研修打合せ | ||
| 部落解放同盟高知市協23デー | ||||
| 24 | 水 | 県立施設運営活性化懇談会 | ||
| 高知市上下水道局打合せ | ||||
| 25 | 木 | 広域避難所運営マニュアル検討会 | ||
![]()
坂本茂雄のブログはこちらから
![]() バックナンバー 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
バックナンバー 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
| 12月20日「議会で、衆議院議員定数削減法案に反対する意見書が僅差で否決」 |
 県議会12月定例会は最終日の19日、国の総合経済対策を活用した防災・減災対策を盛り込んだ320億6800万円の一般会計補正予算案など、執行部提出の38議案を全会一致または賛成多数で可決、承認、同意し、閉会しました。
県議会12月定例会は最終日の19日、国の総合経済対策を活用した防災・減災対策を盛り込んだ320億6800万円の一般会計補正予算案など、執行部提出の38議案を全会一致または賛成多数で可決、承認、同意し、閉会しました。
中でも、国会で自維政権によって強引・拙速な議論が進めめられ、臨時国会では成立しなかった衆議院議員定数削減法案に反対する「地方の民意切り捨てにつながる衆議院議員定数削減に反対する意見書」を共産党(6人)と県民の会(3人)、公明党(3人)、自由の風(1人)で提出したものの、残念ながら賛成少数で否決されました。
衆院定数削減法案は、現行の465から1割を目標に45以上減らすと規定し、与野党協議会で1年以内に結論が出なければ小選挙区25、比例代表20を自動的に削るとの内容を盛り込んでいることから、法案について意見書では、「与野党の合意形成を軽視した強硬な進め方で、このまま成立すれば民主主義を毀損する」とし、国に削減を行わないよう求めました。
賛成討論を行った西森雅和議員(公明)は、「有無を言わさず削減する法案は議論の否定だ」と指摘しました。
採決では、提出会派に加えて一燈立志の会(3人)も加わり賛成16になったが、自民(18人、議長除く)が反対し、否決されました。
自民県議団は反対討論を行いませんでしたので、なぜ反対するのかという意思は明らかにされませんでしたが、マスコミの取材に対して、弘田兼一会長は「法案を提出した党として意見書には賛成しかねるが、地方の声を大切にすべきという思いや懸念は理解できる。丁寧に議論を尽くすよう党本部に伝える」とコメントされています。
引き続き通常国会での成立を図ってくるだろうが、今回の採決で、自民党以外の会派が一致して闘えたことを踏まえて、県民との共闘で何としても阻止していくことが求められています。
| 12月19日「委員がちゃぶ台返ししたくなる県体育館整備案」 |
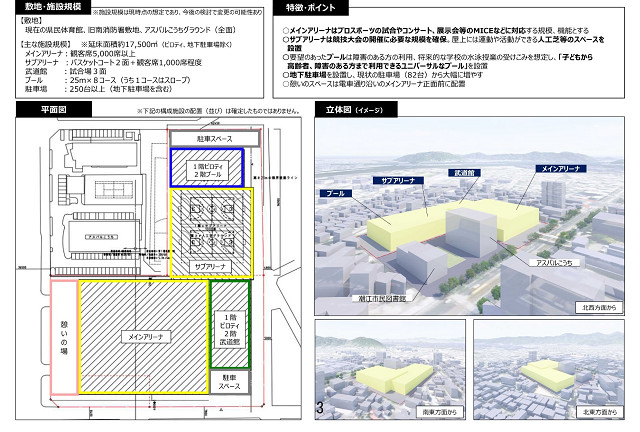
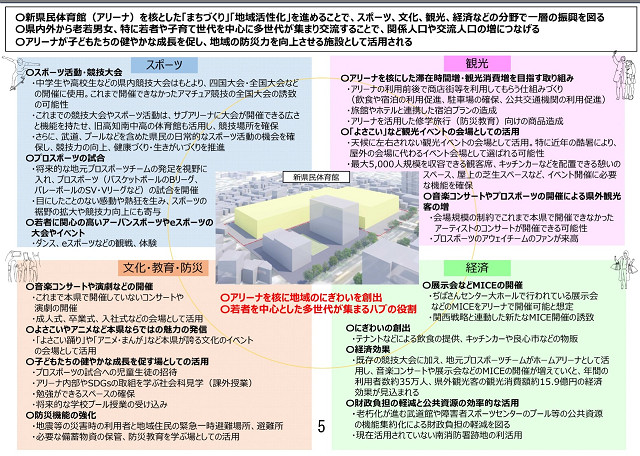
本日、閉会を迎える12月定例会で、本会議でも産業振興土木委員会でも多くの質疑のあった県民体育館の現地建て替えに伴うアリーナ新設について、昨日は第4回新県民体育館整備等基本計画検討会が開催され、傍聴してきました。
検討会では、冒頭に前田委員長(高知工科大講師)が「県民アンケートも終わっていない状況で、県市トップの判断で決まるのは拙速。意見が反映されないなら、検討会の意義は何なのか」と経過への強い疑問が提起され、異例の開会となりました。
有識者委員から「拙速」「情報不足」「インクルーシブプールへの懸念」「狭い場所にあれもこれも機能を詰め込んで将来機能不全を起こすのではないか」「最初プールや武道館はなかった」「敷地の狭さ、アスパルのグランド問題、プール問題などが議論を停滞させてきた。じばさんセンター跡地での議論も必要か。」「浸水で地下駐が機能するか」「設計ありきて検討するのは順番が違う」といった異論が出され、予定した配置の決定には至りませんでした。
前田委員長から「丁寧に議論すべき。今回の意見を踏まえ、これまでと比較できるような案を次回示して欲しい」とまとめたことに対して、小西観光振興スポーツ部長は「次回までに今回の意見をどう反映したか報告したい」と言いながらも「県が責任もって県民・議会に説明していく」と述べ、最後は県が判断することだと言わんばかりの締めに、会長はじめ検討委員の皆さんは違和感を覚えたのではないでしょうか。
また、事業費に関しては、ランニングコストも含む概算事業費が30年間で整備費約210億円に、維持費約85億円、改修費約94億円を加えて約390億円になると説明したが、試算想定を疑問視する声も出されました。
いずれにしても、拙速な議論による弊害がここかしこに噴出する新体育館整備議論は一旦立ち止まった方が良いのではないでしょうか。
| 12月18日「大規模火災に備える」 |

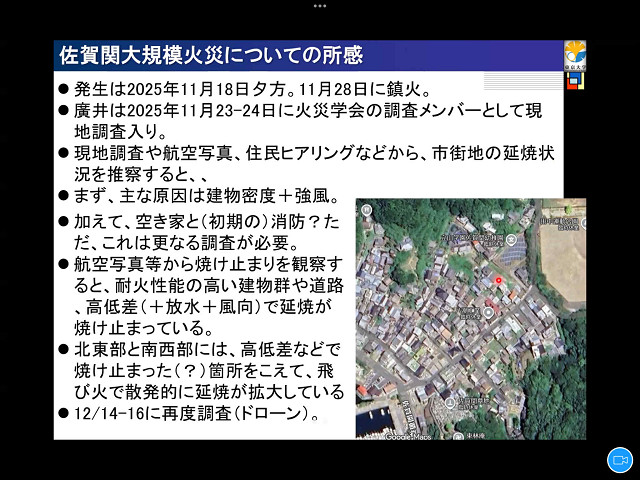 今朝の朝日新聞2面「時時刻刻」で、大分市佐賀関の大規模火災についての記事が特集されていました。
今朝の朝日新聞2面「時時刻刻」で、大分市佐賀関の大規模火災についての記事が特集されていました。
木造家屋がひしめく狭い路地の奥で発生し、強風で広範囲に飛び火し勢いを増す炎を、消防はいかに抑え込もうとしたのか。被災建物の4割を占めた空き家の火災への備えも課題として浮かんだことなどが、記されています。
大分市消防局幹部によると、当時消火活動にあたった隊員らは「火炎が迫ってきて、身の危険を感じた」「視界が悪く退路も絶たれる可能性があった」などと話していたと言い、消火活動にあたる隊員が、今回の火災では火勢で後退する際にホースを現場に置いて退避してしまう人もいたというほどで、「経験したことのない火災。訓練通りの行動ができないほど、難しい現場だったと思う」と振り返られていたということです。
この記事では、東京大学先端科学技術研究センターの廣井悠教授(都市防災)による「瓦や窓が破損した建物は、飛び火のリスクも高まる。住人不在だと消火も遅れる。空き家の火災対策としては、周辺でも鳴動する火災報知機の設置、家屋に火が回る起点となる軒先や窓に、火や熱に強い素材を使う「防火改修」などが有効だ」とのコメントを紹介されています。
丁度15日の「全国防災関係人口ミートアップ」で、廣井先生から「広域火災とその対策~近年に発生した3件の大規模火災について」話題提供頂いていたばかりですので、コメントの背景とかもよく分かります。
その際に廣井先生も主な原因は、「建物密度+強風」加えて「空き家と初期消火」と述べられていましたが、室崎益輝先生(神戸大名誉教授(防災計画))も、記事の中で「佐賀関地域の『木造密集』『道路の狭さ』『強風』といった点は全国各地が抱える課題でもある」とした上で、「延焼リスクをもっと早く判断して応援部隊を要請できるような体制の構築などを検討することも求められるのではないか。今回の火災を『特異な事例』として片付けるのではなく、見えてきた課題を教訓として生かすべきだ」とのコメントも紹介されていました。
そんな中でも、私たちが自助・共助の中で「飛び火の監視、発煙箇所等の発見、早期通報、自主的な予防散水」など、できることもあるということを学んでいくことの必要性も廣井先生から求められることとして提起されました。
| 12月16日「県民・市町村には『はったり』かまさぬよう」 |
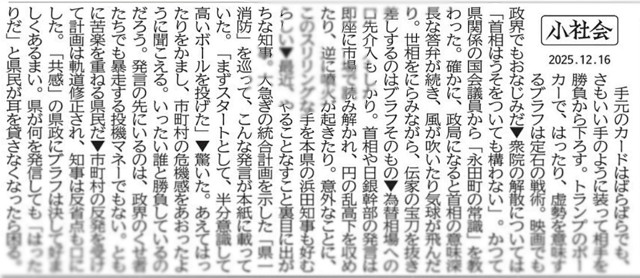 今朝の高知新聞の「小社会」は今の浜田県政を「はったり」をかますようなやり方との厳しい視点で捉えていました。
今朝の高知新聞の「小社会」は今の浜田県政を「はったり」をかますようなやり方との厳しい視点で捉えていました。
12月7日付け「【賢い縮小】「県一消防」戸惑う市町村―問われる「共感」~浜田知事 2期目折り返し(3)」の記事にあった「県一消防」を巡っての記者とのやりとりで、「まずスタートとして、半分意識して高いボールを投げた」と明かしたことについて「小社会」では次のように書かれていました。
「驚いた。あえてはったりをかまし、市町村の危機感をあおったように聞こえる。いったい誰と勝負しているのだろう。発言の先にいるのは、政界のくせ者たちでも暴走する投機マネーでもない。ともに苦楽を重ねる県民だ。」とありました。
「はったりをかます」という言葉は、大げさに言って相手を混乱させたり、相手に何かをし掛けたり、相手に向かって強い衝撃を与える時に使うと言われるが、そんなことで意識して高めのボールを投げられたりしていたら、県民や消防職員や市町村長はたまったものではありません。
そして、「市町村の反発を受けて計画は軌道修正され、知事は反省点も口にした。」とあるが、その過程でどれだけの人々が苦悩したのか知事は考えているのでしょうか。
これは、最近の県有施設の指定管理者公募問題や新県立体育館建設案などでも同様に「かます」手法が取り入れられているのではないかと思えてなりません。
「小社会」では最後に「「共感」の県政にブラフは決して好ましくあるまい。県が何を発信しても「はったりだ」と県民が耳を貸さなくなったら困る。」と結ばれていますが、県民が耳を貸さないと同時に高知県政に対して「疑心暗鬼」になることを恐れています。
| 12月14日「広域避難者支援から広域避難を考える」 |




昨日は、「第8回被災者支援ソーシャルワーク研修 @高知市下知地区」が下知コミュニティセンターで開催されました。
今回は、「広域避難者支援」がテーマでしたので、高知市山中防災政策課長から「広域避難支援をはじめとした災害対策」、私からは下知地区減災連絡会の活動と下知地区防災計画・事前復興・広域避難との関係、そして西村二葉町防災会長からは二葉町防災会の活動となぜ広域避難と訓練に取り組んできたのかなどについて報告させて頂きました。
そして、「東日本大震災における広域避難者支援について」主催者の一般社団法人ほっと岡山のはっとりさんからお話し頂きました。
「避難者一人ひとりの生活再建・自己の回復」「苦悩・葛藤に寄り添うこと」「県外避難者への理解が得にくいこと」「さまざまな避難の葛藤、語りにくい願い」「広域避難者にまとわりつく問題が構造的であること」「「孤立」の背景にある「関係性」「将来性」「自律性」3つの喪失」など避難者の方々を取り巻くさまざまな悩みや課題があることについて、お話し頂きました。
被災者支援を長く続けられてきた中で、避難者一人ひとりの多様な悩みや課題と寄り添われてきたからこその言葉が刺さりました。
私たちも、南海トラフ地震発災時には広域避難することになるであろうことを想定した事前の取り組みの中でも、広域避難を求める多様な捉え方を認めた取り組みを積み重ねる必要があることを考えさせられる貴重な時間となりました。
会場参加、オンライン参加あわせて40名近い参加者の皆さん長時間ありがとうございました。
| 12月13日「新県民体育館のあり方などは拙速とならないよう」 |


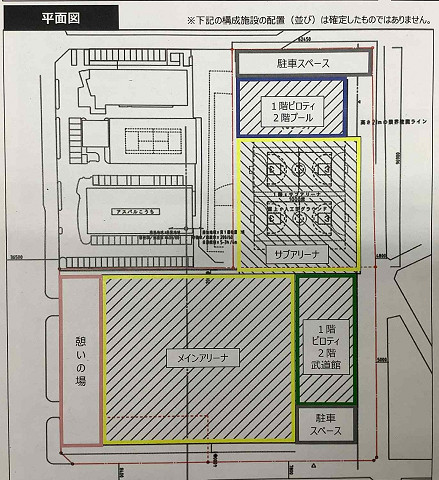
本会議の質問戦も昨日で終り、15日からは常任委員会での審査が始まります。
本会議では、県内15消防本部を統合して「県一消防」を目指す消防広域化問題や特別職として「参与(官民連携推進監)」を設置したこと、新しい県民体育館の整備の課題などをはじめ多岐にわたる質疑が行われました。
私の所属する産業振興土木委員会では、報告事項ではありますが新県民体育館のあり方について議論がされることと思います。
本会議の質問戦では、「解体や駐車場整備などを含め210億円余り」と見込んでおり、財源は、総事業費の半分程度を国が支援する地方債の活用を検討することなどが明らかにされました。
また、整備案では、5千人規模のメインアリーナやサブアリーナ、武道館、屋内プールなどを配する内容となっています。
それらの特徴とポイントとしては、メンアリーナは、プロスポーツの試合やコンサート、展示会などのMICEなどに対応する規模、機能とすること。
サブアリーナは、競技大会の開催に必要な規模を確保し、屋上には運動や活動ができる人工芝などのスペースを設置する。
要望のあったプールは障害のある方の利用、将来的な学校の水泳授業の受け込みを想定し、「子どもから、高齢者、障害のある方まで利用できるユニバーサルなプールを設置」する。
地下駐車場を設置し、現状の駐車場82台から250台以上へと大幅に増やす。
憩いのスペースは電車通り沿いのメインアリーナ正面前に配置することなどがあげられています。
このことによって、知事は、新施設でのプロスポーツの試合やコンサート、展示会の開催などを例に「とりわけ若者や子育て世代から愛され、誇りに思ってもらえる象徴的な施設にしたい」と強調しています。
また、18日に開く有識者検討会で、収支見通しや経済波及効果の試算を提示。利用団体などの意見を聞き、年度内に基本計画を取りまとめる方針も示されていますが、一気に取りまとめるのは拙速ではないかとの意見もあり、産業振興土木委員会でも報告に対する質疑を重ねて置きたいと思います。
| 12月11日「高知市下知からの『被災者支援ソーシャルワーク研修』」 |
 8日の青森県東方沖を震源とする地震では、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測され、被害の全容も明らかになりつつありますが、寒さの中での避難生活で二次被害が出ないことを願うばかりです。
8日の青森県東方沖を震源とする地震では、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測され、被害の全容も明らかになりつつありますが、寒さの中での避難生活で二次被害が出ないことを願うばかりです。
近年、災害の頻発化・激甚化により各地で甚大な被害が発生しています。
災害により住み慣れた土地を離れ避難する「広域避難」によって、さまざまな問題が引き起こされます。
そのような中で、「被災者支援ソーシャルワーク研修」を主催される一般社団法人ほっと岡山さんが、避難者支援を強化するための体制構築を目指し、平時も含めだれ一人取り残さない、互いに助け合う災害文化を醸成し、広域避難者支援コーディネートを目的として、学び合う機会を設けて下さっています。
しかも、第8回研修会は私たちの下知地区で開催して頂けます。
2025年12月13日(土)13:30(13:00開場)〜17:00
下知コミュニティセンター4階多目的ホール(高知市二葉町10番7号)
[内 容]
(1)二葉町自主防災会(下知地区減災連絡会内)による仁淀川町への広域避難の取組み
講師:西村 健一さん (二葉町自主防災会会長、下知地区減災連絡会副会長)
(2)高知市下知地区減災連絡会における減災の取組み
講師:坂本 茂雄 (下知地区減災連絡会事務局長、高知県議会議員)
(3)高知における広域避難者支援の考え方
講師:山中 晶一さん(高知市防災政策課長)
(4)東日本大震災広域避難者支援の取組み
講師:服部 育代さん((一社)ほっと岡山代表理事)
(5)パネルディスカッション(広域避難支援の今後に向けて)
コーディネーター:青田良介先生(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科)
拙い報告になるかもしれませんが、他の皆さんの報告は参考になる話ばかりだと思いますので、是非ご参加ください。
会場参加だけでなくオンライン参加も受け付けています。
お待ちしています。
| 12月9日「青森県東方沖地震で『北海道・三陸沖後発地震注意情報』」 |
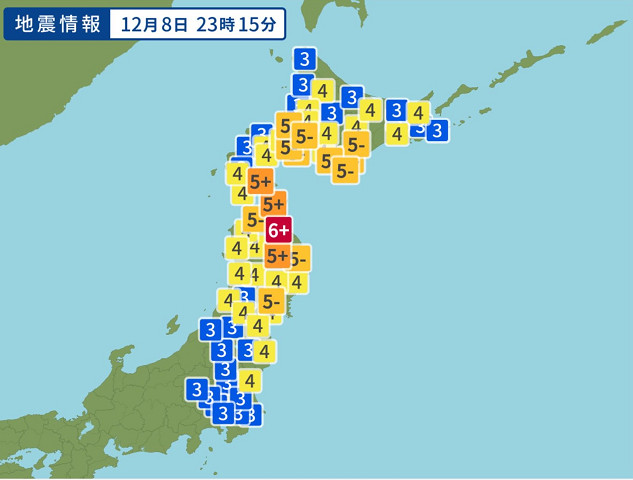 昨夜、午後11時15分ごろ、いつもテレビよりも早く鳴る緊急地震速報時ラジオから、速報が鳴って驚いたことでしたが、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測されました。
昨夜、午後11時15分ごろ、いつもテレビよりも早く鳴る緊急地震速報時ラジオから、速報が鳴って驚いたことでしたが、青森県東方沖を震源とする地震が発生し、マグニチュードは7.5と推定され、同県八戸市で最大震度6強が観測されました。
気象庁によると、青森県で震度6強を観測したのは1996年10月に観測計を設置して以降初めてで、気象庁はこの地震で、北海道太平洋沿岸中部と青森県の太平洋沿岸、岩手県に津波警報を出したほか、北海道沿岸の東部、西部、青森県日本海沿岸、宮城県、福島県に津波注意報(今朝6時20分にはすべての注意報は解除)を発表しました。
津波は9日午前2時までに、いずれも最大波で岩手県久慈市で70センチ、北海道浦河町で50センチ、青森県八戸市と同県六ケ所村で40センチなどが記録されました。
9日未明にあった関係省庁災害対策会議で、赤間防災担当相は今回の地震による負傷者が午前3時過ぎ時点で、計13人に上ると発表していますが、被害状況の収集が図られるに従って被害が大きくならないことを願っています。
また、続いて起きる可能性のある巨大地震への警戒を求める「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表されたことを受けて「今後1週間程度、気象庁や自治体からの情報に留意するとともに、家具の固定など日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる体制を整えていただきたい」と呼びかけられています。
この情報は、南海トラフ地震臨時情報と同様に、大地震の発生可能性が高まった際に注意を促す情報ですが、対象地域や発表条件、情報の呼びかけ方が異なるものです。
いずれにしても、大変寒い時期での避難行動・生活への備えとなりますので、十分体調に気をつけられて備えて頂きたいと思います。
| 12月7日「掘り下げなければならない県政課題の多い12月定例会」 |
 高知県議会12月定例会が、5日開会されました。
高知県議会12月定例会が、5日開会されました。
令和7年度高知県一般会計補正予算など12件で、このうち一般会計補正予算については、人事委員会の勧告に基づく給与改定に伴う人件費の増額など、総額26億円余りの歳入歳出予算の補正並びに総額49億円余りの債務負担行為の追加及び変更を含む補正予算案が提出されています。
条例議案は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案や県職員の柔軟な働き方に向けて「フレックスタイム制」を導入する条例議案など13件です。
また、国の補正予算に伴う追加補正予算も提案されることとなってています。
浜田知事は所信表明で、県内15消防本部を統合して「県一消防」を目指す消防広域化問題や特別職として「参与(官民連携推進監)」を設置したこと、9月定例会で紛糾した公社等外郭団体のあり方見直しについて、さらには「重度心身障害児・者医療費助成制度の拡充」における精神障害のある方への医療費助成拡充、そして新しい県民体育館の整備の課題などについて言及されました。
しかし、それぞれの課題について、市町村や当事者の間で何が課題となっているのかもっと掘り下げた言及がなされてもよかったのではないかと感じたところです。
これらの課題は、本会議や常任委員会でさらに深く議論されることと思いますが、わが会派「県民の会」では、代表質問の予定者であった橋本敏男議員が、市発注工事の入札最低制限価格を漏らした疑いで逮捕された土佐清水市前市長の程岡庸被告が、1日に辞職したことから、市長選挙立候補予定のため4日付けで県議を辞職されたことから、質問の機会を失うこととなりました。
橋本氏は、「市民から『土佐清水を救ってほしい』という声が寄せられ、任期を約1年4カ月残す中、悩みに悩んだが、議員経験を生かして即戦力として働き、声に応えたい」と出馬を決意されたようです。
私たちも、その決意を尊重し、会派に残った3名で引き続き県民の皆さんの思いに応えていけるよう頑張っていきたいと思います。
| 12月3日「県政かわら版第77号やっと発行へ」 |




12月定例会開会日を5日に控えて、やっと「県政かわら版」77号を発行できるようになりました。
現在、郵送や配布の準備をしていますので、来週には地域の皆さんなどにも配布できるかと思いますが、とりあえずこちらからご覧いただけるようリンクを貼っておきますので、ご関心ある方はご一読頂ければ幸いです。
今回の紙面では、9月定例会で県民が関心を寄せられたであろう県有施設の指定管理者の在り方や、私自身の一問一答の質疑と答弁の概要ねそして10月15日から東日本大震災の被災地の復興状況などについて視察した報告などを掲載させて頂いています。
特に、12月議会でも濱田知事が2期目の折り返しを迎えるにあたって県政運営姿勢について質される質問も多くあろうかと思いますが、質問機会のない私の現在の知事の姿勢への思いについて、「知事の県政運営姿勢に生じる懸念」との見出しで、次のようなことを書かせて頂きました。
県立施設の「指定管理者公募問題」をはじめ、昨年から続く「消防の広域一元化」、「精神障がい者の医療費助成」などの課題について、県の姿勢について質してきました。
しかし、県立施設の運営に関わる職員や関係者、自治体消防の管理者である市町村長や消防職員、精神障がいの当事者や家族などとそれぞれの意見交換が十分になされ、その声と真摯に向き合い、寄り添う姿勢は見られません。
さらに、「官民連携の橋渡し役」を期待するとして、県民を二分した参院選挙の候補者を「参与」として処遇しました。知事は、「政治家たる知事の名代として、政治的活動をすることもある。」と、公職に就けた「浪人」中の政治活動を容認しており、中立性・公平性を担保できるのかという懸念が多くの県民から寄せられています。
「知事が県民に共感する」より、「県民が知事に共感する」ことを求めているような最近の知事の姿勢には、懸念を抱かざるをえません。
| 12月1日「紙の健康保険証廃止を撤回し、マイナ保険証との併用を」 |
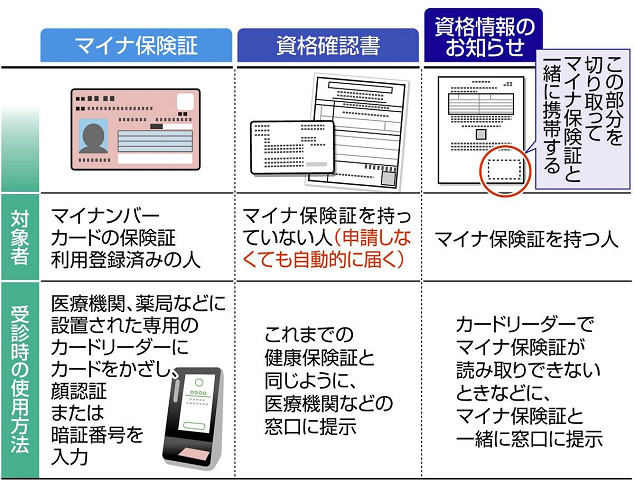 俳優佐藤浩市さんが、CМで繰り返し「12月2日以降、これまでの健康保険証は使えなくなります。」と、マイナ保険証への切り替えを訴えられてきました。
俳優佐藤浩市さんが、CМで繰り返し「12月2日以降、これまでの健康保険証は使えなくなります。」と、マイナ保険証への切り替えを訴えられてきました。
今日12月1日で、従来の健康保険証はすべて有効期限が切れ、マイナ保険証への一本化が基本となります。
しかし、国の統計によると、10月時点の県内のマイナカード保有率は75.8%で、沖縄県(68.9%)に次いで低く、マイナ保険証の利用率も34.43%と低く、全国の37.14%を下回っています。
政府は「混乱を避けるため」として、来年3月末までは加入先にかかわらず、保険加入資格が確認できれば、期限切れの保険証でも使える暫定措置を医療関係団体などに伝達しているが、後期高齢者や国保加入者の保険証ではすでに同様の措置が取られています。
マイナ保険証の不評には、カード読み取り機の不具合や内蔵の電子証明書の期限切れ、要介護高齢者や障害者らへの配慮不足など、さまざまな要因が重なっていますが、法的には任意のはずのマイナンバーカードの取得のはずが、医療を人質にとる形で国民に押しつけようとしてきたことも大きな要因ではないでしょうか。
こうした弥縫策を繰り返せば、利用者に混乱が広がり、医療現場の負担、制度維持に必要な予算はかさむばかりであるだけに、政府は、誰もが簡便かつ確実に医療を受けられる健康保険の原点にこそ立ち返るべきです。
そのためには、政府は従来の健康保険証廃止を撤回し、マイナ保険証との併用を認めるべきではないでしょうか。
| 11月29日「高市首相昨年の総裁選で使った8000万円の調達方法は」 |
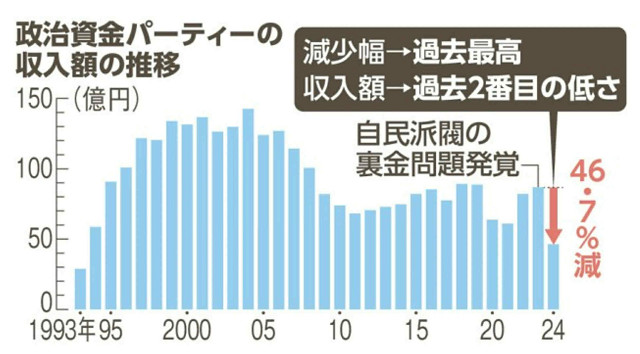 今朝の新聞報道は、政治資金のパーティー収入が半減したとの見出しが多く載っていました。
今朝の新聞報道は、政治資金のパーティー収入が半減したとの見出しが多く載っていました。
自民党派閥の裏金問題で党から処分を受けた39人について、2024年に開いた政治資金パーティーの収入が前年から57.3%(約6億3千万円)減っており、23年12月に発覚した裏金問題を受け、「パーティー控え」の傾向が表れたとみられます。
パーティー収入全体での合計は約46億円で、前年の約87億円より約46.7%減り、記録が残る1993年以降で2番目に少なく、前年からの減少幅は、過去最大となっています。
総務省に収支報告書を提出した団体のパーティー収入は、コロナ禍の20、21年に60億円台に減ったものの、22、23年はコロナ前と同水準の80億円台に戻っていたが、自民は裏金問題を受け、派閥によるパーティーについて、24年1月に開催禁止を決めています。
これによって23年に計約11億円の収入があった主要6派閥のパーティー収入は24年にゼロとなってはいますが、政治家個人によるパーティーは継続されています。
また、2024年の自民党総裁選を巡っては、決選投票で敗れた高市早苗首相の政治団体が、宣伝のために8,000万円超を支出していたことが、政治資金収支報告書から判明しています。
3位だった小泉進次郎防衛相側も、PR会社に約2,000万円を支出するなどしており、多額の費用を投じた宣伝合戦が水面下で繰り広げられていた実態が浮かび上がる総裁選でした。
自民党の総裁選は事実上首相を決める選挙とされてきた一方、公職選挙法の対象ではなく、選挙費用の上限規制や収支の報告義務はない中で、使われる多額の政治資金を捻出しながら「そんなことより」と切り捨てる首相に、呆れるばかりです。
ちなみに、私たち県議会議員など自治体議員の後援会など政治団体の収支報告もされていますので、こちらからご覧いただければと思います。
私の後援会は、約7割が自身の寄付で、他に個人から1万円程度の寄付の積み重ねによる収入総額が2,975,190円(繰越額1,069,917円、本年収入額1,905,273円)となっています。
支出額は、8割が事務所維持費に充てた1,538,462円となっています。
地道に自身と支援して下さる方々の個人個人による支えで頑張って議員活動を継続していきたいと思います。
| 11月28日「自転車も歩行者も自動車も共存できる道路を」 |
 今朝の高知新聞に、自転車での酒気帯び運転に、罰則を設けた改正道交法が昨年11月の施行から1年過ぎ、県警は今年10月末までに県内の59人を摘発したこと、そのうち男性1人は逃走を図るなど悪質だとして「免停」となったことが報じられていました。
今朝の高知新聞に、自転車での酒気帯び運転に、罰則を設けた改正道交法が昨年11月の施行から1年過ぎ、県警は今年10月末までに県内の59人を摘発したこと、そのうち男性1人は逃走を図るなど悪質だとして「免停」となったことが報じられていました。
ご近所の高齢者の方々からは、道路交通法が改正されて、取り締まりも厳しくなるので改めて地域で交通ルールの勉強会をしてほしいとの申し出があります。
自転車の交通違反への反則金制度(青切符)が、来年4月から始まり、16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となります。
例えば、スマートフォンなどを見ながら自転車に乗る「ながら」運転は1万2千円、信号無視が6千円といった内容ですが、113種類全て理解し覚える難しいでしょう。
しかし、このことを機会に自ら改めて改正ルールを勉強したいと思うこと自体は、いいきっかけになるかもしれません。
ながら運転はしない、逆走しない、信号無視はしないなどルールは守らなければいけませんが、その半面、歩道を広げて自転車レーンを作るとか、自転車利用者の暮らしのニーズに沿った環境づくりも念頭に置いて、より安全により走りやすいような道路やルールを整備していくことも求められています。
しかし、自治体にとっても財政状況などから一斉に対策を施すのは厳しいでしょうから、自転車の視点で見て、危険がある地点を突き止めていく必要があります。
そのためにも、自転車の利用者の意見を集めた上で、自治体が設置する地域公共交通会議などで議論し、優先順位をつけて、緊急性の高いところから段階的に改善していくことが求められます。
何よりも、車道を並走し追い抜いたりする際の車は、自転車との間隔に応じて安全な速度で進行しなければなりませんし、自転車の通路を封じるような駐停車も改善しなくてはなりません。
一方、自転車利用者には、余裕を大事に、少し遠回りしても車の少ないルートを選ぶなど、5分早く出発するだけでリスクをかなり抑えられることなどを自覚し、実践してもらうことなどを訴えたいし、自身の戒めにもしたいと思います。
| 11月27日「高市首相の党首討論は、真摯に向き合う姿勢ではない」 |
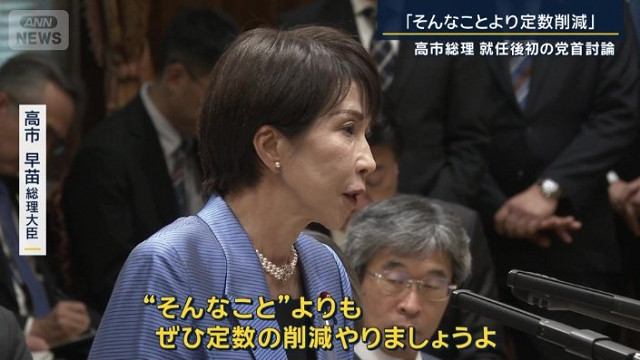 高市首相の初めての党首討論での姿勢には、改めて首を傾げざるをえませんでした。
高市首相の初めての党首討論での姿勢には、改めて首を傾げざるをえませんでした。
台湾有事に関する従来の政府答弁を踏み越えた首相答弁が「国益を損なう独断専行」あり、発言が招いた結果について責任を感じているのかとの立憲民主党野田代表の質問に対して、首相はそれには直接答えず、「政府のこれまでの答弁をただ繰り返すだけでは、予算委員会を止められてしまう可能性もある」「具体的な事例を挙げて聞かれたので、その範囲で誠実に答えた」とまるで質問した方に原因があるかのような答弁。
さらに、企業・団体献金の見直し問題に対しては、「そんなことよりも、定数の削減やりましょうよ」と、いきなり定数削減を持ち出すという答弁には、傍聴していた議員だけでなく、国民の多くが驚いたに違いありません。
自民党の派閥の裏金問題で失墜した政治への信頼回復に向け、この間、与野党で議論を積み上げてきたテーマを「そんなこと」と切って捨てる姿勢に、政治とカネの問題を解決しなければという姿勢は全く伺えません。
また、公明党の斉藤代表が、非核三原則の堅持を求め、三原則が国会でも決議されていることを挙げ、見直しは政府・与党だけではなく、国会での議決を経るべきとの主張に対して、三原則は政府も「国是」と認めているにもかかわらず、首相は「政策上の方針」と表現し、国会の関与については触れず、政権の判断のみで変更できるかのような布石を打つなど、その扱いを軽視しているようにも思えます。
政権運営上抱きこみたい政党には協調姿勢、一方厳しい追及を受ける政党にははぐらかし答弁という姿勢を見せつける高市首相のメッキが剥げるのもそう遠くないと思われます。
| 11月26日「高まらない防災意識」 |
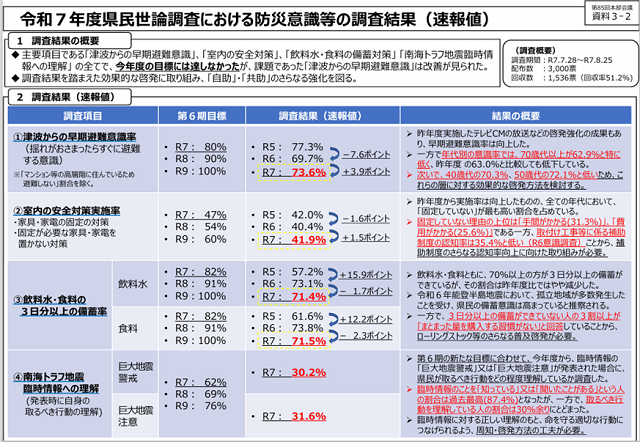 11月14日の南海トラフ地震対策推進本部会議で、県や県内市町村が必要な備蓄をどれだけ達成できているかを示す数値(4月1日時点)が、初めて公表され、飲料水や食料、トイレなど基本の8品目全てで目標を達成しているのは8市町村に止まっていました。
11月14日の南海トラフ地震対策推進本部会議で、県や県内市町村が必要な備蓄をどれだけ達成できているかを示す数値(4月1日時点)が、初めて公表され、飲料水や食料、トイレなど基本の8品目全てで目標を達成しているのは8市町村に止まっていました。
備蓄状況には、市町村間で大きな差があり、県と市町村が定める県備蓄方針では、2027年度を目標達成年としています。
一方、自助での備えが分かる25年度県民世論調査の結果では、「飲料水・食料の3日分以上の備蓄率」は、飲料水・食料ともに、70%以上の方が3日分以上の備蓄ができているが、その割合は昨年度比ではやや減少しています。
そして、3日分以上の備蓄ができていない人の3割以上が「まとまった量を購入する習慣がない」と回答していることから、ローリングストック等のさらなる普及啓発が必要と分析されています。
主要項目である「津波からの早期避難意識」、「室内の安全対策」、「飲料水・食料の備蓄対策」「南海トラフ地震臨時情報への理解」の全てで、今年度の目標には達しなかったが、課題であった「津波からの早期避難意識」は改善が見られたとされています。
それでも、年代別の意識率では、70歳代以上が62.9%と特に低く、昨年度の63.0%と比較しても低下しており、高齢者の避難意識に諦めが生じているとすれば、「一緒に逃げる」という取り組みの実践などによって効果的な啓発に務めることなどが求められていないでしょうか。
臨時情報のことを「知っている」又は「聞いたことがある」という人の割合は過去最高(87.4%)となったが、一方で、取るべき行動を理解している人の割合は3割程度にとどまっており、臨時情報に対する正しい理解のもと、命を守る適切な行動につなげられるよう、周知・啓発方法の工夫が必要とされています。
さらに、防災意識を高め、「知っちゅう」を「備えちゅう」という行動変容につなげていきたいものです。
| 11月24日「東電柏崎刈羽原発の再稼働は容認できない」 |

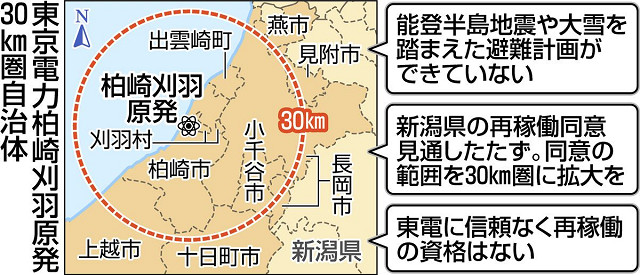 花角新潟県知事は21日、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明しました。
花角新潟県知事は21日、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明しました。
過酷事故を起こした東京電力の原発を再稼働に向かわせる重大な判断を下したものだが、その判断に県民の理解が得られるかは不透明だと言われています。
再稼働に対する県民の不安は依然根強く、新潟県が実施した県民意識調査では、「再稼働の条件は整っているか」との設問に対し、「そうは思わない」「どちらかといえばそうは思わない」との回答が6割を超え、市民団体による調査でも、県民の約6割が再稼働に反対の意を示しています。
まさに、県民合意が形成されたとは言い難い調査結果だったことを踏まえると、知事の判断は県民の意見に逆行するものだと言わざるをえません。
柏崎刈羽原発では、IDカードの不正利用などテロ対策上の重大事案が相次ぎ、21~23年に原子力規制委員会が事実上の運転禁止命令を出す事態に陥り、重大な原発事故を起こしただけでなく、これまでの不祥事も重なり、県民の間で東電に対する信頼が確立していないことは、知事も会見で認めていました。
しかし、東電はテロ対策の改善を図ってきたにもかかわらず、20日には、運転禁止命令期間の前後に別のテロ対策に関する問題が起きていたことも露見しました。
このような事態が続くうちは信頼回復は遠のくばかりで、東電が原発を運転する適格性や信頼性への疑念は払拭されていません。
県民投票や知事選を想定した県民は少なくないだろうが、知事は会見で「制度上、知事の職を止められるのは県議会しかない」と説明し、最終判断が県議会に託されることとなりました。
知事与党の自民党が単独過半数を占めている中で、県議会が知事判断を追認するだけなら県民の声を無視することになると思わざるをえません。
過酷な原発事故に直面した事故の教訓を忘れることなく、改めて原発に依存しない社会を目指すべきではないのかとの問いが突きつけられています。
| 11月22日「大分市佐賀関大火に見る市街地大火の4大要素」 |

 18日午後、大分市佐賀関の漁港近くの住宅密集地で発生した大規模火災は、お一人が亡くなり、被災は約130世帯にも上り、住宅など170棟以上に燃え広がったようです。
18日午後、大分市佐賀関の漁港近くの住宅密集地で発生した大規模火災は、お一人が亡くなり、被災は約130世帯にも上り、住宅など170棟以上に燃え広がったようです。
周囲の山林10カ所程度や、沖合の無人島でも出火していることから、当時は周辺の海上で強風注意報が出ており強風による被害の拡大は否めないと思われます。
焼損範囲は約4万8900平方メートルに及び、2016年に新潟県糸魚川市で起きた大規模火災を超える規模となり、焼損範囲はさらに拡大するとみられています。
昨年は、能登半島地震による輪島市の大火、今年に入って大船渡や今治での山林火災と火災被害が続く中、改めてその背景を明らかにすることと、その備えが問われています。
マスコミ報道では、私たちも日頃防災対策などでご指導いただく神戸大の室崎益輝名誉教授のコメントが掲載されていますが、僅かな字数ですので、もっと伝えたいであろうことを引用させて頂きます。
室崎益輝先生は、ご自身の20日のFBで「佐賀関の市街地大火について」とコメントされています。
(引用開始)佐賀関の大火について、大火の専門家としての「ささやかなコメント」です。
地球温暖化や少子高齢化や地方切り捨てという、自然の強暴化と社会の脆弱化との関りで、現在の日本の市街地の大火リスクを捉える必要があります。
市街地大火の4大要素である、「強風」「乾燥」「消火ミス」「密集」のうち、乾燥には地球温暖化が関わっており、消火ミスには少子高齢化とコミュニティ崩壊が関わっており、密集には市街地整備の遅れが関わっています。
北海道の雪害も瀬戸内海のカキ災害も東北の熊災害も地球温暖化が背景にあるのですが、佐賀関の大火も地球温暖化が背景にあります。そこに、「市街地の老害化」も関わっています。全てを強風の所為にしてはなりません。
最後に一番大切なこと、被災者や被災地の生活や街並みの「創造的復興」をいかにはかるかが問われています。
強風の所為にしてはいけないのですが、強風が無ければ大火が無かったことなので、強風による自然災害と位置づけて「被災者生活再建支援法」を適用して、全焼世帯には300万円+αの支援金を給付し、被災地の背中を押さなければなりません。(引用終了)
このような背景を事前に把握して、社会の日常の脆弱性として、克服しておくことが求められているのではないかと改めて考えさせられます。
| 11月20日「実力行使の民主主義「高知パルプ生コン事件」」 |
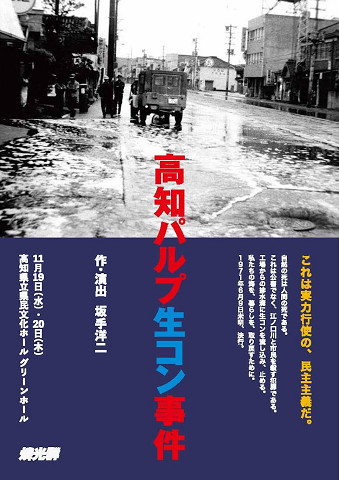
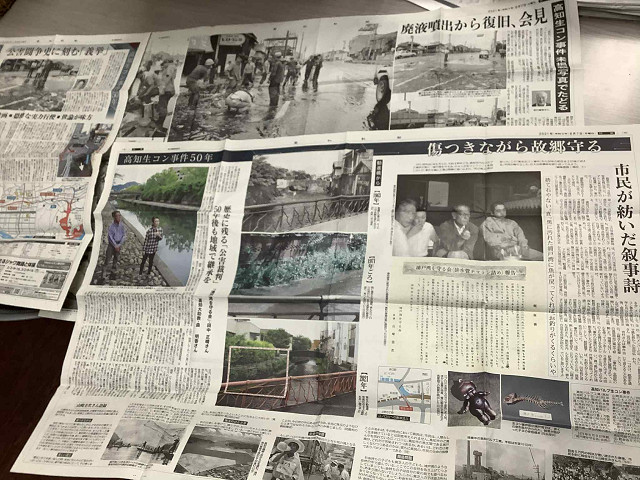 昨夜は、演劇「高知パルプ生コン事件」を県民文化ホール・グリーンで鑑賞してきました。
昨夜は、演劇「高知パルプ生コン事件」を県民文化ホール・グリーンで鑑賞してきました。
見ごたえのある2時間半でした。
もう54年が経つ中で、高知県内でも忘れられようとしているかもしれないが、公害闘争史に刻まれた「義挙」、民主主義を機能させるための実力行使で、当時の高知パルプによって汚染され壊された市内の江ノ口川や浦戸湾の環境と生態系と県民の営みを取り戻すために立ち上がった先人の闘いが描かれた重厚な社会派の演劇でした。
それは、生コン事件の起きる前の戦前の高知パルプ工場の旧工場で製作した風船爆弾や第5福竜丸事件をはじめとしたビキニ水爆実験、そして発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)による水道水汚染の問題など今につながる人間が社会の不条理にどのように抗うかを問われていることを考えさせられます。
私も大学4年生の時に、前年の判決を受けて、帰省した際に高知新聞社を訪ね、当時の新聞の関連記事を読ませて頂き、レポートを書いたことを思い出します。
| 11月18日「精神障がい者への医療費助成制度の対象に当事者の声は届かず」 |
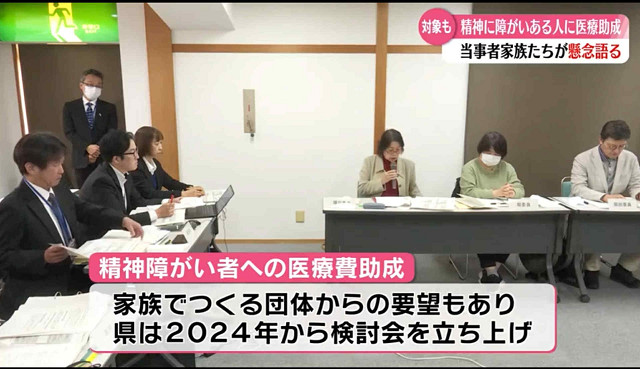
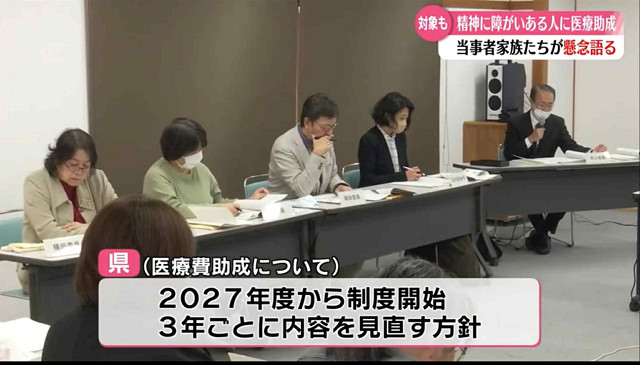

昨日、第6回「精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議」が開催され、ともに医療費助成制度の対象を全ての障がい者とすることを求める運動をしてきた家族会の皆さんらとともに傍聴しました。
検討会で改正案として示された内容は、第5回の素案と変わらず、「令和9年4月から全市町村で開始して、助成対象を1級とし、2級のうち18歳未満で身体や知的に中程度の障害がある方や、2、3級のうち2年に1度の更新で前回の等級が1級の場合とする」とされ、当事者や家族会などが求めてきた全級せめて2級までを対象とする願いに応えるものとはなりませんでした。
県内で精神障害者手帳を持っている8038人のうち、1級は1割未満で残り9割は2級3級であり、委員からは「等級が2級・3級の人も福祉施設での収入は少なく併発した病気の治療を諦めざるを得ない実態がある」との声をはじめ、「せめて2級まで拡大を」、「病院から地域への流れをつくってきた行政はその流れを止めないようにするためにも、地域で暮らせる支援制度が求められる」などの声があげられました。
今後は、助成範囲について「改正から3年をめどに身体や知的も含めた制度全体を検討する」としているが、それと併行して当事者や家族会の意見はしっかり聞いていくことは、事務局も明らかにしました。
また、会長から「今後の検討体制のあり方」「制度の周知」「診断書の書き方など医療機関との意見交換」「相談者への支援の在り方や家族会との関係性」などについて、事務局に課題が提起されました。
そして、会を終えるにあたって、会長からの「課題を残しながら一定の方向性が示された。国への継続した働きかけは求めておきたい。当事者、家族の大変さは誰にも生じるものではないか。お互い様の問題と受け止めて、あらゆる支援施策に反映して頂きたい」との結びの言葉を事務局がしっかりと受け止めた対応をして頂きたいものです。
検討会後には、県精神障害者家族会連合会の横田直子会長やこれまで当事者として声をあげてこられた「はっさくの会」会員らによって、県庁で記者会見し「1級の障害者は全体のわずか7・4%で、2級、3級の人も日常生活が厳しく、就労が難しい状況は変わらない」と強調し、署名の趣旨も実現されていないので、今後も拡充を求めて取り組みを進めていくことの決意を示されました。
| 11月16日「避難者は、ゲストではなく、キャスト」 |

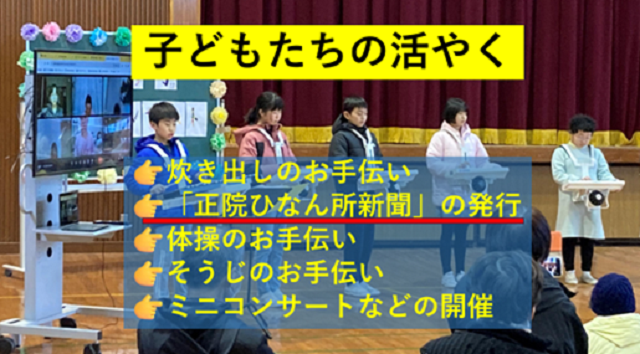


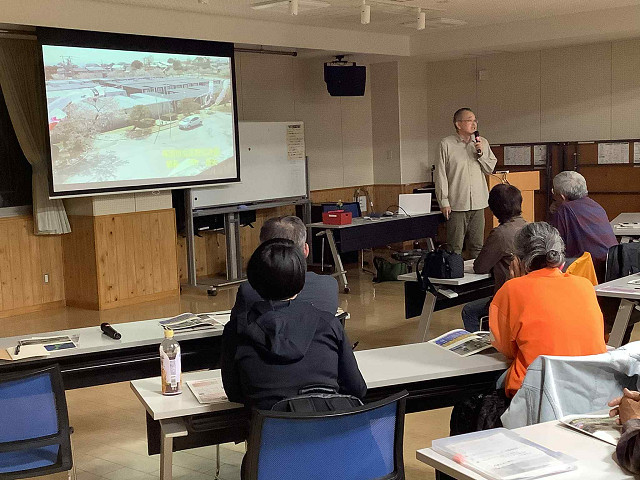
昨夜の下知地区減災連絡会主催事前復興・防災講演会は、昨年元旦に能登半島地震で被災された珠洲市立正院公民館館長の小町康夫さんを講師に迎え「能登半島地震における避難所運営とその後~避難者や支援チームと協力しながら~」と題して、避難生活と復興につながるコミュニティの大切さなどについて、お話し頂きました。
お話は、発災時から避難、避難所開設の状況に始まり、避難所運営のご苦労など時系列で発生した課題、そしてそれをどのように解決していったのか、分かりやすくお話し頂きました。
何よりも、子どもたちを中心にできる役割を担って頂いたことをはじめ、「避難者は、ゲストではなく、キャスト」との言葉が実践できた日頃のコミュニティの大事さを学ばされました。
まとめて頂いた「運営のポイント」は、
①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。
②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。
③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。
①一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。
そして、「今後の課題」として次のことを掲げられましたが、これからの備えに役立てなければならない指摘であることを痛感させられました。
①指定避難所の想定避難者数に見合う備蓄品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。
②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく
今、珠洲市正院地区は、復興に向かって歩み始めています。
正院町未来会議は、「小さな力を集めて大きな力に」して、「全町民の参加型」の「緩やかな連合体」として歩む姿は、これから事前復興まちづくり計画を策定する下知地区にとっても参考になる姿だと思いました。
「今後の課題」は町はずれよりも町なかに、マンションよりも平屋にとの思いの「復興公営住宅問題」、そして、「津波の浸水地域の外側に」「防災機能を備えた建物に」との思いの「公民館の移転問題」などだそうです。
丁度一年前に、正院を訪ねましたが、今度は小町さんたち未来会議の皆さんの思いが反映された復興のまち正院の姿を見せてもらいに行きたいと思いました。
| 11月15日「県消防広域一元化先延ばし・段階的統合も」 |
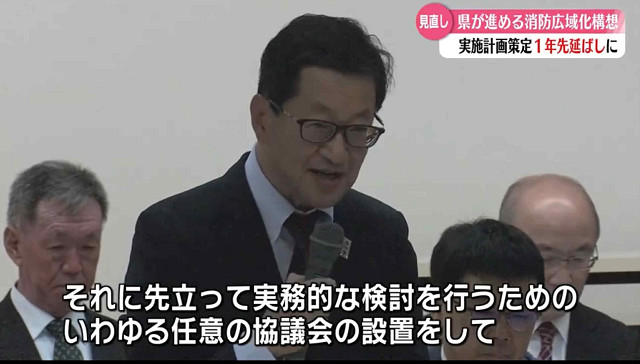
 県は昨日、県消防広域化基本計画あり方検討会を開催し、傍聴しましたが、知事が冒頭にこれまでのスケジュール案を見直すことに挨拶の中で言及されました。
県は昨日、県消防広域化基本計画あり方検討会を開催し、傍聴しましたが、知事が冒頭にこれまでのスケジュール案を見直すことに挨拶の中で言及されました。
県内15消防本部を統合する「県消防広域一元化」の発足時期を当初の令和10年度から遅らせ、最長で令和16年度とする方針を示すなど、全体的に先延ばし、段階的実施とするなど、市町村からのこれまでの意見に答えた形になりました。
県が示した「令和8年度以降の取り組み方針及び目標年次」では下記の通り、これまでの見直しがされることとなっていました。
令和8年度においては、消防本部機能の統合に向けた実施計画の策定に必要な実務的な検討を行うため、地方自治法に基づく法定協議会の設置に先立って任意協議会を設置し、同年度内に実施計画案を取りまとめることとなります。
その際には概ね次の事項を前提条件として検討を開始することとされます。
①令和15年度末までに消防指令システムを全県共同で再整備し、令和16年度から運用を開始すること。
②それまで令和16年4月までの間に県内15消防本部を1本部に統合することを目指して、段階的な統合の可能性も含めて検討協議を進めること。この場合、段階的な統合の形態として、例えば方面消防本部単位などでの地域単位での段階的移行及び人材確保の先行共同実施などの事務事業単位での段階的以降の双方を検討し、これらの方式による場合には、各段階における参加市町村名及び目標年度等を実施計画案において明記すること。
③消防指令システムの再整備事業や前項に掲げる先行的共同事業の実施を含め、消防広域化の実現に向けた共同事業の実施主体として、令和10年4月を目途に「高知県消防広域連合(仮称)を設置すること。
これにより、市町村や各消防本部は消防業務の統合時期をそれぞれ判断することになり、一方で総務や通信部門を集約し、現場隊員を増やしたり、到着時間を短縮したりといった統合の効果が出るのは1~6年遅れることになるとのことです。
これまでも市町村から多様な意見が出されてきましたが、さらに県は丁寧な調整を行っていくことが求められます。
| 11月14日「高市政権の危うさ」 |
 トランプ米大統領への激しい批判は米国内でも広がっている中、媚びへつらい、ノーベル平和賞を与えたいなどと言う高市首相。
トランプ米大統領への激しい批判は米国内でも広がっている中、媚びへつらい、ノーベル平和賞を与えたいなどと言う高市首相。
そして、軍事費のGDP比3.5%を念頭に置いた2%や安保関連3文書の改定の前倒しなどに踏み出す高市首相。
在任中の首相は、「いかなる事態が存立危機事態かは…一概に述べるのは困難」と慎重だったが、高市首相は、7日の衆院予算委員会で、中国が台湾を完全に支配下に置くために「戦艦を使い武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースだ」と強弁していました。
しかし憲法9条は「交戦権」を認めず、専守防衛までは認められているとはいえ、日本が直接攻撃されていないのに自衛隊が武力行使するなど認められるものではなく、周国家主席との会談で、戦略的互恵関係や建設的で安定した関係を構築し、台湾問題でも従来の政府の立場を踏襲することを示しながら、中国に対する挑戦的な発言を繰り返しました。
高市首相は10日になって、「従来の(内閣の)立場を変えるものではない」としたが、参戦すれば台湾に近い与那国島や西表島、石垣島、宮古島が危うく、沖縄本島の米軍基地への攻撃も想定されることを念頭におけば、7日に発言した持論は当然封じておくべきでした。
存立危機事態の具体的要件は対外的に示すのはなじまないものであり、そもそも、安保法制は違憲の疑いが残っているのであって、こうした懸念に対してしっかりと正面から向き合うべきことこそ求められているのではないでしょうか。
トランプ氏に迎合・追随し、東アジアの安全保障情勢の緊迫化に拍車をかけて、沖縄を見捨てるような姿勢の高市内閣こそ、「存立危機事態」ではないかとの批判が高まっています。
| 11月13日「能登半島地震の被災地からのメッセージに未災地の高知で学ぼう」 |
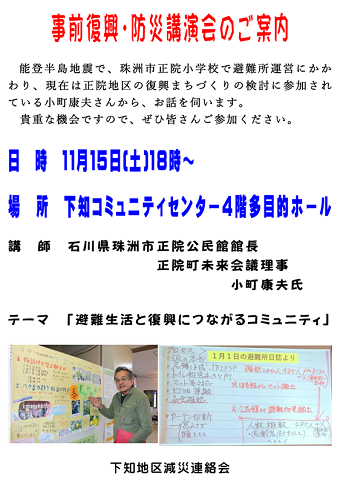

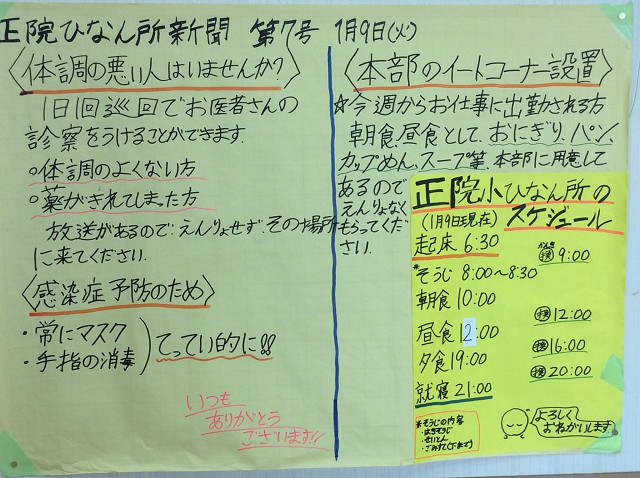

15日(土)18時~下知コミュニテセンターで予定している下知地区防災・事前復興講演会が近づいてきました。
能登半島地震で、震度5強から6強の大きな揺れで、甚大な被害を受けた珠洲市正院地区で500人ほどの被災者を迎えた小学校での避難所運営にあたられた公民館長の小町さん。
そして、小町さんは、今も復興に向かって「正院町未来会議」で、活躍されています。
そんな小町さんからお話を頂きます。
資料として、50枚ほどのスライドを送って頂きました。
貴重なお話を聞かせて頂けると思います。
下知地区の皆さんはもちろん、地域外の皆さんもどうぞご参加ください。
| 11月12日「政治活動保障の参与職で、官民連携」 |
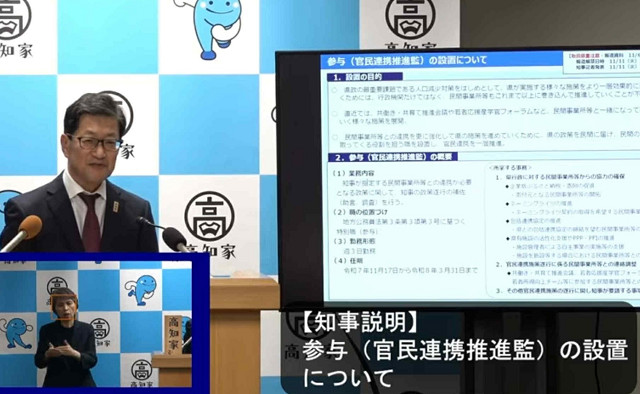


昨日の知事の記者会見による、大石氏の県参与の任用に関する質疑から「政治的任用」の課題がさらに明らかになったと言えます。
「設置の目的」は、一番の目的は「県政の最重要課題である人口減少対策を始めとして県が実施する様々な政策をより一層効果的に遂行していくためには、行政機関だけではなく、民間事業所などもこれまで以上に巻き込んで推進していくことが不可欠。」だから設置したとのことです。
しかし、質疑の中から見えてくる本音としては、現在の県庁職員任せでは、成果が出ないので、何とかしたくて、官民のことを熟知している大石氏以上の「適役」は無いし、丁度今「浪人中」なので、もったいないと思い、要請したということらしい。
知事らの政策判断のサポートを担うが、庁議など県の意思決定の場には加わらず、営業的に庁外に出て「官民連携の橋渡し役」を期待するとしながら、「政治家としての知事の名代として、政治的活動をすることもある。」と、浪人中の政治活動を容認しています。
そのような中で、行政としての中立性・公平性を担保できるのかという懸念に対しては、そのようなリスクを超える形で成果を出すことを期待しているし、そのことで懸念に応えていくと言われています。
そして、新設の参与は、週3日勤務の想定で報酬は年440万円程度だと言いますので、月12日程度の勤務で37万円程ということになります。
任期は、びっくりする来週明けの17日から本年度末で、知事の任期中は更新も可能としています。
大石氏は取材に「身の引き締まる思いで、行政への信頼性が非常に大事だと感じている。」と答えていますが、今回の人事そのものが「行政への信頼を失うことになった」と感じられていないのでしょうか。
今回の人事で、県庁内の組織に少なからず溝が生じ、県民との間の信頼関係にヒビが入るような人事が強行されることは残念でありません。
それでも知事が大石氏を傍に置きたいというのなら、記者質問の中にもあったが、知事の好きな「直指定でなく公募」でもすれば、少しは県民の不信感は和らぐのではないでしょうか。
12月定例会では、知事の参与人事に関する姿勢を質すとともに、大石氏の今後の「言動と成果における中立性・公平性」を注視していきたいと思います。
| 11月11日「知事の参与人事は県政の分断につながるのでは」 |
 今朝の地元紙報道に驚かれた県民の皆さんも多いことでしょう。
今朝の地元紙報道に驚かれた県民の皆さんも多いことでしょう。
7月の参院選徳島・高知選挙区に党公認で出馬して落選した大石自民党参議院徳島高知選挙区支部長を県の特別職として「参与(官民連携推進監)」を新設してまで雇用するとのことです。
しかも、議会の議決を経ずに知事の一存で決められるとすれば、そこまでして採用しなければならない人材なのかと問いたくなります。
報道などによると「県政をよく知るほか、草の根活動で培った幅広い人脈や行動力を持っていることを評価したとみられる。」とのことだが、大石氏個人の人脈が県政施策を進めるうえで、公平性・中立性を確保できる人脈なのかと言わざるをえません。
直近の選挙では、県民を二分した激しい選挙戦を闘った中で、培った人脈に頼る県政は、施策の偏りが生じるのではないかと懸念される県民は多いことだと思います。
うがった見方をすれば、大義は「県政をよく知るほか、草の根活動で培った幅広い人脈や行動力を持っていることを評価したとみられる。」のかもしれないが、実のところは落選した大石氏の職確保をし、次のステップのために知事が手を差し伸べたのではないかと見られても不思議でありません。
自民党が、責任もって職を確保するべきであって、選挙の落選者を県民の税金で雇用する必要性はないはずです。
濱田知事と大石氏の対応を見た時、「頼む方も頼む方なら、受ける方も受ける方」と言いたくなります。
また、最近の知事の施策における強硬姿勢が目につく中、このような人事を強行しようとする知事を、諫める幹部職員はいないのか。
県庁組織のあり方も問われているのではないでしょうか。
今日の記者会見での、知事の説明を注視していきたいと思います。
| 11月10日「信用できない維新の体質」 |


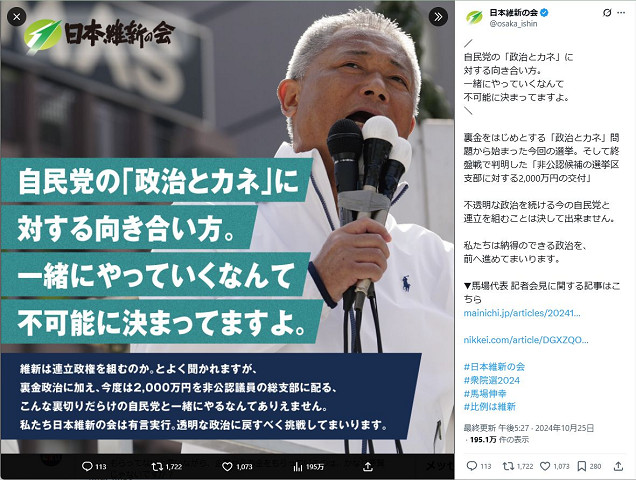
日本維新の会の藤田文武共同代表が、ビラの印刷などを巡り、秘書が代表を務める会社への発注をしていた「還流」疑惑が報じられていますが、本人は違法性を否定した一方、誤解払拭のために今後、発注先を変えるなどと述べていますが、それで説明がつくのかと批判されても当然です。
しかも、その言い訳と同時に、報道したしんぶん赤旗の記者の名前を自身のX(旧Twitter)で名刺によって名前を晒すという卑劣なことも行っています。
維新の会では、今年に限っても、国から公設秘書の給与を詐取したとして、石井章元参院議員が詐欺罪で在宅起訴され、維新の母体となる地域政党「大阪維新の会」から公認を受けた大阪府岸和田市の永野耕平前市長は、官製談合防止法違反などの疑いで逮捕、起訴されました。
まさに、今維新の党がやろうとしているのは「身を切る改革」どころか、実は「身を肥やしていた」のであれば、「定数削減」を言う資格があるのかと言わざるをえません。
政治家が身内に資金を流す行為はかねてから批判されてきました。
例えば、岸田政権下の寺田元総務相や秋葉元復興相など議員の政治団体の事務所賃料を親族に支払う利益誘導の構図が問題視されるなど、他にも不祥事が重なり、両者は更迭されました。
しかし、高市氏は、自民党裏金問題の象徴とも言うべき萩生田光一氏を党幹事長代行に起用し、昨秋衆院選では、自民から非公認とされて無所属で出馬した萩生田氏の応援のため、維新の元代表、松井一郎氏が駆けつけているのです。
さらに衆院選では、維新も自民との対決姿勢を明確にし、日本維新の会のX(旧ツイッター)2024年10月「不透明な政治を続ける今の自民党と連立を組むことは決して出来ません」と投稿し、「自民党の『政治とカネ』に対する向き合い方。一緒にやっていくなんて不可能に決まってますよ」「不透明な政治を続ける今の自民党と連立を組むことは決して出来ません」と投稿していたのです。
それが、自民との連立政権に参加するとなると、この政党は何から何まで、国民の信頼を裏切る政党だと言わざるをえません。
そして、そんな政党と連立する自民党も信頼するには値しないということは自明の理です。
| 11月7日「10年を節目に改めて災害に『も』強い街目指して」 |
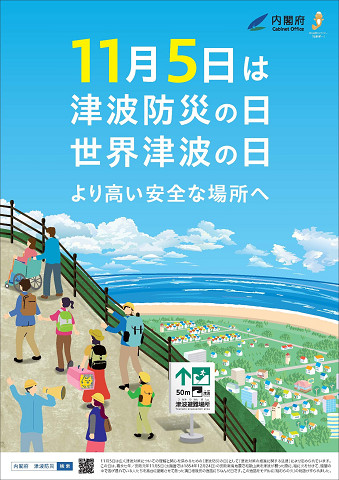

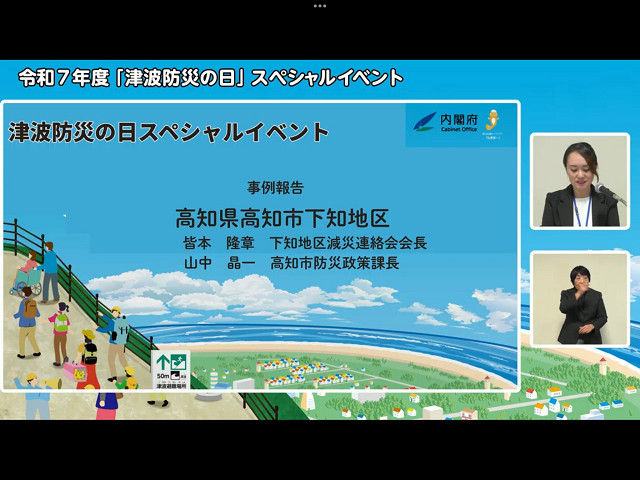
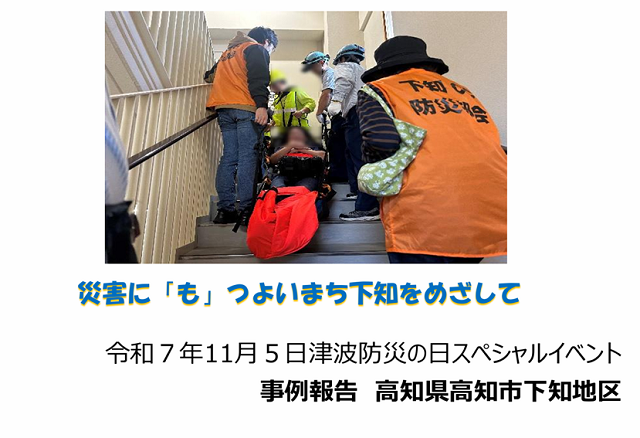
毎年、内閣府は「津波防災の日」の5日、意識啓発イベントをオンライン形式で開催しています。
今年は、高知市下知地区も5年ぶりに事例報告として発表させて頂きました。
私も、途中からのオンライン参加で、平成23年の東日本大震災で被災した岩手県釜石市からの地区防災計画で車避難に取り組まれている荒川地区の事例報告から拝聴させて頂きました。
高知市下知地区の事例報告は、高知市からの「津波被害と対策」について、山中晶一高知市防災政策課長から報告の後皆本隆章下知地区減災連絡会会長から下知地区防災計画とその取り組みについて報告がありました。
下知地区防災計画(津波避難を含む)を取り巻く近年の外的要因と今後の取り組みとして、南海トラフ地震臨時情報への対応やカムチャツカ半島地震における遠地津波の対応、今年3月末の国の新たな被害想定と、これを踏まえた高知県版被害想定及び高知市の各防災計画・マニュアル変更が行われるなどが予定される中、下知地区防災計画の前提となる「魂(住民の主体性)の醸成」をアップデートし、「高知市事前復興まちづくり計画」との融合させていくことが課題となっています。
片田敏孝東大特任教授の基調講演には、間に合わず聞けなかったが、「南海トラフ地震等を見据えた国民の防災意識向上と行動変容」について、「地域事情に関係なく事態が展開するのが災害の本質。あなた自身がどう動くかが問われている」と訴えられたとのことでした。
また、パネラーの鍵屋先生らも共感されていましたが、「説得のコミュニケーション」よりも、自分の行動が家族の命を守るという「共感・納得のコミュニケーション」を通じて、行動変容を促すことが重要だということが強調されていたようです。
磯打先生の下知地区防災計画を「地域コミュニティの継続計画」と称して頂いたり、昭和小の「津波避難ビル巡り」による地域の顔の見える関係づくりとしての視点があることの指摘を頂きました。
また、地区防災計画づくりのアドバイザーとして通って頂いた鍵屋先生が、丁寧に取り組んだからこそ、今に続いている取り組みがあると評価頂いたことに、「脆弱性の高い人が増えてきたが、そんな人たちでも助けられる取り組みがこれからは、求められてくる。」との指摘をしっかり具体化させていくことが、必要ではないかと思ったところです。
12月には、鍵屋先生を久々に下知地区にお招きして講演会を開催予定だが、ますます楽しみになってきました。
| 11月6日「虐待からの今『恩返しに生きる』」 |

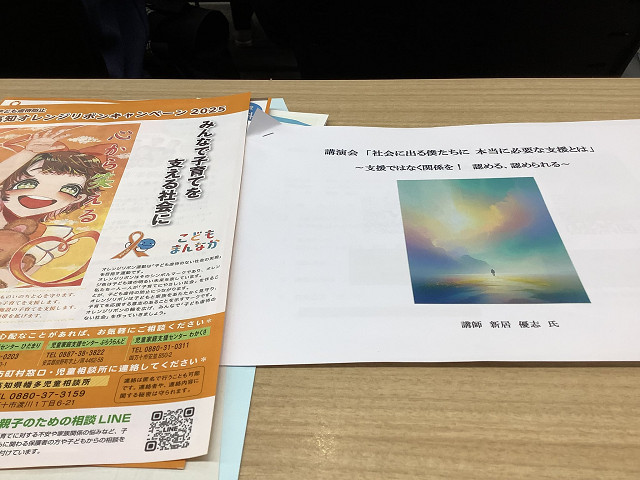 昨日は、事務所近くの「ちよテラホール」で「社会に出る僕たちに 本当に必要な支援とは~支援ではなく関係を!認める、認められる。~」をテーマに、幼少期より壮絶な虐待を受け、自身の過酷な家庭環境と児童養護施設での生活経験を経て、過去を価値に変えてきた新居優志さん(株式会社Fans 代表取締役/鳥取県米子聖園天使園卒園)の講演会がありました。
昨日は、事務所近くの「ちよテラホール」で「社会に出る僕たちに 本当に必要な支援とは~支援ではなく関係を!認める、認められる。~」をテーマに、幼少期より壮絶な虐待を受け、自身の過酷な家庭環境と児童養護施設での生活経験を経て、過去を価値に変えてきた新居優志さん(株式会社Fans 代表取締役/鳥取県米子聖園天使園卒園)の講演会がありました。
講演会は、高知市の社会的養護自立支援拠点事業所「にじいろステーション」と児童家庭支援センター「高知ふれんど」が企画されたもので、長いお付き合いがあり児童虐待予防につい学ばせて頂いていることから、お声かけがあって、参加してきました。
今朝の高知新聞にも記事が出ていましたので、ご覧になった方もおられるかと思いますが、その生き方の中で学ばれたことに、私たちも厳しい環境の子どもたちとの向き合い方を教えられました。
「支援とは何かをしてあげることではなく、信じて待ってくれた人がいたと言う記憶を残すこと。」だと言い、「啐啄同時」という言葉を紹介されました。
それは、卵の中のひなが殻を破ろうとする時、親鳥も同時に卵をつつくことを意味し、「子どものサインなしにつついてもうまくいかない。小さいサインを信じて待つこと、そしてそれに気づくことが大切で、このバランスの支援が本質ではないか」と最初に呼びかけられました。
新居さんは、「過去の自分は、幼い頃から父を一度も見たことがない。母の精神的不調によって家に帰られない。食べられない。公園の水道水で空腹を満たし、公園で寝る日々が続いた。母からの虐待で死を考える毎日があった。高校には行かせない。働いてこい。お前は金を稼ぐために産んだ。」と言われて、育ったことを「否定して生きてきた過去」として紹介されました。
しかし、児童養護施設との出会いが人生の転機になったとのことで、そこで得たことは「学校に行ける喜び。朝昼晩ご飯をが出てくる。高校・大学進学。世界の20カ国以上を訪問できた。」ことで、施設との出会いは光だったと言われています。
「人は何を持っているかよりも、誰に出会うかで人生が変わる。」「過去は変わらない。ただ過去の価値は変えられる。」「人はいつからでも、どこからでも変われる。」「待つ支援。信じる支援。つなぐ支援。という三つの支援がある。」「できたと言う成功体験を積み上げることが大切。環境で人生は決まらない。」「恩返ししたい。恩返しに生きる当たり前に感謝する。自分の話のためにいろんな人が来てくれている。これにも感謝しかない。」などと、自らの体験の中で、得られてきた一つ一つの教えの一言一言が刺さる言葉ばかりでした。
新居さんが「自分を信じてくれたからやろうと思った」恩返しは、「三つの支援」の実践なのかなと考えさせられました。
| 11月4日「文化による抵抗『パレスチナ映画祭』」 |
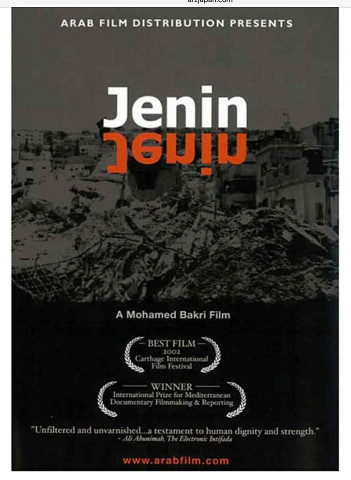
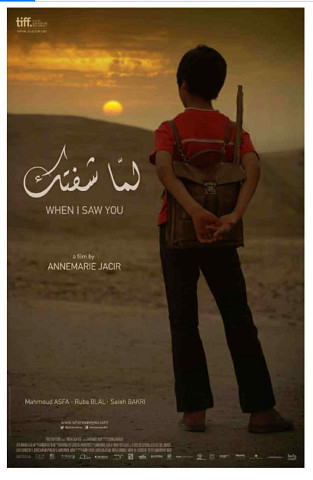 昨日は、11月2日に世界同時開催の「パレスチナ映画祭」の一環として、高知では3日開催となった映画祭を鑑賞してきました。
昨日は、11月2日に世界同時開催の「パレスチナ映画祭」の一環として、高知では3日開催となった映画祭を鑑賞してきました。
1917年11月2日、英国がパレスチナの地にユダヤ人国家を建設することを支持する「バルフォア宣言」を出したことがイスラエル建国に結びつき、今日に続くイスラエルによるパレスチナ人抑圧の要因となったことから23年から映画祭は毎年、この日に開催されています。
イスラエルによる占領と抑圧が続くパレスチナに連帯しようと11月2日、世界94カ国、425都市700会場以上でパレスチナ映画を同時上映する「パレスチナ映画祭」で、日本は60会場以上で最多の開催となっています。
2014年から毎年パレスチナで開かれてきたが23年10月、イスラエルによるガザ地区への大規模侵攻開始後は、全世界で映画上映を呼びかけるスタイルになったと言われています。
高知では三本の映画が上映されましたが、私はイスラエル軍の作戦によりヨルダン川西岸地区のジェニン難民キャンプで多数の死傷者が出た事件を扱い、イスラエルで上映禁止となったドキュメンタリー「ジェニンジェニン」(2002年)と、ヨルダンで難民となった少年の目を通して厳しい現実を描いた「ぼくの見えた道」(12年)を鑑賞しました。
高知でも市民の皆さんとともに、世界同時に展開する「文化による抵抗」に連帯できてよかったです。
| 11月3日「『身寄りなき老後』に苦慮すること」 |
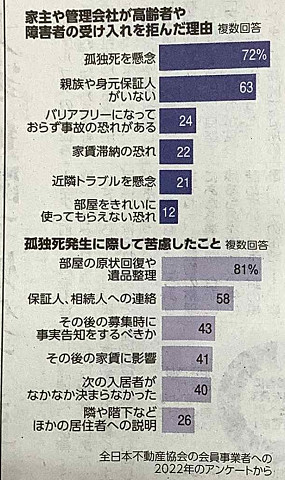 国でも、新たな法改正によって、「居住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確認など生活支援サービスを一体で提供する物件をあらかじめ認定することができることとなったが、この10月に施行されました。
国でも、新たな法改正によって、「居住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確認など生活支援サービスを一体で提供する物件をあらかじめ認定することができることとなったが、この10月に施行されました。
今朝の朝日新聞では、「身寄りなき老後」と題して、単身で頼れる身寄りもいない高齢者が亡くなった場合、残置物の処分を難しい問題として取りあげています。
私も、以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げ、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。
しかし、住宅が確保できても、亡くなられた時の残置物の問題は新たな問題として残っています。
法律上、所有権は相続人にあたる家族親族が引き継ぐもので、大家などが相続人に断りなく処分することはできず、その所在を探して片付けを頼む必要があります。
しかし、必ずしも応じてくれるとは限らず、相続そのものを放棄されることもあり、全員が相続放棄をすれば依頼する相手もおらず、宙に浮いてしまうこととなります。
これまでにも幾度となく指摘してきたが、単身の高齢者が新たに部屋を借りるのは容易ではなく、国土交通省の2021年度の調査では、住宅を貸す「賃貸人」の約7割が、高齢者に貸すことに「拒否感がある」と回答し、その要因は残置物処分の難しさや、孤独死の発見が遅れて「事故物件」になる懸念などとされています。
また、公営住宅には収入が一定以下などの条件があり、地域によっては倍率も高く、国の調査では、高齢の単身世帯は24年に903万世帯を超え、今後も増えていく見通しです。
記事にあるケースの長野県社会福祉協議会の「入居保証・生活支援事業」を利用し、亡くなった場合、残置物は県社協に贈与するという内容で死因贈与契約を結んでいたため社協が処分できたとのことです。
厚生労働省の24年調査では、全国5482万5千世帯のうち高齢の単身世帯が約903万1千世帯を占め、50年には約1083万9千世帯に達するという推計もあり、一方で「持ち家率」は60歳以上では約80%だが、40代は約58%と下がり、今後は高齢期の持ち家率も下がる見通しの中で、高齢者の単身化の問題は加速化するばかりであり、看過できない問題だといえます。
| 10月31日「下知地区防災計画の「事前復興計画」が月刊「世界」に」 |
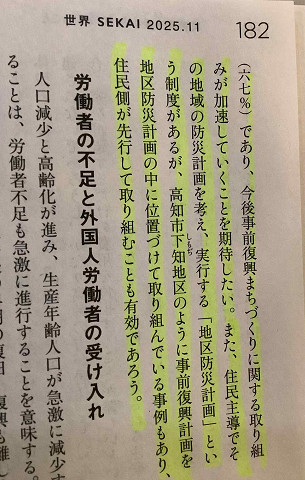
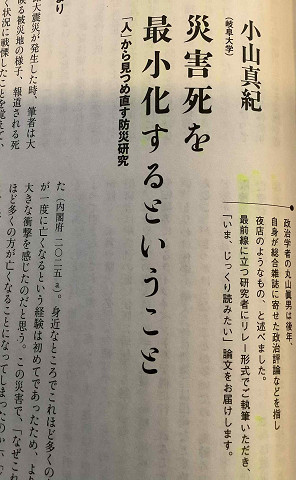
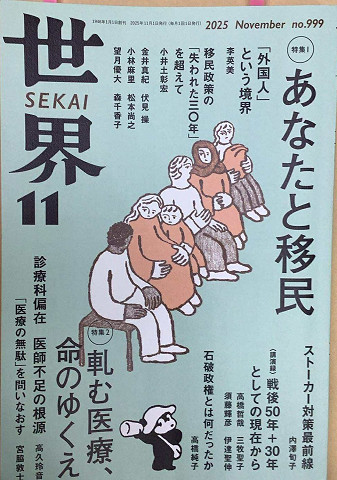
今回の東京行きの旅のお供は読めていなかった月刊「世界」11月号でした。
なんとその中に高知市下知地区の地名が出てきました。
岐阜大学の地域減災研究センター長の小山真紀先生が書かれていた「災害を最小化するということ」との論文の中の「少子高齢化と復興まちづくり」のパートで、「事前復興まちづくり計画を策定している自治体が2%にとどまっているが、関連する何らかの取り組みに着手している自治体は1202にのぼり、今後事前復興まちづくりに関する取り組みは加速していくことを期待したい」とありました。
その中に「住民主導での地域の防災計画を考え、実行する「地区災計画」という制度の中で、「高知市下知地区」のように、事前復興計画を地防災計画の中に位置づけて取り組んでいる事例もあり、住民側が先行して取り組むことも有効であろう」と紹介していただいておりました。
改めて、事前復興のまちづくり計画の中で、「平時と災害時のギャップを埋める取り組みにもつなげ」たり、この小山先生の「災害時の死者や被害を最小化するということは、すなわち、平時の社会をより良くするということと同じことなのである。」との結びを、肝に銘じて、これからもこの地区防災計画の具体化を図るとともに、事前復興計画を来年1月頃から始まるまちづくり計画のワークショップで可視化していきたいと思ったところです。
| 10月30日「地震被害想定検討委員会で、震度分布・津波浸水予測ともに見直し」 |
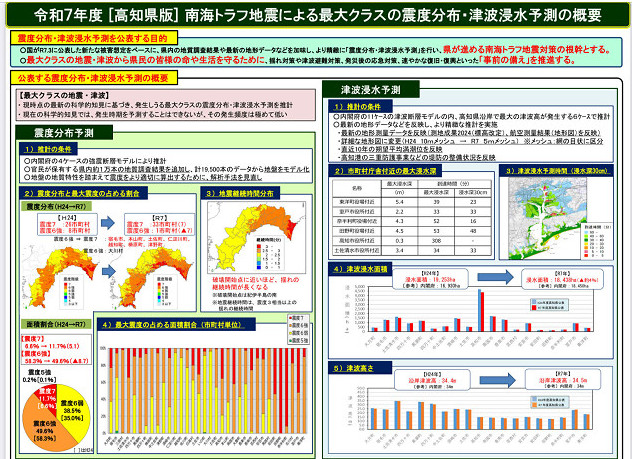 29日、第4回地震被害想定検討委員会が開催され、傍聴してきました。
29日、第4回地震被害想定検討委員会が開催され、傍聴してきました。
「震度分布・津波浸水予測」は、平成24年に高知県が公表したものを、国が本年3月に公表した新たな被害想定をベースに、県内の詳細なデータなどを加味して、より精緻に算出したものであり、震度分布・津波浸水予測ともに見直されました。
震度分布では、高知市周辺の平野部など一部の地域では、震度階級が高くなり、最大震度7に達する市町村が前回の26市町村から33市町村に増加しています。
一方、津波浸水の予測では、国が本年4月に改定した最新の地図情報を活用し、前回よりも詳細な地形図を作成したうえで、近年の潮位データや浦戸湾の三重防護事業などの整備状況も反映し、浸水域を算出したとされています。
その結果、津波浸水面積は、高知県全体で前回の約19,300haから約18,500haに、約4%減少しましたが、いずれにしても、予測は厳しい状況だと言わざるを得ません。
委員からも、「どこの揺れが大きくなったとか、津波浸水域が縮小したとかと受け止めるのではなく、どこも厳しいリスクを抱えていることは変わりないことを踏まえて備えなければならない」「県民には、無茶苦茶分かりやすいパンフレットで周知することに務めなければならない」などの意見が出されていました。
さらに、詳細の検討をするため当初の予定に加えてさらに検討会を追加で開催して、人的被害や建物被害などの被害想定を算出し、今年度末に公表される予定です。
その被害想定をもとに、県では来年度に第6期南海トラフ地震対策行動計画のバージンアップを図る過程で、対策のさらなる強化や加速化を図っていくことが求められます。
| 10月29日「お追従外交で終るのか」 |

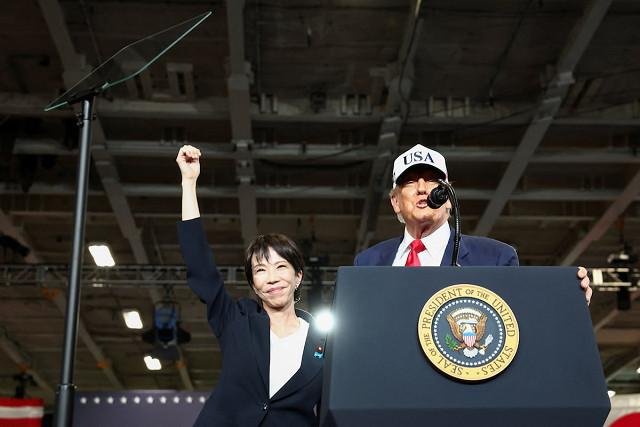 「阿諛追従(あゆついしょう)」という四文字熟語があるが、「人に気に入られようとして、おせじを言ったりへつらったりして機嫌をとること。」だと言われています。
「阿諛追従(あゆついしょう)」という四文字熟語があるが、「人に気に入られようとして、おせじを言ったりへつらったりして機嫌をとること。」だと言われています。
今回のトランプ米大統領に対する高市首相の対応を見ていて、そんな言葉が浮かばざるをえませんでした。
高市氏は、すでにGDP比2%を目標にした防衛力整備の目標を2年前倒しして今年度中に実現するとともに、さらなる増額を視野に、安保3文書の改定に着手する方針を表明しており、トランプ氏には、日本が主体的に取り組む決意を伝え、日米同盟の抑止力、対処力の強化と、同志国連携の推進、さらに、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認しました。
重要鉱物、AI(人工知能)、造船など幅広い分野で経済安全保障の協力を強化し、レアアース(希土類)を含む重要鉱物の確保についての連携に関する共同文書と、日米関税交渉の合意の実施を確認する共同文書に署名しました。
そして、明記されただけでも総額4千億ドル(約60兆円)にのぼる事業規模についても「額が大きすぎる。根拠がわからない」と戸惑う企業もあるなど破格の対米投資を行おうとしています。
加えて、高市氏はトランプ氏の「貢献」を持ち上げるばかりか、米側によると、高市氏はトランプ氏が欲しくてたまらないノーベル平和賞に推薦する考えも明らかにしたといわれています。
こんな、露骨な追従(ついしょう)外交と見られても仕方ない高市外交の先で実現される日米外交は、この国の平和と安定を築くことができるのかと不安を抱かざるをえません。
| 10月28日「避難生活と復興につながるコミュニティについて聞かせて頂きます」 |
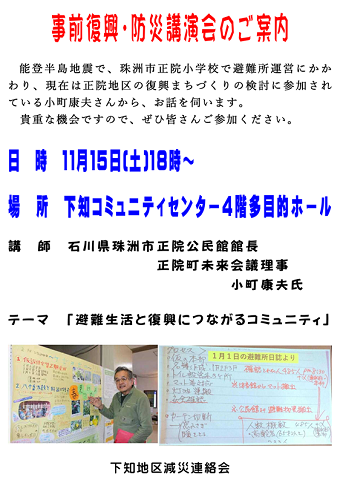 昨年11月3日、能登半島地震の被災地の珠洲市を地域の消防団の皆さんと視察で訪ねた際、正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺わせて頂きました。
昨年11月3日、能登半島地震の被災地の珠洲市を地域の消防団の皆さんと視察で訪ねた際、正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺わせて頂きました。
正院公民館には、正院小学校で避難所開設をしてからの日毎の推移を記録したものや子どもたちが作成した「正院小ひなんしょ新聞」が丁寧に掲示されていて、お話も含めて大変貴重で教訓化したい内容ばかりでした。
特に、「運営のポイント」として以下の5点だと言われました。
①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。
②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。
③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。
➃一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。
また、「今後の課題」としては、次の二点だと話されました。
①指定避難所の想定避難者数に見合う備品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。
②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく。
今回の講演会では、そんな発災直後の避難所運営に携わられた教訓に加えて、全町民が会員のまちづくり団体「正院町未来会議」で理事も務められ、半年間に渡り企画開催し、集まった意見を元に作成した「正院町復興まちづくり方針案」についてのお話も聞かせて頂けるようです。
その小町さんをお招きして、11月15日(土)18時から事前復興・防災講演会を開催します。
まさに、事前復興の学びとして貴重な内容だと思います。
関心ある皆さんは、どうぞお越しください。
| 10月27日「自維連立政権の危うさと社会対立の可能性」 |

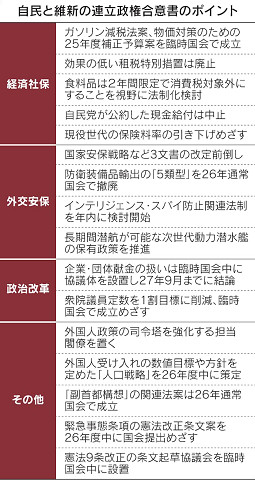 21日の臨時国会で誕生した自民党と日本維新の会のタカ派連立政権による高市内閣は、当初の支持率こそ高いが、その危うさに国民は早く気づく必要があります。
21日の臨時国会で誕生した自民党と日本維新の会のタカ派連立政権による高市内閣は、当初の支持率こそ高いが、その危うさに国民は早く気づく必要があります。
公明党との連立解消で、首相指名が危ぶまれた高市・自民が選んだのが維新であり、両党の合意では、議員定数削減、スパイ防止法制定や社会保障改革、改憲などの国民世論が対立しかねない課題ばかりが並びました。
この政権誕生を歓迎しているのは、安倍政権を支えた保守系団体「日本会議」や、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の「賛同会員」や旧安倍派で政治資金で脛に傷持つ議員らではないかと思われます。
また、自民と維新が交わした連立政権の合意文書に盛り込まれたのは、スパイ防止法の制定だけではなく、維新が「絶対条件」に位置づけた、「社会保障改革」や、「副首都構想」の推進、「1割」を目標とした衆院議員の定数削減などのメニューも並んでいます。
社会保障改革は、9月定例県議会でも我々が反対した市販薬と成分や効き目が似た「OTC類似薬」への公的医療保険の適用見直しの検討が明記されるなど、保険適用外になることへの懸念など社会保障改革を重視する維新との連立政権の誕生で、見直し議論が加速することを危惧されます。
さらに、維新が絶対譲れないとして、最重要項目に格上げされたのが衆院議員定数削減は、国民の声が国会に「さらに届きにくくなることにつながりかねない」と警鐘を鳴らす野党や国民の声が高まっている中、このように重要な課題を今臨時国会で何としても成立させるというその強引さには呆れるばかりです。
いよいよトランプとの会談が迫っている中で、防衛費を対GDP比で2%に引き上げる目標を前倒しで実施しようとするなど、話し合う前からトランプからの要請に応えようとしている高市政権の危うさをしっかりと見極めていきたいものです。
そして、右派政党として再構築された自民党が、タカ派的な政策を実行しやすくなる一方、国内の分断や対立が激化してしまうのではないかという懸念は高まるばかりです。
| 10月26日「防災訓練で新たな視点も」 |





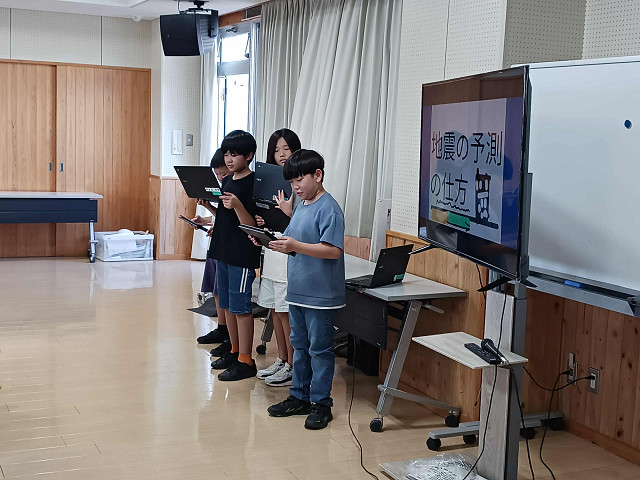


今日は朝から、下知地区総合防災訓練がいろんなメニューの中で開催されました。
10時の避難完了の時点では68名の避難者でしたが、3年目を迎える昭和小学校5年生の防災学習の発表が始まるころには、保護者などの見学も含めた参加もあって、ピーク時には100名を超える参加だったようです。
いろんなきっかけでの参加は有るかと思いますが、一つでも防災についての学びがあったらと思います。
特に今回の訓練では、車椅子ユーザの方が参加して下さって、4階までの階段を使った避難行動支援が行われました。
車椅子ユーザーの方から参加しての感想を全体の参加者の前で聞かせて頂き、改めて避難行動要配慮者への支援のあり方をお互いが学ぶことができました。
そのための機材についても、日常からの使い方を練習しておかないと色々とてこずることも改めて確認できました。
今後も、機会があれば参加させて頂きたいとの要望がありましたので、私たちの学びの場としても歓迎したいと思います。
また、今回の訓練では、多言語ポスターも作成して、ご近所にお住いの外国からの研修生の方などへの参加呼びかけもしてきました。
参加されたときの対応として、コミュニケーションボードなども準備してありましたが、今年は参加がありませんでした。
今後も多様な方々に参加頂ける訓練となるよう企画・運営していきたいものです。
訓練への参加、運営にあたられた皆さんお疲れさまでした。
| 10月25日「教育から見る満州」 |
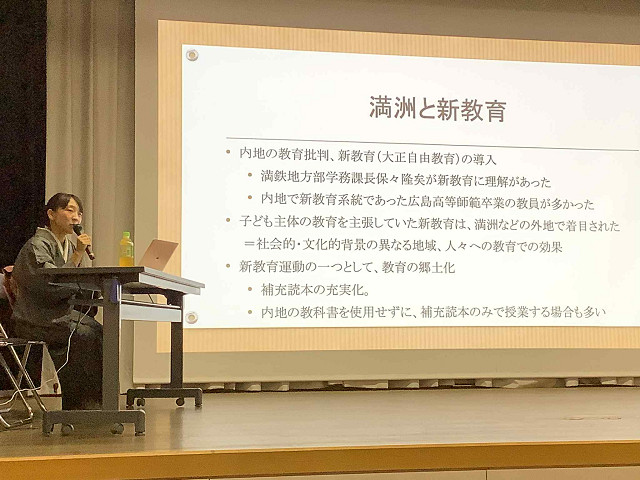
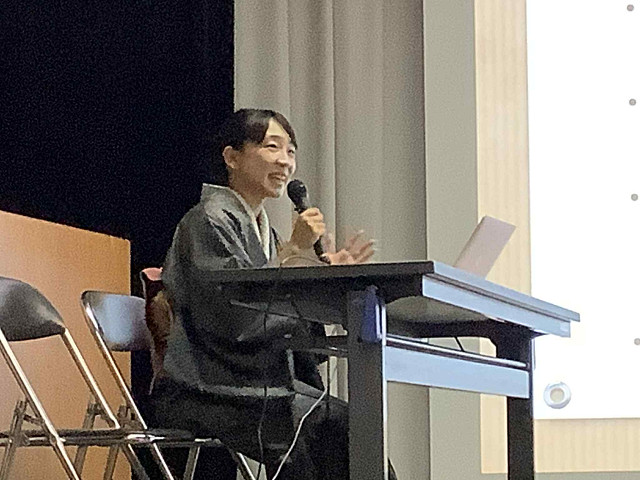
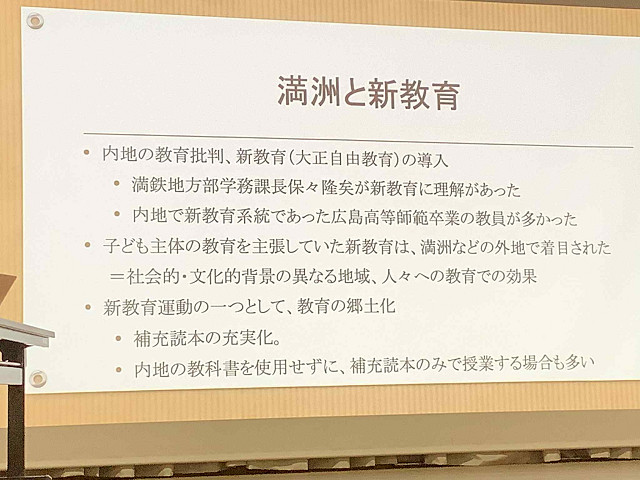
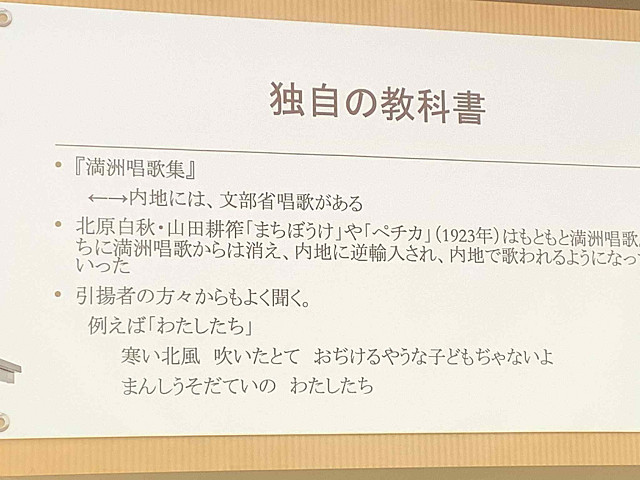
ご案内頂いていた「第8回満洲の歴史を語り継ぐ集い」に参加してきました。
基調講演は、大石茜先生(松山大学准教授)が、「教育からみる満洲―満鉄の幼児教育を中心に―」お話してくださいました。
満洲の教育史を学びながら、保育や幼児教育の在り方についてお話を聞かせて頂きましたが、興味深い話ばかりで、生前の母が、満州の撫順でこのような教育を受けていたから故のその後の生いたちが少し垣間見えたように思えました。
満鉄の新教育は、内地の教科書さえ使用しない現地適応主義だったのが、満州国になつてからは内地延長主義の教育が行われ、日本の生命線としての満州を意識した戦時下の教育に移行した過程や当時の幼児教育なども初めて聞く話ばかりで、改めて教育と戦争について学ぶことの必要性も考えさせられました。
また、県内で収集してきた満洲帰国者の証言の中から、少年少女期の体験をまとめた動画も視聴させて頂きました。
| 10月24日「東日本大震災の被災地・名取市閖上、多賀城高校の復興から、事前復興を学ぶ」 |


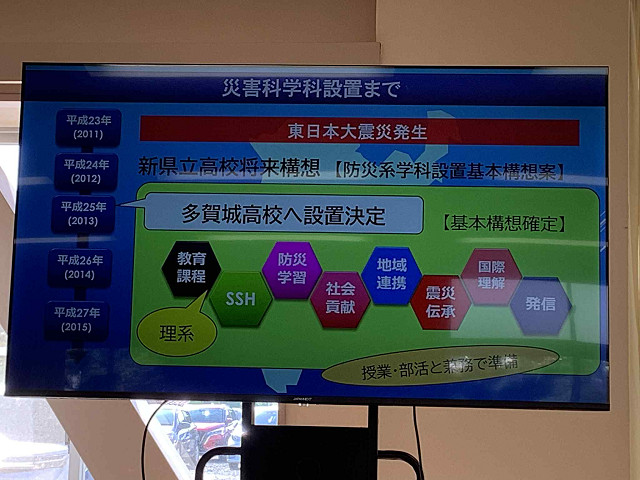



東日本大震災の被災地における復興状況を学ぶ会派の調査視察も18日が最終日となりました。
午前中には、県立多賀城高校災害科学科を訪問し、佐々木教頭先生をはじめ、初代の担任の佐藤先生、現在の担任の石山先生のお話を聞かせていただきました。
ちょうど当日は全校の球技大会のため、授業を見学する事はできませんでしたが、先生方からのお話を聞く中、改めて本県においても、必要な学科であることを考えさせられました。
災害科学科では、普通科の学習内容を防災や減災、環境の切り口も加えて学習し、専門科目では、過去の災害や環境から見られる諸問題を学習題材にするなど、自然科学的なアプローチや人間社会学的視点を養う学習で、幅広い内容を扱っています。
災害科学科では、大学等進学が8~9割を占め、その先にも災害対策に関わる進路を歩まれているとのことです。
高知県議会でも、本県高校における災害科学や環境を学べて、このような学びの中で、命を守る学びと備えの人材を育てる学科の必要性にを提案してきましたが、改めてその必要性を感じたところです。
午後からは、名取市閖上地区の復興の状況について、10年間の交流が続いているふらむ名取の代表格井さんから、日和山で合流し、お話を聞かせて頂きました。
10年前から何度か尋ねましたが、復興の街開きがされてからは初めてでしたので、その代わり様に驚かされました。
まちづくりそのものよりも、格井さんが力を入れてこられたコミュニティ形成のための様々な取り組み、お茶会や餅つき、芋煮会などなど、災害後に新たにできた人と人とのつながりが復興の重要な柱なのだと感じさせられたところです。
そして、周りに見える災害復興住宅の集会室の光景が目に浮かんでくるような気すらしました。
これらの取り組みによって、復興計画では後れをとったが、いいまち「閖上」になったと言われるように頑張られている格井さんたちの思いはを私たちは災害前に築いておかなければならないと考えさせられました。
この地区では、ハードの復興だけでなく、ソフトの復興の重要性について学ばせて頂きました。
| 10月23日「東日本大震災の被災地・石巻市雄勝、東松島市の復興から、事前復興を学ぶ」 |







二日目の16日の最初の目的地は、石巻市雄勝地区で、約束の場所の道の駅を訪ねて、その変貌ぶりに驚くばかりでした。
現地では、10年前に現地で説明頂いたり、これまでに高知にもお越しいただき、下知地区でも復興の状況についてお話を頂いた金沢大学助教の阿部晃成さんが出迎えてくれました。
最大9mの高さの巨大堤防に囲まれた地域は、今までも話には伺っていましたが、本当にこれが復興と言えるのか、そんな思いを抱かざるを得ない現状を見せつけられました。
移転先の高台での災害復興公営住宅の状況や多くの犠牲者が出た雄勝病院跡地にある慰霊碑等を案内頂き、後背地に誰も住まなくなったにもかかわらず、立ちはだかる巨大防潮堤など、なぜこのようになってしまうのか考えさせられる復興です。
そこには、今までも阿部さんから聞かされていた被災者の多くを切り捨てながら、高台移転のミニよる住宅再建と、守るものを失った低平地に巨大防潮堤を建設する宮城県の規定復興が進められた町が作り出され、そこには帰りたくても帰れない人々を除く1/4の住民が戻っただけです。
さらに、阿部さんは、現在能登半島地震の被災地輪島で支援をしながら研究をされている中での課題を将来の南海トラフ地震への備えとして提起もして下さいました。
これらの課題をしっかりと高知に持ち帰りたいと思います。
女川駅前のシンボルエリア経由で、午後からの目的地である東松島市みらいとし機構に移動しました。
東松島市では、分散型地域エネルギー自律都市プロジェクトによる復興まちづくりが行われており、スマート防災エコタウンや電気事業についてお話頂くとともに、防災エコタウンの実際を見学させて頂きました。
大手住宅企業と東松島市が連携して、東日本大震災からの復興をきっかけとした住民の意向を反映した住宅再建や環境配慮のまちづくりを実現したもので、エリア内では災害時に停電した際にも、3日から1週間は電気供給が可能な再生可能エネルギーの新しいモデルとして運営されています。
事前にこのような街づくりが地域地域で行われていれば、災害後の復旧がいかに早く進むかということを考えさせられました。
また、東松島市の野蒜地区は、大変な被害を受けたところとして記憶にもあるところですが、現在は脱炭素先行地域として野蒜地区で取り組まれている事業などについてお話を聞かせていただき、現地の震災遺構や復興伝承館もご案内いただきました。
雨の中を丁寧にご案内をいただいた皆様に感謝です。
また、移動中には少しの時間だけでしたが、大川小学校にも立ち寄り、手を合わせてきました。
| 10月22日「高知県も命を守る選択肢への支援を」 |

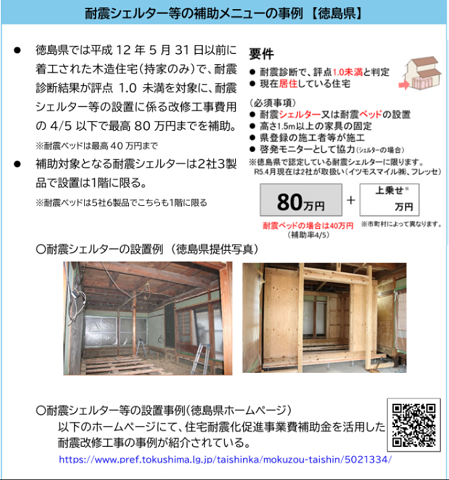 昨日の高知新聞「地震新聞」に「耐震シェルター、命守る選択肢 多くの県で導入補助 高知は「全体耐震基本」」との見出しで耐震シェルターの特集記事がありました。
昨日の高知新聞「地震新聞」に「耐震シェルター、命守る選択肢 多くの県で導入補助 高知は「全体耐震基本」」との見出しで耐震シェルターの特集記事がありました。
住宅の一部に強固な空間をつくる「耐震シェルター」という備え方で、建物全体の大がかりな耐震化が難しい場合であっても、低価格かつ短期間の工事で命を守る可能性を広げようとする方法で、先進的に取り組んできた静岡県、三重県や徳島県など、南海トラフ地震による甚大な被害が想定される静岡から宮崎まで10県のうち8県で、設置に何らかの補助制度があります。
しかし、本県は支援策がない状態だとして、先進県の取り組みの状況や本県がなぜ、支援策がないのか県の考え方などを記事は照会して下さっています。
記事の中にも「シェルターの活用は、高知県議会でも東日本大震災以前から議論されてきた。執行部は「調査、検討する」「他県でも補助実績は伸びていない」と述べるにとどめて今に至る。」とありますが、私がこの課題を初めて取りあげたのが東日本大震災前の2009年2月定例会でした。
以降も、「一室耐震化」というあり方などで取りあげ、2015年12月には、会派の「知事への県政要望」でも、「木造家屋の耐震化については、県産木材の活用を図る一室耐震化についても支援をすること。」を取りあげましたが、「全体が倒壊した場合、外に救出することの困難性などの課題があるので、まずは低コスト工法の浸透や壁柱工法の可能性を検討したい。」との姿勢に終始しています。
記事では、「国土交通省は昨年8月、『木造住宅の安全確保方策マニュアル』を公表し、「何もしないよりはリスクを低減し、人命の安全確保につながる可能性のある暫定的・緊急的な方策を講じることも有効」として、耐震シェルターも盛り込まれた。」とあります。
そして、マニュアルは、閉じ込められる危険性への対応▽シェルターの強度の確認▽家屋全体のバランスを崩していないか―といった留意事項も示し、各県の補助制度なども紹介しています。
記事は、三重県でシェルター開発を担った同県木材協同組合連合会の担当者の「シェルターは耐震化に比べて対象となる人が絞られる。たとえ導入件数が少なくても“弱者”への選択肢として、用意されていることに意味があるのでは」との言葉で、結ばれています。
本県も、命を守る選択肢としての支援策を改めて考えてもらいたいものです。
| 10月21日「精神障がい者への医療費助成で、対象拡大求める声が最後まで」 |
 昨日は、第5回目となる精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議の傍聴をしていました。(写真は、高知新聞デジタル版から引用)
昨日は、第5回目となる精神障がい者への医療費助成を検討する関係者会議の傍聴をしていました。(写真は、高知新聞デジタル版から引用)
9月定例会でも質問し、その素案の方向性を注視していましたが、示された内容は、助成対象を最も重い等級の1級とし、既に助成がある身体、知的障害者と同様の措置を基本とするものでした。
なお、2級のうち18歳未満で身体や知的に中程度の障害がある方や、2、3級のうち2年に1度の更新で前回の等級が1級の場合も対象に含むとされていますが、家族会などが求めてきた全級を対象とする願いに応えるものではありませんでした。
委員の県精神科病院協会の岡田会長は「かなり不満を感じる。医療で支えて初めて維持される、通院だけでも対象を広げるべき。全国で立ち後れた6県の中の本県としては、周回遅れで追いつくだけでよいのか。」と指摘されていました。
また、地域生活支援に携わられている委員からは「在宅でやっと生活している人をサポートできるようにしてほしい。」との声をあげられました。
当事者を代表した委員からは、「実質1級のみを対象とした素案のように受け止められる。これまで求めてきた声が十分に反映されていない。」など厳しい声が出されたが、市町村代表の委員らの多くは、「必ずしも納得いかないかもしれないが、3年後の検討もあるし、まずはスタートしてみることでどうか。」との考えが示されました。
最後まで、「2級まてせは何とか拡げて頂きたい。始まればいいのではなく、遅れを取り戻す必要がある。」「システム変更などで2027年スタートになるのであれば、さらに検討してほしい。」などの意見も出される中、会長は「押してのご意見だと思うので、そのことも含めて最終案への調整を連投して欲しい」と結ばれました。
次回検討会に、出された意見がどれだけ踏まえられるか、注視していきたいと思います。
| 10月20日「東日本大震災の被災地・気仙沼市の復興から、事前復興を学ぶ」 |





県議会「県民の会」では、会派の同僚議員4名で、15日~17日の間、東日本大震災における宮城県の被災地の復興状況を視察・聞き取り調査に行ってきました。
まずは、初日の気仙沼市での調査について報告します。
大谷海岸で、住民の声をその復興状況に反映させた取り組みについて、現地を見ながら、市議会議員の三浦友幸さんからお話を聞かせていただきました。
住民同士または行政との対立構造を生まない合意形成のあり方や海岸の管轄変更、砂浜から後背地までの一体整備環境への配慮、バリアフリーなど復興過程における工夫した点についてご説明頂きました。
さらに、住民にとって復興のまちづくりを進めていく上で、何が最も大事にしなければならないのかという「砂浜を守る」という上位概念を最初に作ったのが、大きな力になったということを教えられました。
住民合意がない中で工事は進めない。
対立の火種は、いつも残っていたが、お祭りやコミュニティで乗り越え、対立構造を生まないようにした。
事前復興を取り組む高知においても、大変重要なスタンスを聞かせていただきました。
その後は、防潮堤と一体的に整備した内湾地区の商業施設「迎(ムカエル)」と複合型公共施設「創(ウマレル)」などを見学案内していただき、ここでも復興の賑わいの作り方などについてお話を聞かせていただきました。
昼食の合間には、寸暇を惜しんで、震災遺構の向洋高校にも足を運んできました。
| 10月18日「自維連立で社会保障・憲法の危機」 |
 自民党高市総裁誕生以降、さらに政治空白が長期化し、連立のあり方を巡って離合集散が繰り広げられています。
自民党高市総裁誕生以降、さらに政治空白が長期化し、連立のあり方を巡って離合集散が繰り広げられています。
そのキーワードとなった「政治とカネ」の問題が、ここにきて素通りされようとしています。
臨時国会での首相指名選挙を前に、自民党と日本維新の会の連立協議が大詰めを迎え、維新は自民に対し、12項目の政策の実現を求ています。
その中で、吉村代表が最優先事項に挙げたのが、「副首都構想」と社会保障改革で、それら国会議員の定数削減も「絶対条件」に加えられました。
しかし、12項目の中でも、優先順位からすると政治資金問題をなおざりにされているのではないかとの見方もあります。
公明党が政権離脱した最大の要因である受け手規制を強化する公明案より、維新案は厳しいもので自民が応じるはずはないと見られています。
そうであれば、維新は自民党に本気で政治資金問題を求めていないと言えるのではないでしょうか。
自民党が衆参選挙ともに敗北したのは、自民派閥の裏金問題に端を発する国民の政治不信にあるにもかかわらず、このまま不透明な資金の流れの温床となる企業・団体献金を残そうとしている自民党が維新と連立を組むとしたら、維新の政治改革に対する姿勢は見透かされているということになりそうです。
議員定数削減を持ち出したのも、政治とカネの問題から論点をずらす思惑があるのではないかとの見方もされているようです。
保険料負担を軽減する社会保障改革は医療サービスの水準切り下げにつながりかねないし、何よりも憲法の危機が強まると見ておかなければなりません。
多党化の状況では、連立協議を避けては通れないものの、参政党などにも接近しているとすれば、それは究極の数合わせによる政治の危機ではないかと思われてなりません。
| 10月15日「9月定例会閉会日に指定管理者公募へ」 |



14日の県議会9月定例会閉会日、多くの議員から議論のあった県立5施設の指定管理者を公募に切り替える方針を巡って、各施設に収益向上策を助言する有識者懇談会の設置費用58万円を一般会計補正予算案から削減する修正動議に対して賛成討論をさせて頂きました。
今朝の高知新聞にも、私が動議に賛成の立場で討論し、「自由度を高めるという大義名分での収益優先の公募に、お墨付きを与えることにつながる」と訴えたと記事にして頂いていましたが、賛成少数で否決されました。
なお、知事はこの議論を巡って、県のホームページに「令和7年10月14日 県立文化施設、公社等外郭団体に関する議論を巡ってーーー私の所感」として見解を示すという異例の対応をしています。
| 10月14日「閉会日本会議での討論」 |
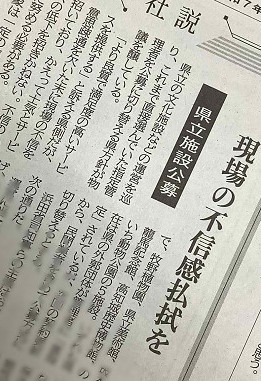 この連休中に、会派で議論を重ねたり、改めて県民の声を聞く中で、「第1号令和7年度高知県一般会計予算に対する修正案」について、賛成の立場から討論することの判断を県民の会会派として行いました。
この連休中に、会派で議論を重ねたり、改めて県民の声を聞く中で、「第1号令和7年度高知県一般会計予算に対する修正案」について、賛成の立場から討論することの判断を県民の会会派として行いました。
修正案は、第1号「令和7年度高知県一般会計補正予算」から県立施設を運営する外郭団体の自律性向上計画の策定支援を行う県立施設運営活性化懇談会の経費587千円を削除するものであります。
なぜ、修正案に賛成するのか、会派を代表して討論を行いますので、お聞きいただけたらと思います。
| 10月11日「自公連立に終止符」 |
 26年間に及んだ自公の連立に終止符が打たれることになりました。
26年間に及んだ自公の連立に終止符が打たれることになりました。
直接の理由は「政治とカネ」をめぐる自民の対応とされていますが、否定はされていますが、保守的な政治信条の強い高市早苗総裁が率いる新体制への懸念が背景にあることも大きく影響しているのではないでしょうか。
また、公明党内では連立のあり方に反発もあった中で、「与党内でブレーキ役になっている」となだめてきた経過がありました。
しかし、公明党は「平和の党」を掲げながら、2003年の自衛隊のイラク派遣、15年の安全保障法制の成立、22年の安保3文書改定など、自民が推し進める安保政策について、歯止め役として十分な役割を発揮してきたかと言えば、必ずしもそうではなかった面があったように思えます。
裏金問題での逆風も、自民の不記載議員に推薦を出すなど、自らの判断がもたらした側面があったことも、否定できません。
自民は公明票に助けられ、公明にとっては小選挙区で候補者を一本化できるなど、両者にメリットがあり、それを優先し連立維持を図ってきましたが、大枠で見ると基本的に矛盾があったのは否めないと思います。
それが今回の公明の連立離脱の大きな要因としては、「公明切り」とも言える動きを見せる麻生太郎元首相を執行部中枢に据え、公明側の不信感が限界に達したことにあったといえるのではないでしょうか。
いずれにしても、「クリーンな政治」「福祉」「平和」といった党の原点に公明党は立ち返り、自民党政治と対峙していくことが求められているのではないかと思います。
| 10月10日「特定利用港湾での軍事訓練には反対」 |
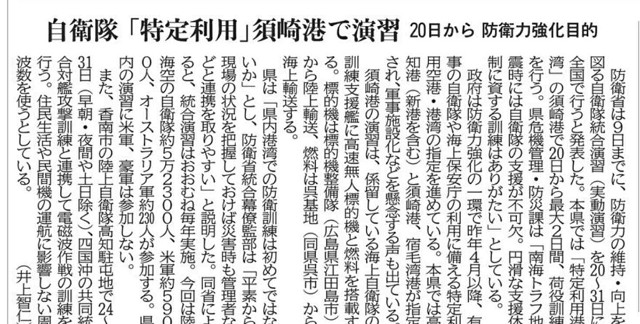 今朝の高知新聞にも、「特定利用港湾」の須崎港で20日から最大2日間、自衛隊の演習が行われるとの報道がありました。
今朝の高知新聞にも、「特定利用港湾」の須崎港で20日から最大2日間、自衛隊の演習が行われるとの報道がありました。
県のホームページによると「須崎港における荷役訓練(統合後方運用)」と「統合電磁波作戦訓練(四国沖で実施される共同統合対艦攻撃訓練に連携)」などが予定されていることです。
防衛省は9日までに、防衛力の維持・向上を図る自衛隊統合演習(実動演習)を20~31日に全国で行うと発表しており、規模も自衛隊52,300人、米軍5,900人、豪軍230名、さらには車両約4,180両、艦艇約60隻、航空機約310機と大規模な演習であり、その一環として本県の須崎港での訓練が行われるものです。
政府は昨年4月以降、有事の自衛隊や海上保安庁の利用に備える特定利用空港・港湾の指定を進め、本県では指定されている高知港(新港を含む)での訓練に続いて、須崎港で行われることとなり、軍事施設化などへの懸念は否めません。
報道によると、県危機管理・防災課は「南海トラフ地震時には自衛隊の支援が不可欠。円滑な支援体制に資する訓練はありがたい」としており、事前の調整で「県民の安心・安全」への留意を要請するに留めています。
「郷土の軍事化に反対する高知県連絡会」としては、このような姿勢の県に対して反対するとともに、次の点を申し入れることとしています。
「今回の自衛隊統合演習(実動演習)を中止するよう高知県として国に働きかけること。すくなくとも、事件・事故等が発生しないよう万全を期すとともに、仮に事件・事故等が発生した場合は、国の責任において迅速かつ適切に対処するとともに、高知県に速やかな情報提供を行うよう国に申し入れること。」そして、「県は、速やかに県民に丁寧に周知し、(仮に訓練が行われる場合)訓練周辺域の県民(輸送道路、須崎港、土佐湾沖の漁業者等)の安心・安全の確保に万全を期するよう国に申し入れること。」
さらには、「調整中である訓練内容について、変更も含めて迅速に情報提供を求め、そのことを県民に周知すること。」を求めています。
また、16日(木)12:15〜12:50をめどに県庁前・木曜市で抗議集会を開催し、20日(月)12:00〜(1時間程度)須崎港現地抗議集会を開催予定としていますので、ぜひ行動への参加もお願いします。
| 10月8日「10月2日質問の仮の議事録ができました」 |
 9月定例会も、明日のとりまとめ常任委員会、そして14日の本会議で閉会となります。
9月定例会も、明日のとりまとめ常任委員会、そして14日の本会議で閉会となります。
今定例会では、県の文化施設等の指定管理者公募問題で、県の文化行政のあり方やその拙速な議論について論議が交わされました。
また、昨年の9月定例会以降議論が始まった消防の広域一元化についても多くの議員が取りあげられました。
私も、一問一答形式での質問において、消防広域化一元化について取りあげましたが、時間も少なく掘り下げた質疑を行えませんでした。
答弁を含めて35分間でやり取りした仮の議事録をこちらからご覧いただけますので、関心ある方にご一読頂けたら幸いです。
| 10月7日「避難所から人への支援強化へ」 |

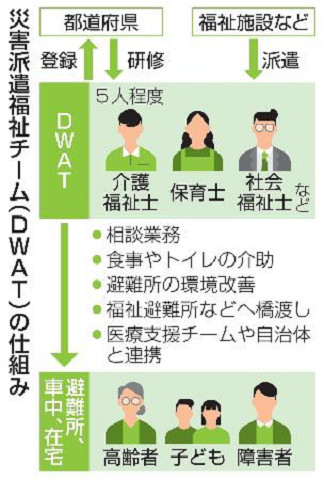 厚生労働省は、都道府県の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動に関する指針を改定しました。
厚生労働省は、都道府県の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動に関する指針を改定しました。
災害関連死が相次いだ能登半島地震を教訓にした災害対策基本法等の一部改正に伴い、ケアの対象を避難所だけではなく、車中泊や在宅避難の人に広げるなど、従来の避難所中心の「場所の支援」から「人の支援」へ転換されました。
DWATは、改定後の指針によると、災害時の具体的な活動は、避難所に加えて在宅避難や車中泊の人を対象とし、配慮が必要となる高齢者や障害者、子どもらの情報を把握し、相談への対応、食事や排せつといった生活上の支援を行い、避難所の環境改善、サポート体制が整った「福祉避難所」への移送、医療支援チームや自治体との連携も担うこととなっています。
私は、2日の一問一答による質問で、災害対策基本法等の一部改正に伴う質問を行い、本県として、今回の法改正を踏まえて、今後の復旧・復興フェーズでどのように生かしていこうと考えられているのか、知事に聞きました。
知事は、法改正で被災者に対する福祉サービスの提供が明記されたことによって、「高齢者などの要配慮者・在宅避難者などに、多様な被災者への福祉的支援を円滑に実施できるようDWATの体制強化に取り組んでいく。」ことになると述べた上で、県としての取組について次のように答弁しました。
県としては、「新たに創設された被災者援護協力団体と、被災時に連携できる体制を構築していくことで、迅速な支援につなげたい。」「南海トラフ地震による大きな被害にたいして、こうした取り組みを通じて、復旧・復興期のいわゆる災害関連死の防止、円滑な生活再建支援に生かしていきたい。」と考えています。
これらの備えの仕組みや取組の具体化を注視していきたいと思います。
| 10月6日「変われない自民党」 |

 石破氏の進退を巡る党内抗争に続き、12日間にわたる総裁選で政治空白は2カ月半に及び、結果として自民党新総裁に、その言動には極めて保守色の強い高市早苗氏が選出されました。
石破氏の進退を巡る党内抗争に続き、12日間にわたる総裁選で政治空白は2カ月半に及び、結果として自民党新総裁に、その言動には極めて保守色の強い高市早苗氏が選出されました。
しかも、総裁選では「政治とカネ」問題を巡る危機感の欠如や、新総裁選びを巡る派閥政治や長老支配は相変わらずで、自民党が党の体質改革に本気で取り組んでいるとは言い難い状況を見せつけられました。
自民党は、参院選総括で「国民の信頼を損なう大きな要因」と分析した派閥の裏金事件について、高市氏は決着済みとして、裏金議員の要職起用にも含みを残し、金権腐敗の元凶とされてきた企業・団体献金の抜本改革には総裁候補5人の誰も踏み込むことがありませんでした。
そして、高市氏と小泉氏との決選投票では、解消されたはずの派閥中心の動きも表面化しました。
このような自民党の金権体質や派閥政治が全く変わらない様相を見せつけられて、「解党的出直し」や「#変われ自民党」も単なるスローガンで絵空事に過ぎないのではないかと思わざるをえません。
高市氏の歴史認識や言動は、対立を煽りかねないだけに、慎重な外交姿勢が求められるとともに、外国人政策の厳格化には違和感を覚える国民も多くいます。
一部のトラブルや混乱の責任を外国人に転嫁せず、共生を目指す政策こそ求められていると言えます。
また、高市氏は新総裁に選ばれた後の最初の挨拶で、「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」と述べ、石破氏から「あそこまではっきり『ワーク・ライフ・バランスをやめた』と言われると大丈夫かという気がしないではない」と苦言を呈される始末でした。
過労死防止法は国会の全会一致で成立し、国をあげてワーク・ライフ・バランスを推進している中で、高市氏は『懸命に働く』という意図だったかもしれないが、法律をないがしろにする発言で問題だとの思いを抱いた方々も多かったと思います。
やはり、この新総裁は危ういと言わざるをえません。
| 10月3日「一問一答、時間が足りず深堀できず」 |
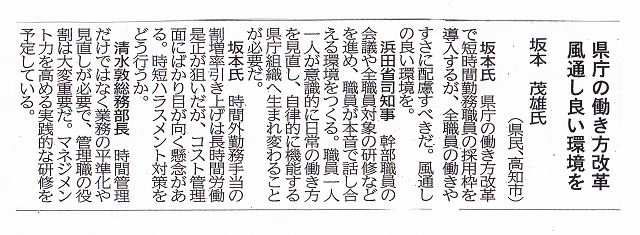


昨日の一問一答では、やはり時間が足らず、最後の方は端折りながらの質問で、答弁に対して掘り下げることもできず残念でした。
新聞の記事では、県庁の働き方についての二問が取りあげられていましたが、他の質疑についてもテープ起こしを行いますので、できたら仮の議事録としてご報告させて頂きます。
昨日も、文化施設などの指定管理者制度の見直しによる公募の在り方について、見直しや白紙化を求める質問が多くありましたが、これまで制度発足以来続けられてきた「直指定」が悪の元凶かのような姿勢で、聞き入れることはありませんでした。
委員会審査で、さらに議論されることとなります。
今日も、一問一答が続き、来週は常任委員会での付託議案の審査が行われます。
| 9月30日「一問一答、35分の持ち時間で17問は欲張りすぎ」 |
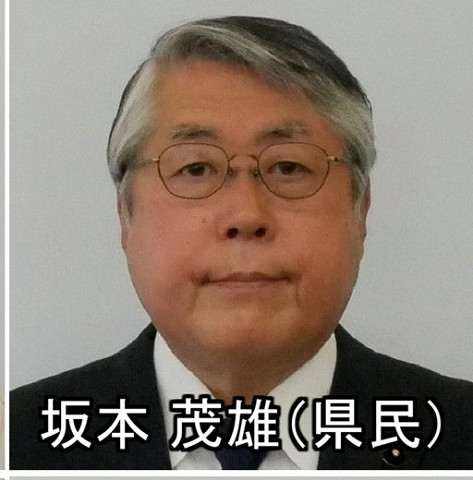 いよいよ10月2日(木)11時25分からの一問一答による質問項目が、ほぼ決まりました。
いよいよ10月2日(木)11時25分からの一問一答による質問項目が、ほぼ決まりました。
初日の代表質問のやりとりを踏まえて、質問を一部変更したものもありますが、議場またはオンラインでの中継傍聴などよろしくお願います。
1 県庁の働き方改革について
(1) 高知県庁の働き方について
2 正職員の「短時間勤務職員」採用に伴う職場環境について
(1) 全ての職員が働きやすい環境の整備について
(2) 職場全体が風通しの良い働きやすい環境の追求について
3 時間外勤務手当の割増率の時限的な引き上げについて
(1) 時短ハラスメント対策などの管理職員研修について
(2) 管理職員を含む職員の時間外勤務に対する意識変化の促進の検証について
4 精神障害のある方の医療費助成について
(1) 県の医療費助成制度の案や要綱案等の検討について
(2) 今後の関係者会議について
(3) 国としての医療費助成制度の具体化について
5 消防の広域一元化について
(1) 市町村の過大な財政負担支援の目安について
(2) 県の財政支援内容が明確にされる時期について
(3) 県の方向性を示す時期について
(4) 知事の答弁に対する考えについて
6 災害対策基本法等の一部改正について
(1) 法改正を踏まえた今後の本県の取り組みについて
(2) 災害ケースマネジメントの実施体制にかかる手引きの改定について
(3) 災害中間支援組織の立ち上げに向けた取り組みについて
(4) 広域避難の円滑化に向けた財政的支援について
(5) 一時滞在後の生活再建支援などに係る課題について
| 9月29日「国勢調査不正で回収率の低下懸念」 |

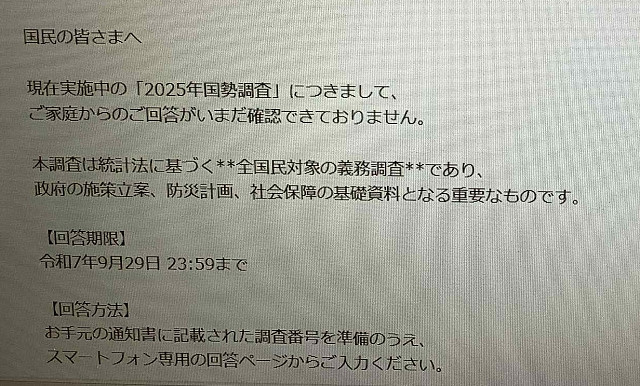 5年に1度行われる国勢調査の調査票配布が20日から始まっており、ご近所の調査員の皆さんも暑い中ご苦労して訪問されています。
5年に1度行われる国勢調査の調査票配布が20日から始まっており、ご近所の調査員の皆さんも暑い中ご苦労して訪問されています。
そのようにご苦労されている調査員の方がいる一方で、調査をかたって電話や訪問で個人情報を聞き出そうとする手口が見られるとして、国民生活センターは、注意を呼び掛けています。
今年に入ってからは、固定電話に自動音声のような声で電話があり、番号を選択するよう言われたとする相談があったり、メールでの調査依頼は行っていないが、調査をかたった不審なメールも多く確認されているとのことです。
私の所にも時々、メールには回答すると記念品がもらえるなどと記され、添付されたURLをクリックするようになっているものも来ています。
調査員さんは専用の手提げ袋と調査員証を携帯し、書類を配布する際には世帯主の氏名や調査票の枚数を確認することはあっても、年収や預貯金額などの資産状況を聞くことはありませんので、不審だと思ったらすぐに話をやめ、場合によっては自治体の窓口や消費生活センター、警察に相談されたらいかがでしょうか。
国勢調査の結果は、国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で欠くことのできない基礎データとしても利用されるものです。
日本唯一の「全数調査」で、全世帯に調査書類が配布されるもので、1920年に始まり、5年に1度、10月1日を調査期日に実施され、今回で22回目となります。
そのように極めて大事な調査でありながら、最近は回収率が低下傾向にあり、前回の未回収率は16.3%となりました。
このように不正に利用されると、さらに回収率が低下するのではと懸念せざるをえません。
| 9月27日「発生確率の変動より『いつ起きても不思議でない』意識の備えを」 |

 今後30年以内に「80%程度」とされていた南海トラフ巨大地震の発生確率が、政府の地震調査委員会は、新たな研究などを踏まえ「60%から90%程度以上」と「20%から50%」の2つの確率を新たに算出し、昨日から報道されています。
今後30年以内に「80%程度」とされていた南海トラフ巨大地震の発生確率が、政府の地震調査委員会は、新たな研究などを踏まえ「60%から90%程度以上」と「20%から50%」の2つの確率を新たに算出し、昨日から報道されています。
今まで「80%程度」とされていた発生確率の上と下の範囲で、しかも2つの確率が併記されるとなると国民は困惑するだけではないでしょうか。
この二つの確率の根拠の違いがどうかということなどより、予測は不確かなもので、自治体も住民もこの数値に振り回されず、いつでもどこでも起きる前提での備えが大切だということを再確認しなければなりません。
下知地区にも10年前に取材に来られた朝日新聞の佐々木英輔論説委員は「計算方法を変えただけに過ぎず、実際の地震が近づいたわけでも、遠ざかったわけでもない。過度におびえたり、安心したりしてはいけない。数字に振り回されることなく、各地で着実に備えを進めるほかない。」と述べられています。
また、NHKのニュースでは、関谷直也東京大学大学院教授は、「数字だけを強調することにとどまるのではなく、最終的に防災につながる方策まで考えた上で情報を発信することが必要だ。」と指摘されています。
現在、国の南海トラフ地震被害想定を受けて2年前に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定について見直しがされていますが、その際に、検討委員のお一人である京大防災研の矢守委員は「この想定で諦めるのではなく、行動計画に結びつけ、県民の行動に結びつけて欲しい」と述べられていたが、そのことにも通ずるものだと思ったところです。
とにかく、今までもいつ起きても不思議ではないとの思いで行ってきた備えを確かなものにしていくことが、求められています。
| 9月26日「質問戦いよいよ開始」 |
 10月2日(木)、一問一答形式の質問戦で3番手として、11時25分から登壇することが、今朝の議会運営委員会で確認されました。(写真は昨年9月定例会の一問一答のものです)
10月2日(木)、一問一答形式の質問戦で3番手として、11時25分から登壇することが、今朝の議会運営委員会で確認されました。(写真は昨年9月定例会の一問一答のものです)
予定している質問項目には、今日からの代表質問と重複したものもありますので、答弁を聞いてから、通告までの間に変える可能性もありますので、その際には最終通告項目をお知らせすることとします。
とりあえず、現時点で予定している質問の大項目は以下の通りです。
1 県庁の働き方改革について
2 正職員の「短時間勤務職員」採用枠について
3 時間外勤務手当の割増率の時限的な引上げについて
4 精神障害のある方の医療費助成について
5 消防の広域一元化について
6 災害対策基本法等の一部改正について
| 9月23日「「3.11を学びに変える」課題と向き合い続けなければ」 |
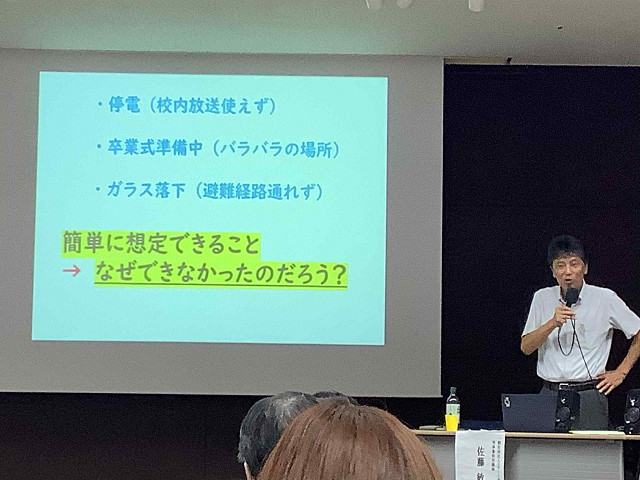

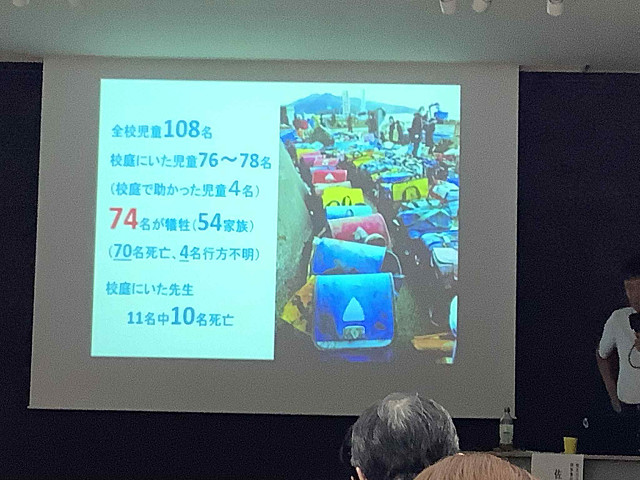
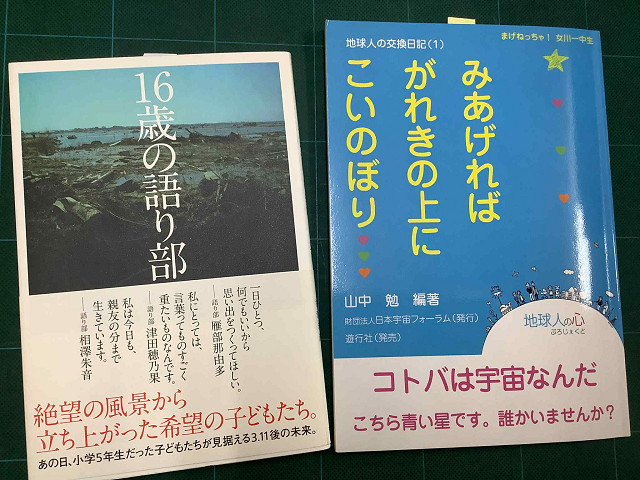
宮城県の元中学校教諭佐藤敏郎先生のお話を初めて聞かせて頂いたのは、2017年潮江中学校でのことでした。
2022年には、次女を亡くされた大川小学校で語り部としての佐藤先生から現場でお話を聞かせて頂きました。
そして昨日は、令和7年度高知市社会福祉法人連絡協議会災害対策連携部会主催研修会「3.11を学びに変える」と題して聞かせて頂きました。
宮城県女川中での被災後、深い悲しみの中にいた中学生達が、素直な気持ちを無理して心の中に閉じ込めておくのではなく、今の素直な気持ちをコトバに紡いでみることで俳句作りの授業をされた中から、ご紹介頂いた紡がれたコトバと向き会い続けなければと思わされました。
「夢だけは 壊せなかった 大震災」「みあげれば がれきの上に こいのぼり」
大川小で、「救えた命」「救わなければならない命」「救いたかった命」を救えなかったことから考えなければならないことは何か。
大川小では、助かるための手段も情報も知っており、時間もあったが、「いくら避難や救う条件としての時間や手段、情報があっても、組織として意思決定できず避難ルートの判断ミスをするのではなく、判断や行動につながるような普段からの意識が大切」であることも突きつけられました。
3年前に、議会の出張で大川小学校で語り部をされていた佐藤先生からお話を伺ってきたことを、下知で話す機会があるたびに伝え続けたいと思っていることがあります。
「裏山が命を守るわけではない。裏山に逃げる判断、行動が命を守ることである。」という佐藤先生の言葉を下知に置き換えて「津波避難ビルが命を守るわけではない。津波避難ビルに逃げる判断と行動することが命を守ることにつながる」と伝えさせてもらっています。
今日は、その判断と行動のスイッチを押すためにはどうするのかということを3.11からどう学ぶのかと質問させて頂きました。
先生が、講演の中で言われていた「防災とは、ただいまを言うことです」「行ってきますと出かけたら、必ずただいまを言う」「それが毎日続いてほしい」ということが、津波避難ビルに登って命を守って「ただいま」を言うことなのだと教えて頂いた様に思えます。
先生が紹介してくれた静岡県沼津市のサッカーチームの子どもたちが、「津波の次の日も、このメンバーでサッカーをしたい」と言われたが、当たり前のことを次の日も続けることが防災なのだということに通じると思われました。
みんなで助かって喜ぶ未来。
ハッピーエンドから逆算する希望の防災。
子どもたちと一緒に考えたいお話ばかりでした。
| 9月20日「課題の多い9月定例会開会」 |

 9月定例議会が昨日19日に、開会しました。
9月定例議会が昨日19日に、開会しました。
一般会計の総額で10億8000万円余りの補正予算案など、39の議案が提出されました。
特に、今定例会では、6月定例会での報告以来課題となっていた美術館など県立5施設の指定管理者を県の外郭団体への直指定から公募に切り替えるという問題を巡って論戦の課題となることが注目されています。
知事は、提案説明で、改めてその目的を「自主事業の実施と利益処分の自由度を増し、財団などの創意工夫を促すことにある」と強調し、「県民や利用者に、より良質で満足度の高いサービスを提供することにつなげたい」と訴えていました。
しかし、知事が、直指定の外郭団体にある職員給与の上限や剰余金の返納といった運営上の制約については、「無競争で県立施設を運営する、いわば特権的な地位を利用して、県直営の場合以上の報酬や利益を享受することは適当でないという考え方で課せられてきた」との言及には、違和感を感じざるをえませんでした。
いずれにしても文化施設をどのような形で県民に受け止めてもらうか、付加価値の高いサービスを提供することがどのような形で行われるのか、深く掘り下げた議論が交わされるか問われています。
私も10月2日に一問一答で質問機会がありますが、その質問準備を急がなければということで、少々焦っています。
また、近づいたら質問項目などを整理して公表しますので、オンライン傍聴などよろしくお願いします。
| 9月19日「思いやる心を育てて交通安全」 |





「秋の全国交通安全運動」が、9月21日(日)から9月30日(火)の10日間実施されます。
明日9月20日(土)は 10時~15時まで、中央公園で「第33回交通安全ひろば」が開催されます。
「交通安全クイズラリー」や、参加した子どもたちに子ども安全免許証が交付される「交通安全標識ビンゴゲーム」、「白バイ・パトカー・消防車・赤バイ・ボンネットバス・ミニ電車の乗車体験」、「無料おもちゃすくい」、「リサイクル自転車即売会」などのブースが設けられますが、私たちも昭和校区交通安全会議のメンバーはシートベルト着用体験コーナーでお世話をしています。
皆さんも、ぜひお越し下さい。
今秋の全国交通安全運動は以下の項目を重点目標として、交通安全の意識啓発と事故ゼロに向けて取り組んでいきます。
【重点目標】
1 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
●交通ルールの理解と遵守の徹底
●ながらスマホの根絶
●飲酒運転の根絶
●妨害運転等の防止対策
●夕暮れ時以降の交通事故を防止する取組
●運転者の歩行者優先意識等の徹底
●後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
●高齢運転者の交通事故防止対策
●二輪車の運転者に対する広報啓発
●自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底と新たなルールの周知
●自転車利用者の乗車用ヘルメット着用促進と安全確保対策
★自転車安全利用五則★
①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
これらをしっかり守ってくれたら、失う命やケガをされる方が一人でも少なくなることと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。
今日から9月定例会が始まりますが、明日の交通安全ひろばのお手伝いや21日からは、早朝の街頭指導も行いながらの10日間となりますので、議会質問の準備とかとあわせて慌ただしい日が続きます。
| 9月17日「難病患者さんたちの意思伝達権利の保障を」 |
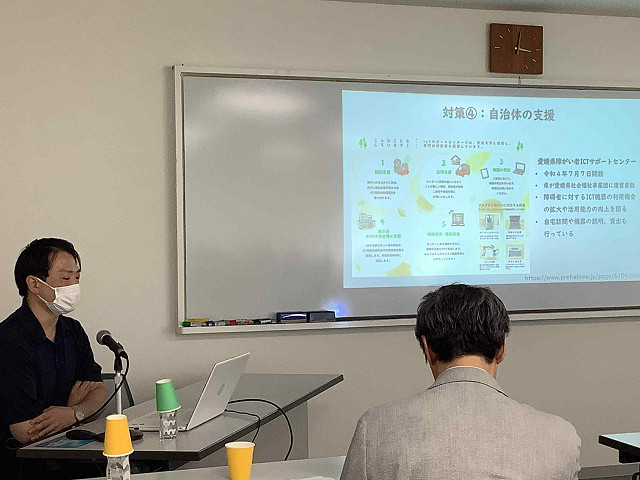
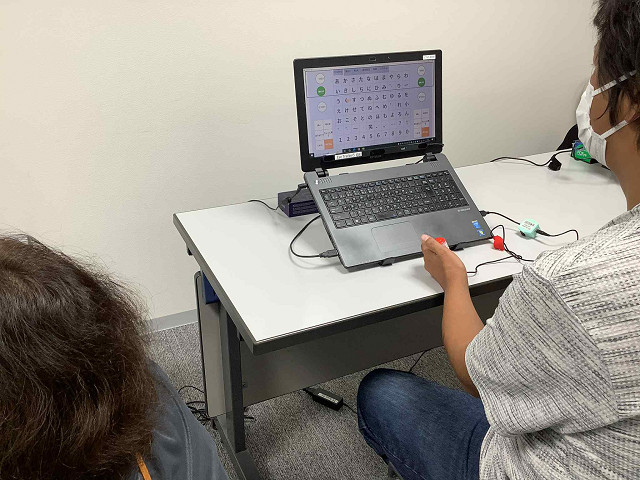
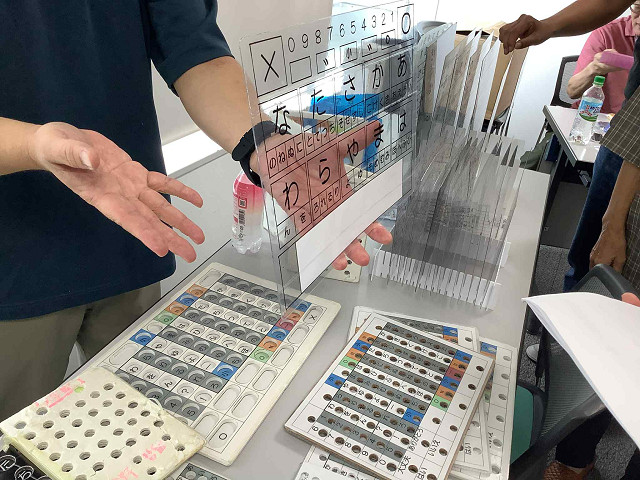
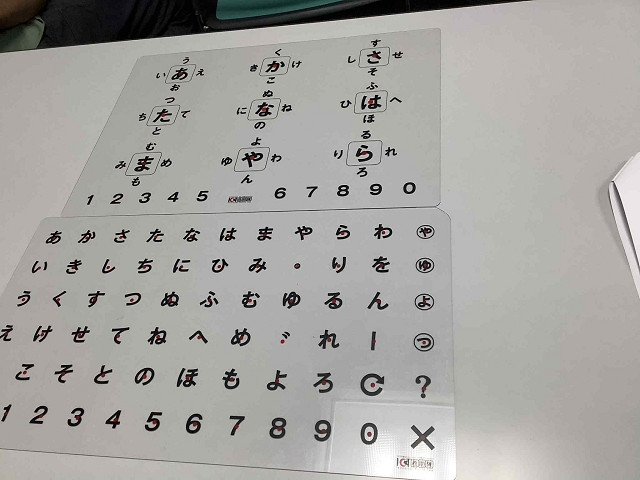
13日から14日にかけて、難病団体連絡協議会の「地域で支えようICTコミュニケーション」をテーマに研修会が開催されました。
これは、難病患者さんに対して、地域でのコミュニケーションの支援が出来る体制つくりに向けた研修会で、意思伝達装置や支援機器の体験と実践に向けた支援の仕組みづくりに向けた講演を聴講するとともに、機器の操作の体験もさせて頂きました。
また、「神経難病のローテクコミュニケーション」について、医療機関で実践されている言語聴覚士さんの患者さんの「伝えたい」を患者さんの立場に立って支援の工夫と改善がどのようにされることが必要なのかなど貴重な話ばかりでした。
この講演とあわせて、実際の文字盤を使って文字確認をする体験もしながら、神経難病患者とコミュニケーションをとり続けるために大事なことについて学ばせて頂けました。
先進的な取り組みから、「神経難病患者とのコミュニケーションを取り続けるため」に、「病気を見るのではなく、『人』を見る」「サインを見逃さない」「声(音声)による会話より時間がかかるため、ゆっくりとした時間の流れを楽しむ気持ちが重要」であり、「適切なコミュニケーション手段」「本人のコミュニケーション意欲」「支援者側のあきらめない、決めつけない気持ち」があればコミュニケーションを取り続けることは可能ということをしっかりと踏まえたローテクとハイテクを上手に併用してICTコミュニケーションを地域で支えていくことの重要性を痛感させられました。
こういう全国の状況を見た時に、本県では難病患者がどこにいてもコミュニケーションがとれる体制が未確立で、ICTコミュニケーションについて支援者側の知識啓発やICTコミュニケーション機器の提供支援などの体制をどのように確立するか、本県では県をはじめとした公的支援のありかたが求められています。
参加者の情報交換会でも、支援者側の人材育成や相談・支援拠点との連携・支援機器の提供サービスの事業化などモデル事業化をはじめとして、県下に横展開していくことへの要望が出されており、難病患者さんたちの意思伝達の権利を保障するための支援の仕組みを築くため、県の課題を明らかにしながら取り組んでいきたいと考えさせられた研修でした。
| 9月15日「高齢者が話し集える場を」 |
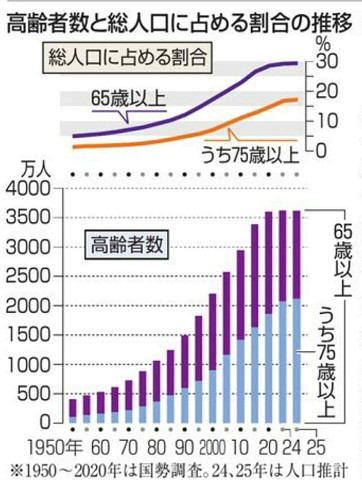
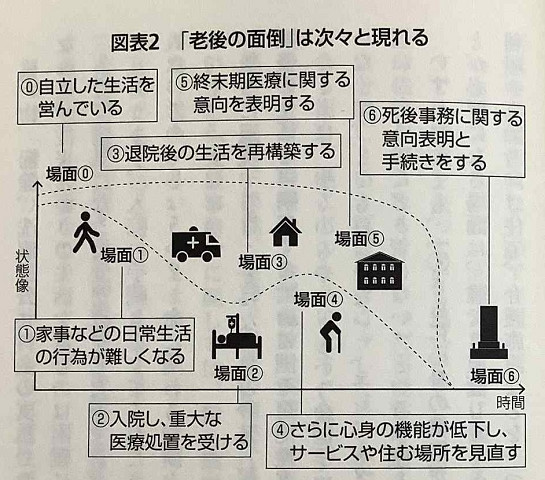

今日9月15日は敬老の日です。
数日前から、地域の民生委員さんが、地域の後期高齢者宅を訪問して、お祝いのお菓子を配布されています。
そんな県内には、100歳以上の高齢者は1031人(15日現在)で昨年同期に比べて4人増え、9年連続で過去最多を更新しています。
人口10万人当たりの人数で見ると、高知県は157.16人で、都道府県別では13年連続最多の島根県(168.69人)に続く2位で、全国平均は80.58人となっています。
65歳以上の高齢化率も高知県(36.6%)は2位で、秋田県(39.5%)に続く高さで、3位は青森、徳島県(35.7%)で、全国平均は29.3%となっています。
年齢を重ねても元気はつらつ、いきいきと活動する年配の方々が多く、地域活動のリーダーとしても活躍されている方が多くおられます。
元気はつらつとした方が多くを占める「65歳以上」を高齢者とみなす考え方は多くの国で共通していますが、始まりは1956年の国連の報告書だそうです。
既に70年近くがたち、日本人の平均寿命は20年ほど延びた中で、高齢者の年齢見直しは社会保障や定年など多くの制度に影響し、慎重な議論が必要になっていくのは当然かもしれません。
ただ、半世紀以上も前に生まれた「高齢者」の概念を私たち一人一人が問い直すことは、老年の暗い側面が強調されがちな社会の空気を変え、気持ちを前向きにするきっかけにもなりますが、そのことを支えていく社会の仕組みや制度の変革もあわせた議論が必要になろうかと思います。
高齢者が働く理由は、生きがいややりがいを求めるだけでなく、「収入のため」が半数を超えている背景もしっかりと捉えておく必要があります。
諸物価は高騰し、介護保険料も上昇が続く中、そもそも低年金で、働かなければ生活できない人も多い中、支え手として頼りにするだけでなく、老後の生活を支える制度の充実も欠かせません。
お一人お一人が元気な高齢者は、以前より増えているかもしれませんが、生き生きとした暮らしを遠ざけている「孤独」の課題と向き合わざるをえない高齢者の方々は多いのではないでしょうか。(図表2は沢村香苗著「老後ひとり難民」より)。
高齢者の単身世帯は増え続け、何日も誰とも話さないという人も少なくありません。
私のご近所でも、話し合いのできる場が欲しいとの声もあります。
近所の公園で毎朝ラジオ体操をしている高齢者グループの方がいますが、ラジオ体操が終わった後は、それ以上の時間をかけて、おしゃべりタイムが続きます。
機会あるごとに紹介させて頂く近所の町内会とマンションで隔月一回行っている「おしゃべりカフェ」は、平時からの語らいの場として、顔見知りの関係や地域の支えあいの関係を築き、いざという時には津波避難ビルに避難したり迎え入れたりできる関係を築かれています。
そんな「話ができる」「支えあう」地域力づくりにもつながるきっかけを、考えられる敬老の日になればと思います。
| 9月14日「ひきこもりに寄り添うとは」 |

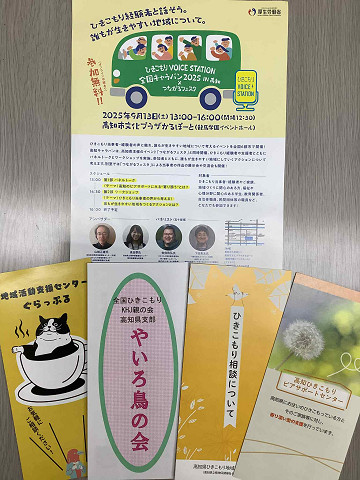 昨日は、 ひきこもり状態にある方やそのご家族が孤立することなく、地域社会においてひきこもりに関する理解を深め、相談しやすい環境づくりを進めるための「ひきこもりVOICE STATION 全国キャラバンin高知」に、参加していました。
昨日は、 ひきこもり状態にある方やそのご家族が孤立することなく、地域社会においてひきこもりに関する理解を深め、相談しやすい環境づくりを進めるための「ひきこもりVOICE STATION 全国キャラバンin高知」に、参加していました。
「かるぽーと」で開かれた会場には、オンラインも含め約90人が参加されていて、「高知のピアサポートにみる“寄り添う”とは?」とのテーマで、高知らしい元当事者の体験談などを聞かせて頂きました。
ひきこもり当事者だったピアサポーターが仰っていましたが、上から目線の「寄り添い」ではなく、「一緒に楽しめることを取り戻す」ことが「寄り添う」ことでもあり、「履歴書は真っ白であっても、その間に苦しんでひきこもったことに価値があると思って欲しいし、それが生きていくうえでの武器になるような社会になればいい」との言葉に共感できる寄り添いが必要だと感じさせられました。
| 9月13日「深く議論を」 |
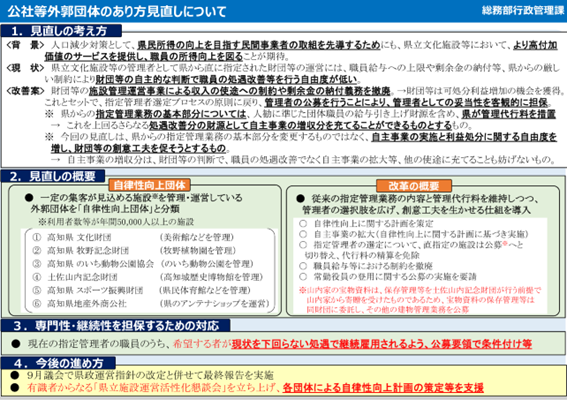 高知県は、指定管理者として外郭団体が運営している牧野植物園など県立5施設について、管理者を直接指名する「直指定」から、民間業者を含めて公募とする方針を6月定例会で示しました。
高知県は、指定管理者として外郭団体が運営している牧野植物園など県立5施設について、管理者を直接指名する「直指定」から、民間業者を含めて公募とする方針を6月定例会で示しました。
しかし、事前に対象となる施設との十分な意見交換もされておらず、現場に混乱を招き、パブリックコメントでは、301者から延べ延べ794件の意見出されました。
その多くは、県の考え方に異議を唱えるものであり、「直指定から公募への切り替えによる雇用不安、人材確保が困難、専門性が低下するという趣旨」「制度移行に際して、関係団体等との意見交換の機会を設けるべきという趣旨」「制度の枠組みなどの詳細を提示するべきという趣旨」「公募による管理者の選定ではなく、県の直営体制を検討すべき」「県が代行料の削減など、財政負担の解消を目的としている、または結果としてそうなってしまうという趣旨」「選定の際は単なる運営能力だけでなく、学術的・公共的視点から審査すべきという趣旨」などであり、県としてもこれらの声に応えて、「現在の指定管理者の職員のうち、希望する者が現状を下回らない処遇で継続雇用されるよう、公募要領で条件付け」など何らかの見直しをせざるを得ませんでした。
また、高知城歴史博物館の山内家の宝物資料等の保存管理の業務は公募には馴染まないことから、この部分は県の直営(財団に委託予定)とし、事業の企画・広報・運営、施設の利用許可、施設の利用料金の収受、施設・設備の維持管理は公募による指定管理とするなどの見直しがされています。
他施設も含めて、これだけの混乱を現場に残しながらの公募制度導入は今後に禍根を残すことになるのではないでしょうか。
職員の処遇改善や県民が文化行政・サービスを享受できるようにするための責任を県が果たすためにはどうするのかもっと深く掘り下げた議論をすべきではないでしょうか。
高知市との間に混乱を招きかねない新体育館構想についても、観光やイベントが優先されるあまりに県民の体育向上などが軽視されかねない議論などが懸念されるような本質を見失いがちな議論では、県民の理解と納得が得られないのではないでしょうか。
8月末に発刊された高知県立高知城歴史博物館令和6年度年報の「はじめに」の項には、次のようなことが書かれています。
「高知城歴史博物館としては、不可欠とすべき活動の柱は2つある。」「1つは学問を基礎にした活動」で「博物館が学問・科学の発想と方法を捨てる事はありえないと言う事。」
そして、二つ目は「公共への還元」ということで「公が設置する施設は、国民・県民のものであり、博物館の機能と活動は必ずやそこに還元される必要がある」として、「文化振興への幅広い寄与についても専門職員を配置し、地域との連携活動の拡充を検討し始めている」と言うことです。
いずれにしても、「職員の不断の蓄積と、活動を受け入れ支持してくださる県民の皆さんあってのものであり、人々の営々たる暮らしの軌跡を振り返り、今に生かす歴史博物館の活動はじっくりと腰を据えての継続的取り組みが不可欠であります。」と渡辺館長は述べられています。
まさに、今回の高知県が提案した施設公募方針に対する自律的向上団体として名指しされた文化施設などを代表した見解ではないかと思われます。
| 9月12日「子どもの命を奪わぬために」 |
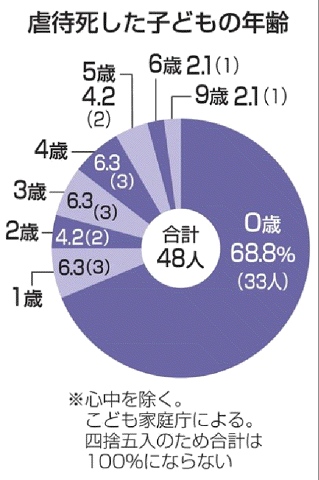 こども家庭庁は、2023年度に虐待を受けて亡くなったことが分かった子どもは65人だったとする検証結果を昨日発表しました。
こども家庭庁は、2023年度に虐待を受けて亡くなったことが分かった子どもは65人だったとする検証結果を昨日発表しました。
前年度よりは7人減ったものの、心中を除く48人中、0歳児が33人で68.8%を占めており、0歳児の占める割合は、16、20両年度の65%を超えて過去最多となりました。
特に0歳児のうち、生後24時間に満たない「0日児」は16人で、08年度に次いで過去2番目に多くなっています。
16人の死因は、7人が出生後に放置されたことによるもので、4人が窒息させられており、5人は不明などでした。
また16人のうち、医療機関の関与があったのは1人だけで、ほかは公的機関の関与もなかったという結果になっています。
07年から23年3月までの心中事例532人にでは、死亡した子どもの年齢は6歳以上が271人(50.9%)で、主たる加害者は実母が356人(66.9%)、実父が100人(18.8%)となっています。
加害動機は、実母のみの場合は「保護者自身の精神疾患、精神不安」36.2%、「育児不安や育児負担感」25.7%。実父のみの場合は「夫婦間のトラブルなど家庭に不和」29.2%、「経済的困窮」20.8%でした。
虐待死を検証するこども家庭庁の専門委員会委員長の明星大の川松亮教授は「相談するにはハードルがあると感じると思うが、人に頼ることも大事だと伝えたい」と話されています。
これまでにも、相談事や悩みを抱えた方々が「助けて」と言える社会を築こうと常に訴えてきたが、改めてそんな社会が求められていることを感じざるをえません。
ましてや、「助けて」と言えない乳幼児の命を守らなければならない親の悩みに寄り添うためにもそんな社会が求められているのではないでしょうか。
| 9月10日「党内事情でさらに長期の政治空白へ」 |
 自民党は昨日の総務会で、全国の党員・党友も投票する党員参加型(フルスペック型)で総裁選を実施することを決定しました。
自民党は昨日の総務会で、全国の党員・党友も投票する党員参加型(フルスペック型)で総裁選を実施することを決定しました。
このことによって、10月4日までの投開票日まで、国民不在の長期の政治空白が作り出されることとなります。
自民はこれまで、総裁の任期中に辞任した場合は「政治空白」を避けるため、総裁選は党員投票を省いた「簡易型」で行うのが通例だったとされており、2020年、安倍元首相が辞任を表明した際などは、そこから2週間あまりで菅義偉氏を新総裁に選出した経緯もあります。
そうした経緯を踏まえてもなお、党員参加型を選択したのはなぜなのでしょうか。
国政選挙の連敗により、衆参両院で少数与党となったことを重くみた時、次の選挙も見通した顔のすげ替えをする必要があったからではないでしょうか。
本来なら、選挙前に国民の関心の高い物価高対策や政治とカネの問題に手も付けず、国民の人心が離れた結果を受けて、早く向き合わなければならない課題を先送りにしてでも、フルスペック型で臨むのは、真に国民に向き合うのではなくまずは離れかけた党員の支持をつかみ直したいということだけなのだと見透かされてしまいそうです。
想定されるメンバーは1年前とほぼ同じ顔ぶれの顔見世興行であり、このような総裁選を通じて「解党的出直し」を実現できると思っているとすれば、いよいよ見切りをつけられるのではないでしょうか。
| 9月8日「自民総裁党内抗争・国民不在の退陣劇」 |
 衆参両選挙で民意の厳しい審判を受けながら、政権トップとしてけじめをつける決断が遅れ、政治の混乱を深めたその責任が求められる中で、ついに昨日石破茂首相が退陣を表明しました。
衆参両選挙で民意の厳しい審判を受けながら、政権トップとしてけじめをつける決断が遅れ、政治の混乱を深めたその責任が求められる中で、ついに昨日石破茂首相が退陣を表明しました。
その理由として、「党内に決定的な分断を生みかねない」などと言われているが、賛成多数で事実上の「総裁リコール」が成立する可能性が高まっていたことの回避であり、そのような状況を作り出した自民党内の内紛によるものと言わざるをえません。
しかも、退陣は当初から不可避の情勢であり、首相の進退を巡る分断は深刻化し、事実上の政治空白が50日以上も続けた石破氏をはじめとした自民党の責任は大きいものがあります。
ガソリンの暫定税率廃止に向けた与野党協議は進まず、物価高対策を巡っても、現金給付を公約した与党と、消費税減税を掲げる野党の溝は埋まらないままとなっています。
しかし、政治空白は党内の総裁選によってさらに引き延ばされるが、この間、「石破おろし」を主導した裏金問題で党への信頼を失墜させた旧安倍派をはじめ、旧統一教会とつながってきた面々が復権を果たしたりするようであれば、自民党の内紛は、復権をめざす権力闘争でしかなかったといえます。
まさに、それは、参院選総括で「解党的出直し」を誓ったことを裏切り、国民の信頼回復など到底得られるはずもなく、政治不信を強めるだけになるでしょう。
国民は、自民党が「解党的出直し」を図れるような論戦がされるのか、旧態依然たる内紛を見せつけられるのか、注視していることを自民党は肝に銘じておかなければなりません。
| 9月7日「ぼうさいこくたいに多様な視点で学ぶ」 |

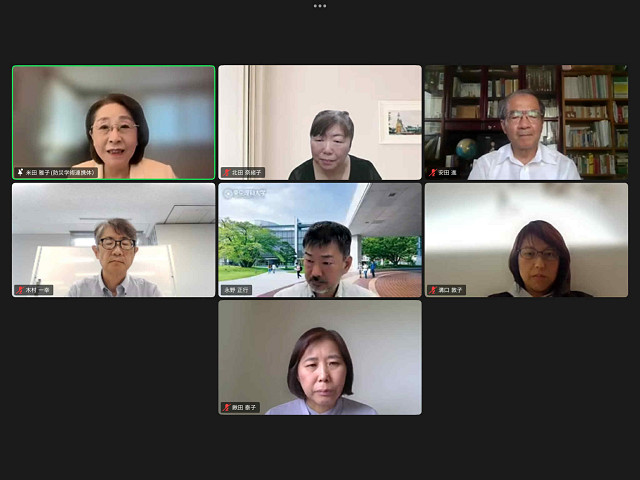
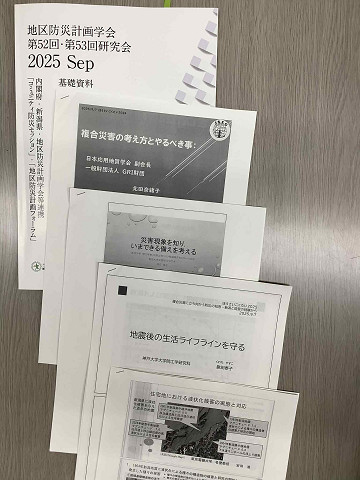
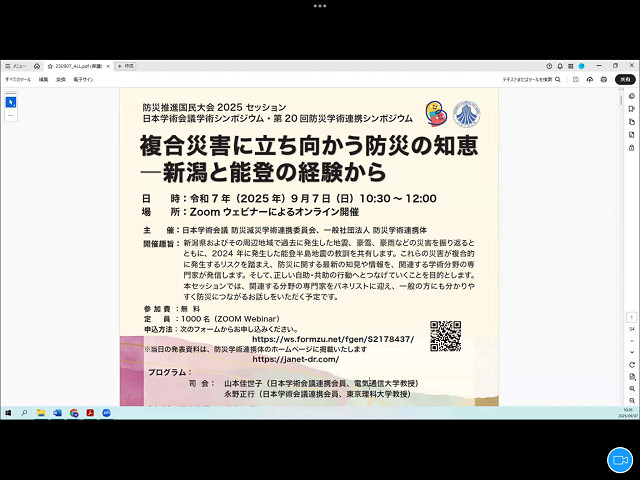
昨日から、「ぼうさいこくたい2025in新潟」が開催されており、高知からも参加されている方々がおられます。
私は、仕事が溜まっていますので、昨日から今日にかけて、三つのセッションにオンライン参加しています。
まずは、昨日14時30分から内閣府・地区防災計画学会連携「コミュニティ防災セッション」、そして16時30分からは「地区防災計画フォーラム」で、皆さんの貴重な話を聞かせて頂きました。
そして、今朝は10時30分から先ほどまで、日本学術会議 防災減災学術連携委員会・一般社団法人 防災学術連携体主催の「複合災害に立ち向かう防災の知恵―新潟と能登の経験から」に参加させて頂きました。
いずれもオンラインで数百名という多数の参加のようでした。
午後からは、下知地区減災連絡会事務局会やマンション防災会役員会のレジュメ作成に着手しています。
| 9月6日「最低賃金は誰のために定めるのか」 |
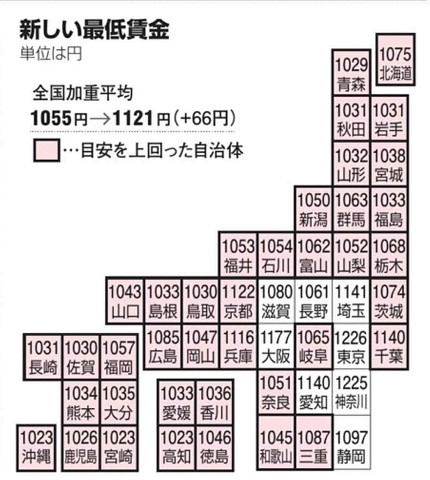
 昨日、最低賃金の今年度の改定額が47都道府県で決まったことが、報道されています。
昨日、最低賃金の今年度の改定額が47都道府県で決まったことが、報道されています。
歴史的な物価高を踏まえ、初めて全都道府県で1000円を超え、39道府県で目安額を上回り、新しい最低賃金の最高額は東京の1226円、最低額は高知をはじめ、宮崎、沖縄の1023円で最高額と最低額の差は前年より9円縮んで203円となっています。
全国で高水準の引き上げが相次いだ一方、準備期間が必要だなどとして、発効時期を遅らせる動きが目立ち、例年10月発効が通例だが、通例どおりは栃木など20都道府県にとどまり、秋田は最も遅い来年3月31日となりました。
同様の動きは秋田にとどまらず、今年は27府県が11月以降となり、福島、徳島、熊本、大分は来年1月に越年し、78円引き上げる群馬は来年3月1日に発効します。
発効遅れの主な要因としては、最低賃金の急激な引き上げで、政権側も目安を上回る引き上げを求める中、交換条件のように各地の審議では使用者側の負担軽減が最大の焦点となり、年末の働き控えを防いだり、賃金体系の変更のための準備期間を要するために発効日を遅らせる必要が生じたとされているが、発効の遅れは、労働者の手取りの目減りにつながりかねません。
北海道大学安部由起子教授の試算によると、10月から1年間の収入を考えた場合、発効日を年度末にした秋田は、年間を通じた実質の引き上げ額は40円となり、目安を37.5%下回る水準となります。
全国では25府県が実質的に目安を1円以上下回る結果となり、1円以上上回った12道県の2倍になっています。
使用者の不満を少しでも和らげて、賃上げを受け入れやすくするために発効日に配慮したしわ寄せは、発効日の遅れとなって顕在化し、過去最高の引き上げとなった最低賃金が物価高に苦しむ労働者の恩恵として届くには時間がかかる事態を招くこととなりました。
物価高で実質賃金はマイナスが続いている中、春闘で大企業の正社員の賃上げは進んだが、最低賃金に近い水準で働く労働者は全国約660万人とされる中、発効が遅れることで低賃金労働者の賃金は改善が進まずに不利な状況が続くことになっていることをしっかりと見据えて、連帯した闘いを継続しなければなりません。
| 9月5日「議会産業振興土木委員会で県外調査」 |
2日から4日まで、県議会産業振興土木委員会で県外調査のため岩手県を訪れてきました。


最初の調査先は矢巾町にある東北エリアの物流拠点「プロロジスパーク盛岡」で、東北エリアの物流動脈である東北縦貫自動車道盛岡南インターチェンジから至近距離にあり、東北地方広域への配送に最適な立地であり、「物流の2024年問題」にも対応されている拠点として注目されている施設でした。
また、まちづくりの推進を始め、行政や地域社会とともに取り組み、社会インフラとしての重要性を見せつけらました。
さらに、その規模からも地域の雇用確保やまちづくり戦略などにも寄与されている面を考えさせられました。
2日目の午前中は、紫波町の中央駅前都市整備事業オガールプロジェクトについて調査でした。


平成21年度から紫波中央駅前都市整備事業は行われていて、紫波町公民連携基本計画に基づいたもので、プロジェクトの中核となる施設オガールプラザは図書館や地域交流センター、子育て支援センターや民営の産直販売所、カフェ、居酒屋、医院や学習塾などで構成される官民複合施設となっています。
図書館などの集客力のある公共施設をテコに民間施設が稼ぐ仕組みで、建設時の借金返済は終わっているとのことでした。
隣接した矢巾町に岩手医科大学矢巾キャンパスなどができたことなどもあって、人口は微減ながら世帯数は増加しているとの事でした。
午後から調査した陸前高田市の復興まちづくりの中でも、このオガールプロジェクトの整備構成等について参考にさせて頂いたとの話もありました。
陸前高田市では、復興のまちづくりの状況について、陸前高田ほんまる株式会社永山取締役からお話を聞かせて頂きました。



被災市街地復興土地区画整理事業では、地権者の意向に配慮した高台移転を行うために、「新たに高台造成地を確保する」また、「従来の宅地は盛り土して嵩上げをする」「地権者の意向確認の上、任意の申し出により換地を計画する」ことなどで、「安全安心な住宅地形成と早期再建」に向けて取り組んでこられたそうです。
それでもやはり、嵩上げ部の宅地については、住民被災者からの意向調査などをもとに見直しを行ってきたが、縮小しきれずに意向以上の宅地となったこともあって、空き地が残っていることなども要因としてあるとのお話に、いかにきめ細かな被災者との話し合いが必要かと考えさせられました。
また、グループ補助金を使った商業者の復興の課題についても聞かせて頂きました。
最後には、陸前高田から事前復興への教訓として、「まずは命を守る」「復興の拠点、情報を守る」「高台移転先の想定、事前準備」「まちを担う体制作り」「より良い街づくりの検討」「協力体制への想定、専門家との連携等」についてアドバイスも頂きましたので、今後の高知県における事前復興まちづくりの参考にさせて頂く点や気づきのある調査となりました。

最終日は、大船渡市で地域の稼ぐ仕組みづくりと地域に人が集まるまちづくりの支援に取り組まれている「一般社団法人 大船渡地域戦略」の「大船渡さんぽ」のお話などを聞かせて頂き調査を終えました。
| 9月2日「関東大震災と今の排外意識」 |
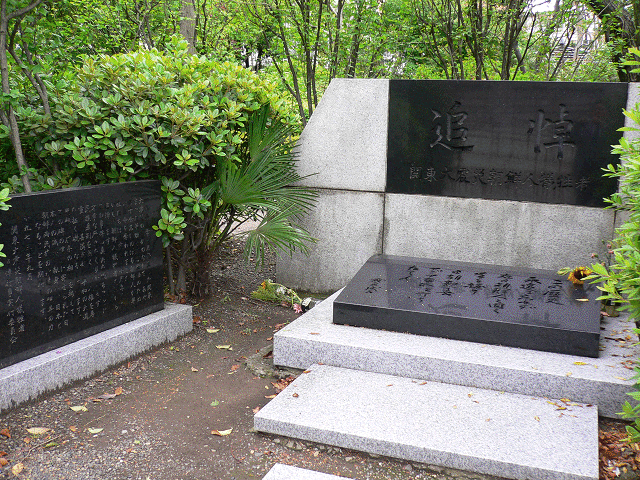
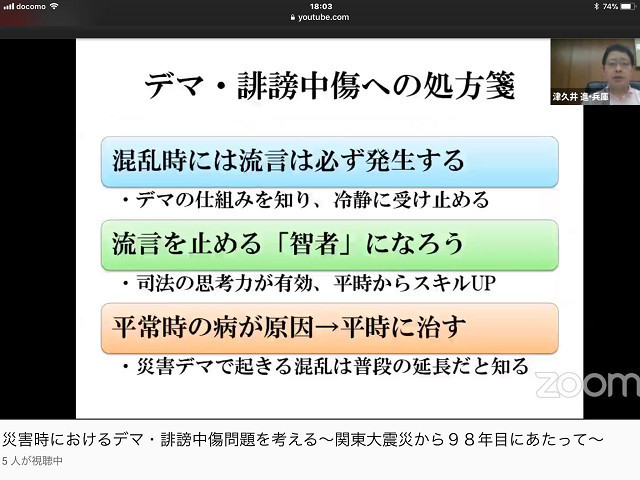 昨日、防災の日の朝日新聞「天声人語」は、「関東大震災と排外意識」と題して、沖縄出身の歴史家、比嘉春潮氏が、著書『沖縄の歳月』で振り返っている関東大震災の数日後の自警団によって言葉の違いを物差しに 、朝鮮人や中国人に加えて日本人も殺傷したことを紹介しています。
昨日、防災の日の朝日新聞「天声人語」は、「関東大震災と排外意識」と題して、沖縄出身の歴史家、比嘉春潮氏が、著書『沖縄の歳月』で振り返っている関東大震災の数日後の自警団によって言葉の違いを物差しに 、朝鮮人や中国人に加えて日本人も殺傷したことを紹介しています。
天声人語にも書かれていますが、映画にもなった「福田村事件」のことも思い出します。
関東大地震発生から5日後、千葉県福田村に住む自警団を含む100人以上の村人たちにより、香川から訪れた薬売りの行商団15人の内、讃岐弁で話していたことで朝鮮人と疑われた幼児や妊婦を含む9人が殺害された事件です。
天声人語では「言葉があやしい、態度がおかしいと線引きし、うむを言わせない。矛を向けた先はちょっと異質とされた存在であり、その典型が当時は朝鮮人であったのだろう。「不安」と「正義感」に駆られた群衆の恐ろしさである。」と書き、「では、いまはどうか」と問いかけています。
そして、いまは「先の参院選では、外国人を排斥する言葉がSNSで飛び交った。根拠のない情報が真実かのように伝播された。」ことに驚かざるをえませんでした。
さらに「参院選の最終日に参政党の神谷宗幣代表は、子供が誇りをもてるような国にしたいと演説し、「それに反対する人は日本人だったらいないはずだ。嫌がるのは、日本を潰したい人たちですよ」と続けたと紹介し「どんな国を誇らしいと思うのか。誇りに思わねばいけないのか。勝手にふるいにかけられるのは、まっぴらだ。」と結ばれています。
2021年の「防災の日」に、関東弁護士連合会が開催した「災害時におけるデマ・誹謗中傷問題を考える」とのテーマで兵庫弁護士会の津久井進弁護士が、デマをジェノサイドに至らせないために紀元前4世紀の中国の思想家である荀子の名言「流言は智者に止まる」ということを引用されて、リーガルマインドを備えた人として「智者」になろうと語られていました。
また、「デマ・誹謗中傷は平時課題の表出」であり、「平時のトレンドを加速する、その社会の課題(弱点)を一気に表出させる」ことになるので、平時にこそ課題解決をしておく必要があることの大切さを強調されました。
関東大震災の頃に逆戻りするかのような「いま」の平時にこそ課題解決をしておかないと「勝手にふるいにかけられてしまう」危機感さえ感じる昨今です。
| 8月31日「災害ケースマネジメントをどう実装するか」 |
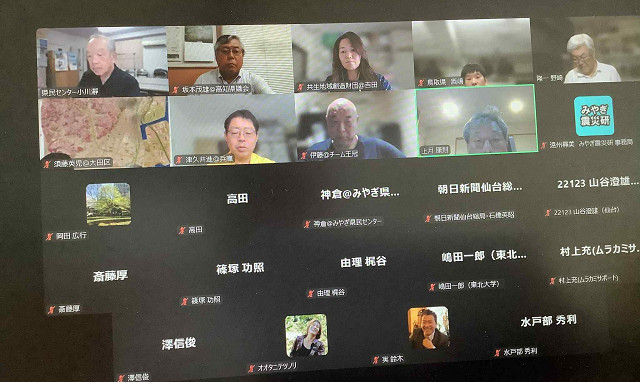
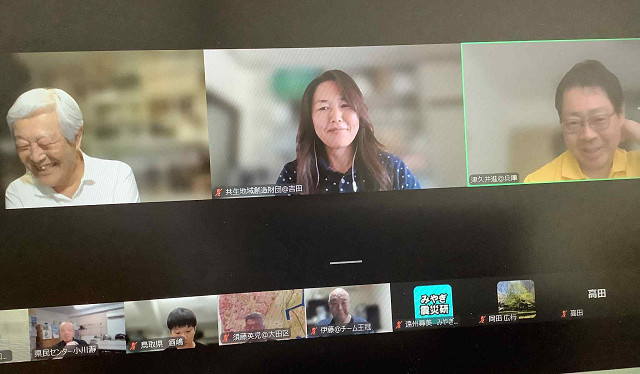 今日の午後は、オンラインで「災害ケースマネジメント構想会議」に参加していました。
今日の午後は、オンラインで「災害ケースマネジメント構想会議」に参加していました。
24回目となる本日は「災害ケースマネジメントをどう実装していくか?」というテーマで、本年7月に災害対策基本法等が改正施行されたことを踏まえて、その内容の共有や津久井進弁護士から「今回の法改正で何が変わり、何が期待でき、何が足らないか」「現場の支援者は何を自分に実装したらよいのか」などについて課題提起頂きました。
国は「被災者に対する福祉的支援等の充実」と「被災者援護協力団体の登録制度の創設」を中心に、地方公共団体への支援強化、広域避難の円滑化などを進めようとしていますが、法改正によって被災者支援がどれだけ進むのか、実効性を伴うのか考えさせられました。
高知でこの法改正に伴う災害ケースマネジメントを担う県内の支援者をどのように育成していくのか、また、県外からの支援者と県や市町村が連携しながら被災者の生活再建支援に伴走できるのかが問われているかとも思いました。
いつもご指導いただいている津久井弁護士や野崎先生のご指摘、さらにはお聞かせいただいた鳥取県や徳島県の現状なども踏まえて、高知県でどのように実践していくのか改めて考えてみたいと思います。
| 8月30日「膨張の一途を辿る軍事費予算は見直しを」 |

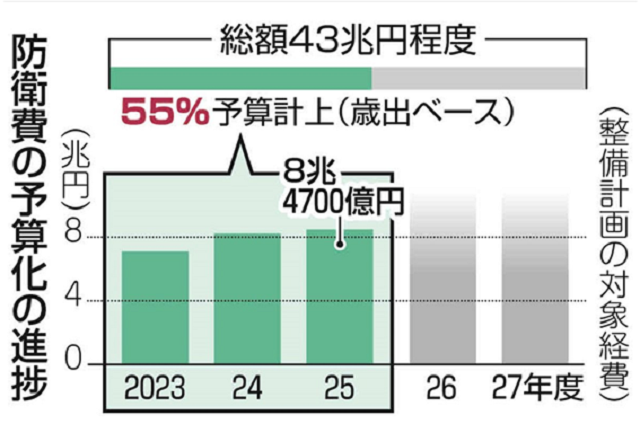 国の来年度予算案の編成に向けて、昨日各省庁が財務省に概算要求を提出し、物価上昇などが経費全般の押し上げにつながり、要求総額は過去最大を更新して一般会計で122兆円台となる見通しだと報じられています。
国の来年度予算案の編成に向けて、昨日各省庁が財務省に概算要求を提出し、物価上昇などが経費全般の押し上げにつながり、要求総額は過去最大を更新して一般会計で122兆円台となる見通しだと報じられています。
中でも、防衛省予算は、今年度当初予算を約1450億円上回り、過去最高を更新する8兆8454億円となっています。
敵の射程圏外から攻撃でき、敵基地攻撃能力として活用する「スタンド・オフ防衛能力」の関連経費に1兆246億円、ドローンなど「無人アセット防衛能力」の関連経費にも今年度予算の約3倍となる3128億円を充てるなど、防衛力の強化を急ピッチで進めています。
当時の岸田政権が2022年12月、防衛力の抜本的強化に向け、防衛力整備計画を策定し、2027年度までの5年間に必要な防衛費の総額を、従来の1.6倍となる43兆円とする方針で増やし続け、来年度は4年目にあたり、最終年度の27年度には他省庁の研究開発費など関連予算を合わせてGDP比2%とする方針で、膨張の一途をたどっています。
しかし、「抑止力」の柱と位置づける「スタンド・オフ防衛能力」の強化のための1兆246億円などは、専守防衛を空洞化させかねず、米軍との役割分担も不明確なままで、配備が予定される自治体では反対の声もあがっており、軋轢を生じさせていると言っても過言ではありません。
政府が「必要な内容を積み上げた」と言いながら、国会にも、防衛力整備計画の積算根拠となる43兆円の内訳を示そうとしなかったことから、東京新聞は内訳資料を情報公開請求したが、防衛省は、全文を「不開示」としています。
43兆円に増えれば2027年度には、戦後おおむね1%で推移してきた防衛費のGDP比が2%に倍増するわけで、もともとGDP比2%は、1期目の米トランプ政権が同盟国に求めていた水準であり、野党は「額ありきで決めたのではないか」と追及し、政府に必要な経費を積み上げたという根拠を示すよう要求していました。
しかし、東京新聞の情報開示請求に対して不開示とすることは、どこまで精緻な積み上げがあったのか不明のままで、「額ありき」の疑念はさらに深まったと言えます。
今度のトランプ政権は、GDP比3.5%と米軍駐留経費(思いやり予算)の負担増額をさらに求めています。
政府は、現状において財源確保の目途も立たない中で、他の政策課題へのしわよせも懸念されている中、大幅な見直しをためらうべきではないし、さらなるトランプ要求に対して毅然とした姿勢で臨むべきではないでしょうか。
| 8月29日「子どものSOSを受け止めて」 |
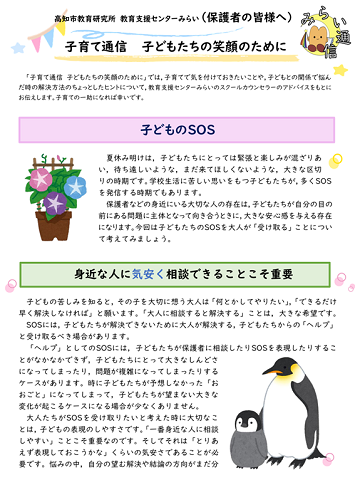
 昨日、地元の昭和小学校を通じてオンラインで保護者に送られていた高知市教育研究所教育支援センターみらいの「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、子育てで気を付けておきたいことや、子どもとの関係で悩んだ時の解決方法のちょっとしたヒントについて、書かれていました。
昨日、地元の昭和小学校を通じてオンラインで保護者に送られていた高知市教育研究所教育支援センターみらいの「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、子育てで気を付けておきたいことや、子どもとの関係で悩んだ時の解決方法のちょっとしたヒントについて、書かれていました。
まずは、「子どものSOS」ということで、「夏休み明けは、子どもたちにとっては緊張と楽しみが混ざりあい、待ち遠しいような、まだ来てほしくないような、大きな区切りの時期です。学校生活に苦しい思いをもつ子どもたちが多くSOSを発信する時期でもあります。保護者などの身近にいる大切な人の存在は、子どもたちが自分の目の前にある問題に主体となって向き合うときに、大きな安心感を与える存在になります。今回は子どもたちのSOSを大人が「受け取る」ことについて考えてみましょう。」と始まっていました。
同様に、昨日の高知新聞社説では「夏休み明け 子どもの叫び受け止めて」と題して、「夏休みが間もなく明ける。県内では既に2学期が始まった学校もある。この時期は子どもの自殺が増える傾向にある。勉強や人間関係に不安を抱いている子にとって学校再開は大きなストレスになり、精神的に追い込まれることが多いとみられる。身近にいる大人が早めに兆候をつかみ、寄り添う必要がある。痛ましい状況を早く変えなければならない。」とあります。
また、社説によれば、大人を含めた全体の自殺者が減少傾向にある中、子どもの自殺には歯止めがかかっておらず、小中高生の自殺は新型コロナウイルスの国内流行が始まった2020年に以降に増加し高止まりする中、22年以降は500人超で推移し、厚生労働省と警察庁によると、24年は統計のある1980年以降で過去最多の529人で、10代の死因の1位が自殺であることなど世界的に見ても深刻な状況にあるとされています。
だからこそ、子どもが安心して過ごせる居場所づくりも急ぎ、中でも思春期の子どもにとって、学校や家庭と距離が取れ、居心地のよい場所は不可欠だとしています。
「子育て通信 子どもたちの笑顔のために」では、SOSを受け取るときに大切なのは、SOSを受け取ることのできた大人が問題と向き合うことではなく、子どもとの関係に大人が寄り添うことであり、「大人が問題に向き合う」形になって、子どもが置き去りにしないことであるとアドバイスしています。
そして、「子どもとの関係に寄り添う」ということは「今あなたはこんな状況に置かれていて、こんなふうに感じているんだね」と受け止め理解したうえで「どうしたいと考えているの?」「どんなことで手助けができる?」など子ども自身の想いを聴き、子ども自身が主体となって物事と向き合うことができるようなサポートの大切さを指摘されています。
夏休み明けにこそ、子どもが安心して過ごせる多くの居場所づくりやSOSを受け止められる大人のゆとりも必要なのかもしれません。
| 8月27日「軍事費拡大よりも、インフラ老朽化の維持修繕で安全・安心を」 |
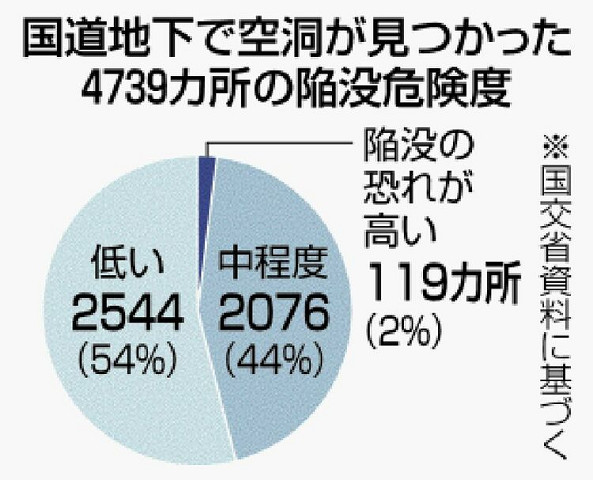
 埼玉県八潮市で起きた道路陥没を受け、国土交通省は毎年行っている国道での空洞調査の結果を25日初めて公表し、国道4739カ所で地下の空洞を確認し、うち119カ所は陥没する恐れが高かったとしています。
埼玉県八潮市で起きた道路陥没を受け、国土交通省は毎年行っている国道での空洞調査の結果を25日初めて公表し、国道4739カ所で地下の空洞を確認し、うち119カ所は陥没する恐れが高かったとしています。
調査は、直轄している国道のうち橋やトンネル区間を除く2万810キロを対象に5カ年計画で実施し、24年度はこのうち3079キロの状況を調べ、空洞の深さや広がりに応じて危険性を3段階に分類しています。
25年3月末時点で陥没の恐れが「高い」と判定したのは、深さ20センチ、幅1メートル程度の空洞といった基準に該当した119カ所で、より深い場所で見つかった「中程度」(2076カ所)と、「低い」(2544カ所)は、交通量が多いなど重要度の高い計232カ所で修繕を優先的に進めるとのことですが、すでに、119か所については、ほぼすべてで修繕を終えたということです。
陥没の恐れがある要因として、付近の老朽化した上下水道管からの漏水や地下水の影響、地盤の強度不足などが挙げられており、国交省は3月、トンネルなどを除く国道の全区間を調査する方針を示しており、28年度までに残りの約1万8千キロも調べることとされています。
国交省が同時発表した道路インフラの老朽化点検結果によると、25年3月末時点で修繕・撤去が必要なトンネルは全体1万1290のうち3152カ所に上っているとのことです。
政府では、今後とも大規模地震に備えて道路や上下水道、橋の耐震化を進め、5年かけて耐震化の取り組みを加速し、それぞれのインフラに対し耐震化率100%に向けた中長期目標を設定しています。
国交省は26日、インフラ老朽化対策や大地震に備えた防災・減災対策に重点を置いた前年度比19.0%増の7兆812億円の一般会計総額を2026年度予算概算要求として計上しています。
米トランプ政権によって、日本に対し防衛予算をGDP比3.5%に増やせと要求し、在日米軍駐留経費増を求められていることに応えるよりも、せめて維持・修繕によるインフラ老朽化対策などで国民の安全と安心を確保していくことが求められているのではないでしょうか。
| 8月25日「改めて広域避難を考えさせられる仁淀川町での防災キャンプ」 |





3・11東日本大震災以降、二葉町町内会・自主防災会を中心に、南海トラフ地震が来たら二葉町は水没し長期浸水し、生活も仕事もできなくなる恐れがある中、震災復興に要する長期間、生活できる中山間地域と交流し、疎開先を探すことから始まった仁淀川町との交流でした。
二葉町の皆さんと仁淀川町長者だんだんくらぶの皆様との交流が深まり、仁淀川町での田植え体験やキャンドルナイト、下知地区での昭和秋の感謝祭での仁淀川町の産品の販売も人気を博しました。
その後は、下知地区防災計画の中に「浸水域外との事前交流」として、「長期浸水域から救助されたのち、下知地区の住民がどこに二次避難するのか、町内単位で避難できるのか等は不明な状況です。このため、事前に浸水被害の少ない地域(高知市内、高知県内外)と顔の見える交流を行い、公民館、集会所、空き住宅などを避難所として借用できるように協力をお願いしておきます。これにより、避難先が確保されるとともに、被災後の見通しが立てやすくなります。」との課題を書き込みました。
その二葉町を中心に事前交流を重ねながら、高知市との意見交換も行い、2022年11月1日に、仁淀川町と高知市は「広域避難における避難所としての施設の使用に関する協定書」を締結しました。
そして、仁淀川町から災害時に避難所として提供される予定の旧大崎小学校体育館(160人収容)と泉川多目的集会所(80人収容)を昨年1月20日に、高知市防災訓練の一環として、市民25人が避難体験をし、泉川多目的集会所で地元の皆さんと交流し、旧大崎小学校体育館も見学させて頂きました。
そして、具体的な避難体験交流を重ねるために、昨年8月に予定した「防災キャンプ」が、台風のため中止となり、今年8月23~24日にかけてやっと実施することができました。
仁淀川町の皆さんの丁重な受け入れ体制のもとで、夕食のカレーライスやバーベキュー、さらにはキャンプファイヤー交流など、何より40人を超す参加者が取り囲んだキャンプファイヤーは、参加者の皆さんの心を1つにした取り組みだったと思います。
本当に仁淀川町の地元の皆さんの気持ちのこもったおもてなしをしていただき、参加者一同大感激でした。
また、それぞれが持ち寄ったアウトドアグッズや防災グッズなどを披露しあいながら宿泊をし、翌朝は下知地区得意のラジオ体操も行い、炊き出しの朝食に満足した後、片付け・施設の掃除を行った後、次回を約束しながら二日間の日程を終えました。
日程の中では、「広域避難における避難所としての施設の使用に関する協定書」にもとづいて施設を避難所としてどのように運営するのか、マニュアルについても議論しました。
しかし、「広域避難における避難所」というが、その受け止めがそれぞれに違うことも明らかになりました。
「そもそものきっかけは疎開避難である。」ということから、一般的に言われる「広域避難」の受け止めでいいのかとの意見もあり、「広域避難の認識が一致しているか、限界があるだろうが、できる事は何か、考えていきたい。」との意見も出される中、各自がこの避難所をどのように受け止めるのかについて意見交換して頂きました。
「住まい、事業所ともに下知地区にある私にとっては、本社機能を維持させるという意味で、南トラが起きる前に二拠点の準備をする。」「マンションに住んでいることからも、在宅避難となる応急期のイメージとして捉えていた。」「勤務先は高台移転する予定なので、仕事が再開されるまでの期間と母とペットは住まわせることで考えていた。」「1年以内の避難生活なら市内でする。1年以上になれば考えても良い。」「地元の人と交流することの大事さ。」「イメージとして被災時にここまでたどり着けるか、道路啓開がどれだけできるだろうか。長期的スパンで捉える。」「広域避難を前提とした時、この避難所は仁淀川町民の利用について、どうなっているのか。」など疑問や率直な意見が出されました。
多様な意見が出されたように、いろんな生活スタイルがあるので、選択する避難の在り方として適当かどうかは、個人の判断になるだろうが、もう少し避難所の位置づけや広域避難の捉え方を継続的に議論することが必要ではないかと感じたところです。
ただ、最近よく言われる「二地域居住」の問題とも関連して、事前の「関係人口」が被災後には「市民権」が保障される復興過程を歩まなければならなくなることも課題となるのではないかと思ったりします。
しかし、避難者が避難先でどれだけのスパンで、どのような避難生活を送るのかによってこの避難所の活用が線引きされてしまうことにならないのであれば、避難開始直後の避難所運営のあり方だけでも決めて、後はフェーズ毎に避難者と避難元自治体と避難先自治体との連携で方向性を決めていくことになるのではないかと思うところです。
| 8月22日「県震度分布・津波浸水予測は10月下旬頃公表」 |

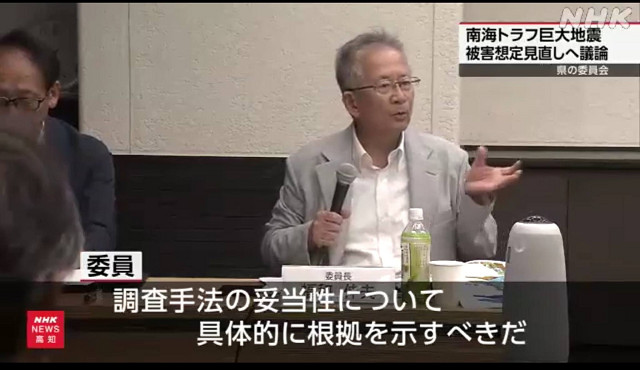
3月、国が南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を公表したことを受けて、県は県版の想定について見直しを進める第3回「県地震被害想定検討委員会」(委員長:福和伸夫名古屋大学名誉教授)が20日開催されました。
当初は、この3回検討委で地震動と津波浸水の想定をまとめる予定だったが、国土地理院が7月31日に更新した標高データを反映させ、最新データを活用するための追加作業が必要だとして10月下旬頃に公表することが確認されました。
委員からは、「説明性が、何より大事で、国との違いや前回との違いなどについて、合理的な説明が必要であることからも、そのための論拠を用意すること。」、「被害想定がどのような目的で使われるのか、役立つ情報であるのかが大事である。災害時対応に資する場所などは、どのように想定するかなどは検討が必要。」、「人的被害は何をすれば減るのか、何をしなければ増えるのかわかるようにして、対策効果について示す。」、「ライフラインのあり方からのリスク評価、地下水位のあり方、長期浸水エリアの議論についても、さらに深める。」などの多岐にわたる意見が出されました。
また、情報提供、防災教育、地震対策の検討の目的に資する「被災シナリオ」についての複合災害について、火山噴火や感染症、異常気象などとの複合が補強されたが、原発災害については、どなたからも言及されず、残念でした。
いずれにしても、県民に対して説得力を持たすための想定される震度分布や津波予測が求められており、そのための調査検討の要請がされました。
今後は、10月の想定公表を踏まえて、議会からも指摘する必要が出てこようかと思います。
| 8月19日「中山間地でも事前復興を」 |


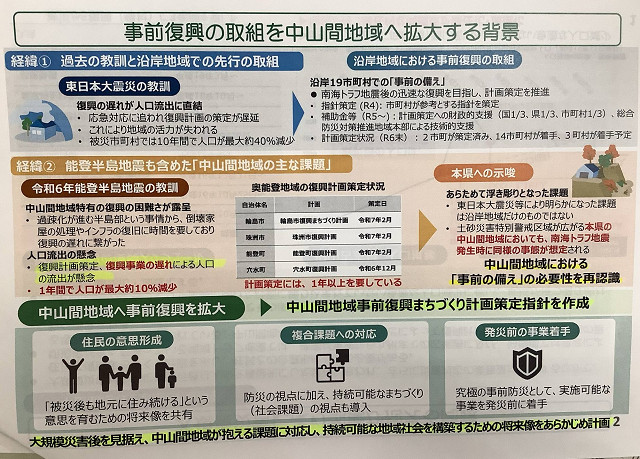
昨日は、「高知県中山間地域事前復興まちづくり計画策定指針検討会(第1回)」を傍聴しました。
本県では、津波被害が想定される沿岸地域の市町村を対象に、事前復興まちづくり計画の策定支援を行い、沿岸2自治体では策定され、現在は高知市などでも策定されています。
私の住む下知地区でも来年早々からワークショップを行うこととなっています。
しかし、能登半島地震の被災地で復興が遅れた教訓を踏まえ、事前復興の取組を沿岸地域の市町村に加え、中山間地域の市町村に拡大することとし、事前復興まちづくり計画を策定する際に参考となる市町村向けの「指針」を策定するため設置した本検討会の第1回を開催したところです。
第1回目の検討会では、中山間地域で事前復興まちづくり計画を策定することの必要性の整理や、指針の構成などについて議論をし、指針構成案に対する委員からの補強意見が出されました。
委員長になられた牧紀男・京都大学防災研究所教授は「中山間地域で事前復興に取り組むのは、おそらく高知県が初めてだろうと思われるので、しっかり議論を」進めたいとの決意も示されました。
「物理的被害に加えて、もともとその地域にある課題が顕在化するので、そのことをイメージする必要がある」「仮設住宅や瓦礫置き場には、災害復興住宅も建てられないなど中・長期の視点が必要」「空間単位をどのように捉えるか集落のあり方などの検討」「誰が復興の主役かを考えた時、人口や担い手のこともしっかり踏まえたものにする」「住民のアイデンティティとして歴史や文化の継承も柱にすえて欲しい」「事前に何ができるのか発災前の事業着手にもつながる計画づくりを」「選択肢を可視化できるように」「事前復興計画の実効性をどう担保できるのか」など、被害想定が難しい中で、多岐にわたる意見が多く出されました。
今後は、本年度内に指針をまとめ、2026年度からの当該市町村に計画策定を促すこととなります。
| 8月17日「第50回高知酒害サマースクール」 |
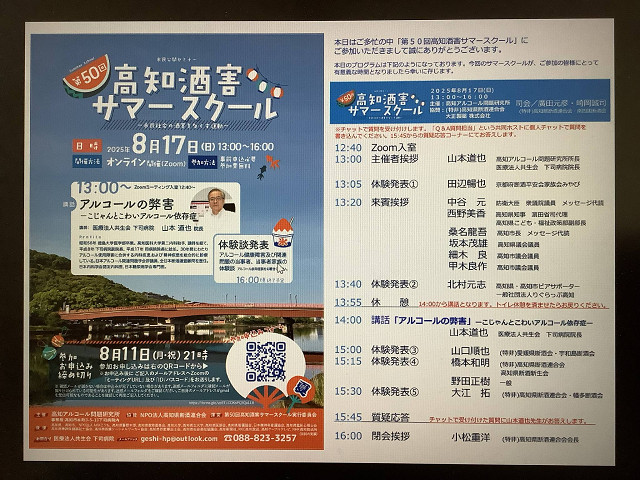
 今日の午後は、第50回目となる「高知酒害サマースクール」に出席し、挨拶をさせて頂いた後は、各地の断酒会メンバーによる体験発表を聞かせて頂くとともに山本道也先生(高知アルコール問題研究所所長、下司病院院長)の講演で「アルコールの弊害―こじゃんとこわいアルコール依存症」について、聴講させて頂きました。
今日の午後は、第50回目となる「高知酒害サマースクール」に出席し、挨拶をさせて頂いた後は、各地の断酒会メンバーによる体験発表を聞かせて頂くとともに山本道也先生(高知アルコール問題研究所所長、下司病院院長)の講演で「アルコールの弊害―こじゃんとこわいアルコール依存症」について、聴講させて頂きました。
山本先生の飲酒により悪化しうる内科疾患・精神疾患、飲酒と依存症の生命予後などの詳細データをもとに、「こじゃんとこわいアルコール依存症」に「たまるかー」がつくほどの怖さについて、聞かせて頂きました。
アルコール健康障害の早期発見、早期介入、切れ目のない治療・回復支援を実現するため、内科・救急等の一般医療、一般の精神科医療機関、専門医療機関、相談拠点、自助グループ等の関係機関の連携体制がきめ細かく組織されることが求められます。
| 8月16日「8.15に学ぶ「前事之不忘 後事之師」」 |

 昨夜は、「8.15平和と人権の集い2025―日本と中国今とこれから」に参加していました。
昨夜は、「8.15平和と人権の集い2025―日本と中国今とこれから」に参加していました。
約2時間半いろんな立場の方々から、戦争と平和と人権、中国との関係について考える思いが伝えられました。
パネラーは、NPO高知県日中友好協会岡林俊司会長、高知県日中友好中国帰国者の会中野ミツヨ会長、高知県平和運動センター谷英樹事務局長、さらに会場におられた藤原充子弁護士からもお話をいただきました。
岡林さんからは、平和を脅かす脅威があるという敵となる相手に対して、彼らは自分たちより野蛮で劣っていると侮蔑し憎悪をするという形で集団的心理をが現れてくるが、それを国民の意識の中に植え付けてきたことが、今につながっているのではないか。
だから、民間レベルの交流を通じてもっと中国について知ることから始まることが、今こそ必要。
また、中国残留孤児として、戦中戦後を通じて祖国の日本から見捨てられた孤児にとっては、中国は死の淵から救い育ててくれた命の恩人だし、日本は母国であると言うことを踏まえて、戦争は許さないし、悲惨な歴史が二度と繰り返されないようにするために自らの歴史を伝え続けている中野さんからは「前事不忘 後事の師」と歴史の教訓に学び生かすことと戒められました。
平和運動センターの谷事務局長からは戦中、戦後の歴史に学びながら、戦争を支えさせられた国民の意識がどこから生まれたのか、そして2007年以降日本の貿易相手国中国にアメリカと一緒になってミサイルを向けるのか、主権国家としてアメリカに対してもしっかりものを言い、戦争をしないさせない政治を築いていくことの必要性などが訴えられました。
明治維新、大正、昭和の戦争の歴史について、自作の年表を配布頂いていた藤原弁護士からのお話は、改めて9月14日(日)14時からの「戦後80年 平和を考える集い」(高知会館)で詳しく聞かせて頂くこととなります。
皆さん、そちらにもお越し下さればと思います。
フロアーからの質問も含めて、戦争の歴史を繰り返さないことを決意しあう貴重な150分の集いとなりました。
| 8月15日「『戦後80年』を『戦前』にしないために」 |

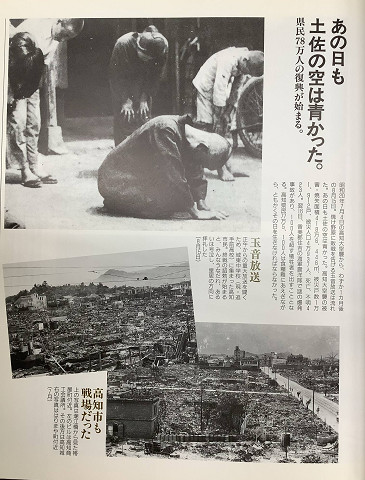
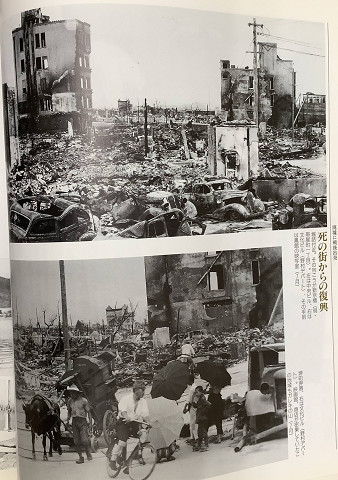
「戦後80年」でもある今年の敗戦記念日は、誰もが「戦争を絶対繰り返さない」と言いながら、「戦前」という危機感も感じる8.15ではないかと思わざるをえません。
石破総理は、この日に合わせて過去の戦争を振り返り、未来へどう伝えていくか戦後80年の総理談話の発表を見送り、個人的見解を出す予定です。
総理談話とは、国の重要な事柄に関する総理の公式見解のことで、閣議決定して発表されることになります。
しかし、「植民地支配」「侵略」「痛切な反省」「心からのお詫び」というキーワードを軽視し、「あの戦争に何ら関わりのない私たちの子や孫、そして、その先の世代の子どもたちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」という、将来にわたる戦争責任を放棄しようというような10年前の安部談話を継承するぐらいなら、出さなくてよいと思わざるをえません。
石破総理は「形式はともかくとして、この風化というものをさけるために、そして、戦争というものを二度と起こさないためのそういうような発出というものは、私は必要だと思っています」と言っているが、「戦後80年」を「戦前」とするようなメッセージだけは発しないでほしいと願うばかりです。
11日付の高知新聞で報じられていましたが、日本世論調査会の世論調査結果によると戦後の歩みの中で良かったことを問うと「他国と戦争をしなかった」が最多の50%に上り、「治安が良い状態が保たれた」の42%が続き、憲法に関しては2015年の戦後70年時の調査と同様に「このまま存続させるべきだ」が60%、複数回答で評価する点を聞くと、80%の人が憲法の「戦争放棄・平和主義」を挙げていました。
核兵器は「必要はない」が79%、非核三原則を「堅持するべきだ」は80%に上り、「台湾有事」の際に、政府が取るべき対応は「外交努力や経済制裁など非軍事の手段で対応する」が42%と最多で、次が29%の「中立を保ち介入しない」でした。
日本社会が「悪い方向」に向かっていくと答えたのは「どちらかといえば」を含めて計72%で、10年前の計52%から大きく増加しています。
また、世界の秩序や価値観が「望ましくない方向に変化している」としたのは75%となっています。
このような国民の感覚が、「戦後80年」が「戦前」になるかもしれないという危機感であるし、そうさせないために我々に何ができるかということが問われているのではないでしょうか。
2016年に発刊された集英社新書「『戦後80年』はあるのか」で、歴史学者の山室信一氏は「戦後が戦前に転じるとき」の3つの転機を次のように指摘しています。
▼1つは、国際情勢の変化の中で、仮想敵国と軍事同盟の話が現れてくる時、平和が戦争の正当化の口実となる戦争が終わることで、平和になると言うのではなく、平和を実現するために出兵すると言う論理。
▼2つ目の契機は平和を脅かす脅威を煽り、敵を侮蔑し憎悪する集団的心理が現れてくる時、なぜ戦争が必要なのかと言えば、平和を脅かす脅威があると言う敵となる相手に対して、彼らは自分たちより野蛮で劣っていると侮蔑し憎悪をする。そういう形で集団的心理が現れてくる。
▼3つ目の契機はある一線を踏み越えると言う感覚が個人に現れてくる時。これまでは何とか穏便にやってきたけれども、もはや堪忍袋の緒が切れたと言う興奮状況に追い込まれる。
以上のような転機を少なからず感じるようなことがないでしょうか。
「戦後80年」を「新しい戦前」にしないため、アメリカに言われるままに軍備拡大したりするのではなく、戦争を回避する「新しい外交」に舵を切らせるために、私たち一人ひとりが声をあげていくことで、「戦後90年」を迎えたいものです。
| 8月14日「万博、帰宅困難者で混乱」 |

 大阪・関西万博会場で、当初から心配されてきた危機管理の不十分さが、昨夜露呈しました。
大阪・関西万博会場で、当初から心配されてきた危機管理の不十分さが、昨夜露呈しました。
これまでにも、「大屋根リング」の下の護岸が約600メートルも浸食されていた問題をはじめ、夢洲は台風で多数のコンテナが吹き飛ばされるほどの被害を受けてきた地域で自然災害に対する脆弱性は克服されていなかったり、爆発下限界を超えるメタンガスの濃度が検知されたGW工区では、ガス爆発不安は完全に払拭されないという状況が懸念されていました。
そんな中で、昨夜9時半頃万博会場への唯一の鉄道路線大阪メトロ中央線が、コスモスクエア―大阪港駅間での停電の影響で、夢洲―長田駅間で運転を見合わせ、夢洲駅から東ゲートまで大勢の来場者が滞留しました。
水や食料などがどこで配布されるかなどの情報もほとんどなく、大屋根リングの下では、子どもを抱いて座って休む人の姿もあり、来場者からは、交通や滞在する人への支援状況などについての情報不足を批判する声があがったとのことです。
会期が始まったばかりでもないのに、水や椅子を配ったり、運転再開見込みのアナウンスをしたりする臨機応変な対応がされていないことに対する不満の声があがったり、大阪市消防局によると、14日朝までに、熱中症や混雑による気分不良などを訴えた計36人が救急搬送されたとのことです。
大阪・関西万博の入場券の販売枚数が8日時点で1809万枚となり、主催の日本国際博覧会協会が運営黒字化の目安とする1800万枚を超えたという一方で、アンゴラ館業者が万博無許可工事で捜索を受けたりましており、万博運営黒字化ありきの裏にある課題は、十分に解消されないままに、進んでいるとしか思えません。
そして、今回顕在化した危機管理の不十分さについて、自然災害が多発する時期を迎え、余程の対策を講じておかなければ、生命に関わる問題が生じるのではないかと、懸念しています。
| 8月13日「寺田寅彦の『天災と国防』について改めて考える」 |
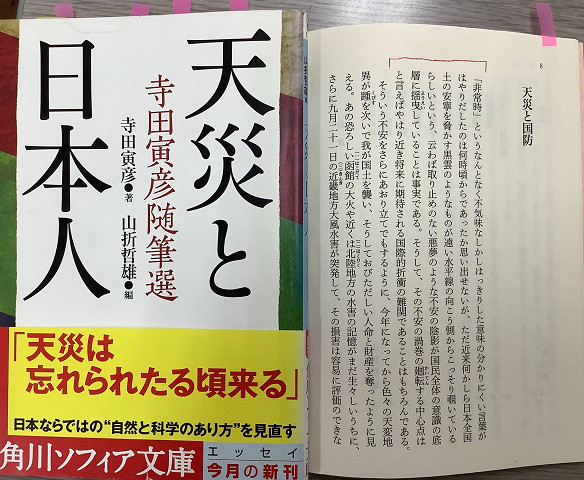
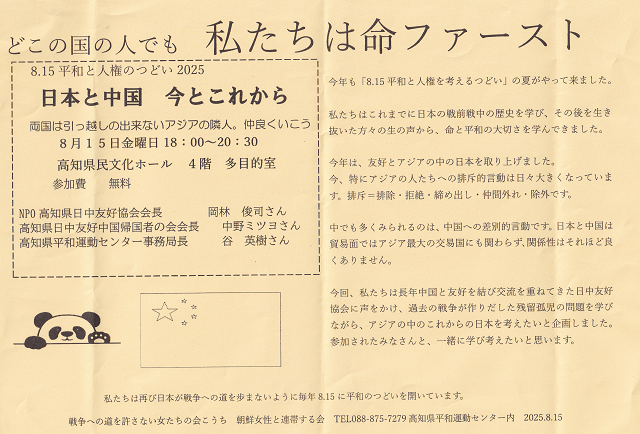
「天災は忘れられたる頃にやってくる」と言う言葉を残した寺田寅彦は、1934年つまり満州事変の3年後に「天災と国防」と言う随筆で次のように書き始めています。
「『非常時』というなんとなく不気味なしかしはっきりした意味のわかりにくい言葉がはやりだしたのはいつごろからであったか思い出せないが、ただ近来何かしら日本全国土の安寧を脅かす黒雲のようなものが遠い水平線の向こう側からこっそりのぞいているらしいという、言わば取り止めのない悪夢のような不安の陰影が国民全体の意識の底層に揺曳していることは事実である。そうして、その不安の渦巻の回転する中心点はと言えばやはり近き将来に期待される国際的折衝の難関であることはもちろんである。」
実態のわからない「非常時」と言う不気味な状況が作られ、国防ということが言われるようになると、戦争に突破口を求めようとして、そうした危険性に無関心になる国民心理の変化に注意すべきだと忠告されているのではないかと思われます。
まさに、今の我々に対する警告であるとも受け止められるのではないでしょうか。
しかし、戦争はあくまでも人為によって起きるものであり、戦争は忘れた頃に自然にやってくるわけでもありません。
そして、「天災と国防」には、「文明が進むに従って人間は次第に自然を征服しようとする野心」をもって、「いやが上にも災害を大きくするように努力しているものは誰あろう文明人そのものなのである」と人為による「複合災害」についても警告しています。
そして、戦争との「複合災害」について、「それはとにかく、今度の風害が、『いわゆる非常時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなかったのは、実に何よりのしあわせであったと思う。これが戦禍と重なり合って起こったとしたら、その結果はどうなったであろうか。想像するだけでも恐ろしいことである。」と警告しています。
だからこそ、「戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけにはいかない」と、言われているように、災害が多様化し、頻発化、連鎖化、巨大化、複合化する時代の今こそ「戦争の避け方」を考え、実践する文明を発展させる国民でありたいと思うところです。
その一つとして、、「どの国の人でも命ファースト」に考える「8.15平和と人権の集い」が開催されますので、どうぞご参加ください。
8月15日 18時~ 県民文化ホール4階多目的室
| 8月12日「日航機墜落事故から40年の教訓を生かせているか」 |
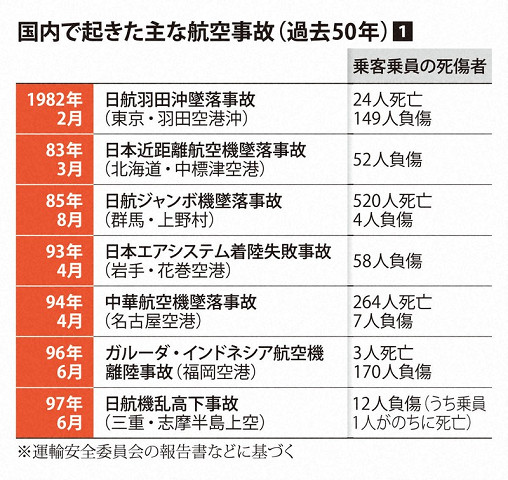
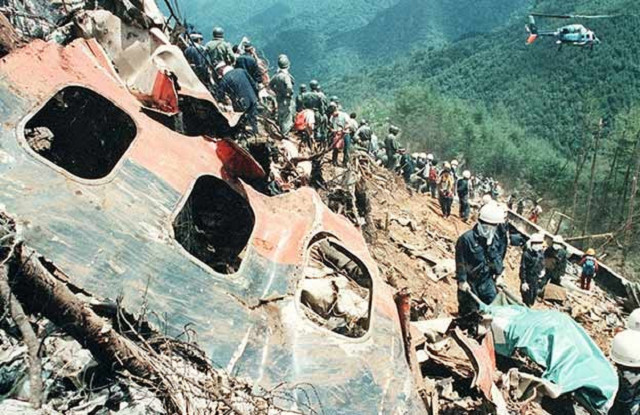 1985年に羽田発伊丹行きの日航ジャンボ機(ボーイング747)が墜落した事故から、40年になる今日、航空機をはじめ、公共交通機関の安全運航が求められていることを改めて考えさせられます。
1985年に羽田発伊丹行きの日航ジャンボ機(ボーイング747)が墜落した事故から、40年になる今日、航空機をはじめ、公共交通機関の安全運航が求められていることを改めて考えさせられます。
10年前の30年目の時には、この欄に「交通機関の事故は、列車事故、バス事故、船舶事故と繰り返される度に、再発防止が言われてきたが、何よりも「命と安全」が優先されるはずの体制や規制が経営効率などによって、先送りされてきた面はいなめません。高知では、多くの将来を担う中学生、高校生を亡くした紫雲丸事故、上海列車事故という交通機関事故、さらには東名高速飲酒運転事故という風化させてはならない事故があります。いずれにしても、事故の教訓は決して風化させることなく、真の意味で原因の本質に迫り、「再発防止」に本気で取り組む責任を交通事業者は問われているのではないでしょうか。」と書かせて頂いたが、果たしてその責任を果たしてきたと言えるでしょうか。
羽田空港で昨年1月、新千歳発の日航機と海上保安庁機が衝突し海保機の5人が死亡し、日航機の乗客乗員は炎上する機体から間一髪で脱出したが、この時も人的ミスの連鎖が重大事故につながりました。
訪日客の増加で羽田などで発着の過密化が著しく、国は、他空港への機能分散や人員不足が深刻な管制官の一層の増員などに取り組む必要があります。
そして、海外では、飛行制御システムの不具合が原因の事故が続いたこともあり、メーカーは品質管理に万全を尽くすべきだと言われています。
事故に至らない人的ミスも多発し、パイロットの乗務前の飲酒もなくならない中で、40年が過ぎて事故が風化し、現場に気の緩みが広がっていないだろうか。
2010年1月、日本航空は政府の方針で破綻と再建が進められ、再建の過程で「更生計画」の人員削減目標を大幅に達成し、営業利益も12月時点で目標の2.5倍となる1,586億円を上げたにもかかわらず、大晦日にパイロット81名と客室乗務員84名を年齢と病欠歴を基準に整理解雇しました。
165名の解雇は、利益を最優先するために、モノ言う労働者の排除と労働組合の弱体化を狙ったもので、安全に逆行するものであったことは、明らかであると争議団の皆さんは争議の解決は、“安全運航の確立”、失われた利用者からの信頼回復にも繋がるとして闘い続けています。
そんな体質を抱えた日本航空自体に教訓を継承すること、命を預かる責任の重さを自覚することができるのだろうかと問いかけたいと思います。
| 8月10日「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」 |

 昨日の長崎市での平和式典の挨拶に、石破首相は地元の大学で被爆した永井隆博士の言葉の一節「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ。」と盛り込みました。
昨日の長崎市での平和式典の挨拶に、石破首相は地元の大学で被爆した永井隆博士の言葉の一節「ねがわくば、この浦上をして世界最後の原子野たらしめたまえ。」と盛り込みました。
長崎医科大学で被爆された故・永井隆博士が残された言葉であり、長崎と広島で起きた惨禍を二度と繰り返してはならないとの強い思いが込められた言葉です。
さらに、首相の挨拶は「天を指す右手が原爆を示し、水平に伸ばした左手で平和を祈り、静かに閉じた瞼に犠牲者への追悼の想いが込められた、この平和祈念像の前で、今改めてお誓い申し上げます。私たちはこれからも、「核戦争のない世界」、そして「核兵器のない世界」の実現と恒久平和の実現に向けて力を尽くします。」と結んでいます。
しかし、その石破首相は、記者会見で、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加の是非については、「核兵器を持っている国を交え、議論をしていかなければならない」と否定的な見解を示しました。
挨拶で、述べたことを一つでも前に向けようとする決意の感じられない見解でしかありません。
「核抑止力」が、本当に抑止につながるものであると言えるのか、それは核使用につながる可能性があることを肝に銘じておかなければなりません。
アメリカには、「警報下発射」と呼ばれるシステムがあり、発射されたという警報が出されると、大統領はただちに報復攻撃を指示することになるものです。
ロシアでも同様の監視体制をとっているそうですが、この警報が、誤ったものであったとしたらどうなるかとの不安は拭えません。
これは杞憂ではなくて、間一髪だったことが過去の事実で明らかにされています。
元米国防長官ウィリアム・ペリーは著書「核のボタン」の中で、「我々が知る限り、冷戦期に米国で少なくとも3回、ソ連では2回、そうした誤警報があった。二度と起きないと考えられる理由はない。人間は間違いやすく、機械は故障する」とあります。
昨日の長崎市の鈴木史朗市長が平和宣言で訴えた「『武力には武力を』の争いを今すぐやめてください」との言葉に、全ての各国リーダーに答えてもらうしかありません。
| 8月9日「災害ケースマネジメントで『その人らしい』生活再建を」 |
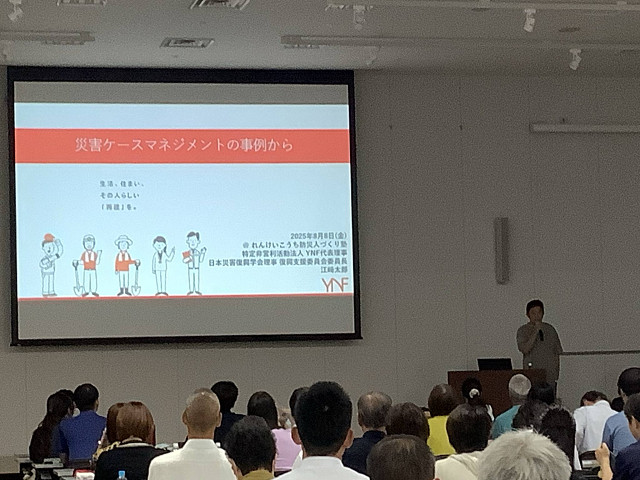
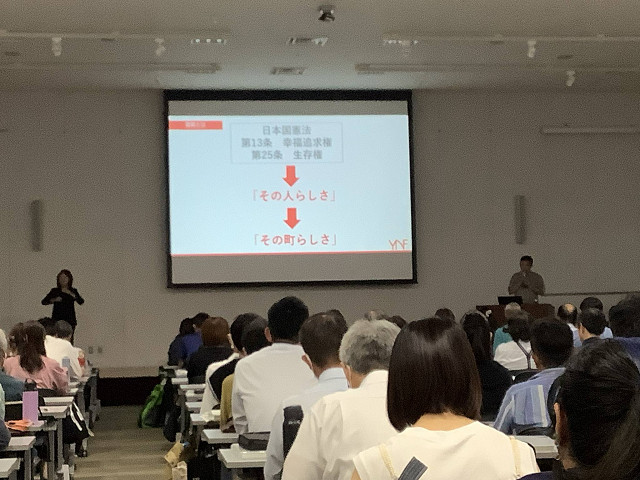
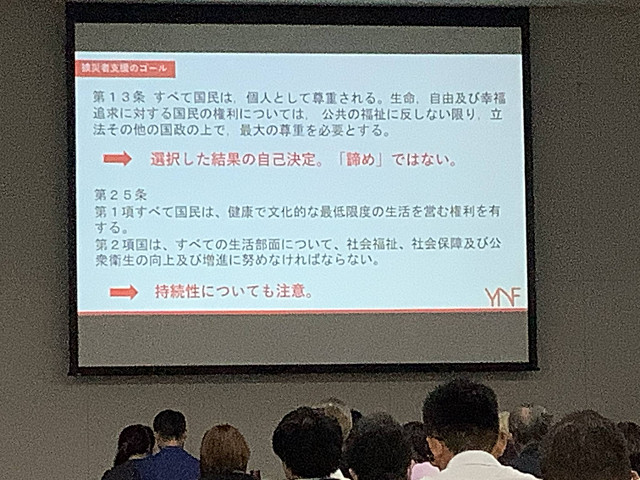
昨夜の高知市防災人づくり塾は、県での制度導入を求め、その具体化が各自治体で取り組まれるように求めてきた「災害ケースマネジメントの事例から」がテーマで、講師も8年前に熊本での日本住宅会議サマーセミナー「熊本地震の被害と復興」でお会いして以来オンラインなどでお付き合いさせて頂いていた特定非営利活動法人YNFの江崎太郎さんでしたので、会場に出向いて、臨時聴講させて頂きました。
災害ケースマネジメントについて、初めて詳しく話を聞かれる方も塾生には多かったことと思いますが、いろんな会場で話されてきた江崎さんは、「この会場の皆さんは、ほかの会場よりも反応が良かった」と仰っていましたので、参加者の皆さんも災害からの生活再建でどのような課題と向き合うのかということを新たな自分ごととして聞かれていたのではないかと思いました。
「災害ケースマネジメント」とは内閣府の「災害ケースマネジメント実施の手引き」から引用すると「被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しながら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントする取組」と定義していることを紹介されたうえで、そこにある課題について紹介されました。
課題として、「自ら声を上げられない被災者の存在」「在宅避難者の増加」「支援漏れの発生」「被災者の抱える多様な課題の存在」「行政の対応が難しい課題の存在」「その場での対応だけでは、必ずしも課題の解決につながらない場合がある」「個々の被災者に寄り添った支援が必要」などがあげられるが、被災者の自立・生活再建が進むようマネジメントすることで、その課題を克服して、「被災者の自立・生活再建の早期実現、コミュニティーや街づくりなどの地域の復興を通じ地域社会の活力維持に貢献」していくことが求められています。
これまでの被災地での実践を通して改めて被災者支援の課題として次のことも明らかになっています。
「現行制度でカバーできない問題がある。(救済策がない)」「生活再建支援の重要性が低い。(何が必要か理解がされていない)」「担い手がいない。(平時から被災者支援従事する人は、地域の中にいない)」「支援活動の財源がない。(利用できる制度が少なく、ボランティアベースで設計されたりする)」「支援対象者の数が膨大になることがある。(大規模災害の発生時など)」「支援対象者が地域外に出てしまうことがある。(広域避難の問題)」「支援ノウハウが確立していない。(支援経験者の数の圧倒的不足)」「福祉的支援でカバーされていない課題の対応も必要。」
そして、「モレのない支援の実現」をするためには、何回も訪問するしかないと言われていたが、被災者も意識して情報を得ようとすることを事前に習慣・文化としておくことの必要性も訴えられていましたが、そのことの大切さを改めて考えさせられました。
江崎さんは、現在珠洲市を拠点に行われている能登半島地震における支援活動がどのような事業としてされているのか話された中で、最初は安否確認だが、時間が経つにつれて深く悩み始まるので「被災者見守り相談支援事業」として繰り返し戸別訪問を重ねられる丁寧な取組の必要性にも言及されていました。
いずれにしても、江崎さんが師匠と言われる津久井進弁護士もよく言われますが、被災者支援がめざすのは、日本国憲法「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」「第25条第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という幸福追求権、生存権の実現をめざした被災者支援が進められるべきなのです。
そして、そのことを通じて「その人らしい」生活再建を図り、「その町らしい」復興のまちづくりが果たされることまでを見据えた取組が復興であることで結ばれました。
災害ケースマネジメントに関わって来られた方々のお話を聞かせて頂くたびに、災害は、地震や豪雨などという原因で発生しているが、それによって壊され、影響を受けた被害は、一人ひとり違っており、その被災生活、復興のあり方も一人ひとり違っているということを受け止めて、その人権が尊重される復興過程があるべきなのだろうということを常に感じさせられます。
久しぶりでしたので、講演が終わった後に土佐の酒と肴で、続きのお話を聞かせて頂きました。
| 8月8日「特定利用空港指定候補撤回の申し入れ」 |

 先日、「特定利用空港・港湾」の候補に、高知龍馬空港が挙がっていることに関しての報道がされていたことをお知らせしましたが、緊急ではありましたが6日には、「郷土の軍事化に反対する高知県民ネットワーク」で、県に対して指定見送りを国に働き掛けるよう申し入れました。
先日、「特定利用空港・港湾」の候補に、高知龍馬空港が挙がっていることに関しての報道がされていたことをお知らせしましたが、緊急ではありましたが6日には、「郷土の軍事化に反対する高知県民ネットワーク」で、県に対して指定見送りを国に働き掛けるよう申し入れました。
申し入れ書は下記の通りで、「指定は『台湾有事』の動きに沿ったもので、空港周辺の住民の生命が危機にさらされかねない」ことなどを指摘し、「高知龍馬空港の特定利用空港としての指定を見送るよう、高知県として国に申し入れを行うこと。」と「武器・弾薬などを含む物資輸送・保管があるのか、また具体的な用途や整備内容等について明らかにするよう国に説明を求めること。」について、申し入れました。
県からは、特定利用空港は、自衛隊や海上保安庁が有事に円滑利用できるよう機能を整備し、そのための仕組みづくりをしておくためで、この枠組みで米軍機が利用することはないといい、空港内に新たな施設整備をするとは聞いてないこと、特段に訓練が増えるとは聞いてないことなどが説明されました。
また、県がなぜ高知空港なのかと聞いたら、「空港の近傍に部隊がいることなどを考慮した」と説明したというが、国はそのことこそが本音なのではないかとも思われます。
申し入れメンバーからは、「自衛隊や海上保安庁だけでなく、米軍機も来るのではないかという不信がある」「訓練が日常化するのではないか、その際に騒音に県民が悩まされることになる」「災害支援の際のメリットにも言及されているが、最大クラスの地震の際には空港の半分ほどが津波浸水想定なのに、活用できるのか」「高知県としてできることは、ちゃんとしてほしい」などのもう入れに対して、県は、「今日申し入れがあったことや、心配の声があることを国に伝える」と答弁されました。
今後も、県民の不安な声を国に伝えるとともに、指定見送りを求めるよう県に働きかけ続けたいと思います。
| 高知龍馬空港の特定利用空港指定を見送るよう 高知県として国に働きかけることなどを求める申し入れ書 県民福祉の向上に向けた日ごろからのご努力に敬意を表します。 さて、8月5日の新聞報道によりますと、政府担当者が4日高知県庁を訪れ、高知龍馬空港について2025年度末をめどに「特定利用空港・港湾」に指定する旨説明があったとされています。また、その際、具体的な用途や整備内容には言及せず、「空港の近傍に部隊がいることなどを考慮した」との説明があったとのことです。 そして、これらに対し、高知県として①県民の理解が得られる丁寧な説明、②県民生活に影響が出ないよう民間利用を優先、③安全に万全を期し、県民の問い合わせや事故には国が責任を持って対応する、ことを申し入れたとも聞いているところです。 国管理の高知龍馬空港ですが、私どもは、高知県民の安全と安心を確保する観点から、高知県として高知龍馬空港の特定利用空港としての指定を見送るよう、国に申し入れを行ってもらいたいと強く要請します。 現在、沖縄県・九州各県を中心に自衛隊のミサイル基地や弾薬庫などが急ピッチで整備されています。いわゆる「台湾有事」を想定した動きですが、有事の際には、自衛隊基地はもちろん、自衛隊利用を想定した空港や港湾も攻撃対象になりうるものです。防衛力整備計画には「有事にも活用する」と記され、アメリカのシンクタンク・戦略国際問題研(CSIS)報告には「中国が攻撃しなければならない駐機場を大幅に拡大し、日米の損失を軽減することができる。もし米国と日本が中国のミサイルのサブミッションズが覆える範囲よりも広く航空機を地上に配置できれば中国は航空機1機につき1発のミサイルを使用しなければならなくなります。これにより、中国の保有ミサイル数は急速に枯渇するでしょう。」と記されています。そうした流れに沿った今回の高知龍馬空港の特定利用空港指定の検討とみなければなりません。 特定利用空港問題で考えなければならないのが、国際人道法の基本原則です。ジュネーブ諸条約第一追加議定書の48条では、軍事目標主義と軍民分離の原則がうたわれています。すなわち、紛争当事者は軍事目標だけを攻撃の対象とする、そして住民と戦闘員、民用物と軍事目標とを常に区別するということが規定されています。 したがって、民間空港であっても平時から自衛隊等が利活用しておれば、国際法的にも「特定利用空港」は「民用物」とはされず、「その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物」、ジュネーブ諸条約第一追加議定書52条第2項の「軍事施設」とされて攻撃対象となる危険性、攻撃されても国際法的な批判ができない恐れがあるということを直視する必要があるのではないでしょうか。そして、空港周辺の住民の生命が危機にさらされることになりかねません。 近年、日米合同軍事演習が頻繁に行われ、自衛隊と米軍は、民間空港・港湾・公道での訓練演習を積み重ね、空港での戦闘機による訓練など訓練演習内容は実戦さながらで、エスカレートしており規模も拡大して利用する空港・港湾も増えています。全国の空港の軍事利用に向けた既成事実づくり・地ならしではないかと危惧するものです。それに米軍も加わるのではないとの懸念もあります。さる3月下旬から5月下旬にかけて長期にわたる米軍機(F35Bステルス戦闘機)の長期駐機もありました。 すでに沖縄では、住民を対象とした「有事」の際の避難訓練が行われ、自衛隊基地の「地下化」も具体化される段階に入っており、それだけ「戦争への準備」が進められ、住民の生命・財産の危機が現実のものとして認識される段階に入っているといわざるを得ませんし、沖縄県民がこのことに大きな不安を抱いています。 したがって、今回の高知龍馬空港の特定利用空港指定問題について、県民の命を守る立場から次のことを申し入れますので、真摯に対応されますようよろしくお願いします。 記 1 高知龍馬空港の特定利用空港としての指定を見送るよう、高知県として国に申し入れを行うこと。 2 武器・弾薬などを含む物資輸送・保管があるのか、また具体的な用途や整備内容等について明らかにするよう国に説明を求めること。 |
| 8月6日「『継承』の担い手として核廃絶を自分ごとに」 |


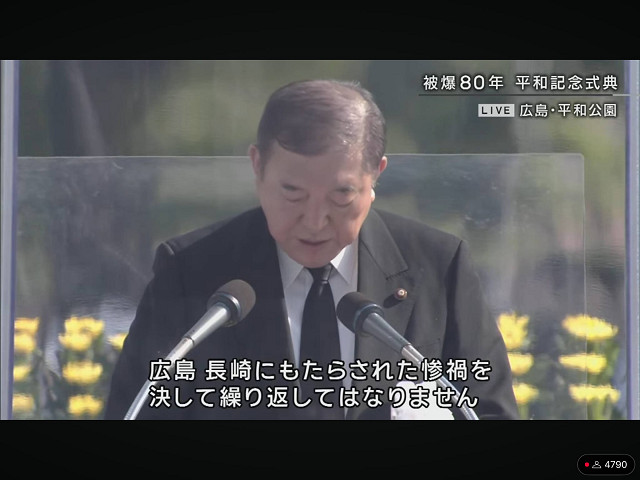

ノルウェー・ノーベル委員会のフリドネス委員長が7月に広島と長崎を訪れた後、都内で「ヒバクシャは戦争の犠牲者であるだけでなく、証人であり、教え諭すべき指南役でもあるのです」「記憶にとどめることはあらがうこと。変革への力にもなりえます」と述べられました。
ノーベル委員会が日本原水爆被害者団体協議会に平和賞を授賞してから7カ月余り、被爆者とその記憶の継承に努める人たちを再び讃え、改めて「継承」によって、核廃絶を呼びかけられています。
広島市の市民団体「ANT―Hiroshima」理事長の渡部朋子さんは、「単に受け継ぐのではなく、記憶が自分の中に生き続けて、わたくし事になる」と継承をこう表現されています。
今日の平和記念式典での小学生代表も「その事実を自分のこととして考え、平和について関心を持つこと」「私たちが被爆者の思いを語り継ぎ一人ひとりの声を紡ぎながら平和を創り上げていきます」と述べられたことに、次世代の「語り部」への決意と受け止めました。
そして、私たちには、被爆の実相を知り、平和の大切さを思うだけでなく、広島、長崎まかせになりがちな核廃絶活動を国内はもちろん海外にも広げていくことが改めて求められていると思います。
米調査機関ピュー・リサーチ・センターが米国民に尋ねた世論調査の結果として、原爆投下を「正当化できる」は35%、「できない」が31%で、18~29歳では「できる」の27%を「できない」の44%が大きく上回っています。
80年前にギャラップ社が日本への原爆投下について聞いたときは「支持する」が85%だった事から考えると、被爆者が米国で訴え続けてきた成果といえるのではないかと思われます。
6月に米国が核保有国とされるイスラエルが、敵対するイランの核兵器保有を恐れて先制攻撃し、米国がイランを攻撃し、加勢しました。
その際に、トランプ氏は攻撃が「戦争を終わらせた」と主張し、「広島、長崎と本質的に同じだ」と言い放ったのです。
国連憲章に反するだけではなく、米国大統領は、核の使用が国家間の争いに決着をつける手段として正当化されるという認識を持つことを明らかにしたのです。
未だに、このような認識のリーダーがアメリカでは君臨している中でも、アメリカの若者たちの半数近くが「正当化できない」と声をあげ始めているのです。
広島と長崎に米国が原爆を投下し、約21万人が命を奪われてから80年になる今、被爆者たちは苛烈な体験に向き合い、「核なき世界」の実現を訴えてきましたが、まだまだ訴え続けよと言われているとしたら、それはこれからの私たちが「継承」していかなければならないのです。
日本には、核兵器が使われてはならないという規範を守り、広げ、不使用から軍縮、最終的な廃絶につなげる外交が求められています。
現状、米国の核の傘に頼る日本は核禁条約に加わらず、締約国会議へのオブザーバー参加も拒んでいることに対して、私たちの力で動かしていくしかありません。
核廃絶への歩みを主導することが、唯一の戦争被爆国・日本に期待される役割であり、日本にしか出来ない役割でもあることを考えたら、「核廃絶はわたし事」という決意をしあう80年目にしたいと思います。
| 8月5日「高知空港も特定利用空港候補に」 |
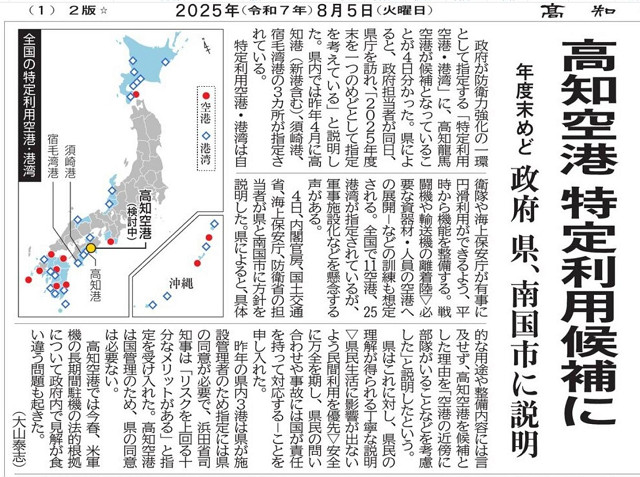
 今朝の高知新聞一面の記事で、政府が防衛力強化の一環として指定する「特定利用空港・港湾」に、高知龍馬空港が候補となっているとの報道がありました。
今朝の高知新聞一面の記事で、政府が防衛力強化の一環として指定する「特定利用空港・港湾」に、高知龍馬空港が候補となっているとの報道がありました。
県によると、政府は、「2025年度末を一つのめどとして指定を考えている」として、具体的な用途や整備内容には言及せず、高知空港を候補とした理由を「空港の近傍に部隊がいることなどを考慮した」とのことです。
県はこれに対し、「県民の理解が得られる丁寧な説明」「県民生活に影響が出ないよう民間利用を優先」「安全に万全を期し、県民の問い合わせや事故には国が責任を持って対応する」ことを申し入れたとのことです。
県内では昨年4月に高知港(新港含む)、須崎港、宿毛湾港の3カ所が指定されており、その指定合意には県民世論を二分しながら、県民の十分な理解と納得がえられないままに知事が判断されました。
しかし、高知空港は国管理のため、県の同意は必要ないので、余程県民の声をあげていかなければなりません。
しかも、3月には米軍ステルス戦闘機が高知龍馬空港に予防着陸という実質緊急着陸を行い、県民に対して十分に説明のないまま全国でも最長の42日間も駐機し続けるなど、高知空港の特定利用前提の予備訓練だったのではないかと思わざるをえません。
2月にも岩国基地のF35が緊急着陸した松山空港も7月、国が「特定利用空港」の候補として検討しているし、高松空港でも5月に「特定利用空港」の候補にあがっています。
いよいよ高知でもとなると四国は完全に南西諸島や北海道、九州など特定地域に偏っていた国防インフラの配置の全国分散の拠点とされようとしていることが明らかになっています。
空港は、国管理だからといって、勝手に指定させないように、自治体としてもしっかりと議論していかなければなりません。
| 8月3日「アナウンサーたちと戦争」 |
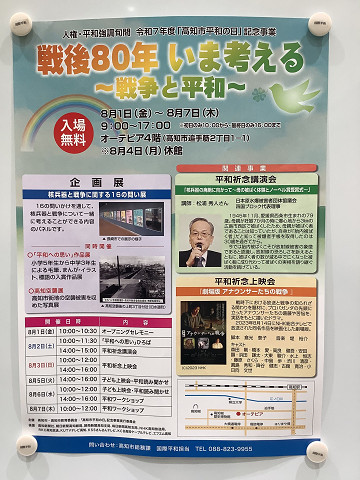
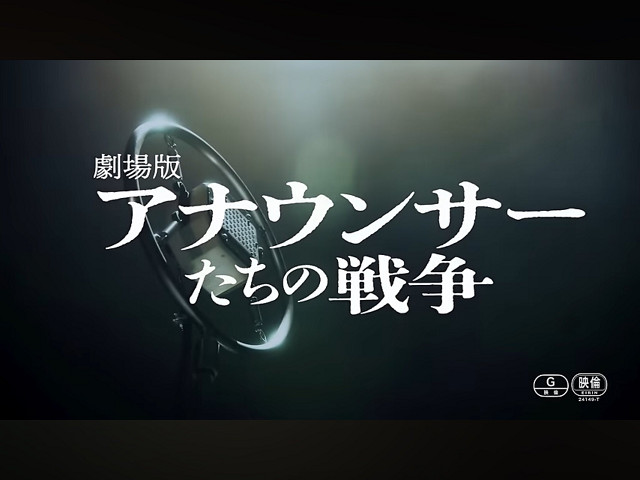
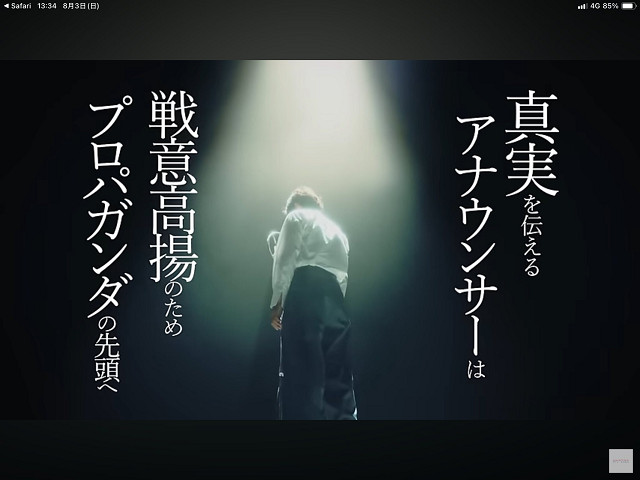
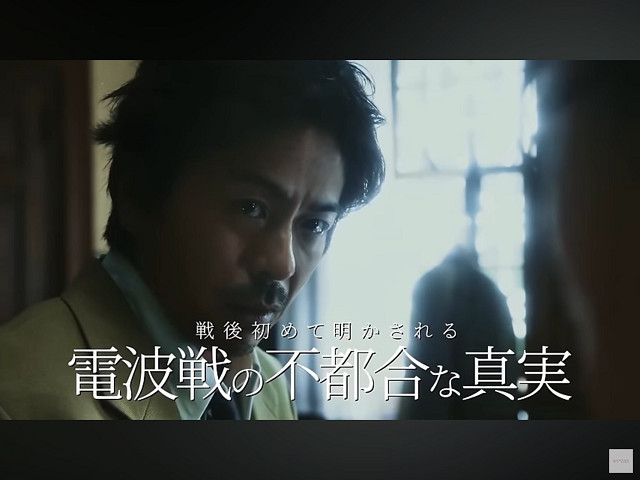
今日は、午前中の会議が終わってから、オーテピアで開催されている「高知市平和の日記念事業」に立ち寄り、映画「アナウンサーたちの戦争」を、鑑賞してきました。
太平洋戦争から80年、2023年8月14日にNHK総合テレビで放送された同名作品を映画化した劇場版の上映でした。
戦時下における放送と戦争の知られざる関わりを題材に、プロパガンダの先頭に立ったアナウンサーたちの葛藤や苦悩を、実話をもとに描いたドラマとして
日本軍の戦いを、もう一つのラジオ放送による「電波戦」という戦いが支えていました。
ナチスのプロパガンダ戦にならい「声の力」で戦意高揚・国威発揚を図り、偽情報で敵を混乱させていたが、それを行ったのは日本放送協会とそのアナウンサーたちで、戦時中の彼らの活動を、事実を元に描かれていました。
太平洋戦争が始まり、日本が南方に勢力圏を広げていくと、フィリピン、シンガポール、インドネシア、ミャンマーなどにも次々と放送局を開設し、そこで放送を支え「電波戦」を行っていたのが、当時の日本放送協会の職員たちだったのです。
アナウンサーは日本一のアジテーターであり、国家の意思をマイクに載せて運ぶ「電波戦士」の任務を果たしていたのです。
戦地で命を失った者もいたが、アナウンサーたちは、言葉で日本を勝たせるために日本軍も、国民をも真実ではなく嘘で鼓舞・扇動したことへの反省を敗戦の中でします。
戦後、謀略放送に参加したアナウンサーは、「真実の報道」の確立に尽力されました。
そして、戦後80年、平時の今でさえ、マスコミ・メディアにおけるファクトチェックが求められています。
さらに、マスメディアだけでなく当時よりも多様なツールが拡散する中で、「信用のない言葉ほど惨めな言葉はない」と言われるようなことが横行していることを危機として捉えざるをえない局面を打開するためにも、80年前のアナウンサーたちの苦悩と葛藤に学ばなければなりません。
| 8月1日「殺処分ゼロにするため」 |


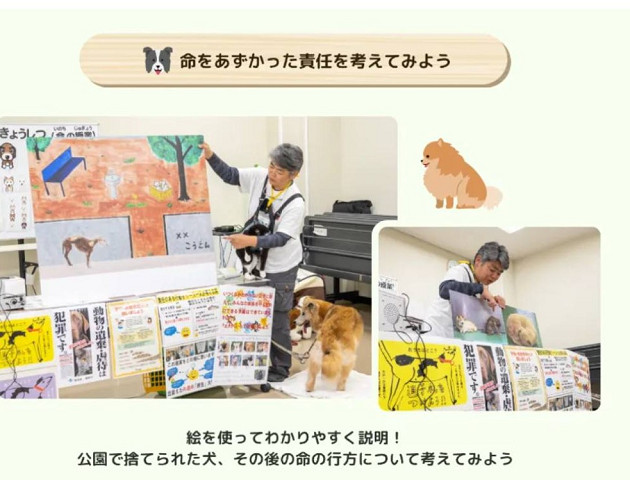
ペット用品通販の「ペピイ」のホームページに、 「動物愛護センターに行ってきました」のコーナーがあり、そこに「高知県中央小動物管理センター編」が紹介されているのを県動物愛護推進員の方に紹介頂きました。
そこには、「殺処分ゼロ」の本当の意味を考える施設とは、「動物の命を捨てる人をゼロ」にすること「命を粗末に考える人をゼロ」にすること、「無責任な飼い主をゼロ」にすること、「幸せになれない命をゼロ」にすること―とありました。
その記事の中でも紹介されている動物愛護推進員の方に初めて出会い、「命の授業」を見学させて頂いたのが2008年11月26日のことでした。
休憩をはさんだ90分間の授業で、3人の推進員さんが手際よく「危害を防ぐ方法」「犬と仲良くなる方法」「生命の大切さ」「動物を飼うことの責任」などを低学年の児童にも分かるように教えていく中、生徒達の反応は大変良くて、熱心に集中していたことを思い出します。
授業では、犬猫の殺処分ゼロを進めるためにも、「飼い始めたら最後まで飼う」「散歩の時に糞の始末はキチンとする」「放し飼いにしないこと」「不幸な命をつくらないために手術をすること」の念押しされて終わりでした。
終えた後に推進員の方が言われていましたが、この学びの重要性は学力の以前にあってもいいほどの大切な内容を持っているものだと感じましたし、子どもだけではなくおとなにも学び直しをして欲しい内容だと感じ、以降多くの学校で「命の授業」を取り組んで頂くことや動物愛護推進員さんの奮闘ぶりなど当時の知事に授業見学も要請したものでした。
今回の記事は、丁寧に取材して下さっており、「殺処分ゼロ」の大前提となる「収容される動物がそもそもいない」を目指す、県中央小動物管理センターの取り組みや動物愛護推進員さん、そして「命の授業」について紹介されています。
県では、令和9年に、新しい動物愛護センターへと場所を移す計画が、進められていますが、「新しい施設は、設備もスペースも拡充され、エンリッチメントと動物福祉の視点からも申し分ないため、馴化トレーニングや譲渡事業など、より良い環境でスムーズに効率よくできそう」だと、県衛生課職員の方の説明もあります。
「一人ひとりが動物の命と福祉について関心を持ち、自分にできることを考えていく。その積み重ねが、結果として、収容される動物の数を減らしていくことにつながります。人と動物がともに安心して暮らせる社会にしていくために。誰もが動物の命に目を向け、自分ごととして考えていくことが、不幸な命を生まない未来につながっていきます。」と結ばれたこの記事を、できるだけ多くの方に読んで頂きたいと思います。
こちらからリンクを貼ってますので、ぜひご覧ください。
| 7月31日「遠地津波の課題と教訓の検証を」 |


昨日は、ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた巨大地震による津波警報や注意報によって国内の太平洋沿岸地域に緊張が走りました。
結果として高低差はあったものの22都道府県に津波が到達し、200万人に避難指示が出されたとのことです。
全国的には、迅速な避難が強く呼びかられ、潮位は時間がたつにつれて各地で次第に高くなったことなどから、多くの住民が長時間の避難を強いられるケースがありました。
そのため、猛暑の中、熱中症の疑いで体調を崩す人や避難途中のけが人や事故による死者などもあり、鉄道の運休など国民生活に大きな影響が及びました。
遠地津波は、住民らが地震発生を知らない可能性がある分、いかに速やかに、適切に避難を呼びかけるかが問われます。
また、遠地からの津波は長時間にわたって繰り返し押し寄せ、後から到達する方が高い場合もあったり、長時間の避難になりやすく、津波による直接的な被害がなくても、今回のような真夏の屋外避難は熱中症や持病の悪化なども招きかねないという複合災害のリスクも心配されます。
屋外避難だけでなく、津波被害が大きくなれば、避難所開設も判断しなければならない中で、冷房設備がまだ不十分な中での避難生活の継続はさらにそのリスクを大きくすることもあわせて、今後の対応と備えの検討が急がれるのではないでしょうか。
北海道新聞は、「震源に近いロシアの地域は5~6メートルの津波に襲われたという。現地からの映像は、建物が津波に激しく押し流される様子を伝えていた。東日本大震災を想起させる。甚大な被害が出ているに違いない。ウクライナ侵攻以降、関係が冷えているとはいえロシアは隣国だ。政府は人道支援の手を早急に差し伸べるべきだろう。」と報じています。
この思いも、我が事として受け止めたいものです。
| 7月30日「ロシア・カムチャツカ半島付近の地震で津波」 |
 今朝方、ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震で、最初は、本県には津波注意報も出されていませんでしたが、県の沿岸部に午前9時40分に津波注意報が発表されました。
今朝方、ロシア・カムチャツカ半島付近で起きた地震で、最初は、本県には津波注意報も出されていませんでしたが、県の沿岸部に午前9時40分に津波注意報が発表されました。
私は、丁度10時から県議会産業振興土木委員会に出席する予定でしたので、下知コミュニティセンターでの対応について、職員に指示した後、委員会に出席していました。
市町村からの要望事項に対する執行部の答弁まとめを議論したうえで控室に帰り、報道を注視していました。
本県では、想定される津波到達想定時間は満潮時刻とはズレていたことにも、少し安堵しながらも、丁度土木部港湾海岸課と協議している時でしたので、状況について報告を受けました。
沿岸19市町村は津波浸水区域や沿岸部、堤防の外側などに避難指示を出し、職員や消防、警察署員が海沿いの地域を巡回したり、海から離れるよう呼びかけたり、「通常は出入りのために開けている堤防の陸こうについては、到達予想時間の正午までに閉鎖する」ように指示したことなどの報告も受けたところでした。
岩手県久慈港では13時52分1.3mの津波が押し寄せていますが、1952年の今回と場所・規模が類似した地震(M9.0)では、岩手県久慈港に1mの津波が襲来していますが、この津波が到達したのは、地震からなんと「9時間後」だったということです。
今回も、港によっては、時間が経過される中で、津波の高さが更新されており、警報や注意報が解除されるまでは、気をつけておかなければなりません。
それと今回は災害級の暑さの中での避難ですので、熱中症との複合災害のリスクにも気をつけておきましょう。
| 7月29日「消防広域化基本計画あり方検討会専門部会開催続く」 |
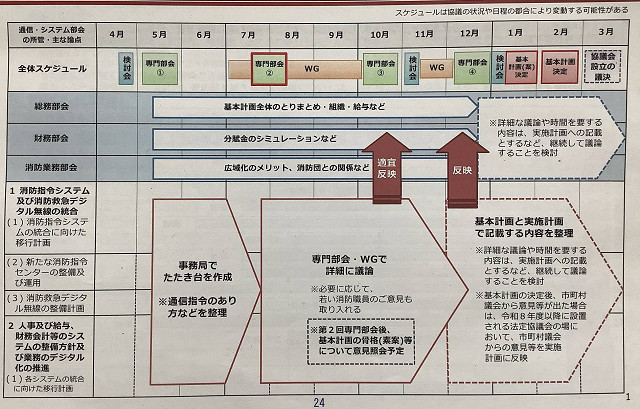 昨日は、「県消防広域化基本計画あり方検討会」の第2回専門部会の傍聴をしていました。
昨日は、「県消防広域化基本計画あり方検討会」の第2回専門部会の傍聴をしていました。
午後1時からの「消防業務部会」そして3時15分からの「通信システム部会」と引き続く部会での議論は、委員の皆さんから多様な意見が出されていました。
県が担う事務局から示された方向性で今後進められるものもありますが、さらにワーキンググループなどでも意見交換をしながら、10月に行われる専門部会で一定の合意を見出すのが事務局の予定です。
提案される内容が事前に示されているとはいえ、直前であることから現場では十分議論をして部会議論に臨めるほどの時間的余裕もなく、専門部会の中でも十分に煮詰まらない課題も多くあります。
昨日の議論を踏まえて、8月末をめどに、さらに現場の意見を踏まえた意見反映をしていただくよう事務局からも要請がありましたので、現場での議論がこれからどのように反映されるかが注視されます。
来週には、「総務部会」と「財務部会」が予定されていますので、これも傍聴しなければと思っています。
| 7月28日「浸水リスク最悪の本県医療・福祉施設」 |
 今朝の朝日新聞1面、24面、27面で南海トラフ津波被害の国の新想定では、2300医療機関が浸水リスクを抱えていることがで取りあげられています。
今朝の朝日新聞1面、24面、27面で南海トラフ津波被害の国の新想定では、2300医療機関が浸水リスクを抱えていることがで取りあげられています。
南海トラフ巨大地震が起きると、全国で約2300の医療機関と、約7300の福祉施設が津波で浸水するおそれがあり、災害医療の中核を担う災害拠点病院も12施設が立地し、機能に支障が出る可能性もあるとされています。
30センチ以上浸水するエリアにある医療機関は21都府県の2347施設で、21都府県の医療機関数の3.2%にあたり、県別では徳島県(260施設、県全体の31.6%)に次いで本県が252施設、38.2%となっています。
また、福祉施設は23都府県の7270施設で、割合は4.2%で本県が1286施設、33.4%と徳島県(1199施設、28・1%)、愛媛県(925施設、13・2%)を上回って全国で最多となっています。
しかし、事業継続計画(BCP)を策定済みの災害拠点病院や救命救急センターなどは2022年度時点で60%にとどまっており、2024年から、災害に備えたBCPの策定がすべての介護サービス事業者に義務づけられたもののBCPをどう生かすかは施設次第で、災害時の対応は、事前にどこまで具体的な事態を想定しているかに左右されることになります。
ちなみに、本県における要配慮者利用施設における避難確保計画の作成率は69.7%で、避難訓練の実施率は51.5%と半分ほどに止まっていることが、先の第84回南海トラフ地震対策推進本部会議でも報告されています。
記事では、昨年元旦の能登半島地震における特別養護老人ホームなどの福祉施設で、給水車だけでは施設は守れないことや、食事も1月中は1日2食しか提供できなかったこと、発災から数日経つと、災害派遣医療チーム(DMAT)など支援の手が届くようになったことなどが照会されています。
石井美恵子・国際医療福祉大学大学院教授は「病院の入院患者や福祉施設の利用者は、自力での避難が難しい人も多い。津波は、大雨や台風と比べて避難にかけられる時間が短く、事前の備蓄や訓練、計画がより重要になる。防災の観点から外部のサポートを受けつつ、各施設のスタッフが事前の備えや発災時に優先すべきケアの項目を整理し、各施設にとって最善の事業継続計画(BCP)や訓練を模索していくことが大切だ。」と述べられています。
全国で圧倒的に多くの災害リスクを抱えた本県の医療機関や福祉施設が、少しでもリスク回避を行うための移転も含めたハード整備とBCPの実効性を高める取組を加速化しないと、多くの利用者の命を失うことになるということを肝に銘じておかなければなりません。
| 7月26日「医療センター赤字でも、県民のための医療機能の維持に向けて」 |
 昨日は、県・高知市病院企業団議会が開催され、議員協議会において、高知医療センターの2024年度決算が12億6700万円の赤字になるとの見込みが報告されました。
昨日は、県・高知市病院企業団議会が開催され、議員協議会において、高知医療センターの2024年度決算が12億6700万円の赤字になるとの見込みが報告されました。
資材価格や人件費の高騰に加え、20年度以降の収益を押し上げてきた新型コロナ関連の補助金がなくなり、5年ぶりに赤字となるものです。
医療センターは感染症指定医療機関として、コロナ下では非常時に備えて空きベッドを確保しながら、県内最多の延べ1100人余りの入院患者を受け入れ、20~23年度の4年間で国と県から空床補償などで計98億6千万円の補助金を受けてきました。
この効果で、18、19年度の赤字決算から20年度は黒字に転換しましたが、24年度には補助金がなくなりました。
24年度収入は、入院の診療単価上昇で医業収益は過去最高となったものの、コロナ補助金がなくなったことから医業外収益は大幅に減少し、前年度比5億5400万円減の245億8800万円となりました。
一方、支出は人事院勧告に伴って給与費が増加し、材料費も物価高騰などによって増加したため、経常収支は前年度の3億1200万円の黒字から、12億6700万円の赤字に転換しました。
企業長は、提案説明の中で、「物価や賃金上昇が続く中、診療報酬の改定が取り残され、官民を問わず多くの医療機関が支出増を増収分で賄いきれず、厳しい状況に置かれている」と指摘しつつ、25年度は5年ごとに更新する経営計画の最終年度に当たることから、「これまでの取り組みの成果と課題を的確に評価し、次期計画の策定に取り組む」と述べられました。
私からは、自民・公明・維新による病院病床11万章削減の方針に対して、20周年の高知医療センターが本県医療機関の中で果たす医療機能と役割を踏まえて、院長のいう「これまで通りの機能を維持するのが難しい時代。役割分担の議論をすぐにでも始めないといけない」ことと、企業長のいう「当院が果たすべき役割や責務を再確認し、次期経営計画の策定に取り組む」ということとの整合性をどう図るのかと指摘させて頂きました。
企業長からは、「がんセンター、循環器病センター、地域医療 センター、救命救急センター、総合周産期母子医療センターの5つのセンター機能とこころのサポートセンターなどの機能はしっかり維持し、経営計画の中でもその強みを活かしたものとしていきたい。そして、9階休床分をどうするのかということもあるが、経営計画の中で削減案まで示すことにはならないと考えている。」と答弁がありました。
いずれにしても、丁寧で慎重に、県民にも公開した議論を求めさせていただきました。
診療報酬改定が、物価高騰などに追いつかない中、また、医療人材の確保などが困難な中、厳しい医療環境は当分の間続くと思われますが、病院企業団議会としても、しっかりと注視していきたいと思います。
| 7月23日「『日本人ファースト』だけでない参政党の危うさ」 |
 今回の選挙結果を左右し、なおかつ比例票で立憲民主党をも上回る得票数を得た「参政党」について考えさせられます。
今回の選挙結果を左右し、なおかつ比例票で立憲民主党をも上回る得票数を得た「参政党」について考えさせられます。
神谷代表の「高齢の女性は子どもが産めない」の発言をはじめ、後からいろいろと釈明はするものの、国民を分断する発言が多く、戦後80年の間に積み上げられた歴史認識を否定するような認識を背景とした言動にも看過しがたいものも多くあると言わざるをえません。
6月23日の那覇市での街頭演説で、日中戦争について「中国大陸の土地なんか求めてないわけですよ。日本軍が中国大陸に侵略していったのはうそです。違います。中国側がテロ工作をしてくるから、自衛戦争としてどんどんどんどん行くわけですよ」をはじめとした「事実認識としては誤った戦前から存在する典型的な陰謀史観」と指摘されることも多い発言がされてきました。
戦後80年の節目に、歴史的事実を無視した極端な議論が「面白い」「新しい」と受け取られてしまう状態が広がっていることを、転換しなければならないと考えさせられます。
しかも、参政党の創憲案なるものを見ると、このような国の国民として生きていくうえで主権者たる国民の人権がどのように尊重され生きていくことができるのかと考えざるをえません。
天皇を頂点とした全体主義国家を目指し、「国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母語とし、日本を大切にする心を有することを基準として、法律で定める。」とあり、何をもって「日本を大切にする心」なのかは結局は権力次第であり、政府に批判的な主張はすべて「日本を大切にしない」非国民の言説と見なされかねず、思想統制・言論統制につながるような条文となっています。
「家族」については、各人の自由や人権の保障よりも「家族」が「あるべき家族」として成立していることを重視しており、困難は家族で助け合って解決することを求め、勝手な家族観を押し付けています。
人権保障の規定はほとんどなく、権力は自由自在に制約が可能であり、他の条文で思想・言論統制や宗教の強制も予定されていて、トータルで見ても人権保障規定はほぼないと言っても過言ではありません。
また、自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要としているが、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとするということで、結局は、どんな場合でも政府が「緊急やむを得ない」としてしまえば事前の国会承認はいらないわけで、何の縛りにもなっていません。
他にも、このような国に暮らしたくはないと思える条文の列記された創憲案を批判すれば「私が作ったものではなく、党員の思いをまとめたものである」と逃げる代表のもとの参政党を信頼することができるのでしょうか。
そして、アフターコロナで外国人観光客が増え、日本人には手が出ないような高価なものを買っていき、ホテル代はうなぎ登り、経済大国だったはずの日本が実は急激に貧しく弱くなっているような現象を突きつけられている現状で、参政党が「日本人ファースト」を掲げ、「外国人」にターゲットを定めた途端、人々は反射的にそれに飛びつき、まるでホンモノの敵が見つかったと言わんばかりの感情が参政党の支持者の間に広がったのではないでしょうか。
参政党は今回「日本人ファースト」を掲げて躍進しましたが、今後、彼らの定義する「日本人」の定義は狭まり、「真の日本人」は日本国籍であることだけではなく、国のために尽くすことを宣言したものだけになることも警戒しておかなければならなりません。
| 7月21日「参院選後の流動的な政治状況に注視を」 |


事実上の「政権選択選挙」と言われた参院選で、自民、公明の与党が大きく議席を減らし、昨年の衆院選に次いで参院でも与野党逆転となりました。
結果は以下の通りです。
自民党39、立憲民主党22、公明党8、日本維新の会7、共産党3、国民民主党17、れいわ新選組3、参政党14、社民党1、日本保守党2、諸派1、無所属8。
今回の選挙は、SNSを駆使した新興勢力の台頭は、既成政党に対する不信や不満の表れと見られ、排外主義やポピュリズムが、この国の針路に影響を与えるかどうかも問われるような戦後政治の大きな転換点になるかもしれません。
そのような中で、政権交代のある政治をめざした衆院選の小選挙区比例代表並立制導入から30年経過しても、期待したような2大政党には遠く、政権批判票がこぞって野党第1党の立憲民主党に向かうことはなく、複数の野党に分散するという多党化時代を迎えようとしています。
中でも急伸した日本人ファースト」を掲げる参政党は、国民の多様な価値観を反映する多様な政党が国政に参入するということ自体には意味があるかもしれないが、その訴えには危うさを感じざるをえません。
特に、今回の参院選では、参政が引っ張る形で、外国人政策のあり方が争点となり、党代表の街頭演説では、排外主義ともとれる発言や根拠不明な物言いも目立つなど外国人への差別や偏見を助長するような主張は看過できるものではありません。
選挙戦なら何でもありということで許されるはずはないと指摘してきたが、その言動には驚くばかりで、時間が経つほどその政党の本質が明らかになり、ただ「若者の政治参加の機会が増えたからよかった」だけではすまないことをしっかりと踏まえて、共生社会に逆行する動きを放置しないようにしていきたいものです。
そんな中、選挙区では、私たちが支援して闘い抜いてこられた野党共同の無所属の広田一さんが自民党公認・公明党推薦候補に63272票の差をつけた264891票を獲得して勝利しました。
しかし、高知・徳島選挙区でも政権への批判票の受け皿が立憲野党となって前進するのではなく、危うい参政党など新保守勢力が一定の受け皿となる結果が見られただけに、この状況をしっかりと見極め、改めて立憲野党と市民をつなぐ社会課題と寄り添う政策を繋いでいきたいものです。
| 7月18日「よい くにを つくること」 |
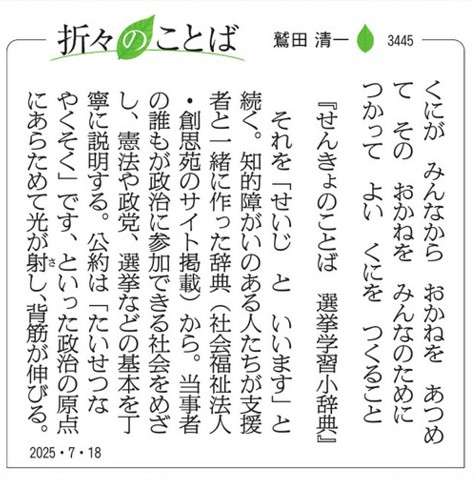 今朝の朝日新聞「折々のことば」で「くにが みんなから おかねを あつめて その おかねを みんなのために つかって よい くにを つくること」(『せんきょのことば 選挙学習小辞典』)それを「せいじ と いいます」と続くと紹介されていました。
今朝の朝日新聞「折々のことば」で「くにが みんなから おかねを あつめて その おかねを みんなのために つかって よい くにを つくること」(『せんきょのことば 選挙学習小辞典』)それを「せいじ と いいます」と続くと紹介されていました。
これは、知的障がいのある人たちが支援者と一緒に作った辞典(社会福祉法人・創思苑のサイト掲載)から引用したもので、当事者の誰もが政治に参加できる社会をめざし、憲法や政党、選挙などの基本を丁寧に説明しています。
こちらから、ご覧いただくことができます。
執筆された鷲田清一さんは、「公約は『たいせつな やくそく』です、といった政治の原点にあらためて光が射し、背筋が伸びる。」と結ばれています。
そんな思いで、真摯に政治や選挙と向き合おうとしている人がいるのに、自らの党の創憲案を「法律の知識を持たない党員の「思い」を形にしたものであり、素人でつくったんですよ。」などと言い、「日本人ファースト」というスローガンは、外国人を敵視する排外主義だと批判を浴びたら、「選挙のキャッチコピーだから、選挙の間だけなので。終わったらそんなことで差別を助長するようなことはしない」などという政党の支持が伸びようとしていることを看過できないのは私だけでしょうか。
そして、「みんなのために つかって よい くにを つくる」財源を、航空自衛隊のF15戦闘機に、敵基地攻撃能力(反撃能力)を担う「スタンド・オフ・ミサイル」を搭載するための改修など関連経費の費用の見通しが1.5倍超に膨らませて1兆円にするような使い方をする政党に政治を任せてよいのでしょうか。
常に、「政治を変えるとは税金の使い方を変えることであります。国民に寄り添った政策に税金を使うことです。」と訴えてきた広田一候補の勝利で、昨年の衆院選で勝ち取った与野党逆転を参院選でも勝ち取り、国民の求める政治のあり方を実現していきましょう。
| 7月17日「『政治とカネ』に向き合わない自民党」 |
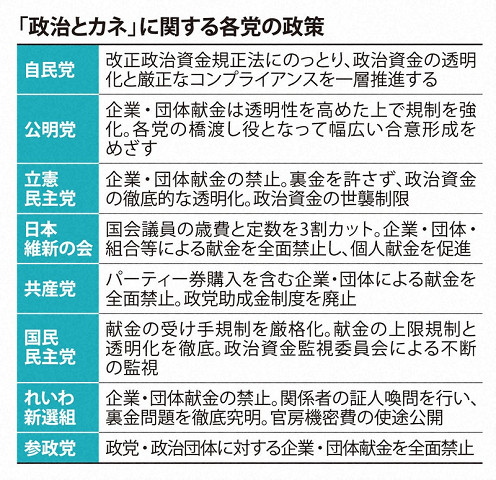 投票日まで、今日も含めて三日間となりました。
投票日まで、今日も含めて三日間となりました。
改めて、気づかされるのは、自民党は参院選で「政治とカネ」が争点化することを徹底的に避けているということです。
選挙戦での言及はほぼなく、公約でも昨年の衆院選では前面に押し出していた政治改革についてわずかな記載にとどまり、党内では企業・団体献金の禁止・廃止や規制強化への警戒感が強く、「先送り戦術」を続けて逃げ切りを図ろうとしていると思われます。
自民党幹部は応援演説でも、野党を無責任だと批判しながら、自らは通常国会で企業・団体献金の存続を前提に透明性を向上させる法案を提出したが、採決すらせず、一時、公明、国民民主両党と規制強化に向けた案も検討したが、法案提出に至りませんでした。
自民の消極姿勢が顕著に表れているのが参院選の公約で、政治改革は公約で示した三つのビジョンに含まれず、企業・団体献金の廃止や規制強化に言及せず、「(現行の)改正政治資金規正法にのっとり、政治資金の透明化と厳正なコンプライアンスを一層推進する」と記載するにとどめ、公約からは、このまま幕引きを図りたい自民の思惑が見て取れます。
自民の「政治とカネ」と正面から向き合わない姿勢は、参院選の候補者擁立にも表れています。
昨年の衆院選では、裏金事件に関与した旧安倍派議員ら12人を非公認としたが、参院選では裏金事件に関与した旧安倍派議員13人は、参院政治倫理審査会での弁明を終えているため、「一定のみそぎは済んだ」といずれも党公認で擁立しています。
一方、公明は、選挙区から出馬した旧安倍派議員10人のうち、3人の推薦にとどまったのは、衆院選で、自民が非公認とした裏金議員を公明が推薦したことへの批判が強まったことからと思われますが、3人推薦したことにも公明内からは、「昨年の衆院選の二の舞いになりかねない」と不満が噴出しているとのことです。
とにかく、「政治とカネ」の問題から逃げる自民党では、本気の政治改革はできないと言わざるをえません。
| 7月15日「参院選で自公政権の退場を」 |



米不足や物価高騰、金権裏金政治が争点の参院選はいよいよ終盤を迎えました。
全国に32ある改選数1の「1人区」で自民党の苦戦が目立ち、比例代表でも与党は厳しい戦いを強いられています。
与党過半数維持に向けて「頼みの綱」の公明党も苦戦しており、今回も「少なくとも選挙区5、比例5の10議席は堅い」(自民幹部)との見方が大勢だったが、大きく下回るかもしれないと言われています。
そこで、いわゆる立憲野党勢力にとって、庶民の生活と政治不信を生み出した自公を参院でも少数に追い込めるのか、政権の補完勢力を痛撃することも大きな課題となっています。
ここに来て、「日本人ファースト」など外国人への差別と排斥の主張がデマを含めて広がりを見せているが、これはかつて維新が公務員バッシングで足場を築いたのと同じ思考で有権者の分断を図っていると言えます。
内政が行き詰まると外敵を作り、戦争への道を歩もうとする政治勢力を許すことなく、戦後の民主主義と平和主義、基本的人権が問われる闘いに勝ち抜く候補の勝利と立憲野党の前進に向けて闘い抜かなければなりません。
そのためにも、選挙区では無所属で自公の巨大な権力と闘う広田はじめ候補の勝利に向けて最後まで全力を尽くします。
そして、比例区は、自治体に働く仲間とともに闘う「立憲民主党の岸まきこ」候補の再選と水道の民営化に反対し、トラック運転手のまともな働き方を求め、平和を守るために初挑戦する「社民党のかい正康」候補の勝利で立憲民主党、社民党の前進を図るために頑張っています。
いずれにしても、自公政権に「退場」を突きつけるのが、この参院選です。
皆さん、ともに頑張りましょう。
| 7月14日「ヘイトスピーチは選挙戦でも許されない」 |
 投票日まであと一週間となった参院選では、「日本人ファースト」「違法外国人ゼロ」、「外国人優遇策の見直し」だとかが掲げられるなど政党によっては、排外主義扇動を競い合っている状況が見受けられ、さながら選挙戦において外国人に対するヘイト合戦のようなことが横行しています。
投票日まであと一週間となった参院選では、「日本人ファースト」「違法外国人ゼロ」、「外国人優遇策の見直し」だとかが掲げられるなど政党によっては、排外主義扇動を競い合っている状況が見受けられ、さながら選挙戦において外国人に対するヘイト合戦のようなことが横行しています。
このようなことに対して、「『外国人が優遇されている』というのは根拠のないデマ」だとし「違法外国人」という用語についても外国人が「違法」との偏見をあおるものだと批判し、外国人労働者や難民の人権問題に取り組むNGOなど民間8団体が8日、参院選で政党によっては、外国人や外国にルーツを持つ人々を敵視するような政策を打ち出しているとして、排外主義の扇動に反対する「参議院選挙にあたり排外主義の煽動に反対する NGO 緊急共同声明」を発表し、すでに266団体が賛同しています。
緊急声明では「政府や国会などの公的機関は人種差別撤廃条約に基づき、ヘイトスピーチをはじめとする人種差別を禁止し、さまざまなルーツの人々が共生する政策を行う義務がある」と強調し、各党や候補者に排外主義をやめ、政府・自治体には選挙運動におけるヘイトスピーチが許されないことを徹底して広報するよう求めています。
法務省は2019年3月12日の事務連絡で「選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について」を発出し、「不当な差別的言動は、選挙運動等として行われたからといって,直ちにその言動の違法性が否定されるものではない」と警告しています。
ヘイトスピーチ、とりわけ排外主義の煽動は、外国人・外国ルーツの人々を苦しめ、異なる国籍・民族間の対立を煽り、これから本気で築いていかなければならない共生社会を破壊し、さらには戦争への地ならしとなる極めて危険なものである以上、現状の参院選挙戦での一部の政党のキャンペーンがこのまま看過されていいのでしょうか。
罰則つきのヘイトスピーチ禁止条例のある川崎市は7月7日、ホームページで「STOP!不当な差別 ~ 特定の国の出身者を排斥する差別的言動は許されません ~」と題して、「 選挙運動、政治活動の自由は、民主主義の根幹をなすものですが、川崎市内の道路や公園等の公共の場所で、拡声機等を使用し、特定の国の出身者をその居住する地域から退去させることを扇動する等の不当な差別的言動を行うことは、条例により禁止されています。 特定の国の出身者を排斥する差別的言動は、インターネット上においても許されません」と掲載しています。
また、「日本人ファースト」というスローガンを掲げている政党が比例代表の投票先で上位に浮上していますが、ここには外国人というだけでファーストではない、ないがしろにしていいかのようなメッセージも含まれており、米国ではアメリカファーストとのスローガンの下、日本人に対し暴力的な排斥がなされていることからも排外主義につながっていると言えます。
米などの物価が上がり、賃金は上がらず、皆が生活に困っているのは外国人のせいではなく、これまでの政府の政策が原因であり、外国人を攻撃して排除しても私たちの生活が良くなるわけではないのに、外国人がそのような不満のスケープゴートとされていることをしっかりと見極めることが必要です。
声明では「私たちは、選挙にあたり、各政党・候補者に対し排外主義キャンペーンを止め、排外主義を批判すること、政府・自治体に対し選挙運動におけるヘイトスピーチが許されないことを徹底して広報することを強く求めます。また、有権者の方々には、外国人への偏見の煽動に乗せられることなく、国籍、民族に関わらず、誰もが人間としての尊厳が尊重され、差別されず、平和に生きる共生社会をつくるよう共に声をあげ、また、一票を投じられるよう訴えます。」と、結ばれていますが、私たちもそのことをしっかりと訴えていきたいものです。
| 7月13日「要配慮者の避難の在り方」 |
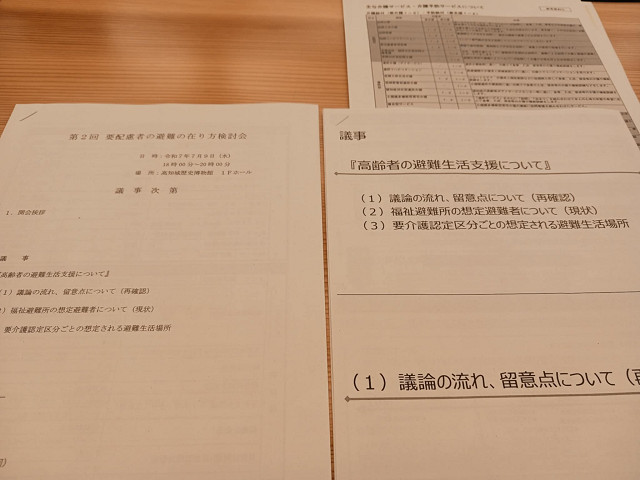 7月9日に、災害時の要配慮者の避難生活のあり方について検討する「第2回 要配慮者の避難の在り方検討会」の傍聴をさせて頂きました。
7月9日に、災害時の要配慮者の避難生活のあり方について検討する「第2回 要配慮者の避難の在り方検討会」の傍聴をさせて頂きました。
この検討会は、南海トラフ地震等の大規模災害が発生した際に、要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者)の心身の健康状態の悪化を防ぐため、適切な避難先の確保等、具体的な避難対策について議論するための検討会で、昨夜の議題は「高齢者の避難生活支援について」であり、議論で目指すところは、「具体性のある福祉避難所への想定避難者数及び福祉避難者受け入れ可能人数」を算出しようとするものです。
「議論のゴール」としては、福祉避難所が限られる中、要配慮者の健康や要介護度の悪化を防ぎつつ、安全な避難場所を確保するため、要配慮者の属性ごとに避難生活を送る対象者の目安を示すこととしています。
➀避難所ではなく、病院や社会福祉施設への移送が必要な人➁福祉避難所への避難が必要な人➂一般避難所の福祉スペースで生活可能な人などの属性ごとにどうあるべきかなどが検討されていました。
お聞きしていて、令和3年5月「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」が改定されているが、例えば福祉避難所への直接の避難の促進など改定内容が踏まえられた議論になっているのか。また、執行部の説明の中でも度々使われていたが、今は「丼勘定の把握」と言う現状で、その曖昧さがこれから議論する上での前提において、委員の方々との齟齬が生じているのではないか。また個別避難計画との関係等についての議論もこれから重要になってくるのではと考えさせられることが多くありました。
いずれにしても、この議論はまだ緒に就いたばかりと言わざるを得ませんが、議論を加速化しないと高知での「災害関連死」は回避できない事になるのではないかと思ったところです。
| 7月11日「観光×防災×福祉」 |

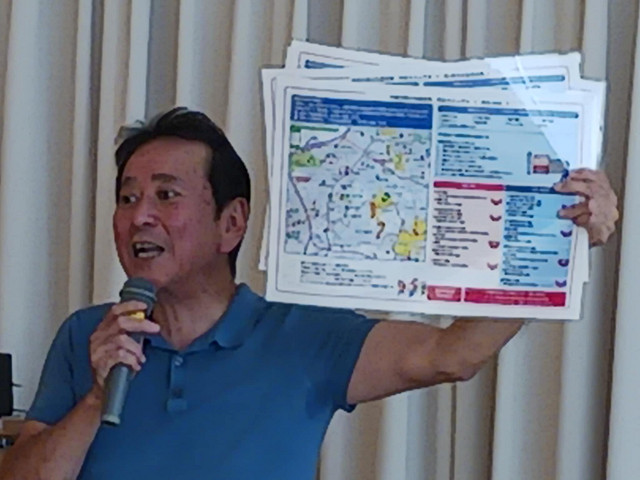


今朝の高知新聞にも記事がありましたが、9日の午後から、「令和7年度高知県バリアフリー観光防災セミナー」に参加させて頂きました。
高知県では、災害発生時に障害のある方を含む本県を訪れている方が円滑に避難できる受け入れ環境の整備に取り組んでいます。
今回のセミナーでは、沖縄県でバリアフリー観光防災に取り組まれているNPO法人バリアフリーネットワーク会議の親川修氏を講師にお迎えし、「沖縄市におけるバリアフリー観光防災について」と題して、バリアフリー観光防災の考え方や取り組みについて講演頂きました。
▼自助と共助どうつなぐのか。そこに障害があった時、どうするのか。福祉で得た情報を観光に提供することは大事なこと。
▼何かが起きたときに置いていかれてはならないからこそ、障がいのある方たちを安全に避難させる『逃げるバリアフリー』の大切さを確認すること。
▼『入り口のバリアフリー』は徐々に進んでいるが、『出口のバリアフリー』の改善は進んでいるのか。安心と安全は、すべての人に公平に確保されなければならない。観光地の要援護者には外国人も含まれる。
▼災害に対する心構えとして、最善と最短を常に考える。宿泊施設や公的な施設では、利用者・宿泊者は健常者だけではないということの想定をし、訓練には当事者を参加させること。
▼『入り口』も『出口』もバリアフリーであるところこそ、真の観光地である。
など、しっかりと受け止め、具体化に繋げなければならないことを沢山学ばせて頂きました。
| 7月10日「被災地・被災者に真に寄り添えない政治家は許せない」 |
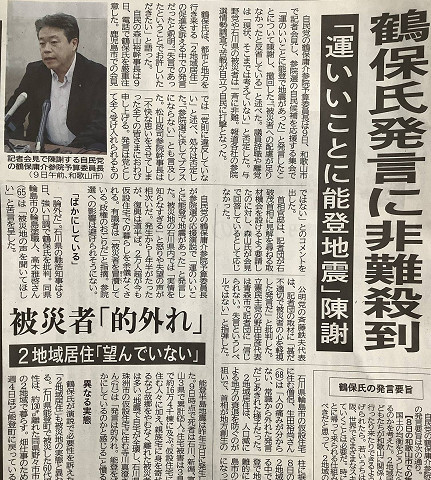 自民党の鶴保庸介参院予算委員長が8日の参院選の応援演説で、都市と地方に拠点を置く「二地域居住」について話す中で「運のいいことに能登で地震があった」と発言し、被災地をはじめ多くの国民から非難を受けています。
自民党の鶴保庸介参院予算委員長が8日の参院選の応援演説で、都市と地方に拠点を置く「二地域居住」について話す中で「運のいいことに能登で地震があった」と発言し、被災地をはじめ多くの国民から非難を受けています。
鶴保氏は謝罪のコメントを出し、発言を撤回し、記者会見を開いて「被災地への配慮が足りなかった」と述べたが、看過できるものではないというのが、被災地の多くの皆さんの怒りだと思います。
二地域居住を巡っては、地方への人の流れを生むことなどを目的として昨年11月に「改正広域的地域活性化法(二地域居住促進法)」が施行されているが、被災地では誰もが求めて二地域居住をしているわけではなく、災害に対して国の救助・復旧・復興支援策の後れで強いられてきた二地域居住なのです。
災害関連死も含めて約640人に上る被災地での被災者に思いを寄せたら、こんな発言には至らないことでしょう。
過去にも、「被災者を傷つける」自民党議員は、繰り返し現れました。
2017年に今村雅弘復興相が東日本大震災に関し、「まだ東北であっちの方だったからよかった」と発言し、19年にも桜田義孝五輪相が被災地を地盤とする議員を「復興以上に大事」と持ち上げ、いずれも直後に更迭されています。
いくら石破政権が「防災庁」設置を掲げても足下の自民党には、被災者や被災地、本当に困っている生活者に寄り添う姿勢がないという本質が改めて露呈した発言と言わざるをえません。
法政大大学院白鳥教授は、鶴保氏の発言を「突然、日常奪われた被災者へ寄り添う気持ちが全く感じられない」と非難し、「度重なる失言の原因は、12年から続く長期政権の奢りによるものとし、政権の姿勢が問われる。参院選で有権者は厳しく判断するだろう。」と指摘されていますが、そのような結果を示さなければ、この人たちは心の底から反省するということはないでしょう。
| 7月8日「国民は自民党の政治とカネの問題を忘れていない」 |
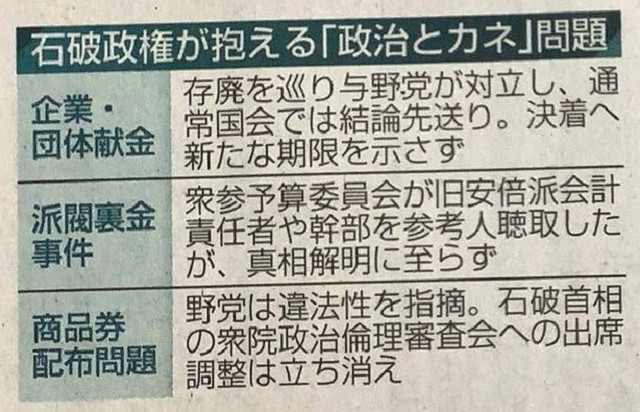 自民党が、この参院選では、隠そう隠そうとしているようにしか思えない自民党派閥裏金事件に端を発した企業団体献金禁止に応じず、結論を2度にわたって先送りした政治改革問題。
自民党が、この参院選では、隠そう隠そうとしているようにしか思えない自民党派閥裏金事件に端を発した企業団体献金禁止に応じず、結論を2度にわたって先送りした政治改革問題。
石破首相は、裏金事件の実態解明に積極的に動かず、真相はうやむやのままにしてきました。
そして、首相自身による衆議院1期生への10万円商品券配布問題にしても、野党から違法性を指摘されたもののこれも決着がついていません。
野党は、もともと企業団体献金廃止の禁止の是非について3月末までに結論を得ると合意していたが、存続前提の自民、公明、国民民主党と、禁止でまとまる立憲民主党など野党の溝は埋まらず、4月以降に持ち越しました。
そして、6月22日の通常国会会期末が迫り、結論を得るのが絶望的になると、新たな期限を求める野党と意見が折り合わず、自民党は何の確約もしないまま国会は閉会しました。
朝日新聞が行った参院選候補者に対する自民党派閥の裏金問題を受けた政治改革で、見直しの結論が先送りされた企業・団体献金の意識調査について、「全面禁止」派は、立憲民主党で86%、日本維新の会でも89%を占めたのに対して、自民ではゼロだったと今朝の紙面で報じられています。
政治と金の不祥事が続いているのに、この件に関しては反省もできないし、改めることのでくない党であることが明らかになったとしか言いようがありません。
国民は、忘れていないことをしっかりと意思表示する結果を出さなければなりません。
| 7月7日「個別避難計画づくりで日頃の見守りを」 |
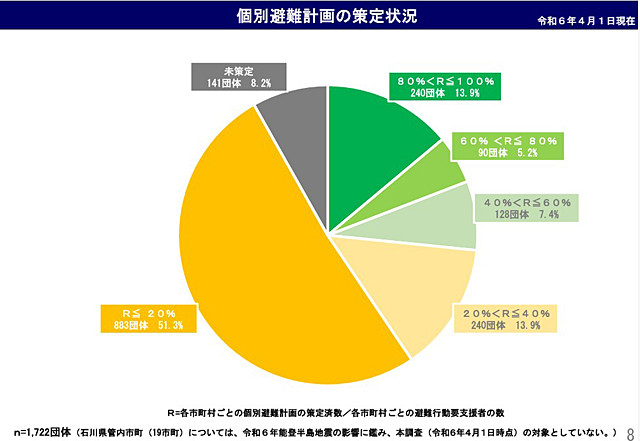
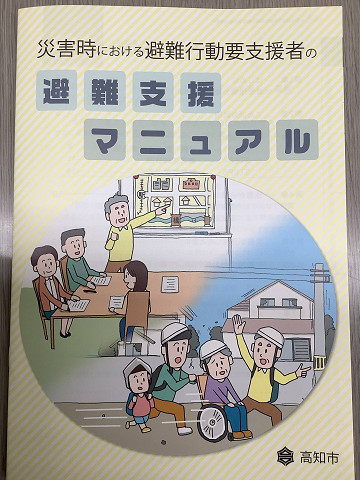
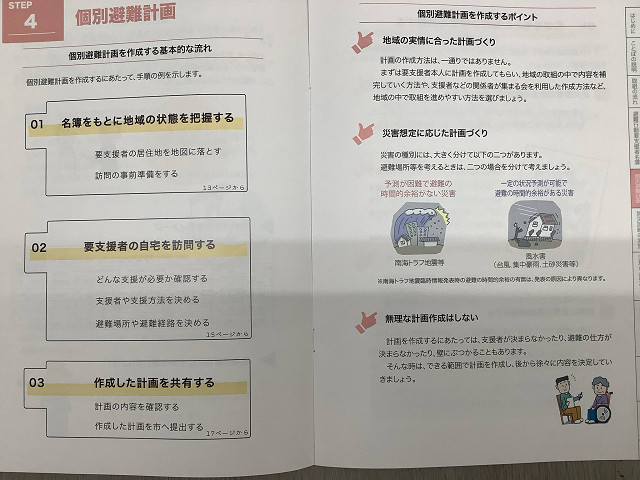
2018年6月28日から7月8日にかけて、西日本を中心に北海道や中部地方を含む全国的に広い範囲で発生した、台風7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨を私たちは西日本豪雨と呼びますが、あれから7年目の7月7日です。
死者が263人、行方不明者8人で特に多かったのは広島県(114人)、岡山県(64人)、愛媛県(27人)の3県となっています。
そして、犠牲者の多くが高齢者で、自力で避難が難しかったり、情報が伝わらずに逃げ遅れたりしたことが一因とみられており、いわゆる避難行動要支援者への支援の大切さが浮き彫りになったことを忘れるわけにはいきません。
この教訓から、2021年改正の災害対策基本法で、自力避難が難しい人の避難手順をまとめる「個別避難計画」の策定が自治体の努力義務となって、市町村が作る「要支援者名簿」に基づいて個人単位で作成し、最寄りの避難所や支援者などを記載することとなりました。
しかし、その策定状況も全国の自治体では、まだまだ進んでおらず、本県においても県下全体では39.9%、高知市では37.4%に止まっており、これが津波浸水エリアでは、高知市は15.8%となっています。
近年は本人が日常的に利用している介護や障害者サービスの利用計画と一緒に災害時の個別避難計画を作る動きが広まっているが、その計画を、いざという時に動いてくれる地域住民と共有し、避難の具体策の検討や訓練を行う自治体もあるといわれています。
高知市なども、そのようにして策定されている場合もあるが、そのために大切なのは、手助けを必要とする人々と地域が平時から積極的につながりを持つことであり、どんな支援が必要か、積極的に話し合える機運を地域で高めていくことが求められています。
昨夜も、マンション防災会の定期総会で、この課題について議論する中、策定したもののいかに計画の実効性をあげていくことが大事かとの議論もされ、改めて平時からのつながりづくりを検討していきたいとの意見が出されました。
| 7月5日「防災人づくり塾で『事前復興』」 |

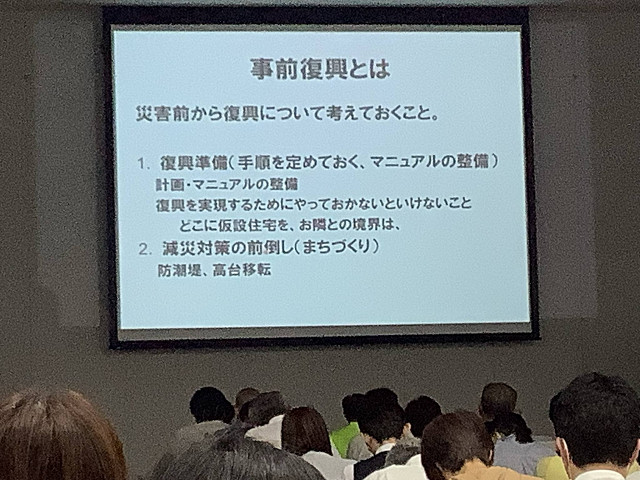
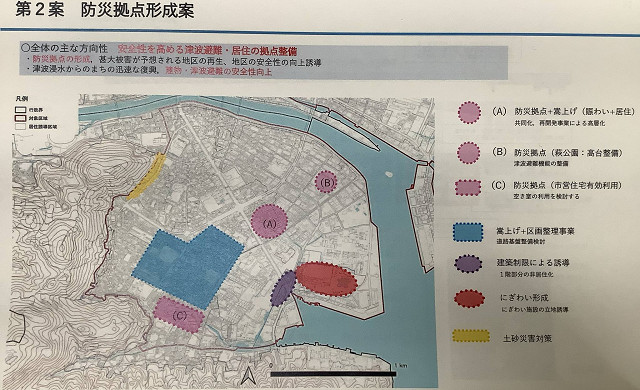
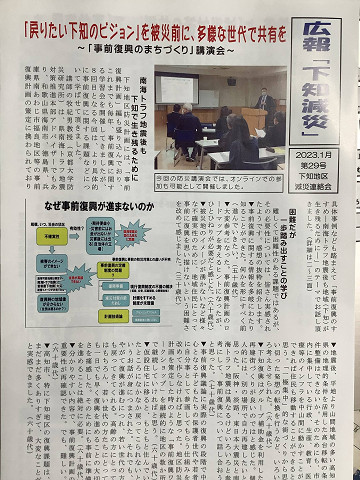
昨夜は、傍聴という形で、高知市の「防災人づくり塾」を聴講させて頂きました。
昨年も、特別聴講させて頂いたのですが、京都大学防災研究所の牧紀男教授による「事前復興のすすめ 南海トラフ地震後の高知の生き残り」です。
昨年の臨時情報を通じて、南海トラフ地震情報の歴史であるとか、多様な発生形態の問題などについてまずは理解を深めさせて頂きました。
その上で、平成の時代のすべての被害復興課題を包含する地震動による建物倒壊、延焼火災による災害、孤立・避難、人口減少社会での復興、津波被害などを通じて、改めて登半島地震について考え、事前防災でどのように被害を少なくできるのかについて確認させて頂きました。
だからこそ、復興の課題を知り、その課題も頭に入れて「事前復興」について考えるのか、東日本大震災における復興のあり方や現状からいくつかの課題についてお話しいただきました。
復興のまちづくりを考える上で、注目すべき3つのプロジェクトとして、地方都市の商店街のモデル、防潮堤とテラスなどを一体化した事例、グループ補助金による再建等について具体的な事例としてキャッセン大船渡、気仙沼市「迎(ムカエル)」、名取市閖上の「かわまちテラス」などのお話を聞かせて頂きました。
また、復興がうまくいっているのか、震災後の人口がどうなったのか、それらの課題から南海トラウ地震が起きた後、私たちが何を考えるべきなのか、そのような課題について東日本大震災での教訓をお話し頂きました。
高知市でも、南海トラフ地震後の復興について、災害前から考える「事前復興」の取り組みが行われています。
最後に、牧先生が座長を務められている高知市事前復興まちづくり計画策定検討委員会で議論され、ワークショップが始まる三里地区と潮江地区の素案事例についてご紹介も頂きました。
私たちも下知地区で、来年の1月頃からワークショップが始まる予定で、そこに向けた準備を下知地区減災連絡会で始めたところです。
牧先生からは3年前に下地地区減災連絡会で、事前復興についてのお話を聞かせて頂いて以来、課題意識を持ちながら向き合ってきましたが、いよいよこれから本格的な議論になっていきます。
先生が仰る「復興感が高くなる傾向にある若い人が転出しまうと、なかなかその街は復興していけなくなる。若い人が残れる復興事業ができれば良いのではないか。そのためにも若い人たちと共有できる事前復興計画を作っておくことが必要。例えば名取市閖上地区では、災害後はとても戻れる状況ではないと思われていたが、復興できた姿を見て帰ってくる人が多くなっているとの事。個人だけのことを考えれば1人で地区外へ出て行って自力再建をすると言うことになるが、これだけでいいのか地域が復興すると言うことも考えれば、そのギャップを埋めるのは『事前復興』でしかできない。」
この言葉を、私たちの地域で実践していきたいものです。
| 7月4日「平和と暮らしの危機を招かぬ政治を」 |
 昨年の衆院総選挙では、金権・腐敗政治への怒りが自民党を過半数割れに追い込みました。
昨年の衆院総選挙では、金権・腐敗政治への怒りが自民党を過半数割れに追い込みました。
少数与党に陥った自公政権が、もう少しはまともに国民の声に耳を傾けた姿勢で臨むのかと思いきや、数合わせでの法案修正などに止まってきました。
石破政権が予算編成で掲げたのは「賃上げと投資をけん引する成長経済への移行」であったが、その実体は軍拡と巨大企業への財政投入であり、生活に苦しむ国民を置き去りにする内容であり、多くの国民は、物価高で疲弊するばかりです。
消費税減税を拒否し、原発事故はなかったことにするエネルギー政策、血税を注ぎこんで戦争ができる国家へと突き進む政府・与党の本質を絶対見失ってはなりません。
戦後・被爆80年の節目の参院選でありながら、相変わらずのロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・パレスチナ・イランの交戦と何よりも許せないガザでのジェノサイド、それにアメリカ・トランプ政権による軍事介入や軍事費拡大を求められ、戦争への準備は止まりません。
今こそ、不戦・非武装、脱原発、所得分配を求める共同の闘いとともに、「武力で平和は実現できない」と訴える立憲野党や政治勢力の前進が不可欠で、この訴えが「物価高騰対策」によってかき消されてしまうことがあってはならないと懸念しています。
そして、選挙区では、与野党逆転の政治の流れの端緒となった広田一さんの再選を勝ち取るために、皆さんとともに全力で闘い抜きたいものです。
| 7月3日「気仙沼の防災・減災・復興に学ぶ」 |



20年来ご指導いただいている跡見学園女子大学教授鍵屋一先生のご紹介で、2017年1月に、お会いさせて頂いた気仙沼市元危機管理監の佐藤健一さんが、昨日「令和7年度高知県市町村職員防災基本研修」の講師として来られていて、夜の時間にお付き合い頂きました。
2017年8月には、当時の昭和小学校の先生方とともに、被災地の学校現場調査の際にあわせて気仙沼市内の復興状況や高台避難で大きな犠牲を出された杉ノ下地区等ご案内頂き、高知での減災や災害復興のあり方や避難場所としてのビルや高台などの課題をいろいろとお話し頂いたことでした。
その後、高知にお越しになった際にも2度ほど短時間でしたが、お声をかけて頂きましたが、昨夜はじっくりと2時間半、防災に関する積もる話をさせて頂いたことは貴重な機会でした。
3.11以前に備えられた気仙沼市の住民主体の事前防災は、被害が大きくても復興につながる住民と行政の信頼関係を築いていたことの大切さを改めて学ばせて頂きました。
これから高知で向き合う事前復興のまちづくりは住民と行政の協働作業として取り組まれなければならないと思います。
今後もいろいろとご指導いただき、高知の備えに活かせて行けたらと思うひと時でした。
今日公示となる参院選においても、災害リスクの大きな未災地の私たちにとっては、命と暮らしをまもる防災政策も大きな争点だと思っています。
| 7月1日「政務活動報告で県民と課題意識を共有」」 |
 毎年7月1日には、県議会で政務活動費が公表され、高知新聞に記事が掲載されます。
毎年7月1日には、県議会で政務活動費が公表され、高知新聞に記事が掲載されます。
昨年は、私の記載欄で誤発表があり、後日記事の訂正されましたが、今年はそのようなことがなく、個人分では「調査研究費」22千円、「広報公聴費」612千円、「資料作成費」34千円、「資料購入費」235千円、「事務費」5千円で合計91万円でした。(詳細はこちらから)
この支出分を除いて769千円は返還しています。
県議会全体では、県議個人と会派への交付総額は1億2236万円で、支出は1億544万円で、全体の使途別では、県政報告の広報紙の印刷、配送代などに充てる広報広聴費が3852万円で、11年連続で最多となっています。
政務活動費全体では、1753万6千円が各会派・議員個人から返還されいます。
私は、この報告において重要なのは、政務活動費の決算だけでなく、活動報告で自らの政務活動を報告することによって県民の皆さんと調査内容を共有することではないかと思っています。
今回も、昨年の67頁を大きく上回る84頁と多めで、お目通し頂くのは恐縮しますが、ご関心があればこちらからご覧いただけます。
これからも、日頃のこのホームページでの情報共有と政務活動調査報告書での共有で県政の課題理解を深めて頂けるよう努力するとともに、政務活動費を個人、会派ともに有効に活用していきたいと思います。
| 6月30日「生活保護引き下げ最高裁違法判決」 |
 国が2013~15年にデフレによる物価下落を理由に食費や光熱費など生活費部分の基準額を最大10%引き下げ、計約670億円を削減したことを違法と認め、減額決定を取り消す最高裁判決が27日に出されました。
国が2013~15年にデフレによる物価下落を理由に食費や光熱費など生活費部分の基準額を最大10%引き下げ、計約670億円を削減したことを違法と認め、減額決定を取り消す最高裁判決が27日に出されました。
最高裁は、 通常の改定時には行われる専門家による検討を経ていないこと、それまでと違って物価変動だけを直接の指標としたことを指摘し、合理的かどうかについて、専門的知見に基づいた十分な説明がされていないことを重視し、厚労相の判断過程に誤りや落ち度があったと結論づけました。
引き下げ前の2011~12年頃、リーマン・ショック後の世界的大不況の影響で生活保護利用者が右肩上がりで急増し、一般世帯の暮らしも上向かない中で、芸能人の家族の制度利用などをきっかけに、生活保護制度や利用者を狙った「生活保護バッシング」が過熱しました。
そんな中で迎えた12年の衆院選で、野党だった自民党は公約に「給付水準10%引き下げ」を掲げて大勝し、政権に返り咲くことによって厚生労働省は翌年、生活費にあたる生活扶助を3年かけて平均6・5%、最大10%引き下げることとしました。
自民の選挙公約への「忖度」が容易に推認されるみので、生活保護バッシングに乗じて行われた、国による最大の生存権侵害だったと言えます。
生活保護は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るためにあるもので、生活保護は最後の安全網であり、「いのちの砦」なのです。
それが、SNSでは利用者を攻撃する書き込みが後を絶たないし、最近でも、自治体の窓口で申請を拒む露骨な「水際作戦」が明らかになっており、その利用をためらわせるような差別や偏見を社会から取り除けるのか問われているのではないでしょうか。
この当時も自民党は「自助自立」を前面に掲げていたし、菅政権も誕生当時のまずは自助優先の政治姿勢の自民党が参院選で国民の置かれた暮らしとどのように向き合うかが問われているのではないでしょうか。
| 6月29日「自民党と党公認参院立候補予定者の政策対応の違い」 |
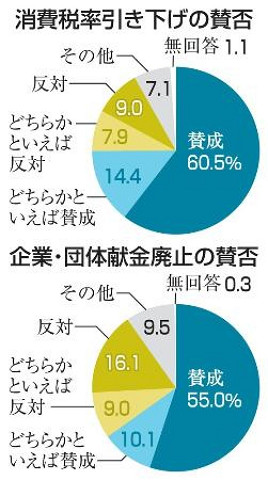
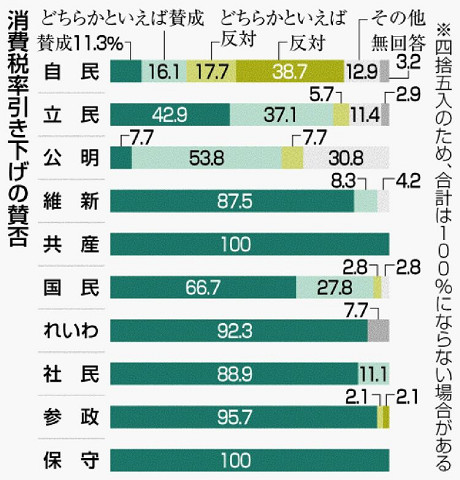 共同通信社が参院選の立候補予定者を対象に政策アンケートを行った結果について、今朝の地方紙面に記事となっています。
共同通信社が参院選の立候補予定者を対象に政策アンケートを行った結果について、今朝の地方紙面に記事となっています。
367人から回答を得た中で、消費税の税率引き下げについて「どちらかといえば」を含め74.9%が賛成で、反対は16.9%でした。
国会では、消費税税率引き下げについて頑なに反対し続けた自民党の27.4%が「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答し、公明党は61.5%が賛成派でした。
自公はそれぞれ参院選の公約に消費税減税を盛り込むことを見送ったが、候補者内には税率引き下げを求める意見が一定数ある実情が浮かび上がっています。
また、企業・団体献金廃止は賛成が65.1%が賛成し、自民党の中で企業・団体献金廃止に賛成したのは僅か3.2%で、何らの体質の変化は見られません。
そして、参院選後に優先して取り組む課題を三つまで聞くと「物価高対策」が70.6%と最多で、「年金、医療など社会保障」46.3%、「子育て支援、少子化対策」45.8%と続いています。
備蓄米を順次放出した政府のコメ価格高騰対策が十分だったかどうかの質問には、「十分」は3.5%にとどまり、「不十分」が74.7%を占めています。
自民党の公約・国会での対応との違いが見受けられる自民党の予定候補者の二枚舌をしっかり見極めていくことが必要となってきます。
| 6月28日「6月定例会閉会」 |



昨日で、県議会6月定例会は閉会となりました。
閉会日の本会議では、「とさでん交通」についてコロナ禍で増えた債務12億円の解消に向けた返済の支援費として、およそ8億円などを計上した全体で24億1700万円の一般会計補正予算案など、執行部提出の18議案を全会一致で可決、承認、同意し、閉会しました。
補正予算には、高校の授業料の支援において、これまで設けていた年収910万円未満とする世帯収入の要件を撤廃し、すべての高校生を対象に基準額の年間11万8800円を支給するための費用3億3700万円余りをはじめ、香南市の県立青少年センターの敷地内に、南海トラフ巨大地震などの災害時に活用する支援物資の備蓄倉庫を整備するための設計費用として1500万円余りも計上されています。
総務委員会で全会一致で提出することとなっていた「イスラエルのイラン攻撃に端を発する大規模軍事衝突の早期収束を求める特別決議案」は、「停戦合意」に至っている状況の中、タイミングとして出すのは無理ではないかとの一部会派からの申し出があり、全会一致とならず取り下げられました。
再度今の情勢に合わせて文言修正をしてでも再提出をすればとの思いがあり、文言修正案も考えていただけに、「停戦合意」が確かなものとなるのかどうかの懸念は残ります。
意見書議案については「消費税の減税を含む物価高騰対策の実施を求める意見書」については、共産党会派と県民の会は賛成しましたが、自民・公明党などの反対で否決されました。
一方、「納得のできる米の価格と安定供給を求める意見書」は全会一致で可決しました。
また、共産党会派と県民の会で提出した「日本学術会議の独立性と自主性を保障することを求める意見書案」について、私が賛成討論をさせて頂きましたが、賛成少数で否決となりました。
| 6月26日「災害への備えで求められるご近所づきあい」 |

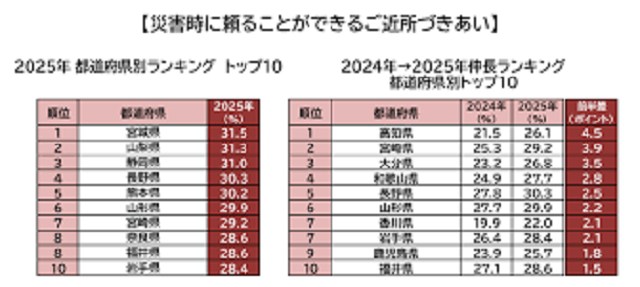
株式会社マクロミルという調査会社が全国20万人を対象とした防災意識調査「マクロミル・チャリティーアンケート」を実施し、その都道府県別結果も発表されました。
この調査は、今後起こり得る災害に備える一助となることを目的に、生活者の防災意識を調査によって可視化する取り組みで、全国20万人を対象として2024年より開始し、今年で2回目だそうです。
今回の調査では、南海トラフ臨時情報の発令地域においては、防災意識の高まりが「非常用持ち出し袋の準備」や「避難経路の確認」といった自助行動を強く後押ししており、具体的なリスクが可視化されたときに、人々が素早く自己防衛に動く傾向を裏付けているようです。
一方で、「災害時に頼れるご近所づきあい」ができていると答えた人は相対的に伸び悩んでおり、地域の共助体制には依然として課題が残っています。
共助は効果が見えにくく、日常生活では優先順位が下がりがちなようです。
そして、時間的・心理的な負担が大きく、人間関係への気遣いも伴うため、忙しい都市生活のなかでは後回しにされやすい構造があると考えられるとのことです。
そのような中で、「災害時に頼ることができるご近所づきあい」の準備状況については、2025年都道府県別ランキングで第1位の宮城県であっても31.5%に留まっています。
昨年と比較した伸長ランキングを見ると、高知県、宮崎県、大分県といった南海トラフ臨時情報対象地域がトップ3を占めるも、共助への意識は自助に比べて低い傾向です。
高知県は、伸び率が4.5ポイントと全国でもっとも高くなっているが、26.1%とけして上位ではありません。
私たちも、「コミュニティのつながりの強化」を呼びかけ、共助の備えを平時にどれだけ取り組んでおくか、そして、そのことが「災害時に『も』」助け合いの強みを発揮できると言ってきたが、まだまだであることの分かる調査結果となっていました。
| 6月25日「停戦合意を早期に確実に」 |
 イスラエル政府が6月13日、イラン国内の核関係施設など複数の施設に大規模な先制攻撃を行い、以降も続けられるイラン国内への攻撃に対して、イラン政府も反撃を行っており、中東情勢が緊迫していました。
イスラエル政府が6月13日、イラン国内の核関係施設など複数の施設に大規模な先制攻撃を行い、以降も続けられるイラン国内への攻撃に対して、イラン政府も反撃を行っており、中東情勢が緊迫していました。
そのような中、県議会では、共産党会派と県民の会で「イスラエルによるイランへの大規模先制攻撃を避難する決議(案)」を提出していましたが、その後、米国がイスラエルに同調する形で、イランの核施設空爆に踏み切る中で、中東の事態はさらに深刻な局面を迎えていました。
昨日の総務委員会での決議の扱いを巡り、各会派で一致して「イスラエルのイラン攻撃に端を発する大規模軍事衝突の早期収束を求める特別決議(案)」を採択することとしました。
しかし、昨日早朝、イスラエルとイランの「停戦合意」が報じられることもあって、その扱いはさらに流動的な局面を迎えることもあります。
今朝の段階でも、その「停戦合意」が確かなものであるとの確信が得られる情勢ではなく、注視しながら27日の閉会日を迎えることとなります。
| イスラエルのイラン攻撃に端を発する大規模軍事衝突の早期収束を求める特別決議(案) イスラエル政府は6月13日、イラン国内の核関係施設など複数の施設に大規模な攻撃を行い、以降もイラン国内への攻撃を続けている。イラン国内では、女性、子供を含む400人以上が犠牲となっており、さらなる民間人被害が強く懸念される。 イラン政府も反撃を行っており、中東地域における緊張の激化と軍事衝突の連鎖が深く憂慮される中、22日、アメリカ合衆国がイラン国内の核施設の空爆を実施し、事態はさらに深刻な局面を迎えている。 これら一連の攻撃は、いずれも人命を脅かし、地域の安全保障を著しく損なうものであり、看過しがたい国際秩序の破壊行為と言わぎるを得ない。とりわけ、核開発をめぐる緊張が続く中での軍事衝突のエスカレーションは、第三次世界大戦の引き金にもなりかねず、全人類にとって極めて重大な脅威である。 高知県議会は、イスラエルのイラン攻撃に端を発する大規模軍事衝突の拡大を強く非難するとともに、両国を含めた関係諸国に、事態の早期鎮静化に向けた最大限の努力を求める。 石破茂内閣総理大臣は、イランの核問題の平和的解決に向けた外交努力が継続している中でのイスラエルの軍事攻撃は許容できないと述べ、「極めて遺憾で今回の行動を日本として強く非難する。事態をエスカレートさせるいかなる行動も慎まなければならない」と表明している。 政府においては、この立場を堅持し、イスラエル政府に対し即時攻撃停止を強く呼びかけるとともに、イスラエル政府、イラン政府双方が自制し、国際連合憲章と国際法に基づいた事態の収束が図られるよう尽力することを訴える。 以上、決議する |
| 6月23日「沖縄慰霊の日に中東の戦火拡大を止める決意を」 |

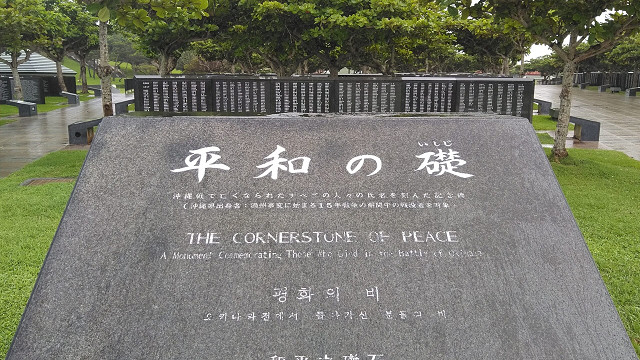
今日、沖縄戦80年の慰霊の日を迎えます。
米軍との戦闘の末、日本軍が壊滅状態となり組織的戦闘が終わったとされる日です。
沖縄県民は激戦地となった糸満市摩文仁をはじめ各地の慰霊碑に集まり、戦争犠牲者を悼み、平和への誓いを常に新たにしてきた日です。
しかも、今年は80年という節目の年でもあり、さらに沖縄戦を語り継ぎ、真の平和を築くための決意を国民全体で固めあう日でもあるように思います。
にもかかわらず、国際情勢は県民の願いとは逆の方向に進んでおり、2022年2月、ロシアとウクライナの激しい戦闘が始まり、23年10月にはハマスの奇襲に端を発したイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの激しいジェノサイドが続いてきました。
そして、こともあろうに慰霊の日前日の22日、イスラエルに続いて米国がイランの核施設を攻撃しました。
トランプ政権の許しがたい愚行に、怒りを禁じえません。
イスラエルが一方的にイランの核保有が間近だと主張して先制攻撃を加え、イスラエル単独では破壊できない地下施設などの攻撃に米国が協力した今回の攻撃は、自衛権の行使を例外に紛争の武力解決を禁じた国連憲章に反するもので、グテーレス国連事務総長が「国際の平和と安全に対する直接的な脅威だ」と批判したのは当然だと言えます。
トランプ氏は2週間以内に決めると声明を出した2日後に、だまし討ちのように攻撃し、しかも、同盟国である英仏独の外相がイラン外相と会談し、外交解決を模索していたさなかでもあり、その身勝手さは許されるものではないでしょう。
改めて、国内では、沖縄戦を含むアジア・太平洋戦争を推進した日本の方針、日本軍の行為を正当化、美化するような歴史認識に立ち、沖縄戦の実相を意図的に無視したり、ゆがめたりする政治家の発言が続いているような動きと歩調を合わせるように、「台湾有事」を名目とした自衛隊増強が沖縄で急激に進み、西日本各地の空港や港湾の基地化が進んでいます。
ロシアとウクライナの停戦、中東の戦火を拡大させないためにも声をあげ続けていくことを決意する6.23にしたいものです。
| 6月20日「共助の地域防災力の点検、下知地区減災連絡会総会」 |

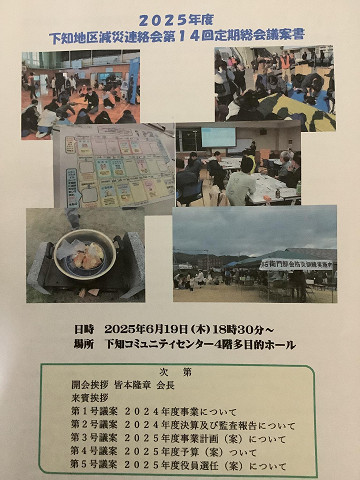 昨夜は、県議会終了後、2025年度下知地区減災連絡会第14回定期総会の会場に駆けつけ、すでに取り掛かって頂いていた会場設営に始まり、次々と参加いただいた代議員の皆さんとともに総会を開催しました。
昨夜は、県議会終了後、2025年度下知地区減災連絡会第14回定期総会の会場に駆けつけ、すでに取り掛かって頂いていた会場設営に始まり、次々と参加いただいた代議員の皆さんとともに総会を開催しました。
総会は、44人(委任7名)の出席者で、成立しました。
第1号議案2024年度事業報告、第2号議案2024年度決算及び監査報告について承認いただいた後、第3号議案2025年度事業計画(案)については、課題も盛りだくさんで出席代議員から「住宅の耐震化と家具固定の推進の取り組み」や、「事前復興について」の意見が出されました。
とりわけ、今年度後半には高知市の「地区別事前復興まちづくり計画素案」にもとづくワークショップも開催されることから、その検討のありかたなどについて、意見が出され、同席した高知市防災政策課事前復興担当係の皆さんにしっかり受け止めた準備を要請させていただきました。
2015年度から3か年かけて作成した「下知地区防災計画」の中の肝となっている「事前復興計画」の議論を改めて深堀しながらこれからのワークショップに生かしていくことになると思います。
さらには、「広域避難における広域避難所運営マニュアルの検討や仁淀川町での広域避難防災キャンプ交流」、「防災・避難訓練のとりくみ」「昭和小の防災教育との連携」「やえもん部会の活動活性化」「事業所の加入促進と事業所部会の発足」、「女性部会の活性化」「PWJとの連携」「デジタル防災」など多様な事業計画を承認いただきました。
昨年度末に発足した女性部会の取り組みも活性化したり、正式に加入いただいた事業所会員さんも出席頂くなど多様な構成で開催された総会でのご意見が、今後の下知地区減災連絡会の取り組みを前に進めていくことになればと思いました。
当日配布議案や資料もあり、直前までバタバタでしたが、皆さんのご協力で何とか総会で新たな事業計画に取り組んでいくことを決定頂きましたが、これからも災害に「も」強いまち下知を目指して平時から顔の見える関係で協力しあっていきたいものです。
| 6月19日「精神障がいのある方への医療費助成でさらに当事者の声を聞いて」 |
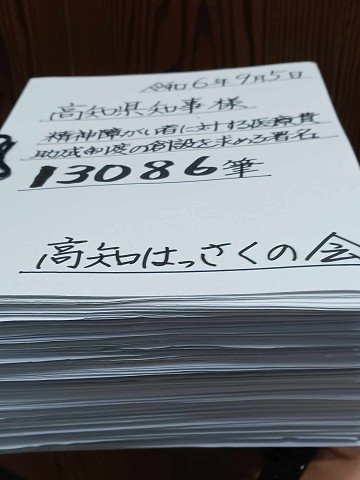

昨日から、県議会6月定例会の代表質問が始まりました。
「県民の会」を代表して岡田竜平県議が森林林業政策を中心に質問されましたが、中でも会派として昨年来取り組み続けている精神障がい者への医療助成について、現状の検討状況の課題などについて質しました。
これまでの関係者会議をともに傍聴し続けてきた岡田議員は、その中で精神障がいのある方本人や家族など当事者の声が反映されにくい構成について質問し、県としては「本制度の検討にあたり、当事者の声をお聞きすることが重要と考えており、これまでも会議の場以外でもご家族の皆様のご意見を伺ってきた。また第3回関係者会議では、委員から精神障がいのある本人にも意見を聞いてほしいとのご発言があり、こうしたことを受け止めて改めて本人やご家族の方のご意見をお聞きする場を設けたいと考えている。」との答弁を引き出しました。
また、精神障がい者への医療助成について、本来求められている支援に向けた議論が進められていない可能性について所見を聞かれた執行部は、「関係者会議については当事者の声をお聞きし、他県の実施状況や市町村の意向調査を踏まえ、現行の医療費助成制度に精神障害のある方を加えることを目的に設置している。」ことを述べた上で、「関係者会議において議論を積み重ねている中で、一部の委員から現行の医療費助成制度とは別に新たな制度を創設してはどうかとのご意見を頂いている。この点についても専門家を含めた皆様のご意見を聞き、その上でどのように制度設計していくのか検討していく必要はあると考えている。また実施主体は市町村であるので改めて市町村の意向もお聞きし検討を進めていく。」と答弁されました。
昨年、9月に当事者や関係者から県に提出された1万3086筆の「精神障がい者に対する医療費助成制度の創設を求める署名」について、知事は、昨日改めて「精神障害者は就労が不安定で、経済的にも厳しい環境にあると認識しており、署名は大変重く受け止めている」と答弁しているだけに、重く受け止めていることに答えるような制度設計の検討を注視していきたいものです。
| 6月17日「マンション防災でのトイレ問題」 |

 今夜は、マンション防災会の総会に向けた役員会を開催することとなっています。
今夜は、マンション防災会の総会に向けた役員会を開催することとなっています。
私たちのマンション防災会は、結成して20年目を迎えますが、昨年来、2017年に作成した「南海トラフ地震対策・津波避難防災マニュアル」の改定検討をする中で、「災害時のトイレ使用マニュアル」、コロナだけでなく「感染症対策」と「在宅避難」の視点と最新の情報などを取り入れる必要性を確認してきました、
しかし、マンションの場合、これまでの学習会の中から、地震後の排水管機能の確認が課題になり、トイレの問題をはじめとした排水の問題に大きな影響を及ぼすこととその対応について、どこまでマニュアルで言及するのかについて懸案課題となりました。
マニュアルに書き込むだけでは、啓発の域を出ず、協議した結果、規約改定などを踏まえ、一定の規制に根拠を持たせることとしました。
その後、マンション防災計画策定の際に助言頂いたMALCA(一般社団法人マンション防災協会)のご指導を仰ぎ、管理組合に規約及び使用細則の改定を求め、総会では3/4以上の賛成を必要とする特別決議で管理規約と使用細則を改定して頂きました。
災害関連死を防ぐために必要とされる「TKB48」とは、避難所・避難生活学会が提唱する防災コンセプトで、災害発生から48時間以内に、被災地へ「T:トイレ」「K:キッチン」「B:ベッド」を迅速に届け、被災者の尊厳と生活の質を守ることを目的とした取組が能登半島地震以来加速化それています。
その意味でも、今回規約改正まで行った被災時のトイレを始めとした排水問題の規制をそれぞれが自分事として意識し、備えの動機づけと促進を図るため、非常用トイレセットを20周年記念事業の一環として全世帯に配布することを今夜提案することとしました。
今までも、自助の取組として提案してきましたが、ご高齢の方の中には、どこで買えばいいのか分からないとのことで備えられていない方もいたりします。
今夜の議論でも、いろいろと皆さんからマンション防災力の向上に向けていろいろとアイデアを出して頂けたらと思っています。
| 6月15日「『35年目のラブレター』と、なくてはならない夜間中学」 |
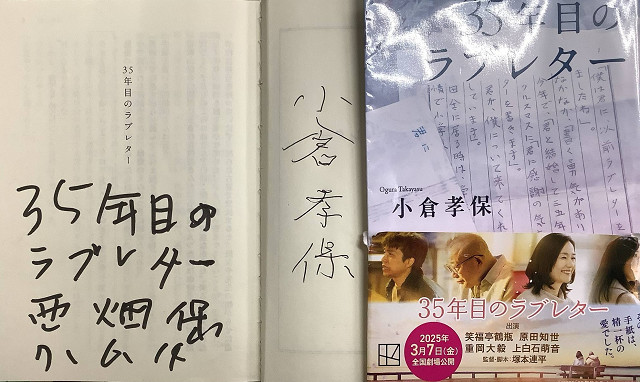
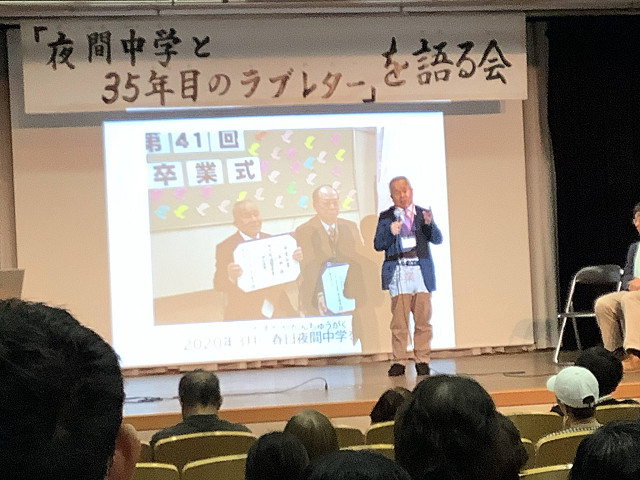

昨日午後、自由民権記念館で「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」の主催で「夜間中学と35年目のラブレターを語る会」が開催され、参加してきました。
会では、最初に、高知国際中学校夜間学級に在籍の2人の高齢女性が登壇し、夜間学級に入学したきっかけや学ぶことの楽しさ、先生方が丁寧に教えてくれるこの夜間学級に必要とされる方の多くの方に入学して欲しいことを訴えられました。
そして、その後には映画「35年目のラブレター」で笑福亭鶴瓶さんが演じた主人公のモデルとなった西畑保さん、原作本の作者である小倉孝保さん、そして奈良市立春日中学校夜間学級元教頭の深澤義隆先生が登壇されました。
映画を鑑賞し、原作を読んでからお話を聞かせて頂きましたので、西畑さんのお話が余計に浸み込んできました。
学校へ行けなかった背景にある貧困と差別の問題。学校で学べなかったことによる字が書けないことで受けた社会や職場でのいやがらせや困難性。
それでも一生を過ごす連れ合いさんの皎子さんと幸せな生活を送りますが、字を書けないことを知られることを常に恐れていたが、知られてもなお深まるお互いの愛情などにも学ばせて頂きました。
定年で退職してから、改めて夜間中学に入学し、改めて文字を覚えて皎子さんにラブレターを書かれました。
そんな西畑さんが学んだ春日中学校夜間学級元教頭の深澤先生は、「夜間中はあってはならないけどなくてはならない学校です」と言い、西畑さんの生き方を本にされた小原さんは「効率化という考え方を持ち込んだら行けないのが教育と福祉。中でも、夜間中学は、費用対効果でいうと最も効率が悪いかもしれない。しかし、人間の心の豊かさをつくっている夜間中学こそ大事である。」と言われ、会場の皆さんが納得されていました。
西原さんと出会われた方の多くが、西原さんから学ばされると言われますが、お話を聞かせて頂き、その通りだなと思ったところですが、これも小原さんが言われていましたが「学びは遅くなっても夜間中学で学ぶことで、分厚い人間になる」そんな学びの場として、全国の夜間中学・夜間学級で学び続けられる方がいることを応援していきたいものです。
西畑さんが学んだ奈良県には、公立夜間中が3校、自主夜間中学が3校あり、さらに自主夜間中学が1校開校予定ということを聞くにつけ、1校に止まる本県でさらに、夜間中学で学べる県下の環境を整備しなければと思わされたところです。
貴重なひと時でした。
| 6月14日「6月定例会知事提案説明への懸念」 |

 県議会6月定例会が昨日13日開会しました。
県議会6月定例会が昨日13日開会しました。
浜田知事は所信表明で、人口減少対策について「若者が活躍でき、魅力ある高知県の実現にはオール高知で取り組みを進めていくことが不可欠だ」と強調し、9月をめどに「若者応援産学官フォーラム」を設け、県内就職の促進や魅力ある仕事の創出を目指す考えを示しました。
本県の推計人口は4月1日時点で65万人を割り込み、2024年の出生数は過去最少の3108人で、若年層を中心とした転出超過も続いており、24年度から始めた人口減対策の「県元気な未来創造戦略」も、「大変厳しい船出になったが、婚姻数は増加に転じるなど明るい兆しも見え始めている」と説明しました。
また、昨年度来注視してきた人口減に適応して公共サービスを見直す「4Sプロジェクト」の一つである消防の広域化について、次のように言及されました。
「消防の広域化については、有識者や県内全ての市町村長、消防本部の消防長による検討会を4月に初めて開催し、県の試案として示した基本構想を基に議論を開始した。その中では、「広域化による財政負担や組織体制の変化に関する定量的なシミュレーションの結果を早期に提示すべき」、「地元出身の職員を優先的に配置できる仕組みを設けるべき」といった様々なご意見を頂いた。先月からは総務、財務、消防業務、通信・システムの4つの専門部会を設けてテーマごとの議論も始めており、こうした意見も踏まえて具体的な検討作業を加速した上で、引き続き、市町村や消防本部と丁寧に協議を進める。今回の消防広域化は、管理部門の整理統合で生じる余力を現場力の強化に振り向けること、そして消防職員を志す若者たちに選ばれる、魅力のある職場づくりを通じて人材確保を図ることを旨とするものである。今後、こうした広域化の基本的な姿について市町村のコンセンサスを得た上で、新たな「基本計画」をとりまとめ、年度内を目途に、各市町村議会及び県議会における議決を得て法定協議会を設置し、次のステップに進むことを目指す。」
2月定例会でも、私の方から「広域化は移行案のスケジュールありきなのか、変更もあるのか」と質した際に「全ての市町村と消防本部の理解やコンセンサスなしには、この消防広域化を進めていくことはできない、そういう性格のものだと考えている。従って、今後、具体的に広域化の作業を進めていく中では、各プロセスの進捗状況を踏まえて、節目節目で次なる目標の時期は具体的にどこに置くかということを設定して、取り組んでいく。そうした性格のものだと考えている。その中で、関係者の理解を得られるように、必要な調査、分析を行い、十分な意思疎通を図りながら、丁寧に進めていきたいと考えている。」とのことでした。
今後も、スケジュールありきでなく、丁寧で慎重な検討を求めていきたいと思います。
補正予算案では、物価高騰対策として、LPガスの9月分の料金を値引く2億3200万円、地域医療体制を充実させるため周産期医療や小児科など少子化の影響を受けている医療機関への支援費用などにおよそ5億800万円を。高校の授業料無償化に向けて家庭の収入要件を撤廃し授業料相当額を支援する費用などにおよそ3億5000万円を充てています。
さらに「とさでん交通」についてコロナ禍で増えた債務12億円の解消に向けた返済の支援費として、およそ8億円など全体で25年度一般会計補正予算案24億1700万円が計上されています。
他にも、条例改正議案など16議案が提出され、27日までの15日間の会期となっていますが、今回は私は質問できませんので、他の議員の質問や常任委員会での質疑を注視させて頂きます。
それにしても、米軍戦闘機が高知龍馬空港に長期にわたって駐機し県民に不安や懸念を与えながらも、十分な情報提供ができなかったことや、令和の米騒動の背景や米価の高騰対策についても県民に何らの説明がなかったことは、残念でした。
| 6月13日「日本の学術の『終わりの始まり』」としてはならない」 |

 菅政権下で、任命拒否問題が発端となった日本学術会議を特殊法人化する法律が成立してしまいました。
菅政権下で、任命拒否問題が発端となった日本学術会議を特殊法人化する法律が成立してしまいました。
政治の干渉は学問の多様な視点を損ない、健全な発展を妨げ、国力に直結する研究力にも悪影響を与えかねないと思われますが、そうした動きに対する防波堤となる存在が学術会議だったと言われています。
新法の下で、政権による学術に対する実際の介入をいかに許さないかが問われるだけに、今後の政府の具体的な人選や新しい学術会議のあり方を注視し続けなければなりません。
新法では、業務監査する「監事」や意見を述べる「評価委員会」は首相の任命であり、会員候補の「選定助言委員会」も新設されるなど、学術会議への有形無形の圧力が危惧されます。
坂井学・内閣府特命担当相は国会で「特定の人を排除してきた懸念」を指摘する一方で、学術会議の会員解任規定について「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員は解任できる」と答弁するなど右派であれ左派であれ、特定の意見の排除がされるとすれば、極めて危険だと言わざるをえません。
また、学術会議は軍事研究に厳しい姿勢を示してきたし、政府から依頼を受けて「高レベル放射性廃棄物の処分」を審議したときには、現政策の抜本的な見直しも迫った経過があります。
学者が政府の言いなりとなって戦争に加担した反省から戦後、学術会議が設立され、独立を重視し、学術会議法の前文には「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し」とうたわれていたが、新法では、この前文はなくなっています。
新組織が政府の顔色をうかがい、政策への「お墨付き」に利用されるようになれば、存在意義に疑問符が付き、国際的な評価も落ちてしまうことになってしまいます。
このままでは、今後、学問の自由は守られるのかが懸念される中で、私たち一人ひとりが関心を持ち、声をあげ続けなければ、瓦解しかねません。
この改組を梶田隆章・前学術会議会長が言うように「日本の学術の『終わりの始まり』」にしてはならないのです。
| 6月12日「相変わらずのジェンダー平等後進国」 |
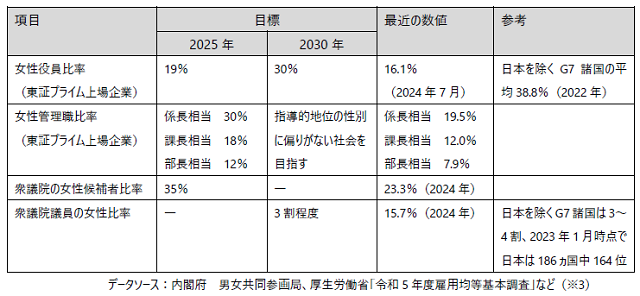 世界経済フォーラム(WEF)が、世界の男女格差の状況をまとめた2025年版の「ジェンダーギャップ報告書」を発表しましたが、日本は調査対象148カ国のうち、前年と同じ118位で、主要7カ国(G7)で最下位でした。
世界経済フォーラム(WEF)が、世界の男女格差の状況をまとめた2025年版の「ジェンダーギャップ報告書」を発表しましたが、日本は調査対象148カ国のうち、前年と同じ118位で、主要7カ国(G7)で最下位でした。
報告書は教育・健康・政治・経済の4分野で「男女平等」の度合いを分析したものですが、男女が完全に平等な状態を100%とした場合、日本の達成率は前年から0.3ポイント改善して66.6%だった。教育と健康ではほぼ平等を達成しているが、政治と経済の分野で後れをとり、前年同様の118位に止まったものです。
政治分野の達成率は8.5%(前年は11.8%)に低下しているが、一方、企業での管理職・役員への女性登用の状況などを反映した経済分野の達成率は61.3%(同56.8%)と改善したものの、他国と比べて後れをとつています。
日本政府が、国連の「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム」で発表する予定のSDGs(持続可能な開発目標)の進捗に関する「自発的国家レビュー」報告書を公開していますが、2021年の前回報告から4年、国内におけるSDGsの一層の浸透を評価したものの、長年の課題であるジェンダー平等の遅れを明確に認めています。
2009年から16回連続トップの「ジェンダー平等最先進国」アイスランドのトーマスドッティル大統領は日本について、「私が歴史から学んだところでは、日本は何かを本気で考え、『質』を重んじて取り組めば、成功する国です。ジェンダー平等について本気で考えられるなら、日本の未来は非常に明るいものになるのではないでしょうか」と指摘されています。
しかし、この国は、この問題を本気で考えようとしない政治家たちによって政権を握られて久しいことからも展望が見えていないのかもしれません。
| 6月11日「映画『35年目のラブレター』の主人公と語る会」 |

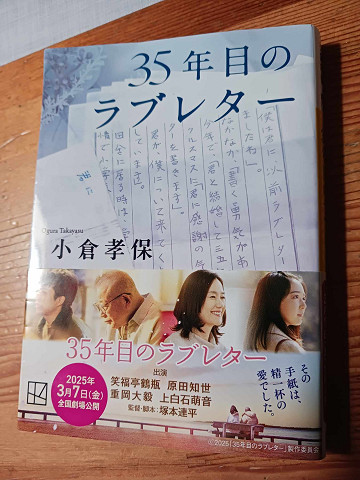 映画「35年目のラブレター」を鑑賞した時、改めて夜間中学の必要性と高知にも学び直しの場と機会があることを知って頂ければと思ったことでした。
映画「35年目のラブレター」を鑑賞した時、改めて夜間中学の必要性と高知にも学び直しの場と機会があることを知って頂ければと思ったことでした。
そして、県立高知国際中学校夜間学級の卒業式と入学式に出席し、多様な思いを実現するために頑張ってきた卒業生、これから頑張ろうとする入学生の決意を聞かせて頂きました。
そんな中で、「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」が主催する映画「35年目のラブレター」のモデルとなった西畑さんを招いて夜間中学について語る集いが14日(土)13時30分から自由民権記念館で開催されます。
原作の文庫本を読んでいるところだが、映画では描き切れなかった「学ぶ」ことと「人権」について、ご本人から聞かせて頂くことを期待しています。
14日は西畑さんのほか、県立高知国際中学校夜間学級に通う女性2人も参加されます。
定員100人、運営協力費1千円ですが、ぜひご参加ください。
問い合わせは「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」の世話人細川さんまで(090・7787・6962)。
| 6月8日「「平成30年西日本豪雨災害の教訓をを絵本で伝える」 |
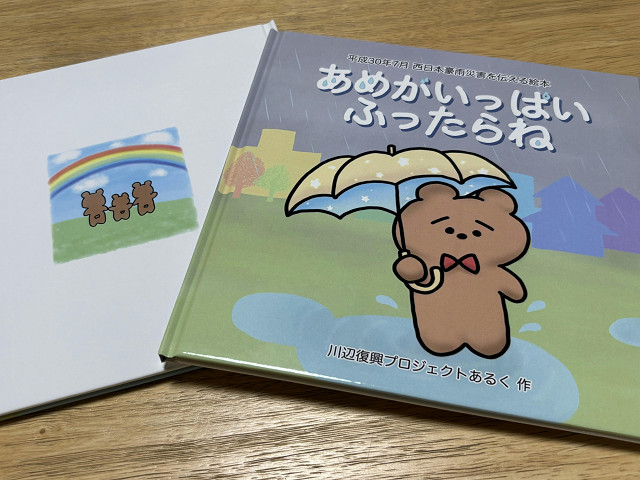

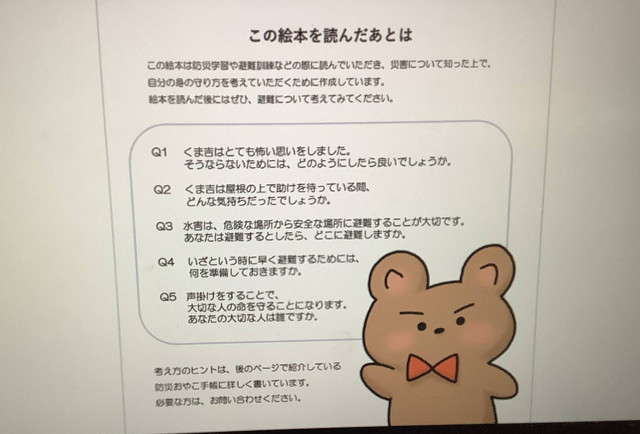
下知地区が、以前から防災交流のあった西日本豪雨災害で大きな被害を受けた倉敷市真備地区の皆さんに学ばせて頂いたのは2年前でした。
その「川辺復興プロジェクトあるく」の皆さんが「平成30年西日本豪雨災害を伝える絵本 あめがいっぱいふったらね」を作成中で、クラウドファンディングをされています。
あの「痛い体験」を、自分たちの言葉で分かりやすくイメージしやすく、伝えていくことが、「子どもたちの未来」につながると考えられた取組です。
絵本ができたので、読み聞かせの会が6日(金)20時から、ZOOMで開催されるというので、参加させて頂きました。
絵本誕生秘話・絵本の読み聞かせ・絵本の活用方法例のご紹介などが槙原さんを中心に関わられた皆さんからもいろいろとコメント頂きました。
しっかりと絵本をつくる目的、そして描き方や、その絵本をどう活用するか、さらに絵本の内容が子どもさんたちにどのように定着するかまで考えて作られていることに驚かされました。
この絵本を手に取った親御さんや保育士さんが子どもさんたちに読み聞かせた後、しっかりと話し合われている姿が瞼に浮かんできます。
槙原さんたちの思いであるこの絵本が全国にひろがっていくためにも、ぜひクラファンを達成させたいものです。
リターンで、この絵本を手にすることもできます。
皆さんのご協力をお願いします。
| 6月7日「許せない東電旧経営陣の賠償取り消し」 |
 2011年3月の東電福島第1原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠り東京電力に巨額の損失が生じたとして、株主が旧経営陣ら5人に23兆円超を東京電力に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁でありました。
2011年3月の東電福島第1原発事故を巡り、旧経営陣が津波対策を怠り東京電力に巨額の損失が生じたとして、株主が旧経営陣ら5人に23兆円超を東京電力に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁でありました。
訴訟は、旧経営陣らが巨大津波を予見し得たか、対策によって事故を回避できたかが争点で、東電内部では2008年、最大15.7メートルの津波が来ると試算しており、その根拠となった政府の地震調査研究推進本部の「長期評価」(2002年公表)の科学的な信頼性が争われました。
高裁の木納敏和裁判長は、津波試算の根拠になった長期評価について「地震学のトップレベルの研究者による議論に基づき、尊重するべきものだった」と認めたが、実際に自治体の防災対策に取り入れられていなかったことなどから、事故責任を問うための予見可能性の根拠にはならないとして、株主側の請求を棄却しました。
判決理由の最後で、木納裁判長は原発事業者に対して「いかなる要因に対しても過酷事故の発生を防ぐ措置を怠ってはならない」と述べ、「原子力発電事業のあり方について、広く議論することが求められる」と述べたというが。そこまで言及するなら、なぜこうした判決となるのか、理解に苦しみます。
まさに、これでは原発の安全を守れないと捉えざるを得ない判決であり、「次の原発事故を招く判決」であると原告団は怒り、上告するのは当然です。
折しも同日、この国は、自公政権が、2023年5月末に強行成立させた「GX脱炭素電源法」が全面施行し、原発依存を加速しようとしています。
このように、自公政権は「原発依存社会」に暴走していますが、彼らが何を求めようとも、政治的思惑あるいは経済的利益で、原発の老朽化を防ぐ技術、安全性を高める技術、使用済み核燃料の処理・処分技術が急に向上することはありません。
彼らが暴走すればするほど、原発過酷事故の確率は拡大することを踏まえて、反対の意思表示を明確にしていく必要のある6月6日となりました。
| 6月6日「アベノマスク情報公開訴訟」 |
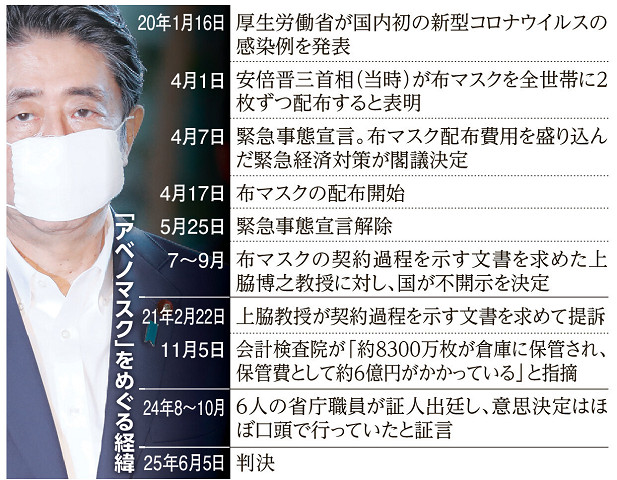
 コロナ禍初期には、アベノマスクという文字が連日新聞紙上に踊っていたが、久々に新聞紙上で目にすることとなったのはアベノマスク判決が今朝の新聞紙上で報道されていたためです。
コロナ禍初期には、アベノマスクという文字が連日新聞紙上に踊っていたが、久々に新聞紙上で目にすることとなったのはアベノマスク判決が今朝の新聞紙上で報道されていたためです。
新型コロナ対策で当時の安倍首相が2020年に各戸配布を主導した通称「アベノマスク」について、上脇博之神戸学院大教授が業者との契約過程を示す文書の開示を国に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は5日、「やりとりはほぼ口頭だったため、原告が求めるような文書はない」という国側の主張を一蹴しました。
判決は、国の対応について「不開示の判断を維持するために、限定的な解釈を事後的に考え出して主張した」と批判し、国が言う「保存期間1年未満の文書」でも公文書に変わりはないのに、最初から「1年未満」を理由にして対象から外していたとも指摘し、賠償まで認めました。
「初めから不開示という結論があったからこそ、国はうそにうそを重ねる弁明に終始した。裁判所がそこを見抜いてくれた」と、公文書を扱う姿勢を厳しく批判した判決を、原告側は「市民感覚」に沿うと高く評価しています。
判決が確定すれば、国は開示するかどうかを改めて判断することになりますが、上脇教授は「国民への説明責任」という情報公開法の趣旨を踏まえ、「政権の都合ではなく、国民の知る権利に応える。この原点を忘れないでほしい」と述べられています。
普通に考えて、400億円、3億枚の契約は、業者ごとに内容も異なるだろうに、口頭だけのやりとりで行った杜撰極まりない契約など通用するはずがありません。
この情報公開によって、その背景にあった当時のアベ政治の本質も明らかにして頂きたいと思います。
| 6月5日「不当解雇・空の安全と闘うJAL闘争団」 |


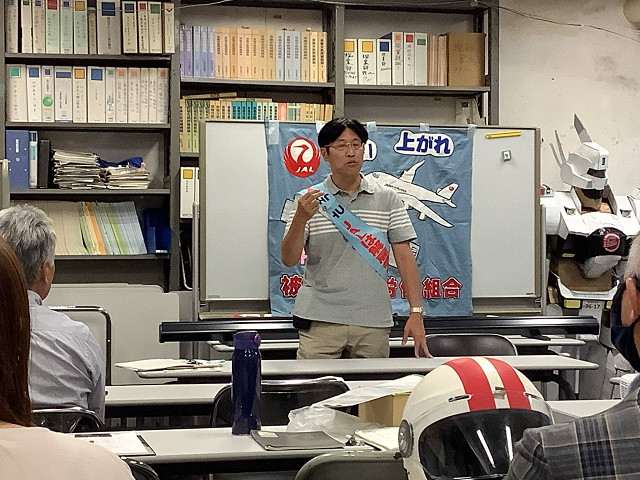
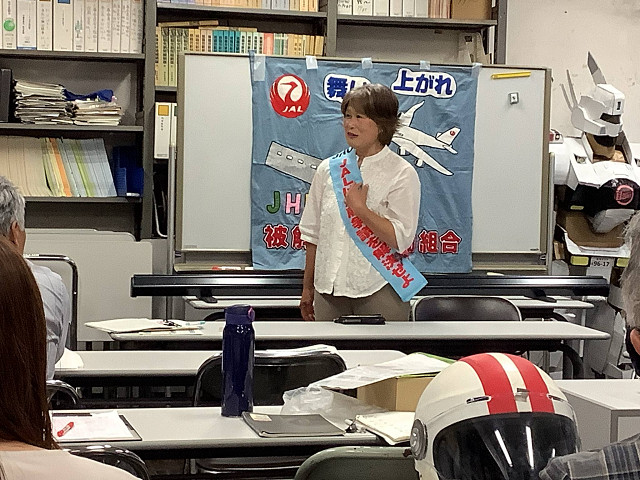

昨日は、JAL解雇撤回・最賃1500円実現四国キャラバン高知行動が行われ、闘争団メンバーとともに、ひろめ市場での街頭宣伝や高知労働局での交渉が行われました。
私は、昼の行動には参加できませんでしたが、夜の集約集会に参加し、闘争団からの報告で改めてJAL解雇撤回闘争の現状について学ばせて頂きました。
2010年1月、JALは政府の方針で破綻と再建が進められ、再建の過程で「更生計画」の人員削減目標を大幅に達成し、営業利益も12月時点で目標の2.5倍となる1,586億円を上げたにもかかわらず、大晦日にパイロット81名と客室乗務員84名を年齢と病欠歴を基準に整理解雇しました。
165名の解雇は、利益を最優先するために、モノ言う労働者の排除と労働組合の弱体化を狙ったもので、安全に逆行するものであったことは、明らかです。
JALは経営再建後、パイロット約700人以上、客室乗務員7,500人以上を新規に採用し、今後は、外国人パイロットを70人以上採用しようとしているのに、解雇した乗務員を一人も原職復帰させていません。
人員削減した企業は経営状況が回復し、再び人員を採用する場合には、解雇された人を優先的に雇用することが国際労働基準であり、世界の常識であるにもかかわらず、日本政府も認めたこの国際労働基準について、JALは「国内法に定められていない」と開き直り、政府もこれを放置しています
JALでは、安全上のトラブルが相次いで起こっていますが、空の安全輸送には「知識」「技術」「経験」「チームワーク」が重要な要素であり、これは過去の連続事故の教訓です。
しかし、これまでJALが行ってきた職場の“要”である“モノ言う労働者”の解雇は「空の安全」に逆行するものと言えます。
集会の場で、現役パイロットの和波さんも、解雇撤回の闘いとともに、民間機・空港の軍事利用にも反対の声を上げ、とりわけ九州や沖縄・南西諸島の空港では軍民共用化が進められ「空の安全」が脅かされていることにも反対し、JAL争議は「労働者の権利」はもちろん「空の安全」「平和」を守る闘いであることの決意も述べられました。
争議の解決は、“安全運航の確立”、失われた利用者からの信頼回復にも繋がる闘いとして、15年目を闘っています。
昨年12月に斡旋は打ち切りとなり、9月ごろに予定される命令に向けて、闘いのさらなる広がりを勝ち取るためのキャラバン行動と言えます。
ひろめ市場でチラシを受け取って下さった市民の皆さんと、語り合った争議団の皆さんの連帯の輪の広がりが、闘争勝利の後押しになることと思います。
| 6月4日「私たち抜きに、私たちのことを決めないで」 |
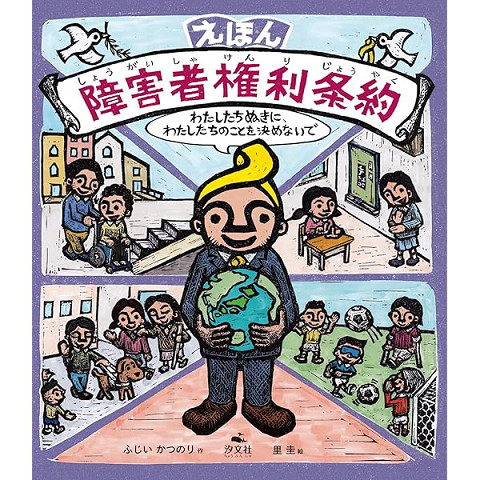 昨年来、精神障害者当事者・家族会「はっさくの会」の皆さんとともに、「精神障害者のための医療費助成制度創設」に向け、連携した取組をし、議会質問でも取りあげ、「医療費助成事業に係る関係者会議」も傍聴してきました。
昨年来、精神障害者当事者・家族会「はっさくの会」の皆さんとともに、「精神障害者のための医療費助成制度創設」に向け、連携した取組をし、議会質問でも取りあげ、「医療費助成事業に係る関係者会議」も傍聴してきました。
これまでの「助成対象とする範囲」に加えて6月2日の第3回検討会では「助成対象とする障害の程度」について、精神障碍者保健福祉手帳の等級に基づいた検討がされました。
しかし、身体、知的障害の等級との比較や助成対象となる医療費の試算などをもとに、検討がされると三障害での均衡や財源論が立ちはだかってしまうことに、当事者・家族の理解と納得は得られないのではないかと思われます。
当事者団体の代表として参加する委員から「精神障害者のための医療費助成制度創設に向けた意見」が文書で提出され、その中でも、最後に言及された部分を他の委員さんにもしっかり受け止めて次回以降の検討を進めて頂きたいと思います。
「単に財政負担を云うだけでは説得力を持ち得ません。しかも、財政負担規模のみで政策立案の当否が判断されるべきでもありません。また、本委員会は、行政関係者、専門機関、有議者でほとんどを占められており、当事者・家族代表委員は1名のみです。障害者権利条約では、『私たち抜きに、私たちのことを決めないで(Nothing
abOut us,withOut usl)』が基本的な政策立案姿勢とされていますが、このような当事者尋家族の声が反映されにくい委員会構成で、精神障害当事者・家族の生活に直結する重要な政策立案がおこなわれてよいのでしようか。」という訴えに、今こそ他の委員さんが耳と心を傾けて頂きたいと思いました。
| 6月2日「県総合防災訓練で防災関係者の顔の見える関係作り」 |
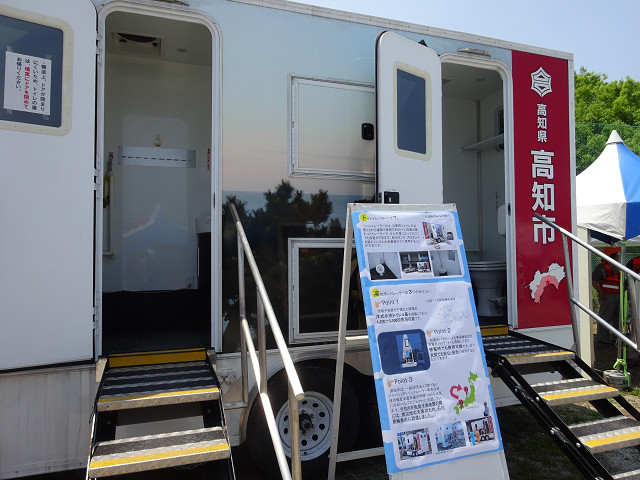




昨日は、令和7年度高知県総合防災訓練に参加してきました。
訓練会場の高須浄化センターのグランドでは、地域防災フェスティバルも開催されており、多くの県民の皆さんが様々な展示ブースで防災について学んでおられました。
地域防災フェスティバルに展示されていた本県では配備がされていないモバイルファーマシー(移動薬局)などは愛媛県から来て頂いてましたが、本県でも急ぎ配備される必要があることを痛感させられました。
これは、日常的には、中山間地や薬局過疎地での活動にも役立つのではないでしょうか。
トイレトレーラーにも多くの皆さんが関心を示されており、本年度から高知市以外に高知県での5台、市町村には10台などが配備され、全国のネットワークで活用されることが期待されています。
トイレに関する様々な展示ブースがあり、能登半島地震でのトイレの大事さについて関心が高まっていることも特徴ではなかったかと思います。
また、滅灯した信号機を電気自動車を使って復旧させる訓練も目新しく感じました。
いずれにしても、様々な支援協定団体等が協働して活動することを通じて、顔の見える関係づくりの場になっているのも大事なことではないかなと思いました。
| 6月1日「マンション再生は日頃のコミュニケーション」 |
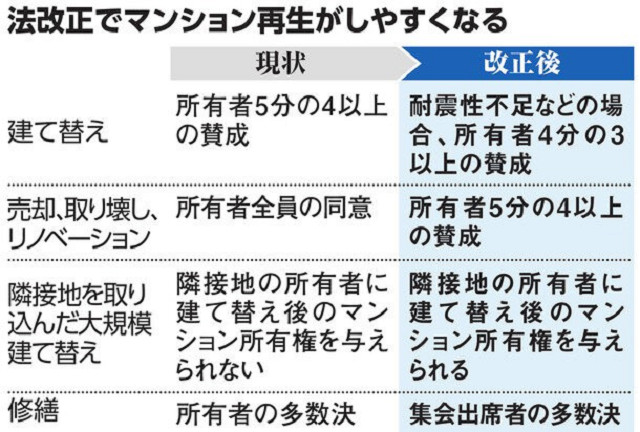 5月23日に、老朽化が進むマンションの再生を促すための改正法が、参議院本会議で可決、成立しました。
5月23日に、老朽化が進むマンションの再生を促すための改正法が、参議院本会議で可決、成立しました。
手続きに必要な住民の決議に関する要件を緩和し、建て替えや売却を促進するための法改正が、来年4月から施行されます。
現在は、マンションの建て替えには「区分所有権」を持つ所有者の5分の4以上の賛成が必要でしたか、改正により、耐震性の不足など一定の要件を満たす場合は、割合を4分の3に引き下げられ、建物・敷地を売却したり、取り壊したりする時は原則全員の同意が必要だったが、5分の4以上の賛成でできるようになります。
そんな中で、昨夜の私の住むマンション管理組合の総会では、災害時に共有部分を緊急的に保全を図るために、自主防災会の議論で理事会から提案して頂いた規約改正で4分の3の賛成をえる議案を可決させるため、総会最中にも出席を求めるため、部屋のインターホンを鳴らし続けて下さる方がいました。
採決時点で、委任状や議決権行使も含めて4分の3に達して、可決しました。
そうやって可決に尽力して頂いた方に、「お手数かけました。ありがとうございました。」というと、その方は「せっかく坂本さんたち防災会の役員の皆さんが、考えてくれた災害時のための規約改正案だから、何とかとおしたかった。」と言ってくれました。
昨夜の総会が、終わったのが22時半、議論がいろいろありましたが、築後36年を経過したマンションは建物も老朽化するし、区分所有者も高齢化する中で、安心して住みやすくなるためには、年一回の総会や数回の理事会だけでなく、日頃のコミュニケーションの大切さを改めて考えさせられた総会になりました。
| 5月31日「『場所の支援』から『人の支援』へ災害対策基本法等一部改正」 |
 5月28日、参議院本会議で「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が可決され、改正災害対策基本法及び改正災害救助法が成立しました。
5月28日、参議院本会議で「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が可決され、改正災害対策基本法及び改正災害救助法が成立しました。
法改正の背景ともなった昨年1月1日に発生した能登半島地震は、直接死228名、災害関連死364名(5月時点)、全半壊住家約2万5千棟という甚大な被害をもたらし、昨年9月20日の大雨による奥能登豪雨では16名が犠牲となり、特に山間部では多数の土砂災害等により地震から復旧した住家が再び被災する複合災害につながりました。
そのような中、中央防災会議「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について」(令和6年11月)では、能登半島地震等の教訓を踏まえ、被災後でも人の生命と尊厳が守られるべきであるとし、「場所(避難所)の支援」から「人(避難者等)の支援」へ、考え方を転換するという理念が示されました。
そして、食料、トイレ、ベッド・入浴設備等の避難生活に必要な物資等の十分な備蓄や支援を行うこと、避難生活環境の確保及び、保健・医療・福祉の支援(救命医療から福祉サービスへのシームレスな連携等)が図られるべきであること、在宅避難者・車中泊避難者等も含めて支援すべきこと等が明確にされ、今回の法改正でこれらの提言の一部が取り込まれました。
さらに、これも念願だった災害救助法が定める「救助の種類」(災害救助法4条第1項)に「福祉サービスの提供」(同法4条第1項6号)が追加されました。
これは、1953年に、救助の種類に飲料水の供給、被災者の救出、住宅の応急修理、応急仮設住宅等が追加されて以来、実に72年ぶりとのことです。
私も、今年の1月知事への要望事項で、災害救助法第4条「救助の種類」に「福祉」を追記し、「医療・助産及び福祉」とすることで災害救助法等と福祉法制の連携が図られ、社会的脆弱性を抱える人びとを「福祉」の視点で支える災害救助の枠組みの構築を求めました。
知事も全国知事会とも連携し、災害救助法の救助活動の範囲を拡大して、福祉支援を明確に位置づけることなどを要望、提言してきたので、国の改正方向を見守りたいとの考えを示されていましたので、被災者と支援者の声と後押しで実現できたことを本当に嬉しく思います。
災害ケースマネジメントについも、県議会で令和2年9月定例会で初めて取りあげて以来、南海トラフ地震対策行動計画に途中で盛り込まれ、高知県地域防災計画にも明記されてきましたが、今回の法改正に伴う「福祉サービスの提供」によって、災害救助段階・初期段階から、中長期の復旧・復興・生活再建段階に至るまでの「災害ケースマネジメント」の充実化と両輪で実施されることが期待されます。
そして、何よりも災害前からの社会的弱者の見守りと災害ケースマネジメント型の被災者生活再建支援の連携を図ることができるなどフェーズフリーの「防災×福祉」の取組につながるよう実践していきたいものです。
| 5月29日「在日米軍駐留経費の負担増額求めるトランプ」 |

 米トランプ政権が5月上旬、日本政府に対して、在日米軍駐留経費をめぐる日本側負担を増額するように打診していたことが報じられています。
米トランプ政権が5月上旬、日本政府に対して、在日米軍駐留経費をめぐる日本側負担を増額するように打診していたことが報じられています。
これを受け、日本政府は駐留経費負担のうち、在日米軍の隊舎や家族住宅、管理棟、防災施設などを日本側が建設し、米軍に提供する「提供施設整備費」について数百億円規模を上積みする方向で検討に入ったとのことです。
具体的な対象施設は米軍側の要望を踏まえ、防衛省が決めるということです。
トランプ米大統領は1期目当時から、在日米軍駐留経費をめぐる日本側負担について「不公平だ」と不満を表明しており、さらなる増額を迫ってくる可能性も否定できず、日米交渉の行方は流動的だとされています。
しかし、在日米軍駐留経費の日本側負担は、特別協定による基地従業員の給与や光熱費、訓練経費に加え、予算措置による米軍施設整備と日米沖縄特別委員会(SACO)などの経費を加えてすでに年間8000億円を超えているとされています。
本来、地位協定は、「維持経費は米側負担」と定めているのだが、日本による経費負担は、1978年、円高ドル安の中で米軍関係者を支援する“思いやり”で始まっており、その背景にあった貨幣価値の差は今や逆転している中で、地位協定の“思いやり”という“特例”が50年近く継続しているのは異常ではないでしょうか。
許されることではないが、米側は地位協定3条で基地における特権的な排他的管理権を認められており、それが故に、施設維持経費は米側負担とされているにもかかわらず、その経費の大半は日本負担という例外が常態化しているのであれば、もともとの3条の特権的地位が見直されなければなりません。
現在の特別協定は来年度で終了しますので、アメリカが駐留経費負担の継続・増額を求めてくるなら、それを地位協定における米軍の特権的地位の見直しを議論するチャンスにすることもできるとの指摘もあります。
日米地位協定の改定を持論としてきた石破首相が今回の提案に唯々諾々と従うのならば、いよいよ今までの持論は何だったのかと責められるのは当然です。
| 5月27日「米不足・高騰の抜本対策を早期に」 |

 小泉進次郎新農相の「6月初旬にも店頭で税抜き5キロ2千円程度で並ぶことを目指す。」との歯切れ良い言葉に、一部国民は期待されているかもしれません。
小泉進次郎新農相の「6月初旬にも店頭で税抜き5キロ2千円程度で並ぶことを目指す。」との歯切れ良い言葉に、一部国民は期待されているかもしれません。
確かに、そうなったとしても、それで「令和の米騒動」は治まるのか。より根本的なコメ不足解消の道を早期に示してほしいと願う国民が多いのではないでしょうか。
そして、減反政策に翻弄され続け作りたくても作れない米、作っても生産者の収入は増えることなく農家が経営を継続でき、消費者が比較的安価な価格で買える仕組みや緊急時対策の備蓄の強化策がを求められているのではないでしょうか。
小泉農相が言うように、随意契約によって5キロ2千円のコメを放出しても、今回の放出量は国内需要の半月分程度に過ぎず、実際必要とする人に、どこまで行き渡るかは分かりません。
さらに、農相は「無制限で放出する」とも表明したが、放出を続ければ、本来の備蓄目的である災害や凶作などの緊急時に対応できない恐れも生じます。
政府が長く、減反などで生産量を抑えてきたことが今の米不足の背景にあるだろうし、トランプ関税に関連して、強要されるかもしれない米など農産物輸入拡大によって、国内農家の衰退を加速し、結局、消費者のためにもならないようなことも想定されるだけに、国内生産を促進し食料自給率の向上を図るなど、抜本的な農政改革を進めることこそが求められています。
| 5月26日「児童虐待予防へ「カンガルーの会」総会」 |
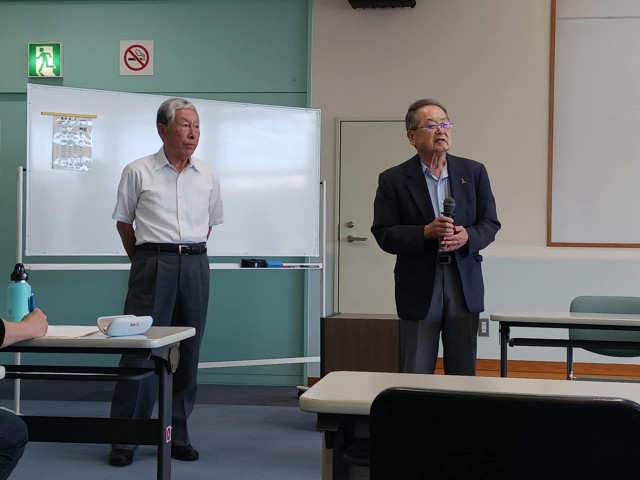 昨日の午後は、朝倉の福祉交流プラザで開催されたNPO「カンガルーの会」の総会に、出席してきました。
昨日の午後は、朝倉の福祉交流プラザで開催されたNPO「カンガルーの会」の総会に、出席してきました。
この会は、「児童虐待の予防、子育て支援を図るため、周産期から児童に関わる関係者に対して、研修会や講演会を開催する事業を行い、児童の健全育成を支援し公益の増進に寄与することを目的とする」もので、①児童虐待予防の為の研修会を実施する事業②妊婦、幼児期や児童に関わる関係者に対しての研修事業③一般の方に児童の健全育成、児童虐待予防を啓蒙啓発する事業④①~③を実施する為の指導者を養成する事業を行う会で、2009年6月20日に発足しました。
そして、16年間で499回の研修を開催し、保育士さん、保健師さん、助産師さん、看護師さんや行政職員、そして民生・児童委員さんや保護者など多様な皆さんが延べ13864名が受講されてきました。
そんな16年間の取組の先頭に立ってこられた小児科医師の澤田敬理事長や県職員時代に長らく児童福祉に関わられた中西稔副理事長、そして子育て支援・相談の専門機関でお母さんや子どもたちに寄り添われている谷本恭子理事が退任されて新たな体制でスタートされる総会となりました。
今日は、総会に出席された会員全てが、なぜカンガルーの会と関わってきたのかお話も聞かせて頂き、私も発足以来のメンバーですが、貴重なお話ばかりに多くのことを学ばせて頂きました。
澤田先生からは、児童虐待を予防するという「カンガルーの会」の取組が、全国にひろがりつつある中で、理事長を退任してからも、まだまだご活躍されることだと思います。
新たな理事メンバーも、児童虐待予防の実践者であり思いの強い方たちばかりですので、児童虐待予防に向けた今後の取組をさらに発展させて下さることだと思います。
| 5月24日「事前復興計画策定の後押しを」 |
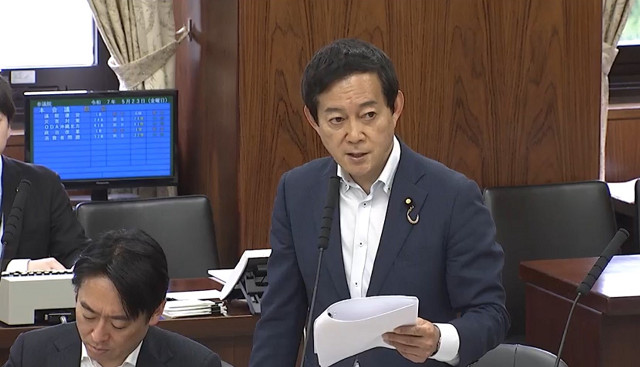 昨日は、広田一参議院議員が、参議院災害対策特別委員会で25分と言う短い時間ではありましたが、南海トラフ地震被害想定や住宅の耐震化促進、日常生活用具給付等事業、災害に強い道づくりなどの質問に加えて、事前復興の取り組みの強化について質疑されました。
昨日は、広田一参議院議員が、参議院災害対策特別委員会で25分と言う短い時間ではありましたが、南海トラフ地震被害想定や住宅の耐震化促進、日常生活用具給付等事業、災害に強い道づくりなどの質問に加えて、事前復興の取り組みの強化について質疑されました。
それぞれに重要な課題でしたが、高知県の沿岸自治体での取組に始まり、今年度から中山間地の自治体でも取り組み始める事前復興まちづくり計画の取り組み強化については、その必要性となかなか進まない取り組みについてのインセンティブを働かせるよう検討を求められました。
いまだ全国で策定されているのは33市町村という状況を政府は明らかにするとともに、国土交通省の取り組みを紹介するにとどまりました。
広田議員は、そのような状況を踏まえつつも、自治体に寄り添い支援するとともに、計画を作れば、財政上、税制上の優遇措置を図るとか、採択の優先順位を上げるとか、計画策定に向けたインセンティブが働くような検討を強く要請されました。
昨日の委員会での質疑を踏まえて、私たちも地域で防災力の強化、事前復興まちづくり計画の策定に向けて頑張っていきたいものです。
| 5月23日「孤立・孤独・困りごと解決へ」 |
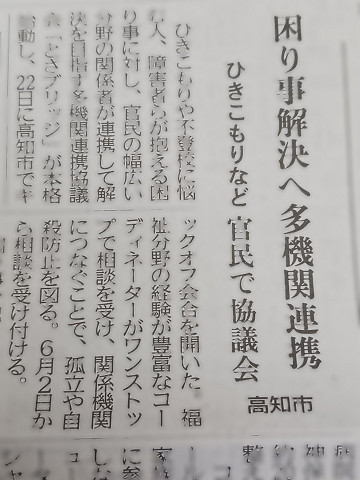
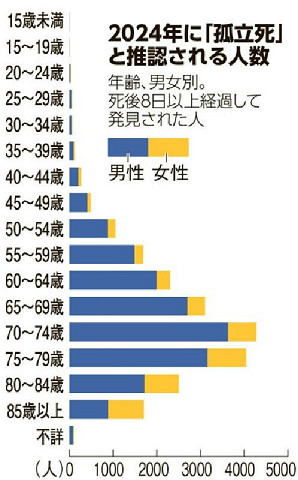 昨日、ひきこもりや不登校に悩む人、障害者らが抱える困り事に対し、幅広い分野の関係者が連携して解決を目指す多機関連携協議会「とさブリッジ」が本格始動したことが、報じられていました。
昨日、ひきこもりや不登校に悩む人、障害者らが抱える困り事に対し、幅広い分野の関係者が連携して解決を目指す多機関連携協議会「とさブリッジ」が本格始動したことが、報じられていました。
福祉分野の経験が豊富なコーディネーターがワンストップで相談を受け、関係機関につなぐことで、孤立や自殺防止を図り、困り事を抱える人の支援として、分野をまたぐ課題には対応していくこととしています。
内閣府は、2024年4月に施行された孤独・孤立対策推進法に基づく重点計画について、今夏までに改定する方針で、高齢者らの孤立死や、子どもの自殺の防止に向けた課題を充実させて、孤独・孤立対策に取り組む自治体の先行事例についても他の自治体の参考となるよう周知するとの考えです。
24年の小中高生の自殺者数は、前年比16人増の529人で、統計が残る1980年以降で最多となり、孤立死に関しては、社会的に孤立していたとみられる人が死後8日以上経過して発見されたケースを孤立死と位置付け、24年は2万1856人が孤立死したとの推計結果が公表されています。
また、孤独・孤立のリスクを抱える65歳以上の単身高齢世帯数も増加傾向となっており、政府の推計によると、全世帯に占める単身高齢世帯の割合は20年は13.2%だったが、50年には20.6%に増えると見込まれており、対策が必要となっています。
これらの背景をもとに、本県での課題解決の一環としての取組の一つであると思われますが、ぜひ実効性のある取り組みとなるよう期待します。
| 5月22日「特定利用港湾指定のメリット見えず」 |

 丁度一ヶ月前の4月22日付けのこの欄で、業務概要調査における港湾海岸課とのやりとりで、特定利用港湾の関連予算について、28億円のうちの「一部」というだけで、どれだけ県に回ってくるかも分からないし、明確に増額したとも言えない状況だったことを報告しました。
丁度一ヶ月前の4月22日付けのこの欄で、業務概要調査における港湾海岸課とのやりとりで、特定利用港湾の関連予算について、28億円のうちの「一部」というだけで、どれだけ県に回ってくるかも分からないし、明確に増額したとも言えない状況だったことを報告しました。
その後、出先機関調査で、特定利用港湾の高知新港・須崎港・宿毛湾港を所管する各土木事務所で、それぞれから特定利用港湾の指定を受けたことによる財源のあり方について聞いてみました。
しかし、それぞれからは「特定利用港湾指定における影響はないものと見られる。」「いろいろと調べてみたが、特定利用港湾になったからといって予算が加算されたわけでなく、通常ベースである。」「特定利用港湾の指定に合意したからと言って、特別な予算はついていない」などの返答ばかりでした。
指定に合意した際の「特定利用港湾 高知県版Q&A」のQ5に対して「「特定利用港湾」に指定されると、公共事業の採択などの判断に当たり、自衛隊・海上保安庁のニーズという安全保障上の観点からの重要性が加味され、岸壁・航路などの港湾施設の整備が加速されることが期待されます。」というものや、昨年12月定例会の県民の会橋本議員の質問に答えた知事答弁「防波堤の延伸工事、津波対策工事など民生利用及び自衛隊などの利用の双方にプラスとなる、そうしたインフラ整備の加速が期待できるというふうに考えている。」という見解は改めて何だったのかと言わざるをえません。
昨年、特定利用港湾の指定を受けた福岡市の博多港にても、「全て昨年度からの継続事業。自衛隊や海保の利用を念頭に置いたものではなく、国と市の負担割合もこれまでと変わらない。今回の指定について、福岡市は国から『予算配分で配慮する』と説明を受けたというが、『今のところ予算面で実感できるメリットはない。』」との市幹部のコメントが、報道されていたこともあります。
今回、出先機関等の調査で感じたの、結局は、指定を受けなかったら予算をつけないぞという脅しだったのかと思わざるをえません。
くわえて、今回の高知龍馬空港における米軍機の予防着陸に伴う長期駐機の法的根拠も明確でないのに居座り続けたことなどによる自治体の空港・港湾の基地化がこのように進められるのかと懸念される中で、今後の動きを注視していきたいと思います。
| 5月20日「江藤農水相では令和の米騒動は治まらぬ」 |

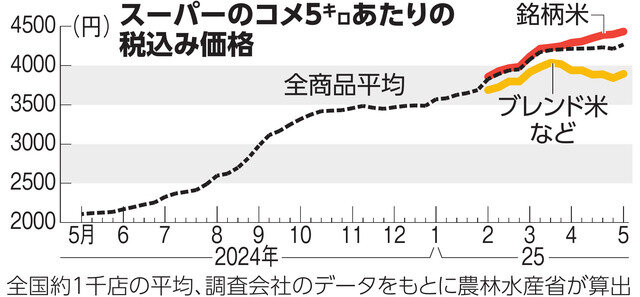
昨日から、マスコミ報道を騒がせているのは自民党江藤農水相が政治資金パーティーの講演で「コメを買ったことはありません。支援者がたくさんコメをくださるので、売るほどあります。大変なんですよ、もらうのも。」との発言です。
折しも、米の価格が前の週に昨年末以来18週ぶりに下がったものの、5~11日に全国のスーパー約1千店で売られたコメ5キロの平均価格は税込み4268円で、前の週より54円(1・3%)高く、2週ぶりに上昇したとの報道がされている時にです。
昨秋からの「令和の米騒動」が続く中、米の生産を抑える減反政策は続き、米価は高止まりしたままで、農業問題に詳しい東京大大学院の鈴木宣弘・特任教授は「今こそ食糧安全保障の強化が求められるのに、コメ政策は逆行している」と国の誤った政策を強く批判しています。
鈴木特任教授は、「騒動の最大の要因は、コメの生産が減りすぎていることであり、それはコメは余っているという政府の認識自体が間違っているからである。あれほどのコメ不足で、しかも米価は今も高いままだというのに、農林水産省は未だに農家に減反を迫っている。」と指摘しています。
日本が、国産で賄える穀物は米だけで、有事の際は米でしのぐしかないのに、このままではいざという時、国民の命は守れないことを自覚した政策が求められています。
減反政策というのは、コメの生産を減らして市場価格を上げようとするもので、農家が米から別の作物に転作すれば政府が毎年約3500億円にも上る補助金をだしており、こんな大金をかけて、わざわざ米価を上げようとするものだとも指摘されています。
今、農水相が先頭に立ってやらなければならないのはこのような愚策を見直すことなのです。
それが、国民の理解を得るどころか感情を逆なでする妄言を発していて、許されるはずはありません。
政治家の政治資金などに詳しい神戸学院大・上脇教授は関連業者との接触に当たって、国民の疑惑を招く行為を禁じた「大臣規範」の存在を挙げ、農水相の行為や発言は軽率だと批判し、「罰則はないが、政治責任を伴い、支援者からのコメはもらうべきではなかった」とも述べられています。
こんな大臣の続投を認める石破政権の国民の生活や命を守る本気度が問われます。
| 5月19日「被災者に届く災害ケースマネジメントであるために」 |
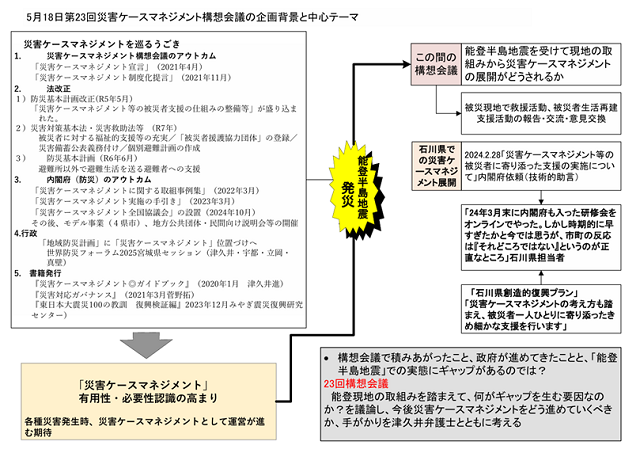 昨日は、会議を掛け持ちしていたことから、録音して後から聞いた第23回「災害ケースマネジメント構想会議」で、災害ケースマネジメントの現在の到達点となぜ実行されないのかという課題について、津久井進弁護士の提起を聞かせて頂き、改めてこれからの実践に繋げなければと考えさせられたことです。
昨日は、会議を掛け持ちしていたことから、録音して後から聞いた第23回「災害ケースマネジメント構想会議」で、災害ケースマネジメントの現在の到達点となぜ実行されないのかという課題について、津久井進弁護士の提起を聞かせて頂き、改めてこれからの実践に繋げなければと考えさせられたことです。
まずは、災害ケースマネジメントって何かという「大前提」と「共通認識」が欠如していること。
さらには、災害ケースマネジメントは誰がやるものかということで、「行政がやるもの」「民間がやるもの」「協働でやるもの」と言いながらも、「担い手」が欠如していること。
では、進めるうえで、「障害物」として、「人的課題」「経済的負担」「個人情報の壁」「業務量の限界」「ネガティブイメージ」「平時からの因習」があるとの指摘。
そして、最後に「ゴール」の欠如、「ゴール」は何なのかということで、「被災者にとって」「支援者にとって」「行政にとって」のゴールについて提起されました。
「被災者に届かない災害ケースマネジメント」では意味はないという現状となぜ実行されないのかという課題について、整理されたようなお話だったと思います。
高知もまだまだ、災害関連死を出さず、被災者の生活再建・復興の取組は緒に就いたばかりですので、参考にしながら頑張りたいと思います。
| 5月18日「災害後に残し守り伝える地域の記憶」 |
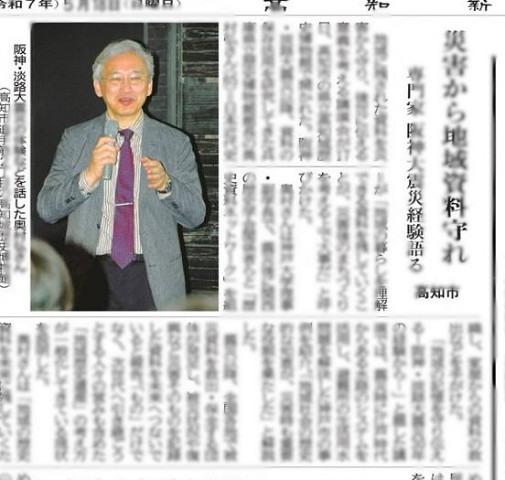
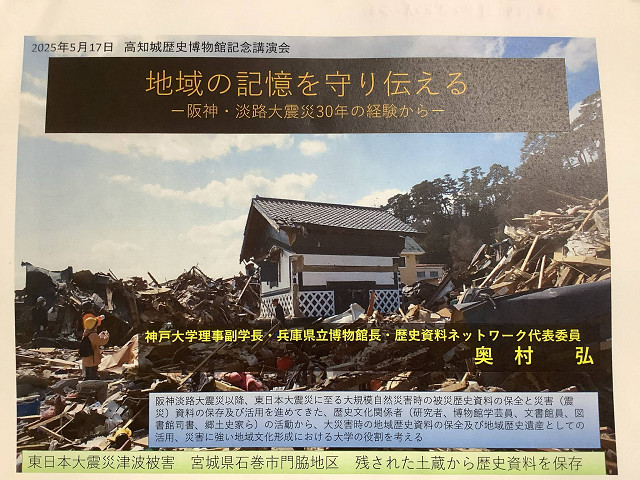
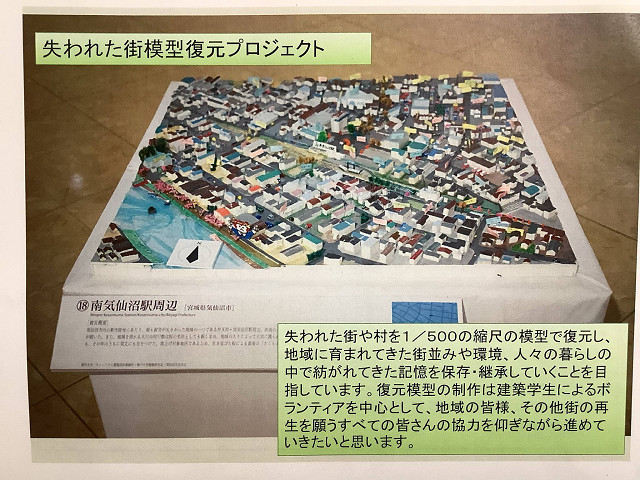
昨日の午後は、高知城歴史博物館で開催中の企画展「高知の地震災害史 紡がれた記憶と記録」の一環で行われた「地域の記憶を守り伝える―阪神・淡路大震災30年の経験から―」とのテーマの講演会に参加していました。
講師は、阪神・淡路大震災以降、資料の保存活用を研究してきた兵庫県立歴史博物館館長の奥村弘さんで、地域に残された資料を災害から守り、後世に伝える意義を考えることが、災害後のまちづくりを考える上で大事であることを訴えられました。
災害後に、どのような形で、資料を復元したり、保存していくのかなどの事例紹介もして頂きました。
その中には、私自身東日本大震災の翌年に訪ねた石巻市門脇地区に残された土蔵に保管されていた歴史資料のことや変わりつつある歴史研究の手法として変化する専門知と社会知(市民知)の関係による「失われた街模型復元プロジェクト」など昨年珠洲市で行われていたものを見学したものもありました。
震災以降、全国各地で被災資料を救出・保全する団体が発足し、被災状況や復興など災害そのものを記録した資料を未来へつないでいるのが、これからは高知など未災地で発足しようとしていることなども報告されました。
地域遺産は単に「ある」のではなく「なる」もの、地域の文化の継承とともに価値を増していく存在であり、地域社会への豊かな感性を育てるものとのお話は、これからの街づくりの中で考えさせられることとして聞かせて頂きました。
「復興」するためには、「前」がしっかりと把握される必要があるということからも、これからの「事前復興の街づくり計画」の中にも生かされることだと考えせられました。
| 5月17日「日米地位協定の壁を突き破ろう」 |
 昨日今日と高知新聞一面は、米軍戦闘機の高知空港長期駐機を通じて見える「日米地位協定の壁」について、書かれています。
昨日今日と高知新聞一面は、米軍戦闘機の高知空港長期駐機を通じて見える「日米地位協定の壁」について、書かれています。
改めて、沖縄の基地の問題が全国の基地化の問題として、考えさせられる課題であることを突きつけられているのではないでしょうか。
元琉球新報編集委員長で沖縄国際大学大学院教授の前泊博盛さん等によってまとめられた「日米地位協定入門」には、「日米地位協定は、1952年に旧安保条約と同時に発行した日米行政協定を前身としています。その日米行政協定を結ぶにあたって、アメリカ側が最も重視した目的が、➀日本の全土基地化②在日米軍基地の自由使用だった」ことが研究者によって明らかにされていると言及され、「アメリカが占領期と同じように日本に軍隊を配備し続けるための取り決め。もっと露骨に言うと、日本における米軍の強大な権益についての取り決めと言えるかもしれません。」とあります。
まさに、そのことの具体化が、全国の11空港、25港湾、道路6カ所の「特定利用空港・港湾」としての指定であるのかもしれません。
1960年改定の日米安全保障条約に基づき、28条からなる「日米地位協定」は同年発効していますが、日本に駐留する米軍と軍人・軍属、家族の法的地位や基地の管理・運用を定め、発効から一度も改定されていません。
自民党総裁選に臨んだ石破氏も「見直しに着手する。運用の改善で事が済むとは思わない」と意欲を見せていたが、首相になったとたんにトーンダウンしてしまっています。
浜田知事は防衛省に、5月9日付で、中国四国防衛局長宛に「的確な情報提供と説明に努めることを米軍に求めるよう」要請し、同日、中国四国防衛局から「米軍側に伝える」と電話で説明があったというが、米軍からは中国四国防衛局を通じたコメントがあっただけだといいます。
彼らにとって、42日間民間空港に居座ったことについて何の痛痒も感じていないのでしょう。
そういう関係性を見直すためにも、今回の課題を通じて、令和2年11月5日付けの全国知事会による日米地位協定の抜本的見直しを求める「米軍基地負担に関する提言」の実下など含めて日米地位協定の壁を低くし、突き破る取組を具体化することが求められているのではないでしょうか。
| 5月15日「県内東部の貴重な資源の有効活用を」 |

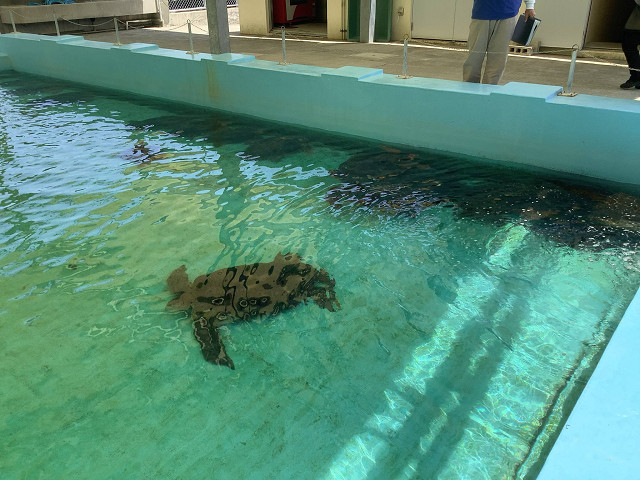
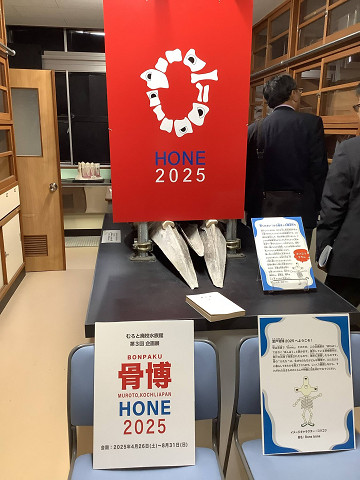

昨日の出先機関調査は室戸方面で、最初は、「室戸市海洋生物飼育展示施設室戸海の学校」いわゆる「室戸廃校水族館」でした。
指定管理者制度によってNPO法人日本ウミガメ協議会が管理しているが、指定管理料収入もない中で、館長の様々なアイディアと職員の多彩な技術などを駆使して、運営されており、開館から7年間の入館者合計は70万人を超えています。
開館初年は足摺海洋館のリニューアル開館時の17.6万人に対して16.8万人と遜色ない入館者で、今年のゴールデンウィークも県内観光施設で10位の足摺海洋館に迫る12位と健闘しいます。
地元にある豊富な海洋資源を活用した「地産外商」の施設で、多いに県外観光客の誘致につながっています。
現在も、大阪万博に対抗して室戸骨博(ぼんぱく:骨は英語でボーンということでボンパクと読ませています)を開催し、ユーモアとウィットに富んだ企画展や運営は大きな魅力となっています。
しかし、課題として古い学校施設のため、バリアフリー対応が弱く、高齢者の団体や養護学校等の利用者への対応に困り、周辺の飲食店や宿泊施設の現象によって滞在型観光の実施が難しくなっていること。
また、水族館として、海水取水設備は最も大事な設備だが、度重なる故障や取水、水量の少なさに飼育管理の面で苦労されているとのことですので、何らかの支援も必要ではないかと思ったところです。
県立室戸体育館は、県から室戸市への移管準備のため、東日本大震災などの被害事例を踏まえた最新の耐震診断をしたところ、屋根部に問題があったためアリーナが昨年3月1日から閉鎖になっており、今年度中に耐震化工事がされる予定だが、室戸市への移管後は、さらなる利活用や災害時の避難場所としての活用が望まれます。
県立室戸広域公園は、施設的にはさらに利活用が望まれますが、地元の有力な宿泊施設の廃業等があり、県外からの合宿利用に対応しきれておらず、利用状況が低下しています。
このままではジリ貧の状況があり、せっかくの施設でもあるので、室戸観光の強化という意味でも、宿泊施設の再建を含めて検討されることが望まれます。
| 5月14日「厳罰だけでなく、自転車にも優しい街づくりを」 |
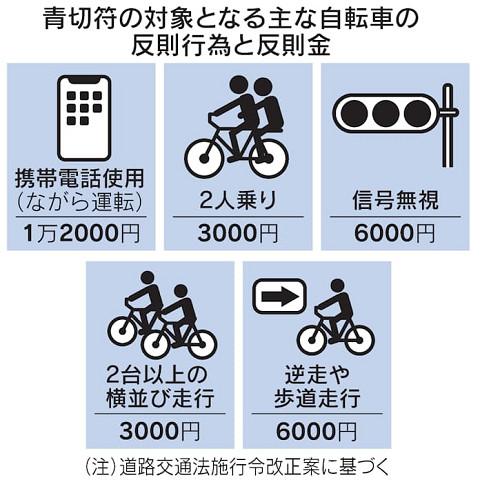


昨夕、会長をさせて頂いている県サイクリング協会の総会に向けた打合せをしている中で、来年4月1日に施行される見通しの自転車の交通違反に「青切符」を交付して反則金を納付させる改正道路交通法のことについて話題になりました。
反則金は原付きバイクと同水準で、違反の内容に応じて、3000~1万2000円とされていますが、違反した場合に警察官に青切符を切られ、反則金を納めれば刑事罰を科されない制度に自転車が加わことになります。
自転車の反則金は、指定場所一時不停止や通行禁止違反、傘差しやイヤホンの装着といった公安委員会順守事項違反などが5000円、信号無視のほか、右側通行や歩道通行といった通行区分違反などは6000円となります。
スマートフォンや携帯電話を使用して走行する「ながら運転」のうち、通話や画面を注視する違反は1万2000円となります。
2台以上が横に並んで走る並進も禁止されており、反則金は3000円で、2人乗りなどの軽車両乗車積載制限違反も同額となっています。
これらの違反は、私たちが早朝や夜間に交通安全指導をしていても、よく見かけ指導することの多いものです。
これらの順守事項を子どもから高齢者まで徹底させるのは、大変なことだろうと思います。
確かに事故を起こさないためにも、交通ルールを守ることは当然ではありますが、車道があり、歩道があるなら、自転車道も設けられるべきだと思います。
自転車先進都市・コペンハーゲンの自転車道は温室効果ガス削減、市民の健康増進などを目指し、計画的に整備されたといわれてますが、日本の自転車行政も、規制とともに自転車に優しいまちづくりを両輪とするぐらいの決意で臨んでもらいたいと思います。
| 5月12日「やっぱり紙の保険証全廃は無理なのでは」 |
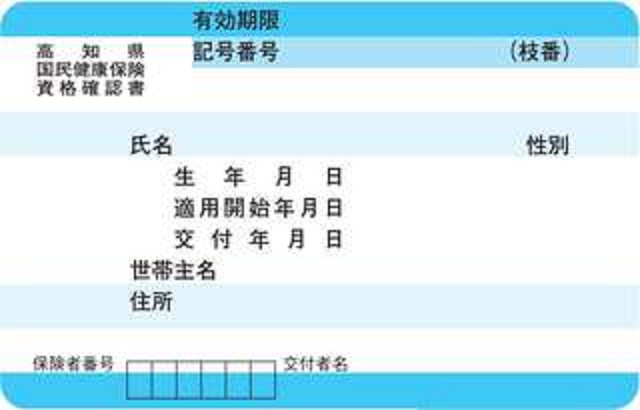
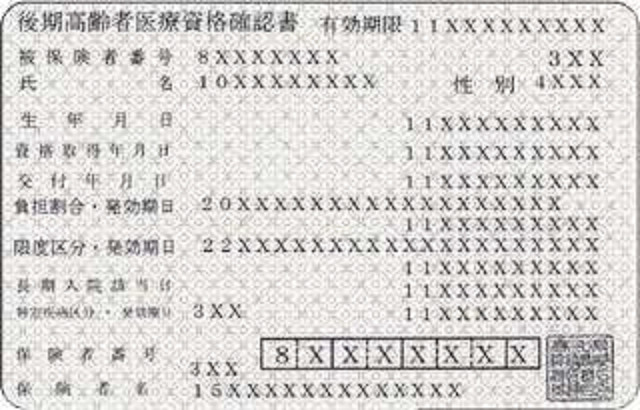
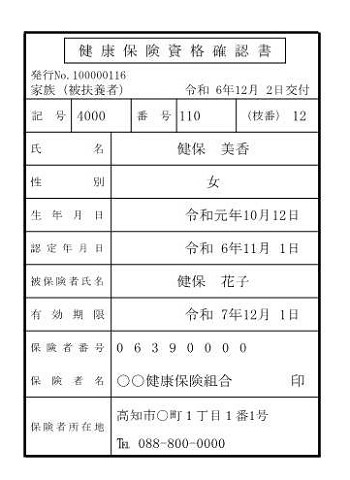
昨年12月2日付で従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」への一本化が進められてきました。
ところが最近になって、従来の保険証を全廃しようとする国の方針に無理があることが明らかになっています。
厚生労働省は今年4月3日付で地方自治体に向けて通知を出し、約2000万人といわれる75歳以上の「後期高齢者」のすべての人を対象に、保険証代わりに使用できる「資格確認書」を郵送する方針を打ち出しました。
まさに、これまでの保険証廃止およびマイナ保険証への一本化という政策を事実上、見直さざるをえなくなったことを意味するのではないでしょうか。
マイナ保険証での受診時の何らかのトラブル発生は相変わらず続いています。
そのような中で、保険証廃止を7月末に控え、資格確認書交付を希望する人が自治体に押し寄せることによる混乱を懸念して、一定の条件を課したうえで希望者に限って発行していた資格確認書を、後期高齢者全員に配付するとのことです。
自治体職員の間では、マイナ保険証に関する事務作業の負担は、問い合わせへの対応も含めて増大しており、混乱の発生を心配しているとの声もあるが、もう国民全員に資格確認書を配付するしかなくなるのではないでしょうか。
<申請によらず交付する方>
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
| 5月11日「紫雲丸事故から70年改めて教訓を生かして」 |

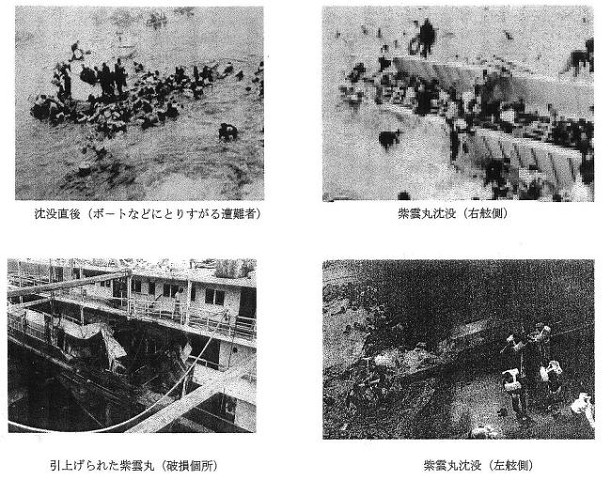
1955年5月11日、高松市沖で起きた宇高連絡船「紫雲丸」の沈没事故から、今日で70年を迎えました。
その節目に、高知新聞や朝日新聞では連載記事も特集されていました。
事故では168人が犠牲になり、修学旅行の南海中の生徒が巻き込まれ、28人が犠牲になったことは、忘れてはならない事故として「教訓」が伝え続けられなければなりません。
「紫雲丸事故を語りつぐ会」が2012年11月に発行した「検証 紫雲丸事故-南海中学校の悲しみ 28人の犠牲をムダにしないために『伝えなければならない教訓』」という「事実検証資料」によると、事故の最大の原因、犠牲者拡大の要因は「国鉄当局の運行方針に事故を誘発する要因があったこと」「紫雲丸の左転行動が沈没事故の直接原因を誘発したこと」「引率教諭、国鉄職員らの避難誘導の放棄が『犠牲を広げた原因』をつくったこと」とされています。
事故後、本四架橋建設の機運が高まり、小中学校で水泳授業の充実に向けてプール整備が進んだとされていますが、その南海中学のプールで起きた昨年の長浜小学校の4年生の男子児童が水泳の授業で溺れて亡くなりました。
事故検証委員会報告を受け、市教委は今年4月、授業の事故防止マニュアルを作成し、プールの水深は「全ての児童の両肩が水面から出るラインを目安」と定めましたが、この基準は、12年に京都市で起きた小1女児の死亡事故を受け、同市教委が作成した指針を参考にしたそうです。
県内では18年の夏休みにも、プール開放中に高知市の潮江小の3年女児が一時重体になる事故が起きており、長浜小男児が亡くなってようやく、安全対策が明文化されたことになります。
今朝の高知新聞の「語り継ぐ命 紫雲丸事故から70年(下)」の記事には、昨年の5月11日の追悼慰霊式での校長先生の言葉「事故は戦後の大量輸送時代に技術や利便性、採算性を優先するあまり、何よりも大切にされるべき人命や安全対策が軽視されていたことから引き起こされた」「安心安全な学校づくりに努めてまいります」との言葉が引用されています。
今回のプール事故でも「何よりも大切にされるべき人命や安全対策が軽視されていた」とすれば、紫雲丸事故の教訓が生かされていなかったということにならないでしょうか。
紫雲丸事故から70年の今日、改めて子どもたちの命と安全安心を守るための最善策を常に考え、対策をとり続ける必要があることを痛感させられます。
| 5月10日「沖縄戦の教訓に基づいた謝罪と撤回を」 |

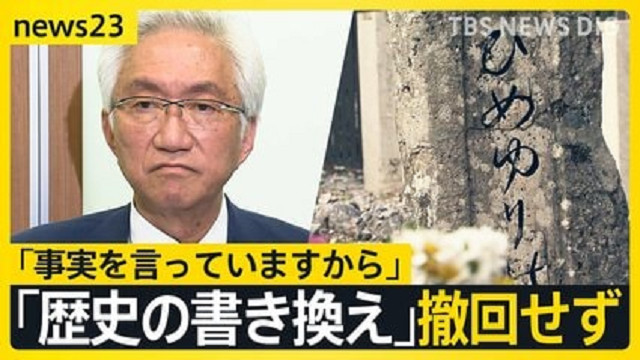
自民党参院議員の西田昌司氏が憲法記念日に那覇市内で開かれた「憲法シンポジウム」で行った沖縄戦犠牲者や遺族を含む県民を傷つける発言は断じて許されません。
西田氏は、何十年か前に訪れたというひめゆりの塔について「要するに日本軍がどんどん入ってきて、ひめゆりの隊が死ぬことになった。アメリカが入ってきて沖縄は解放されたという文脈で書いている」と述べていますが、少なくとも、ひめゆりの塔の前にある1975年建立の石碑に刻まれている「ひめゆりの塔の記」にはそのような「文脈」はありません。
「歴史の書き換え」と断ずるような文章などと、あいまいな記憶で沖縄戦の事実をゆがめるような発言をしてはならないはずです。
西田氏は「まるで亡くなった方々が報われない。歴史を書き換えられると、こういうことになっちゃう」とも述べ、「かなりむちゃくちゃな教育をされている」とまで言い切るなど、沖縄戦の史実をゆがめ、体験者証言や沖縄戦研究を愚弄しています。
一連の発言を巡っては県内外から謝罪と撤回を求める声に対して、「あの場でひめゆりの塔を持ち出して話すことが、県民の皆さんの心に傷を負わせた」とし、あたかも場をわきまえなかったことのみを詫びているようであり、あいまいな記憶に基づいて「あそこはひどい」と侮辱し、「歴史を書き換えた」と決め付けたことは撤回しようとしていません。
沖縄は米軍統治が27年間にわたって続いたことを挙げ「アメリカに都合がいい教育をしてきた」として「反日教育」に染まったと主張しているのです。
沖縄の平和教育は、惨禍を二度と繰り返さないという県民の決意、「軍隊は住民を守らない」という教訓を踏まえているのであって、体験者証言と沖縄戦研究に基づいた平和教育の実践があります。
そのような経緯を無視し、沖縄戦の実相をゆがめようとしている国の側によって歴史の書き換えが強要されようとしてきたことに抗ってきた県民と向き合ったうえで、心底からの謝罪と撤回がされるべきではないでしょうか。
| 5月8日「産業振興土木委員会出先機関調査始まる」 |


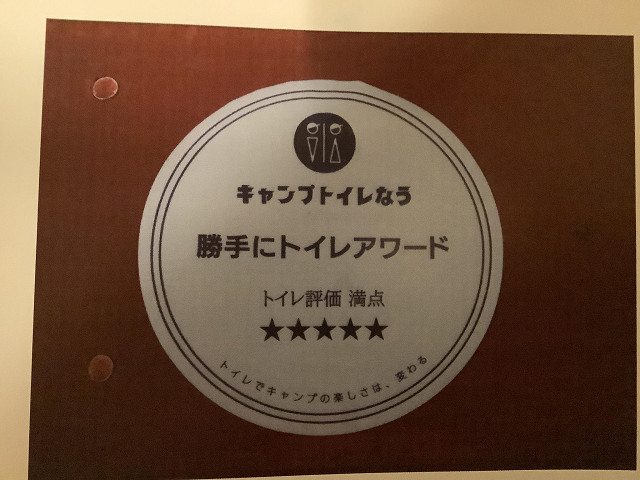


昨日のスタートは、国土交通省中村河川国道事務所で、管内の河川の管理状況、道路の整備状況等の説明を受けました。
流域治水プロジェクト、南海トラフ地震対策事業、堤防拡幅事業、河道掘削事業、渡川総合水系環境整備事業、窪川佐賀道路、佐賀大方道路、大方四万十道路の整備状況等についての現状が報告されました。
その後、土佐西南大規模公園で県からの指定管理を受けている公益財団法人四万十市公園管理公社からオートキャンプ場「とまろっと」の施設利用や管理について、一時期と比べて停滞したキャンプブームの中でのコロナ禍での影響や一昨年の台風、南海地震臨時情報によるキャンセルで、利用者が減少していることなどの報告を受けました。
しかし、長年にわたる管理の丁寧さがキャンプ場のトイレが、きれいなトイレとして、星5つの評価を頂いていることなども、このキャンプ場の魅力になっていると思われます。
午後からは、平成13年9月の高知県西南豪雨で、大きな被害をもたらした貝ノ川川での洪水被害をなくし、安定した用水維持や水道用水の安定供給などを目的とした春遠生活貯水池建設事業の第一ダムの建設現場で説明頂きました。
令和5年から工事に着手されていますが、現状では特に大きな想定を超えるような事態の変化などはなく、順調に工事は進捗し令和8年度末までの完成予定であるとのことでした。
足摺海洋館SATOUMIでは、リニューアルオープン5周年の今年これまでの課題となってきた「新しい水族館だから行くではなくて、来館者が何度来ても満足感を与えられる施設環境作りを目指す」ということで、様々な企画が行われています。
これらの企画が、さらに西南地域の観光の拠点として発展していくよう願っています。
5月からは、山崎製パンとコラボした期間限定商品のパンを中国、四国地方の全県と兵庫県の量販店で販売し、認知度を高め、売り上げの一部が寄付されるという取り組みの報告もありました。
これから30日まで9日間にわたって、出先機関・現場や関係機関の調査を継続していきますので、折に触れて報告していきたいと思います。
| 5月7日「パレスチナ・ガザに連帯して凧揚げを」 |



イスラエルの残虐な無差別攻撃により、既にガザでは5万名を超える人々が殺され、そのうち7割が女性と子どもという残虐さです。
イスラエルは、ガザを自国のものにし、パレスチナ人は全員殺すか追い出す意図を持つことが鮮明になっています。
パレスチナ・ガザにおいて一向に止むことのないイスラエルによるジェノサイドに心を痛めている皆さんともに、パレスチナ・沖縄連帯実行委員会によって改めて「パレスチナ・ガザ連帯凧あげin高知」の呼びかけがされています。
昨年も11月17日には、「パレスチナ連帯凧あげ」が行われました。
バレスチナの人々は凧あげをする伝統があるとのことで、「天井のない監獄」というか今では「天井のない地獄」にいる人々にとっては、平和と自由への希望の象徴なのかもしれないとの主催者の皆さんの思いをのせて老若男女で凧揚げに息を切らしたことでした。
トランプ氏の「アメリカによるガザ保有発言」はイスラエルの狙いをアメリカが代行すると宣言したに等しいとも言われています。
私たちには何ができるのかということで、パレスチナ・沖縄連帯実行委員会では様々な活動を続けてきましたが、今回は1948年5月15日のナクバ(イスラエルのパレスチナ侵攻と土地収奪)の日にあわせて、再び「パレスチナ・ガザ連帯凧揚げin高知」を取り組まれますので、ぜひご参加ください
「パレスチナ・ガザ連帯 凧あげin高知」
日時:5月18日(日)16:00~
場所:高知市鏡川沿い「鏡川緑地公園」(鏡川河川敷「月の瀬橋」と「柳原橋」の間の北岸です。
| 5月6日「米軍機長期駐機の原因と背景究明は必要」 |
 高知龍馬空港に3月25日に緊急着陸して以来、長期駐機していた米軍岩国基地所属のF35ステルス戦闘機が昨日5日午前11時8分にやっと離陸しました。
高知龍馬空港に3月25日に緊急着陸して以来、長期駐機していた米軍岩国基地所属のF35ステルス戦闘機が昨日5日午前11時8分にやっと離陸しました。
この間、米軍関係者によるエンジン交換などで整備が長期化し、駐機は42日に及び、過去5年で国内最長となりました。
緊急着陸より危険性の低い「予防着陸」と説明した米軍は、日米地位協定に基づいて空港の一部を占有し続け、不具合の詳細も説明せず、整備と駐機は長引き、県民の間では「これだけ修理に長期間かかるのは、墜落の危険さえあるような故障だったのではないか。」との懸念も生じていました。
しかも、その間国土交通省高知空港事務所や、防衛省中国四国防衛局、県危機管理部は県民が納得できるような情報の提供や説明もありませんでした。
そのような中で、「郷土の軍事化に反対する高知県民ネットワーク」としては、県に対しての要請行動や空港周辺での抗議行動も行い、安全重視の予防着陸はやむを得なかったものの、米軍は不具合の内容や今後の見通しを説明せず、民間空港の一部を占有し続けていることに抗議し、過去に米軍機の墜落事故が相次いだ本県では、「墜落につながる重大な故障が原因ではないか」と不安視する声を伝えてきました。
何ら説明されないまま放置されている県民が、「なぜ着陸したのか、なぜ離陸しないのか、」具体的に説明を求めるのは、当たり前の行動であったと思います。
米軍はこれまでも日本各地の民間空港・港湾の軍事利用の規制事実を積み上げてきたと思われる利用として、2012~21年の米軍機の九州・沖縄の空港への着陸は、2034回、同期間の日本全国の空港への米軍の着陸回数合計の約7割にも上ると言われていいます。
そのうち九州・沖縄の空港への着陸が最多だった2020年は269回で、全体の約9割に達しています。
2023年の米軍期の民間空港への着陸回数は、過去最多の453回で、そのうち約8割が九州・沖縄に集中していますが、ここにきて本年2月にも岩国基地のF35戦闘機が松山空港に緊急着陸しており、同じF35戦闘が高知龍馬空港に緊急着陸した3月25日には、長野松本空港に沖縄普天間基地所属のオスプレイが緊急着陸するなど、まさに「訓練中の警告灯」を理由に、米軍は全国の空港での着陸訓練を試みているのではないかとの疑念を生じさせています。
今回の離陸にあたっても、「ネットワーク」では、「欠陥機でなければ、なぜ長期整備が必要だったのか。米軍、防衛省、県は県民に原因を説明すべきだ。離陸に安堵せず、こんな事態が繰り返されないよう危機感を持ってほしい」と指摘しています。
これで、一件落着ではなく、今回の米軍機高知空港長期駐機の原因と背景を明らかにさせるとともに、台湾有事を利用し、有事体制に組み込まれようとする自治体として空港・港湾の軍事利用にどう抗っていくのかが問われているのではないでしょうか。
| 5月5日「子どもを育てたい社会を」 |
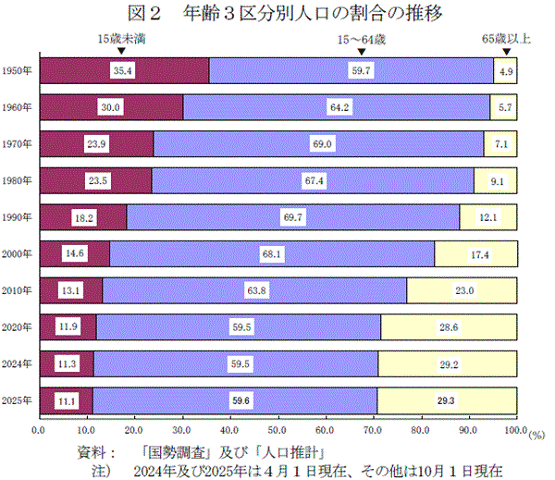
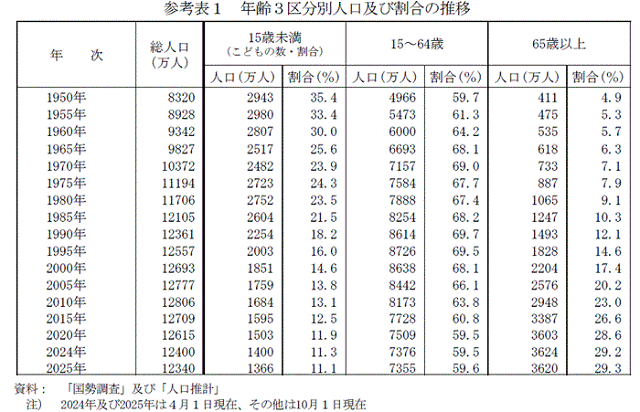

総務省は、5日の「こどもの日」に合わせて15歳未満の子どもの推計人口(4月1日現在)が、前年より35万人少ない1366万人で、44年連続の減少となり、比較可能な1950年以降で最少を更新したことを公表しました。
総人口(1億2340万人)に占める割合は前年比0.2ポイント減の11.1%と51年連続で低下し、過去最低となりました。
本県は6万7千人で人口に占める割合は10.3%となり、割合の低い方から5番目となっています。
「こどもの日」が国民の祝日として制定されたのは、太平洋戦争の終結後間もない1948年であり、子どもの人格を重んじ、幸福をはかる日とされています。
先の戦争は弱い立場の子どもたちに多大な犠牲を強いたことからも、この祝日は愚かな戦争への反省を土台としているとも言われています。
54年には国連が11月20日を「世界子どもの日」と定めているが、ここにも平和への願いが込められています。
しかし、戦後80年を迎えた今も、世界のあちこちで戦争や紛争が続き、子どもたちの未来が奪われているし、この国も子どもには冷たい社会になっています。
子どもに自己責任を押しつけ、子どもの間に格差は生じ、諦めも生じさせている面があるのではないかと思われることもあります。
子育てをしている人がベビーカーを押していると、蹴られ、文句を言われたりもするので、一日中何回も「すみません」と言わなければらないとこぼされている社会で、積極的に子どもを生み育てようと思わないのではないでしょうか。
子どもはそういうことを、まざまざとみせつけられると、言ってもしょうがない、どうしようもないとなって希望を失ってしまいます。
そして、2024年は、小中高生527人が自殺をし、統計のある1980年以降で過去最多となったているのです。
子どものSOSのサインに、しっかり関心を払い、向き合いながら、それに応えてすべてのことを変えるぐらいのことをおとながしなければ、子どもが命を絶つことは止まらないでしょう。
| 5月4日「連休の過ごし方」 |
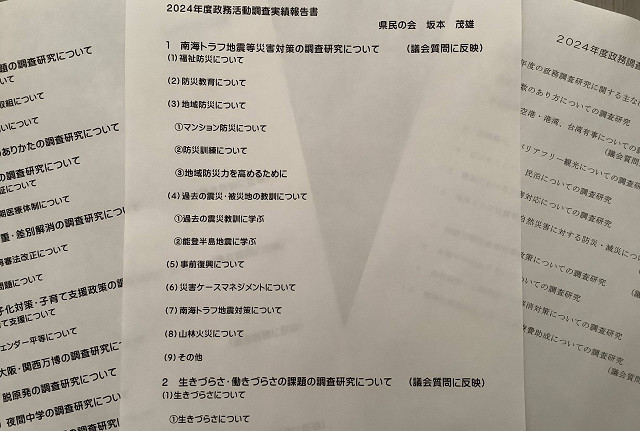 連休中の前半で4月中に提出した政務活動調査報告は、相変わらずの分量。
連休中の前半で4月中に提出した政務活動調査報告は、相変わらずの分量。
個人分の報告は84頁、目を通して下さる方はいないかもしれませんが、こちらからご覧いただけるようにリンクを貼っておきます。
正式には、県議会で令和6年度分政務活動費の公表が7月1日には、公表されますので、決算状況などもご覧いただけます。
連休後半は、地域防災の昨年度事業総括と今年度事業計画の策定に取り組んでいます。
こちらは、下知地区減災連絡会とサーパス知寄町Ⅰ自主防災会の両方に取り組んでおり、何とか仕上げたいと思います。
ただし、今日だけは4年前に亡くなった母の三回忌を行うため、今から準備です。
| 5月3日「戦後80年に憲法の具体化を『国民不断の努力』で」 |
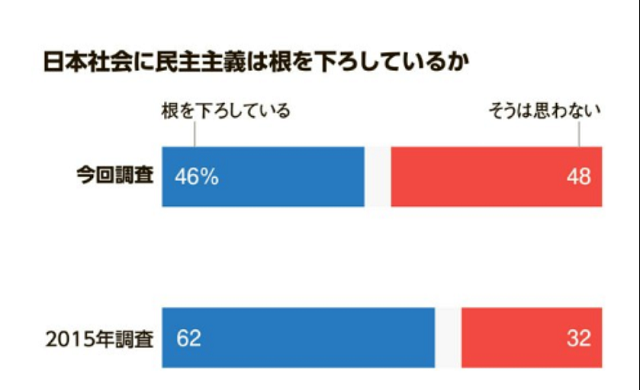
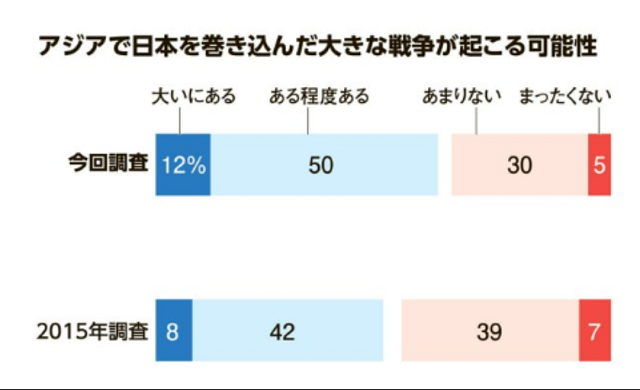 日本国憲法は本日施行78年を迎えました。
日本国憲法は本日施行78年を迎えました。
しかも、今年は戦後80年という節目でもあります。
しかし、戦後80年の憲法記念日は、世界のあちこちで戦禍による尊い命と人権が奪われ続けています。
むき出しの権力が猛威を振るう世界で、米国はトランプ関税脅しで自由貿易体制を危うくし、ロシアはウクライナ侵略をやめず、ガザではイスラエルによるジェノサイドとも言える惨劇が繰り返されています。
日本国憲法前文にはこうあります。
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
国際平和の希求は、戦争の惨禍を生き延びた人々の切実なる願いであり、犠牲となった人々や国際社会への誓いでもあるとしたら、近年、集団的自衛権の行使容認や敵基地攻撃能力の保有など、憲法9条に反する動きが加速し、防衛費の増大や防衛力の強化が続き、「新しい戦前」を迎えているなどと言われないような決意と行動を改めて示すべきではないでしょうか。
今朝の朝日新聞世論調査記事に「日本社会に民主主義が根を下ろしている」は46%で、10年前の2015年調査の62%より大きく減ったとありました。
そのような中で、アジアで「日本を巻き込んだ大きな戦争」が起こる可能性があるという回答が計62%に上り、10年前の調査の計50%より増えています。
まさに、民主主義が後退している中で、戦争の危機が高まっている中で、「新しい戦前」を迎えている状況を転換させるのは、戦禍から生まれた日本国憲法前文と9条をはじめとした自由、民主主義、国民主権、人権尊重、平和主義の具体化を図る「国民の不断の努力」(第12条)があってこそだと思います。
そんなことを考える戦後80年目の憲法記念日です。
| 5月2日「災害復興の王道である憲法の実践を」 |
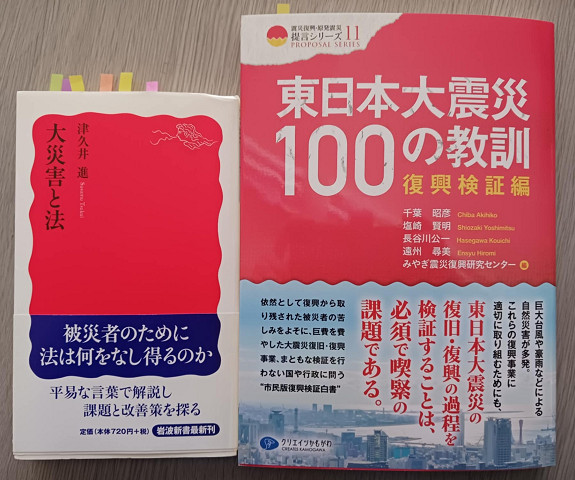 憲法記念日を前に、手にしている2023年12月発刊の「東日本大震災100の教訓 復興検証編」の各論「復興現場からの検証と教訓」に「日本国憲法と震災復興」の項があります。
憲法記念日を前に、手にしている2023年12月発刊の「東日本大震災100の教訓 復興検証編」の各論「復興現場からの検証と教訓」に「日本国憲法と震災復興」の項があります。
被災地で実施された各施策や現行の震災関連法制が、日本国憲法の保障する基本的人権に適ったものだったのかどうかを、事例を題材に考察されています。
「在宅被災者」には、憲法13条(個人の尊重、幸福追求権)、25条(生存権)、14条(平等原則)の趣旨が生かされなかったこと。
「災害危険区域―集団移転促進事業」が憲法29条1項(財産権)、22条(居住・移転の自由)、14条(平等原則)などに抵触するのではないかとの指摘。
「被災者生活再建支援制度」は憲法29条1項(財産権)に抵触するとは言えず、むしろ13条(個人の尊重、幸福追求権)、25条(生存権)の趣旨にかなっていること。
「生活再建支援制度以外の復興政策―各種補助金制度」らついても、前述されたように憲法29条1項(財産権)に抵触するとの指摘は容れられない解釈てあるばかりか、震災復興の政策目的の実現にとって支障となっていること。
以上のように、各施策や現行の震災関連法制が、日本国憲法の保障する基本的人権に適ったものなのかを考えされらることが多くあります。
いつもご指導いただく兵庫弁護士会の津久井進弁護士の著書「大災害と法」には、「憲法は、被災者を救うために存在するのであって、苦難を強いるために存在しているのではない。その理念があるからこそ最高法規なのである。あらゆる災害法は、被災者を救うという強い思いを持って解釈、運用、適用すれば、それが憲法に適合する。災害復興の王道は、憲法を実践することに他ならない。」と書かれています。
| 4月30日「タウンモビリティステーション『ふくねこ』10年の成果とこれからの課題」 |
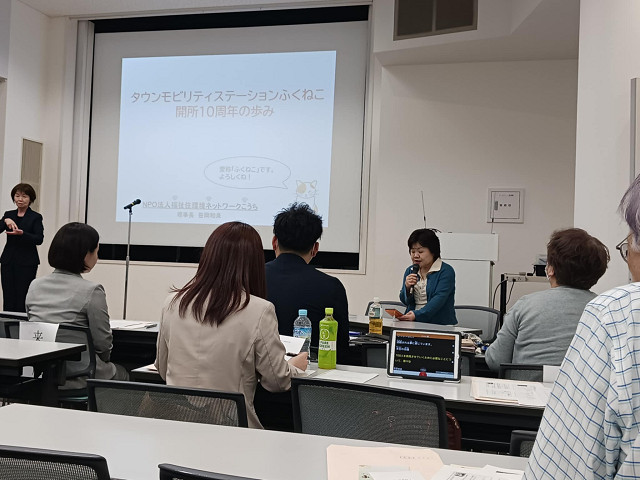

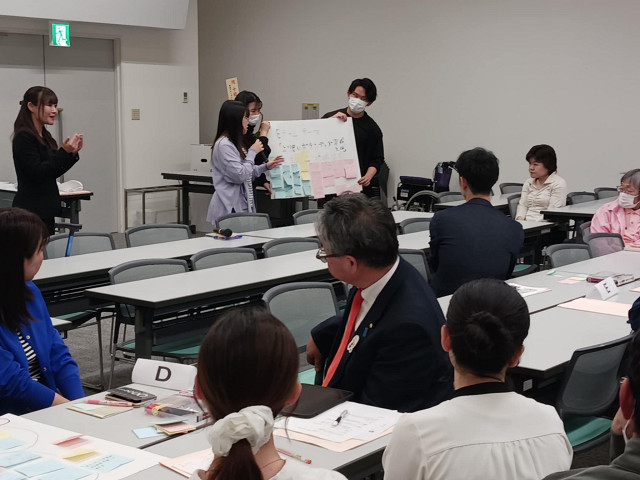
昨日は、開設当初から学ばさせて頂いてきた「タウンモビリティステーションふくねこ」さんの開所10周年記念イベントが開かれましたた。
私は、午前中のメーデーが終わってからの参加になりましたので、午後の式典のみの参加になりました。
笹岡和泉理事長から、障害者や高齢者らのニーズに答えることで始まった外出支援の拠点として構えた京町商店街でのタウンモビリティステーションでのこれまでの成果とこれからの課題について報告がされました。
そして、高知でのタウンモビリティ活動のきっかけにもなった福岡県久留米市六ツ門商店街にてタウンモビリティを実践されていたNPO法人高齢者快適生活つくり研究会の吉永美佐子代表理事からの「タウンモビリティの経緯、現状と今後」についてのお話も、示唆にとんだお話しでした。
両方に、共通しているのは、人材と財源を自前でどう確保しながら、「移動という権利をどう継続的に、快適に保障し、参加できる環境をどう維持していくか。そして、移動が作り出す街の賑わいを取り戻す」ということだと考えさせられました。
そのことが、講演の後のワークショップでの意見交換の主な課題にもなったようで、日頃から「ふくねこ」に関わられている大学生や利用者、行政職員、関係者の皆さんから多様なアイデアも出されていました。
私自身は、昨年の9月定例会で笹岡さんとの意見交換をもとに提案させて頂いた「福祉×防災×観光」という視点に、「ふくねこ」さんが、さらに「商店街」をかけ合わせて取り組まれている「福祉×防災×商店街×観光」の取組こそが、これからの高知の「タウンモビリティの伸び代」ではないかと改めて感じさせていただきました。
さらなる10年、ハードにバリアが残っていても、ハートにバリアがなくなり、当たり前に誰一人遠慮することなく移動の権利が保障される環境づくりに向けて、皆さんとともに頑張っていきたいものです。
| 4月29日「県一消防広域化の検討は慎重に」 |
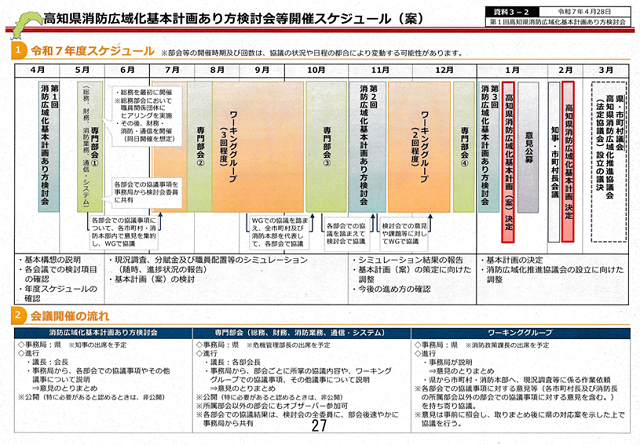
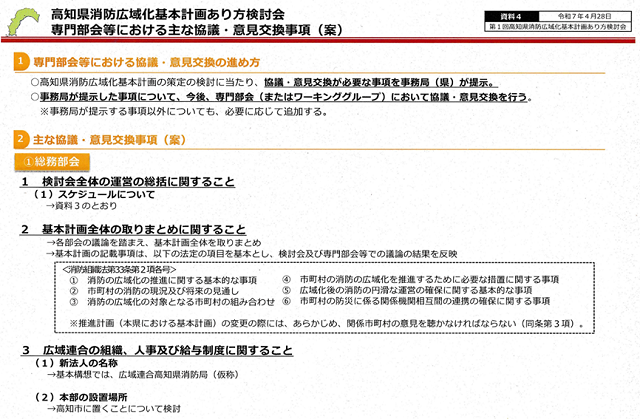
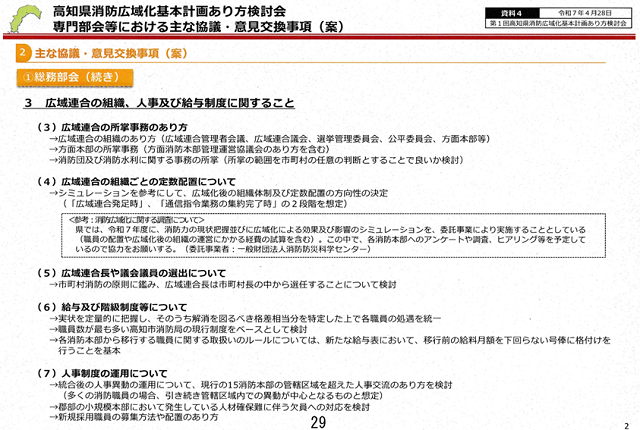
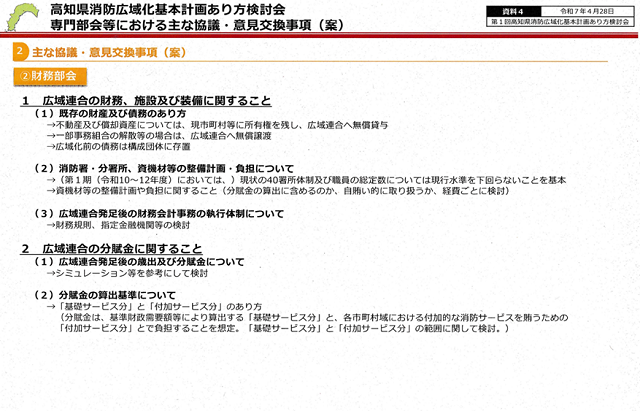
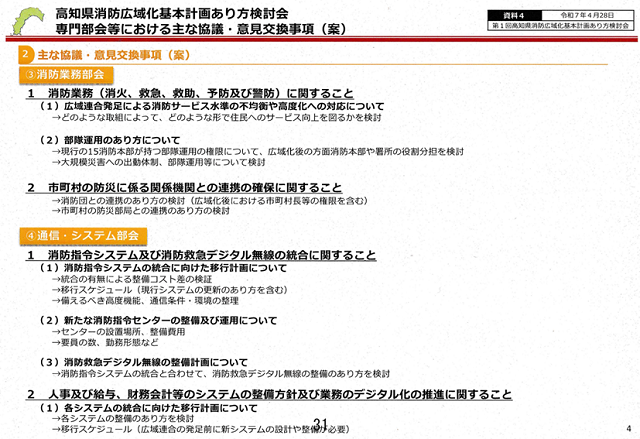
昨年の秋以来、県議会でも議論をしてきた県一消防広域化の議論が、昨日の「県消防広域化基本計画あり方検討会」の初会合で本格化し始めました。
検討会は34市町村の首長や15消防本部の消防長、有識者らで組織され、人事や財務、通信など統合に向けた諸課題を実務者によるワーキンググループや専門部会で協議し、来年1月までに計画案を作成するスケジュールが確認されました。
統合後も各地域の消防署や分署は維持する方針などが説明されたが、質疑では、市町村長らが「消防隊員は人事異動への抵抗感が強い」と懸念を示し、「現場の権限がなくなり、サービスが低下しないように」「住民にメリットをしっかり示してほしい」と要望したとのことです。
これまでの県議会や県内自治体議会の議論でも、多様な意見が出されているので、それらを踏まえた慎重な議論がされることを求めておきたいと思います。
| 4月28日「市民による武力によらない平和を築く」 |

 昨日は、高知城ホールで開催されていた「4.27憲法集会」に参加しました。
昨日は、高知城ホールで開催されていた「4.27憲法集会」に参加しました。
羽場久美子青山学院名誉教授から「東北アジアに平和への道すじ~戦後80年戦争を繰り返さない。日中韓と、市民による平和こそ未来をつくる」と題した講演に会場で170名、4カ所のオンライン会場で200名が耳を傾けました。
先生が交通機関の事情で、間に合わずオンラインでお話を伺いました。
日清戦争から130年、日露戦争120年、第一次世界大戦勃発110年、第2次世界大戦終結80年という節目の年に世界では戦争が続いているが、この国はあまりにもその教訓に学んでいません。
先生は、その教訓の中から、「停戦の遅れは、国民の命にかかわる」ことからも「戦争は止めることができる」ことを様々な視点から指摘されました。
地域別世界人口の推移予測や世界経済見通し予測、世界名目GDPランキング、購買力平価ランキング、ゴールドマンサックス経済統計などから見える姿は、2050年には中国がアメリカを抜く先進国となることであり、その上位にはアジアなどの新興国が入ってくることになっています。
中国に抜かれる前にアメリカは中国にダメージを与えようとする戦略があるのではないか。
その戦略の片棒を日本は担がされようとしているが、日本の貿易相手国ランキングは1位の中国をはじめ10位までのうち7か国がアジア諸国なのに、それらの国々にミサイルを向けるのかが問われている。
しかし、我が国は、アメリカに追随しながら、隣国に向けて沖縄をはじめ、九州から全土にかけてミサイル配備を進めようとしている。
今こそ、アメリカの戦争政策、関税政策に追従するのでなく、日中不再戦、東アジアの連帯、アジア、BRICS、グローバルサウスとの連携、沖縄との連携によって地域の協力によって、市民が平和と繫栄を作っていくことが求められていると訴えられました。
改めて、市民が地域から、職場から平和を作る必要性を考えさせられる時間となりました。
| 4月26日「高知空港の米軍機なし崩し利用は許さない」 |

 高知龍馬空港に緊急着陸した米軍のF35ステルス戦闘機は、着陸から32日目の昨日も空港にとどまっていました。
高知龍馬空港に緊急着陸した米軍のF35ステルス戦闘機は、着陸から32日目の昨日も空港にとどまっていました。
同日、これまでも県に申し入れをしたり、空港周辺での抗議行動を行ってきた「郷土の軍事化に反対する高知県民ネットワーク」は、県などに対して着陸原因などの究明と県民への説明を求める記者会見を行いました。
県民ネットワークとしては、今回の事態は、まず、警告灯ランプが点灯したことで緊急着陸したということで、人命第一の観点から、そのこと自体を否定するものではないことを表明した上で、高知県の場合、過去に米軍戦闘機が早明浦ダムに墜落(1994年)、また土佐湾沖でも同様のことが起きており、これが民家に墜落しておれば、大惨事になっていたかもしれないので、緊急着陸に至った原因の徹底究明と再発防止が必要であり、そのことを県民の皆さんに明らかにすることを求めています。
しかし、4月1日に高知県知事に「米軍機の高知龍馬空港「緊急着陸」の真相究明及び再発防止の働きかけを求める申し入れ書」に対しても、県の姿勢は、物足りなさが否めず、「予防着陸」とはいえ、尋常ならざる事態であり、もっと深刻に受け止めて、毅然として情報収集や再発防止の申し入れ、そして県民の皆さんへの説明、情報公開をきちんとすべきことをさらに、求めていくことが表明されています。
知事も、昨日の定例会見で、「異例の長さ。見慣れない戦闘機の駐機が県民に少なからず不安を与えているのは事実だ」と指摘し、米軍に対し、「できるだけ早く解消してもらいたい」と24日に防衛省中国四国防衛局を通じて米軍に早期離陸を求めたが、「今のところ具体的な返事はない」とのことです。
県は、県民の不安を解消するためにも、もっと積極的に随時早期離陸を求めていくべきであり、今後も注視していきたいと思います。
| 4月25日「JR福知山線脱線事故から20年―教訓は今」 |
 乗客ら107人が死亡し、562人が負傷したJR福知山線脱線事故から20年が経ちました。
乗客ら107人が死亡し、562人が負傷したJR福知山線脱線事故から20年が経ちました。
鉄道業界では運転士らの人為的ミスを巡っての処分のあり方など模索が続き、大規模事故を起こした場合、事業者自体が刑事責任を負うべきとの声に十分向き合えていないという課題などはまだ残されています。
判断や行動の誤りによるヒューマンエラーは「起こりうる」との前提で、事象を組織内で共有、分析することが重要になるとのことで、JR西日本は事故後、ミスによる懲罰的な再教育「日勤教育」を取りやめたうえで、16年には事故が起きた場合も含めて処分しない「非懲戒」制度を導入しています。
処分しないことで職場の規律が乱れるといった慎重論もある中でも、鉄道の安全に詳しい関西大の安部誠治名誉教授は「そもそもミスを起こそうと思っている乗務員はいない。安全向上のために非懲戒とする制度を導入する意義はある」としたうえで「重大な事故が起きた場合、運転士らを処分しないことに納得が得られるのかという懸念は解消されていない。さらなる議論が必要になるだろう」と語り、「社会の理解」を求めています。
また、もう一つの課題である組織罰の導入問題です。
事故後、JR西日本の歴代社長4人が業務上過失致死傷罪に問われ、現場の急カーブで自動列車停止装置(ATS)を設置するなどの安全対策を取るべきだったかなどが争われたが、全員の無罪が確定しました。
甚大な事故を起こした企業責任はどこにあるのか、問い続けられている「組織罰」の導入が求められてきたが、議論が活発とは言いがたい状況が続いています。
脱線事故の遺族らによって16年4月設立された「組織罰を実現する会」が提案する「組織罰」は、業務上過失致死傷罪を適用できる特別法を創設し、法人に対して罰金刑を科す仕組みで、安全対策が十分だったと言える場合には免責する規定を設けることで、普段からの安全対策の充実や事故の真相解明にも寄与できると考えられています。
遺族に寄り添いこの事故と向き合い続けてきた被災者支援や災害復興における法制化にも取り組まれている津久井進弁護士は「明治時代にできた刑法では、企業活動が原因の大事故は想定していない。法の欠陥は是正されなければならない。しかし、法制化に向けては世論のうねりがもっと必要だ」と訴えられています。
また、同志社大の川崎友巳教授(刑法)も、「企業活動で多くの人命が失われても法人に罪を償わせる機会がないのが現状だ。組織罰の必要性について、社会への問題提起を続けなければならない」と指摘されています。
私は、当時「この事故は、際限のない競争の行き着く先の結果であり、はじめから安全運転を無視した運行ダイヤ、ミスを犯した運転士に対する「日勤教育」と称した人権無視の再教育、まさに採算性重視の競争優先による命と安全軽視の姿が浮き彫りになりつつある。」と指摘させて頂きました。
そして、その年の12月定例会では、「107人もの死者を出したJR西日本福知山線の尼崎事故における生命の安全よりも利益優先の競争と効率性を重視した超過密ダイヤと新ATS増設のサボタージュ。そして、ここにきてさらに命よりも競争・効率性が優先された耐震強度偽装事件の発覚。前者は公共サービスの民営化の成功事例と言われた国鉄民営化。そして、後者は阪神淡路大震災後の規制緩和の中で飛躍的に伸びてきた「民間指定確認検査機関」という大震災の命の教訓を生かすどころか、むしろ踏みにじる代物であったと言うことです。そのいずれもが、人の命よりも利益の方が重いという方針が貫かれているということです。」と指摘しながら質問をしたことを思い出します。
| 4月24日「被災者が借金しなくても生活再建できる支援を」 |
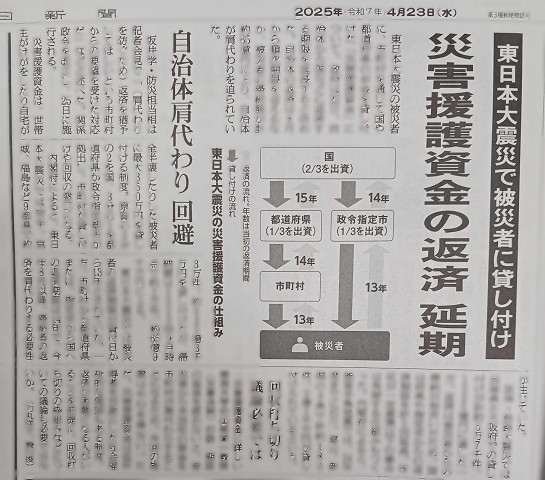
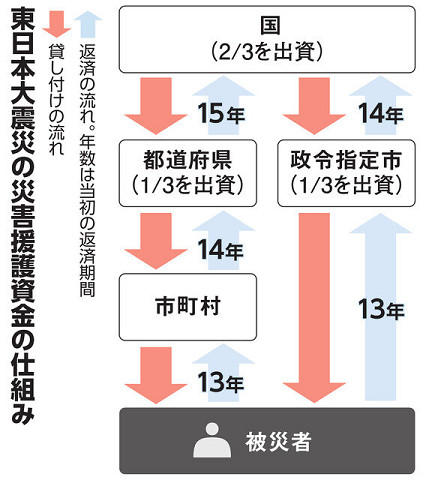 23日付の朝日新聞に、「災害援護資金の返済、延期」の見出しで、東日本大震災の被災者に、市町村を通じて国や都道府県のお金を貸し付けた「災害援護資金」について、政府が自治体から国などに返済する期限を延長することを決めたとの記事がありました。
23日付の朝日新聞に、「災害援護資金の返済、延期」の見出しで、東日本大震災の被災者に、市町村を通じて国や都道府県のお金を貸し付けた「災害援護資金」について、政府が自治体から国などに返済する期限を延長することを決めたとの記事がありました。
自治体の返済は8月から順次期限を迎えるなか、被災者の滞納額が計約65億円に上り、自治体の肩代わりが迫られており、返済を猶予してほしいという市町村からの要望があげられていたとのことです。
災害援護資金は、世帯主がけがをしたり自宅が全半壊したりした被災者に最大350万円を貸し付ける制度で、原資の3分の2を国、3分の1を都道府県か政令指定都市が拠出し、市町村が貸し付けや回収の窓口になるものです。
東日本大震災では岩手、宮城、福島など9都県で約3万件、約525億3千万円を貸し付けられているが、滞納額は2023年9月時点で約1万件、約65億9千万円に上るそうで、被災者の返済期限が貸付日から13年とされていました。
一方、市町村から都道府県または、指定市から国への返済期限は14年で、今年8月以降、滞納者の返済を肩代わりする必要性が生じていたとのことです。
阪神・淡路大震災の際にも返済は被災者からの滞納が相次いだため、国は府県や指定市からの返済期限を計5回延長し、年収が一定基準以下の場合は免除する仕組みもつくられています。
災害援護資金に詳しい関西大学の山崎栄一教授(災害法制)は、「災害援護資金の貸し付けには『1人世帯で年間220万円未満』などの所得制限があり、低所得者を対象にした社会福祉的な側面もある。もともと返済能力が低い人にも貸し付けているため、最初から返済や回収が困難になることを内包している制度であることが、問題の根底にある」と指摘されています。
また、「今後の災害を見越せば、被災者は持ち家の再建にこだわらず、家計状況に応じて公営住宅に入居するなどの選択肢を自治体が積極的に提示すべきであり、被災者が借金をしなくても、一人ひとりに合った『生活再建』ができるよう助言したり、相談を受けたりすることは重要性を増すだろう」とも述べられています。
改めて、「借金しなくても生活再建可能な支援」で寄り添う災害ケースマネジメントが求められているということだと思います。
| 4月22日「『特定利用空港・港湾』で、指定自治体に財政的メリットなしか」 |
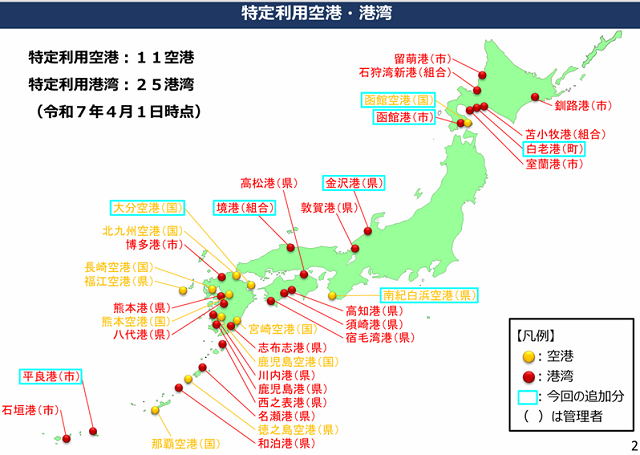 政府は、総合的な防衛体制強化のための公共インフラ整備に関する関係閣僚会議を4月1日に持ち回りで開き、「特定利用空港・港湾」に石川県の金沢港など計8施設の追加を決定し、11空港、25港湾、道路6カ所の整備も確認し、2025年度の関係予算は計968億円(前年度370億円)に上ると発表しています。
政府は、総合的な防衛体制強化のための公共インフラ整備に関する関係閣僚会議を4月1日に持ち回りで開き、「特定利用空港・港湾」に石川県の金沢港など計8施設の追加を決定し、11空港、25港湾、道路6カ所の整備も確認し、2025年度の関係予算は計968億円(前年度370億円)に上ると発表しています。
しかし、昨年私たちの会派「県民の会」で調査に伺った石垣市でも、2025年度当初予算で石垣港整備事業の関連予算は24億8千万円と例年通りの額にとどまり、国交省は八重山毎日新聞社の取材に、特定利用に指定された空港・港湾に対して特別枠の予算配分や事業を前倒しして行うなどの優遇措置は「ない」と回答しています。
石垣市長らは予算枠の新設や既存事業の促進による港湾整備の前倒し、空港の滑走路延伸・エプロン等の整備などが加速することに大きな期待を寄せているが、国交省が新年度当初予算で示した石垣港の整備事業には、既存計画の岸壁や泊地、防波堤整備などの予算は組まれているが、特定利用指定に伴う新たな予算や事業促進策は含まれていないとされています。
同省港湾局担当者は「特定利用になっても、現港湾整備事業の別枠に新たな予算が付くわけではない。あくまで今までの整備事業の予算を引き続きやっていく」と予算が特別に付くことを否定したと4月3日付八重山毎日新聞は報じています。
高知県でも、高知港18億、須崎港8億、宿毛湾港2億と前年度と同様の額で、しかも県の財源としてはこの中の一部とされているだけに、石垣港同様、「特別枠の予算配分や事業を前倒しして行うなどの優遇措置は「ない」」ということになるのではないでしょうか。
先日の業務概要調査で、港湾海岸課に対して、この関連予算について聞いても、28億円のうちの「一部」というだけで、どれだけ県に回ってくるかも分からないし、明確に増額したとも言えない状況でした。
その意味では、「特定利用港湾 高知県版Q&A」の「Q5「特定利用港湾」への指定に同意し、自衛隊艦船に協力すれば何か国からの見返りはあるのですか?」に対して「「特定利用港湾」に指定されると、公共事業の採択などの判断に当たり、自衛隊・海上保安庁のニーズという安全保障上の観点からの重要性が加味され、岸壁・航路などの港湾施設の整備が加速されることが期待されます。」というのは、絵に描いた餅でしかなかった言えます。
いずれにしても、県は県民に対して、丁寧な説明が必要だと言えます。
| 4月20日「異様な米軍機長期駐機の説明を」 |

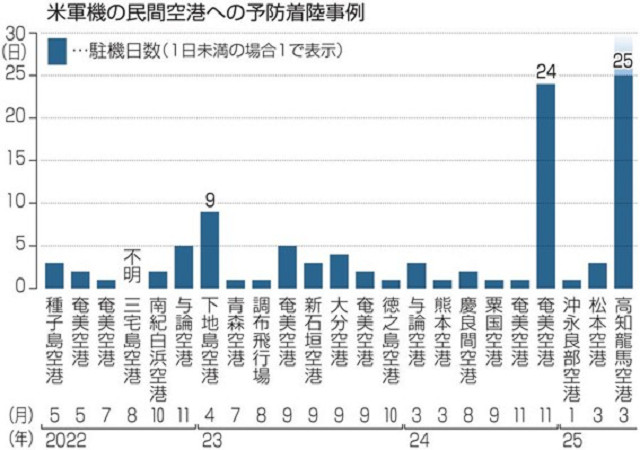

昨日の高知新聞一面では、「米戦闘機、高知空港に25日間 過去3年『国内最長』」との見出しで、理由が明確でないままに、高知龍馬空港に長期駐機を続ける米戦闘機についての記事が掲載されています。
記事によると、防衛省中国四国防衛局は「米軍機が日本の民間空港に予防着陸する例はあるが、25日間もの駐機は異例。過去3年では国内最長とみられる」と言われています。
米軍機の国内民間空港への「予防着陸」は2022~24年度に23件発生し、うち19件が5日以内に離陸しており、最長は24年11月の奄美空港(鹿児島県)の24日で、高知の25日はこれを抜いて過去3年で最長になっています。
着陸以降、空港には岩国基地から輸送機で資材が何度も運び込まれ、エンジンを交換したものの、回転数を上げる前に噴射口から炎が噴き出したりして、未だにエンジンを外し、離陸する気配はないと報じられています。
そのような中で、11日に私も参加した郷土の軍事化に反対する県民連絡会の抗議行動に対して、中谷防衛相が自身のフェイスブックで「市民団体が現場に押しかけ(中略)早期に立ち去るよう求めました。異国で飛行機材トラブルで、命からがら高知空港に着陸し、修理を求め、燃料補給を必要としている人に対して、こんな事を言う人たちは、心ある人とは思えません」と投稿したことも記事にされていました。
私たちは、「警告ランプが点灯したということで、緊急着陸はやむをえない。しかし、何の具体的説明もいっさいないまま長期間とどまるのはおかしいのではないか」とスピーチをしたのであって、中谷氏の「人権や人格を傷つける言葉を喚き散らした」という修正前の見てきたかのような記述は、防衛相の書くべきことなのかと疑問視していますす。
高知新聞も指摘しているように、「命からがら」と記すからには、墜落の危険がある重大な不具合が見つかっていたのかとの質問に対して、緊急着陸ではなく予防着陸だったとの説明を繰り返したとのことだが、予防着陸と「命からがら」ではニュアンスが違うという問いにも明確に答えられていない防衛相の姿勢こそ、問題だと思います。
私たちは、そこの説明を政府なり米軍は明確にせよということを求めているのです。
緊急着陸より危険性の低い「予防着陸」というが、米軍は不具合の内容や今後の見通しを説明せず、民間空港の一部を占有し続けているのであり、過去に米軍機の墜落事故が相次いだ本県では、「墜落につながる重大な故障が原因ではないか」と不安視する声が上がっても当然です。
だからこそ、なぜ着陸したのか、なぜ離陸しないのか、具体的に説明を求める行動は、当たり前の行動ではないのか。
本来なら、中谷防衛相は県民の不安を解消すべく県民・国民の立場に立って米軍と向き合うべきではないのでしょうか。
米軍機の長期駐機は、説明もないまま今日27日目を迎えています。
| 4月19日「 これからの防災教育は学校と地域の連携強化」 |
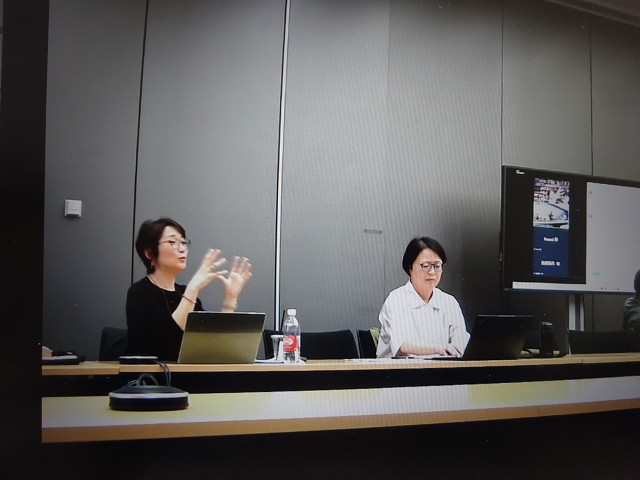
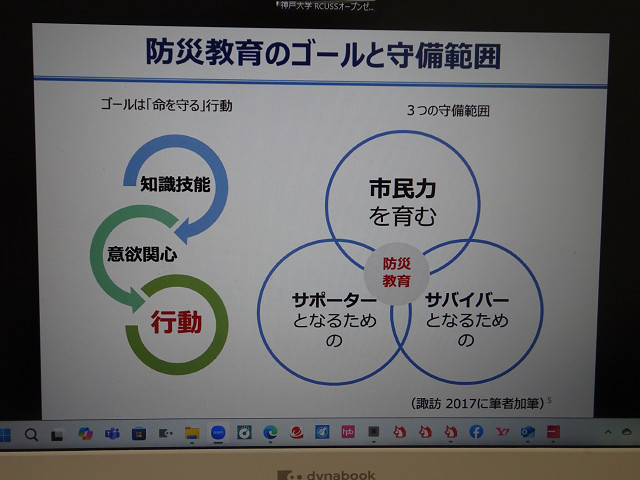
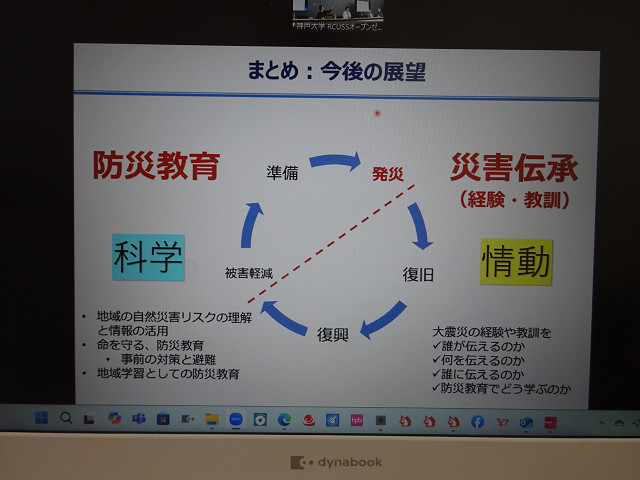

今朝は、第303回神戸大学RCUSSオープンゼミナールで、桜井愛子神戸大学大学院国際協力研究科教授から「阪神・淡路大震災30年の防災教育と今後の展望〜学校防災の視点から〜」と題したお話を聞かせて頂きました。
2016年に当時の昭和小の教頭先生たちと東北大学を訪ねて、桜井先生から石巻市鹿妻小の復興マップ作りなどにもとづいた防災教育のお話を聞かせて頂きましたが、今日のお話の中でも触れられていました。
日本の防災教育は、阪神・淡路大震災以降の被災経験を基に発展し、東日本大震災などの教訓を踏まえて進化してきたとのことで、地震・津波・気象災害に対応するマルチハザード型の防災教育や教員研修の充実が求められ、学校では教育のみならず、施設の耐震化や防災管理を含む包括的な取組が行われてきたことことなどが報告されました。
今後は、防災教育を通じて学校と地域の連携をいかに深化させていくかが重要な課題と言われていましたが、学校と保護者世代を巻き込む地域との防災連携の難しさを改めて考えさせられているだけに、先進事例の集約と横展開への提供がされれば良いのにと思うばかりです。
| 4月18日「常任委員会で業務概要調査」 |

 昨日まで、県議会各常任委員会では、本庁業務概要調査を行っていました。
昨日まで、県議会各常任委員会では、本庁業務概要調査を行っていました。
今年度は、産業振興土木委員会に所属しており、「産業振興推進部」「観光振興スポーツ部」「土木部」の各課から本年度事業についての説明を受け、質疑を行ってきました。
特に、土木部では、都市計画道路はりまや町一宮線が4車線での供用開始に伴い、今後の環境保全のモニタリングや交通量調査を行うことの確認や、特定利用港湾指定に伴う事業費関連予算の検証など注視すべき課題について、質問しましたが、今後も継続して取り組んでいきたいと思います。
なお、各部が所管する課は、次の通りです。
「産業振興推進部」では、産業政策課、産業イノベーション課、地産地消・外商課、統計分析課。
「観光振興スポーツ部」では、観光政策課、国際観光課、地域観光課、スポーツ課、スポーツツーリズム課。
「土木部」では、土木政策課、技術管理課、用地対策課、河川課、防災砂防課、道路課、都市計画課、公園上下水道課、住宅課、建築指導課、建築課、港湾振興課、港湾・海岸課。
| 4月17日「大阪・国際万博の防災対策」 |

 日頃から、災害への備えに関して、的確な指摘をされている室崎益輝先生がFacebookへの3日前の投稿で「大阪万博の防災対策について・・老婆心で疑心暗鬼と思いつつ」と題されて、いくつかの指摘をされています。
日頃から、災害への備えに関して、的確な指摘をされている室崎益輝先生がFacebookへの3日前の投稿で「大阪万博の防災対策について・・老婆心で疑心暗鬼と思いつつ」と題されて、いくつかの指摘をされています。
的を射たものばかりだと思いますので、ご紹介をさせて頂きながら、いろいろと課題がある中でも開幕した大阪・国際万博が安全に運営されることを願うばかりです。
室崎先生は、まず、「明石の歩道橋事故に示されるように、多くの来場者をという思いが先行しすぎて、防災対策がなおざりになってしまって、重大事故を許してはならない」と指摘し、「正しく恐れて正しく備えることが欠かせないので、想定が外れて最悪の事態が起きた時、どうするのかを考えておかなければなならない」と4点について言及されています。
(1)本当に最悪を想定しているのか。
「地球温暖化などの影響もあり、災害の時代だけに、記録になかった破壊力がもたらされる危険性があり、過去最大を前提としていたことが裏目に出た阪神・淡路の誤りを繰り返してはならない。」
そして、「埋立地のリスクについても、仮設建築のリスクについても、大群衆のリスクについても、まだまだ未解明の部分があり、液状化が起きないとか地震で壊れないと言い切れるのかどうか。とくに、メタンガスに象徴されるように、埋立地の防災については未解明な部分が少なくない。」ことを戒めています。
(2)個々のパビリオンの対策は万全か。
「会場全体については防災計画が示されているが、個々の施設やパビリオンについては、その防災計画の内容が示されていない。仮設建築に要求される安全性のチェックは、法規に従ってなされてはいるはずだが」と懸念されるのは、その建設を急ぎすぎた余りの懸念として、当然だと思われます。
「新技術や稀有なデザインには、それなりの新たなリスクが生じるので、耐震や防火面での科学的な検討が必要」との指摘もされています。
(3)群衆避難計画は策定されいるのか。
「地震や台風のリスクよりも、日常事故や群衆避難事故のリスクが大きいと思っています。明石の群衆事故を受けて、直後のワールドカップの会場についても、詳細な防災計画をつくりました。そのような、群衆事故が起きないようにする計画が策定されているのか。個々のパビリオンについても、群衆避難計画の策定は不可避です。」という指摘はそのとおりで、大屋根リング上での混乱などが起きた時の心配など、最も教訓とすべきことだと思います。
(4)来場者とのリスクコミュニケーションは万全か。
「来場者が正しく危険を認識することが欠かせません。恐れすぎてもいけないし、恐れなさ過ぎてもいけません。単に、たばこを吸うなといった注意喚起だけでなく、災害時にどうすればいいのかといった行動提起を、あらかじめ来場者にパンフなどで知らせておく必要がある。」ことを促し、最後に「安全安心を提供する万博であってほしい。イベント防災のモデルにして欲しい。」ことを求められていますが、これらの思いが日本国際博覧会協会に届くことを願うばかりです。
| 4月16日「熊本地震から9年目に考える課題」 |
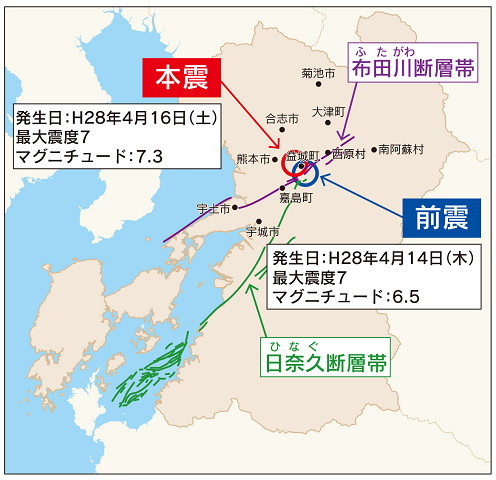
 最大震度7を連続して記録し、災害関連死を含む278人が亡くなった熊本地震は今日16日、本震から9年を迎えます。
最大震度7を連続して記録し、災害関連死を含む278人が亡くなった熊本地震は今日16日、本震から9年を迎えます。
2016年4月14日午後9時26分に前震が、16日午前1時25分に本震が発生し、益城町では観測史上初となる2度の震度7を観測しました。
熊本地震は、前震から一日おいて本震が発生し、最大震度7の地震が2回発生するというこれまでにない地震であったこと。
そして、直接死50人の4.56倍となる228人、亡くなられた方の約8割が災害関連死だつたことも大きな課題として突きつけられた地震でした。
鹿児島大学・井村隆介准教授は、「揺れそのものでは助かった命を、どう次の行動に、本人とまわりが生かしていくのかを突きつけた地震が熊本地震だった」と言われています。
まさに、そのことを教訓として、災害関連死は「人災」だとの思いで、災害関連死を招かないための避難所運営や被災者支援などのあり方の改善が求められてきたが、昨年1月の能登半島地震でも亡くなられた方570人の6割に当たる342人が災害関連死となっています。
23年の熊本日日新聞の調査では、復興住宅の入居者のうち、65歳以上のみの高齢世帯は58%を占め、高齢者の1人暮らしも全体の34%に上っています。
県地域支え合い支援室によると、復興住宅ではこれまで6人の孤立死を把握しているとのことで、地元の民生委員や民間が担っている高齢被災者の見守り活動をどう充実させるかが課題になっているそうです。
改めて、長期に及ぶ継続的な災害ケースマネジメントの取組の重要性が問われる熊本地震からの9年目です。
| 4月14日「発見まで死後8日以上の孤立死が2万1千人」 |
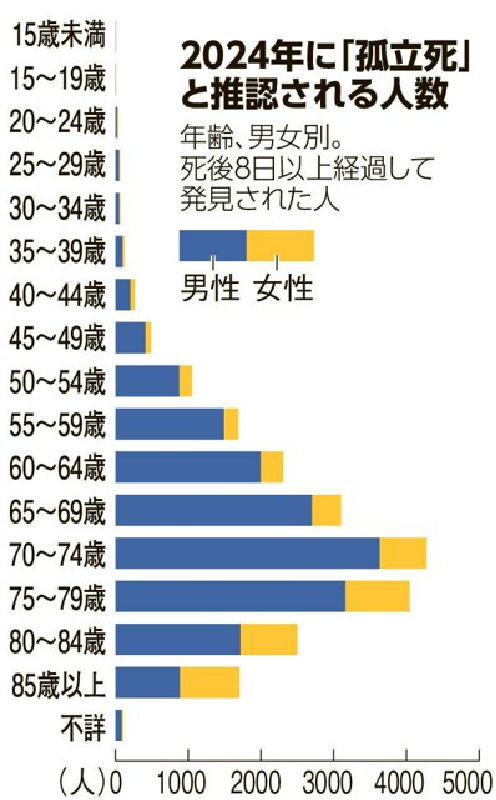 午前7時半から交通安全指導をしていると、高齢の方が杖をついたりしながら開店したばかりの喫茶店に向かう光景を目にします。
午前7時半から交通安全指導をしていると、高齢の方が杖をついたりしながら開店したばかりの喫茶店に向かう光景を目にします。
そこのお店は、モーニングを食べに来られた高齢者で満席になるそうです。
そんな方たちにとっては、そこが語らいの場でもあり、安否確認の場なのかもしれません。
そんなことを思いながら交通安全指導で挨拶をかわす日々の中、4月12日付けの朝日新聞に「死後8日以上、「孤立死」2万1千人」との見出し記事に考えさせられました。
昨年に警察が取り扱った死者20万4184人のうち一人暮らしで自宅で亡くなった人は4割近くの7万6020人で、65歳以上の高齢者が5万8044人と8割近くを占めていたとのことです。
死亡してから数日以内に発見される人が目立ち、4割近くが当日か翌日に発見され、7割超は1週間以内に見つかっている一方で、死後8日以上経過して発見された2万1856人のうち、1カ月以上は6945人、1年以上は253人となっているそうです。
そして、死後8日以上経過したケースでは、男性が8割を占めています。
内閣府の作業部会は、「孤立死」者数を把握するための目安として、死後8日以上経って見つかったケースを扱うことが適当と指摘し、このケースは生前に社会的に孤立していたことが強く推認されるとしています。
2月25日付けのブログで「『独り』の現役、『独り』の老後に寄り添って」と題して、「孤立した現役世代」と「老後ひとり難民」の生きづらさの問題について、取りあげたことがあります。
改めて考えさせられるのは高齢者になってから顕在化する問題ではなく、60代になれば体の不調も増え、介護を受けるかもしれないが、自分には世話をしてくれる相手も、誰かに頼めるだけの経済力もないという潜在化した現役世代が、高齢化した時に「老後ひとり難民」にならないためにも、早くから人や地域やサービスとつながる仕組みの必要性だということです。
| 4月13日「『高知の地震災害史~紡がれた記憶と記録~』に学ぶ」 |


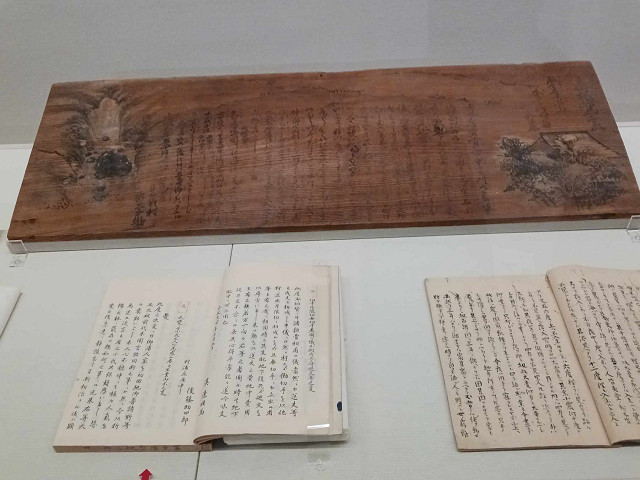
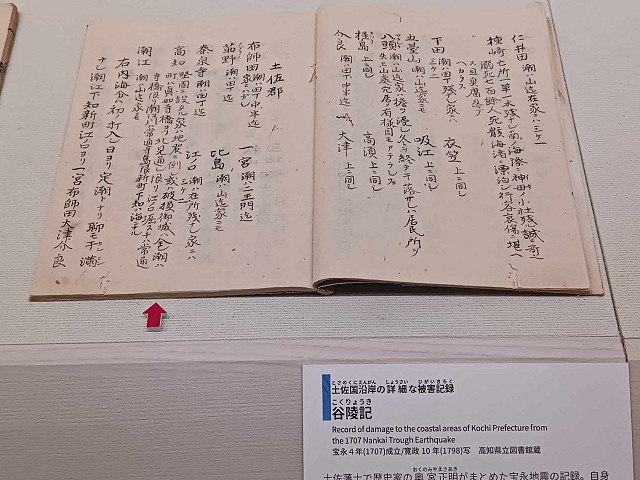
昨日は、午前中のバドミントン大会、郷土の軍事化に反対する連絡会総会に続て、午後からは、高知城博物館で開催中の「高知の地震災害史~紡がれた記憶と記録~」を観た後、展示関連企画で水松啓太(企画担当学芸員)さんの講座「高知の地震災害史」を聴講しました。
「高知の地震災害史~紡がれた記憶と記録~」では、江戸時代以降に高知を襲った南海トラフ地震を中心に取り上げ、古文書・絵画・写真など多様な資料から、これまでの被害や災害への人々の向き合い方を考えさせられるものです。
水松啓太学芸員のお話から、「紡がれた記憶と記録」が、後世に同じような被害に遭ってもらいたくないとの思いで、残し紡がれたものであることがよく分かります。
今でも、南海トラフ人の被害想定とされる揺れ、津波はもちろん、液状化や地盤沈降、長期浸水のことの記述がされています。
災害が起きるたびに問題となるデマに扇動されてはいけないとの戒めなどの絵馬の紹介などもありました。
また、1854年の安政地震以降の余震や台風、そして感染症(コレラ)などの連続複合災害などについても「午春秋自記帖」から紹介いただきました。
非常に、興味深いお話ばかりでしたが、過去の災害史に学ぶことが、必ず繰り返す南海トラフ地震において、災害を減らしていくとこにつながるようになればと思います。
展示品の中には、昭和南海地震体験者への調査結果もあり、そのことに学ぶだけでも大事な備えになることを感じます。
この企画展は、5月25日まで開催されていますので、ぜひご覧頂けたらと思います。
また、5月17日(土)14時~15時半まで、奥村弘氏(神戸大学名誉教授)による記念講演会「地域の記憶を守り伝える ~阪神・淡路大震災30年の経験から~」も開催されます。
| 4月12日「米軍戦闘機の高知空港長期居座りに抗議して」 |



昨日は、「郷土の軍事化に反対する連絡会」が高知空港に緊急着陸してから、県民に情報を隠したまま居座り続ける米海兵隊F35ステルス戦闘機への抗議行動を行いました。
緊急の呼びかけでしたが、40名の皆さんとともに参加し、空港の軍事利用に繋がる情報隠しの長期駐機は許さないとの抗議の声をあげてきました。
もはや18日目となる長期居座りに対して、県平和運動センター谷事務局長は「人命に関わるので緊急着陸は仕方ないが、駐機がこれだけ長期間になると、県民を慣れさせて軍事利用の地ならしをしているのではないかと心配だ。米軍は不具合の原因をきちんと説明してほしい」と訴えました。
県としては、早急に抗議の声を届けるとともに、県民への説明責任を果たさなければなりません。
| 4月10日「大阪・関西万博開幕への不安と混乱」 |


大阪・関西万博は、まだまだ物議を醸すことも多く、安心して4月13日の開幕を迎えることができるのだろうかと思わざるをえません。
3日間で約10万人が参加した「テストラン」(4~6日実施)では次々と課題が浮き彫りになっていますが、関係者は成功を信じて疑わないと言わざるを得ない状況です。
開幕前の運営リハーサルにあたる5日5日は約3万人がテストランに参加し、万博協会は開幕の13日に約15万人分の来場予約があるとし、1日あたり最大22万人超の来場者を見込でおり、その7分の1の来場者数ですら、この混乱ぶりですから、一体どうなるだろうかと不安が増大するばかりです。
このテストラン期間中も海外館の一部では建設作業が続いており、日本国際博覧会協会の説明では、参加国が独自に建てるパビリオン42館のうち、建設が完了したところは3日時点で22館にとどまっているとのことです。
2日目以降は入場ゲート前に長い行列ができ、指定された入場時間から大幅に遅れてしまう来場者も多くいたことから、「並ばない万博」が看板倒れとなることも懸念される事態となっています。
万博の成否を占うチケット販売の損益分岐点は1840万枚で、赤字を逃れるには、前売りチケット約1100万枚を除き、残る700万枚をさばかなければいけないと言われており、「開幕すれば、来場者が伸びるはず」などという楽観ぶりに誰が責任を取るのかと心配せざるをえません。
建設費344億円をかけた「大屋根リング」の下の護岸が約600メートルも浸食されていた問題をはじめ、夢洲は台風で多数のコンテナが吹き飛ばされるほどの被害を受けてきた地域で自然災害に対する脆弱性は克服されていません。
そして、テストラン中に爆発下限界を超えるメタなガスの濃度が検知されたGW工区では、過去にも同様の数値が確認されており、協会は、この一帯で濃度計測を毎日しており、同日朝の計測では安全な数値だったというが、まだまだガス爆発不安は完全に払拭されるという状況にはないことが判明しました。
3日後に開幕を控え、不安要素満載・混乱必至の大阪・国際万博を国民の多くが冷ややかに見つめているのではないでしょうか。
●共同通信(25年3月22、23日実施)行きたいと思う24.6%
●産経新聞・FNN(25年3月22、23日実施)とても行きたい9.2%ある程度行きたい22.0%
●読売新聞(25年3月14~16日実施)行ってみたいと思う31%
●時事通信(25年3月7~10日実施)行きたいと思う22.0%
●毎日新聞(25年2月15、16日実施)行きたいと思う16%
| 4月9日「新しい可能性を広げる学び直しの夜間学級入学式」 |

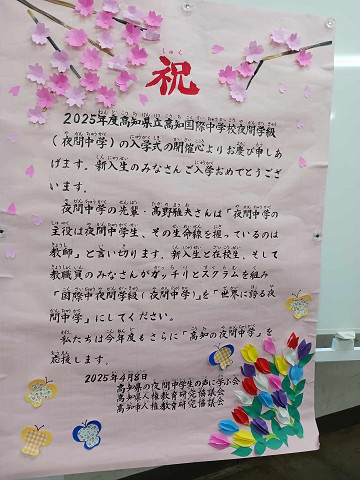
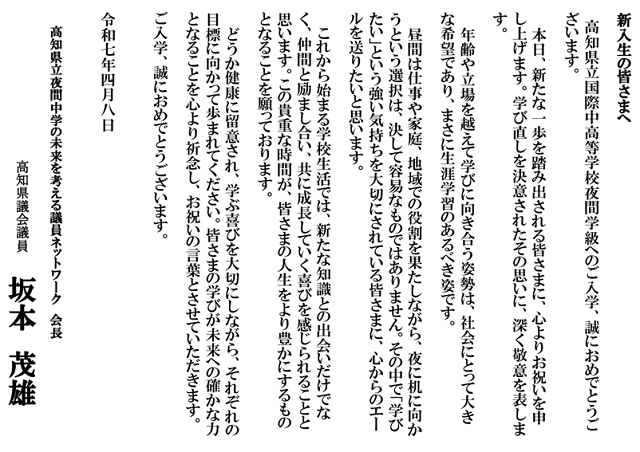
昨夜は、県立国際中学校夜間学級入学式に出席させて頂きました。
昨年発足した「高知県立夜間中学の未来を考える議員ネットワーク」の代表として、3月の卒業式に引き続きの出席となります。
今年度の新入生は7名で、外国籍の生徒さんもいます。
夜間学級の教育理念は「生徒の様々な学びのニーズに応え、生徒が学ぶ喜びを実感しながら、個々の状況に応じた、義務教育の学び直しができる中学校夜間学級」であり、多様な7名の生徒さんの思いが感じられる入学式でした。
生徒さんの代表挨拶では、冒頭に学び直しができる場に立てていること自体に喜びと感謝を表明されました。
そして、「もともとの学校環境に馴染めず、心から楽しく勉強することができなかったが、恥じらいやためらいを捨て、学び直しができることを喜ぶとともに、これまでの支えに感謝し、過去の自分に向き合い、新しい可能性を広げていきたい」という自分の言葉での決意に、感動しました。
そんな生徒さんたちとしっかり向き合ってくれる夜間学級であることを期待するとともに、生徒の皆さんに心からのエールを送らせて頂いた入学式でした。
| 4月8日「地方からジェンダーギャップの解消を」 |

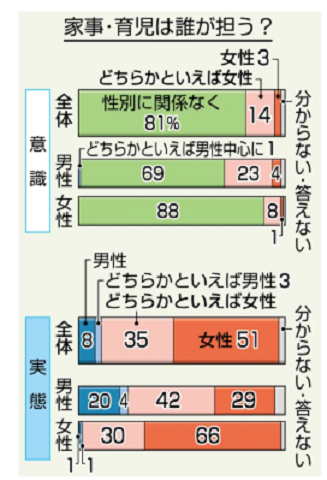 今朝の高知新聞20面に「『性差別で地元出た』8割女性」と「『男は仕事、女は家庭』影響深刻」の見出しが大きく出ていました。
今朝の高知新聞20面に「『性差別で地元出た』8割女性」と「『男は仕事、女は家庭』影響深刻」の見出しが大きく出ていました。
高知新聞など全国21の地方紙や専門紙が昨年12月に実施した合同アンケートで、男尊女卑や家父長的な古い価値観、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業意識が、女性の人生に深刻な影響を与えている実態が浮かんだとの記事です。
「性別による偏見や差別などを理由に地元を出たいと思ったり、実際に出たりしたことがあるか」との問いに、出ようと「思ったことがない」が4349人(65%)を占め、行動には至らなかったものの「思ったことはあった」人は1146人(17%)いたとのことです。
女性(3969人)のうち、「実際に出た」が362人(9%)で「思ったことはあった」が881人(22%)で、今回のアンケートでは性別を「その他」とした人が33人いたが、この中で「実際に出た」と答えたのは11人。出ようと「思ったことはあった」も8人と、それぞれ割合が高くなっており、性的少数者(LGBTQなど)であることを理由に偏見や差別などを受けた可能性があると分析しています。
高知県では回答した139人のうち、「思ったことはあった」が26人、「実際に出た」が10人。計36人のうち、性別は女性が27人、男性が7人、「その他」「答えない」が2人でした。
記事では、介護をどちらが担うかなどの実態を踏まえて性別役割分担意識の根深さなどが書かれていますので、ぜひ記事も読んで頂きたいと思います。
記事では、NPO法人Gender Action Platform理事の大崎麻子さんが、「性別役割分業の「意識」は薄まっているものの、「行動」や「慣行」が変わっていないことが分かる。性別役割分業の押し付けや差別的扱いが、女性が地方を離れる要因の一つになっていることも読み取れるし、地方創生の施策には長い間、ジェンダーの視点が欠けていた。」と指摘し、「性別による職域分離(仕事内容や配置の偏り)や不明確な評価基準の見直しなど、慣習や構造に踏み込んだ施策を行えるかが問われる。もはや「意識を変えよう」と言う次元ではない。」と断じています。
私も、2月定例会では、若い女性が地方から都会へ流出する理由として、地方のジェンダーギャップの大きさと多様な女性の排除が指摘されていることや、前述の大崎麻子さんがアドバイザーをされている兵庫県豊岡市がジェンダー平等施策を推進しているように、全国の人口減少が進む地域では、ジェンダーギャップへの危機感が高まっていることを踏まえ、高知県のジェンダー平等施策のさらなる取り組みへの知事の決意と県内自治体による市町村版のジェンダーギャップ指数の作成について質問しました。
知事からは、「社会的な男女格差、いわゆるジェンダーギャップの解消は、若者や女性に選ばれる高知の実現に向けた重要な要素の1つであると考えており、目指すべき3つの高知県像といった県の基本政策の実現に向けて、さまざまな施策をバランスよく展開する中で、男女間格差の解消にもしっかりと取り組んでいく。なお、市町村におけるジェンダーギャップの現状については、来年度に予定している、こうち男女共同参画プランの改訂作業の過程で、関連する統計指標の状況を整理した上で、示すよう検討していく。」との答弁がありました。
若い女性に、地元に残って頂きたい一つの施策として、ますます地方からのジェンダー平等の施策が求められているのではないかと考えさせられる記事です。
| 4月6日「お花見防災」 |




今日は、絶好のお花見日和。
満開の桜のもと、お花見しながら、赤ちゃん連れのママさん、パパさんにちょこっと防災のお話をさせて頂きました。
企画は、下知消防分団員の西森さんが代表を務める「kidszou」の交流講座です。
4組のママさん、パパさんに、花見をしながら和やかに防災を意識してもらえればとの思いで伝えさせて頂きました。
前半30分が私で、後半30分は四国4県で赤ちゃん連れ親子防災、 子育て支援者向け講座を行われている防災士でベビーウェアリングコンシェルジュをされている松原香奈美さんでした。
松原さんは、私などと違って、優しく分かりやすくママさんパパさんの視点で語りかけられており、私も随分と学ばせて頂きました。
会場の交通公園は、ご家族連れの花見客で一杯で、隣のグループの方から「坂本さん、こんなところでも防災の話をされているんですか」と声をかけられたりもしました。
終わるやいなや、地元町内会のお花見にかけつけましたが、青柳公園の桜も一番の見ごろとなり、町内会の70人強の皆さんが参加して大いに賑わいました。
今回は、下知地区減災連絡会の二葉町以外の町内会や防災会からも参加もありました。
やはり、皆さん口にされていたのは、「こんな交流が絶対災害の時にも役に立つ」ということでした。
テント組立なども防災備品のチェックになりますが、私は、午前の部があり、準備がお手伝いできませんでしたので、片付けだけでも手伝わせて頂きました。
皆さん、結構出来上がっていたのですが、終了後30分で全て片付けがすみました。
「土手の花見」ではありませんが、お花見は地域防災力の向上に繋がることを実感されている方が、多いです。
| 4月4日「都市計画道路「はりまや町一宮線」4車線で開通するも」 |

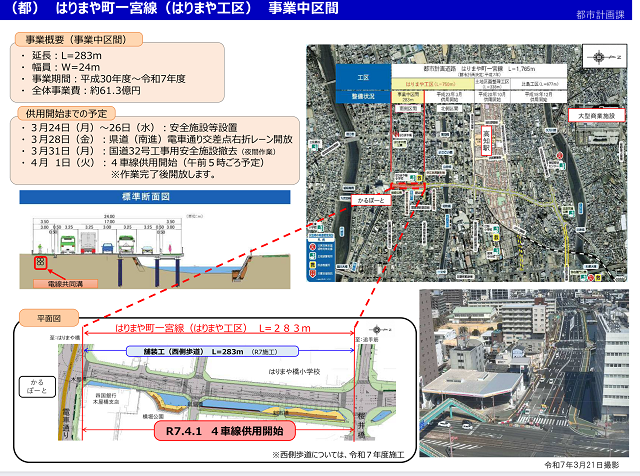

希少生物の保存や歴史的景観の保全を巡り、2011~20年に工事が中断していた都市計画道路「はりまや町一宮線」(はりまや工区)が、4月1日から4車線で供用開始しました。
しかし、年度初めの4月1日の通勤時間というのに、それほどの交通量が見られないのも供用開始が知られていなかったのか、想定交通量が計画時よりも減少しているということなのか、いろいろと考えてしまう閑散とした光景でした。
隣接した「横堀公園」には、界隈の歴史的な説明や生息している希少動植物の説明看板が掲示されています。
しかし、昨年の12月2日付けの高知新聞記事がによると、隣接する新堀川にすむシオマネキやトビハゼなどの希少生物は保存されたものの、アカメの稚魚などのすみかだった水草のコアマモは移植により消滅し、回復していないことが報じられていました。
今後の検証では、看板倒れになるかもしれないと思わざるをえません。
2006年9月定例会で、「4車線化ありきではなく自然環境との共生や文化的、歴史的意義を持つ史跡と共存する、中心街の貴重な水辺空間を生かしたにぎわいのまちづくりへと方向転換する」ことの可能性などについて質問して以来、8回にわたって質問してきました。
その間には、自然との共生だけでなく、観光面、人口減少下の交通量、交通安全、コストの視点から議論してきましたが、県の事業費は検討段階から1.5倍以上の61億3千万円に膨らんできました。
そして、今日の開通を契機に、今後この都市計画道路の功罪について検証しなければと思っています。
| 4月3日「フジテレビ問題で考える『ビジネスと人権』」 |
 フジテレビの一連の問題をめぐり、第三者委員会が会社全体の人権意識の低さと企業統治の不全を問う、踏み込んだ内容の調査報告書を公表しました。
フジテレビの一連の問題をめぐり、第三者委員会が会社全体の人権意識の低さと企業統治の不全を問う、踏み込んだ内容の調査報告書を公表しました。
報告書は、フジのアナウンサーだった女性が元タレントの中居正広から性暴力を受けたこと、被害は「業務の延長線上」のものと認定し、「女性への二次加害」も指摘しています。
さらに、報告書は、全社的なハラスメントの蔓延も指摘される中で、報告書の求める人権意識の改善に貢献する能力をもった役員に刷新されたといえるのでしょうか。
社員らの人権を犠牲にした上でビジネスを続けることは許されるものではなく、取引先や社会が何に失望しているのか、理解と反省なしには信頼回復は困難だし、人権意識が低く、ハラスメントが容認されやすい企業風土を作り出している他の組織も戒めとしてしっかり受け止めるべきではないでしょうか。
今、「ビジネスと人権」の行動計画の必要性が企業に求められていますが、国際人権法学会理事の伊藤和子弁護士が新著の「ビジネスと人権―人を大切にしない社会を変える」の「はじめに」の最後で「企業が人を人とも思わないやり方で人を搾取し蹂躙し差別する社会は、誰にとっても危険な社会であり、次のターゲットは自分かもしれにい。そんな生きにくい社会を変える力を私たちは持っている。」と結ばれています。
私たちの力で、人権が尊重されないビジネスや組織、そしてそれを許すような社会は、変えていかなければなりません。
| 4月2日「龍馬空港への米軍機着陸を二度と繰り返すな」 |
 高知龍馬空港に米軍岩国基地所属のF35ステルス戦闘機が緊急着陸してから8日目を迎えた昨日も、空港で整備が続けられたとのことです。
高知龍馬空港に米軍岩国基地所属のF35ステルス戦闘機が緊急着陸してから8日目を迎えた昨日も、空港で整備が続けられたとのことです。
同日午前、テントと車が動かされ、米軍関係者が前日に取り付けたエンジンをかけて機体を点検する姿が見られたとのことだが、防衛省中国四国防衛局が米軍に問い合わせているとのことだが、何の回答もないとのことです。
本来ならすぐ飛び立ちたいのだろうが、これだけ駐機しているのは、その間に龍馬空港の情報を得ようとしているのか、余程重大なトラブルだったのかと危惧されます。
そんな中で、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」は昨日県に対して真相究明と再発防止の働きかけを求める申し入れ書を提出しました。
申し入れ書は、下記のような内容ですが、他県の空港でも米軍機の緊急着陸が続いていることから、「『訓練中の警告灯』を理由に、全国での着陸訓練を試みているのではないか」と警戒し、県に「真相究明について米軍と防衛省に説明を行うよう求め、二度とないよう強く申し入れること」を求めたものです。
出席したメンバーによると、対応した江渕危機管理部長は「中国四国防衛局を通じて原因などの情報を求めている。必要に応じて県民にも知らせたい」などと答えたようだが、一週間前に私が照会した時から、何ら変わっていないことに危機感を覚えます。
| 2025年4月1日 高知県知事 濵田省司 様 郷土の軍事化に反対する高知県連絡会 米軍機の高知龍馬空港「緊急着陸」の真相究明及び再発防止の働きかけを求める申し入れ書 県民福祉の向上に向けた日ごろからのご努力に敬意を表します。 さて、3月26日の新聞報道によりますと3月25日2時ごろ、米軍岩国基地所属のF35ステルス戦闘機が高知龍馬空港に緊急着陸、滑走路は一時閉鎖されたものの約10分後に解除されたようですが、その影響で民間航空機の出発が5分ほど遅れたことが報じられています。そして、防衛省中四国防衛局が飛行目的や緊急着陸の原因について米軍から「保安上の理由から運用の詳細は言及しないとの回答があったとのコメントも記事に書かれてありました。そして、4月1日時点においてもまだ高知龍馬空港にとどまっている状況です。 このような米軍機の高知龍馬空港への緊急着陸はおそらく初めてのことではないかと思われますが、万一県内の民家等に墜落していれば大惨事を招いたかもしれません。なぜ、自衛隊の基地や米軍の施設ではなく、高知龍馬空港だったのか、疑問が生じています。オスプレイのように何か構造的な機体のトラブルということであれば、きちんと事故の原因を究明し、二度とこのようなことが起こらないようにすべきですし、1994年の早明浦ダム湖に墜落した米軍機の事故を思い起こすものです。 もう一つの懸念があります。本年2月にも岩国基地のF35戦闘機が松山空港に緊急着陸しており、同じF35戦闘が高知龍馬空港に緊急着陸した3月25日には、長野松本空港に沖縄普天間基地所属のオスプレイが緊急着陸しています。まさに「訓練中の警告灯」を理由に、米軍は全国の空港での着陸訓練を試みているのではないかとの疑念を生じさせるものです。 私たちの反対にもかかわらず、高知県は昨年3月、高知県管理の3港について「特定利用港湾」の指定に同意しています。その際、米軍の使用は想定していないとのことでしたが、自衛隊と米軍は、民間空港・港湾・公道での訓練演習を積み重ね、民間空港での戦闘機による訓練など訓練演習内容は実戦さながらでエスカレートしており規模も拡大して利用する空港・港湾も増えています。指定していてもしていなくても全国の空港・港湾を使う意図があるのではないか、さらに日本全国の空港・港湾の軍事利用に向けた既成事実づくり・地ならしであり、民間空港で戦闘機や輸送機が離着陸する姿を繰り返し見せて、国民・県民に日常の光景として思わせていく狙いがあるのではないかと思わざるを得ません。 したがって、今回の緊急着陸等に関して県民の命を守る立場から次のことを申し入れますので、真摯に対応されますようお願いします。 記 1 今回の「緊急着陸」について、その真相究明について米軍及び防衛省にきちんと説明等を行うよう求めるとともに、今後二度とこのようなことのないよう高知県として強く申し入れること。 2 米軍及び防衛省からの回答について、県民にていねいに情報公開及び説明を行うこと。 |
| 4月1日「南トラ被害想定を行動につなげて」 |
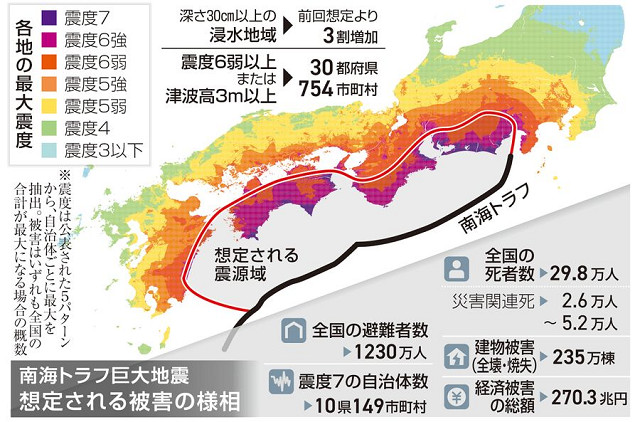
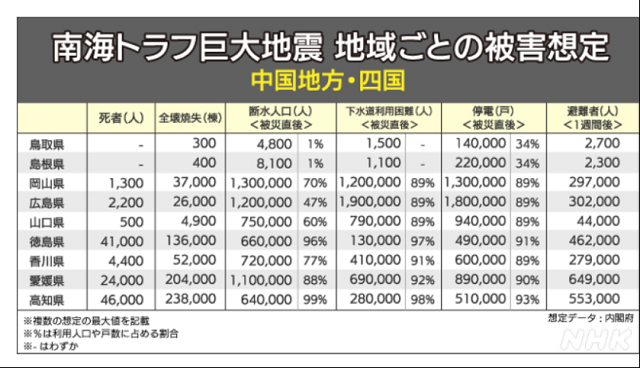
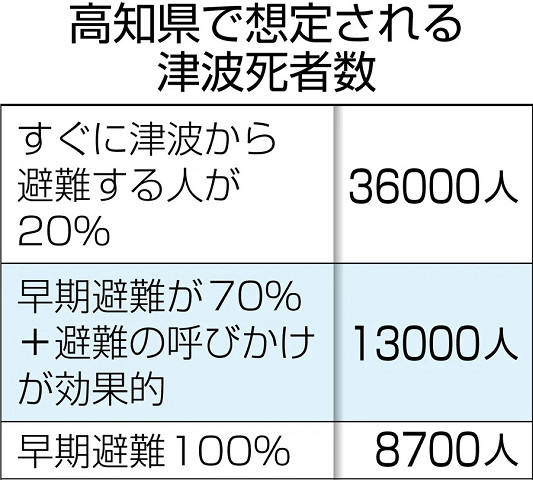
「南海トラフ巨大地震」について、国の有識者会議は31日、最悪の場合は直接死が29万80000人、全壊・焼失建物が235万棟に上るとする新たな被害想定を公表しました。
2012年の前回想定では、それぞれ32万3000人、238万6000棟とされており、政府は23年度末までに死者を8割、全壊・焼失建物を5割減少させる目標を立てていたが、いずれも1割にも満たない減少にとどまり、遠く及びませんでした。
さらに、経済被害は、間接的な影響も含めると292兆円と物価高騰も反映して前回想定より72兆円増え、国家予算の2.5倍に達することとなっています。
また、高知県内では最大4万6千人が死亡するとの新たな被害想定となっており、2012年の前回推計は4万9千人で、防災施設整備が進んだにもかかわらず、死者は約6%、3千人の減少にとどまりました。
地震後すぐ避難する人の割合を20%と設定しており、これが70%に上がると死者は2万3千人に半減するとし、死因の多くを占める津波から早期に避難する重要性があらためて示されることとなりました。
新想定では、直接死とは別に、避難生活に伴う体調悪化などで生じる「震災関連死」を初めて試算し、全国で2万6千~5万2千人としているが、都道府県別は出しておらず、本県でも県内の実情をより精密に当てはめた県版の被害想定を25年度内にまとめることで、「震災関連死」についても試算することとされています。
2月3日に、「県地震被害想定検討委員会」が開催され、今回の国の有識者会議のメンバーでもある福和伸夫あいち・なごや強靱化共創センターセンター長・名古屋大学名誉教授が会長となり、検討が始まりました。
今回の検討では、12年前に出された想定以降、住宅耐震化、津波避難タワーと避難路、堤防の整備など一定の対策の効果を踏まえて、新たな想定がされるが、逆にこの間前回想定には踏まえられていなかった課題も「被害想定の実施項目」として踏まえられることになります。
委員からも出されていた災害関連死や長周期地震動、複合災害など以外にも津波火災などをはじめ14項目が新たに想定項目として追加されています。
矢守委員の「この想定で諦めるのではなく、行動計画に結びつけ、県民の行動に結びつけて欲しい」との意見とも通ずるが、福和委員長が指摘されていた「これまでは自治体が頑張るための被害予測になっていた。県民の行動を促すようなものに変えないといけない」という指摘も重要な視点であると思いました。
2022年に、74名の児童が犠牲となった石巻市立大川小学校で次女を亡くされた語り部の佐藤敏郎先生のお話を聞く機会がありました。
「多くの皆さんが、裏山があったのにと言われるが、山があるだけでは命を救えない。命を救うのは山ではなく、山に登るという判断と行動です。その行動に結びつけるのが防災であり、それが未来を変えるのです。」と佐藤先生は言われました。
下知地区に「津波避難ビル」や避難所があるから、命が助かるのではなく、そこに皆で声かけあって避難するという行動につなげなければならないし、その判断ができる日常のつながりと訓練が求められています。
その避難意識が100%行動につなげても、津波死者想定は減少はするが8700人が死者想定として残るなら、一人も亡くさないためにどうするのかは、取り組み続けなければなりません。
2万6千~5万2千人と想定される「震災関連死」など人災と言われるものは、徹底的に削減できるような対策が講じられなければならないということを改めて考えさせられる想定の公表です。
| 3月31日「児童虐待への支援が届くように」 |
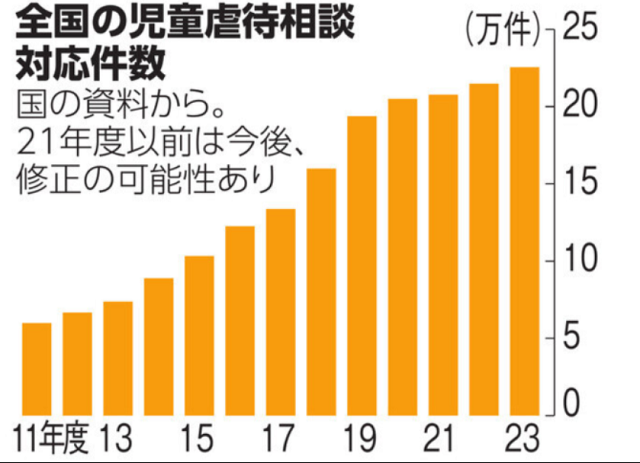 全国の児童相談所が2023年度に虐待相談として対応した件数が22万5509件に上り、前年度から1万件余り増え、33年連続で最多を更新したことが、厚生労働省とこども家庭庁のまとめで分かったことが26日報道されました。
全国の児童相談所が2023年度に虐待相談として対応した件数が22万5509件に上り、前年度から1万件余り増え、33年連続で最多を更新したことが、厚生労働省とこども家庭庁のまとめで分かったことが26日報道されました。
高知県でも448件と、高止まりの状況が続いています。
「生きづらさを抱えた子どもの背後には生きづらさを抱えた親がいることもある。家庭全体を支えていく視点が大切だ」と言われる中、支援が必要な子どもと親を支える児童相談所の重要性は高まる一方ですが、現場の体制は追いついていないのが現状です。
虐待通告があった場合、原則48時間以内に安全確認するというルールの徹底を政府は児相に求めている中で、対応件数の増加によって業務負荷が増しており、児童福祉司らの疲弊が進んでいるのも実態です。
こども家庭庁によると、23年度は全国で633人を採用したが、退職者も270人おり、うち8割以上は定年以外の理由で「心身の不調」「業務内容・量への悩みや不満」が目立っているとのことです。
児童福祉司らが深刻な事例に集中できるよう、役割分担を進めることも必要ではないかと言われ、市区町村や民間団体との連携を進め、児相の負担軽減に努めることが重要だとも言われています。
子どもと親を支える要となるのが、児童相談所に勤務する児童福祉司で、全国に6482人で、政府の増員計画によって2017年度と比べて倍増している一方、勤務経験3年未満が約5割を占める経験の浅い若手が増えており、職場だけで若手を育てるのは簡単でなく、自治体は人材育成に試行錯誤しているとのことです。
政府は、昨年4月に施行された改正児童福祉法に基づき、母子保健と児童福祉に関する相談支援を一体運営する「こども家庭センター」を26年度までに全国で整備する目標を掲げていますが、設置状況は昨年5月時点で全国の市区町村の約5割、県内では約2割にとどまっています。
県では、「各市町内での関係者が協働したこども家庭センター運営強化とこども家庭センター設置促進」「児童虐待防止対策の推進(予期せぬ妊娠や困難を抱える妊産婦等に対する相談支援体制の強化)」を図ることとしていますが、虐待を減らすには早期発見も大事ですが、虐待予防をと言ってきた中で、妊娠期から苦しむ親に相談や支援が確実に届くような寄り添いの体制整備が急がれているのではないでしょうか。
| 3月30日「ミャンマーでの地震被害深刻」 |

 ミャンマー中部を震源に28日発生したマグニチュード7.7の地震で、死者が1644人、負傷者が3408人、139人が行方不明になつているとのことです。
ミャンマー中部を震源に28日発生したマグニチュード7.7の地震で、死者が1644人、負傷者が3408人、139人が行方不明になつているとのことです。
在ミャンマー日本大使館によると、第2の都市マンダレー在住の日本人2人がけがをしたが、命に別条はないとのことですが、在留届ベースでミャンマー国内には約2千人の日本人がおり、そのうち十数人がマンダレーと近郊に在住しており、安否確認が進められています。
今回の地震は、国土を縦断する長大な断層の一部分が、200キロ以上破壊されたことで起きたもので、現地は200年近く地震が起きていなかった「空白域」にあたり、専門家は「起こりうるところで起こってしまった」と指摘されています。
さらに、震源近くのマンダレーやザガインのほか、マンダレーから南に約200キロ離れた首都ネピドーでも、建造物の倒壊や道路の陥没、橋の崩落といった深刻な被害が報告されており、震源から約1千キロ離れた隣国タイの首都バンコクでも、建設中の高層ビルが倒壊しています。
気象庁や専門家は、バンコクで被害が生じた要因として、「長周期地震動」の可能性を指摘しており、東京大地震研究所の纐纈一起・名誉教授(応用地震学)は「震源から数百キロ以上も離れた場所での被害に驚くかもしれないが、長周期地震動が被害を及ぼす範囲としては十分あり得る距離だ」と説明されています。
まさに、国内でも2011年に発生した東日本大震災で、長周期地震動によって震源から700キロ以上離れた大阪市にある高層の咲洲庁舎が左右に大きく揺れ、被害が生じたケースなどがを思い出さざるをえません。
ミャンマーは、2021年以降の軍事政権ではあるが、国軍最高司令官は国際社会に支援を要請したとのことで、各国から支援表明がされており、高知県が支援協定を締結し、下知地区でも連携して頂いているピースウィンズジャパンが運営する災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」は、地震発生直後から情報収集を開始、緊急支援を決定しています。
そのような中で、日本政府が未だ支援表明をしていないことについて危惧される中、ミャンマーやタイでの被害者救援が急がれます。
| 3月28日「消防県一広域化への懸念の払拭へ」 |
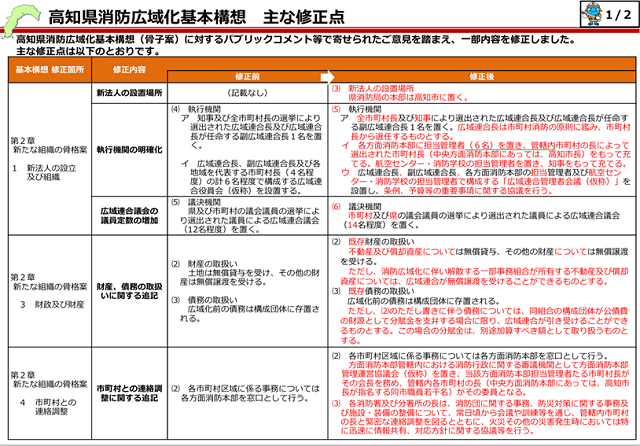
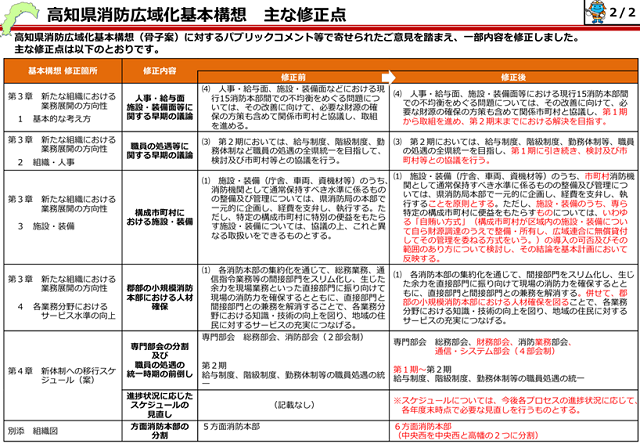
2月定例会でも、私をはじめ多くの議員が質問をした消防の県一広域化について、骨子案に対して届けられた市町村や消防の関係者から提出されたもので、全体で26通およそ138件の意見がありました。
県では、これらについて整理し、特に消防職員自身の処遇に関わる内容が多い中で、議論のスケジュールなどに反映した高知県消防広域化基本構想を策定し、意見に対する「Q&A」もとりまとめて、公表されました。
Q&Aで取りあげられている項目の主なものとして「なぜ消防広域化で、一気に県一が必要なのでしょうか?」「県一消防広域化で、消防署の統廃合が進む可能性はありますか?」「消防広域化によって、消防団と消防署の関係はどうなりますか?」「消防広域化に対して国や県からの財政支援はあるのでしょうか?」「県一消防広域化によって、各市町村の財政負担は増えるのでしょうか?」「消防広域化後、消防職員の充足率は向上するのでしょうか?」「消防広域化後、消防職員の採用はどのように行われますか?」「消防職員の給与等の処遇については、早めに検討すべきではないでしょうか?」「消防広域化後、消防職員の異動はどのように行われますか?」「通信指令業務の集約化を前倒しすべきではないでしょうか?集約化までの間、現消防本部の消防指令システムの更新はどのように取り扱えばよいのでしょうか?」「消防広域化は、スケジュールありきで進めるのでしょうか?」などなどがありますが、それらに対する現時点での考え方が示されています。
いずれにしても、令和7年度から始まる「消防広域化あり方検討会」での議論によって煮詰まるものもあり、注視していく必要がありますが、地域消防力の向上につながるとともに、担うべき職員の処遇確保によって、モチベーションが維持されなければならないと思います。
なお、県が公表した資料はこちらからご覧いただけます。
また、私が議会で質問したやりとりは、こちらからご覧いただけます。
| 3月27日「米軍機『予防的着陸』も訓練か」 |


25日午後2時ごろ、高知龍馬空港に岩国基地の米軍戦闘機F35ステルス戦闘機が緊急着陸し、県民の間に不安が生じています。
私も、昨日県の危機管理部に問い合わせたものの、防衛省中国四国防衛局や米軍のプレスリリース以上の情報はなく、すでに報道されているように、飛行中に機内の警告灯が出たため、予防的に高知空港に着陸したものであるということ以外には、情報がありませんでした。
中国四国防衛局は飛行目的や緊急着陸の原因について「米軍から『保安上の理由から運用の詳細は言及しない』と回答があった」としており、結局詳しい理由は明らかにされることはないでしょう。
2月にも岩国基地のF35が松山空港に緊急着陸しており、同じ25日には、長野松本空港に沖縄普天間基地所属のオスプレイが緊急着陸しています。
その際にも、オスプレイについて、アメリカ軍担当者は「訓練中に機内の警告灯が出たため、安全に着陸させた」としています。
まさに、「訓練中の警告灯」を理由に、全国の空港での着陸訓練を試みているのではないかと推測してしまいます。
それでなくても、特定利用空港・港湾が指定されている中で、空港・港湾を平素からの訓練にも使用するという意図の具体化を、指定されていない民間施設でも実践しようとしているのではないでしょうか。
自衛隊と米軍は、民間空港・港湾・公道での訓練演習を積み重ね、民間空港での戦闘機による訓練など訓練演習内容はエスカレートしており、規模も拡大して利用する空港・港湾も増えています。
それらは、日本全国の空港・港湾の軍事利用に向けた既成事実づくり・地ならしであり、民間空港で戦闘機や輸送機が離着陸する姿を繰り返し見せて、国民の目に日常の光景化していく狙いがあるのではないかと思わざるをえない、出来事が連続しています。
このような動きを「当たり前化」させないように、注視・警戒する取組を強化していきましよう。
| 3月26日「旧統一教会に解散命令出るも闘いは続く」 |

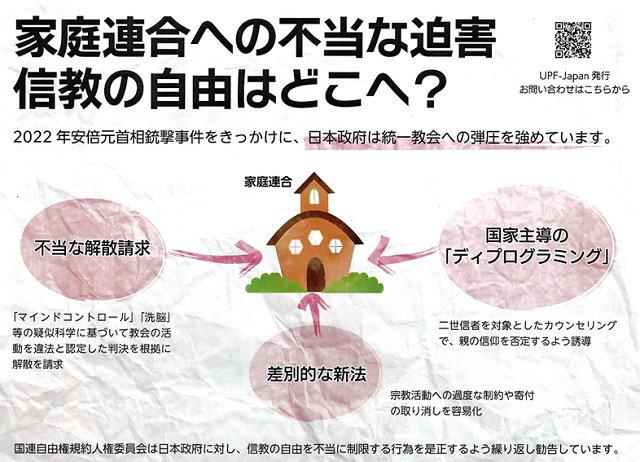 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の請求を受け、昨日、東京地裁が教団への解散命令を決定しました。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の請求を受け、昨日、東京地裁が教団への解散命令を決定しました。
教団は不服として即時抗告を東京高裁に行っており、解散命令の是非は、最高裁まで争えることから、まだまだ時間がかかると思われます。
しかし、今回の解散命令で、世間が「これで問題が解決して一件落着」と受け止めてしまうことが危惧されています。
これまでに、高知市内でも、教団側の宣伝ビラが各種配布されているが、そこで強調するのは家庭連合に対する日本政府の解散命令請求は国連人権規約違反であり、自らの正当性を訴えたものばかりです。
東京地裁は、信教の自由も踏まえた上で、献金被害が甚大で看過できず、「やむを得ない法的措置」と判断したものです。
このことによって、教団は物理的な活動はしにくく、不便になることは否めませんが、信仰の自由自体は侵害されていないのではないかとの声もあります。
そして、このことによって政治家が、社会問題化した団体との緊密な関係を維持し、両者の関係性によって、民意がゆがめられてきた可能性があったことから、自民党が教団との関係を断つことを表明せざるを得ないところまできました。
しかし、過去の検証をせず、本当に関係が切れるのか、あいまいなままであり、本来は、第三者委員会で調べたり、国政調査権を使ったりして、真の断絶を検証しなければならないことも求められています。
高知県議会においても、今回議長に就任した自民党三石議員は、過去に自転車イベント「ピースロード」出発式挨拶、「日韓トンネル」試掘現場(佐賀県)見学、オープン礼拝参加、日韓トンネル推進高知県民会議行事出席、同会議議長就任などこれまで旧統一協会との関係性が幾度も指摘されてきているが、改めて旧統一協会との関係性については、自らの説明責任が求められのではないかとの声も上がっています。
元妻が教団に入信し、多額の献金などで家庭が崩壊したと訴え、「旧統一教会被害者と支援者の会・高知」を設立し、被害者の相談に乗ってこられた南国市の橋田達夫さんも「ここからがスタート。教団は非を認めて、被害者救済を進めるべきだ」と言われています。
被害者をはじめ社会全体の不信感が消えない限り、この闘いは継続していかなければなりません。
| 3月25日「頑なな自民党の選択的夫婦別姓否定」 |



昨日、高知県議会2月定例会は閉会しました。
一般会計の総額で4741億円余りの県の新年度の当初予算案をはじめ、追加提出した西森裕哉子ども・福祉政策部長を副知事に、今城純子教育次長を教育長に選任する人事議案など執行部提出の計76件を全会一致、または賛成多数で可決、同意、承認しました。
議員提案の意見書では、共産党と県民の会が提出した「選択的夫婦別姓の早期導入を求める意見書」や公明党が提出した「選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書」に対して、自民党や一燈立志の会の一部、自由の風の議員が反対し、いずれも賛成少数で否決されました。
上の左端の写真のような採決結果となるのは、極めて稀な状況と言えます。
自民党は、「制度を導入すれば、家族の一体感や親子の絆に悪影響を与える恐れがある。メリットとデメリットを比較した場合、デメリットがあまりにも大きい」などと、選択的夫婦別姓制度の導入検討さえも認めない姿勢に終始しており、自民党国会議員の少数ながらでも選択的夫婦別姓を支持するものがいる傾向とは異にしています。
諦めることなく、地方からもしっかりと声を上げ続けたいと思います。
また、自民党会派の都合で一年ごとに正副議長が辞職し、後任人事を巡って、正副議長選挙が行われました。
今の自民党会派による期数たらい回しの正副議長に対して、民主的運営さらには今議論されている議員定数や選挙区の見直しにも消極的な自民党会派の独占に風穴を開けるため、県民の会と共産党会派に推されて議長選挙に挑みましたが、両会派のみの10票に止まりました。
今後は、自民党会派の議会運営に注視していきたいと思います。
なお、私は2025年度は、産業振興土木委員会に属することとなりますので、本県の産業振興や災害対策のハード整備などに県民の声を反映すべく頑張ってまいります。
| 3月22日「選択的夫婦別姓に関する意思表示」 |
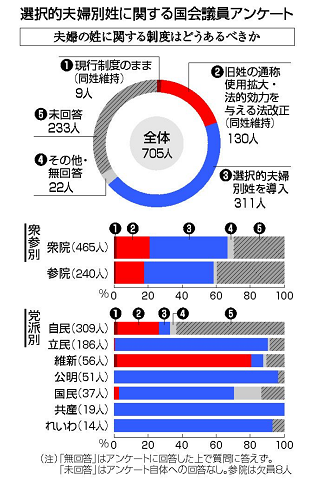
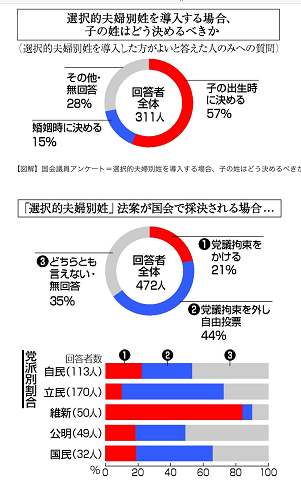 24日の閉会日には、意見書案が7件提出されますが、そのうち4件が常任委員会で不一致となり再提出されるものです。
24日の閉会日には、意見書案が7件提出されますが、そのうち4件が常任委員会で不一致となり再提出されるものです。
そのうちの2件が選択的夫婦別姓に関するもので、県民の会と共産党会派で提出する「選択的夫婦別姓の早期導入を求める意見書」と公明党が提出する「選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書(案)」となっており、閉会日本会議で採決されることとなります。
常任委員会での議論では、自民党はいずれにも反対するとの意思を示していました。
そのような姿勢が、まさに3月7日に公表された時事通信社の全国会議員(705人)を対象に選択的夫婦別姓制度に関するアンケートと傾向を一にしていると思わざるをえません。
全体の44%(311人)が同制度を「導入した方がよい」と回答し、「旧姓の通称使用拡大または旧姓に法的効力を与える法改正をした方がよい」18%(130人)と「現行制度のままでよい」1%(9人)を合わせた同姓維持派を大きく上回っています。
全体の33%に当たる233人は未回答で、このうち自民党議員が約8割を占めており、自民党の回答者の72%が同姓維持を支持し、選択的別姓は18%でした。
選択的別姓を支持する人の理由としては、「時代の変化や価値観の多様化に合わせ選択肢を増やす」が85%で最も多く、「姓の変更で不便・不利益がある」(75%)や「女性が姓を変える場合が多く不平等」(59%)が続いています。
また、夫婦同姓維持の理由は、「旧姓使用拡大で十分対応できる」が89%で最多で、「日本社会に定着した制度だから」(41%)や「選択的別姓を認めると子どもに好ましくない影響を与える」(40%)などを引き離しています。
法案採決時の党議拘束を巡っては「外して自由投票」(44%)が、「かけた方がよい」(21%)を上回っているが、県議会での意見書採決を巡って、自民党が会派拘束をかけるかどうか注目してみたいものです。
| 3月20日「夜間中学で取り戻した文字で『35年目のラブレター』」 |

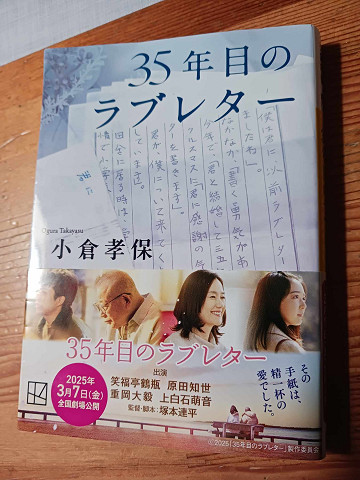 昨日、映画「35年目のラブレター」を鑑賞してきました。
昨日、映画「35年目のラブレター」を鑑賞してきました。
予想以上に、ほぼ最初から涙腺緩みっぱなしでした。
笑福亭鶴瓶さんと原田知世さんが夫婦役を演じ、最愛の妻にラブレターを書くため還暦を過ぎて退職してから、文字を取り戻しに夜間中学に通い、妻に対する感謝も込めたラブレターを書くのに、出会ってから36年5か月かかりました。
その夫を支え続けた妻が先だった後に、妻が生前書いていたラブレターを目にし、夫は改めて妻の返事をもらうことになりました。
戦時中に生まれて十分な教育をうけることができず、文字の読み書きができない65歳の西畑保さんと、いつも彼のそばにいる最愛の妻・皎子、生きづらくても支えあえる人がそばにいてくれる、学びあう仲間がそばにいてくれることの素晴らしさにのめりこんだ2時間でした。
映画館には、鶴瓶さんの若かりし頃を演じた男性アイドルグループ・WESTの重岡大毅さん推しの女子学生がたくさんいて、観客の8割ぐらいが若者だっことに驚かされました。
この若者たちが良質の映画を鑑賞して、涙してくれることは次につながるのだろうなと勝手に思いながら、パートナーと映画館を後にしました。
帰ってから、パートナーから原作を借りましたので、またゆっくり読んでみようと思います。
| 3月19日「精神障がい者への医療費助成の検討は実態と向き合って」 |
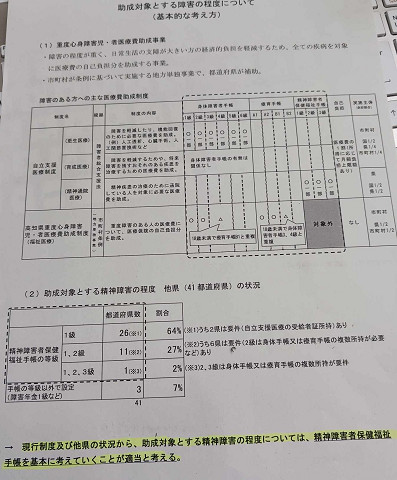 17日には、県内の精神障がい者に対する医療費助成の拡大を検討する県の関係者会議が開かれ、精神保健福祉手帳の等級(1~3級)を基準に助成対象を決める方向性が示されました。
17日には、県内の精神障がい者に対する医療費助成の拡大を検討する県の関係者会議が開かれ、精神保健福祉手帳の等級(1~3級)を基準に助成対象を決める方向性が示されました。
ただ、関係者からは「患者の状態は日々、波があり、等級が参考にならないことがある」と判断の難しさや慎重な運用を求める声が相次ぎました。
私も、2月定例会代表質問で、「重度障害の方を対象とする制度を前提にするあまり、身体障がいや知的障がいとの均衡にとらわれてしまうと、3級の方であっても、ある日は2級に相当する、また、ある日は1級に相当するなど、日によって症状が変化する精神障がいの特性が見失われることになってしまう。そのような実態を抱える当事者や家族に、生きるのがしんどいと言わせない、人間らしく生活できるような医療、衣食住の面での支援が求められている。」ことを踏まえて、質問をさせて頂きました。
知事から「議員から御指摘あった点については、いずれも制度導入に向けて、大変重要な論点と考えており、関係者会議での御意見も踏まえて、年内の取りまとめに向けて、しっかりと検討を重ねていきたいと考える。」との答弁がありましたが、それだけに他県の制度導入状況や身体・知的障害との均衡だけでなく、課題としっかり向き合う検討をして頂きたいと思っています。
特に、県精神保健福祉センター山﨑所長からは、「病状に引きずられやすいが、日常の生活能力の障害を細かく見て欲しい。入院・入所しているのか、家族と同居か、独居か。家族と同居であっても、家族が疲弊している状況や病状を隠している場合もある。手帳の等級だけではわからない状況がある。一人で自立できる社会になっているのか。障がいの程度による差がなくなって、支援されるのが望ましい」など、判定の難しさがある中で、医療機関に丁寧に対応して欲しいとの意見も述べられていました。
また、手帳制度を基本にどこまでを助成対象とするか、助成対象とする医療のあり方などについて、引き続き検討することとしているが、複数の委員から「1級でも症状が軽かったり、2級でも重かったりと日や時間で状態は変わる」などと等級と実態の乖離を訴える声も上がっていることを踏まえて、丁寧に議論して頂きたいものです。
| 3月18日「原発廃炉の廃棄物の行く先は」 |

 廃炉を進めている中部電力浜岡原発2号機で、昨日、運転時に核燃料が入っていた原子炉圧力容器の上ぶたをクレーンで持ち上げて取り外し、原子炉の解体作業が始まりました。
廃炉を進めている中部電力浜岡原発2号機で、昨日、運転時に核燃料が入っていた原子炉圧力容器の上ぶたをクレーンで持ち上げて取り外し、原子炉の解体作業が始まりました。
これまでに建屋内の使用済み核燃料を同じ敷地内にある4、5号機の燃料プールへ搬出し、未使用燃料は敷地外に運び出し、設備の除染やタービン、発電機、原子炉建屋の一部についても解体を進めてきたが、これから始まる原子炉の解体は、廃炉作業の本丸とされています。
原子炉圧力容器や内部の炉内構造物は人が近づけないほど放射線量が高く、作業は専用のロボットを使った遠隔操作などで行うため、高度な技術が求められます。
中部電力は、2号機の原子炉から先行して解体し、12年ほどかけて2基の原子炉を解体するとして、廃炉を完了する時期は42年度を見込んでおり、1号機の廃炉にかかる費用を約379億円、2号機については約462億円と見込んでいます。
しかし、廃炉作業で生まれる大量の金属やコンクリートなどの廃棄物の処分先は決まっておらず、現時点で、18基(東京電力福島第一原発を除く)が廃炉を決めており、ほかにも運転期間が長い原発が多く、今後の廃棄物の処分先が決まらず、廃炉計画の延期が続いている現状にあります。
浜岡原発1、2号機の廃炉作業では、約45万トンの金属やコンクリートの廃棄物が生じるが、このうち約2万トンを占めるのが「低レベル放射性廃棄物」とされています。
低レベル放射性廃棄物は、汚染レベルが高い順に、「L1」「L2」「L3」と分けられ、各レベルごとに地中に埋めて、50年程度~数百年の監視が必要とされており、中電によると1、2号機分の処分先は現時点で未定で、これまでの解体作業で生じたものは、建屋内で保管している状況にあります。
政府が、2023年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」では、放射性廃棄物の保管は廃炉を決めた原発の敷地内に限定していたが、今回の第7次エネルギー基本計画は、同じ電力会社であれば別の原発敷地でのリプレースを認めると対象を拡大しています。
日本の商業炉では、廃炉を終えた原発はまだなく、廃棄物処分の問題が先送りされ続ける中で建て替えが進めば、行き場のない廃棄物がまた増えることは自明の理です。
それぞれの電力会社はもちろん、この国は、地震等の複合災害と向き合わざるをえない中で、数百年に及ぶ放射性廃棄物の管理に責任が持てるのでしょうか。
いい加減に、気づかなければなりません。
| 3月17日「政治とカネでの改革は自民党には無理か」 |
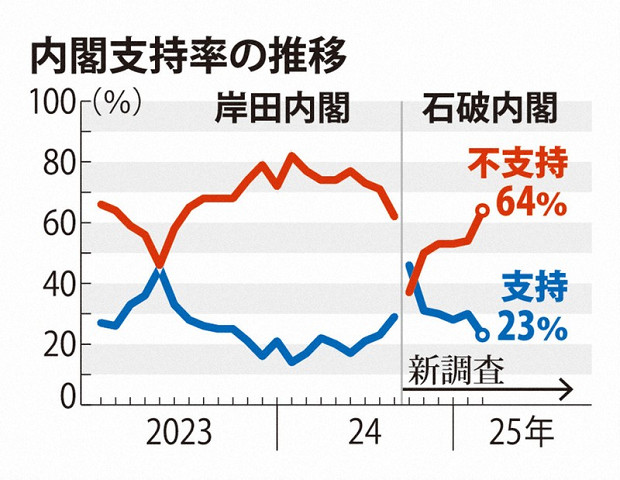
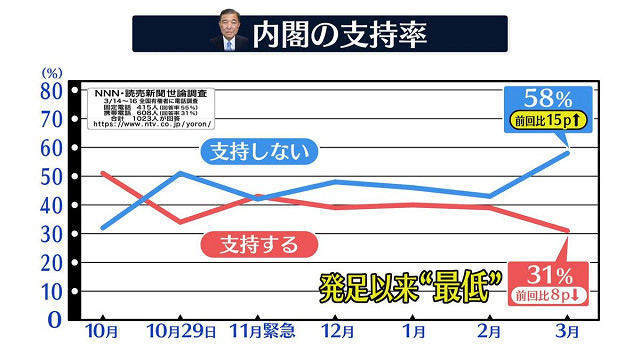 与野党で結論を出すとした3月末を間近に控え、衆院政治改革特別委員会でようやく、企業・団体献金のあり方をめぐる議論が始まりました。
与野党で結論を出すとした3月末を間近に控え、衆院政治改革特別委員会でようやく、企業・団体献金のあり方をめぐる議論が始まりました。
存続か、禁止か、規制強化か、平行線のまま時間切れとなり、現状が温存されるだけなら、政治資金への不信感はさらに高まることになるでしょう。
それだけ、「政治とカネ」の問題に対する国民の関心が高まっているときに、石破首相が今月3日、昨秋の衆院選で初当選した自民党衆院議員15人に対し、1人当たり10万円の商品券が配布されていたことが明らかになりました。
「法的には問題ない」と、いくら繰り返しても、その弁明は説得力を持たず、裏金問題で厳しい審判を受け、与野党で政治資金改革の議論をしているさなかに、無神経きわまるとしか映らないでしょう。
さらに、石破首相が商品券配布問題で苦しい立場に置かれる中、最側近とされる赤沢氏の政治団体で不透明な資金処理も明らかになりました。
こんなことが繰り返される自民党の体質は、解党的出直しでもしない限り変わらないのではないでしょうか。
昨日までの世論調査では、そのことを映し出すかのように、朝日新聞では、石破内閣の支持率は26%で、前回2月調査の40%から大幅に下落し、昨年10月の内閣発足以降で最低となり、不支持率は59%でした。
毎日新聞では、内閣支持率は23%で、前回2月調査の30%から7ポイント下落し、不支持率も前回から10ポイント上昇の64%となっています。
読売新聞社でも、内閣支持率は、31%となり、前回調査から8ポイント下落し、いずれも過去最低を更新しています。
小手先の政策対応で、野党に配慮して予算案を通過させても、本質が変わらない限り、政治そのもののの信頼回復は果たせないように思えて、なりません。
| 3月15日「美術館でも真贋の見極めの困難さ」 |
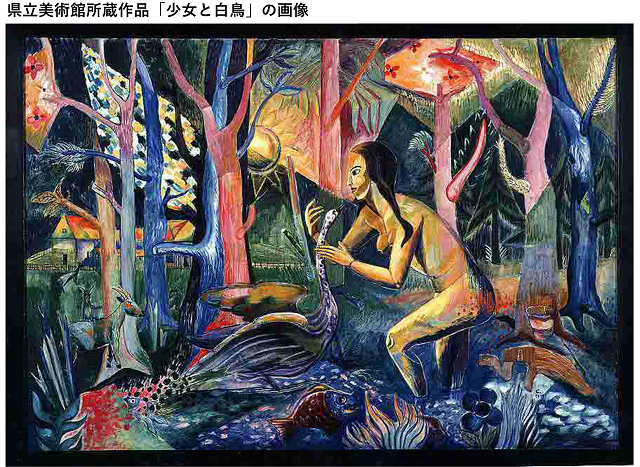
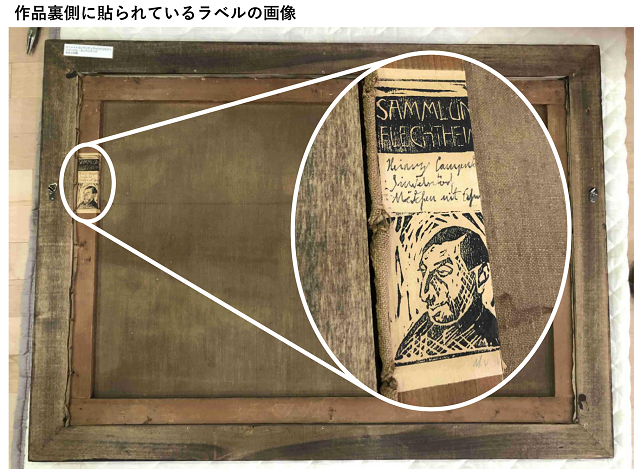 昨日の危機管理文化厚生委員会で、報告事項として、昨年贋作の疑いが持たれた県立美術館所蔵の油彩画「少女と白鳥」について、県と同館は、専門家に依頼していた科学調査の最終報告などを基に、「贋作と判断した」ことを公表しました。
昨日の危機管理文化厚生委員会で、報告事項として、昨年贋作の疑いが持たれた県立美術館所蔵の油彩画「少女と白鳥」について、県と同館は、専門家に依頼していた科学調査の最終報告などを基に、「贋作と判断した」ことを公表しました。
作者は、贋作制作で有名なドイツ出身の画家で、同作を描いたと公言しているウォルフガング・ベルトラッキ氏である可能性が高いとしました。
平成8年に1800万円(税込)で購入したもので、「錯誤を理由に、買主の代金返還請求が認められた例があり、今回は民法上の時効10年はたっているが、請求しないことにはならない」として、今後、購入元の画廊に対し、返金交渉する方針も示されました。
県及び美術館として、当該作品を贋作と判断し、作者は、ヴォルフガング ・ベルトラッキの可能性が高いと考えたのは、以下の理由によるものであることも明らかにしました。
【理由】
①田口准教授の最終報告により、ベルトラッキが贋作制作においてしばしば用いた絵具であり、 かつ、カンペンドンクが本作品を制作したとされる時期(1910年代)には画家の描画用の絵具としては一般的でない材料であった「チタニウムホワイト」「フタロシアニンブルー」「フタロシアニングリーン」が使用されている可能性が高い。
②作品の裏側にはベルトラッキの自作と思われる来歴偽造ラベルが貼付されている。
③ベルリン州警察が作成したベルトラッキの贋作リストには、当該作品とされる「少女と白鳥」が画像とともに掲載されている。
県は「今後の対応方針」について、「過去の裁判例等を参考にしながら、購入先である画廊に対して返金の請求を念頭に置いた交渉を予定」「美術館では、これまでの経緯などとともに当該作品を公開することを検討中」としています。
また、今後は「再発防止」に向けて、「今後作品を購入しようとする際は、資料収集審査会の開催前に来歴や関連情報についてより念入りに検証を行い、審査会において丁寧な説明を行う」「審査会に真贋に係る議題を設定し、委員等からご意見をいただいたうえで、県及び美術館として購入の可否を決定することで、贋作の可能性を少しでも排除することに努める」とされています。
委員会では、私も含めて多数の委員から、今後の対応や再発防止に向けた意見が出されましたが、購入作品の真贋を見極めることは極めて難しいと思われる中で、繰り返さないことは困難を極めることと思われますが、今回の教訓や反省を活かしていく美術館の今後を注視したいと思います。
| 3月14日「後一ヶ月に迫った関西万博への不安」 |

 大阪・関西万博の開幕まで、昨日13日で1カ月となったが相変わらずの準備不足と不安材料が露呈しています。
大阪・関西万博の開幕まで、昨日13日で1カ月となったが相変わらずの準備不足と不安材料が露呈しています。
会場となる大阪市此花区の夢洲では、参加国が独自に建設するパビリオンの外装が完了したのはまだ2割未満で、開幕までにすべて内装まで終えて、来場者を迎えられるかは見通せていないとのことです。
万博に参加するのは、約160の国・地域で、日本国際博覧会協会の幹部によると、海外パビリオンのうち、各国が独自に設計・建設し、「万博の華」ともいわれる「タイプA」(47カ国)で外装が完成したのは10日時点で8カ国にとどまっています。
そして、問題の前売り入場券の開幕まで1400万枚の販売目標は、5日時点で806万枚(57.6%)だそうです。
23年度までの夢洲の埋め立て事業費は約3400億円で、国と大阪府・市が負担する会場周辺の橋や道路の拡幅、夢洲駅開業といったインフラ整備費は、約800億円にのぼっているが、安全・安心面でのリスクは常につきまとっています。
夢洲の一部のエリアでは、廃棄物や汚泥による埋め立てが原因でメタンガスが発生し、昨年3月には工事に伴う火花がガスに引火して、爆発火災が起き、換気設備やガス検知器を新たに設け、ガス濃度の測定結果も定期的に公表しているが、生徒・児童を引率する学校関係者などから懸念の声は根強くあります。
そして、地震などの災害が起こった際には橋やトンネルが通行止めとなり、来場者の孤立も想定されています。
ここにきて、大屋根「リング」が海水と接している部分の護岸計1.1キロのうち600メートルで、浸食被害が確認されています。
2月に海水の注入を始めたばかりで、強風による波などでえぐられたとみられるており、リングの安全性に影響はないが、護岸を砕石で覆って保護するなどの対策を検討するとのことです。
これで、また追加工事にどれだけの費用がかかるのでしょうか。
5年前の2月定例会で、私の夢洲における災害リスクの質問に対して、濵田知事は「一般的なリスク対策は必要でございますし、講じていかなければいけませんけれども、殊さらに夢洲について大きく懸念をするというような状況ではないというふうに思っております。」と答弁されたが、本当にそうなのだろうかとの不安は払拭できないままです。
| 3月13日「見えない手錠を外せぬまま石川一雄さん旅立つ」 |
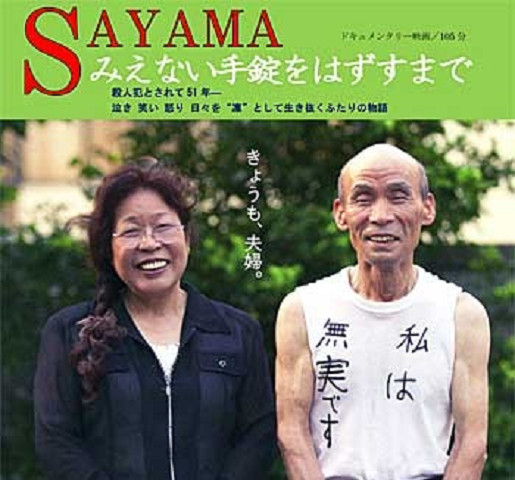
 62年前の1963年、埼玉県狭山市で女子高校生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人容疑などで逮捕され、一審で死刑判決を受け、二審で全面否認に転じたが、無罪主張は退けられ、77年に最高裁で無期懲役が確定して服役、94年に仮釈放された後も無実を訴えて裁判をやり直す再審を求めてきた石川一雄さんが11日、86歳で亡くなられました。
62年前の1963年、埼玉県狭山市で女子高校生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人容疑などで逮捕され、一審で死刑判決を受け、二審で全面否認に転じたが、無罪主張は退けられ、77年に最高裁で無期懲役が確定して服役、94年に仮釈放された後も無実を訴えて裁判をやり直す再審を求めてきた石川一雄さんが11日、86歳で亡くなられました。
驚くと同時に、無念さがこみ上げてきます。
石川さんが亡くなったことを受け、弁護団の河村健夫弁護士は取材に「第3次再審請求も重大な時期に差しかかる中、突然のことで驚いた。言葉もない」と語られています。
今後の手続きについては「コメントできる状況にない」とし「再審法(刑事訴訟法の再審規定)が整備されていれば、ここまで手続きは長引かなかった。法の不備が不利な形で石川さんに影響したのではないか。再審法の早期改正が必要」と訴えられています。
私たちも、そのことを求め、昨年県議会9月定例会で、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」を提出しましたが、自民党、公明党、一燈立志の会、自由の風の反対で、残念ながら否決されました。
そして、再審法改正に向けて動き始めたところでもあっただけに、余計に残念でなりません。
妻の早智子さんが、再審請求に向けて闘い続けていくことの表明もされています。
2月11日付け東京新聞<本音のコラム>で、狭山事件の真実を描き続けてきたルポライターの鎌田慧さんは「裁判所は最後の正義」と題して、「石川さんは86歳。最近、急に体力が低下してきた。鑑定人尋問、再審開始決定、無罪判決、それまでの時間が心配だ。高裁への期待は強い。」と結ばれていました。
再審の扉を開け、無実を勝ち取ることが、石川さんの死に報いることだとの思いで、私たちも闘い続けたいものです。
| 3月12日「14年目の3.11に被災地を想う」」 |

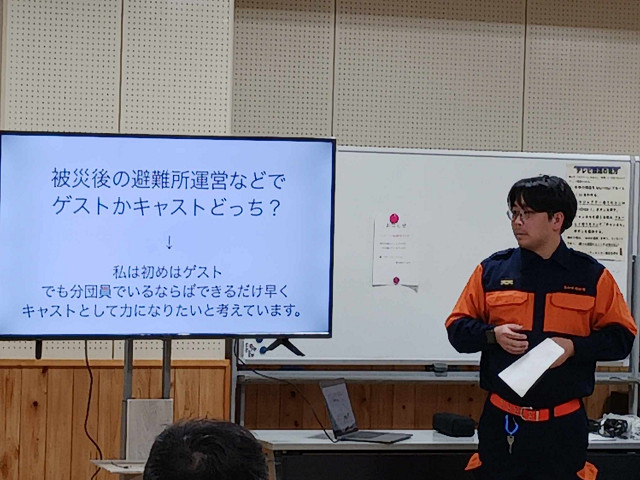


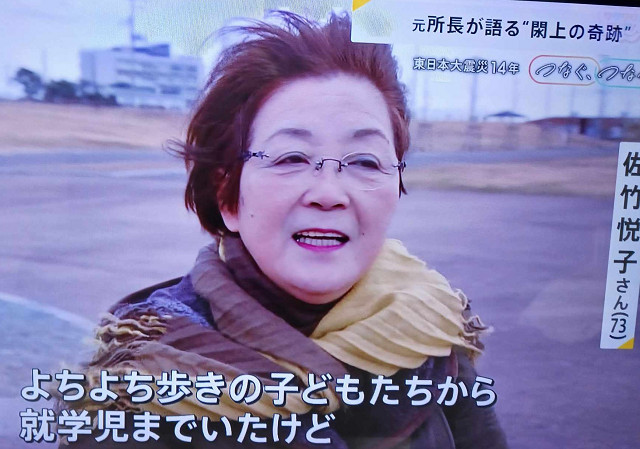
昨日は、東日本大震災から14年。
鎮魂の一日となりました。
午前10時、議会開会冒頭に黙祷。
被災地では、14時46分に合わせた黙とうですが、私たち未災地の高知からは18時30分、今年は、雨が降ったりやんだりの天候の悪い中、近所の皆さん40人ほどが参集し、黙とうしました。
赤ちゃん連れの若いカップルも参加してくれていました。
1.11東日本大震災追悼の集いでは、黙祷に続き、下知地区減災連絡会皆本会長の挨拶に始まり、大﨑副会長から被災体験のお話や耐震改修・家具固定研修の告知、役員の北澤さんから昨年訪問した被災地の復興状況の報告がありました。
集いの後、下知コミュニティセンターで、下知地区減災連絡会女性部会の役員を任命し、記念すべき発足式を行った後、昨年11月に能登半島地震の被災地珠洲市、輪島市を訪ねた下知消防分団の報告がありました。
横田団員を中心に、国見分団長からの報告は、現地で見た率直な感想を伝えて頂きました。
集いには40人、報告会には30人の皆さんが熱心に参加して頂きました。(今朝の高知新聞にそれぞれの様子の記事が掲載されています。)
参加された皆さんが、一つでも次の行動につなげて頂けたらと思います。
全ての片づけを終えて、自宅に帰ってからの夕食は、朝からの非常食の締めくくりでした。
そして、23時過ぎ「News23」に目を向けたところ偶然にも、これまでにも下知の常盤保育園で保育士さんたちを対象にお話をして頂くなどのご指導を頂いた閖上保育所の佐竹元園長先生が登場されていました。
これもつながりだなと思いつつ、先生の優しい口調の中の園児を絶対守るという強い決意のお話を伺いながら、長い3.14を終えました。
| 3月11日「14年目の3.11をきっかけに」 |
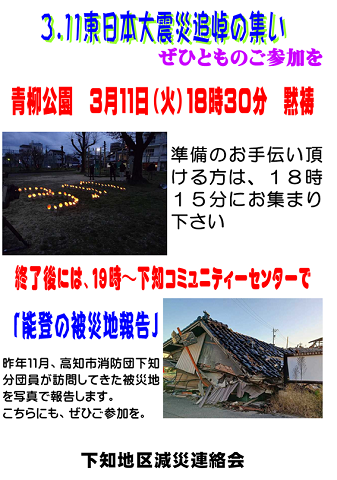 今日は、東日本大震災から14回目の3月11日となります。
今日は、東日本大震災から14回目の3月11日となります。
下知地区減災連絡会では10年を節目に、東日本大震災の教訓を風化させないとの思いで、スタートした「3.11東日本大震災追悼の集い」を開催します。
青柳公園での集いの後には、下知コミュニテーセンターで、昨年11月、高知市消防団下知分団員が訪問してきた「能登の被災地報告」を行います。
その前段には、下知地区減災連絡会で準備してきた「女性部会」の役員の任命式も行い、正式発足をすることとしています。
下知地区減災連絡会は、これまでも女性枠役員を設け、常に1/3ほどの女性役員にともに活動してきてもらいました。
そして、女性の視点は生活者の視点ということで、今後はさらに女性の視点を反映して頂ければと考えています。
内閣府男女共同参画局は20年、女性の視点を取り入れた防災・復興のガイドラインを公表し、取り組むべき事項として着替え場所の確保やパーティションの設置などを挙げています。
また、内閣府防災担当は昨年12月、劣悪と評される避難所の環境を改善するため、自治体向けの指針を改定し、居住スペースの最低限の広さなどを追記されました。
一方で、神戸市の認定NPO法人「女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ」の正井礼子代表理事は、「災害時のケア労働が女性に偏らないよう、平常時からジェンダーギャップの解消に取り組み、意思決定の場に女性が3割はいる状態を作らなければいけない」と強調されています。
また、公益財団法人「ほくりくみらい基金」など4団体が能登半島地震被災地の女性に実施した聞き取り調査では、「ボランティアが入る前は炊き出しに1日7時間。睡眠2、3時間の日が続いた」とか、「避難所生活で、女性は高齢男性から地域の嫁として用事を言いつけられる。避難所を出て在宅避難をし始めた女性にも避難所で炊き出しをするように連絡が来ていた。若い世代はそのような価値観は耐えられない」など、災害時のジェンダーギャップに苦労する女性の姿が浮かび上がったとの報道もあります。
女性部会の発足を機に、避難所運営などが一部の人に偏らず、男性中心の運営にならないようジェンダーフリーの地域防災活動に繋がればと思うところです。
| 3月10日「国際女性デーに考える「ジェンダー平等」」 |

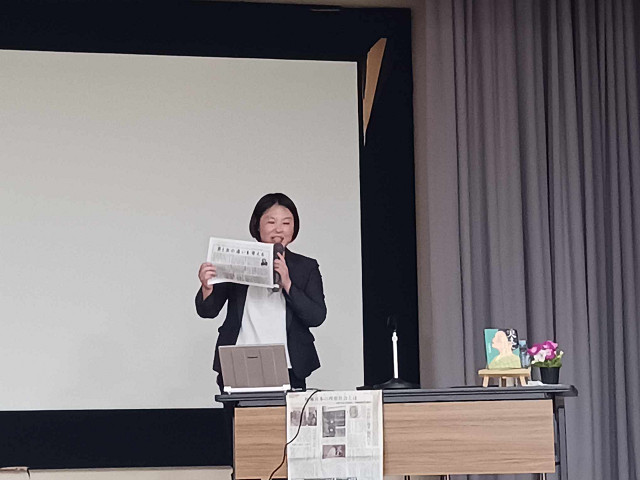
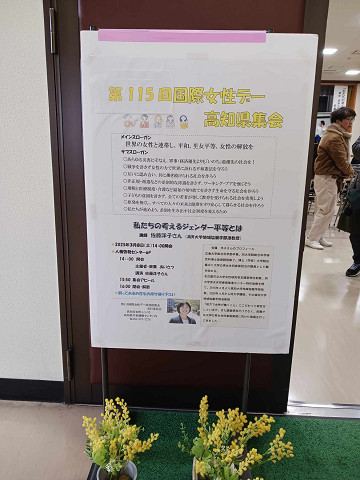
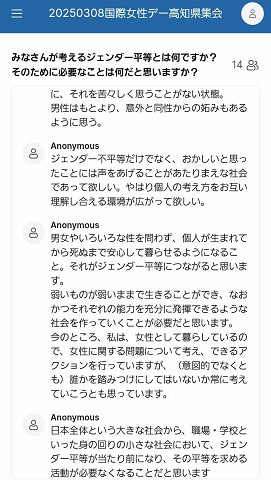
昨日は、人権啓発センターで開催された「第115回国際女性デー高知県集会」に参加していました。
講師の高知大学佐藤先生は高知新聞24年11月1日付け朝刊12面の「男と女の違いを考える」意見広告、それに関する公開質問状や新聞社の回答などを通じてジェンダー平等について考えました。
しかも、参加者の意見をスマホを通じて画面上で共有しながら考えていくやり方で、より多様な意見に触れ合うことができたのではないでしょうか。
今、少子化対策の中で、労働力を再生産する手段として若年女性への支援施策が強調されているが、それだけでいいのか。
若い女性はジェンダー問題が性の多様性の問題と勘違いしている人も多いと先生は言われていましたが、固定的性別役割分業意識の解消をはじめ、誰もが性による社会的・文化的差別を受けることなく、自らの能力を自由に発揮することができ、個々の人権が尊重されるような職場、地域、社会が築かれるようにお互いが取り組んでいけたらと、改めて考えさせられたひと時でした。
| 3月9日「約2時間の質疑の記録」 |



2月28日の代表質問の質疑応答約2時間分のテープ起こしができましたので、報告させて頂きます。
大きくは「地方創生と人口減少対策について」「消防広域化のあり方について」「南海トラフ地震対策について」「精神障がい者に対する精神科医療費及び一般医療費への助成制度について」「政府の第7次エネルギー基本計画と原発、再生可能エネルギーについて」の項目に分類されますが、小項目で35項目に及んだことから分量が多くなっています。
正式の議事録ではありませんが、ほぼ間違いのないテープ起こしですので、こちらに仮の議事録として掲載させて頂きますので、関心ある方はぜひご一読ください。
定例会も後半に入り、11日の一問一答方式による本会議が終われば、常任委員会審議に入りますので、引き続き頑張っていきます。
| 3月8日「地域からのジェンダー平等」 |
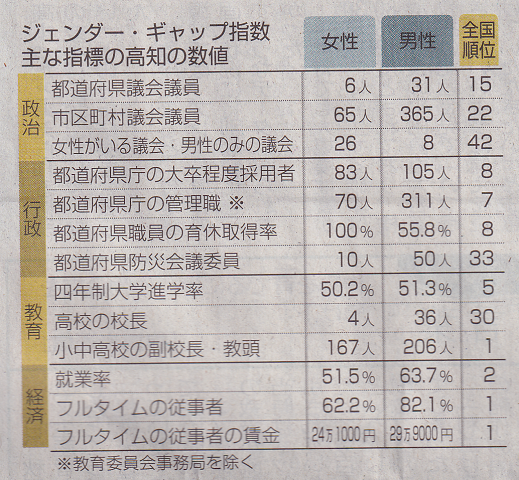 今日は、国際女性デー、しかも2025年は、国連が「国際女性デー」を提唱してから50年という節目の年です。
今日は、国際女性デー、しかも2025年は、国連が「国際女性デー」を提唱してから50年という節目の年です。
2022年から上智大三浦まり教授らでつくる「地域からジェンダー平等研究会」が、国際女性デーにあわせて「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を公表しています。
2025年の「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」で、高知県は4分野とも格差解消が進み、経済は全国1位(前年2位)、教育3位(同7位)、行政9位(同11位)と、順位が上昇したものの、政治は市町村議会の「女性ゼロ議会」の解消が遅れ、35位(同38位)と低迷していることが報じられています。
指標別で見ると、本県の経済では、フルタイムの仕事に従事する男女比(0.758)と、賃金格差(0.804)がともに1位だが、賃金は2位に岩手、3位に長崎が続き、男性の賃金が低い地域は男女の平等度が相対的に高く出る傾向があると言われています。
このほか、「共働き家庭の家事・育児時間」が6位(0.226)だったものの、1位の新潟(0.258)でも、男性が担う時間は女性の4分の1ほどにとどまっており、順位と実態では「固定的な性別役割分担意識の解消」とはなっていないようです。
私も2月28日の本会議質問で、いくつかの事例を出しながら、「全国的に人口減少が激しい地域は、ジェンダーギャップ問題への危機感が大変強まっており、高齢者も変わらなければという意識を持ち、女性参画を進めている。」として、「固定的な性別役割分担意識の解消」にとどまらず、本県もその指数はけして全国低位ではないが、ジェンダーギャップ解消まで掘り下げた取組を求めました。
知事も、「本県の男女間の賃金格差は、全国最少ではあるが、男女間格差の是正もさることながら、男女を通じた所得水準が全国と比べて遜色ないことが求められる。」と、賃金水準そのものが低位であることを認め、「賃金の引き上げに向けた取り組みを強力に推進」するとのことです。
その上で、「さまざまな施策をバランスよく展開する中で、男女間格差の解消にもしっかりと取り組んでいく。」と述べ、「市町村におけるジェンダーギャップの現状については、来年度に予定しいるこうち男女共同参画プランの改訂作業の過程で、関連する統計指標の状況を整理した上で、示すよう検討する。」と答弁されました。
あるシンクタンクは提言書で「若い女性が地方から都会へ流出するのは、都会に比べて地方のジェンダーギャップがより大きく、地方は多様な女性を地域づくりから排除しているためだ」と指摘しています。
改めて、「地域からジェンダー平等」をと声をあげていきたいものです。
今日14時~人権啓発センターで「第115回国際女性デー高知県集会」が開催されます。
高知大学地域協働学部佐藤洋子准教授による「私たちの考えるジェンダー平等とは」と題した講演があります。
ぜひ、お越しください。
| 3月6日「大船渡の山林火災に被災者生活再建支援法を適用」 |

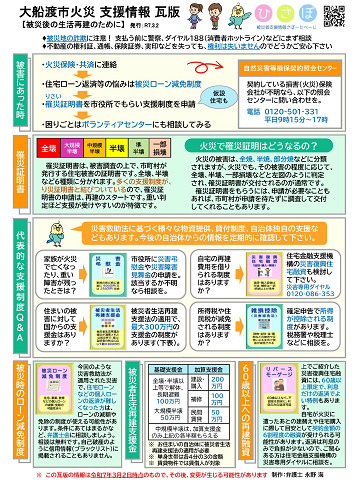 内閣府は本日、山林火災の被害拡大を受け、岩手県が大船渡市に被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。
内閣府は本日、山林火災の被害拡大を受け、岩手県が大船渡市に被災者生活再建支援法を適用すると発表しました。
火災に起因する被害に適用されるのは、2016年12月の新潟県糸魚川市、21年4月の松江市で大規模火災に続く3例目となります。
住宅が全半壊した世帯に対し、被害や住宅の再建方法に応じて最大300万円が支給されます。
大船渡市の調査では今月5日時点で、住宅や空き家を含む建物78棟が焼失したとみられており、強風による大規模な火災で、支援法適用の要件である10世帯以上の住宅全壊が発生した市町村に該当すると判断されました。
政府は、被災地のインフラ復旧などに対する財政支援を手厚くする激甚災害への指定に向けた作業も進めています。
いつも被災地の皆さんの生活再建に向けた支援をされている永野海弁護士は、今回の大船渡の皆さんに対しても「大船渡市火災支援情報瓦版」をすでに3日前に公表されています。
ぜひ、必要とされている被災者や支援者に伝えてあげて頂きたいと思います。
| 3月5日「地球温暖化と山火事」 |
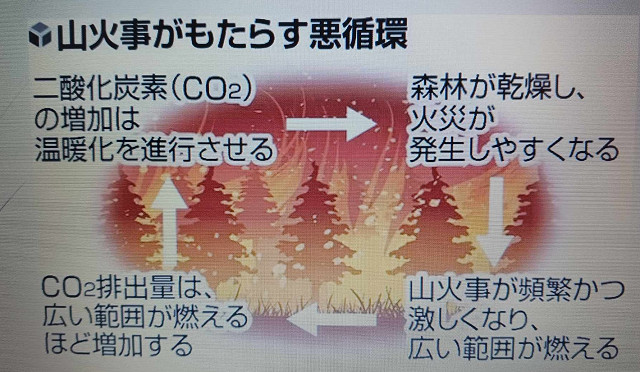
 3日夜、ZOOMで参加した全国防災関係人口ミートアップでは、「令和7年全国山火事予防運動 地球温暖化と山火事〜ふるさとの山を守ろう火の手から〜」として、室﨑益輝先生(神戸大学名誉教授、減災環境デザイン室顧問)に話題提供いただき、地球温暖化と山火事について考えさせて頂きました。
3日夜、ZOOMで参加した全国防災関係人口ミートアップでは、「令和7年全国山火事予防運動 地球温暖化と山火事〜ふるさとの山を守ろう火の手から〜」として、室﨑益輝先生(神戸大学名誉教授、減災環境デザイン室顧問)に話題提供いただき、地球温暖化と山火事について考えさせて頂きました。
大船渡での山林火災が始まって、すでに一週間が過ぎました。
室崎先生は、国の内外において山火事が激甚化していることを改めて痛感せざるをえない実態の確認から始まりました。
この2~3年でロシア、アメリカ、カナダ、ブラジル、ボリビアなどで年間20万ha以上焼失し、スペイン、フランス、イタリア、ギリシャなどで年間2万ha以上焼失、日本では最近5年間の年間平均1300件で年間700haが焼失ということなのだが、今回の大船渡だけで今朝の6時時点で、国内年間平均の4倍以上の2900haが消失しています。
最近の山火事の原因と地球温暖化の関係について、次のように整理されていました。
「素因」として、枯葉や枯れ草の放置という燃えやすい山林に加えて、乱開発と緩衝ゾーンの欠落による山林と住家の接近があります。
そして、「必須要因」としては、摩擦熱とか酸化熱による自然発火、雷、噴火などの「自然的要因」と焚き火、火入れ、放火、タバコなどの「人為的要因」があり、それらを拡大させる要因として熱、乾燥、強風があるが、まさに地球温暖化や異常気象が高熱や乾燥をもたらし山火事の大規模化を引き起こしていると言えます。
そのような中で、「日本の山火事の動向」としては、世界と比較して大規模な山火事が少ないなど、固有の特徴があり、乾燥と春風、ハイキングと火入れなどによって「夏ではなく、春先に多い」ことや、湿潤な気候や山火事対策が進んでいることで「海外に比べ、大規模なものが少なく」、樹種や気温の違いで「人為的要因によるものがほとんど」だとのことです。
火災の燃え広がり方は延焼、燃焼形態、被害程度などで4種類に分けられ、「地表火」「地中火」「樹幹火」「樹冠火」の4つで、強風時に拡大を許すと消火が極めて困難になります。
その特徴としては、早期知覚の困難さや現場到着の遅延という「発見と初動の遅れ」、可燃性の物質の存在、上昇気流、火災旋風、飛び火など地形と気流の影響による「拡大の速さ」、そして、地上消火も空中消火も消防水利の不足や地中の水利が欠落しており、消火活動の困難やヘリ消火の限界などによる「消火の困難性」にあります。
そのような中で、「対策の足し算」としての山火事対策として、山火事を許すと消火が困難なだけに、火の用心的な出火防止対策に力点を置きがちであるが、それに矮小化してはならないとのことで、次の5点をあげられていました。
1 異常気象への対応をおろそかにしてはならない
2 森林の適正な保全や管理に努めなければならない
3 山麓開発や宅地形成での防災的配慮がいる
4 監視技術や消火技術さらには予測技術の進化がいる
5 消防団員の減少などに応える消防体制の見直しも
まさに、そのとおりで、中山間地対策として人、山、水源の持続可能な取組に注力することも、山火事対策に繋がっていく事であることだなと考えさせられました。
| 3月3日「3.11を前に山火事も考える」 |
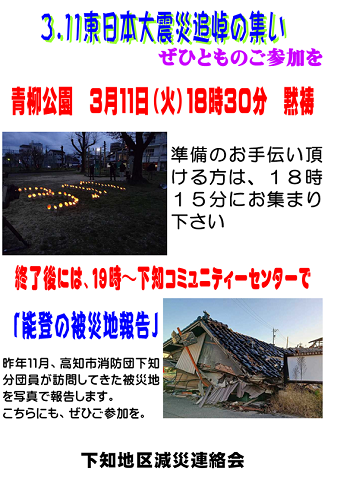
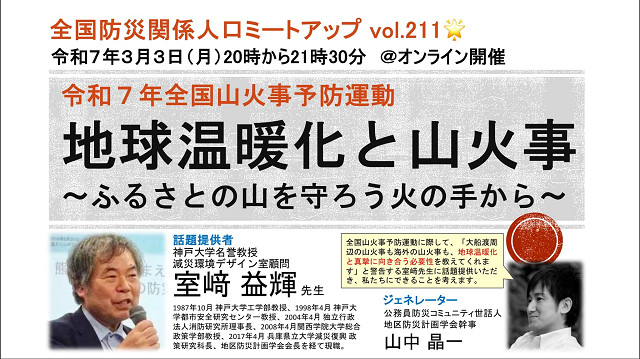 今年は3.11を前に、岩手県大船渡市の山火事は延焼が続き、焼失面積が約1800ヘクタールに拡大しています。
今年は3.11を前に、岩手県大船渡市の山火事は延焼が続き、焼失面積が約1800ヘクタールに拡大しています。
避難指示が三陸町綾里全域と越喜来の3地区、赤崎町の13地区に出されていて、2日午前11時の時点で避難対象世帯が1896世帯で、避難者は1206人となっているとのことです。
14年目の3.11を迎える前に、被災地では新たな災害と向き合っています。
一日も早く鎮火しますとともに、避難されている方にお見舞い申し上げます。
今年の下知地区「3.11追悼の集い」は、そんなことも考える集いにしたいと思います。
お近くの皆さん、ご参加ください。
一方、各地で起きた山林火災で、長野県上田市の現場は2日午前に鎮圧し、山梨県大月市の現場は同日夕も鎮圧していないとのことです。
そんな中、毎週月曜日夜に開催している今夜の全国防災関係人口ミートアップでは、「令和7年全国山火事予防運動 地球温暖化と山火事〜ふるさとの山を守ろう火の手から〜」として、室﨑益輝先生(神戸大学名誉教授、減災環境デザイン室顧問)に話題提供いただき、被災地に心を寄せ、私たちにできることを共に考えることとなっています。
関心ある方は、どうぞご参加ください。ご案内は、こちらからです。
| 3月1日「県政施策は現場の声を大事に」 |
 昨日は、議場に傍聴に来て頂いたり、ネット中継を傍聴頂いたりとありがとうございました。
昨日は、議場に傍聴に来て頂いたり、ネット中継を傍聴頂いたりとありがとうございました。
再質問時間が5分ほどしか残りませんでしたので、納得いかない答弁に十分に再質問をすることができませんでした。
そのような中で、残された最後の15秒で「4Sプロジェクトや県一消防広域化、精神障がい者への医療費助成制度など県政施策は、現場の声を大事にして下さい」と締めくくって終えました。
答弁も含めた質疑が約2時間、テープ起こしができたら仮の議事録をHPにアップしたいと思います。
今朝も事務所に来る途中お会いした方から、「昨日の質問を、新聞で見ましたよ」と声をかけて頂きました。
皆さんの目に触れるのは、ほんのわずか。
これを仮の議事録にして、このHPにアップし、「県政かわら版」を作成・配布することで、皆さんのもとに届けていきたいと思います。
それまで、しばらくお待ちください。
| 2月27日「議会質問で明日登壇」 |

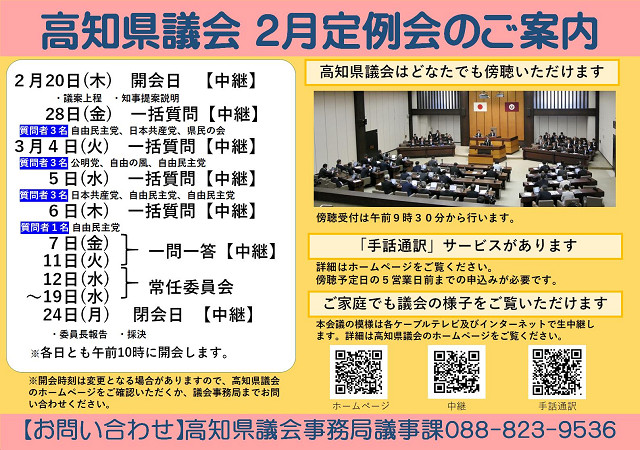 いよいよ明日から県議会2月定例会の質問戦が始まります。
いよいよ明日から県議会2月定例会の質問戦が始まります。
私の登壇予定は、明日の3番目となりますので、15時過ぎ頃が想定されます。
ただし、前段の質問者の質疑時間によって多少の遅れがあるかと思いますが、おかまいなければ議場またはオンラインでの傍聴をよろしくお願いします。
質問は、大項目で5問ですが、小項目で35問になります。
いつもどおり、「多いね」と言われますが、9月定例会の一問一答による質問以来ですので、一括質問形式の代表質問ともなれば時間も長いですので、日頃から聞きたかった質問で質していきたいと思います。
1 地方創生と人口減少対策について
(1) 人口減少対策としての若者の転出超過の抑制について
ア 若者に働いてもらうための雇用環境の改善について
イ 若者世代でも家計比較を行う必要性について
ウ 全国一律最低賃金制度にすることについて
エ 若年女性が求める職場と重点的に進めるべき対策について
オ 県におおける非常勤職員の正規化や正規職員の給与の改善について
カ 正規雇用を増やし、働きやすい職場環境の公務職場の拡大について
キ ジェンダーギャップの解消に向けた取り組みについて
(2) 中山間地域の持続的な発展に向けた取組と4Sプロジェクトについて
ア 「にぎやかな過疎」の具体化について
イ 過疎の地域に住まう県民の「共感」と「前進」について
2 消防広域化のあり方について
(1) 骨子案に対するパブリックコメントについて
(2) 広域消防のあり方と広域化の際のメリットとデメリットの解決について
(3) 「消防広域化基本計画あり方検討会」の構成員について
(4) 通信指令業務の集約や職員の処遇と広域連合高知県消防局の発足について
(5) 広域連合による防災部署と消防本部の関係性について
(6) 通信消防システムの一元化によるコストと更新について
(7) 消防広域化の移行案のスケジュールについて
(8) 広域化で「消火・救急・救助などの現場力の強化」の見通しについて
3 南海トラフ地震対策について
(1) 被災者生活再建支援法の改善について
(2) 受援力向上の県の姿勢について
ア 災害中間支援組織の検討状況と今後の見通しについて
イ 「即時応援県」と円滑な運用を目指す取り組みについて
(3) スフィア基準と避難所確保について
ア 第6期南海トラフ地震対策行動計画案におけるスフィア基準について
イ スフィア基準の指標が示されてない場合の取り組みについて
ウ 外国人の地域の防災訓練参加の具体的なアプローチ方法について
エ 「要配慮者の特性に応じた避難所における要配慮者支援ガイド」の改訂について
オ 広域避難所への資機材・備蓄品の事前整備について
(4) 仮設住宅の用地確保と数量確保の見通しについて
ア 現状の把握状況の詳細と、精査について
イ 2階建ての仮設住宅について
(5) 要配慮者の避難対策の抜本的な見直しについて。
(6) 新たな県民体育館の整備における防災機能・避難所機能について
(7) 市町村における災害ケースマネジメント実施計画の作成支援について
4 精神障がい者に対する精神科医療費及び一般医療費への助成制度について
(1) 医療費助成制度の精神障害者の対象と適用について
(2) 早期の実現について
5 政府の第7次エネルギー基本計画と原発、再生可能エネルギーについて
(1) 基本計画に対する所見について
(2) 原発事故時の本県の避難計画の実効性について
(3) 再生可能エネルギーの県内消費電力の割合について
| 2月25日「『独り』の現役、『独り』の老後に寄り添って」 |
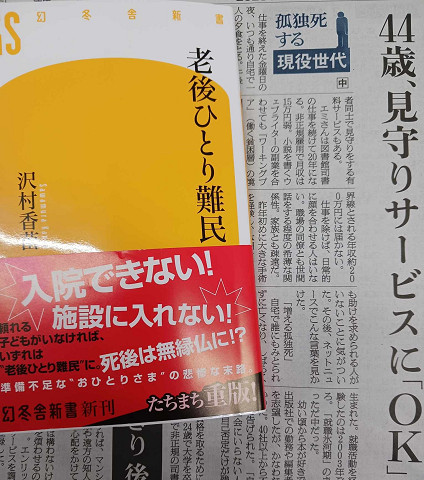 沢村香苗さんの著書「老後ひとり難民」を手にし、改めて切実な実態と向き合うことになりました。
沢村香苗さんの著書「老後ひとり難民」を手にし、改めて切実な実態と向き合うことになりました。
一年間に亡くなった人のおよそ15人に一人が、身寄りがない人や身元がわからない人として行政機関に火葬されているという実態があるそうです。
そして、プロローグに、「家族に看取ってもらえないどころか、死後の葬儀さえしてもらえないというケースは、今や全く 珍しくなくなっています。背景には、結婚しない人、子どもを持たない人、親と同居しない人などが増え、家族 親族のつながりが希薄化する中、いざという時に頼れる人がいない、人が増えているという現実があります。高齢で子どものいない夫婦の場合、一方が倒れたりなくなったりすれば、あっという間に誰も頼れないという厳しい状況に追い込まれることになるでしょう。」とあります。
しかし、朝日新聞の特集記事「孤独死する現役世代」が始まると、高齢者の問題だけでないことが、明らかになり、さらに「老後ひとり難民」の予備軍がバブル崩壊後の就職氷河期に社会に出た「ロストジェネレーション世代」に潜在しているということになります。
孤独死の実態把握の一環として、警察庁は昨年、自宅で死亡した一人暮らしの人の全国的な統計を初めて公表し、1~6月は3万7227人で、生産年齢人口(15~64歳)の「現役世代」がそのうち23.7%(8826人)を占め、高齢者に限った問題ではない実態が浮かびあがっています。
孤独死に詳しい日本福祉大の斉藤雅茂教授(社会福祉学)は、現役世代の特に単身者の場合、高齢者のようにヘルパーなどの日常的な変化に気づける人が少なく、死亡しても発見されにくいリスクがあると指摘しています。
特に、記事でとりあげた男性の場合は「就労が不安定だったり、両親の他界、親族関係の問題など、生前から社会的に孤立しがちな状態にあったことなどは、現役世代の孤独死の典型的なケース」と言い、適切に社会福祉などのサービスにつながれていれば、「助かった命だった可能性がある」と指摘されています。
60代になれば体の不調も増え、介護を受けるかもしれないが、自分には世話をしてくれる相手も、誰かに頼めるだけの経済力もないという現役世代が「老後ひとり難民」にならないためにも、早くから人や地域やサービスとつながる仕組みが求められているのではないでしょうか。
| 2月23日「『8がけ社会』と向き合う」 |
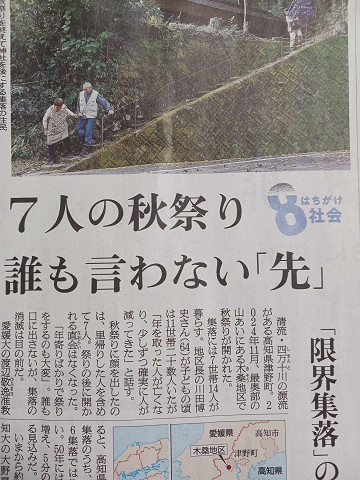 日本の高齢化と少子化の進行により、2040年頃に社会の労働力となる15歳〜64歳の現役世代が現在より1,200万人も減少することが予測される社会が、「8がけ社会」と言われています。
日本の高齢化と少子化の進行により、2040年頃に社会の労働力となる15歳〜64歳の現役世代が現在より1,200万人も減少することが予測される社会が、「8がけ社会」と言われています。
2月21日付の朝日新聞一面の「(8がけ社会)7人の秋祭り」の記事は、7世帯14人が暮らす高知県津野町の最奥部の山あいにある木桑地区で、昨年11月に秋祭りが開かれたことから、人が減り、細るばかりの集落のことが取りあげられています。
そのような集落とどう向き合うのか、人口減少社会の中で行政サービスは縮小するしかないと言われるが、そこに暮らす人々、暮らしたい人々がいる中で、「集落畳み」「村おさめ」ということを突きつけられるています。
否が応でも、議論しなければならなくなっています。
そんな思いを抱きながら議会質問を作成しています。
| 2月21日「2月定例会開会、質問準備に集中」 |

 昨日20日に県議会2月定例会が開会しました。
昨日20日に県議会2月定例会が開会しました。
浜田知事は提案説明で、県政の最重要課題と位置付ける人口減少対策について、2025年度は「一連の施策を抜本強化し、克服に粘り強く取り組む」とし、「若者の所得向上の推進」「移住・定住対策の充実」「多様な出会いの機会充実」「「共働き・共育て」推進」の方向性で施策を強化することを示しました。
その一方で、今後も人口が減ることを見越し、あらゆる分野の担い手不足に適応するため、効率的で持続可能な社会と県民生活の質の向上を目指して「スマートシュリンク=賢い縮小」「4Sプロジェクト」の推進を改めて表明しました。
また、南海トラフ地震対策については、新たに策定する「第6期行動計画」に基づき、その被害を最小限に抑え、県民の命と暮らしを守るべく万全を期するとの決意を示されました。
他にも多岐にわたる県政課題に言及されましたが、2月28日の代表質問では、この2課題を中心に質問を準備しているところです。
質問日が近づき、質問の通告ができましたら、またこちらでご紹介したいと思います。
| 2月19日「ドン・キホーテオープンで周辺道路は終日混雑」 |

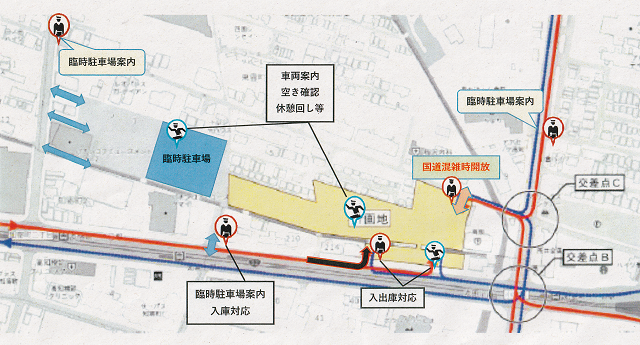
 昨日、私の住む下知地区は、全国最後の設置空白県に進出したディスカウント店「ドン・キホーテ高知店」の開店によって、異常な光景が一日繰り広げられていました。
昨日、私の住む下知地区は、全国最後の設置空白県に進出したディスカウント店「ドン・キホーテ高知店」の開店によって、異常な光景が一日繰り広げられていました。
マスコミなどでは、「待ちかねたドンキファンが大行列をつくり、一時入店制限するほどの大にぎわい」などと報道されていたが、地域での心配事は現実のものになりそうです。
出店にあたっては、地元説明会で地域の課題などについて、意見反映し、少しでも解消したうえで、地域に信頼される店舗を目指して欲しいと声をあげてきました。
大規模店舗審議会でも、店から一度に出す車の台数を決めたり、公共交通機関を利用して店に来る人を増やすことの検討を求める意見も出るなど、交通量や周辺住民の生活に配慮を求める意見が相次いだとのことでした。
これに対しドン・キホーテ側の担当者は近隣施設の協力のもと臨時駐車場を設けるほか、看板や路面標示の設置、誘導員による車両誘導を行い混雑解消につとめる予定と言われ、審議会も開店後の検証を求めていましたし、今後も課題があれば、声を届けていかなければと思います。
私たちは、地域の昭和小学校の学校長、PTA会長とともに、私が会長をさせて頂いている学校運営協議会会長、校区交通安全会議会長の連名による大規模店舗立地法に基づく意見書で指摘した下記項目のチェックを今後も行っていきたいと思います。
① 周辺住民、通勤・通学・通園者の交通安全上への配慮から、敷地北側生活道からの出入り口は、禁じて頂きますようお願いします。
② そのための措置が講じられたとしても、警備員の十分な配置を行い、円滑な運用を図って頂きますようお願いします。
③ 営業時間は、防犯上の配慮、敷地周辺の道路混雑回避に向けた検討を行い、可能な時間短縮を図って頂きますようお願いします。
| 2月17日「遅ればせながらの県政報告をただいま配布準備中」 |




20日から開会される県議会2月定例会を前に、ようやく県政かわら版第75号の発刊に至ります。
印刷は出来上がりましたが、現在、いろんな方のお手伝いを頂きながら郵送や配布の準備をしています。
今週末から来週にかけてお届けできるのではないかと思います。
今回は、9月定例会での私の一問一答の質疑の報告と12月定例会における特定利用港湾の指定同意の撤回を求める請願のことが同時報告になっており遅れて申し訳ありません。
また、知事との県政意見交換の報告も最終面に掲載させて頂いています。
いつものように文字数の多い紙面で読みづらいかもしれませんが、ご一読いただければ幸いです。
なお、郵送や配布より一足早くこちらからもご覧いただけますので、よろしくお願いします。
| 2月16日「県新年度予算の4Sプロジェクトには期待よりも不安が」 |
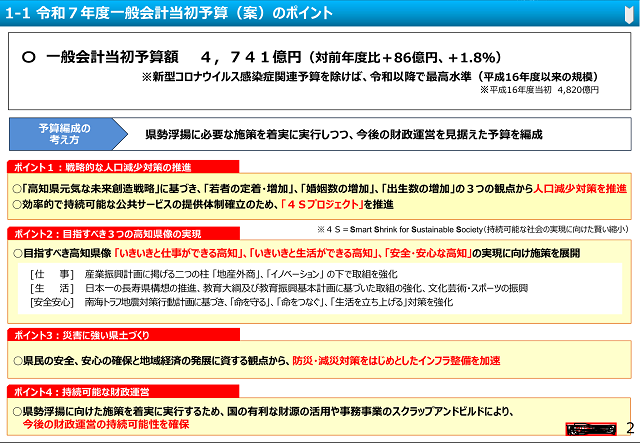

県は、人口減少対策に重点を置いた「積極型」の総額は4700億円余りの2023年度当初予算案を公表しました。
この予算案は、2004年度以来の規模で、新型コロナ関連の予算を除けば、浜田県政となってから、最大のもので、「活力創造予算」として、人口減少の歯止めを図り、特に若者人口の回復を狙い、元気で豊かな高知を実現するとの意向を示しています。
また、この予算案には「スマートシュリンク(賢い縮小)」という戦略が掲げられており、公共サービスの見直しを通じて持続可能な社会の実現を目指しています。
4S戦略のプロジェクトとして、「消防広域化」「周産期医療体制の確保」「県立高等学校の振興と再編」「地域公共交通の確保」「国保料水準の統一」「公共サービスの確保」「地域産業の持続性の確保」「地域の維持・確保」などがあり、具体的な施策として、15消防本部を統合する事業に2900万円、公共交通の確保に2300万円が計上されるなどしています。
「賢く縮小」というが、「人口減少や将来不安がある中でも、賢く縮んでいくことで、必要なところは伸ばす」ことができるのかどうかは、余程慎重な議論が必要だと考えざるをえません。
さらに、老朽化した県民体育館の再整備に3700万円やJ3参入を果たした高知ユナイテッドSCへの財政支援などに1億1900万円が充てられる予定です。
県民体育館の再整備や旧南中高等学校のグランドの有効活用では、津波浸水域での利活用にはどのような災害対策を講じるのか、そして被災時の避難場所としての活用なども十分に検討してもらいたいものです。
これから十分に、新年度当初予算案を検討の上、2月20日開会の2月議会に臨んでいきたいと思います。
28日(金)15時頃からの代表質問で登壇する予定ですので、準備を本格化させていかなければなりません。
| 2月14日「いいかげん能登半島地震の教訓に学べ」 |
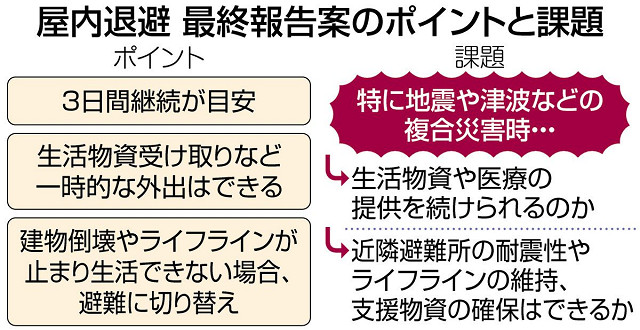
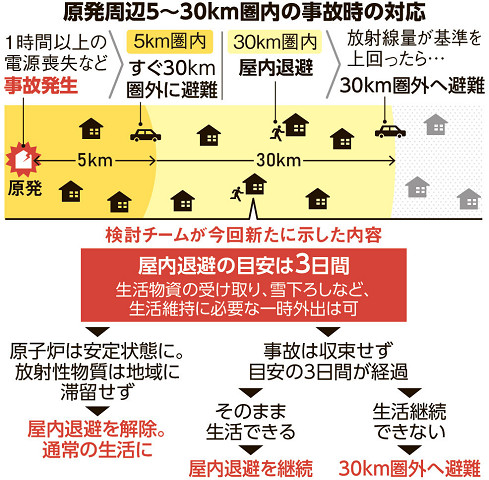 原発事故が発生した場合に、屋内退避も移動も困難な場合があると痛感させたのが能登半島地震ではなかったのでしょうか。
原発事故が発生した場合に、屋内退避も移動も困難な場合があると痛感させたのが能登半島地震ではなかったのでしょうか。
にもかかわらず、原発事故時に住民の被ばくを低減させる目的の屋内退避のあり方を議論したという原子力規制委員会の最終報告書案は、自宅などで屋内退避を続ける期間は3日間を目安とし、建物倒壊やインフラが止まり、とどまれない場合は国の判断で避難に切り替えることなどとして、地震などの複合災害時に、物資や医療の支援を続けられるかなど実効性には疑問を残したままのようです。
「原子力災害は多くの場合、地震などとの複合災害で発生する」と想定し、その上で「人命の安全を第一」とし「自然災害に対する安全確保を優先する」との考え方を明記しながら、屋内退避中に物資の供給が滞ったり、家屋が倒壊したりした場合について具体的な行動指針は示されていません。
原発事故と津波や地震などの複合災害が起きた時の対応について「残されている課題」と認めながら、能登半島地震では多くの住宅が損壊し屋内にとどまれず、避難計画はほころんでいるにもかかわらず、原発の再稼働は進んでいます。
屋内退避が難しいと判断され、多くの人が一斉に避難すれば、大渋滞を引き起こすし、道路が寸断されたような状況では避難すらできないのが現状です。
国内では、東電福島第1原発事故後に作られた新規制基準下で8原発14基が再稼働しているが、今も事故が起きれば、混乱と被ばくが避け難い状況にあり、不十分なままの避難計画で、国は運転を認めている形です。
そんな中での、実効性のない行動指針しか示されない最終報告書案が容認されていいのでしょうか。
| 2月13日「求められる南海トラフ地震への備えの多様化と加速化」 |
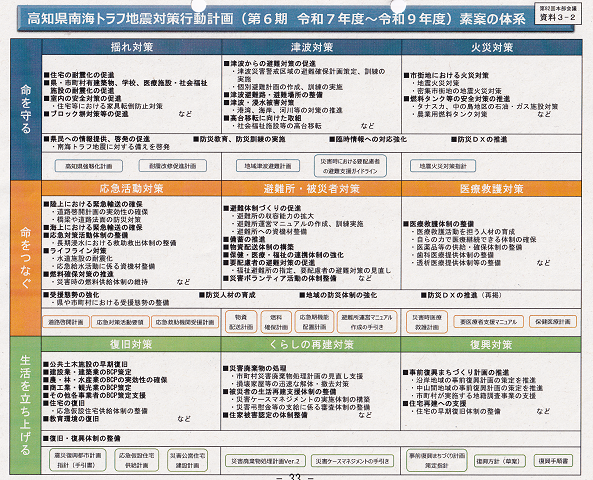 昨日は、第82回南海トラフ地震対策推進本部会議が開催されたことが新聞記事にもなっていますが、合わせて高知市長期浸水対策連絡会が開催されています。
昨日は、第82回南海トラフ地震対策推進本部会議が開催されたことが新聞記事にもなっていますが、合わせて高知市長期浸水対策連絡会が開催されています。
今後、いずれも本格化する対策の方向性を定めていく上で大変重要な会議であり、傍聴したかったのですが、私は2月定例会の会派議案説明会のため、傍聴に参加することができませんでした。
事後に資料を見せていただく限り、毎年新たな自然災害における教訓もどのように行動計画の中に盛り込むのか、年々取り組み課題が多様化しているように思われます。
また、これまでも議会で質問や指摘をしてきた津波火災、長期浸水対策、仮設住宅確保、事前復興まちづくり計画や要配慮者支援対策、災害ケースマネジメント等それぞれの課題の具体化も急がれます。
それらを踏まえて、南海トラフ地震対策第6期行動計画(2025~27年度)案では、津波早期避難意識率や住宅耐震化率を上げ、3年間で想定死者数を現状の4割強に当たる約3500人まで減らす目標を立てていまする
長期浸水対策では、長期浸水域内の避難所での衛生対策、要配慮者の緊急避難対策の課題や福祉避難所の確保、さらには広域避難の課題、救助救出活動の後方支援の問題など様々な課題がまだまだ途上であると言わざるをえません。
昨年、インフラの整備状況が長期浸水面積や止水・排水日数にどう変化をもたらすかの推算で優先エリアにおいては、発災から排水完了までに要する日数が13日から31日と平成25年当時の検討結果からは大幅に短縮されていますが、さらにこれらを短縮していくための取り組みが必要であろうかと思います。
いずれにしても、これらの南海トラフ地震対策第6期行動計画案や長期浸水対策等の素案を十分に検討して、2月定例会での意見反映に努めたいと思います。
なお、南海トラフ地震対策行動計画素案については、パブリックコメントも求められますので、ぜひ県民の皆さんもご検討・ご意見を頂けたらと思います。
| 2月11日「事実から戦争の愚かさを学び「建国記念の日」に反対する」 |
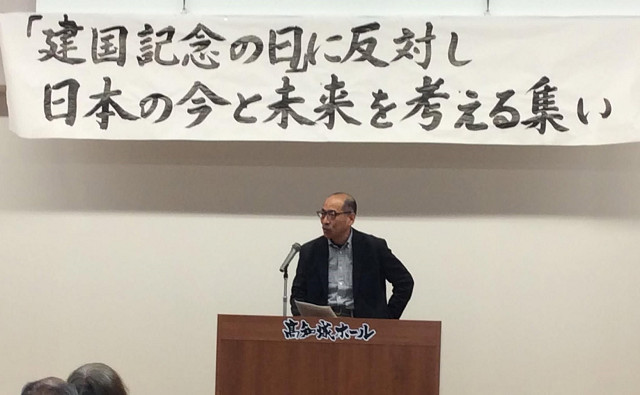
 今日は、「「建国記念の日」に反対し、日本の今と未来を考える集い」に、150名の県民の皆さんとともに、参加してきました。
今日は、「「建国記念の日」に反対し、日本の今と未来を考える集い」に、150名の県民の皆さんとともに、参加してきました。
反対の声を無視する形で「建国記念の日」が制定されて59年が経ちました。
紀元前660年に神武天皇が天皇に即位したと伝承されていることを理由に定めていますが、その時代は日本の最古の古文書と言われるものからでさえ1000年以上もさかのぼる時代であり、科学的に事実とは確認・証明できないのに「記念の日」として、「神話」や「天皇制」「戦前」、そして「戦争」などの賛美に使われている現状を、私たちは憂い続けてきました。
その賛美される戦争の実相とはどのようなものだったのか、高知県で行われた高知大学小幡先生の「忠霊塔などの実証的な研究」の成果から問い直す学びの場となりました。
研究し尽くしても、「軍・戦争と高知」については、分かっていないことが多く、まだまだ探求し続けなければならないと指摘されます。
史実・事実からえられた知見から、戦争で何が犠牲にされてきたのか、そして繰り返してはならないことを明らかにしなければなりません。
| 2月10日「生きづらさを抱えた家庭を支え、子どもたちを大切に」 |

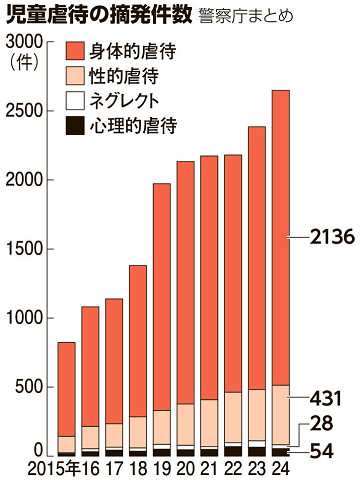 子どもたちを巡る悲しい記事が、続いています。
子どもたちを巡る悲しい記事が、続いています。
1月29日には、2024年の自殺者数(暫定値)は、小中高生が527人と、統計のある1980年以降で過去最多となったとのことです。
全体の自殺者数は2万268人と前年の確定値より1569人(7.2%)減り、2年連続で減少している一方、コロナ禍以降子どもの自殺が高止まりしているという状況です。
特に中高生の伸びが顕著で、人口動態統計によると、10~30代の死因はいずれも自殺が最多となっており、自殺対策白書によると、日本を含む主要7カ国(G7)各国の10~19歳の死因で1位が自殺なのは日本のみという実態です。
22~23年の小中高生の自殺者のうち、自殺未遂をした時期が1年以内だった子どもが過半数だったことから、こども家庭庁は自殺未遂をした子どもや家庭を支えるための調査研究を新たに行うこととしています。
また、警察が昨年1年間で、児童虐待で親などを摘発した件数は2649件(暫定値)に上り、前年から11.1%増えて過去最多になったことも昨日報じられていました。
摘発件数は増加傾向にあり、この10年で3.2倍になり、昨年の摘発件数の内訳は、「身体的虐待」が8割を占め、次いで「性的虐待」16.3%、両親間での暴力といった面前DVなどの「心理的虐待」2.0%、「怠慢・拒否(ネグレクト)」1.1%となっています。
それでなくても「助けて」と言いづらい環境にある子どもたちが「助けて」と言える社会にしていくために、おとなが変えていかなければと思いますが、子どもの自殺支援をされている方は、子どものSOSに気づく立場の大人も相談や助けを求めることができず「苦しい思いをし、孤立している可能性がある」と指摘されています。
「生きづらさを抱えた子どもの背後には生きづらさを抱えた親がいることもある。家庭全体を支えていく視点が大切だ」との言葉を受け止めながら、この社会と向き合っていかなければと思います。
| 2月9日「昭和小防災オープンデーの学びを家庭で、地域で共有へ」 |








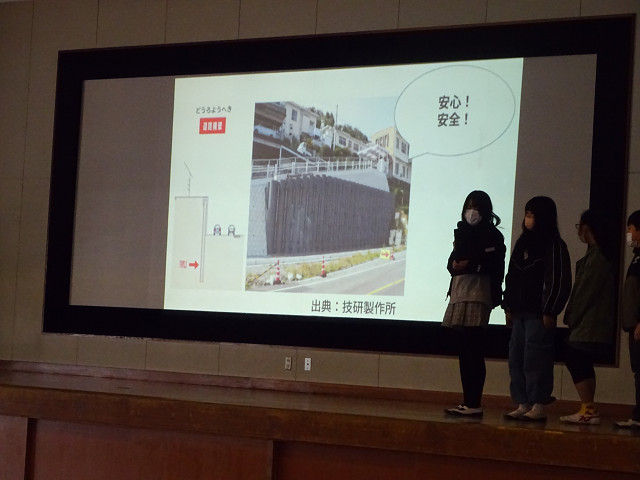

昨日は終日「昭和小防災オープンデー」の開催にあたっていました。
スタッフとして、下知地区減災連絡会だけでなく、たくさんのPTAの皆さんにお助けいただき、何とか全てのプログラムを子どもたちや地域、保護者の皆さんに体験して頂きました。
午前の部は、運動場でピースウィンズ・ジャパン(PWJ)による災害救助犬デモンストレーション、高知消防下知分団によるプール放水体験、消防局東署・中央署によるはしご車救助訓練・煙体験・救助工作車・水難救助車、日産サティオ高知による電気自動車給電デモ、トラック協会による起震車体験に参加して頂きました。
災害救助犬は、昨年能登半島地震で出動していたために、参加が叶わなかったが、今回は参加してくれて、8回にも及ぶ探し当てるデモンストレーションを行ってくれて、子どもたちも災害救助犬の果たす役割を学んで頂きました。
午後からは、13時20分地震発生、シェイクアウト訓練、屋上への避難開始などを行った後は、体育館で5年生の防災学習の成果発表が行われました。
地域や保護者の皆さんの避難訓練には、昨年を大幅に上回る皆さんに参加頂きました。
体育館では、PWJさんから5年生に笛付防災ホイッスルが寄贈され受け取った5年生が「これから防災活動に使っていきたい」と謝辞を述べられました。
私は、地域を代表してお話をさせて頂き、能登半島地震の被災地珠洲市の正院地区の子どもからのビデオメッセージを届けさせていただきました。
その後は、5年生の防災ブースで、「1組」防災バッグ・新聞紙クイズ・避難生活・クロスロード・防災カードゲーム・防災クイズ「2組」学校の備蓄品・津波避難ビル・段ボールベッド・地震の歴史・劇・防災グッズ「3組」防災食・昭和校区のハザードマップ・地震や津波の歴史・お家での防災対策・津波が起こった時の動き・防災アプリのプレゼンが行われ、4年生や保護者、地域の皆さんが見学されていました。
下知地区減災連絡会と市役所、フタガミさんのブースでは「カエルポーズで揺れ体験」「ロープワーク講習」「段ボールベット組み立て」などを体験して頂きました。
参加した皆さんが今日の訓練で「知ったこと」を「備える」ことに繋げて頂けたらと思います。
| 2月7日「森友学園問題は、国は上告断念で一歩踏み出せるか」 |
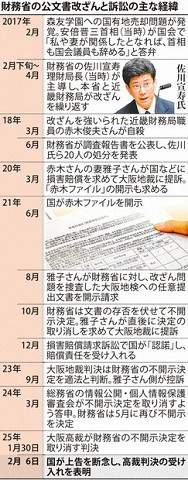 安倍政権下で行われた友達優遇・官僚忖度、隠蔽、改ざん、廃棄というずさんな公文書管理などの代表例でもある森友学園問題にメスが入れられるだろうかと思える動きが出てきました。
安倍政権下で行われた友達優遇・官僚忖度、隠蔽、改ざん、廃棄というずさんな公文書管理などの代表例でもある森友学園問題にメスが入れられるだろうかと思える動きが出てきました。
森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざん問題を巡り、文書不開示とした国の決定を取り消した大阪高裁判決を受け入れ、上告断念を決めました。
これは、石破首相の強い意向で、「本当に強い使命感、責任感を持って仕事に当たったことはいろんな方々から聞いている。自ら命を絶たれたことは本当に重く受け止めなければいけない。赤木さんと遺族の気持ちを考えた時、判決は真摯に受け止めるべきだと考えた」と述べられているが、判決を不服として上告しても、最高裁で判決が覆る可能性は低いとの見方が政府内には強いこともあると言われています。
亡くなられた赤木さんの妻雅子さんは「一歩踏み出すことができた。誰が改ざんを発案し、指示したのか知りたい。『黒塗り』のないものを明らかにしてほしい」と記者会見で述べられているが、首相もその言葉を真摯に受け止めるならば、文書を本当に開示し、内容をどこまで公開するかが最も注目されるポイントとなります。
これで、開示が進まなければ、首相の指示は単なる政治的なパフォーマンスだつたと言われかねません。
赤木雅子さんが言われるように、「一歩は踏み出した」かもしれないが、開示されても黒塗りだらけの文書では意味がなく、文書開示によって森友学園問題の文書改ざんの指示系統を含めて未解明な部分を明らかにしてこそ、二歩目が踏み出せるのかもしれません。
| 2月6日「全国で夜間中学設置自治体・生徒の増加」 |
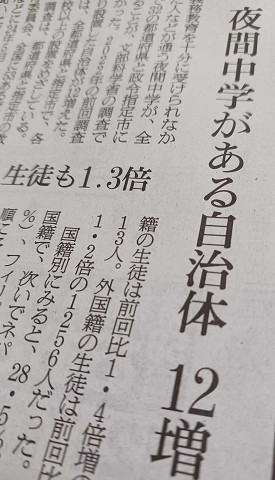
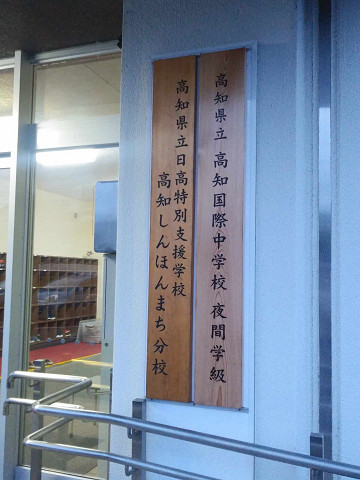 1月16日に、「県立夜間中学の未来を考える議員ネットワーク会議」のメンバーと「夜間中学生の声から学ぶ会」の代表の皆さんで、「県立夜間中学のこれから」について意見交換をさせて頂いたことをここで取りあげました。
1月16日に、「県立夜間中学の未来を考える議員ネットワーク会議」のメンバーと「夜間中学生の声から学ぶ会」の代表の皆さんで、「県立夜間中学のこれから」について意見交換をさせて頂いたことをここで取りあげました。
そんな中で、今朝の朝日新聞に、「夜間中学がある自治体、12増 生徒も1.3倍」との見出しで囲み記事がありました。
義務教育を十分に受けられなかった人などが通う夜間中学が、全国で32の都道府県と政令指定市に設置されていることが、文科省の調査で分かったとのことですが、2022年の前回調査より設置した自治体が12増えています。
全国53の夜間中学の24年5月1日時点の状況では、夜間中学に通う生徒は1969人で、前回の1558人の約1.3倍に増えています。
このうち、日本国籍の生徒は前回比1.4倍増の713人で、外国籍の生徒は前回比約1.2倍の1256人だったとのことです。
国籍別にみると、28.5%が中国籍で、次いでネパール、フィリピンの順に多く、国籍を問わず、特に10~30代の生徒が増えているそうです。
夜間中学で学ばれている理由としては、日本国籍の人では、不登校などの事情があり学び直したい人が増えているとみられ、。外国籍の人では、日本語の勉強や日本の高校入学をめざして学ぶ人が多いとのことで、国は、全都道府県と指定市で、各1校以上の設置をめざしています。
高知で、夜間中学の開校を求めていた時の「夜間中学開校に向けての学習会」に参加していた入学希望の女性が述べられていた「分かった素振りをしないといけないような、ウソをつかせないといけない学校づくりをするのなら夜間中学は必要ない。学ぶ仲間の笑顔が絶えない、通いやすい夜間中学校」が、全国に広がってもらいたいものです。
| 2月5日「『現状維持』に留めず、真摯な議論を」 |
 今朝の新聞で、昨日の県議会の議員定数問題等調査特別委員会のことが、記事になっていました。
今朝の新聞で、昨日の県議会の議員定数問題等調査特別委員会のことが、記事になっていました。
それぞれの会派が独自に意見を出したものですが、私たち県民の会と共産党会派以外は「現状維持」に終始しているようです。
私たちの会派では、昨年の特別委員会が設置された段階から、地方自治や選挙制度に詳しい早稲田大学政治経済学術院教授と意見交換をするなど会派で何度も議論をしてまとめたものを提言しています。
選挙区割は総定数によって大きく影響を受け、基数も変動することになりますので、公職選挙法を前提とし、逆転選挙区の解消は無論の事、人口を基本としながらも経済・文化・歴史的背景も考慮して、中長期的に選挙区のあるべき姿を示すことが大事だと考え議論してきました。
「選挙区の議員定数」は、現行法を前提とすれば、人口比例を柱に検討を行う事は基本ですが、急激な人口減少や面積などは考慮すべきであり、地域代表制も人口比例の制約の中で最大限尊重される区割りとなるべきだと考えています。
自らの選挙区だけのことではなく、高知県全般にわたる政策決定を行うことが県議会の使命であり、県全体のバランスを考え、将来のあるべき姿を見据え、直近の選挙だけではなく、中長期を見据えた制度改革を議論すべきであり、なによりも県民全体の納得感のある制度改革とすべきであると考えています。
その上で、本県のように人口の少ない議員定数の検討をする場合は、市町村間の合区もより弾力的に進め、基数にできうる限り近づけるような区割りを設定し、「一票の格差是正」に努めるべきで、「宿毛市・大月町・三原村」「吾川郡」選挙区については、香美市や土佐市選挙区などの選挙区と対比すれば逆転現象となっており、強制合区の可能性が示唆された黒潮町や長岡郡・土佐郡選挙区、また任意合区となっている土佐清水市選挙区への対応議論など、前回の特別委員会の議論も踏まえれば、あるべき姿を県民に示し、次期県議会議員選挙での新たな区割り・定数を示すべきだと考えました。
それが紙面でも報道されていたもので、安芸市・芸西村区を合区(定数2)▽香美市区と長岡郡・土佐郡区を合区(同2)▽四万十市区と黒潮町区を合区(同3)▽宿毛市・大月町・三原村区の宿毛市区(同1)と分離した大月町・三原村を土佐清水市区に統合(同1)▽吾川郡区を分離して、いの町は土佐市区に統合(同3)▽仁淀川町は高岡郡西区に統合(同2)▽南国市区(同3)とし、他の選挙区は現行とするものです。
いずれにしても、これはあくまでも県民の皆さんのご意見を頂きながら議論する素案であり、今後特別委員会でも、首長や有識者らの意見も聴取し検討していくこととなります。
県民の皆さんのご意見も頂ければと思います。
| 2月4日「県民の行動につながる南海トラフ被害想定の見直し検討」 |
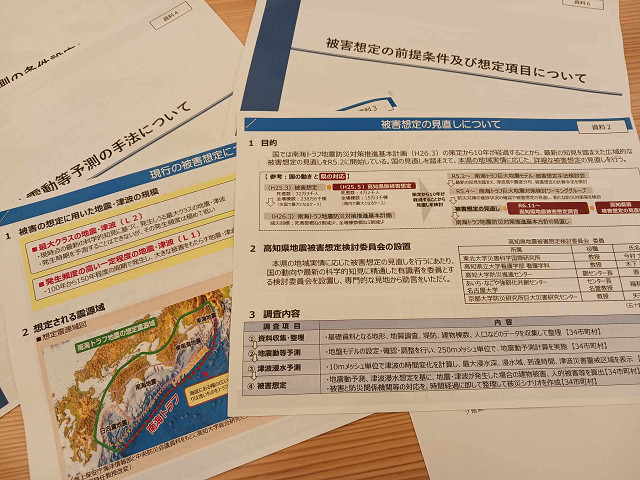
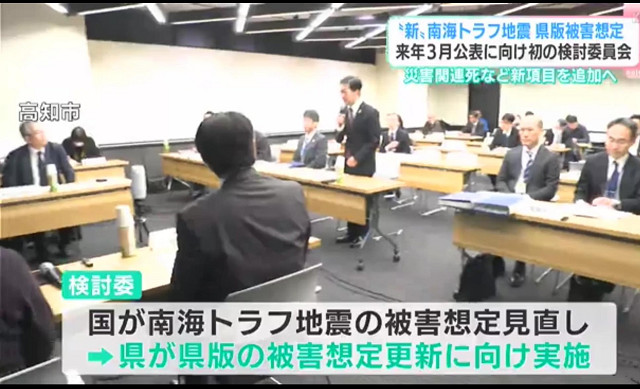

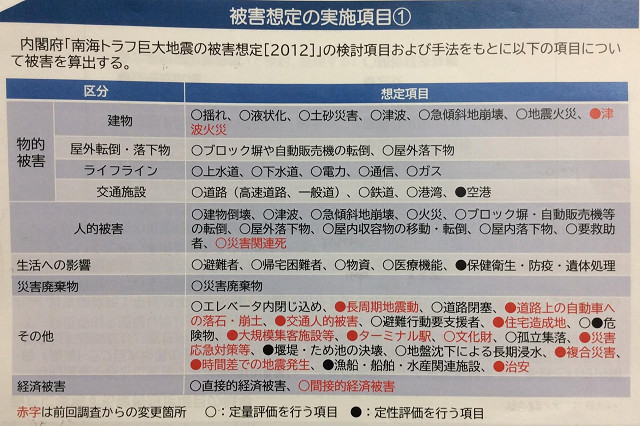
昨日、「県地震被害想定検討委員会」が開催されましたので、傍聴に行ってきました。
県が12年前に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定について見直すためのもので、委員には、今村文彦東北大学災害科学国際研究所教授(津波工学)、木下真里高知県立大学看護学部看護学科教授(災害看護)、原忠高知大学防災推進センター副センター長(地盤工学)、福和伸夫あいち・なごや強靱化共創センターセンター長・名古屋大学名誉教授(地震工学)、矢守克也京都大学防災研究所附属巨大災害研究センター教授(災害社会学)が任命されており、福和伸夫名古屋大学名誉教授が委員長に選任されました。
現行被害想定は、平成25年に国と高知県がそれぞれ公表したが、いずれも策定から10年以上が経過していて見直しの議論が進められており、冒頭の知事挨拶では、2025年度末には検討委員会の報告結果を出し、それをもとに対策を強化するため「第6期南海トラフ地震対策行動計画」を改定することにも言及されました。
事務局が提案した「被害想定の見直しの趣旨」「現行の被害想定」「地震動等予測の手法」「津波予測の条件設定」「被害想定の前提条件及び想定項目」などについて、それぞれの委員から補強意見が出されました。
12年前に出された想定以降、住宅耐震化、津波避難タワーと避難路、堤防の整備など一定の対策の効果を踏まえて、新たな想定がされるが、逆にこの間前回想定には踏まえられていなかった課題も「被害想定の実施項目」として踏まえられることになります。
委員からも出されていた災害関連死や長周期地震動、複合災害など以外にも津波火災などをはじめ14項目が新たに想定項目として追加されています。
相当多岐にわたる被害想定項目ですが、矢守委員の「この想定で諦めるのではなく、行動計画に結びつけ、県民の行動に結びつけて欲しい」との意見とも通ずるが、福和委員長が指摘されていた「これまでは自治体が頑張るための被害予測になっていた。県民の行動を促すようなものに変えないといけない」という指摘も重要な視点であると思います。
6回程度開催される検討委員会の議論を注視し、可能であれば委員会の議論を議会で補強していきたいと思います。
| 2月2日「地方自治、地方財政のあり方にみる縮減社会」 |



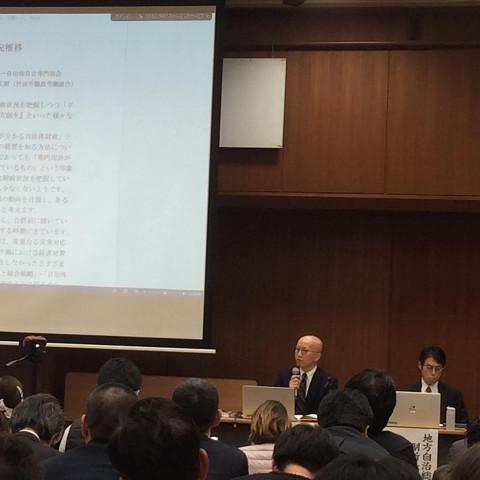
1月30日~31日にかけて東京で、「地方自治総合研究所設立50周年記念シンポジウム」と「2025地方財政セミナー」に参加してきました。
「地方自治総合研究所設立50周年記念シンポジウム」では、1974年3月、地方自治問題を総合的に研究する機関として設立された地方自治総合研究所は、地方自治に関し、幅広い民主的な立場に立って、長期的かつ総合的に理論研究を行う機関として地方自治に関心を持つ人々の結合の場となること念頭において設立され歴史に言及されました。
飛田副所長から「自治総研の歩みとこれから『歴史の峠』の先の道筋」と題した基調講演を受けた後に、駒沢大学内海麻利教授、東京経済大学佐藤一光教授、前多摩市議の岩永久佳さん、総研飛田副所長をシンポジストとして、北村自治総研所長の進行でシンポジウムが行われました。
各シンポジストからの提言には、考えさせられることが多くあり、今後とも自治総研の果たす役割の大きさを改めて感じさせられました。
そして今、縮減社会の中における地方自治のあり方を考えていく上で、改めて現場に視点をおいた研究が必要であることも確認されました。
私たちも、日ごろ自治総研の研究を学ばせていただきながら、県政の課題を見直していくことも多々ありますが、これからも自治総研の果たす役割を期待しながら、研究成果に学ばせて頂きたいと思います。
また、31日の「2025地方財政セミナー」では、元総務大臣で大正大学地域構想研究所所長の片山善博先生から「透明性と説明責任を重んじる財政運営」と題した記念講演をいただきました。
午後からは,総務省自治財政局財政課長から「令和7年度地方財政の姿」について、説明頂きました。
そして、大分県本部自体専門部会メンバーで竹田市職労の園田さんから「地方財政分析の実践報告〜大分県内自治体の財政状況推移」と言うことで経常収支比率の大分県内の自治体における推移からその傾向等についてお話をいただくとともに、自治体職員が積極的に財政分析をすることの意義についてお話を頂きました。
そのレポートを審査された自治総研の飛田副所長から、コメントを頂きました。
最後は、自治総研常任研究員の其田茂樹先生から、2025年度地方財政対策の分析とまとめで、2025年度の地方財政におけるその特徴と私たちがどのような視点でその地方財政と向き合っていくのかお話をいただき、2月定例会の質問の参考にもなりました。
| 1月30日「被災者生活再建の財源を渋るな」 |
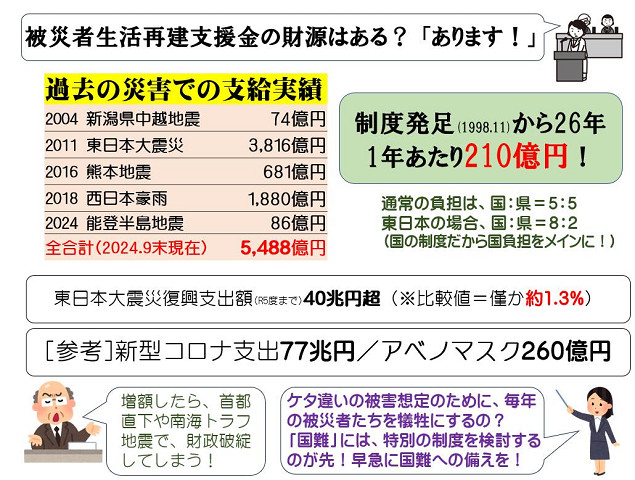
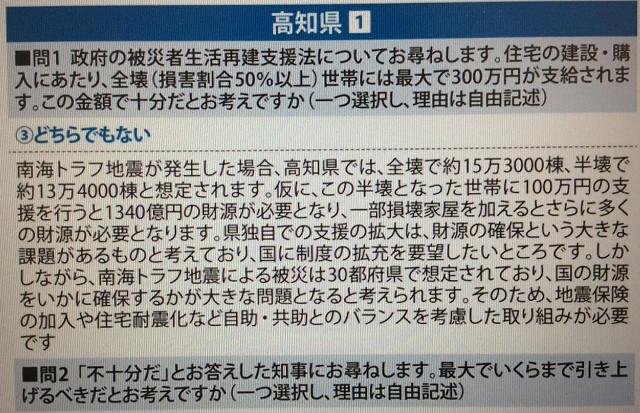
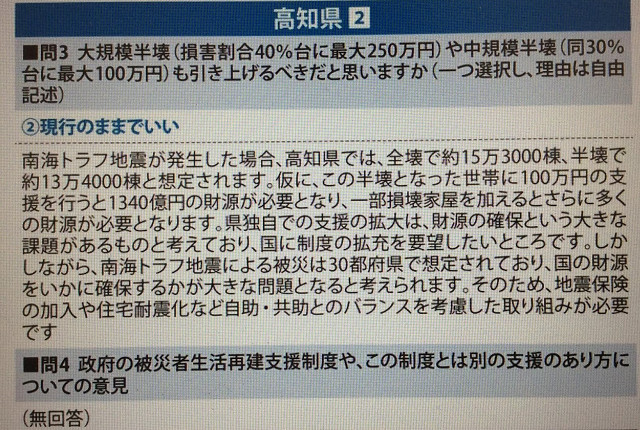
1月27日付毎日新聞で、「住宅全壊に300万円 不十分」「被災者支援 26道府県知事」との見出しで、災害で住宅が「全壊」した世帯に最大で300万円を支給することなどを定めた被災者生活再建支援法について、全都道府県の知事を対象に実施したアンケート結果を公表しました。
結果として、青森県や徳島県など26道府県の知事が300万円では「不十分」と答え、本県など18県の知事が「どちらでもない」と答えています。
また、大規模半壊の世帯に最大250万円、中規模半壊に最大100万円の支給額の引き上げについては、本県は「現行のままでよい」としています。
住宅の再建に当たり、能登半島地震の被災地では「もう少し支援があれば」という声もある中、行政による公助を充実させた方がいいと考える知事が多いのに、本県は財政状況を考慮しての消極姿勢と思われますが、国への働きかけはもちろんですが、被災県民のことを考えたら、国難級の災害にどう向き合うかということを真剣に考えて欲しいものです。
このような状況に対して、日頃から災害ケースマネジメントをはじめ災害復興の在り方についてご指導頂いている兵庫弁護士会の津久井進弁護士は、みずからのFBで、「毎日新聞報道は、そんなことに躊躇せず、「現地が必要だ」という声を強調していて、グッときました。なお、財源論は、実際の数字を見たら、誤魔化しに過ぎない。この26年の平均支出額は年額210億円。アベノマスクより低い!」と、財源はあることをスライドにしていましたので、掲載させて頂きます。
本気で、国会でも議論して頂きたいものです。
| 1月28日「選択的夫婦別姓導入の前向き姿勢はどこへ」 |
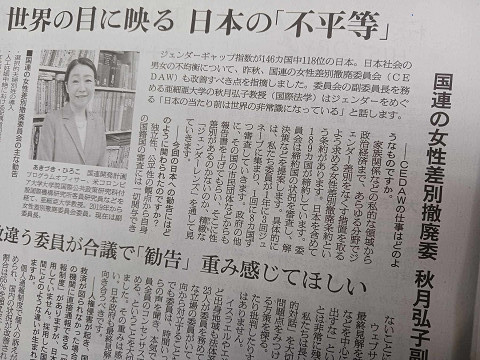 石破茂首相が今国会で焦点の一つとなる選択的夫婦別姓制度導入の是非を巡り、「折衷案」として旧姓の通称使用を法的に広げることも選択肢とする考えを示しています。
石破茂首相が今国会で焦点の一つとなる選択的夫婦別姓制度導入の是非を巡り、「折衷案」として旧姓の通称使用を法的に広げることも選択肢とする考えを示しています。
26日放送のネットメディア「ReHacQ」の番組で、首相は各種世論調査で同姓維持や別姓容認より旧姓の通称使用拡大の支持が多いと指摘した上で、「どちらの考え方にも偏れないなら、折衷案もあり得べしかと思う」と言及しました。
そして、27日の衆院本会議答弁では「家族の一体感や子どもへの影響」も論点だと指摘しました。
昨年の総裁選の際、首相は同姓を強いることによって生じる「不利益」は解消する必要があるとの認識を表明し、「かねて個人的には選択的夫婦別姓に積極的な姿勢を持っている」と明言し、別姓導入に前向きな立場だったが、保守派を中心に自民党内で反対が根強く、配慮が必要だと判断したとみられています。
そのような状況の中で、今朝の朝日新聞では、「世界の目に映る、日本の「不平等」」との見出しで、国連の女性差別撤廃委の秋月弘子副委員長へのインタビュー記事がありました。
「女性差別に誠実に向き合っている国はより解像度の高いジェンダーレンズで自国の状況を見るようになるので、さらに高度で複雑な問題に取り組んでいます。例えば、環境、紛争、ビッグデータ、武器輸出の問題などをジェンダーの観点から改善しようとしています。水不足になった時、災害が起きた時、戦争が起きた時、大きな負担を負い、真っ先に被害に遭うのは女性と子どもだからです。一方、日本は選択的夫婦別姓導入について進展が見られないので4度目の勧告を受けているような状況です。」と指摘されています。
ジェンダーギャップ指数が146カ国中118位の日本社会の男女の不均衡について、昨秋、国連の女性差別撤廃委員会も改善すべき点を指摘しており、委員会の副委員長を務める亜細亜大学の秋月弘子教授(国際法学)はジェンダーをめぐる「日本の当たり前は世界の非常識になっている」と話されています。
いつまでも、諸外国から「世界の非常識」と批判されるこの国の「当たり前」と、石破首相は本気で向き合わなければ、選択的夫婦別姓制度導入など、総裁選だけのリップサービスだけだったと言われかねないことを自覚してもらいたいものです。
| 1月25日「太平洋学園高校の防災授業に期待大」 |


 昨日は、太平洋学園高校の防災授業に、同じ下知地区減災連絡会の高木市議とともにお招きいただき、生徒たちが作成した液状化体験機を体験させて頂くとともに、生徒たちのプレゼンについて意見交換をさせて頂きました。
昨日は、太平洋学園高校の防災授業に、同じ下知地区減災連絡会の高木市議とともにお招きいただき、生徒たちが作成した液状化体験機を体験させて頂くとともに、生徒たちのプレゼンについて意見交換をさせて頂きました。
太平洋学園高校では、災害や減災対策を学ぶ週2コマの選択授業を導入し、自分自身の身を守るだけでなく、周りの人も支えられる力をつけることを目的として、防災教育に取り組まれています。
その過程を通じて、生徒は自身のキャリア形成や学校外市民とのコミュニケーションの場を作ることを目的とされた授業に参加させて頂きました。
自由選択科目として「自然環境と防災」「暮らしと安全」についての科目がある中、今回は、「自然環境と防災」における液状化の体験と学びを通じて、若者をはじめとした県民に液状化の理解を深め、さらには液状化の怖さを知ってもらうアイデアの提言を頂きました。
「web上に液状化の情報を提供するバナーを表示する」「人気アーティストによる啓発」「液状化をVR体験ができるようにする」「液状化が危険であることを知らせる標識の作成」など多様なアイデアにツッコミを入れたり、アドバイスをさせて頂いたりとこちらにも学びの多い授業を過ごさせて頂きました。
高知市や須崎市で地域の訓練やイベントでも、彼らが力を発揮されていることを頼もしく思いました。
| 1月24日「7割の都道府県が日米地位協定改定を求めるのは当然」 |
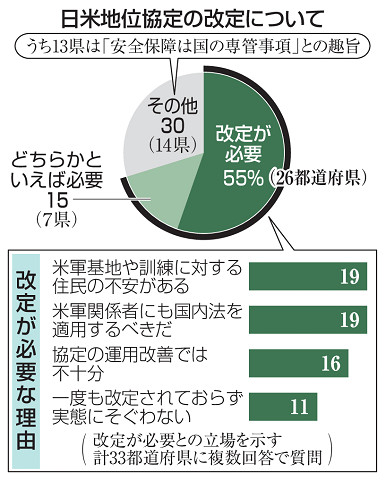 先日、共同通信の配信記事で、在日米軍に法的な特権を認めた日米地位協定について、高知県など7割に当たる33都道府県が「改定が必要」との立場を示したことが、報じられていました。
先日、共同通信の配信記事で、在日米軍に法的な特権を認めた日米地位協定について、高知県など7割に当たる33都道府県が「改定が必要」との立場を示したことが、報じられていました。
多くは、米軍基地や訓練を巡る住民の不安を理由としていますが、日本国内の米兵の事件や米軍機墜落も、日本側の捜査権は強く制約されるほか、飛行高度などの航空法規定が適用されずに米軍機の低空飛行による不安を強いられる米軍専用施設のない21府県も改定を望んでいます。
まさに、これで住民の安心と安全を守れるのかという危機感が地方に広がり、多数の自治体が協定を問題視する実態が浮き彫りとなった今こそ、抜本改定に向け米国との協議を急ぐべきではないでしょうか。
特に、米軍基地の約7割が集中する沖縄では、米兵による性犯罪などが頻発する中、容疑者の起訴前の身柄拘束は今も米側が決定権を握っていることを常に突きつけられてきたが、自治体による有機フッ素化合物(PFAS)の調査でも、米軍基地への立ち入りは極めて限定され、2023年に米空軍オスプレイが鹿児島県沖に墜落した事故では、機体の残骸が米側に渡され、日本側による原因の究明は閉ざされ、米軍機の飛行訓練による騒音、部品落下などに危険と不安を強いられてきました。
もはや、米軍基地や米軍の訓練に対する住民の不安、米軍関係者に国内法が適用されないことに対して、我が事として多くの自治体が問題視し、声をあげ行動に移すべきところに来たとしか言いようがありません。
石破首相は、昨年の首相就任時に、日米地位協定改定について「日米同盟に懸念が生じるとは全く思っていない。同盟強化につながる」とし、「一朝一夕で変わると思っていない」としつつも、「だからといって諦めて良いとは思っていない」と意欲を示していました。
そのことを好ましく思っていないトランプ大統領が就任したからと言って、主権国家として国民の現実の被害や苦しみに目を背けることなく、米軍基地を抱えたドイツやイタリアのように毅然とした関係性を求めていかなければならないと思います。
| 1月22日「次年度当初予算案の詳細注視へ」 |
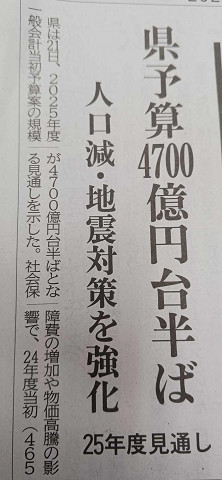 今朝の高知新聞にも、県の2025年度一般会計当初予算案の規模が4700億円台半ばとなる見通しに関した記事がありますが、昨日執行部から会派に対する説明がありました。
今朝の高知新聞にも、県の2025年度一般会計当初予算案の規模が4700億円台半ばとなる見通しに関した記事がありますが、昨日執行部から会派に対する説明がありました。
社会保障費の増加や物価高騰の影響で、24年度当初(4655億6300万円)を上回る見込みとなっていますが、今後知事査定が進み、詳細に詰まっていく中で、2月中旬には予算案をはじめ2月定例会に諮られる議案の説明を受けることとなります。
昨日の説明の中でも、人口減少に適用した持続可能な社会の実現としてスマート・シュリンク・サスティナブル・ソサエティの頭文字をとった「4Sプロジェクト」の推進ということで「持続可能な社会の実現に向けた賢い縮小」として、当面避けられない人口減少に適用するため効率的で持続可能な公共サービスの提供体制確立等への挑戦をするとしています。
その一つが「分娩施設のあり方を含む周産期医療体制の確保」、二つ目に「中央地域の持続可能な公共交通ネットワークの構築と安定的な運営の支援」、三番目に「常備消防組織の業務効率化、現場対応力の強化に向けた消防広域化の推進」などとなっています。
これらの課題の具体化は大事ですが、消防の広域化は、慎重な検討が必要との県民の声が多くなっています。
また、南海トラフ地震対策をしっかり進めるということで、「住宅の耐震化や空き家対策を一層推進する」「災害ボランティアの円滑な受け入れ体制の整備を支援する」「避難所における生活環境の向上のため、トイレカーやキッチンカーなどを導入」「福祉避難所の環境整備のための資機材の購入や円滑な開設、運営のための訓練を支援する」「沿岸部の事前復興まちづくり計画の策定支援を行うとともに、中山間地域にも拡充する」「四国8の字ネットワークなど道路整備を着実に推進するとともに上下水道設備の耐震化を加速化する」「浦戸湾の地震津波対策三重防護など河川海岸堤防の耐震化を推進する」などの項目があります。
中には、27日に知事と県政要望に関する意見交換の課題で要望しているものの具体化やこれまで取りあげてきた課題の整備なども取りあげられています。
日本一の健康長寿県づくりとして、「地域で支え合う医療・福祉・介護サービス提供体制の確立とネットワークの強化を図る」「中山間地域の医療提供体制の充実を図るためのオンライン診療の拡充さらには横展開への支援を行う」「安全安心な周産期医療体制を確保する」ことなどに取り組むこととされています。
教育の充実では、「教職員の働き方改革をよりいっそう進めるため専門的知見を有する事業者によるモデル校への伴走支援を実施する」「不登校対策の推進として、不登校等の児童生徒が自分に合ったペースで学習ができる校内サポートルームの設置」や「不登校児童生徒の学びの機会を確保するためフリースクールへの支援やメタバース上に学びの場を開設」「中山間地域における県立高校の魅力化を図り、全国からの生徒募集の取り組み」の推進・強化が図られることとなっています。
私も、2月定例会では、質問をすることとなっていますので、これら予算の詳細について注視していきたいと思います。
| 1月21日「県立夜間中学生の未来に期待して」 |



昨年発足した「県立夜間中学の未来を考える議員ネットワーク会議」のメンバーと「夜間中学生の声から学ぶ会」の代表の皆さんで、16日に「県立夜間中学のこれから」について意見交換をさせて頂きました。
最初に、所管の県教育委員会高等学校課より現状と次年度入学者の状況などをヒアリングし、情報をどのように各市町村教委や学校現場に伝えていくのか意見交換もさせて頂きました。
市町村教委からの照会や応募状況から、なかなか夜間中学(高知県立国際中学夜間学級)の情報が必要としている県民に届いているのかとの意見も出されていました。
多様な生徒さんが学ばれている中で、以前の中学校で不登校だった生徒が異年齢の方と交流する中での学びも大事だし、それぞれの生徒の困り事と向き合い寄り添っていくなど丁寧な取組が必要である。
また、学ぶ生徒のニーズは教科書の内容だけでなく、工夫した対応が引き続き必要で、生徒の声をしっかり拾っていくことなども運営面の課題として出されていました。
当初から課題であった途中入学も、要件緩和によって、認められるようになり、令和6年度は10名が入学し、現在18名が在学しています。
卒業予定者のニーズをしっかりつかみ、応えられる支援が必要となっています。
なかなか学校が対応できていないことを「学ぶ会」の皆さんがフォローされる中で、生徒さんの悩み事に対応されてきたり、「学ぶ会」の取り組み状況や議員の皆さんからの情報が共有される場にもなりました。
今後とも、自治体と「ネットワーク」、「学ぶ会」の連携で、学びを必要とする県民が入りたい、入って良かったと言える「夜間中学」のあり方を求めて行きたいと確認したことでした。
| 1月20日「黒潮町に学ぶ防災文化」 |




19日は、下知地区の二葉町、若松町、中宝永町三防災会の主催で開催された黒潮町防災研修に参加してきました。
下知地区以外の方もあわせて30人の参加者で、実りの多い研修になりました。
町役場では、情報防災課長から130分程の説明と意見交換に、参加者の多くが教訓を学ばれていたようです。
最大津波34mの想定を突きつけられ、諦めかけていた町民に「避難放棄者を出さない」ために「諦めない。揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ。」との思想から入る防災で、町民の意識を変える防災対策が本気で取り組まれてきたことに、その重要性を感じさせられました。
そして、そのための2012年以降の重点対策として、下記のような取組が列記されていましたが、その一つ一つに思想から入る防災の丁寧さが盛り込まれているように感じられます。
①防災地域担当制
②津波避難タワーなど避難空間の整備
③戸別津波避難カルテ
➃地区防災計画
⑤木造住宅耐震化等の促進
⑥避難所運営マニュアルの作成
⑦防災教育プログラム
⑧防災訓練
とりわけ、参加者の感想からも「戸別津波避難カルテづくりの丁寧さ」「地区防災計画が計画書づくりでなく、計画の中に諦めない思想を具体化すること」「その地区別の取組の共有から始まる『まねっこ防災』」「防災教育の繰り返しと継続で、防災文化を根付かせる」「34mの津波を逆手に取った産業創造」「訓練参加のハードルを下げることになる高齢者が玄関先まで出るだけの訓練になる日本一短い訓練」などなどは、新たな学びになつたようです。
高校生たちの「もっと私たちを頼ってください」という意識が後輩へと継続されたり、「大津波 来たらば共に死んでやる 今日も息(こ)が言う 足萎え吾に」という短歌を詠んでいた高齢者が「この命 落としはせぬと 足萎えの 我は行きたり 避難訓練」と詠むようになったりというのも大きな変化の事例としてあげられていました。
これまでにも、黒潮町の取組として、お聞きしていたことではあるが、改めてその丁寧な取組の中に、防災文化の思想が盛り込まれていることも感じさせられました。
また、防災ツーリズムの支え手でもある佐賀地区の「防災かかりがま士の会」の皆さんからの津波避難タワーでの説明、そして場所を変えての意見交換でも、タワーが特別なものでなく、日常的な生活の中の一部となっていることや、「かかりがましく」おせっかい以上に地域に入り込んだ取組に、考えさせられることも多くありました。
それは、まさに平時のおせっかいが、有事につながる支えあいのしくみになることを、我々も改めて目指していきたいものです。
しかし、黒潮町の行政にしても、地域防災組織でも抱える課題は、他の自治体で取り組んでいる中での課題と共通している部分もあり、そこを交流し学びあう中で、さらに前進させていくことになるという取組ができればと思ったところです。
| 1月18日「震災は終わっていない」 |
 昨日は、早朝から、青柳公園での1.17阪神淡路大震災追悼の集いの開催に追われ、未災地の高知からも犠牲になられた方々への祈りを捧げた一日でした。
昨日は、早朝から、青柳公園での1.17阪神淡路大震災追悼の集いの開催に追われ、未災地の高知からも犠牲になられた方々への祈りを捧げた一日でした。
そして、帰宅した机の上に届いていた「週刊金曜日」1月17日号の表紙に早朝の神戸の追悼会場からラジオで流れていた声の堀内正美さんの写真。
「阪神・淡路大震災から30年 震災は終わっていない」のタイトルに改めて、考えさせられました。
そして手に取った週刊金曜日に特集されていた終わっていない震災として綴られた「被災者支援に取り組んできた俳優・堀内正美さん「他者への思いやり」 今改めて大切にしたい」、「新長田に「箱物」はできても……商店主を苦しめ続ける「権力災害」」、「届かない女性たちの声 30年前と同じ避難所での苦痛」、「進んでいない住宅の耐震化 命を守るための備えを」との見出しが飛び込んできました。
最初の堀内正美さんのインタビュー記事だけでも、胸が詰まってしまいました。
後の記事も、今日の学校イベントが終わったら、またじっくりと読みたいと思います。
30年経っても、震災と寄り添い、災間を生き、南海トラフ地震などと向き合う教訓を実践に繋げていきたいと思わされる一冊です。
| 1月17日「阪神淡路大震災から30年、さらに繋げよう被災地の教訓を」 |

 最大震度7の揺れによって、6434人の命と日常が失われた阪神・淡路大震災から30年を迎えました。
最大震度7の揺れによって、6434人の命と日常が失われた阪神・淡路大震災から30年を迎えました。
私たちは、30年を経た今も、災害で多くの命が奪われ続けるという現実に向き合いながら過ごしてきました。
1995年1月17日以降も、2004年10月23日新潟県中越地震、11年3月11日東北地方太平洋沖地震、16年4月14日熊本地震、18年9月6日北海道胆振東部地震と続き、昨年1月1日の能登半島地震という多様な被害による教訓をけして風化させてはならないとの想いを改めて強くしています。
最優先すべきは命を守ることであり、犠牲者を一人でも減らすために、何ができるのか。
生き残った者の責任として、備えを重ね、社会のありようを問い続けなければならないと言われるが、未災地に暮らす私たちは、その問いかけに応えていくとともに、教訓からの学びを具体的な備えにつなげ、犠牲者を一人でも減らすことではないでしょうか。
私たちが向き合う南海トラフ地震は、昨年から2度の臨時情報が出る中、政府の地震調査委員会は、南海トラフ地震の30年以内の発生確率を70~80%から80%程度に引き上げました。
阪神淡路大震災から20年を迎えた年に、未災地の高知で、教訓を風化させないためにとの想いで、追悼の集いをスタートさせましたが、今朝も、寒い中30名近い方が、青柳公園にお集まり頂きました。
今まで以上に、阪神淡路大震災をはじめ過去の地震災害の教訓を風化させず、教訓を踏まえた備えを真剣に考え、行動に移していきたいものです。
| 1月15日「災害ケースマネジメントと連携」 |
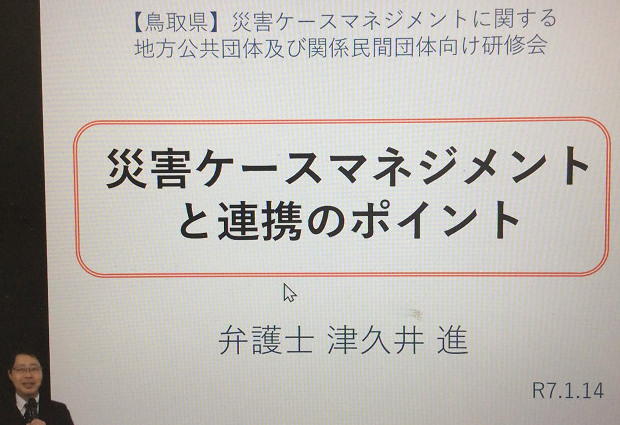 昨日は、内閣府と鳥取県が共催した「災害ケースマネジメントに関する地方公共団体及び関係民間団体向け説明会」のオンライン聴講が可能でしたので、可能な講演部分を聞かせて頂きました。
昨日は、内閣府と鳥取県が共催した「災害ケースマネジメントに関する地方公共団体及び関係民間団体向け説明会」のオンライン聴講が可能でしたので、可能な講演部分を聞かせて頂きました。
災害ケースマネジメントの普及啓発を図るため、関係民間団体を交えた説明会を実施することで知見の共有と平時からの連携体制の構築を行うためということで、全国の数か所で開催されているものです。
災害ケースマネジメントの取組にあたり、官民連携の必要性を学ぶとともに、災害ケースマネジメントの実施方法等を参加者で話し合うことにより、被災者の生活再建支援について考えるためのワークショップも設けられていますが、そちらは会場参加のみとなっていました。
鳥取県における災害ケースマネジメントの社会実装に向けた取組について、鳥取県危機管理政策課の方の報告の後に、導入講義として、日本弁護士連合会災害復興支援委員会前委員長の津久井進弁護士が「災害ケースマネジメントと連携のポイント」について、講演されました。
災害ケースマネジメントのポイントとして「一人ひとり(≠被災世帯)のリアルを把握する」「申請主義を克服するためのアウトリーチ・伴走型支援、声なき声を聞く」「支援の総合化・計画化」「多くの社会資源で重層的に支援する。餅は餅屋で、よってたかって連携し、一人ひとりを支える」「生活再建を図るためという目的を見誤らない」ことが、大事であることが強調されました。
また、事前必聴が求められていた大阪公立大学大学院文学研究科菅野拓准教授もコメンテーターとして参加されていました。
被災者の主体的な自立・生活再建を目指す災害ケースマネジメントと地域福祉などの平時の支援とを連携させ、双方がよくなるフェーズフリーな体制を築いていけたらと思います。
| 1月14日「南海トラフ地震臨時情報・調査終了でも、備えて注視を」 |
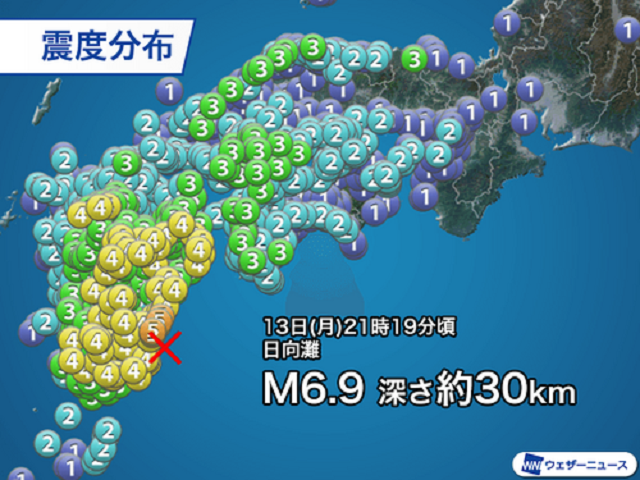
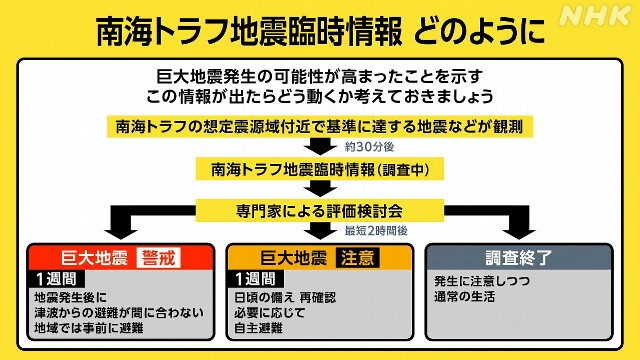 昨夜は、オンラインで全国防災関係人口ミートアップに参加している最中の事務所で、緊急地震速報が鳴り、身構えたところ21時19分頃に日向灘を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生しました。
昨夜は、オンラインで全国防災関係人口ミートアップに参加している最中の事務所で、緊急地震速報が鳴り、身構えたところ21時19分頃に日向灘を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生しました。
緊急地震速報を聞いた時には、1月1日と17日の間に、いよいよ南海トラフかと緊張しました。
結果として高知市は震度2でしたが、結構な揺れを感じました。
津波注意報が出ましたので、オンライン会議は、途中で退席し、津波避難ビルでもあるマンションに引き上げ、マンション内の要所をチェックして情報収集を行いました。
気象庁では、南海トラフ地震臨時情報・調査中を出し、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催し、この地震と南海トラフ地震との関連性について検討しました。
その結果、モーメントマグニチュード6.7の地震と評価し、7.0に満たないことから、南海トラフ地震防災対策推進基本計画で示されたいずれの条件にも該当せず、南海トラフ地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではなかったことから、(巨大地震警戒)、(巨大地震注意)のいずれにも当てはまらない現象と評価し「調査終了」となりました。
ただし、南海トラフ沿いの大規模地震(マグニチュード8から9クラス)は、「平常時」においても今後30年以内に発生する確率が70から80%であり、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から既に約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。
このため、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意し、日頃から地震への備えを確実に実施しておくことが重要ですので、改めて備えのチェックが求められています。
| 1月13日「政治判断でオスプレイの入れ替えか」 |

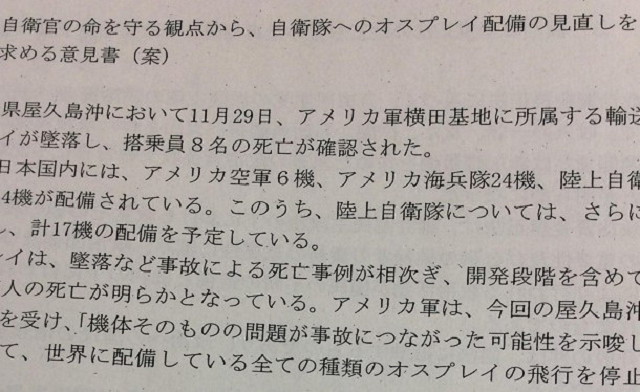 2023年12月定例会で、 オスプレイを運用する自衛官の命をはじめ、県民・国民の生命・財産を守るために、陸上自衛隊へのオスプレイ配備を抜本的に見直すよう求めた「自衛官の命を守る観点から、自衛隊へのオスプレイ配備の見直しを求める意見書」の賛成討論をしましたが、賛成少数で否決されたことがあります。
2023年12月定例会で、 オスプレイを運用する自衛官の命をはじめ、県民・国民の生命・財産を守るために、陸上自衛隊へのオスプレイ配備を抜本的に見直すよう求めた「自衛官の命を守る観点から、自衛隊へのオスプレイ配備の見直しを求める意見書」の賛成討論をしましたが、賛成少数で否決されたことがあります。
しかし、それ以降も、陸自オスプレイは昨年10月、沖縄県の与那国島で離陸の際に事故を起こし、原因解明のため一時飛行を止めたし、11月には、ニューメキシコ州で事故が起きたことを受け、米海軍航空システム司令部が飛行を一時停止するよう提言し、日本政府にも通知しました。
まさに、オスプレイは開発段階から事故が相次ぎ、米軍機は15回の墜落事故で米65人が死亡し、イスラエル等購入を検討した国はあるが、実際には一機も売れず、米国は2026年に生産ラインを閉鎖するとしています。
そんな中で、開発した米国以外で唯一、購入したのが日本なのです。
陸自オスプレイが訓練に登場するのは毎年、数えるほどしかないし、政府は災害派遣での活用を喧伝するが、整地された場所にしか離着陸できず、地面が荒れた被災地での運用には向かないことが明らかになっています。
日本は政治が軍事を統制するシビリアン・コントロールを採用しているが、兵器の選定にまで口を出し、危険で効率の悪いオスプレイを導入したのは明らかにシビリアン・コントロールを逸脱したものと言わざるをえません。
そんな中で、米軍はオスプレイの欠点を克服した垂直離着陸輸送機「V280バロー」を開発し、入れ替えを進めているが、日本ではアメリカの言いなりに政治判断でこれを買わされることになるのかと、心配になるトランプ再登場でもあります。
| 1月12日「今日も阪神・淡路大震災30年に学ぶ」 |
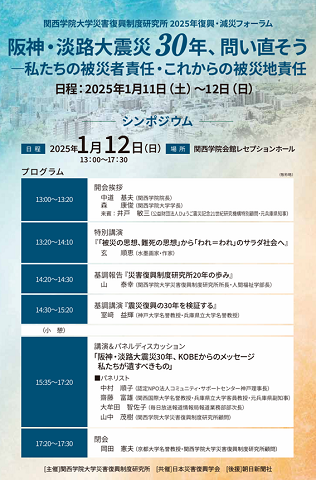
 1.17を週末に控えて 昨日から、設立して20年を迎える関西学院大学災害復興制度研究所が、全国被災地交流集会「円卓カフェ」「KOBEからのメッセージ 私たちが遺すべきもの」と2025年復興・減災フォーラム「阪神・淡路大震災30年、問い直そうー私たちの被災者責任・これからの被災地責任」を開催しており、時間のある限りオンラインで参加しています。
1.17を週末に控えて 昨日から、設立して20年を迎える関西学院大学災害復興制度研究所が、全国被災地交流集会「円卓カフェ」「KOBEからのメッセージ 私たちが遺すべきもの」と2025年復興・減災フォーラム「阪神・淡路大震災30年、問い直そうー私たちの被災者責任・これからの被災地責任」を開催しており、時間のある限りオンラインで参加しています。
しかし、様子の写真撮影やWeb上での公開ができませんので、詳細報告はできません。
私にとっては、母校にこの研究所が設立された2005年に訪ねて以降、阪神淡路大震災をはじめ被災地に防災・減災対策、災害復興に学んできました。
写真も当時のもので、20年前に写したものですから、私も先生方も髪が黒かったなあと思ったりしています。
05年2月定例会で、南海トラフ地震対策条例を制定に向けた議論の中で、「条例化する際には、是非、高知県らしさを盛り込んだ条例としていただくことを要望しておきたい。例えば『揺れと津波への予防と避難と復興までを見通す』『行政の責任と地域の支え合いと県民・事業所の自覚と努力の連携』『防災産業の育成』『高齢県という状況の中で要援護者への支援』『日頃の台風災害予防との連携』など課題は多くある」と「災害復興」への視点を県の防災対行政の中に位置づけることを指摘してきました。
災害復興基本法の制定を求めたり、何よりも復興災害が被災者の生活再建を阻まないようにとか取り組んできました。
そんな思いの中で、1.17を前に開催される復興・減災フォーラムに毎年参加してくる中で、この数年はコロナ禍をくぐって、オンライン参加に止まっています。
今回、テーマとして「被災者責任」、あるいは「被災地責任」という言葉を聞く中で、毎年のように新たな被災地が生まれる中で、その被災地や未災地に「伝える」「届ける」「残す」「つなぐ」ということを阪神・淡路大震災30年から学ばせて頂いています。
| 1月10日「災害用備蓄は避難所により身近な分散備蓄を」 |


内閣府は昨日、都道府県と市区町村ごとの災害用物資の備蓄状況を公表しました。
今回初の調査で、アルファ米やパンなどの主食は全国で計9279万9895食分、簡易ベッドは計57万5204台分が蓄えられているなど内閣府は「主食は一定量が確保されていることが明らかになった」と評価し、ベッドやトイレについても備蓄の支援を進めるとしています。
概要の一覧は写真のとおりですが、都道府県・市町村ごとの詳細は、こちらからご覧いただけます。
昨年元日の能登半島地震では多くの避難所で食料が不足するなど、交通網の寸断により支援物資の輸送も難航しました。
そのことを教訓に、内閣府は24年11月1日時点の指定避難所などでの備蓄状況を、都道府県と市区町村ごとに調べたもので、内閣府は各地の備蓄状況を公表することで、自治体に不足分の確保を進めてもらうものです。
「体育館での雑魚寝を解消するには、簡易ベッドの備蓄をもう少し増やしてほしい」との声もあり、国は簡易ベッドやトイレカーなどの導入費用を補助するため、24年度補正予算に約1000億円の地方創生交付金を計上しており、その一部を充てるとしています。
能登半島地震での教訓から、交通網の寸断により支援物資の輸送が滞ったことから、本県では より住民に近いところに物資が備蓄できるよう市町村での分散備蓄を進めることとしています。
その際に、高知市の長期浸水エリアでは、津波避難ビルなどに居住者や避難者が一定期間取り残されることから、津波避難ビルなども含めて、孤立が想定される地域などの住民に物資が確実に届くような取組も進めていくことが求められています。
| 1月9日「日米は米兵の性暴力事件を本気て断て」 |
 沖縄県警は8日、成人女性に性的暴行を加えてけがを負わせたとして、在沖米海兵隊員の男を不同意性交致傷の疑いで那覇地検に書類送検しました。
沖縄県警は8日、成人女性に性的暴行を加えてけがを負わせたとして、在沖米海兵隊員の男を不同意性交致傷の疑いで那覇地検に書類送検しました。
沖縄では米兵による性暴力事件が相次ぎ、日米が「再発防止」をうたう中で再び事件が繰り返され、地元の強い反発は、当然のことですが、我々も「またか」と怒りの声をあげざるをえません。
日米地位協定では、米軍人・軍属が公務外で事件を起こした場合、日本側の裁判権が優先されるが、米側が身柄を確保していれば起訴まで米側が拘束すると定められています。
しかし、日本側が求めれば起訴前でも米側が引き渡しに「好意的考慮」を払う運用になっているが、男の身柄は今も米軍の管理下にあると言われています。
昨年の事件では、県警の情報が県に共有されていなかったことが問題となり、今回は、書類送検後に米兵検挙の事実を県に伝達したことが明らかになっています。
沖縄県内では昨年、米兵による性犯罪が次々と発覚し、検挙件数は4件(1件は不起訴)で、過去10年で最多となり、県議会は昨年7月、米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全会一致で可決するなど反発が広がりました。
日本政府がアメリカ側に求めた綱紀粛正、および再発防止の徹底についても、飲酒した米兵による器物損壊事件などが那覇市内などで相次いでおり、効果を疑問視する声が上がっています。
沖縄では戦後、米軍関係者による女性への性暴力事件が繰り返されており、2016年には殺人事件も発生し、昨年12月には県内の女性団体が中心となって「県民大会」を開き、約2500人が米兵による性暴力事件に抗議の声をあげたばかりでした。
玉城知事は今回の事件を受け、「女性の人権や尊厳をないがしろにする悪質な犯罪が5件も発生したことは極めて遺憾で激しい怒りを覚える。米軍の再発防止策の実効性に強い疑念を持たざるを得ず、在沖米軍内の規律のあり方が問われる深刻な事態だ」とコメントし、日米両政府に改めて抗議する考えを示しています。
また、林官房長官は今日の記者会見で、この件について、「米軍人による事件事故は地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならない」と述べ、「これまでに米側が発表した一連の再発防止策が実際に再発防止につながることが重要だ。実効性の点も含め、在日米軍に綱紀粛正と再発防止の徹底を働きかける」と述べています。
事ここに至って、再発防止の実効性をあげるための日米両政府の本気度を具体的な行動で示してもらうしかありません。
|
■沖縄での米兵による性暴力事件と関連の動き <2024年3月11日>16歳未満の少女に対する前年末の不同意性交容疑などで、県警が米空軍兵を書類送検【非公表】 <27日>那覇地検が米空軍兵を起訴。外務省が駐日米大使に抗議【非公表】 <4月>岸田文雄首相、国賓待遇で訪米 <5月26日>女性に対する不同意性交致傷容疑で米海兵隊員を緊急逮捕。翌月、外務省が再び抗議【非公表】 <6月17日>那覇地検が米海兵隊員を起訴【非公表】 <25、28日>非公表だった性暴力事件が報道で相次ぎ発覚 <7月5日>米軍関係者による性暴力事件に関し、政府と県警が県への情報共有の運用見直し <12日>駐日米大使らが再発防止策を公表 <9月5日>女性に対する6月の不同意性交致傷容疑で県警が米海兵隊員を書類送検し、県に伝達 <10月1日> 在日米軍司令部が飲酒制限など基地外での行動指針見直し <12月13日> 不同意性交とわいせつ目的誘拐の罪に問われた米空軍兵に懲役5年の実刑判決 <15日>中谷元・防衛相、在沖米軍トップに綱紀粛正と再発防止の徹底要請 <22日>沖縄市で性暴力事件に抗議する県民大会。被害者への謝罪や補償、日米地位協定の抜本改定を求める <2025年1月8日>女性に対する24年11月の不同意性交致傷容疑で、県警が米海兵隊員を書類送検し、県に伝達 |
| 1月8日「交通事故死者数は減少するも、高齢者比率は増加」 |
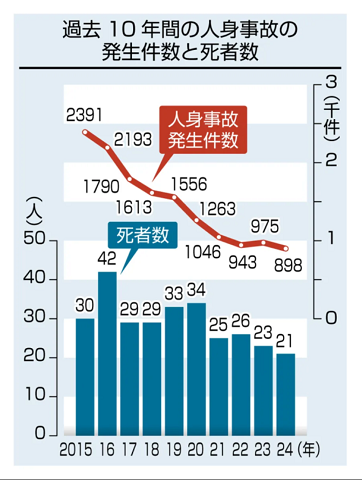
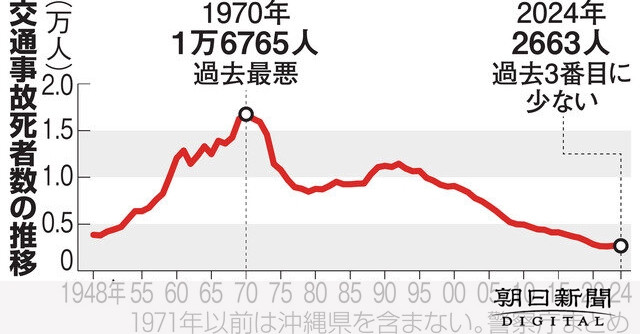
 今朝から、年始の交通安全運動期間がスタートし、冷え込む中、交通安全指導員として皆さんとともに、早朝街頭指導に立ちました。
今朝から、年始の交通安全運動期間がスタートし、冷え込む中、交通安全指導員として皆さんとともに、早朝街頭指導に立ちました。
そこに合わせたかのように、今朝のマスコミ報道で、2024年の全国の交通事故死者数は前年より15人(0.6%)減の2663人だったことが、警察庁の集計で公表されています。
統計がある1948年以降、過去3番目の少なさで、事故件数は1万7138件少ない29万792件、負傷者数は2万1839人少ない34万3756人だったとのことです。
死者が最も少なかったのは22年の2610人で、政府は21~25年度の交通安全基本計画で25年までに死者数を2千人以下にするとの目標を掲げていますが、21年から4年続けて2600人台で推移しており、目標通りには進んでいません。
高知県内の事故死者は、21人で、1971年の198人をピークに減少傾向にあり、2021年以降は20人台で推移し、これまでの最少は23年の23人で、人身事故の件数は898件で前年より77件少なく、1952年の622件に次いで少なかったようです。
都道府県別の死者数では、本県は、最少の島根の9人、そして鳥取15人に次いで少なくなっていますが、死者に占める65歳以上の高齢者の割合は前年比23.6ポイント上昇の71.4%となり、全国平均の56.8%を大きく上回っています。
高齢者の死者に占める比率が高いことや、自転車の絡む事故は39件減の196件発生した中で、負傷者192人のうち151人がヘルメット未着用だったことなど課題は多くあります。
私たち交通安全指導員の目が届くところも限られており、一人ひとりが自覚して交通安全に気をつけて頂くしかありません。
| 1月6日「能登半島連環災害の復興を考える~阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて」 |

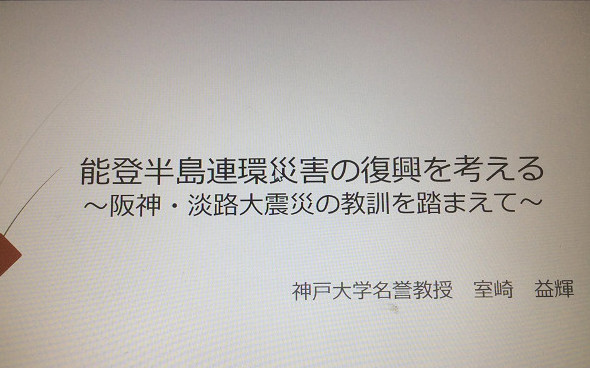
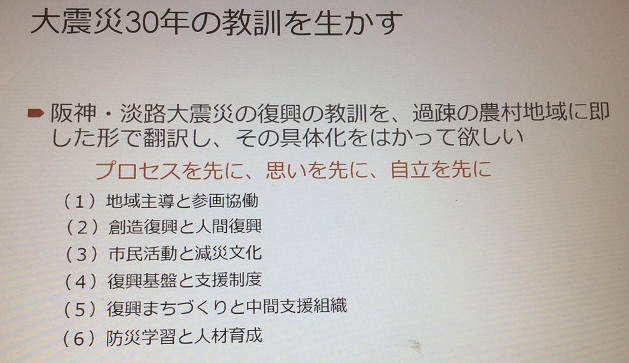
昨日は、「まち・コミュニケーション」の主催で開催された「阪神淡路大震災30年の経験から考察する能登半島地震・豪雨被災地の復興への論点」と題したオンライン勉強会に参加していました。
室﨑益輝先生(神戸大学名誉教授、減災環境デザイン室顧問)から「能登半島連環災害の復興を考える~阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて」と題したテーマで学ばせて頂きました。
30年経過して復興の歴史的評価が見えてくる、また30年経過して復興の課題意識を変えなければならないこともあるとのことで、「能登半島地震から豪雨へと続く災害は、質的にも量的にも前例のない破壊力で前例のない被災をもたらした・・・それだけに前例のない対応、前例のない復興が求められている・・・前例主義からの脱却が不可避」ということが、まさに今問われていると考えさせられました。
そして、私たちが南海トラフ地震からの復興に立ち向かう時には、「前例のない復興」を求められるのであろうと思う時、阪神・淡路大震災から続く国内で連環する災害の復興の教訓を、私たちの地域に即した形で翻訳し、その具体化を図っていくことが求められることを肝に銘じておかなければなりません。
1.17を前に、貴重なお話を聞かせて頂きました。
今年も1月17日には、午前5時46分にあわせて、下知地区減災連絡会では青柳公園で追悼の集いを行うこととしていますが、今年はなおさらの集いになりそうです。
| 1月5日「被災地と向き合う建築家」 |
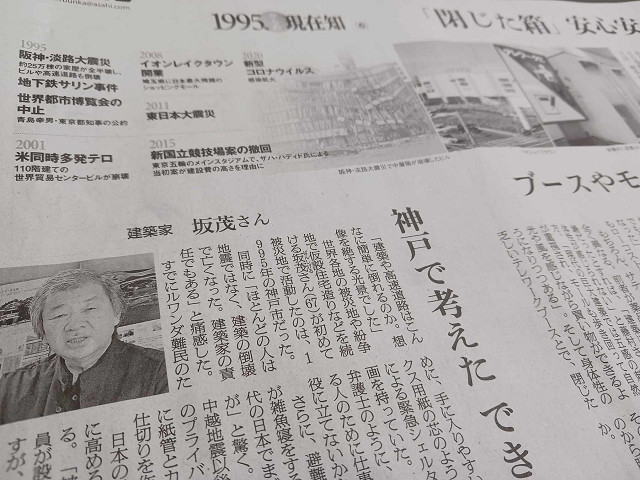
 今朝の朝日新聞の「(1995年からの現在知)「閉じた箱」安心安全でも ブースやモール、分断どうつなぐ」の記事で、「神戸で考えた、できることは」との見出しで、世界的建築家の坂茂さんの記事がありました。
今朝の朝日新聞の「(1995年からの現在知)「閉じた箱」安心安全でも ブースやモール、分断どうつなぐ」の記事で、「神戸で考えた、できることは」との見出しで、世界的建築家の坂茂さんの記事がありました。
建築のことに疎い私が、板さんを知ったのは、能登の珠洲市を訪ねた時に、宝立町に二階建ての仮設住宅(写真は珠洲市のHPに掲載されたものです)ができたとの話を聞かせて頂いた時に、高知でも二階建ての仮設住宅の可能性を求めていただけに関心を持つこととなりました。
その板さんは、「建築や高速道路はこんなに簡単に倒れるのか。想像を絶する光景」を目の当たりにして1995年の神戸市での活動以来、世界各地の被災地や紛争地で仮設住宅造りなどを続けられているとのことです。
神戸で、板さんは「ほとんどの人は地震ではなく、建築の倒壊で亡くなった。建築家の責任でもある」と痛感されたそうです。
そして、避難所で被災者が雑魚寝をする姿に、「近代の日本でまだこんなことが」と驚かれて、2004年の中越地震以後は、避難所でのプライバシー確保のために紙管とカーテンによる間仕切りを作り続けてこられました。
その板さんが、月刊「世界」の1月号で「同じ災害はふたつとない」と題して、災害後の住まいと建築家の向き合い方について、書かれています。
その中には、「建築家には復興の過程でたくさんの仕事が舞い込みます。自分たちの責任とは向き合わず、復興の仕事ばかり意識する建築家は少なくありません。避難所や仮設住宅などの住環境を改善するのも建築家の仕事のはず。それなのに彼らの目には避難所や仮設住宅で過酷な暮らしを強いられる人たちが写っていないように感じました。」とあり、考えさせられます。
そして、「今年6月、珠洲市で石川県産の木材を使用した木造2階建ての仮設住宅を建てました。珠洲市の仮設住宅は原則2年間の入居期間が過ぎても、そのまま使用することができます。被災した人たちは、ただでさえ災害で住み慣れた住居を失って疲弊しているのに、避難所から仮設住宅、災害公営住宅への引っ越しを送り返さなければなりません。避難所の環境を改善し、仮設住宅を組み心地良いの良いパーマネントな状況にできれば、どれだけ被災者の負担が減るか。同じ予算ならすぐに廃棄するプレハブよりも、パーマネントに利用できる住居の方が財政にも、環境にも良いに決まっています。」とあり、南海トラフ地震をはじめ、これからの被災地で生かされなければならないこととして、しっかり受け止めたいものです。
| 1月4日「誰かを『犠牲』にするシステムで成り立つものは疑いうる」 |
 原発報道に携わるある新聞記者が「いったん全てを疑おう」という原発報道の姿勢が決まったことについての記事を読む機会がありました。
原発報道に携わるある新聞記者が「いったん全てを疑おう」という原発報道の姿勢が決まったことについての記事を読む機会がありました。
記者は「見渡してみれば、火力発電所なら東京湾沿いに多数あり、電力会社だけでなく企業の自家発電も無数にあります。」が、「しかし、原発はいずれも周辺人口が少ない地域にだけあり、わざわざ送電ロスもあるのに何百キロも送電線を引いてきているという異常なまでの立地の違いが意味することは、原発が抱えるリスク(危険性)の巨大さにほかならない」と記者は、指摘されています。
「福島で原発事故が起きる前から、電力会社も、許可を出した国も巨大リスクは重々承知していたからこそであり、リスクが現実のものとなった福島第1では、安全対策がいかにもろいものだったか分かっていたにも関わらず、コスト最優先で追加対策をしようとしなかった東電、実施させなかった国のツケがいかに大きいものだったか、既に事実が証明しています。」と言及されています。
そこで、原発関連の現場責任者である記者は「いったん、全てを疑おう」と決意したそうです。
誰かを「犠牲」にするシステの上に成り立つものは、「全て疑う」ことから始まるというのは、2012年に発刊された哲学者高橋哲哉氏の「犠牲のシステム 福島・沖縄」に通ずるものがあることも考えさせられました。
| 1月3日「仮設で「能登復興」の第一歩」 |


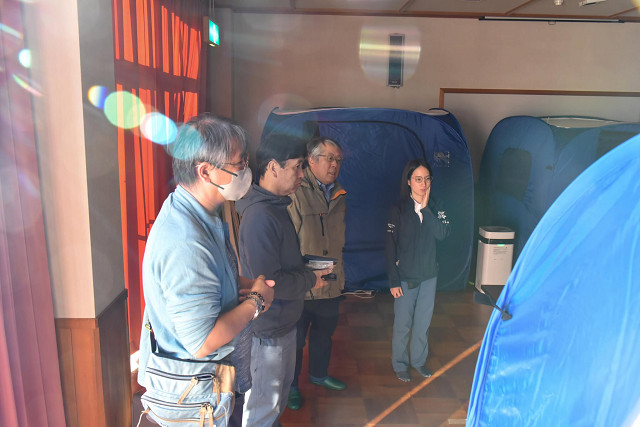

今朝の高知新聞27面に「仮設 能復興の一歩に 住民「現実受け入れ前へ」」との見出しで、能登半島地震から1年、そして集中豪雨なも見舞われた石川県珠洲市若山町の上黒丸地域の今が取材されていました。
私たちも下知消防分団の皆さんと珠洲市を訪ね、集約されてしまう若山町の避難所を案内頂いた時、9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂いたことを思い出します。
お二人が口々に言われていたのは、気づいた時には、浸水が始まっており、やっとの思いで避難したとのことで、「とにかく避難袋を持って逃げるのではなく、身一つで命だけ持って逃げた方がよい」とのメッセージでした。
記事では、11月、23戸の仮設住宅が完成し、散り散りだった約40人が地域に戻り、年末にささやかな「復興祭」が開かれたとのことだったが、あの元気なお二人の高齢者の方も参加されていたのだろうかと思いながら、記事を読ませて頂きました。
| 1月1日「戦後80年、阪神淡路大震災30年の節目に主権者の団結で」 |

 明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます
本年も、よろしくお願いいたします
2025年は戦後80年にあたり、先の戦争についてさまざまな角度から論じられ、戦前元年とも言える年とも向き合わなければなりません。
そして、阪神・淡路大震災から30年でもあり、戦後の80年間に日本で起きた震度6弱以上の地震は71回あり、うち約9割が阪神・淡路大震災の発生した1995年以降に集中していることも明らかになっています。
さらに1995年というのは、戦後50年という節目でもあり、阪神淡路大震災の後には、3月には地下鉄サリン事件が発生し、8月には第2次大戦中に日本がアジア諸国に対して行った侵略や植民地支配を謝罪する「村山談話」が公表されました。
ウィンドウズ95が発売され、インターネット時代の幕が開け、日本経営者団体連盟(日経連)が「新時代の『日本的経営』」というリポートを発表し、「雇用柔軟型」という名のもと「非正規労働者」の拡大が推進され、労働者の貧困化が深化してきました。。
まさに、この年が、現代日本の起点となったとも言えるのではないかと思われます。
さらに、9月には、沖縄では米兵が小学生を誘拐し、性的暴行を行った事件が発覚し、大規模な抗議運動が起き、米軍基地の整理縮小を求める声が高まったが、それからの30年間、日米両政府が基地問題の解決を全く目指してこなかったと思わざるをえない2025年の年明けのような気がします。
日本政府が、戦後50年の1995年から守ってきた日米関係は、日米地位協定を死守して同盟国の軍関係者に幼い子どもを含めた女性の尊厳を踏みにじらせ、沖縄の基地負担の軽減を唱えながら、沖縄の自然を大きく破壊する辺野古移設を進めてきました。
また、阪神淡路大震災から30年の間に突きつけられた東日本大震災の福島原発事故、昨年元旦の能登半島地震の原発震災最終警告にも関わらず、原発回帰への方針転換も図ってきました。
そんな2025年を、主権者の団結で、国民の安全と安心を守らない政府の姿勢を変えて行く年にしたいと思います。
| 2024年「今日この頃」 |
| 2023年「今日この頃」 |