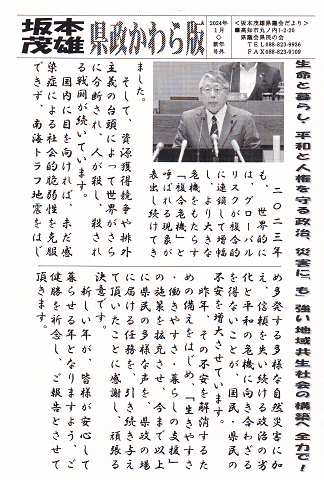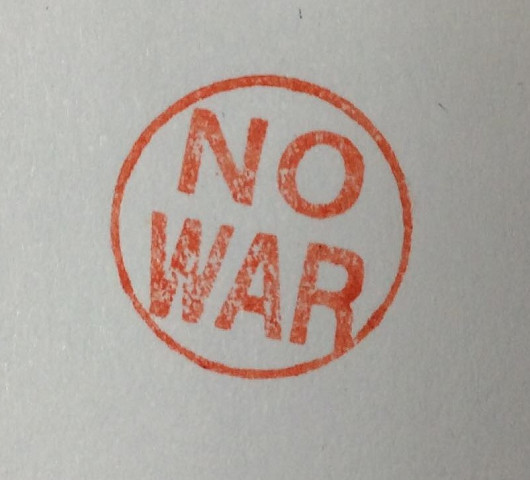| 12月31日「『まさか』を予見し『またか』を断てる明日に」 |
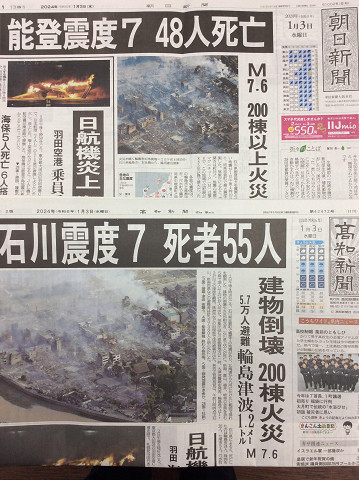
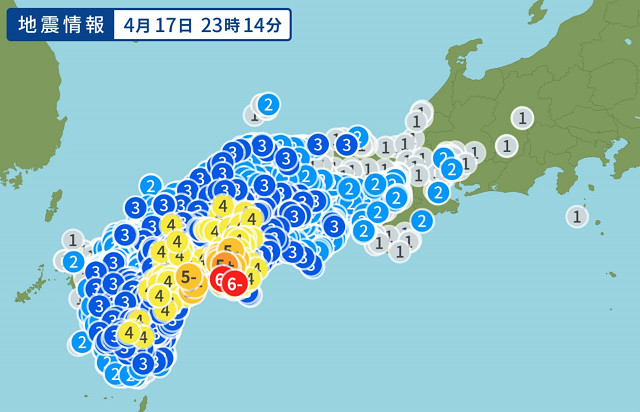

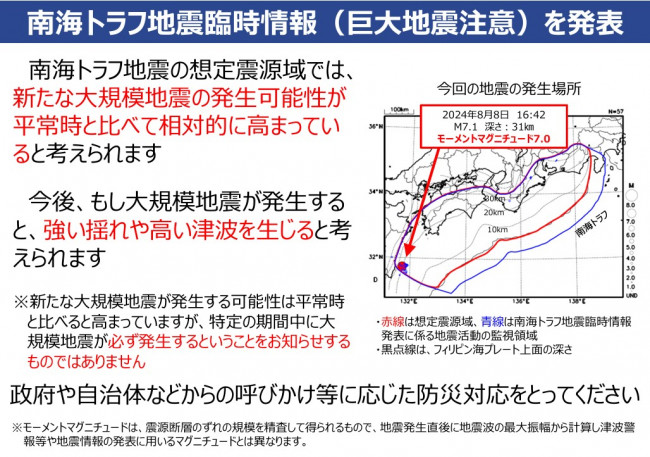
いよいよ大晦日、今年最後のHPとなります。
この一年で、綴ったのは239日分約21.7万字分となります。
今年は元旦に能登半島地震が発生し、4月には県内宿毛市で、現在の震度階級が導入された1996年以降初めての震度6弱以上の揺れを観測しました。
そして、8月8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市で最大震度6弱を観測し、この地震を受けて、気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表し、1週間の初めての臨時情報対応迫られました。
さらに、元旦の震度7地震が襲った奥能登を9月には豪雨災害が襲いました。
なぜこれだけ試練を与えるのだと心が折れかかっている方がたくさんおられた2024年だったと言えます。
自然災害に限らず、あらゆる悲劇・惨事に見舞われたときに、「まさか」と思うことがありますし、人間らしく過ごせない避難所の姿や届かない支援制度の脆弱性を突きつけられた時には、「またか」と思うことがあります。
しかし、「まさか」と「またか」は災害に限らず、あらゆる危機管理に共通してあてはめられる今こそ、「まさか」を予見し、「またか」を断てる明日にしていきたいものです。
下記に、この1年間のタイトルのバックナンバーを掲載しておきます。
12月30日「天災は避けられないが、戦争は避けられる」
12月29日「物価高が生活困窮増加に」
12月28日「辺野古工事の愚行代執行から1年」
12月27日「地震と原発~住民避難の現実~」
12月25日「出生数70万割れで過去最少更新」
12月24日「土佐久礼で防災を学び、街歩きを楽しんで下さい」
12月22日「洪水浸水リスクのある仮設用地の検証を」
12月19日「特定利用港湾指定の同意撤回を求めた請願の賛成討論を」
12月18日「福島、能登を忘れた原発回帰の次期エネルギー基本計画は許せない」
12月15日「避難所の環境整備は喫緊の課題」
12月12日「『特定利用港湾』指定同意撤回を求めて」
12月10日「都市計画道路はりまや一宮線の開通後の検証を」
12月9日「能登地震からの最後の警告を突きつけられる島根原発再稼働」
12月8日「12.8集会「―あの戦争―その時私は・・・」」
12月6日「インフルからの早期復活へ」
12月3日「お国好みの自治体でなく、地域本位に考える自治体に」
12月1日「下知地域で総合防災訓練」
11月30日「県一消防広域化基本構想骨子案公表さる」
11月28日「阪神淡路・東日本大震災復興事業の教訓を能登・南海トラフに活かして」
11月26日「県内精神障碍者の医療費助成へ『等級の壁のない対象拡大』『早期実施』を求めて」
11月24日「寒風の中でマンション防災・避難訓練」
11月23日「日々の取り組みで「我が事」だけでなく「我われ事化」へ」
11月22日「台湾有事と向き合う石垣の特定利用空港・港湾施設でも国の対応は」
11月17日「パレスチナ連帯凧あげ」
11月15日「12月以降も国民の医療を受ける権利が奪われないよう」
11月13日「『ドン・キホーテ』24時間営業は断念、交通事情はさらに改善を」
11月12日「災害時、支援制度の知識が住まい再建の希望に」
11月11日「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名にご協力を」
11月8日「滅多に聴けない事前復興防災講演会にお越しを」
11月7日「困難極める輪島の被災者支援、復興まちづくり」
11月5日「能登半島地震被災地を訪ねて」
11月1日「学校に行きづらい児童生徒と寄り添える体制の拡充を」
10月31日「能登半島地震からの警告を受け止めない女川原発再稼働」
10月30日「自転車の危険運転の厳罰化」
10月28日「自公の過半数割れで政治の変化を注視して」
10月26日「投票に行って、政治を変えよう」
10月25日「高知のバリアフリー観光もこれからもっと前進を」
10月24日「『裏金候補』に『裏公認料』」
10月23日「若者の将来不安に応える政治を」
10月22日「二重被災に苦しむ被災地に寄り添っているのか」
10月21日「自公過半数割れを現実のものとするために」
10月19日「自民党による権力の腐敗・暴走に歯止めを」
10月16日「忘れたらいけないことを刻んで衆院選と向き合う」
10月13日「再審法改正意見書、自民党らの反対で否決」
10月12日「被団協へのノーベル平和賞を各国指導者は真摯に受け止めよ」
10月10日「二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」
10月9日「袴田さん無罪確定、次は狭山事件の再審の扉を開ける」
10月8日「解散総選挙で『変われない自民党』に鉄槌を」
10月7日「化学物質過敏症の理解から、子どもの学ぶ権利、他者理解の大切さを」
10月6日「一問一答の仮の議事録ができました」
10月1日「明日、一問一答で登壇」
9月28日「自民党新総裁は、まずは国会で説明責任を果たせ」
9月27日「県、精神障害医療費助成に本格的検討」
9月26日「一問一答形式で10月2日に登壇」
9月24日「常に存在する複合災害のリスク」
9月23日「沖縄戦の遺骨が語る」
9月22日「奥能登の被災地で仮設住宅も浸水」
9月21日「改憲議論は急ぐべきではない」
9月20日「9月定例会開会」
9月19日「沖縄戦を考える講演と映画」
9月18日「自民党の旧統一教会との新たな組織的関係発覚」
9月15日「国民の信頼回復を図る本気度が見えない自民党総裁選」
9月13日「虐待で亡くなる子どもを救うために」
9月11日「原発事故避難計画を見直さない30キロ圏自治体」
9月10日「現行保険証の廃止扱い自民党総裁選で異議」
9月9日「誰もが"This Is Me"と言えるように」
9月8日「男女共同参画の防災視点で」
9月6日「精神に障がいのある方への医療費助成の実現を」
9月4日「沈み続ける関空の島」
9月2日「問われる新聞と私たちの姿勢」
9月1日「『防災の日』に多様な備えに着手を」
8月31日「台風一過」
8月30日「子どもが追い込まれる前の『逃げる』選択肢」
8月29日「高知市高齢者等避難・避難所開設」
8月28日「『対馬丸事件』の教訓に学んで」
8月27日「本県には最悪コース大型台風10号に備えて」
8月22日「『事前復興』『災害ケースマネジメント』について学ぶ」
8月21日「中身の変わらない自民党本の表紙」
8月18日「被爆体験、戦争体験を風化させずに、戦争させない決意を」
8月17日「8.15に映画「戦雲」を観て」
8月16日「臨時情報『巨大地震注意』呼びかけ終了で、さらに備えの継続を」
8月14日「映画「戦雲」を鑑賞して、沖縄からのメッセージに応える闘いを」
8月13日「『臨時情報(巨大地震注意)』で備える」
8月12日「高知の先駆的女性群像~男女平等と権利のために立ち上がった女性たち~の歴史に学ぶ」
8月11日「『巨大地震注意』臨時情報は空振っても、備えを確かなものに」
8月9日「初の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」」
8月8日「風船爆弾」
8月9日「被爆体験、残留孤児の戦争体験と向き合ってください」
8月6日「核抑止力に依存する為政者は改心を」
8月5日「若者に政治に関心持ってもらうため」
8月3日「欠陥機オスプレイはすぐさま撤退・退役を」
8月2日「文書偽装や再稼働詐欺ともいえる原電の敦賀原発は直ちに廃炉を」
7月31日「『虎に翼』を観ながら、人権問題を我が事として考える視聴者に」
7月30日「最賃は『労働力の再生産を可能にする』生計費であるべき」
7月29日「高知大学図書館『崎山ひろみ文庫』に旧満州の歴史を訪ねて」
7月27日「本県の20歳以下の自殺者は平成以降最多」
7月25日「下知地区での日赤活動の再開を」
7月24日「『選択的夫婦別姓』これでも割れる自民党内」
7月23日「高齢者の住まいの確保のサポートを」
7月22日「被災地支援のリアル」
7月20日「9割が使用する『紙の保険証』を廃止するのか」
7月19日「能登震災は原発災害に対する『最後の警告』」
7月17日「差別克服のために、『学びとであい』」
7月16日「まだまだ老け込む年じゃない」
7月15日「マンション防災から地域防災へ 」
7月13日「『夜間中学生の声』に学ぶ大切さ」
7月12日「沖縄県民の人権を守るためにも日米地位協定の抜本的見直しを」
7月11日「改正されても自民党の裏金体質は変わらない」
7月10日「医療センターでも、周産期医療体制の負担増に四苦八苦」
7月7日「西日本豪雨災害から学ぶ真備地区の取り組み」
7月6日「6月定例会閉会」
7月5日「球磨川氾濫から4年、復興は道半ば」
7月2日「能登半島地震から半年、遅すぎる復旧・復興」
7月1日「新聞紙上での政務活動費公表に誤り」
6月30日「6か月を経た能登から首都直下・南海トラフ地震を見越して」
6月29日「繰り返される沖縄での米軍犯罪は許されない」
6月28日「指示権濫用行使への懸念を意見書で」
6月26日「ドン・キホーテ進出に課題解消せず」
6月24日「沖縄戦の教訓『戦争は民間人を巻き込み、軍隊は住民を守らない』を語り継ぐ」
6月23日「参加・対話・地域主権」
6月22日「6月定例会での知事の決意」
6月21日「地域のことは地域で決める!」
6月19日「地方自治法改悪で国の指示権拡大・自治体関与強まる」
6月18日「2001年4月以降、政権担当しながら自民支持率初の10%台」
6月16日「『県政かわら版第74号』まもなくお届けします」
6月14日「学校給食の無償化を国の責任で」
6月13日「日本のジェンダーギャップ指数は相変わらずの低位停滞」
6月11日「地方自治法『指示権』改悪の強行を許さない」
6月7日「『罹災証明の壁』を超えるために」
6月6日「大阪・関西万博の安全性の総点検を」
6月3日「政治資金規正法改正『再修正案』では、腐敗は断てない」
6月2日「高知で20年前に蒔かれたレスリングの花開く」
6月1日「周産期医療体制の危機」
5月30日「看護職員の養成に注力を」
5月29日「憲法改悪先取りの地方自治法改悪は許せない」
5月28日「線状降水帯に警戒して」
5月27日「ガザ・沖縄から考える構造的暴力」
5月23日「袴田さんも石川さんも無実だ」
5月22日「ドン・キホーテ高知進出に地域の声は届くのか」
5月20日「喰われない自治体になるために」
5月18日「自転車の悪質交通違反にも厳罰」
5月17日「出先機関調査で見える現場のご苦労」
5月16日「孤独・孤立死に至らない社会・地域を」
5月15日「改悪地方自治法の『指示』が自治体へ服従を強いる恐れ」
5月14日「6割が不支持の内閣による政治資金規正法改正は8割が評価せず」
5月12日「成立しても、経済秘密保護法の危険性を批判し続けて」
5月10日「実質賃金24か月連続マイナス」
5月9日「言語道断、水俣病患者の訴え打ち切り」
5月6日「『ケアラー』でも、学び続け、働き続けられるために」
5月5日「50年で半減した子どもたちを大切にする社会を」
5月4日「地震が今年特に多いわけではなく、いつ起きても不思議でないとの備えを」
5月3日「現行憲法理念を国民目線で実現してこそ」
5月2日「前年度政務調査活動報告を県民と共有」
5月1日「増え続ける空き家、『住宅過剰社会』放置のままでよいのか」
4月30日「ひきこもり支援は本人目線で寄り添って」
4月29日「戦争を回避することに尽力した時代があった」
4月28日「人権侵害に苦しむ外国人、歴史から学ぶ戦争しない国へ」
4月26日「世代間の結び目」
4月25日「『消滅可能性』に抗う自治体の元気を」
4月23日「自民党は本気で政治資金規正法を改正できるか」
4月22日「これも防災 復活『おしゃべりカフェ』」
4月21日「マイナ保険証利用消極医療機関を通報」
4月20日「災害ケースマネジメント」
4月19日「県西部地震被害を教訓に」
4月18日「高知、愛媛で最大震度6弱」
4月16日「地元同意なしに再稼働に突き進む東電柏崎刈羽原発」
4月14日「熊本地震の教訓を備えに生かして」
4月12日「緊急事態条項改憲先取りの地方自治法改正に異議あり」
4月10日「万博会場建設現場で、ガス爆発」
4月9日「ダブルケアで離職する前に」
4月8日「種子・農業守ってこその国防」
4月5日「今年度は危機管理文化厚生委員会で頑張ります」
4月4日「被災地の断水で考える水道インフラの事前整備」
能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。
4月3日「7道県16施設の軍事化への一歩」
4月2日「39人の処分で自民裏金プール・キックバック事件の幕引きはさせない」
4月1日「『住まい』の確保の遅れが復興の遅れに」
3月30日「子どもの自殺を防ぐためにも寄り添えるおとなが身近に」
3月28日「特定利用港湾指定撤回に向けて」
3月26日「不登校要因の受け止めに乖離」
3月25日「公共交通こそ我々の社会インフラ」
3月23日「特定利用港湾指定に見る県の強硬姿勢」
3月22日「『特定利用港湾』にはリスクを上回るメリットがあるのか」
3月18日「特定利用港湾の同意に反対を」
3月17日「地方のけじめこそ求められているのではないか自民党」
3月15日「仮の議事録ですが、ご覧ください」
3月13日「震災直後から見続けてきた『震災遺構』」
3月12日「東日本大震災・能登半島地震の教訓で南海トラフ地震に備えて」
3月10日「 道路寸断恐れ109市町村で、避難困難」
3月9日「生涯にわたる男女格差の解消へ」
3月8日「議会質問は、南海トラフ地震対策だけで持ち時間終了」
3月6日「明日、議会質問で登壇」
3月5日「災害時のトイレ問題は人権問題」
3月3日「地区防災計画は今後もさらにコミュニティ防災を強化する」
3月1日「政倫審で実態解明進まず」
2月28日「出生数、婚姻数の減少続く」
2月27日「逃げるな自民『政倫審』は全面公開で開催を」
2月26日「福祉避難所はいざという時に開設できるよう」
2月25日「『県政かわら版』印刷中」
2月23日「県議会二月定例会開会 人口減少対策柱に 地震対策強化の議論も期待」
2月22日「万博のデザイナーズトイレはトイレトレーラーに」
2月21日「地震は止められないが、原発は止められる」
2月19日「8割超の政権不支持の怒りの声を結集して」
2月16日「『共働き・共育ち』は安全高知での本気度を」
2月15日「男女・正規非正規賃金格差の是正も春闘課題」
2月14日「自民党内裏金調査では実態解明は無理」
2月13日「弱者に集中する『災害関連死』をなくすために」
2月12日「映画『雪道』、『建国記念の日に反対し日本の今と未来を考える集い』に学ぶ」
2月11日「昭和小防災オープンデー『防災』で地域と学校をつなぐ」
2月9日「昭和小防災オープンデーで地域と学校の防災交流」
2月8日「過去に蓋する自民党」
2月7日「高知の防災がカリブ、大洋州等の島嶼国にも生かされたら」
2月5日「高校生の考える『地域課題解決策』」
2月4日「マイナ保険証トラブル継続、利用率8か月連続低下」
2月3日「知事自ら能登半島地震を我が事に」
2月2日「能登半島地震から一か月」
1月31日「岸田、麻生に心に滲みこむ言葉は無理か」
1月30日「能登半島地震の今とこれからの課題を南海トラフ地震の備えに活かして」
1月29日「能登半島地震での死亡原因の9割が家屋倒壊」
1月28日「小中高生の自殺者数、過去最高に次ぐ507人」」
1月26日「起きて欲しくないという思いの『想定外』と向き合う」
1月25日「2024年度県予算規模と主要施策の見通し」
1月24日「やっぱり名ばかり改革止まりか」
1月23日「『ふっこう』の現場に学ぶ」
1月22日「中小事業者も、災害前に備えることを学んで取り組んで」
1月19日「派閥解散の本気度は」
1月17日「1.17を『ともに』」
1月16日「港湾の軍事利用には反対」
1月15日「過去の震災の教訓が生かされるように軌道修正を」
1月14日「1.1から29年目の1.17」
1月12日「被災者の権利や利益を守るための『特定非常災害』にも指定」
1月11日「半島地震に見る原発災害の危機」
1月10日「災害関連死をこれ以上拡大させないために」
1月8日「災害関連死を招かないために」
1月5日「能登半島地震に見る耐震改修の高齢世帯での停滞」
1月3日「被害は大きくなるばかり」
1月2日「元旦の能登半島を震度7・津波が襲う」
1月1日「まずは、身近な3.5%の人々とつながる年に」
| 12月30日「天災は避けられないが、戦争は避けられる」 |
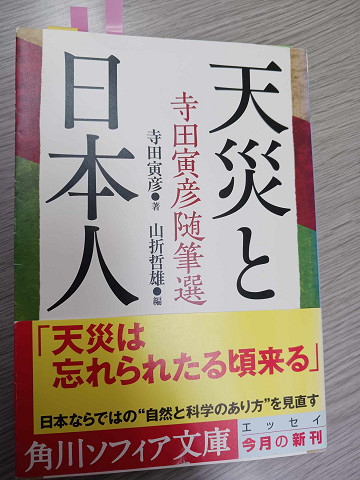 今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。
今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。
中でも、登場する高知県出身の物理学者で随筆家の寺田寅彦の「天災と国防」の中から、「それは文明が進めば進むほど天然の暴威による災害がその劇烈の度を増すという事実である。」「災害を大きくするように努力しているものはたれあろう文明人そのもの」との言葉を紹介しています。
さらに、「災いは時を選ばない。今年は元日に能登半島地震が起き、夏の休暇期に日向灘の地震で南海トラフ地震臨時情報が出された。80年前は大みそかや元日にも東京の本郷区や向島区などで空襲があった。」と言い、「日本は空襲にはおびえずに年越しを迎えるが、世界には戦火にさらされる人々がいる現実がある。」と「戦争と災害」について、考えさせています。
社説には引用されていないが、寺田寅彦の「天災と国防」には「今度の風害が『いわゆる非常時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなかったのは実に何よりの幸せであったと思う。これが戦禍と重なり合って起こったとしたらその結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。」とあります。
その上で、「戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけには行かない」として防災の充実を訴えたことを指摘しています。
社説は、「年が明ければ戦後80年、阪神・淡路大震災30年になる。惨禍に学んだ平和の追求、震災を教訓にした備え、その努力を尽くしているだろうか。」と結ばれています。
しかし、この国が、その努力を尽くさないままに、避けようともせずに戦争する国へと突き進み、震災の教訓を忘れたかのように原発回帰の方向に舵を切ろうとしている今こそ、我々は、改めて寺田寅彦の教えに学ぶ必要があります。
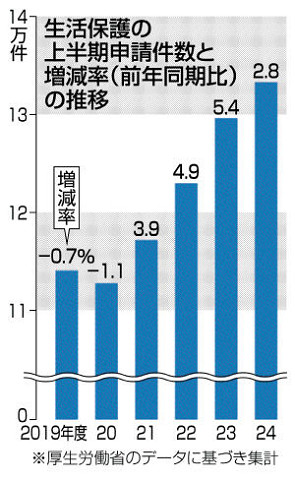 今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。
今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。
2024年度上半期(4~9月)の生活保護申請が前年同期比で2.8%増の13万3274件に上ったことが厚生労働省の公表データを共同通信が分析して、明らかにされています。
新型コロナウイルス感染拡大で景気が悪化した期間や、コロナ禍に伴う生活支援の縮小が低所得者層を直撃した時期の申請件数を実数で上回りました。
賃上げの効果は及ばず、長引く物価高で家計が圧迫されて苦しむ人が多い実情が見て取れます。
現行の生活保護費は、低所得者層の消費実態とのバランスを理由に23年度からの減額が一旦決まったものの、新型コロナウイルス禍や、21年からの物価高が反映されていないとの指摘が相次いだことから、特例で据え置かれた経緯があります。
コメの価格をはじめ、値上がりは広がっており、生活費増を補う視点が欠かせない措置が求められています。
生活保護費を巡っては、安倍政権が13年に実施した保護基準額の引き下げは生存権を冒すものだとして、全国29都道府県で取り消し訴訟が起こされ、地裁では、行政訴訟としては異例の原告勝訴判決が相次いでいます。
政治による恣意的な生活保護費の切り下げは「裁量権の逸脱」として違憲と断じられた判決もあることを政府は重く受け止めねばなりませな。
自治体の水際対策や、全体の中ではごく一部にとどまる不正受給を強調し、周りの目を気にさせる状況も問題視されてきた日本の生活保護制度は、欧米などよりも格段に捕捉率が低い状況です。
この年末年始は最大9連休となり公的機関の多くが閉まるため、困窮や孤立を防ぐ支援が一時的に断たれることも心配されます。

 沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。
沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。
防衛省沖縄防衛局は大浦湾側の軟弱地盤改良工事を今日から始め、7万本以上の杭を海底に打ち込む計画としています。
代執行は地方の自己決定権の剥奪であり、地方自治の破壊につながるもので、法的な対抗手段を失った県の意向を無視して、一方的に工事を進めています。
そして、今年は国が地方自治法を改悪し、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断した場合、自治体に指示権を行使できる特例を設けるという緊急事態改憲の先取りを行ってきました。
さらに、台湾有事を想定した特定利用空港・港湾の指定も含めて、恣意的な運用で地方を従わせる民生利用という名の軍事基地化を全国的に展開しようとしています。
ここに来て沖縄に駐留する米海兵隊の日本国外への移転が動き出し、隊員約1万9000人のうち約9000人が対象となり、第1弾として、グアムへの先遣隊100人の移転開始が発表されました。
しかし、日米が2006年に合意していたものであり18年を経て、すでにグアムでの隊舎や訓練場などの整備費として、全額近くの約3730億円を支出済みであるにもかかわらず、ようやく緒についたばかりと言えます。
これからさらに、日本は移転費用の3割強を負担するにもかかわらず、完了時期など具体的なスケジュールは明示されず、玉城知事は、明確な移転計画を示し、一日も早く完了することを求めています。
今年は米兵による女性暴行事件が相次ぎ発覚し、政府から県への情報提供がないことが問題にもなるなど沖縄の基地被害は何ら解消されていません。
東アジアの安全保障環境は厳しさを増しているものの、沖縄に重荷が押し付けられている現状を改めるとともに、日米両政府は、地元の声と誠実に向き合う姿勢を明らかにしてもらわなければなりません。


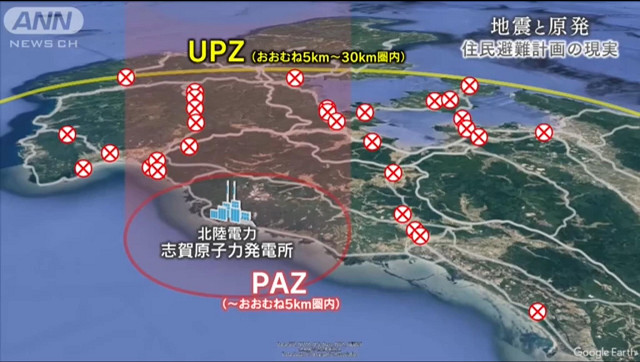

能登半島地震から一年が近づき、その教訓などが多様な側面から検証されつあります。
一般の番組ではあまり取りあげられない「能登半島地震と原発避難」の問題が、テレビ朝日のテレメンタリー2024で取りあげられています。
これまでも、このHPで志賀原発の事故が起きていた時や女川原発2号機の10月29日の再稼働にあたって、避難上の制約については取りあげてきました。
牡鹿半島の真ん中あたりに立地する女川原発の30㎞圏内の3市4町には約19万人が暮らしており、そのうち半島先端部から陸路で避難する人々は、事故を起こした原発に向かって逃げることになるし、その陸路が断たれる可能性もあることなど、避難計画そのものが破綻していることも指摘されてきました。
しかし、番組で描かれているのは、国も県も自治体とも「自分の担当範囲ではない」という押しつけ合いの中で、住民が取り残されるという「集団無責任体制」の姿です。
志賀原発だけの問題ではなく、全国の原発で同じ問題があることからも、原発災害最後の警告を突きつけている能登半島地震であることもしっかりと受け止めておかなければなりません。
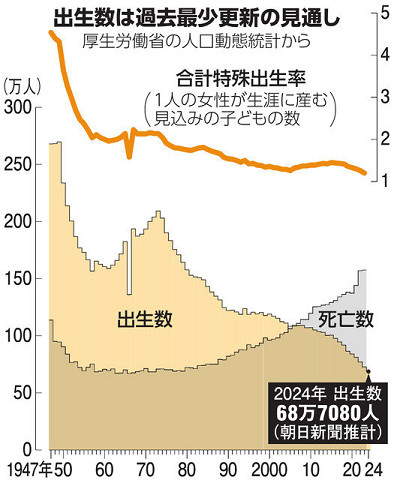 今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。
今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。
国と同じ方法で朝日新聞が計算したところ、2024年に国内で生まれた日本人の子どもは、68万7千人程度と推計され、70万人を下回る見込みとなり、統計のある1899年以降、過去最少を更新し、少子化に歯止めがかからない状況が続いていると報じられていました。
婚姻数は推計で47万5千組程度で、23年の47万4741組からおおむね横ばいの見込みだそうです。
少子化が加速すれば、現役世代の働き手の減少につながっていくことになり、すでに人手不足が深刻な介護分野のほか、地方も都市部もさまざまな業界でサービスが提供できなくなる恐れもあると心配されています。
政府は年3.6兆円規模の少子化対策「こども未来戦略」を昨年末に閣議決定し、少子化対策支援策を講じようとしているが、結果が表れるには、時間がかかります。
女性の正規雇用比率が25~29歳をピークにゆるやかに減少する「L字カーブ」に代表されるように、子育てを希望する女性にとってキャリアとの両立がな課題である中、東京大の白波瀬佐和子特任教授(人口社会学)は「子育てとは切り離して、どういう仕事をし、どう生きたいのかという個人の選択を保障することこそが人づくりの基礎となる。性別役割分担を暗黙の前提とするような教育の見直しや、労働市場において男女にかかわらず人材としての育成が重要だ。同時に児童福祉の観点から保育の提供など子育て支援を両輪で取り組むことが、L字カーブ解消へとつながる」と指摘されています。
有識者でつくる人口戦略会議は、今年「地方消滅2」を出したが、その中で、全国の自治体の4割にあたる744自治体で50年までに20~39歳の女性人口が50%以上減少し、いずれ消滅する可能性があると分析しています。
今、社会は多様な世代の助け合いでできていると改めて感じつつ、縮小する社会を前提としながらも、若い世代が安心して希望をかなえられるような社会を実現するためには、どのような支援策が優先されるべきなのか、そのための財源確保がどのようにされるべきなのか、そしてどのような支えあいの仕組みが必要なのか、中央・地方で真剣に考えられなければなりません。
| 12月24日「土佐久礼で防災を学び、街歩きを楽しんで下さい」 |


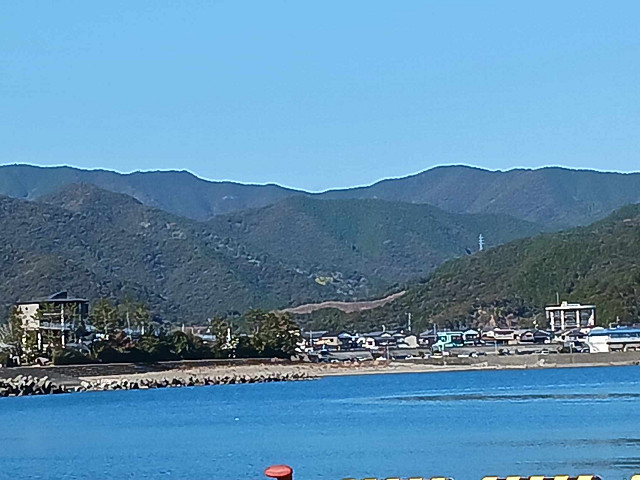

お墓参りにとの思いを持ちながら、お盆の時期は「南海トラフ地震臨時情報」への対応で、久礼湾の目の前のお墓に行くことを控えたり、お彼岸の時期には議会質問の準備などで、この機会も逸してしまい、やっと今日行ってきました。
久々に降り立った土佐久礼駅は、開業85年を期して国の助成を活用し、「駅再活用プロジェクト」でリノベーションした駅舎が出迎えてくれました。
掃除には90分ほどかけたものの、けして十分とは言えないまま帰りのJRの時刻までにとの思いで、帰ってきました。
帰る途中の道の駅の背後の津波避難場所、久礼八幡神社前の津波避難タワー純平号、大正町市場の入り口の山本鮮魚店の海鮮丼、小学校の同級生が看板娘の西村菓子店でパートナーがお土産を購入し、わずかの間だけ、久礼の今を確認して、駅に向かいました。
| 12月22日「洪水浸水リスクのある仮設用地の検証を」 |

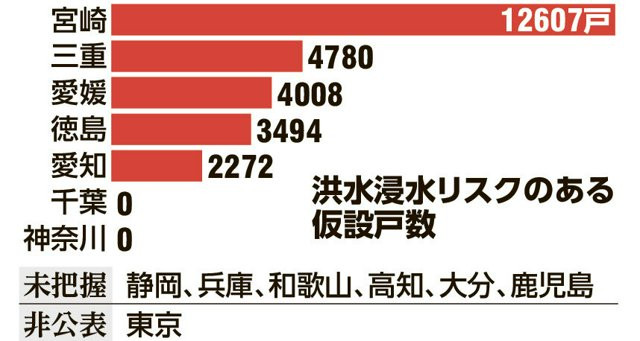 復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。
復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。
石川県によると、能登半島地震の被災地を襲った9月21日の豪雨で、輪島市と珠洲市の計6カ所の仮設住宅218戸総戸数の約4割が床上浸水し、土砂や浸水により住宅約700棟の全半壊が確認されるという「二重被災」が起きました。
このことを受けて朝日新聞の取材によって、南海トラフ巨大地震発生時に大きな津波被害が予想される14都県のうち5県が用地を確保した仮設住宅約2万7千戸は、大雨の洪水で浸水する恐れのある区域内に含まれ、5県全体の15%にあたることが分かりました。
二重被災の恐れがある区域内に仮設の候補地を含めているのは愛知、三重、徳島、愛媛、宮崎の5県で、愛知県は、建設を見込む5705戸のうち約40%がこの区域内にあり、愛媛(34%)、宮崎(30%)と続いています。
一方、9月定例会で質した時にも「民有地の抽出では、洪水浸水や土砂災害等のリスクの有無、道路への接道状況といった情報も含めて、リストアップしているところであり、今後、災害リスク等の情報の精度を高め、土地の安全性を確認していく。」という高知をはじめ静岡、兵庫、和歌山、大分、鹿児島は確保した建設候補地が洪水リスクのある場所か把握しておらず、能登の豪雨被害を受けて調査を始めるとのことです。
知事は、議会答弁の際に「今後は、取り組みを総合的に進める中で、次期南海トラフ地震対策行動計画の期間内には、浸水などに対しても安全性の高い候補用地が選定できるよう、最大限努めていく。」とされていました。
記録に残る1361年の正平地震以来、1948年明応地震、1605年慶長地震、1707年宝永地震、1854年安政東海地震・安政南海地震、1944年昭和東南海地震 1946年昭和南海地震と約100年~150年間隔で繰り返す南海トラフ地震が昨日昭和南海から78年を迎えました。
繰り返される様々な自然災害から学べる備えに、向き合い続けるしかありません。
| 12月19日「特定利用港湾指定の同意撤回を求めた請願の賛成討論を」 |
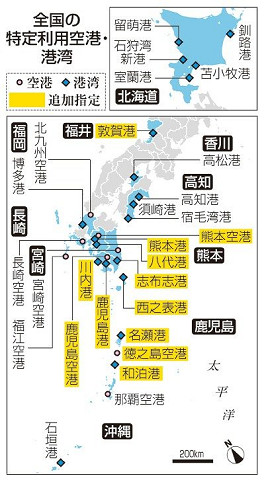 明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。
明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。
この請願には、県民9989人分の署名による県民の思いが添えられています。
特定利用空港・港湾の指定について、国は、安全保障環境を踏まえた対応を行うためとして「平素から、必要に応じて自衛隊・海上保安庁が民間の空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者である地方共団体等との間で『円滑な利用に関する枠組み』を設け、これらを特定利用空港・港湾」として、全国の「沖縄化」が始められてきました。
インフラ整備や大規模災害対応に資するというメリットばかりを強調した上で、県は指定に同意したことに対して、軍事的な側面、いざというときに果たして周辺住民の命が守られるのかという最大の問題に県民が不安を抱えたまま進められていることを明らかにし、一旦指定の同意撤回を行い、有事の際のリスクについて、徹底的に議論されるべきではないかと思われます。
そのことを訴え、同僚議員の賛同を求めたいと思います。
| 12月18日「福島、能登を忘れた原発回帰の次期エネルギー基本計画は許せない」 |
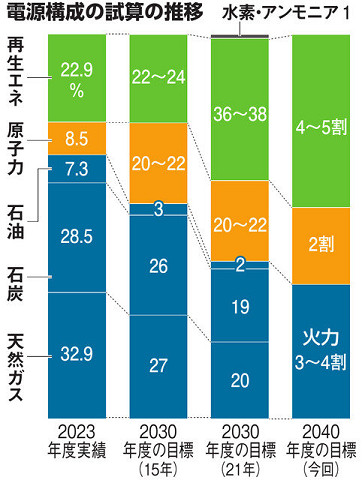
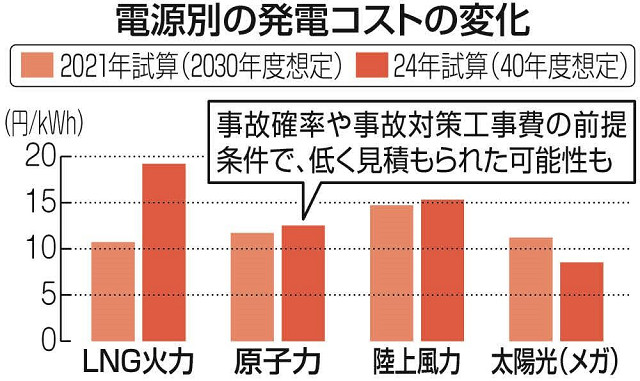 経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。
経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。
しかも、この1月には能登半島地震から原発災害最後の警告が発せられていながらであります。
「原発依存度低減」は、安倍政権下での第4次計画で「エネルギー政策の出発点」として盛り込まれ、その後も現行の第6次計画まで維持され、様々な圧力にさらされながらも、原発回帰への歯止めになってきました。
しかし、今回の経産省素案はこれを削った上で、「再エネと原子力をともに最大限活用することが極めて重要」と明記し、方針を180度転換させたものに等しいと言わざるをえません。
福島原発の廃炉の終わりは見えず、復興も道半ばであり、過酷な災害が多い国土の条件や、未解決の「核のごみ」の問題など、原発の抱える根本的な難点は何ら変わらないままです。
事故の「深い反省」の上に歴代政権が維持してきた基本姿勢を、原発推進派が大多数の審議会の議論だけで変えることは許されるものではなく、政府は東日本の被災地の声はもちろん、より多様な声を踏まえ、計画のあり方を徹底的に議論すべきです。
既存原発の再稼働さえ、電力会社の不祥事や地元の不安などで、経産省の想定通りには進んでこなかったし、原発の建て替えについては、同じ電力会社なら他の原発の敷地内も認める方針を示しました。
岸田政権が2年前に「最大限活用」を打ち出したときでも「廃炉を決定した敷地内」に限っていたものを早速緩和し、事実上の新増設容認にほかならないとも言えます。
また、発電にかかるコストは、原子力が事業用太陽光(メガソーラー)を上回っており、専門家が「計算の前提条件が、原子力など既存の大型電源に有利」と疑問を呈する甘い想定の中でも、原子力が安いとは言えなくなっています。
過去の計画も原発や火力を楽観視してきたことで、エネルギー構造の転換を遅らせてきたが、今回も同じ過ちを繰り返してはならないとの声をあげていかなければなりません。
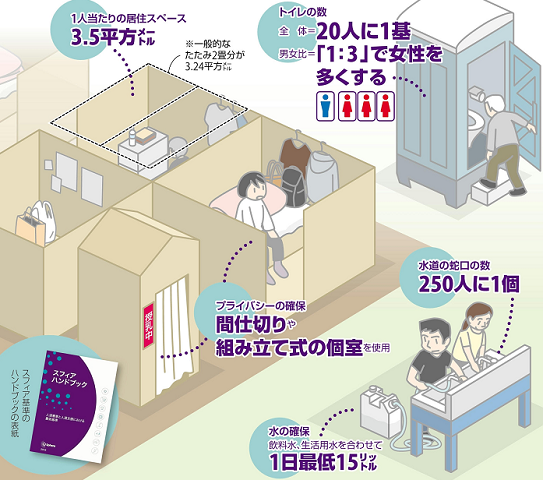
 今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。
今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。
改定指針では、具体的な数値目標として、トイレの数は、災害の発生当初から50人に1個用意し、一定期間経過した後は20人に1個、女性用は男性用の3倍にするよう求めています。
また、専有面積については、1人当たり最低3.5平方メートル(2畳程度)と定め、生活空間を確保するため間仕切りの備蓄も求めています。
このほか、仮設入浴施設の設置基準や、キッチンカーなどによる温かい食事の提供方法も例示しています。
避難所環境は、大規模災害のたびに改善が図られてきましたが、国は高齢者への配慮などを示した運営ガイドラインを策定し、被災地の要望を待たずに物資を送る「プッシュ型支援」なども進めているというが、道路が寸断されたりしたときに、届くのかとの心配はなかなか解消しません。
2016年の熊本地震では、災害関連死は熊本県で直接死の4倍超に上り、能登地震でも災害関連死は247人となり、直接死228人を上回っています。
高知県では、来年度からの南海トラフ地震対策行動計画に避難所の環境整備を重点課題として位置付けるとしているが、私が、高知県でもスフィア基準に基いた避難所環境の整備を求めたのは平成30年の議会質問で、県議会では初めての質問でした。
その二年後にも本気で避難所環境の整備を求めたものでしたが、いくつかの災害を体験してやっと追いついてきたとの感がしています。
| 12月12日「『特定利用港湾』指定同意撤回を求めて」 |

 政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。
政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。
県民の会では、共産党会派の皆さんとともに紹介議員となっています。
請願書は下記の通りです。
「特定利用港湾」指定同意の撤回について
請願の趣旨及び理由
この度の請願は、国からの要請に応じ、本年3月 22日 に高知県が高知港、須崎港及び宿毛湾港の「特定利用港湾」指定を受け入れたことについて、高知県議会として県民の生命等の安全をはかる立場から、指定同意撤回を高知県に求めることを請願するものです。
あわせて、高知県民の皆さんから「特定利用港湾」指定受け入れの撤回を求める請願署名10,023筆 を提出いたします。
「特定利用港湾」については、平時から有事へと切れ目のない利活用が想定されており、本年10月 23日 から11月 1日 まで行われた日米合同軍事演習(キーンソード25)で
は、いくつかの特定利用空港が使用されました。
米国のシンクタンクCSIS(戦略国際問題研究所)の国際安全保障プログラム報告書「次の大戦の最初の戦い一中国による台湾進攻を想定したウォーゲーム」には「空軍機を民間空港に分散させることで、中国が攻撃しなければならない駐機場を大幅に拡大し、日米の損失を軽減することができる」としています。これは、港湾も同様で沖縄だけでない軍事基地化とその拡大で、長期戦・継戦能力の強化をめざしているものです。
国際人道法といわれるジュネーブ条約第1追加議定書では、民間施設(空港、港湾など)を軍隊が攻撃することは許されていません。しかし、その民間施設を自衛隊等が使用するということは、軍事施設であるとみなされ、攻撃対象としてその施設や周辺の民間人の生命を危険にさらすことにもつながりかねません。「特定利用港湾」高知県版Q&Aでは、Q9において特定利用港湾に指定されることが「リスクの軽減に寄与するのではないか」としていますが、逆にいざ有事となれば真っ先に攻撃対象になりかねず、高知県の認識はまことに甘いといわざるを得ません。歴史的にもアジア太平洋戦争で旧日本軍が真っ先に攻撃したのは、真珠湾、シンガポール、香港、フィリピン、ダーウィンなどの空港・港湾でした。
さらに、「存立危機事態」や「重要影響事態」などいわゆる「グレーゾーン事態」にも利用されるものであり、周辺の高知県民の生命・財産が危険にさらされる危険性は高くなります。
「特定利用空港・港湾」は、現在10道県28か所が指定されていますが、軍事基地強化が急速に進む沖縄県では「沖縄戦がまた起きるのではないか」との県民の不安から指定に慎重な対応がなされています。
高知県議会におかれては、この請願の趣旨を十分にお考えいただいて、指定同意の撤回を高知県に求めていただきますようお願い申し上げます。
請願の項目
「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求めること
|
| 12月10日「都市計画道路はりまや一宮線の開通後の検証を」 |




希少生物の保存や歴史的景観の保全を巡り、2011~20年に工事が中断した高知市中心部の都市計画道路「はりまや町一宮線」(はりまや工区)の拡幅工事が進み、来年3月にも4車線で開通する見通しになったことについて、12月2日付けの高知新聞記事が報じていました。
しかし、記事によるとその過程において、隣接する新堀川にすむシオマネキやトビハゼなどの希少生物は保存されたものの、アカメの稚魚などのすみかだった水草のコアマモは移植により消滅し、回復しておらず、高知県の事業費は検討段階から1.5倍以上の61億3千万円に膨らんでいることも明らかにしています。
2020年9月定例会で、議題となったこの路線の事業費がこれまでの公表額38.7億円に対して今回の見込み額が53.8億円と1.4倍にもなっていたことについて、委員会審査で指摘したことがありました。
当時、都市計画課によると平成29年度に事業費を積算した際に、労務単価について平成22年単価を29年単価と誤認し算定した事によって道路本体の工事費が約9億9千万円の大幅増となったことや専門家からの意見を踏まえて石垣保存の工法や干潟の造成作業を追加したほか消費増税分などで約5億2千万円が積み上がったことなどによるとされていました。
今回は1.5倍以上の61億3千万円に膨らんでいることも含めて、開通後には、この都市計画道路の功罪について検証する必要があるのではないかと思っています。
| 12月9日「能登地震からの最後の警告を突きつけられる島根原発再稼働」 |
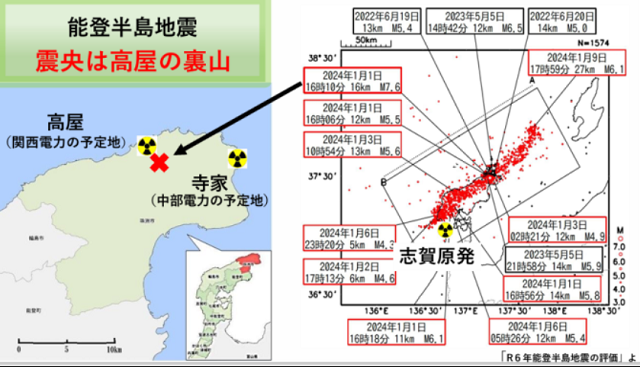 全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。
全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。
島根原発2号機は2011年3月に事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型で同型の再稼働は東北電力女川原発2号機(宮城県)に次いで2基目で、福島事故後、国内で再稼働した原発は8原発14基となります。
島根県は12年に全国に先駆けて広域避難計画を策定し、訓練を重ね、見直してきたが、自力で避難が難しい要支援者約5万7千人への対応など課題は多いと言われているが、能登半島地震を見たら自力避難が困難な方だけでなく45万人の避難がいかに現実性がないか自覚するべきではないでしょうか。
中電は13年12月、2号機の新規制基準適合性審査を規制委に申請してから、島根原発の南約2キロを走る「宍道断層」の長さ評価が申請時の全長約22キロから約39キロに延びるなど合格まで7年9カ月を要しました。
安全対策で基準地震動(耐震設計の目安となる揺れ)を820ガルに設定し、海抜15メートルの防波壁を建設したり、電源や冷却手段も多様化し、原発全体の安全対策工事費は現時点で約9千億円に上っています。
11月29日に、志賀原発差し止め訴訟原告団長の北野進さんのお話を聞かせて頂いたが、北野さんたちが高屋・寺家という群発地震の巣の中に予定されていた珠洲原発を泊めてくれた闘いがあったこと。
一企業の、電気を生み出す一手段に過ぎない原発のために、多くの住民の命や暮らしが危険に晒され続け、数十万人の避難計画が必要な原発って本当に必要なのか?
日本海が放射能汚染の海になり、仮に避難できたとしても、財産を奪われ、ふるさとを追われることを繰り返すのかと「最後の警告」を突きつけられているだけに、島根原発の再稼働は撤回すべきではないかと思うばかりです。
| 12月8日「12.8集会「―あの戦争―その時私は・・・」」 |

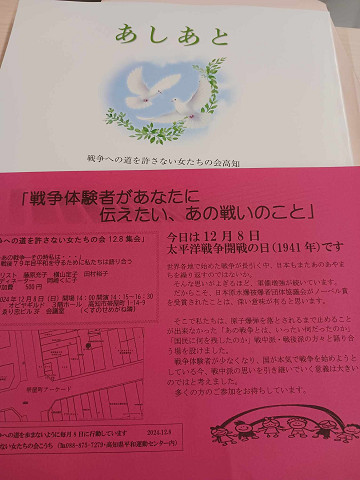

今年も戦争への道を許さない女たちの会12.8集会が開催されました。
ガザでのジェノサイドをはじめ世界各地の戦争が長引く中、日本原水爆被爆者団体協議会がノーベル平和賞を受賞された今年、大いに考えさせられる12.8集会でした。
今年の12.8集会は、「―あの戦争―その時私は・・・」原子爆弾を落とされるまで止めることができなかったあの戦争とは一体何だったのか、戦中派・戦後派の方々が多いに語ってくれました。
藤原充子さん95歳、横山定子さん90歳、田村裕子さん79歳が、それぞれに開戦の時、高知大空襲、敗戦の時、戦後をどう考え、生きたかその思いを聞かせてくれました。
その思いを実践し続けて来られた家族や仲間の支えがあった労働運動や平和運動の大切さ。
そして、戦争体験者が少なくなり、国が本気で戦争を始めようとしている今、引き継いでもらいたい「戦争は絶対いや、繰り返してはだめ」との思いを広げ、声を大にして言える子どもたちを育ててくれることが求められている中で、私たちには語りつなぐ責任がある。
「もっとたくさんの人を集めて、こんな大事な話を聞かさんといかん」とお怒りの98歳松﨑敦子先生のお言葉や「戦争が絶対嫌だか10人の仲間とともに参加した」という80歳の高知県日中友好中国帰国者の会会長中野ミツヨさんの思いも受け止めて、参加者で集会宣言を確認して、終えました。
会場近くの中央公園では、戦争こそ最大の人権侵害と言われる中、その人権尊重が呼びかけられる第26回人権啓発フェスティバル「ここるんフェスタ」が開催されていました。
 更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。
更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。
インフルエンザに感染したため二日ほど寝込んでおり、今日から復帰しました。
38度5分の高熱に悩まされましたが、医療機関で処方頂いた薬を服用し、やっとしのぎました。
今日は、早朝交通安全指導は休ませて頂きましたが、12月定例会開会日に出席し、議会中の対応などに奔走してきました。
たった二日間の療養でも、これほど自分の中で停滞すると、やっぱりなかなか休めないんですよね。
今夜から、何日かは、夜の予定はキャンセルさせて頂くことになりますが、申し訳ありません。
| 12月3日「お国好みの自治体でなく、地域本位に考える自治体に」 |

 12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授
兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。
12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授
兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。
講師からは、地方から首都圏へ、人も財も権限などの全てが吸い寄せられている中で、「東京圏と地方圏の現状」「これまでの地方創生をふりかえる」「人口減少社会にどう対処するか」「鍵になる生産性向上」「DXによる社会変革」「地域本位に考える力と真の地方創生」などに関してお話し頂いたり、さらにインタビューやフロアとの質疑応答で議論が深められました。
私にとって内容のポイントになる点として受け止めたことを、書き記しておきたいと思います。
いずれにしても、自治体が国の言いなりになるのではなく、まずは自分たちの地域にとって何がいちばん大事か、地域本位に考え、施策を進めていくことの重要性が訴えられていたと思います。
▼国ばかりに頼らない。頼っていた面を軌道修正することも必要だし、その際には地元の大学の知見も必要。
▼これまでの地方創生はどうだったのか。肝心の地方が真剣にな考えていなかったのでは、自治体毎に総合戦略を策定したが、8割近くが東京のコンサルに丸投げだった。どこの自治体も人口減少を横ばいにするためには、移住や観光振興など金太郎飴で、政府も早く提出せよとの無言の圧力をかけていたが、本来は自治体が自分たちで十分考えて下さいというべきだった。
▼移住促進は、人とカネをかけて奪い合っているものだ。地方創生2.0は「奪い合い」は止めた方が良い。安倍政権が2015年に統一地方選挙に向けて、地方創生の予算もプレミアム商品券など本来の趣旨と違ったよこしまな使い方がされるなど効果が上がらなかった。
▼人口は当面の間、減少することを前提に考えなければならない。将来の働き手が減少する中で、税収が減ったり、教育など公共サービスが後退したり、年金・医療・介護が危うくなる中で、働き手を確保しなければならない。外国人を実習生であれ労働者として迎え入れるのであれば、権利保障もキチンとすべき。それでも、働き手が十分確保できないとすれば、一人ひとりがこれまで以上に自分の能力を発揮できるような環境にして、生産性を高めることが求められる。
▼自治体の「国の言うことは聞く」というスタンスを「国の言うことも聞く」という方向に転換すべきでは。知事の当時の2005年に国から職員定数5%削減などの集中改革プランを実施せよとの指示があったが、普段から適正な定員管理をしているからと、聞かなかった。地方に魅力ある仕事を作り出し、何が自分たちの地域にとっていいのかをしっかり考えることが必要。「あなた(国)好みになる」という奥村ちよ的自治体はやめ、「地域本位に考える力と真の地方創生」が求められている。
▼地方自治法改悪は、国の言うコロナ禍の対応を理由ににしても、国自体の対応に誤りも多く、立法事実が説明できない。早いうちに、法律を改正して条文を取り除けばよい。
▼ふるさと納税は、以前から批判してきたが、税金の奪い合いであり、正当な流通も乱すものであるので、止めた方が良いと思っている。
▼「合区」問題は、各県に1名は保障し、人口の増えた県に定数を上積みしていくなど法律で改正できることはあるはず。
▼国からの指示に従わないリスクは、議会などから批判されることを恐れているだけで、特にリスクがあるわけではない。






今日は、朝8時前から二葉町・若松町・中宝永町・下知総合防災訓練の準備に始まり、「たいさく君」と「ヘルパちゃん」の着ぐるみが出迎える中、9時避難開始。
10時からは4階多目的ホールでのシェイクアウト訓練、すずめ共同作業所所長から地域交流祭り等のお話、避難所運営の問題点をテーマに防災寸劇、昭和小5年生の防災学習研究発表、防災紙芝居朗読、段ボールベッド(4種類)組立て訓練などを開催し、避難者の皆さんにも参加して頂きました。
私は、この4階でのメニューの進行役をしながら、防災寸劇では避難所運営委員長役を仰せつかい出演させて頂きました。
皆さん、それぞれに協力いただき、可能なものは体験もして頂きました。
さらに、下知消防分団による屋上ドローン撮影で、4階のモニターを見ながら、上空からの下知地区の様子を国見分団長から説明してもらいました。
昭和小5年生は、今年の研究テーマに8月の「臨時情報」を取り上げるなどの頑張りに皆さんから大きな拍手がありました。
今年の炊き出しおにぎりとシチューは、誰もが絶賛。さらには食後には、ピースウインズジャパンさん提供の東ティモールコーヒーと毎年提供頂く地元の老舗西川屋さんの銘菓が振る舞われました。
誰もが避難したくなる避難所となるためにも、訓練の積み重ねで、避難者のニーズに応えられるようになるといいかなと思います。
10時段階で集計した避難者137名を高知市の災害対策本部に報告しましたが、運営スタッフで受付ができなかった方もおられるかと思いますので、昨年同様150人以上の参加はあったかと思われます。
先週のマンション防災避難訓練、そして今日の総合防災訓練、さらには来年2月8日昭和小防災オープンデーへと地域住民のコミュニティ防災の取り組みは続きます。
| 11月30日「県一消防広域化基本構想骨子案公表さる」 |
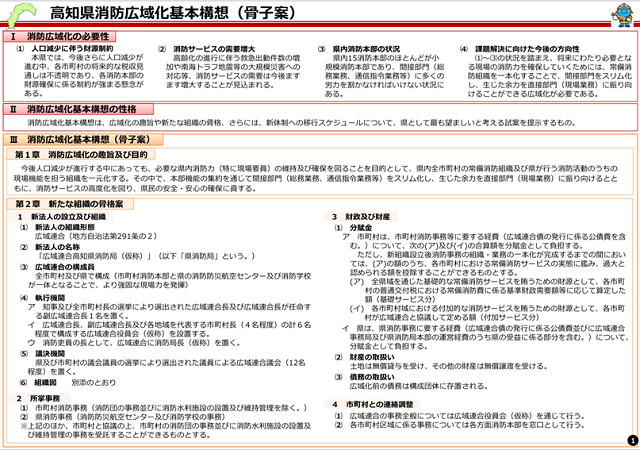
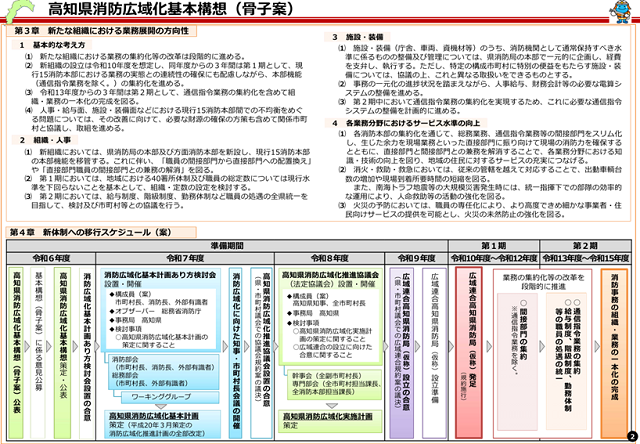
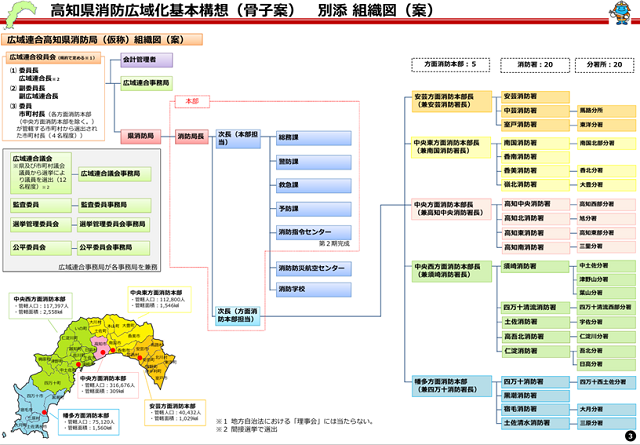
先の9月県議会定例会で、浜田知事が消防の県一広域化を目指す方針を表明され、私も一問一答で県の姿勢について質問したことでした。
知事は「基本構想として、県の試案としてお示しする。その過程でも、御意見は幅広くお聞きした上で、年度内には、県としての試案としての基本構想を策定し、お示しすることにしたい。」との回答を踏まえて、叩き台となる「消防広域化基本構想骨子案」として、昨日示しました。
「消防広域化の趣旨及び目的」は、「今後人口減少が進行する中にあっても、必要な県内消防力(特に現場要員)の維持及び確保を図ることを目的として、県内全市町村の常備消防組織及び県が行う消防活動のうちの現場機能を担う組織を一元化する。その中で、本部機能の集約を通じて間接部門(総務業務、通信指令業務等)をスリム化し、生じた余力を直接部門(現場業務)に振り向けるとともに、消防サービスの高度化を図り、県民の安全・安心の確保に資する」というものです。
そのための組織としての広域連合は、県と34市町村で組織され、1カ所の本部(設置場所未定)に加え、市町村や現場と本部のつなぎ役となる中核署「方面本部」を、「幡多(四万十市)」「中央西(須崎市)」「中央(高知市)」「中央東(南国市)」「安芸(安芸市)」の5エリアごとに設置するとされています。
各20ある消防署と分署は維持しつつ、2028年度に広域連合高知県消防局(仮称)を立ち上げ、給与制度なども統一し、33年度までに通信指令などの機能を一元化することとしていますが、現場の消防力を担う職員の処遇議論は後回しとなっており、このような「新体制への移行スケジュール(案)」で良いのかと疑問を持たざるをえません。
県は公表した昨日から1月6日まで基本構想案のパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、構想を正式策定するというが、これも拙速ではないかとの声もあります。
各消防本部や市町村長、住民の意見を丁寧に聞きながら進めるというが、現場の消防力を担い、隊員の士気に影響することからも職員の生の声を聞きながら進めて頂きたいものです。

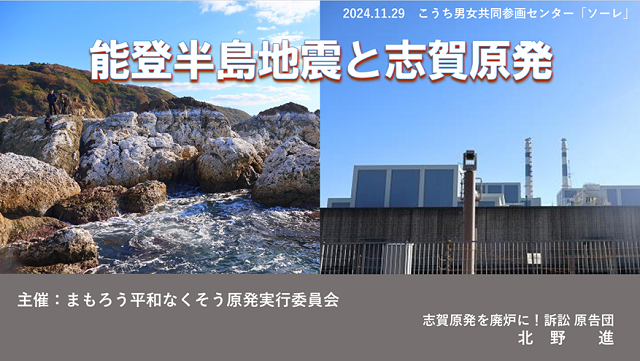 これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。
これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。
「地震は止められない 原発と戦争は止められる!」をスローガンに9時15分中央公園北口集合でデモ行進の後、10時から中央公園で開催します。
ステージでのいろんな催しやブースが出展されています。
また、前日の今夜には志賀原発差し止め訴訟原告団長の北野進さんをお招きして講演会も行います。
「珠洲原発が建設されていたら・・・」「珠洲原発 地震と原発も争点」「志賀原発反対運動の歴史」「能登半島地震と志賀原発への影響」「複合災害で避難はできない」などについて、今回の能登半島地震が、原発災害への最後の警告であることをお話し頂きます。
ぜひ、皆さんどちらもご参加ください。
| 11月28日「阪神淡路・東日本大震災復興事業の教訓を能登・南海トラフに活かして」 |

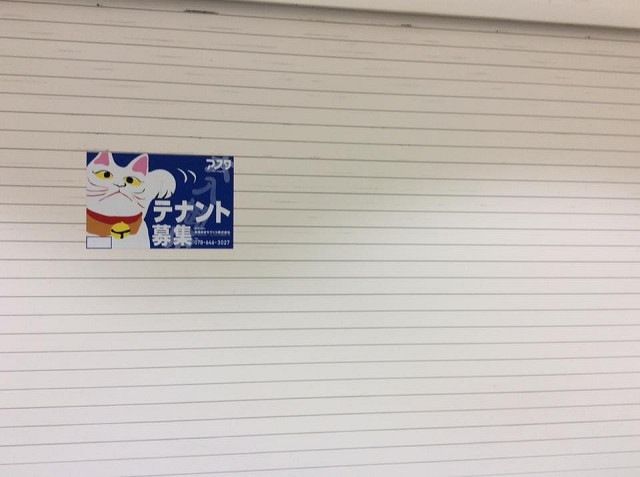


来年1月17日で、阪神淡路大震災から30年を迎えるが、地震と火災で壊滅状態となった「新長田駅南地区市街地再開発事業」という、ようやく完了した神戸市の巨大復興事業から教訓をくみとり、今後にどう生かしていくかが改めて問われようとしています。
市は事業を検証し、21年に報告書を公表し、耐震・耐火策が充実し、人口が増えたことで「事業目的はおおむね達成」との基本認識を示したというが、5年前に新長田駅周辺を訪ね、「兵庫県震災復興研究センター」出口事務局長にお話を伺い、現地を視察した時からそのようなことは言えないものだと感じていました。
出口さんは、「復興災害をもたらした要因には2つのものがあり、1つは復興に名を借りた便乗型開発事業の側面であり、もう1つは復興プログラムの貧困さ、非人間性、非民主性、官僚制、後進性であった。」と指摘されていました。
さらに、お会いした商店街の皆さんは、「高い管理費、高い固定資産税、そして借金返済」という三重苦の負担にあえぎながら、「コストのかかる街」で営みを続けられていますが、「活性化(にぎわいづくり)の課題」と「まちの正常化・あたりまえの街にするという課題」を克服することが求められているとのことで、神戸市の言う「達成した事業目的」とは、一体何だったのかと言わざるをえません。
そして、東日本大震災で被災された石巻市雄勝地区の阿部晃成(現金沢大学・能登官民連携復興センター)のお話を昨年もお聞かせ頂いたり、「検証なき復興フェードアウトに抗して」という東日本大震災の復興事業の検証講演動画を見せて頂いたりする中で、東日本大震災においても復興事業の検証にもとづいた教訓も共有しておかなければなりません。
総延長433km、1兆3621億円を費やした防潮堤の背後には人家のない荒地も目立つ地域が多くあり、1区画当り最大1.9億円,平均6700万円を費やしながら対象世帯の1/3の参加にとどまった防災集団移転事業では、移転元跡地利用は進まず、未だ30%が未利用地が残っています。
大船渡市や七ヶ浜町の差込式防集など、事業費を抑えながらコミュニティに配慮した優れた事例は評価すべきですが、全体像は生活再建を置き去りにした巨大土木事業の推進だったと言わざるをえない復興事業について、退任した遠藤宮城県副知事は,臆面もなく,「住民合意の軽視が過剰スペックとなり,モラルハザードを生んだ」と述懐したという報告に驚かざるをえません。
これから能登半島地震の復興事業が進められることになりますし、私たち高知では事前復興議論が進められることになりますが、復興事業がもたらした災害ともいえる弊害を教訓として学びながら、今後に生かしていくことが求められるのではないでしょうか。
| 11月26日「県内精神障碍者の医療費助成へ『等級の壁のない対象拡大』『早期実施』を求めて」 |

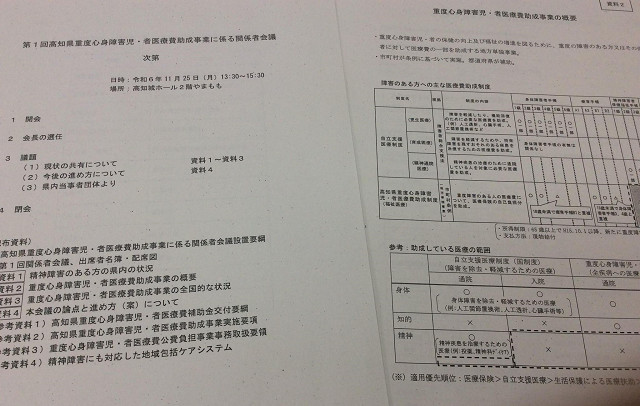 昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。
昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。
高知県の精神障害者に対する医療費助成については、精神疾患を原因とする通院のみで、他の疾患や入院は自己負担で、当事者や家族の不安の解消の求めに応えていく必要がありました。
そこで、6月定例会で県民の会の同僚議員の岡田議員がその対象拡大を求める質問をし、県内の精神障害者の親でつくる「高知はっさくの会」(東岡美佳会長)の皆さんとともに、署名活動に取り組んだうえで、県に対しては約1万3千筆の署名を子ども福祉政策部長に提出し、助成創設を求めてきました。
部長は、「知事とも話して判断したい」と踏み込んだ考えも示されていましたが、9月定例会では、知事が「対象とする障害の程度や財政負担の規模などを、1年程度かけて検討を深める」と答弁をしてきた経過を踏まえて、今回「高知県重度心身障害児・者医療費助成事業」の対象に精神障害者を加えることを検討するにあたり、事業の実施主体である市町村をはじめ、福祉、医療、当事者家族など精神障害の関係者から幅広く意見を聞くための関係者会議が開催されました。
県からは、「現状の共有」「今後の進め方」が報告されるとともに、県内当事者団体として「はっさくの会」より当事者や家族の窮状が訴えられました。
県内では全市町村が、県の補助を受け「重度心身障害児・者医療費助成制度」を導入し、重度の身体障害者と知的障害者はあらゆる疾患での通院・入院に助成があり、医療費の自己負担はないが、精神障害者は対象外になっています。
それゆえのご苦労について、関係者会議と言いながらも、十分に認知していなかったり、あまり深刻に受け止められていなかったのかなという感じがしました。
事前の意向調査では、県が補助制度を導入した場合の助成については、8割の自治体が積極的な回答をしているものの、制度化による自治体の財政負担を心配したり、対象とする障害の程度や他の障害の医療費の助成制度とのバランスなど検討が必要な課題についても多くの回答が寄せられていましたし、会議でも意見が出されていました。
今後、課題については検討し、県は助成対象となる障害の程度や医療の範囲、所得制限について協議を進め、2026年度の実施を目指すとのことです。
「等級の壁は取り除く対象拡大」と「できるだけ早期実施を」との思いの強い当事者・家族の皆さんは、昨日の議論を忸怩たる思いで聞かれていたのではないかと思わざるをえない関係者会議だったように思えてなりませんでした。
この会での当事者の皆さんの思いを受け止めた議論となるよう注視していきたいものです。
| 11月24日「寒風の中でマンション防災・避難訓練」 |





今日は、今年度のマンション防災・避難訓練を行いました。
昨年と同様の「津波避難・安否確認訓練」「初期消火・水消火器使用訓練」「防災資機材使用訓練」を行いましたが、最初の避難・安否確認訓練では「安否確認シート」を貼り出し4階以上に避難して頂く行動の確認がされた方が54世帯で、当初から予定があり参加できないという申し出があった方を除いて6割ほどの確認率で、全体で確認し終えたのは、避難を開始し始めてから30分近くかかりました。
避難・安否確認訓練の終了後には、6階の一室から出火したという想定で火災発生通報、初期消火、水消火器使用訓練も行いました。
この段階では、結構な強風が吹いて寒くて参加を遠慮される高齢者の方もいて、参加者は30人ほどになっていましたが、可能な皆さんに水消火器の体験をして頂きました。
最後の防災資機材使用訓練については、風も強く簡易トイレのカバーも倒れてしまう状況で、寒くなっていたので、組み立てたり稼働させたりしたもの以外は、使い方の説明などを行って終えました。
皆さんに披露した資機材は、エアマット式担架、折り畳み担架、イーバックチェアーなど避難行動要配慮者支援用の資機材や、発電機各種、移動式投光器、救助ボート、簡易トイレなどの組立を行いました。
ポリマー式水嚢は、リユースができるということでしたが、リユースするためには長時間水に浸す必要があることも分かりました。
最後に、参加世帯の皆さんには、「災害対策ハンドブック・レジャーシート」を配布させて頂き、世話役の皆さんが残って片付けなどもスムーズに行って頂きました。
また、男性の世話役さんが少なかったことから下知地区減災連絡会のメンバーにもお手伝い頂き、感謝しています。
日陰で、風が強く寒い中での訓練でしたので、残念ながら参加者が例年より少かったのですが、参加申し出のあった避難行動要支援者の方との事前打合せで、日頃から使用していない救助用具での救出訓練は不安に感じられていて、個別避難計画の中でご本人と話し合っていく必要性を感じたことや、世話役を自主的に申し出て頂いた方と同じフロアーのベテランスタッフの方が訓練を通じて仲良くなられたことなどは、訓練を行ったからこその成果だったと思います。
少しずつ若い世代の方も参加頂いているところに今後も期待したいところです。
終了してから、役員の方に同乗させて頂いて、三里消防署まで水消火器を返還して、食事をするまもなく、オンラインで災害ケースマネジメント構想会議に参加しました。
ここでも新たな学びをさせて頂いています。
| 11月23日「日々の取り組みで「我が事」だけでなく「我われ事化」へ」 |

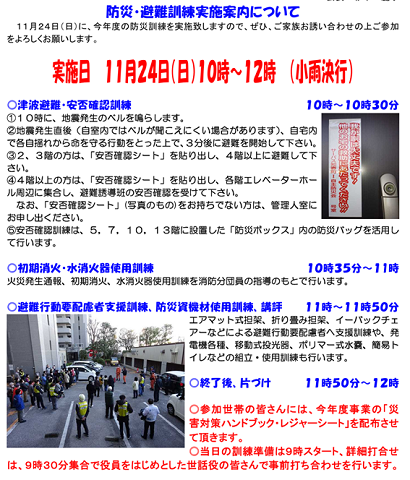 先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。
先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。
明日、訓練が終わったら12月議会の準備にも取り掛かります。
正直一日ゆっくりしたいとの思いで、今日もスタートしました。
まずは、午後の講演で、しっかりと伝えたいことが伝えられれて、明日の訓練で少しでも減災への備えを「我が事」だけでなく「我われ事化」できればと思います。
| 11月22日「台湾有事と向き合う石垣の特定利用空港・港湾施設でも国の対応は」 |







11月18日から、県民の会で2泊3日の行政視察に行ってきました。
今回の調査目的としては、台湾有事と向き合わざるをえない沖縄県、八重山諸島に位置する石垣市、竹富町で、本県でも受け入れた特定利用港湾指定の位置づけなどについて、聞き取りをすることでした。
初日は石垣市にある沖縄県庁八重山合同庁舎で、沖縄本島の県庁港湾課・空港課、基地対策課・防災危機管理課とオンラインによって特定利用空港・港湾、台湾有事等々の意見交換を行わせて頂きました。
二日目の午前中は、石垣市役所で、建設部港湾課から台湾有事等を想定した特定利用港湾対応など、観光文化課から国際観光(クルーズ船・台湾定期船)やオーバーツーリズム、ユニバーサルツーリズム対応などについて聞かせて頂くとともに、特定利用港湾指定で整備を期待されている石垣港を見学させて頂きました。
昼食もそこそこに、昨年整備されたばかりの陸上自衛隊石垣駐屯地周辺まで行き、午後には石垣市内の竹富町役場で、防災危機管理課から地域防災計画・特定利用港湾の対応などについて意見交換をさせて頂きました。
また、最終日は、僅かな時間にも関わらず石垣市議の砥板芳行氏、大道夏代氏、井上美智子氏、田盛英伸氏にお集まりいただき、意見交換をさせて頂きました。
詳細は、改めて報告させて頂きますが、県・市・町の立場や市議会議員さんの率直なご意見を聞かせて頂き、台湾有事と向き合わざるをえない石垣における特定利用空港・港湾への国の対応を知ることができるなど大変有意義な調査となりました。
ご協力いただいた皆様に感謝しかありません。




2023年10月7日以降、ガザへのイスラエルの軍事侵攻とジェノサイドは、停戦を求める国際的な世論に反して、「民族絶滅」政策の様相を示しています。
パレスチナの平和を願う国民有志は、イスラエルによるガザ軍事侵攻とジェノサイドに反対する、日本、そして世界のすべての人々に、ガザ、そして占領下パレスチナで、自由と平等と、尊厳ある生を求めて闘っているパレスチナの人々に対する連帯の思いを込めた、全国一斉凧揚げアクションに賛同して、高知でも今日の午後3時~「パレスチナ連帯凧あげ」が行われました。
バレスチナの人々は凧あげをする伝統があるとのことで、「天井のない監獄」というか今では「天井のない地獄」にいる人々にとっては、平和と自由への希望の象徴なのかもしれないとの主催者の皆さんの思いをのせて老若男女で凧揚げに息を切らしていました。
全国一斉アクションを通して、イスラエルによるジェノサイド下のガザの人々に対する連帯の意志を表明するとともに、イスラエルに即時停戦と、12カ月以内にガザ、東エルサレム、西岸から軍および入植地を撤退させるという国連総会決議の速やかな履行を要求し、そして、日本政府に対しては、日本国憲法の理念に則り、パレスチナの国家承認と平和的解決に尽力するよう求めています。
バレスチナの人々は凧あげをする伝統があるとのことで、「天井のない監獄」というか今では「天井のない地獄」にいる人々にとっては、平和と自由への希望の象徴なのかもしれないとの主催者の皆さんの思いをのせて老若男女で凧揚げに息を切らしていました。
| 11月15日「12月以降も国民の医療を受ける権利が奪われないよう」 |
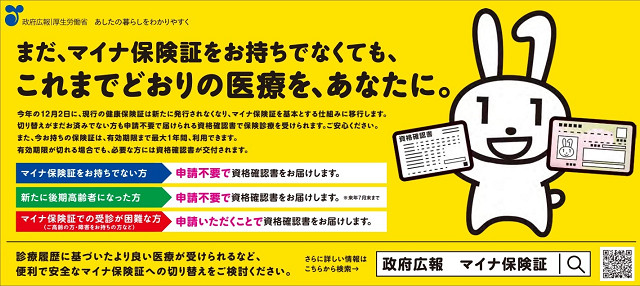 来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。
来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。
ただ、最近の政府広報は、トーンが変わって「マイナ保険証がなくても医療が受けられる」というメッセージが前面に出ています。
変更の背景には、首相が代わり、マイナ保険証の旗を振っていた河野太郎デジタル相が閣外に去ったことがあると言われるが、それなら始めからそう言えよと言いたくなります。
これまで、マイナ保険証に別人の情報がひもづいたり、病院の窓口で負担割合が誤って表示されたりする事態も重なり、期限を切った「廃止」という強い言葉が、多くの国民に「不安」と「不信」を増幅させ、直近でも、受診者に占めるマイナ保険証の利用率は「13・87%」(9月末現在)に留まっています。
毎日新聞によると、情報システムの専門家でつくる一般社団法人「情報システム学会」の元常務理事で博士(情報管理学)の八木晃二さんは、DXを積極的に推進する立場だが、「マイナ保険証は危険すぎる」と指摘されています。
そして、「国民がマイナ保険証の導入に反対しているのは、今のマイナンバー制度にセキュリティー上の抜け穴があることに多くの国民が気付き許容できないと思っている」からだと言い、加えて、「マイナカードは国民視点、ユーザー視点からの運用設計が欠如している。」とも指摘しています。
結局政府は、つぎはぎの修正を迫られ、12月以降は、現行保険証とほぼ同じ機能の「資格確認書」を発行し、マイナ保険証を持たない人に加え、健康保険証が失効する75歳以上には当面、全員に送るとのことです。
現行保険証の併用に比べ複雑さが増え、新たなトラブルも心配されますが、何より国民の医療を受ける権利が損なわれる事態だけは回避するよう政府は責任ある対応をとらなければなりません。
| 11月13日「『ドン・キホーテ』24時間営業は断念、交通事情はさらに改善を」 |

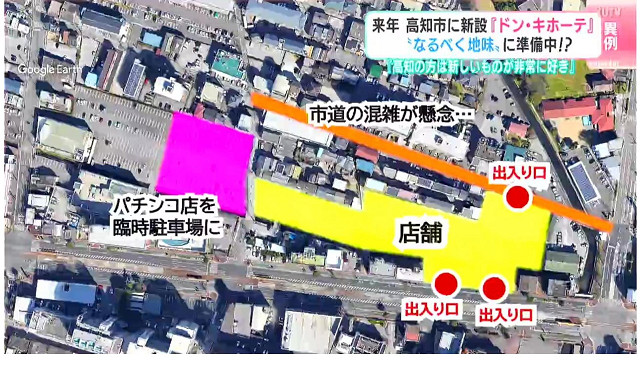

これまでも、機会あるごとに県内初進出のドン・キホーテの地元説明会の課題などについて、お知らせしてきたところですが、昨日、県大規模小売店舗立地審議会で、新店舗「ドン・キホーテ高知店」(仮称)の説明、審査が行われました。
傍聴はしていませんが、報道などによると次の点が明らかになったようです。
計画によると、駐車場243台と駐輪場108台を設けるが、新店舗のオープン日や営業形態について同社広報室は、現時点で開示できる情報はないなどとしており、審議会では営業時間についても審議されなかったようです。
ただし、現状、営業時間を「24時間」で届け出ていますが、審議会後に「24時間営業はしない」方針を明らかにしたようです。
また、店舗用地は国道32号沿いにあり、審議会には地域住民から「大渋滞になり交通事故がおきる危険度が高くなる」などの懸念が寄せられていたことから、委員からは、南側出入口に面する国道の交通量に関して本線を利用する車の列が長くなる可能性が高く、店から1度に出す車の台数を決めたり、公共交通機関を利用して店に来る人を増やすなどの施策を積極的に検討してほしいといった意見も出るなど、交通量や周辺住民の生活に配慮を求める意見が相次いだとのことです。
これに対しドン・キホーテ側の担当者は近隣施設の協力のもと臨時駐車場を設けるほか、看板や路面標示の設置、誘導員による車両誘導を行い混雑解消につとめる予定であると述べ、審議会としては、開店後も検証など行うよう、但し書きをつけた上で県に答申するとのことです。
私たちが、小学校関係者や交通安全関係者とともに、これまでに提出した大規模店舗立地法に基づく意見書の内容を踏まえた対応されている面もありますが、まだ対応して頂きたい面については地域の皆さんとともに、注視していきたいものです。
| 11月12日「災害時、支援制度の知識が住まい再建の希望に」 |
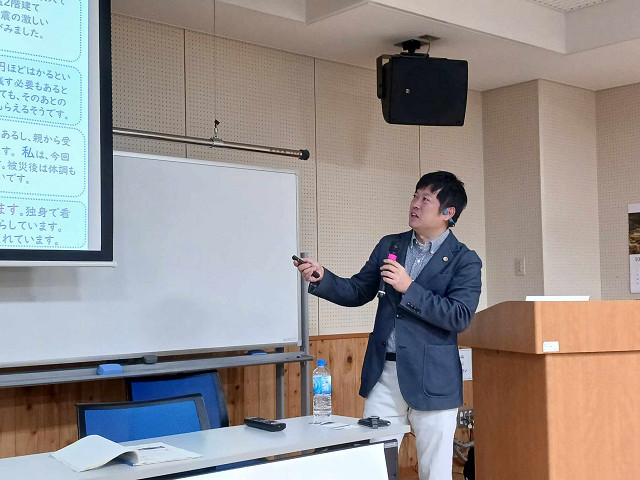
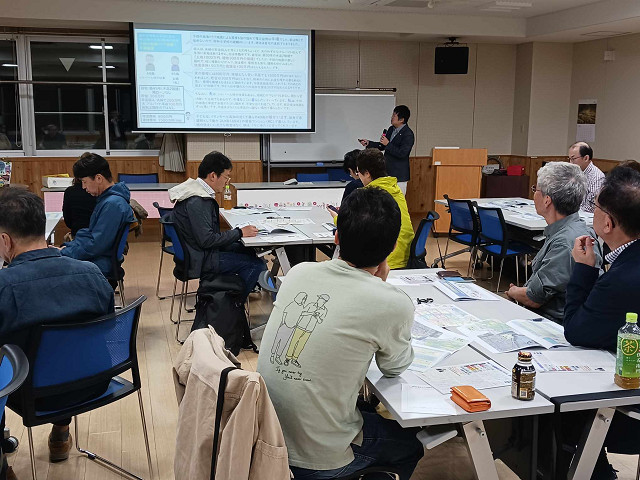
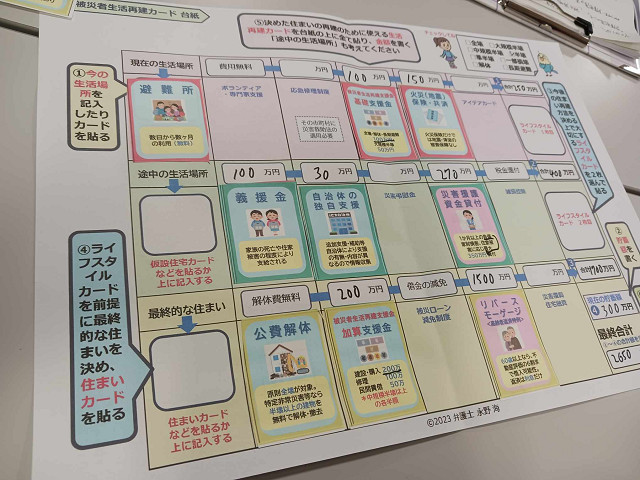
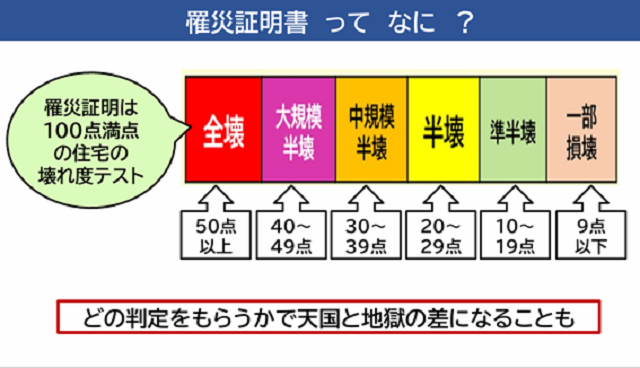
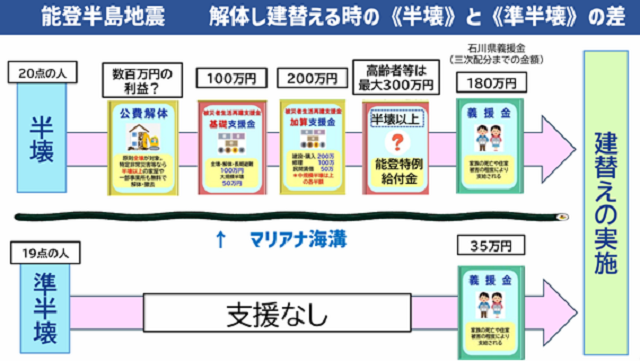
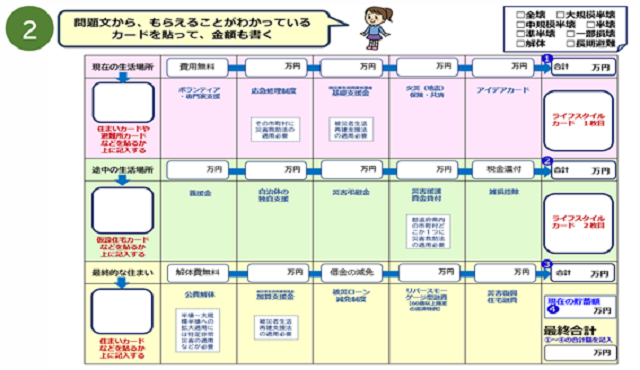
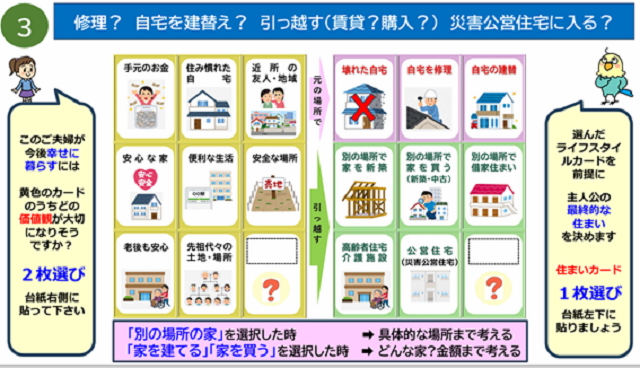

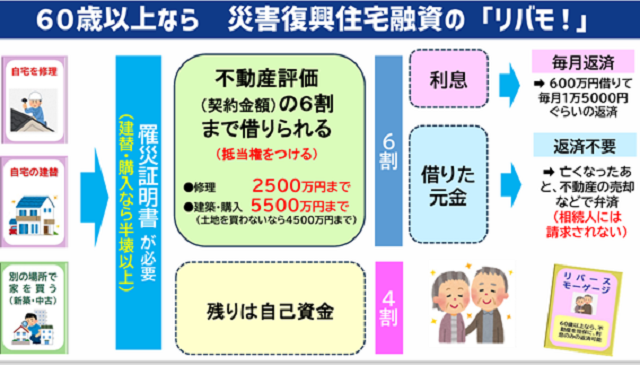
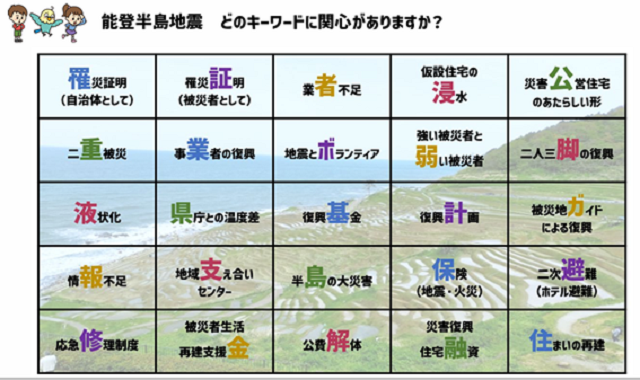
11月9日は、全国各地で講演中のお忙しい中、永野海弁護士に下知にお越しいただき「被災後の生活再建に必要な支援制度を事前に知る」とのテーマで、事前復興講演会を開催しました。
ケーススタディの事例が、偶然にも昭和小近辺にお住いの二人暮らしの高齢夫婦が、被災したことを想定した生活再建支援でしたので、参加者の皆さんも身近に感じながらお話しを聞かせて頂きました。
6段階の罹災証明で、どの判定を貰うかによって天国と地獄の差になることもある中で、事例の世帯が「半壊」であることを前提に、当事者がどのように生活再建をするのか、相談され支援するとしたら、仮設住宅に入る段階で、どのような支援があるか、その支援金や最終的な住まいの選択に当たっての支援制度は何があるのかなど、グループごとに話し合いながら、住まいカードやライフスタイルカードを貼って、支援金額などを記入していきます。
そのことによって、一定の金額が手元に構えられるとしたら、生活再建への希望が持てるのではと思えることを実感されたようです。
50代の方からは、「ワークショップ形式でシュミレーションしたら「自分事」になりやすいことが分かりました。難解な制度を知ること、使いこなせることで、その後の人生も変わってくることがよく分かりました。『知識が会ったら希望が持てる』という言葉がとても大切に聞こえました。」との感想もありました。
「支援制度の組み合わせによっては貯金が少なくても住宅再建できる」とのアドバイスに、参加者からは、被害に会わないのが一番良いが、どうせあうなら何としても「半壊」の判定を勝ち取らなければとの声もあがっていました。
被災地での相談会でも、質問が出されることで、他の人の質問を通して、共有化できるとのお話しがありましたが、この講演会でも今までにはないほどの質問が制限時間一杯出されました。
詳しい内容やこの支援制度のカードなどは、永野弁護士の「ひさぽ」(被災者支援情報さぽーとぺーじ)というHPからご覧いただけますので、ご紹介しておきます。
| 11月11日「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名にご協力を」 |

 12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。
12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。
国は、自衛隊等が「有事」を見据え、自治体管理の港湾を整備活用する「特定利用港湾」に高知港(高知新港含む)、須崎港及び宿毛湾港を指定し、濵田高知県知事は3月に受け入れを表明しました。
多くの県民に十分な理解を求めることもなく、議会での議決もなしに、知事が受け入れたことを、私たちは容認できません。
街頭でお声をかけてくれた県民からも、「私たちもあまり知らない中で、そんな大事なことが議会の議決なしに決められるなんておかしい」との声を頂きました。
「高知県議会として「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を高知県に求めること。」の一点での請願にどうぞ、ご署名下さい。
請願署名用紙はこちらからダウンロードできますので、どうぞご活用ください。
| 11月8日「滅多に聴けない事前復興防災講演会にお越しを」 |
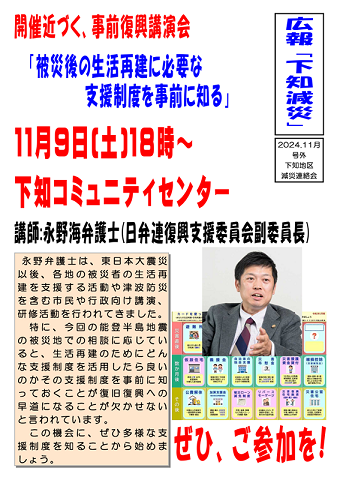 4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。
4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。
永野弁護士は、参加者が多かったのは、「いままでは死なないこと、生き抜くことで精一杯で、お金のことや支援制度のことなど考えられなかった。仮設に入れたことでようやく少しそういうことが考えられるようになった。」ことなどが影響されていたのではと、FBに書かれています。
能登半島地震での支援活動など被災地での被災者支援に尽力されている永野弁護士は、被災前から支援制度を知っておくことが、行政にとっても市民にとっても生活再建の多様な選択肢を活用し、諦めることなく復興に向けて歩み出すことにつながるお話を聞かせて頂く下知地区での講演会が、明日に迫ってきました。
身近に聞かせて頂く機会は、滅多にありません。
どうぞ、ご参加ください。
予約なしで結構ですが、ご一報頂ければ有難い限りです。
なお、駐車場はありませんので、公共交通機関か隣の有料パーキングをご利用ください。
日 時:11月9日(土)18時~20時
場 所:下知コミュニティセンター・4階多目的ホール
テーマ: 「被災後の生活再建に必要な支援制度を事前に知る」
| 11月7日「困難極める輪島の被災者支援、復興まちづくり」 |
能登視察の最終日に訪ねた輪島市での調査内容について、報告します。
【11月4日 輪島市】
10時15分~
 輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。
輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。
11カ所の仮設住宅に500前後の世帯があり、水害の被害も大きく支援者も足りない状況だと言われていましたが、門前地区でも支援者は3名とかで、その負担量は大変だと思わざるをえませんでした。
輪島の方は、大きな家に住んでいた方が多く、土間ほどの広さの間取りで、2人で暮らすことにストレスを感じられている方もいるし、仮設浦上団地では4月に入居して、9月に浸水で、入居者は疲弊しており、メンタル面での支援が必要であるとのことでした。しかし、集会所もなく、今後サロン活動を充実させていくことが課題となっているそうです。
当日は、支所の駐車場にバスが2台止まり、若い方たちが周辺に多くいましたが、水害復旧のボランティアバスが出されており、ボランティアの受け入れ体制も調整されているとのことでした。
訪問した前日には、永野海弁護士が開催された被災者の相談会では、春先より質問も増え、具体的になったと仰られていましたが、永野弁護士のFBでは、「いままでは死なないこと、生き抜くことで精一杯で、お金のことや支援制度のことなど考えられなかった。仮設に入れたことでようやく少しそういうことが考えられるようになった。」ことなどが影響されていたのではと書かれていました。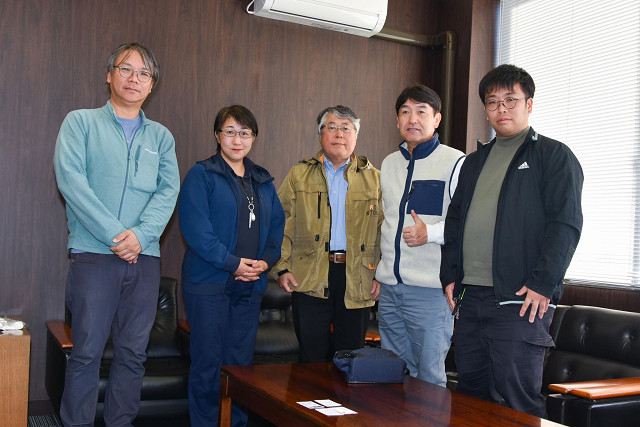
避難所は、8月に一旦閉鎖されていたが、水害で再開されているとのことです。
買い物難民に対しては移動販売もあるが、通院難民は深刻な問題であるとのことでしたし、これまで支所で公費解体の申請受付をしていたのが、11月からは輪島市役所に一本化されたということで、こちらも車の運転ができない高齢者には、大変な負担になることだと思いました。
これから仮設への支援活動に出られる前に時間を取って頂いた山中さんに、感謝し、総合支所を後にしました。
11時~




能登半島のいわゆる外浦と呼ばれる沿岸部で、最大4mを超える地盤隆起があると言われていたが、支所から10数分のところにある門前町黒島の地盤隆起の現場を見てきました。

 今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。
今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。
また、伝統的建造物群保存地区の黒島地区も、中まで入り込む時間はありませんでしたが、道路側から写真だけは撮影してきました。
高知県でも、今後は室戸吉良川地区や安芸市土居廓中での備えの教訓とすべきことだと思う次第です。
12時15分
大地震発生後およそ1時間10分後に火災発生の一報に始まり、地震による断水や津波への恐れで海へも近づけず、消火活動が遅れる中、火は燃え広がり、朝市通りと呼ばれる本町商店街周辺を焼きながら拡大しました。2日7時半ごろ火災を鎮圧、6日午後5時10分鎮火したとの記録があります。



消失面積は約49000㎡、焼損棟数約240棟に上ったと言われています。
そして、象徴的建物だった倒壊ビルの公費解体も始まったばかりの街並みをどのように復興させていくのか、これからの課題であることを突きつけられた輪島市内の火災跡でした。

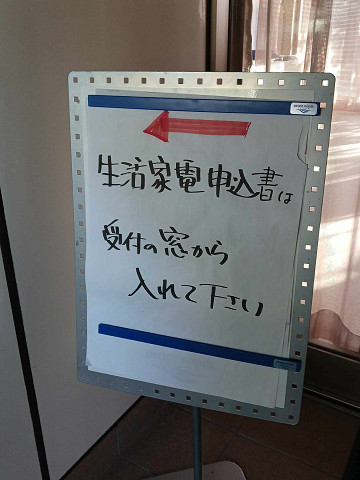 能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。
能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。
【11月3日 珠洲市】
10時~
今は、生活家電支援でお忙しいPWJ珠洲事務所を訪ねて、木下看護師から早速ということで、移動しながら当日の打合せをし、まずは神戸大学建築学槻橋先生とその学生たちによる「記憶の街」ワークショップin珠洲・寺家の展示を案内頂きました。

 この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。
この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。
会場は、最終日ということもあって、たくさんの方が駆けつけており、地元でそのジオラマづくりに関わられていた方々とお手伝いをされた学生さんたちの間で話が弾まれていました。
私も槻橋先生にご挨拶をさせて頂いて、今後下知地区の事前復興に関わって頂きたい旨のお願いもさせて頂きました。
これまで下知地区で取り組んできたワークショップを、さらに「可視化」していくことにも通ずるのではないかと思ったところです。
11時30分~


 会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。
会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。
道の駅の敷地内も液状化部分があり、浮き上がっている施設などもありました。
また、隣接地には、トレーラー型仮設住宅も設置されていましたが、PWJ木下さんの話では、表札がかからず、番号表示のみなのでコミュニティが形成しにくい感じがするとのことで、高知での活用の際にも検討しておかなければならないことだと考えさせられました。
13時~

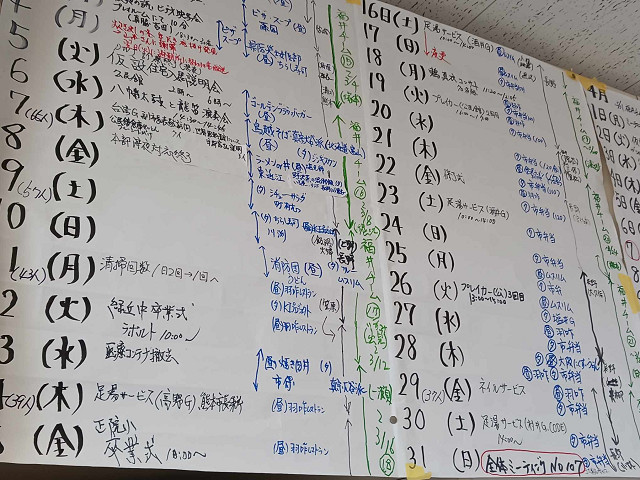
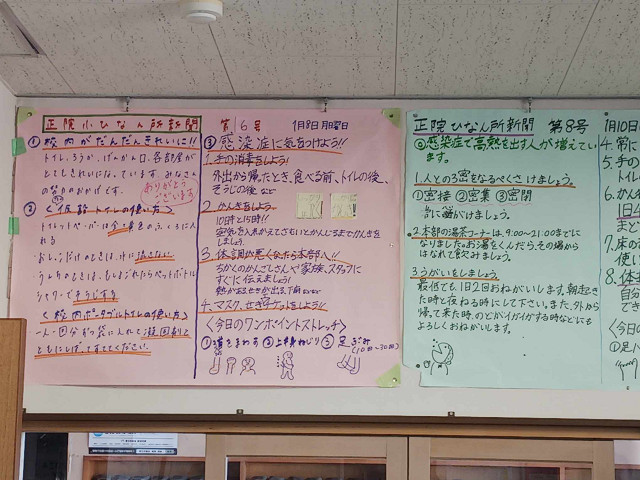
正院公民館長の小町さんから、発災時の避難所運営について、お話を伺ために向かう途中にあった解体工事の廃棄物の仮置き場は満杯状態で、一時解体工事が中断するとの話もありました。
出迎えてくれた小町公民館長が、まず敷地内の断層について説明頂き、施設そのものも傾いており、現在活用されてはいるが、現地修復ではなく移転も視野に入れた検討がされているとの話でした。
事務所や集会室に入って驚かされたのは、正院小学校で避難所開設をしてからの日毎の推移を記録したものや子どもたちが作成した「正院小ひなんしょ新聞」が丁寧に掲示されていたことでした。
このような形で記録されているものを、ぜひ未災地で教訓化して頂きたいとの思いがしました。
お話の中での印象に残った部分を下記に記しておきます。
▼正院地区では震度4以上で公民館長は避難所に駆けつけることになっていて、情報収集・避難所開設を行うこととなっている。
▼避難されていた方々の中で、対策本部を設置して、名簿作りを先ず行ったが、485人+車中泊で約700人だったが、車中泊まで手は回らなかった。正月だったので、帰省客なども多かったので、県外の方も多くいた。
▼消防団員が中心になって、仮設トイレを校庭につくったりしながら、避難所開設を行ったが、その後プッシュ型で仮設トイレや凝固剤が届いた。
▼避難所スタッフで仕事に復帰する方などもいたので、長期の避難所体制に備えるため、10日に班体制などを見直し・再編成をした。
▼1日~15日まではミーティングを朝晩と2回行っていたが、16日からは夕方のみ1回にした。
▼消防団は、見回りを行い、在宅の方の安否確認などにも回ってくれたし、リヤカーでの水の運搬など193日間の避難所運営に23人の団員が、ずっと関わってくれて、八面六臂の活躍だった。また、団員2名が避難者として過ごされていたので、避難者も安心感を持たれていた。
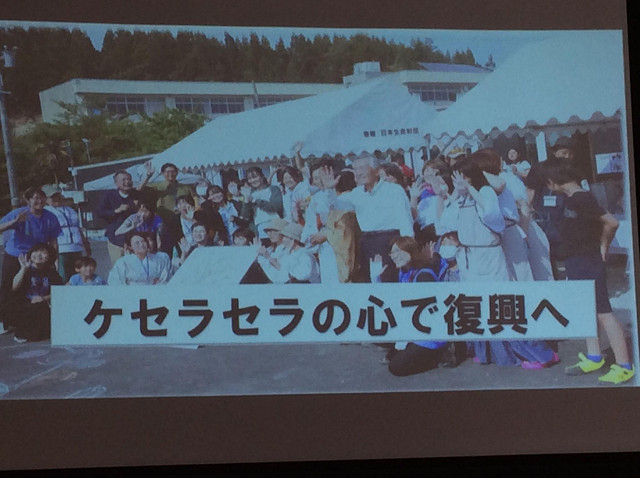
▼避難所としての学校を子どもたちが使えるようにする準備もしていった
▼感染症が出始める中で、運営の当番には「オールキャスト」で臨んだ。
▼小中学生が作成した「正院小ひなんしょ新聞」にも、その対応が呼びかけられるなどした。ひなんしょ新聞は「ケセラセラ」と名付けて、子どもたちが、希望を持たせてくれた。
▼支援物資も届き体育館で管理したが、子どもたちに体育館を使ってもらうために、支援物資を整理して、体育館をできるだけ使ってもらうようにし、卒業式も行えた。避難所と学校の共存をめざした。
▼昨年の5月の地震の際に、ボランティアで来てくれた縁で富山の方が炊き出しも行ってくれた。
▼運営のポイント
①県内外の支援チームの力を借りる。受け入れ体制を整えてその専門知識や知恵を活かす。
②運営が円滑に行くよう班構成を工夫する。避難所の変化に伴って班構成を見直す。
③避難者、スタッフ、県内外の支援チームが運営方針を共有できるようにミーティングを重ねる。
➃一人に負担が集中しないよう各班で連携を深める。順番に休息が取れるように体制を工夫する。
▼今後の課題
①指定避難所の想定避難者数に見合う備品(水、食料、簡易トイレ、毛布、個別テント、段ボールベッド、マット、パーテーションなど)の充実を図る。定期的な点検を怠らない。
②「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを念頭に、公民館や自主防災組織などを中心に置きながら、地域住民が協力できる体制を作り上げていく。
▼避難所運営については、避難者の多くが、地域の中で顔の見える関係があったことが、うまくいったことにもつなかったと思う。いずれにしても性善説にたって避難所運営にあたるという心持が大事だと思う。
▼150年以上続くお祭り「奴振(やっこふり)」があるし、運動会もあるが、コロナで中断していたものの昨年再開した矢先だった。公民館事業もできるだけ早く復活したい。
15時~
 若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。
若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。
気づいた時には、浸水が始まっており、やっとの思いで避難したとのことで、私たちに「とにかく避難袋を持って逃げるのではなく、身一つで命だけ持って逃げた方がよい」とのメッセージを頂きました。
今度の日曜日には、避難所の集約によって、今の避難所から引っ越さなければならないとのことで、PWJの木下さんと相談をされていましたが、地震・水害という二度の災害が大きくダメージを与えている被災者の気持ちを考えた時、我々も「複合災害」への向き合い方を考えておかなければならないことを痛感させられました。
16時30分~

 津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。
津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。
一方で、世界的建築家がデザインした、木造2階建て仮設住宅6棟90戸が完成しており、接着剤を使わず接合した集成材「DLT」で作った箱型ユニットを積み重ね、仮設住宅では初の木造2階建てを実現し、県内産の杉が使われているとのことです。
仮設住宅用地が、大幅に不足している本県においても、2階建て仮設住宅の参考となるのか、検討が必要となります。
4日早朝には、宿泊させて頂いたPWJ珠洲事務所の周辺を見て回ったが、公費解体工事が7時から始められていると状況を目の当たりにしたが、やっと公費解体が進み始めたということだと感じる街並みでした。




3日間の連休を利用して、下知消防分団の国見団長らとともに、能登半島地震の被災地を訪ね、現地を視察の上、支援団体や地域の公民館長などから当時のお話を聞くなどしてきました。
初日は、豪雨の中を北上していった関係で、金沢市内の高台団地崩落現場は時間的に視察できませんでしたが、11月3日の珠洲市~4日の輪島市にかけては、何とか予定通り視察・ヒアリングを行わせて頂きました。
日頃からご指導いただいているPWJさんの事務所に宿泊させて頂くとともに、正院公民館さんをアテンド頂くとともに、被災地を順次案内頂きました。
また、輪島では門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われているJOCAの山中弓子さんから門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。
お世話になった皆さんに感謝する次第です。
しかし、調査内容が多岐にわたりますので、後日改めて報告させて頂くこととします。
| 11月1日「学校に行きづらい児童生徒と寄り添える体制の拡充を」 |
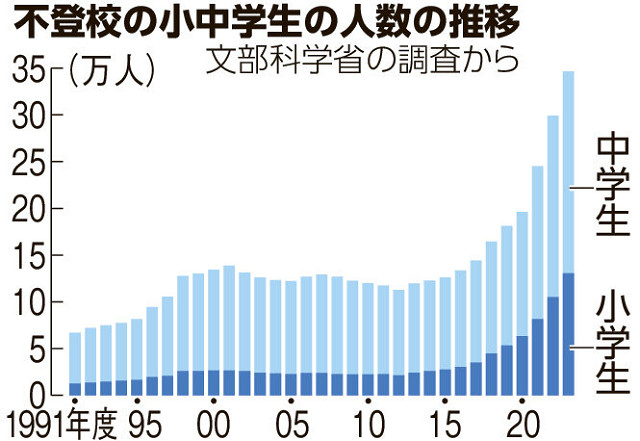 年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。
年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。
前年度より4万7434人増加し、30万人超は初めてで、11年連続の増加で、特に20年度以降に約15万人増えています。
文科省によると、「不登校」は、病気や経済的理由を除き、心理・社会的な要因などで登校できない状況を指しており、不登校の子は小学校13万370人(前年度比2万5258人増)、中学21万6112人(同2万2176人増)で、小中学生全体の3.7%(同0.5ポイント増)をしめているとのことです。
文科省は不登校の子の前年度からの増加率は、今回は15.9%で22年度の22.1%から下がり、増加の勢いは鈍っており、23年から不登校対策プランを打ち出し、居場所づくりや相談体制の充実などを進めており、効果が出始めているともみています。
県内における小中学校の不登校の児童・生徒は1604人で千人当たりでは過去最多の34.3人となり、全国で15番目の少なさとなっており、登校しづらい児童生徒の早期支援や校内サポートルームなど現場の取り組みも全国より増加率を抑えていることにつながっている面もあるのではないかと、言われています。
不登校の子が急増した理由について、文科省は、「コロナ下の生活リズムの乱れ」「コロナ下の行事縮減などで登校意欲が減退」「障害などの理由で配慮が必要な子への適切な指導・支援が不足」などを挙げています。
朝日新聞記事の中で、東京大先端科学技術研究センターの近藤武夫教授は教員の気づきと配慮を挙げ、立命館大大学院の伊田勝憲教授(教育心理学)、教員らの増員や職員研修の充実が必要と説き、大阪公立大の山野則子教授(子ども家庭福祉)は、学校と関係機関の間に立つスクールソーシャルワーカー(SSW)を軸にした早期の対応の必要性を指摘されています。
いずれにしても、児童生徒と向き合う教職員や学校組織のあり方が問われているが、そのように児童生徒と寄り添える体制の拡充なしに、求めても限界はあると思われます。
日頃、地域活動を通じて、学校現場を見せて頂く機会も多いですが、先生方は手一杯であることを目の当たりにします。
教職員を増員し、児童生徒たちとしっかりと向き合い、寄り添えて、早期支援に取りかかれる体制がどうしても必要なのではないでしょうか。
| 10月31日「能登半島地震からの警告を受け止めない女川原発再稼働」 |

 東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。
東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。
2011年3月11日に地震と津波に被災し、電源設備に甚大な被害を受けて火災を発生させた女川原発だが、再び原子炉災害を起こせば避難も困難な原発の再稼働に抗議せざるをえません。
女川原発2号機は、東日本大震災後、被災地では初の再稼働であり、沸騰水型軽水炉の82.5万キロワットで、建設時期が異なるものの震災でメルトダウンした福島第一原発2、3号機と同型炉であります。
東北電は約5700億円を投じて、海面からの高さ29m、延長800mの防潮堤や、海水の浸入を防ぐ厚さ30~40㎝の防潮壁を築くなどの対策を実施し、6年にわたる長期審査を経て、新規制基準に「適合」となりはしたものの、無論「安全のお墨付き」ではなく、住民の不安は残ったままです。
地元紙の河北新報が3月、県内有権者を対象に実施したインターネット調査で、女川再稼働に「反対」と答えた人が44%と「賛成」の41%を上回っている中で、原子炉に再び火を入れた東北電の責任は極めて重大であると言えます。
牡鹿半島の真ん中あたりに立地する女川原発は、避難上の制約が強く、地震や津波に原発事故が重なる「複合災害」のリスクも計り知れません。
原発30㎞圏内の3市4町には約19万人が暮らしており、そのうち半島先端部から陸路で避難する人々は、事故を起こした原発に向かって逃げることになるし、その陸路が断たれる可能性もあります。
東日本大震災時には、女川1号機タービン建屋で火災が発生したが、地震で道路が寸断されて消防車が出動できず、所員が粉末消火器で消し止める事態も起きています。
能登半島地震で避難道路がほぼ使えない状態になったことを教訓とするならば、こうした場所に原発は建てられないはずであるし、建っている以上再稼働ではなく、廃炉を急ぐべきではないのでしょうか。
能登地震からの警告を真摯に受け止めるべきです。
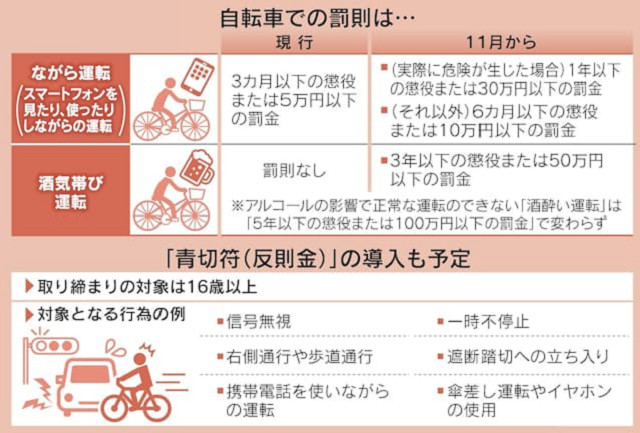 改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。
改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。
酒気帯び運転は、これまでも禁止されていたが、正常に運転ができないおそれのある「酒酔い状態」のみが罰則の対象でした。
これからは、酒気帯び運転の基準は車と同じで、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを含んだ状態についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、酒気帯び運転になると知りつつ酒を提供するなどした人も罰則の対象になります。
また、自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンを使う「ながら運転(ながらスマホ)」の厳罰化は、違反した場合は最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。
自動車は2019年に厳罰化され、ながらスマホによる事故は一時減少しましたが、ここ数年は再び増加に転じているとのことです。
警察庁によると、今年上半期(1~6月)に全国であった自転車のながらスマホによる死亡・重傷事故は、前年同期比約2.3倍の18件で、統計が残る07年以降で最多となっています。
自動車のながらスマホは、19年12月にも罰則が強化され、死亡・重傷事故は19年の105件から20年は66件に約半減しましたが、その後再び増加に転じ、23年は厳罰化前を上回る122件に上っています。
ながら運転の罰則強化について、専門家は「危険性が十分認識されなければ、厳罰化しても事故は再び増加しかねない。取り締まり一辺倒になれば、不満だけが残ってしまう。法律とともに、危険性をよく知ってもらうような地道な活動が必要ではないか」と話されています。
私たちも、早朝や夜間に交通安全の街頭指導を行いますが、厳罰化されるこの「飲酒」と「ながら」運転以外にも、ヒヤリとさせられるのが、右側運転の多さです。
これも、いつ事故につながるか分かりません。
「自分は大丈夫」と思っている方は多いかも知れませんが、災害と同じで、「正常性バイアス」を働かせるのではなく、我が事として、安全運転に注意することこそが、求められています。
| 10月28日「自公の過半数割れで政治の変化を注視して」 |
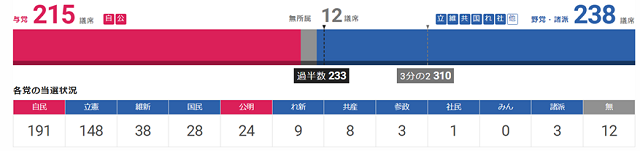 石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。
石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。
立憲民主党をはじめ野党議席の増加、自公の敗北という全国的な傾向の中で、高知で見える政治の景色が、大きく変わることはなかったことは、残念な結果でありました。
全国的な傾向は、「政治とカネ」の問題にけじめをつけられない自民党に「ノー」を突きつける有権者の審判であり、変革を望む国民の期待を裏切る形となった石破茂首相への失望感の表れでもあると言えます。
自民の最大の敗因は、第2次安倍政権以降に深刻化した政治のゆがみやおごりを、根本から正そうとしなかったことで、森友・加計両学園問題などの疑惑が表面化し、安倍氏の死去後には、旧統一教会との組織的な深い関わりも明るみに出、裏金問題もウミを出し切ることができなかったことによると思われます。
石破新体制になっても、裏金議員は、最終的に一部を非公認としたものの、当初は裏金議員も「原則公認」としようとしたし、選挙戦後半には、非公認が代表を務める政党支部にも、税金が原資の政党交付金から2千万円の活動費を支給していたことも明らかになるなど、「反省」は口ばかりであることが白日のもとに晒されました。
もっと政策論争をするべきだったという声もあるが、それこそ石破氏が当初言っていたせめて予算委員会での議論がされていたら論争すべき政策も明らかになっていたでしょうが、それを避けてボロが出る前の短期解散総選挙に打って出たのは、ブレブレの石破首相自身でした。
今回の結果を受けて、早速「ねじれて決まることも決まらなくなる」という人もいますが、これまで数の力を頼みとして異論に耳を傾けず、国論を二分するような課題でも、国会を軽視して自公の閣議決定のみで決めていくという独善的な政権運営が、せめて国会の場で議論されて国民の目に明らかになることが余程大事だと思って頂きたいものです。
今回の過半数割れを起こした自公が野党にどのような懐柔策を講じてくるのか。また、野党もそのことと、しっかりと対峙していくよう、そして、我々は本来の国民のための政治が行われることを求めて注視していかなければなりません。
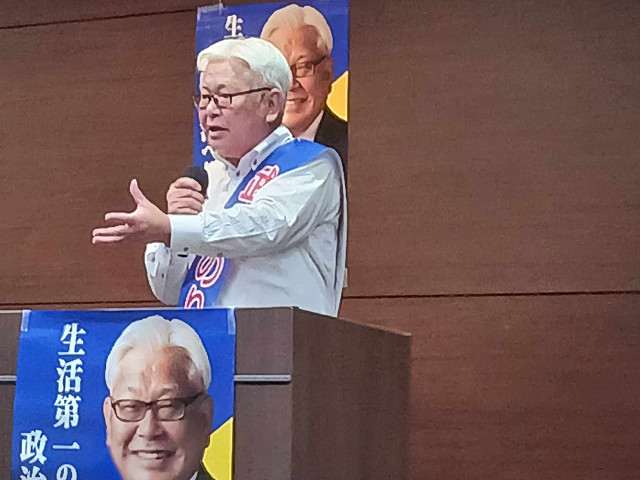
 今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。
今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。
1996年に小選挙区制が導入されて以降の投票率で、最も高かったのは旧民主党に政権交代した2009年の67.64%で、自民党が政権復帰した12年に53.89%と下がり、14年は戦後最低の50.98%を記録しました。
前回21年の投票率は57.34%と前々回からは5.47ポイント上昇したものの、近年は50%台に低迷しています。
昨日付け高知新聞「決戦の視角」で、「教育、仕事、家族にもきしみ」と題して東大本田由紀教授は「総選挙を目前にして、見えるのは亀裂や機能不全、聞こえるのはきしみや悲鳴である。」と嘆き、「「自己責任」や家族内での相互扶助が当然視されているため、個人や家族が抱えるさまざまな困難は個々の世帯に抱え込まれ、孤独死や、親子間・夫婦間の凄惨な暴力に至る場合も少なくない。困窮する個人や世帯が増加しているにもかかわらず、セーフティーネットは希薄なままである。」と指摘しています。
こうした全ての亀裂や悲鳴を生み出し、あるいは放置してきたのが、これまでの日本の政治であり、政権党たる自民党の裏金政治、旧統一教会との癒着によって権力の座を維持することによって行われてきた政治を批判し、次の言葉で結んでいます。
「いま求められる施策は、教育・保育に投入する公的資源の拡大と改善、賃金水準の向上、そして個人を対象とする生活保障の拡充である。政治は人々の命と暮らし、尊厳を支えるためにこそあるはずだ。諦め続けていてはならず、票という形で選択を突き付けなければならない。」と「諦めずに投票へ」と呼びかけています。
投票率があがれば、2009年のような状況を作り出すことが期待されます。
「投票に行って、政治を変えよう」、残された時間で武内のりお候補と一緒に、金権裏金政治を「生活が第一、まっとうな政治」に変えるため、もう一回り働きかけていきましょう。
| 10月25日「高知のバリアフリー観光もこれからもっと前進を」 |

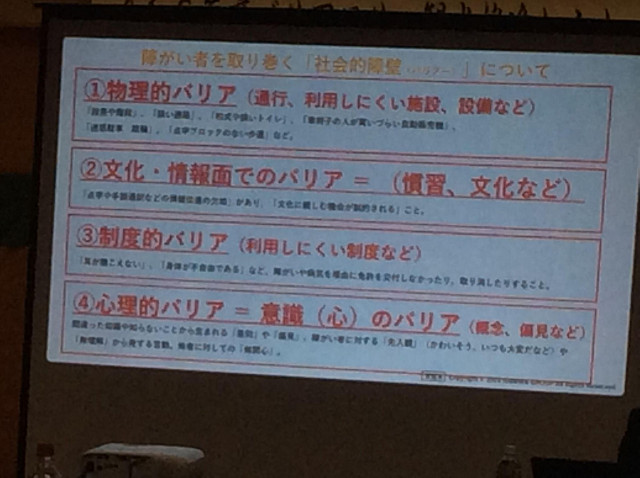

昨日は、9月定例会でも取り上げさせて頂いたバリアフリー観光の推進についてのセミナーが、県観光政策課おもてなし室主催、県旅館ホテル生活衛生同業組合協力で開催されていましたので、参加させて頂きました。
参加対象として、観光・宿泊施設や観光案内業務に従事する方など観光関連事業者の方々で、会場参加・Zoom参加あわせて50名ほどの方が参加されていたようです。
基調講演で「バリアフリー・ユニバーサルデザインがもたらす旅館のビジネス価値」について有限会社なにわ旅館代表取締役社長勝谷有史氏からは、2006年から段階的にフロアごとに全面改修を行い、露天風呂付バリアフリールームをオープンするなど「商売としても、従業員にとっても、十分な合理性があり、将来に向け重要な取り組みである。」をモットーに、お客様に一つバリアフリーを提供するときは、従業員にも一つ改善点を提供するなどソフト面の強化も図りつつ、旅館のバリアフリー化を進めてこられた経緯などのお話は、貴重な内容で、誰もが宿泊したくなるコンセプトの旅館であることを痛感させられました。
障がい者を取り巻く社会的障壁として「物理的バリア」「文化・情報面でのバリア」「制度的バリア」「心理的バリア」を解消してきたが、これに加えて食元「食のバリアフリー」にも取り組まれていることの紹介もあり、宿泊施設における合理的配慮について具体的に学ばせて頂きました。 そして、この取り組みが、収益の向上にも繋がっていることも披露して頂きました。
また、トークセッションでは、「高知県が目指すバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について」ということで、講師の勝谷有史氏をはじめ山本祥平氏 (ネスト・ウエストガーデン土佐 代表取締役、有瀬智寛氏(県観光政策課おもてなし室チーフ)らによって、「車椅子ユーザーにとってのシャワーの位置の配慮」だとか、「旅館・ホテルは部屋ばかりでなく浴室・トイレの様子などの写真も紹介して欲しい」、黒潮町の海辺のホテルでは、「自然の恵みと災いのつながり、避難へのバリアフリーの課題」などの意見が出されました。
勝谷社長からは、「『逃げるバリアフリー』は簡単なマップや障がいごとのチャートが必要。避難弱者を迎え入れられるようにクラファンで段ボールベッドを購入した。伸びていく分野なので、成功体験つくって欲しい。」とのアドバイスも頂きました。
また、勝谷社長は、困った時のバリアフリーツアーセンター頼みと言われていましたが、高知でも行政と県バリアフリー観光相談窓口と観光施設・旅館・ホテルがさらに連携できるしくみが築いていけることを願っています。
セミナーが終わってから勝谷社長と名刺交換をしながら話していると、「高知のバリアフリー観光相談窓口も随分と情報やスキルを蓄積されているので、県内のホテルなどはもっと活用すれば良い」と話されていました。
また、県観光政策課おもてなし室有瀬チーフが、「県としては、これからはバリアフリー観光×防災の対応などにも取り組み、高知県のバリアフリー観光も進んでいるねと言われるようになりたい」との思いを述べられていましたが、一歩ずつ進んでいくことを期待しています。
最後の事例報告として県子ども・福祉政策部 障害福祉課前島チーフから「障害者差別解消法改正後の高知県の現状について ~合理的配慮とは~」、 県バリアフリー観光相談窓口で奮闘されているNPO法人福祉住環境ネットワークこうちの笹岡和泉理事長から、「今すぐ書ける!心のバリアフリー認定制度の申請の仕方について」の紹介がありました。
いずれにしても、ソフトから入りつつも、遅れることなくハードも整備するバリアフリー化が観光や防災分野などあらゆる分野で当たり前になっていくことを共に取り組んでいきたいと感じさせられるセミナーでした。

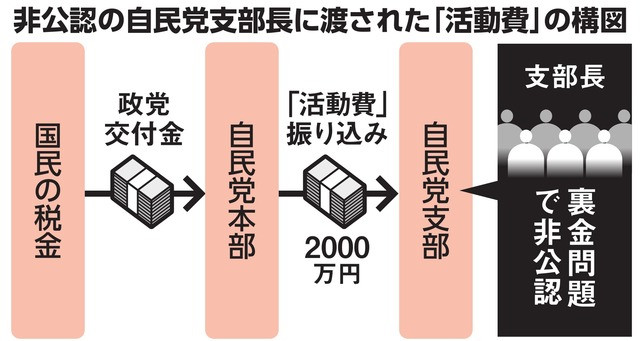 今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。
今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。
自民党の派閥裏金問題で、非公認になった候補にも、党本部から各候補が代表を務める政党支部へ2千万円の活動費が支出されていたことが明らかになりました。
自民党森山幹事長は「候補者に支給したものではなく、党勢拡大のため」とし、個人の選挙目的ではないと言い訳していますが、公認候補へも同時期に公認料と活動費をあわせた計2千万円が支給されており、非公認候補への「裏公認料」ではないかとの批判が高まっています。
公認候補には衆院解散の9日、政党交付金から公認料500万円と活動費1500万円の計2千万円をそれぞれの政党支部へ振り込まれており、非公認や不出馬になった人が代表を務める政党支部に対しても、活動費として2千万円が支給されたと言われています。
これでは、公認候補がいる支部の活動費は1500万円なのに、非公認候補の支部の活動費は2000万円と500万円も多いこととなり、説明がつかないのではないでしょうか。
いずれにしても、こんなやり方では、裏金問題の責任を取らせる形で公認しなかったという説明と矛盾するし、このような自民党が責任をとり、今後の政治とカネの問題で国民の信頼を取り戻すことはできないと明らかにしているようなものです。
残された期間はわずかとなりましたが、自公の過半数割れを現実のものとするため、全力で闘い抜きましょう。
 衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。
衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。
不安の選択肢「仕事」「ワークライフバランスの充実」「車を買う」「家を建てる」「結婚」「子育て」「親の介護」「南海トラフ地震」「高知で一生を過ごす」「老後の生活」「その他」の中からも1~3位を選び、得点づけをして、146点で1位となったのが、「南海トラフ地震」で31人がトップに挙げたということでした。
「高台に引っ越したいがお金がない。」「生き延びても、その後どうなるか。助けが来るのは最後になりそう。」「復旧は高知も相当後回しにされるだろう。見捨てられないようにして。」などといった声とあわせて、男女を問わず「避難所では、プライバシーが守られるようにして。」との声が目立ったとのことでした。
記事では「一位は当然というべきか、南海トラフ地震」と書いてあったが、そうであれば、日頃からその不安を自分事にできているのだろうかと思わざるをえませんでした。
政治に臨むこととともに、不安を平時から解消するために、今の若者が何ができるのか、共助の担い手が高齢化して、手薄になっている中で、若者が少しでも担ってくれたら、そこの中での課題を含めて、南海トラフ地震への公助を政治に求める声にも迫力と説得力がもたらされるのではないかと思ったりします。
いずれにしても、今回のアンケート結果を、総選挙の結果を踏まえた政治の場でしっかりと受け止めた政策の具体化を図って頂きたいものですし、県政の場でも、我々はしっかり受け止めなければと思ったところです。
| 10月22日「二重被災に苦しむ被災地に寄り添っているのか」 |



10月8日に参加した日弁連主催オンラインシンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」でも、「罹災証明」問題を勉強させて頂きましたが、9月の豪雨災害から一か月経った今、改めて二重被災した被災者の罹災証明が着目されています。
1月の能登半島地震の被災地では、住宅の被害認定が実態に即しておらず、再建のための支援金も不十分と指摘されている中、今回の豪雨災害で二重被災した方への生活や住まいの再建を後押しする仕組みが求められています。
これまでの災害では、判定は災害ごとに実施されていましたが、9月の豪雨による被害は、元日の地震の影響で拡大した可能性があり、個別に判定すると、一部損壊などの判定を受けた世帯が、十分な支援を受けられないおそれがあることから、地震で一度判定を受けていても、修理前に豪雨で再び被災すれば、豪雨後の調査をもとに新たな判定を受けられるようになりました。
例えば、従来の判定なら地震で準半壊、豪雨で一部損壊となる場合でも、豪雨後の被災状況を一体的に調査し、半壊の認定を受けられる可能性があり、半壊以上と認定されれば、今回の災害では仮設住宅に入居できたり、住まいへの支援など、受けられる支援が手厚くなります。
11月9日に、私たちの下知地区でも講演をお願いしている日弁連災害復興支援委員会副委員長、永野海弁護士は「認定結果が半壊未満だと、受け取れるお金は大きく減る。罹災証明書が小切手のようになっており、(被害を)きちんと見てもらいたい」と述べられています。
地震と豪雨の「二重被災」に苦しむ能登半島でも、解散総選挙が始まりました。
「選挙どころじゃないのに」との声があがる中、住民基本台帳の住所へ送られる投票所の入場券は、有権者の手元に届いているのでしょうか。
避難所や仮設住宅で暮らす住民が転送手続きはどのくらいしているのか、被災者の皆さんの投票する権利さえ奪われかねない今、なぜここまで急いで解散総選挙をしなければならなかったのか。
防災省を検討するという石破首相のもとで、被災者に寄り添い、被災者と向き合う本気度を伺うことはできません。
| 10月21日「自公過半数割れを現実のものとするために」 |
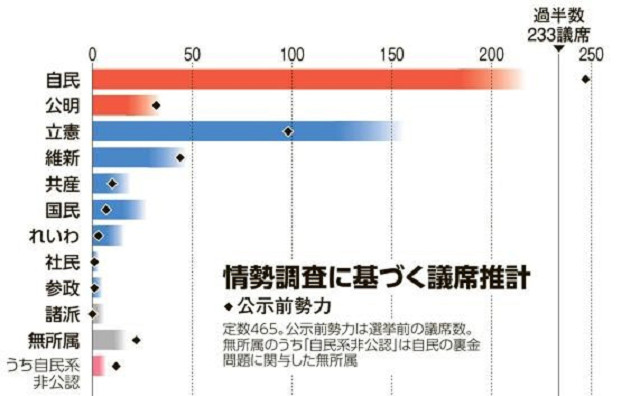
 昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。
昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。
行き交う車や通行人の方からの反応は3年前より、手応えは良くなっているという感じを受けました。
それを「感じ」ではなく、確実なものにしていくためさらなる支援の輪を広げて頂くよう訴えていきたいと思います。
市役所近くで声をかけられた知人は、職業柄明らかに自民党を支援する団体に所属されていると思われる方でしたが「もう自民党はいかん、坂本さんが応援しよう人に今期日前で入れてきたき」と仰ってました。
今朝のマスコミ報道でも、「自公過半数、微妙な情勢」とあり、自民は単独過半数割れの公算が大きくなっているようですが、その結果を確かなものにするには、これからの闘い次第です。
朝日新聞社の情勢調査では、現時点では、①自民党、公明党の与党は過半数(233議席)を維持できるか微妙な情勢で、自民は公示前の247議席から50議席程度減る見通し②立憲民主党は公示前の98議席から大幅増③国民民主党、れいわ新選組に勢いなどの情勢となっているそうです。
また、投票先を決めるとき、自民党の裏金問題を「重視する」が54%で、「重視しない」の38%より多かった一方で、裏金問題に関与し、今回の衆院選に立候補した46人のうち半数が当選をうかがっているということが残念でなりません。
なんとしても、自民党の金権腐敗の権力による暴走をこれ以上許さないために、最後までの闘いを強化していきたいと思います。
| 10月19日「自民党による権力の腐敗・暴走に歯止めを」 |
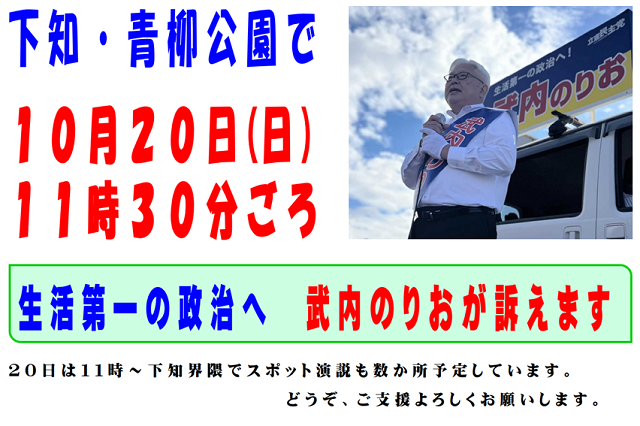 今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。
今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。
まさに、この課題は、長期的で絶対的な権力が腐敗して暴走したことによってもたらされたものと言わざるをえません。
自民党は、1955年の結党から現在に至るまで行われた22回の総選挙において、21回第一党の位置を占めてきました。
下野したのは2回、4年間だけで残り65年間は、自民党は常に日本の権力中枢に居続けています。
普通選挙が実施される民主国家において、これだけの期間一党独裁の状態にあるのは異常と言えるのではないかと指摘されることもあります。
国民に対して十分な説明もしない、国会審議もしないで閣議決定によって、憲法違反の国の方針・路線をいとも簡単に転換してしまう暴走を止めることができなかった責任を感じつつ、今回ばかりは腐敗した権力によるこれ以上の暴走に歯止めをかけたいものです。
高知一区では、立憲民主党武内のりお氏の勝利に向けて、県民に訴える機会をつくるために明日は候補者に同行してともに訴えていきたいと思います。
| 10月16日「忘れたらいけないことを刻んで衆院選と向き合う」 |

 衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。
衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。
天声人語は、「人間は忘れる生き物である。」ということで、19世紀のドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスの有名な実験にもとづいて、「忘却は急速に進むが、その速度は徐々に落ちていくこと。一定の期間を経ても覚えていることは、長く記憶に刻まれるらしいこと。」だそうです。
今回の衆院選は、「目の前の石破政権を問う選挙であると同時に、この3年間の岸田政権への審判である。さて、と自戒を込めて考える。前回の総選挙からの政治を、いったい私たちはどれだけ覚えているか」と振り返られています。
お互い、しっかりと振り返り、裏金や旧統一教会の問題だけではなく、納得できな買ったことと向き合って、審判を下すべきではないでしょうか。
私たち以上に「記憶にない」を常套句を口にする政治家を国会の場に送ることのないようにしなければと思います。
そして、34面には、余りにも次々と迫りくる自然災害の中で、忘れられてはならない地域のことが取り上げられていました。
東日本大震災の復興過程で人口が1/4になってしまった石巻市雄勝町は、小選挙区が1減となった全国10県のうちの一つで、仙台市に近い内陸部の都市などと共に宮城4区になりました。
被災地の雄勝の声は、今まで以上に届かなくなるのではとの有権者の声が、「私らは枝っこの枝っこ」に表れています。
そして、記事には、雄勝町の復興の課題について、ずっと教えて頂いてきた阿部晃成さんのコメントが掲載されていました。
「雄勝町で生まれ育った阿部晃成さん(36)は語る。慶応大大学院を経て、宮城大と金沢大で災害社会学を研究しながら、能登半島にも通う。ふたつの被災地で目にしたのは、「効率の悪い地方は捨てる」という集落再編の議論だった。災害が多発し、過疎が進み、議員が減る。この構図が進めば、「日本中のまちが取捨選択の対象となりかねない」と語る。」とあります。
そんなこの国の構図をつくってきたのが、自民党の政策による、地方の「選択と集中」だったのではないでしょうか。
今回も自民党は「日本創生」というが、また切り捨てられるのではないかと不安にさいなまれている能登半島を中心とした被災地の皆さんがいることを忘れてはなりません。
| 10月13日「再審法改正意見書、自民党らの反対で否決」 |

 県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、賛成の立場から討論させて頂きました。
県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、賛成の立場から討論させて頂きました。
9月26日、静岡地方裁判所は、1966年強盗殺人罪などに問われ、1968年に死刑判決を受けた袴田巌さんに再審無罪の判決を言い渡され、逮捕から58年、死刑判決が確定してから44年、2023年10月の再審開始から15回の審理を経て出されたこの判決に対して、10月8日に検察当局が、控訴を断念し、88歳の袴田巖さんの無罪が確定しました。
しかし、逮捕と死刑判決によって袴田さんが失った膨大な時間を取り戻すことはできず、拘置所で長年自由を奪われたことによって引き起こされた拘禁症とは今後も闘い続けなければなりません。
今も、狭山差別事件をはじめ多くの冤罪事件で、再審が求められている中で、このような過ちが繰り返されないためにも、無実の者を冤罪から迅速に救済するためにも、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を行うことが求められているのです。
本意見書は、総務委員会では、不一致となりましたが、その後、検察当局が、控訴を断念し、袴田巌さんの無実が確定し、再審に関する法整備を求める世論が高まり、最高検も今回の再審請求の長期化について検証するといわれている中、多くのマスコミが、制度改正への歩みを進めるべきではないかと問うている中での本会議再提出でした。
常任委員会では、賛成できなかった議員の皆さんも、この間多くの報道や識者のコメントを目にする中で、しかも国会では、自民党をはじめとした各党首が名を連ねた超党派で308名に上る「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が、改正を求めている中で、賛成してくれるのではないかとの思いで討論を行いました。
しかし、「再審に際し捜査で集めた検察官の手持ち証拠を全面開示すること。」と「再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(上訴)を禁止すること。」を求めた本意見書は、自民党、公明党、一燈立志の会、自由の風の反対で、否決されてしまいました。
地方議会では、今回のような再審法改正を求める意見書が、8月20日現在で、12道府県議会と323市町村議会で採択されている中、高知県議会の多数会派の皆さんの人権意識に疑問を持たざるをえません。
| 10月12日「被団協へのノーベル平和賞を各国指導者は真摯に受け止めよ」 |
 昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。
昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。
ノーベル委員会は授賞理由に、二つの要素を挙げており、一つは、「核兵器のない世界の実現に尽力してきたこと。」そして、もう一つは、「核兵器が二度と使われてはならないと証言してきたことだ。」として、被爆者の存在を「唯一無二」と讃えています。
そして、ノーベル委員会のヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長は、取材に対して、「被爆者とその証言が、いかにして世界的な広がりを持ったか。いかにして世界的な規範を確立し、核兵器に『二度と、決して使ってはならない兵器』という汚名を着せたか。それこそが、この賞の本質なのです」とも答えています。
「核兵器の使用を二度と認めてはならない。そうした国際的な規範を意味する。」ことは、被爆者が戦後80年近く、証言に証言を重ね、その意義を固め、訴え、日本国内外でコツコツと築き上げてきたものとしての被爆者への敬意が、フリドネス委員長の発言からは、滲んでいます。
「核兵器の全廃は非現実的だ」との声にどう反論するかと問われた委員長は「核兵器に安全保障を依存する世界でも文明が生き残ることができると考える方が、よほど非現実的ですよ」と即答されたそうです。
さらに、フリドネス委員長の「被爆者の体験談、証言は、核兵器の使用はどれほど受け入れられないものかを思い起こさせてくれる重要なものです。彼らの声を聞くべきです。そして、すべての指導者が、痛ましく、強烈な被爆者の話に耳を傾け、核兵器が決して使われてはならないと思い起こしてほしいと願っています。」との言葉を、肝に銘じて欲しいものです。
そして、何よりも「広島と長崎への原爆投下後、過去80年近く戦争で核兵器が使われなかったことも、被爆者一人ひとりの尽力があったからだ」との言葉こそ被団協、被爆者のへの感謝の言葉だと思います。
私たちも、常にその声に耳を傾けながら被爆者の「理解できないほどの痛みや苦悩」を理解しようと努力し、繰り返さないための警鐘を世界に発し続けていきたいものです。
| 10月10日「二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」 |



10月8日は、常任委員会審査が休会だったので、オンラインで日弁連主催のシンポジウム「能登半島地震 二人三脚の復興を目指す~罹災証明問題を考える~」に参加できました。
早川潤弁護士(金沢弁護士会元副会長)の「金沢弁護士会の活動報告」、江﨑太郎氏(特定非営利活動法人YNF代表)の「復興支援『ミツバチ隊士業派遣プロジェクト』で見えてきた現状」についての報告の後に、「二人三脚の復興を目指す ~罹災証明問題を考える~」をテーマにパネルディスカッションが行われました。
パネリストには、報告に引き続き江﨑太郎氏をはじめ、林正人氏(一級建築士、能登復興建築人会議)、お隣徳島県の堀井秀知弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会副委員長)、今度下知で講演頂く永野海弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会副委員長)が並び、いつもご指導いただく津久井進弁護士(日本弁護士連合会災害復興支援委員会元委員長)が、コーディネーターを務められました。
罹災証明書による認定によって、いかなる支援が受けられるのかが決まり、被災者の将来が決まってしまいます。
しかし、災害が発生するたびに、罹災証明書をめぐる課題が指摘されています。
罹災証明書による認定によって、いかなる支援が受けられるのかが決まり、被災者の将来が決まってしまいます。
被災者と行政が対立するのではなく、復興という方向に向いて、被災者と、自治体、支援専門家等の二人三脚、三人四脚による生活再建、地域の復興を実現するために大切になる視点や問題点等のお話を聞かせて頂きました。
被災地で誰に聞いても、罹災証明のことを十分に知らないのに、申請期限を設けて打ち切るなどということがあってはならない。
被災者が罹災証明の申請の窓口を怖がらないように、「一緒に頑張りましょう」の一言で受付が始まると随分違う。
被災地、被災住民のための復興であり、そのための罹災証明であって欲しいとの思いの伝わるメッセージをありがとうございました。
また、昨日7日付けで石川県から発出された地震と豪雨の二重被災での罹災証明の判定方法についても、情報提供いただきありがとうございました。
| 10月9日「袴田さん無罪確定、次は狭山事件の再審の扉を開ける」 |
 58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。
58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。
しかし、袴田さんは、誤った判決によって半世紀近く自由を奪われ、死刑執行を恐れて心を病み「拘禁症」と向き合い続けています。
この人権侵害を起こした関係機関の責任は問われ続けるのではないでしょうか。
本来なら、誤判をなくすことがまず求められるが、人間が担う裁判に完璧はなく、再審はその非常救済手続きとして認められる制度です。
しかし、再審の可否を決める再審請求審の進行が見通せない上、再審開始決定が出ても検察官の上訴でさらに年月がたつうちに、関係者が高齢になって実質的な救済をなしていない実態が突きつけられているのです。
袴田さんは、その象徴的な実例でもあり、袴田さん以外の再審請求にも、私たちが支援して闘い続ける狭山差別事件の石川一雄さんにも言えることです。
このような事態を招く最大の原因は、刑事訴訟法に再審手続きについての規定がほとんどなく、進行が担当裁判官次第となっていることにあると言われます。
だからこそ、このようなことを繰り返さないために、今9月定例会に、国に対して「再審に際し捜査で集めた検察官の手持ち証拠 を全面開示すること。」と「再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(上訴)を禁止すること。」を求める「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案を提出しました。
総務委員会では、全会一致とならず、本会議に再提出をして、私が賛成討論をすることとなっています。
この機会を逃さず、再審法制の不備を改めるための闘いと狭山事件の再審の扉をあけるための闘いを、前進させていきたいと思います。
| 10月8日「解散総選挙で『変われない自民党』に鉄槌を」 |
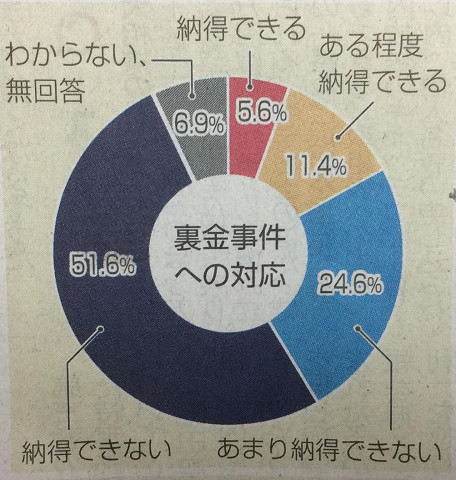
 高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。
高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。
総裁選でこそ威勢の良かった石破新首相は、解散総選挙での裏金議員の公認・非公認では、右往左往し、安倍派幹部ら一部を、小選挙区で公認しない方針や公認する場合も、比例区への重複立候補を認めないとかの判断はしました。
しかし、首相が判断基準とした党の処分自体が、真相究明を置き去りに、形だけのけじめを急いだものであり、真相究明を求める声は止まらないことを忘れてはなりません。
昨日からの、首相の所信表明演説に対する各党の代表質問でも、首相の答弁は総じて、過去の政府の説明をなぞるもので、総裁選で導入に前向きな姿勢だった選択的夫婦別姓については、「国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえ、さらなる検討をする必要がある」というものでした。
金融所得課税の強化についても、総裁選では「実行したい」としていたが、昨日は「貯蓄から投資への流れを推進していくことが重要で、現時点で強化について具体的に検討することは考えていない」と否定的な考えを示しています。
そして、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への移行時期の見直しについても、総裁選では延期を含めた見直しに言及していたが、これまでの政府決定を踏襲し、今年12月で現行の保険証を廃止する意向を示しました。
また、石破内閣の副大臣と大臣政務官計54人の中で旧統一教会との接点がこれまでに確認されているのは24人であり、「新たな接点が判明した場合には速やかに報告、説明し、未来に向かって関係を持たないよう徹底することが大切だ」と述べるに留まっています。
その後退姿勢は、首相だけでなく重要閣僚にも共通しており、何よりも首相は衆院解散前の国会論戦の重要性を再三指摘しておきながら、総裁になるや「最速」での選挙実施を表明し、明日には党首討論を行った後解散することを表明しています。
こんな「変われない」自民党を変えるためには、我々がその権利を行使できる総選挙で、まっとうな政治を取り戻すための一票を投じるしかありません。
| 10月7日「化学物質過敏症の理解から、子どもの学ぶ権利、他者理解の大切さを」 |

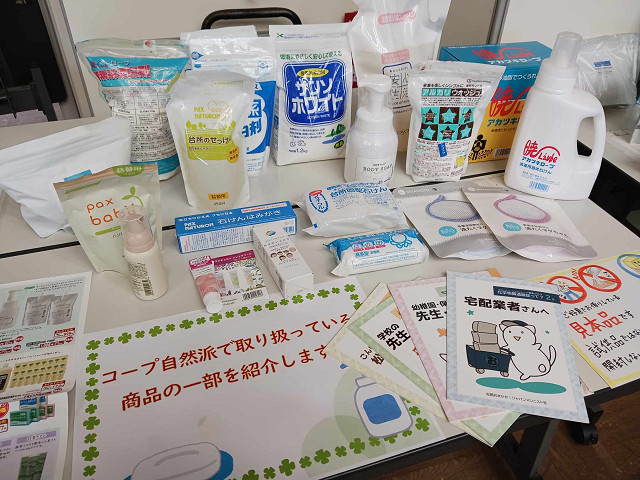

昨日、「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の会の皆さんの主催で「講演会~化学物質過敏症、成人と小児の現状から子ども達の未来を考える~」が開催され、参加してきました。
まだまだ、あまり認知されていない成人と小児の化学物質過敏症(以下 CS)について周知し、CS 患者の現状を通して、子ども達の未来のためにできることを県民の皆さんとともに考えたいとの思いで開催された会場には、当事者家族や教育関係者なとがたくさん参加されて、積極的に学ぼうとされていました。
講師は、県内でCS について詳しく、診療もされている医療法人高幡会大西病院、国立病院機構高知病院小児科小倉英郎先生で、詳細にお話し頂きました。
また、後援して頂いているコープ自然派しこくやNPO 法人土といのちの方による無添加のハンドソープや石鹸、洗濯用洗剤等の商品展示もされていました。
私自身、2017年4月のアースデーで初めて「化学物質過敏症・ゆるゆる仲間」の会の皆さんからお話を伺い、9月定例会で「化学物質過敏症」の方の相談窓口や子どもの学びの場である学校での対策などについて質問したことが、きっかけでこれまでにもいろいろとともに取り組ませて頂きました。
農薬散布や啓発の問題、避難所での対応などもありましたが、やはり一番多かったのが、子どもさんたちの学びの場の確保の問題でした。
昨日も、CSの子どもたちと向き合っている学校の先生方とお話しする機会もありましたし、ミニシンポジウム(体験談から見える、必要な対応と対策とは)では、学校での課題が多く事例報告として出されていました。
子どもたちが、安心して学べる場の保障として、学校施設の改善だけでなく、先生方の協力、同級生やそのご家族などの協力が必要になっていることの意見交換がされていました。
まさに、それは他者のことについて相互に理解しあうことの大切さであり、この社会で生きづらさを感じる方だけでなく、誰もが生きやすくなる地域や社会を築いていくことだと改めて考えさせられました。
 10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。
10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。
質問項目に対する、答弁のみですので、詳細の議事録(仮)は、リンクを貼っておきますので、関心ある方は、こちらからご覧いただけたらと思います。
とくに、「消防広域化」の課題については、翌日にも慎重な検討を求める自民党議員の質問もあり、今後の検討状況を注視していくことが求められています。
1 仮設住宅用地の災害リスクについて
(1)仮設住宅用地の選定における自然災害リスクの想定について
【土木部長】災害後の仮設住宅につきましては、南海トラフで想定される最大クラスの地震や津波被害に対し、7万7,000戸が必要となりますため、既存住宅の借り上げを見込んでおります戸数を除きました6万9,000戸分の用地、すなわち690ヘクタールの確保が必要でございまして、そのうち、現在、公有地で230ヘクタール、これを確保しているというところでございます。で、残る460ヘクタールにつきましては、民有地の活用を考えておりまして、現在、その土地情報の抽出につきまして、市町村と連携して取り組んでいるところでございます。
この民有地の抽出に当たりましては、洪水浸水や土砂災害等のリスクの有無、あるいは、道路への接道状況、こういった情報も含めて、リストアップしているところでございます。
把握した民有地情報につきましては、今後、災害リスク等の情報の精度を高めまして、土地の安全性を確認してまいりたいと考えております。
(2)仮設住宅用地の安全性確保について
【知事】御指摘ございましたように、今回の石川県輪島市及び珠洲市におかれましては、能登半島地震後に建設された仮設住宅が、豪雨により浸水するという被害に見舞われております。
本県に置き換えて考えました場合、南海トラフ地震発災後におきましても、低地では台風などの豪雨により浸水するおそれがございますので、安全性の高い仮設住宅用地の確保は重要な課題であるというふうに考えております。
この用地の確保に関しましては、先ほど土木部長も答弁いたしましたように、残る460ヘクタールの民有地のリストアップが、なお途上にあるということでありまして、そうした中で、安全性の高い用地を候補地として選定できますように、市町村と連携して取り組んでいく考えであります。
一方で、南海トラフ地震の被害想定自身が、ここ向こう一、二年の間の見直しを、今、予定しているところでございまして、これ、予断を許しませんけれども、10年前に比べますと、例えば、堤防などのインフラ整備は一定進んでおるわけでございますので、ある程度、想定される被害の規模は減少の方向になるのではないかと。そうでありますと、この460ヘクタールという数字も軽減の方向になるのではないかというような期待も、持つことは持っているところでございます。
今後につきましては、こうした取り組みを総合的に進めます中で、来年度からの次期南海トラフ地震対策行動計画の期間内には、浸水などに対しましても安全性の高い候補用地が選定できますように、最大限努めてまいるということを、まず取り組んでまいりたいと思っております。
2 災害中間支援組織について
(1)本県における災害中間支援組織の現状について
【子ども・福祉政策部長】災害中間支援組織は、被災者や被災地の多様なニーズに対応するために、県内外の専門性を有するボランティア団体、NPO等と連携して支援をつなぐ組織でございますが、現在のところ、本県では設置までに至っていない状況であります。
このため、本県での体制構築に向けまして、内閣府のモデル事業を活用し、検討を進めているところであります。現段階としましては、先進県や過去の被災県における体制の情報を収集し、内閣府から助言を受けながら、災害中間支援組織のあり方の検討を開始したところでございます。
(2)今後の進め方について
【子ども・福祉政策部長】徳島県では、平時からNPOの活動を支援する団体が中心的な役割を担っておりまして、取り組みが進んだと伺っているところでございます。
本県では、これまで、高知県社会福祉協議会が、NPOに対する相談支援や研修、交流、ネットワークづくりなどの支援に取り組んでいるところです。こうしたことも踏まえまして、県社協とも連携しながら、災害中間支援組織の立ち上げに向けて、一つ一つ課題を整理しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
今後、検討を進めるに当たりましては、内閣府のモデル事業を活用して、有識者の意見を伺う検討会を立ち上げるということも、選択肢の一つとして考えてまいりたいと思います。
3 消防の広域化について
(1)広域化に関する各消防本部との「共通の理解」について
【知事】この消防の広域化に関しましては、昨年11月に、県と全ての消防本部の長の間で構成をいたします消防広域化検討会を設置いたしまして、3回にわたり協議を行ってまいりました。
この現場要員の増強などの広域化のメリットを期待する意見があった一方で、ただいま議員からも、るる、お話ございました、今後、消防の装備や施設の充実を図る場合のスケジュールをどうするのか、あるいは、財政負担はどう分担し合うということにするのか、こういったあり方などにつきましては、今後、より具体的な検討が必要だというような意見もあったところであります。
このように、広域化後の、いわば各論の部分については、さまざまな御意見はありましたけれども、人口減少が進む中で必要な消防力を確保していくという方向のためには、広域化の議論を避けては通れないという大きな方向性に関しましては、全消防本部の長が共通の理解に達したというふうに理解いたしております。
(2)基本構想策定過程における関係者からの意見聴取の必要性について
【知事】まず、この消防広域化の基本構想を県において策定して、それに基づきまして議論を進めていくという手法をとりたいと思っています。
この基本構想におきましては、広域化の趣旨や新たな組織の骨格、さらには、新体制への移行スケジュールにつきまして、県としての試案をお示しするものという形でつくっていきたいと思います。これ、議論のスタートということだと思います。
なお、その構想をつくります際も、まず、この骨子案を年内には公表いたしまして、市町村や消防本部の意見を聞きたいというふうに思っておりますし、担当者会等のさまざまな機会を通じて、消防職員、団員を含みます関係者の御意見もお聞きする、さらには、広く県民の皆さんからも御意見を伺うような進め方を考えているところでございます。
【知事】結論から申しますと、この基本構想の策定過程でも、市町村、消防本部の意見もお聞きし、消防団員、あるいは、消防職員を含む消防関係者の御意見、さらに、広く県民の皆さんからの御意見も募った上で、この基本構想を検討して、お示しするという段取りを考えております。
今までところは、メリット・デメリットという議論はされておりますけれども、それでは、具体的にどんな組織をつくっていくか、そして、どんな活動を目指していくか、スケジュールはどうするか、こういったところの具体論というのが、今、議論のベースがないわけでありますから、それを基本構想として、県の試案としてお示しする。その過程でも、御意見は幅広くお聞きした上で、年度内には、県としての試案としての基本構想を策定し、お示しするということにしたいと思います。これが議論のベース、スタートになるということだと、私は理解しておりますので、来年度に入りましたら、また、新しい有識者なども交えた検討組織を設置いたしまして、その場で、より具体化に向けました議論を、さらに関係者に深めていただくというような段取りで進めていくべきだと考えております。
4 バリアフリー観光と観光・福祉防災の連携について
(1) 県バリアフリー観光相談窓口の機能充実について
ア 防災に関する情報発信について
【観光振興スポーツ部長】災害時に、障害のある方を含め、本県を訪れた全ての方が円滑に避難できるよう、平時から発信していくことが重要です。
このため、県バリアフリー観光サイトにおいても、高知県防災アプリや防災啓発冊子のリンク先を掲載し、平時から周知を図っているところです。また、県バリアフリー観光相談窓口では、コミュニケーション支援アプリを活用し、障害のある方や外国人の方にもスタッフが直接、防災情報などを案内しております。
加えまして、県内の宿泊や観光施設などにおいても、観光客への防災アプリの活用を促していきたいと考えております。
イ 地域の防災ツーリズム主催団体等とのつなぎ役を担うことについて
【観光振興スポーツ部長】例えば、黒潮町では、津波避難タワーの見学や夜間の避難訓練など、命を守る知識を学ぶとともに、地域ならではの観光体験も行える防災ツーリズムを推進しております。
県バリアフリー観光相談窓口がつなぎ役となり、こうした防災ツーリズムに福祉防災の視点をつけ加えていくことは、防災ツーリズムの魅力向上にもつながっていくものだと考えております。また、観光客や主催団体のバリアフリーに関する学びが深まりますとともに、発災時の対応力の強化にもつながっていくものだと考えております。
こうした取り組みを県内外に情報発信することで、防災ツーリズムの誘客の拡大や県全域でのバリアフリー観光を推進していきたいと考えております。
ウ 機能を充実させる上で必要となる施設の拡充に向けた取り組みについて
【観光振興スポーツ部長】防災情報をまとめた新たな特設ページの作成や障害のある方と一緒に避難するといった実践的なバリアフリー防災セミナーなどを開催することで、バリアフリー相談窓口の機能の充実を図ってまいりたいと考えております。
施設面につきましては、現在の相談窓口は、高齢の方や障害のある方の街歩きを支援する高知市の事業と同じフロアを共有しております。
こうしたことから、まずは、両事業のお客様の利用の状況の推移とか、フロアの有効活用などを検証した上で、相談窓口業務を運営いただいている団体や高知市と検討していきたいと考えております。
(2) 帯屋町筋東部への多目的トイレ整備について
【観光振興スポーツ部長】帯屋町筋の東部には、はりまや橋ターミナルがございまして、クルーズ船の外国の方も含め、多くの観光客が訪れております。相談窓口では、障害のある方や車いすを利用される方から、トイレのお問い合わせがあった場合には、現在、中央公園の多目的トイレやはりまや橋地下駐車場のトイレを案内させていただいております。
新たなトイレの整備につきましては、候補となる適地や費用面からも、すぐに整備することは難しく、一定の時間を要すると考えております。
まずは、民間事業者への協力も呼びかけながら、高知市中心商店街のトイレマップを作成し、相談窓口やはりまや橋バスターミナルなどで配布していきたいと考えております。
さらには、お客様の声なども丁寧にお聞きしながら、公共トイレの整備につきましても、地元の高知市にも相談していきたいと考えております。
5 暑熱適応への多様な支援策について
(1) 暑さ指数が31以上となった場合における対応の実態について
ア 体育の授業や運動部活動等、学校現場での対応について
【教育長】各学校では、体育授業や運動部活動を実施する際、まず、活動場所の暑さ指数の計測を行い、暑さ指数が31以上の場合には、適切な水分・塩分の補給や休憩を小まめにとるなどの熱中症対策を行っております。その上で、学校によっては、児童生徒の状況に応じて、運動強度の軽減や活動の時間帯、場所を変更するなどの対応をとっております。
また、本県の中学校及び高等学校の体育連盟が主催するスポーツ大会におきましては、暑さ指数の計測に加えまして、給水タイムの設定など、競技ごとに必要な熱中症対策を講じた上で、大会運営を行っている状況でございます。
イ 学校以外でのスポーツ大会における対応について
【観光振興スポーツ部長】一部の競技で、夏場は大会の開催を避けたり、暑さの状況により中止したケースがございます。多くは、熱中症対策を講じて、開催している状況です。
主な対策としまして、定期的な水分補給や換気、休憩時間の確保のほか、暑さのピークを避けた試合時間の設定などを行っております。また一部の競技団体では、暑さ指数を計測した上で、大会を実施しているといった事例もございます。
(2) 百歳体操などで高齢者が集う場への冷房設置に対する公的支援について
【観光振興スポーツ部長】こうした、いきいき百歳体操などの施設に対する冷房機器の設置については、住宅改造支援事業費補助金という県単独の制度を設けております。この制度は、地域住民の生きがい活動や防災活動の拠点となっている施設の改修や改築への支援を行うものでございまして、空調設備での活用は、過去5年間で4市町、9件となってございます。
(3) 暑熱適応の街づくりについて
【知事】熱中症対策につきましては、御指摘ございましたように、国において法律改正も行われまして、熱中症対策実行計画も策定されております。地球温暖化が進行する中で、熱中症の発生リスクを抑制しながら、社会経済活動の継続、街のにぎわい創出などを図るためには、街中の公共の場などにおける暑さ対策は不可避だと考えております。
国の計画も踏まえまして、まちづくりに関するさまざまな分野で、暑さへの対応を念頭においた施策を講じていく必要があるというふうに考えております。
 自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。
自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。
そして、新内閣の布陣などから、アベ政治からの転換かと思われたが、昨日の所信表明を聞く限り、肝心なところは、そうでないことも明らかになったと思います。
総裁選の出馬会見で「リクルート事件のとき以上に国民の怒り、不信が高まっている。自民党は変わる。それを実現できるのは自分だ」と語り、同じ日には「全閣僚出席型の予算委員会というものを一通りやり、この政権は何を考えているのか、何を目指そうとしているのかということが、国民に示せた段階で可能な限り早く信は問いたい」と言われた方が、首相になったのですから、多くの国民は、当然そうなるだろうと思っていたにちがいありません。
蓋をあければ、裏金事件をめぐっては、新事実が判明していない現段階での再調査を否定し、「必要があればそういうことも行いますが、現在そういう状況にあるというふうには承知をしていない」と言い、旧統一教会と自民党との関係について、演説では素通りで、予算委員会もなしに、早々と解散総選挙の日程だけは決めてしまいました。
沖縄の戦中戦後の苦難の歴史に言及しながらも、米軍普天間飛行場の辺野古移設は推進、期待を持たせた日米地位協定の改定に触れることもありませんでした。
石破内閣は基本方針として、「ルールを守る」「日本を守る」「国民を守る」「地方を守る」「若者、女性の機会を守る」という「五つの守る」を掲げていたが、「言ったことを守る」ことのない限り、国民の納得と共感は得られるはずはありません。



昨日の一問一答形式の質問が終わり、今朝の新聞には「仮設住宅候補地選定 災害考慮しているか」との見出しで一問が取り上げられていましたが、他の質問も含めて、テープ起こし中です。
テープ起こしができ次第、アップしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。
―高知新聞引用―
【質問】能登半島地震の被災地では先月の豪雨で仮設住宅が浸水した。南海トラフ地震に向け、今回の事例を教訓にしたい。県内では災害リスクを考慮した選定をしているか。
【横地和彦土木部長】最大クラスの地震(L2)では7万7千戸が必要になる。確保できていない4万6千戸分の用地は洪水浸水や土砂災害のリスク、道路の状況などの情報も含めてリストアップしている。把握した情報の精度を高め、土地の安全性を確認していく。
【浜田知事】能登の事例を高知に置き換えると、低地では台風などの豪雨で浸水する恐れがあり、用地の確保は重要な課題だ。市町村と連携して、安全性の高い候補地を選定できるように取り組む。
 県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。
県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。
私は、明日2日(水)午後1時からの登壇となります。
下記の質問項目を予定していますが、持ち時間は答弁を含めて35分間ですので、掘り下げた質疑ができそうにありません。
しかし、どれも重要な課題ですので、頑張りたいと思います。
おかまいない方は、議場またはネット中継での傍聴を、よろしくお願いします。
1 仮設住宅用地の災害リスクについて
(1) 仮設住宅用地の選定における自然災害リスクの配慮について(土木部長)
(2) 仮設住宅用地の安全性確保について(知 事)
2 災害中間支援組織について(子ども・福祉政策部長)
(1) 本県における災害中間支援組織の現状について
(2) 今後の進め方について
3 消防の広域化について(知 事)
(1) 広域化に関する各消防本部との「共通の理解」について
(2) 基本構想策定過程における関係者からの意見聴取の必要性について
4 バリアフリー観光と観光・福祉防災の連携について(観光振興スポーツ部長)
(1) 県バリアフリー観光相談窓口の機能充実について
ア 防災に関する情報発信について
イ 地域の防災ツーリズム主催団体等とのつなぎ役を担うことについて
ウ 機能を充実させる上で必要となる施設の拡充に向けた取り組みについて
(2) 帯屋町筋東部への多目的トイレ整備について
5 暑熱適応への多様な支援策について
(1) 暑さ指数が31以上となった場合における対応の実態について
ア 体育の授業や運動部活動等、学校現場での対応について(教育長)
イ 学校以外でのスポーツ大会における対応について(観光振興スポーツ部長)
(2) 百歳体操などで高齢者が集う場への冷房設置に対する公的支援について(子ども・福祉政策部長)
(3) 暑熱適応の街づくりについて(知 事)
| 9月29日「袴田さん無罪判決、次は、再審への法改正を」 |
 9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。
9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。
無実の訴えから半世紀余、早く真に自由の身とするためにも、検察は控訴してはなりません。
最高裁は1975年、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則が再審制度にも適用されるという決定を出しており、この原則に立てば、もっと早く袴田さんに無罪が届けられたはずです。
死刑確定の翌年に第1次の再審請求がされたが、再審が確定するまで実に42年もかかりました。
事件から、58年もたって、やっと「無罪」の声を聞いたが、袴田さんの姿を見た時、刑事司法関係者は深刻な人権問題だと受け止めるべきではないでしょうか。
これを契機に、「開かずの扉」と評される再審制度も根本的に問い直されなければなりません。
袴田さんの無罪はゴールではなく、刑事訴訟法の再審規定(再審法)を改正するためのスタートとも言えます。
いったん再審が決まれば、検察官の不服申し立ては禁止する法規定が必要だし、今回の無罪判決についても、検察は控訴せずに無罪を確定させるべきです。
さらに、無罪に結びつく、すべての証拠を検察側に開示させる法規定を設けるなど再審法の改正は喫緊の課題です。
現在、超党派の国会議員による「再審法改正を早期に実現する議員連盟」ができているが、私たち県議会でも、今定例会において「刑事訴訟法の再審規定」の改正を求める意見書を提出予定です。
いよいよ、次は狭山事件の再審の扉を開けるときです。
| 9月28日「自民党新総裁は、まずは国会で説明責任を果たせ」 |
 昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。
昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。
国会議員の支持はほぼ二分されたことからも、石破氏が党をまとめつつ、過去の膿を出し切り、国民の信を取り戻すという道のりは、けして容易ではないでしょう。
総裁選では、最初威勢の良かった各候補のトーンも、投票日が近づくにしたがってトーンダウンし、裏金問題で処分された議員への責任追及や旧統一教会との組織的関係の真相究明も新総裁には期待できないと思う国民が多くいるのではないでしょうか。
石破新総裁が、裏金議員や、教団との接点があった議員に対して、厳しい対応が取れないのなら、国民が断罪するしかありません。
安倍政権以降続く、国会での説明軽視の自民党政権の姿勢が変わったのかを見極めるためにも、所信表明演説に対する代表質問だけではなく、最低限、一問一答形式の予算委員会や党首討論を行い、与野党の対立軸を示した後で、国民に判断を求めて頂きたい。




高知県の精神障害者に対する医療費助成は、精神疾患を原因とする通院のみで、他の疾患や入院は自己負担で、当事者や家族の不安の解消の求めに応えて、まずは6月定例会で県民の会の同僚議員の岡田議員がその対象拡大を求める質問をしてきました。
そして、県内の精神障害者の親でつくる「高知はっさくの会」(東岡美佳会長)の皆さんとともに、今年6~8月に署名活動を行い、県に対しては約1万3千筆の署名を子ども福祉政策部長に提出し、助成創設を求めてきました。
その際に、6月定例会でも岡田議員の質問に答えて「県内の精神障害のある方の実態や、市町村の意向、また、既に補助金の対象に含めている他県の状況などの情報収集・把握を行っていく」との姿勢を示していましたが、現時点での取り組み状況についても聞かせて頂きました。
そのうえで、「皆さんからの訴えを聞く中で、改めてご苦労なさっていることが分かった。先行事例としての他県の深堀把握や市町村の意向確認も進めながら合意形成も図っていきたい。」と述べられ、最後には「知事とも話して判断したい」と踏み込んだ考えも示されていましたが、昨日の自民党議員の質問に、知事が「対象とする障害の程度や財政負担の規模などを、1年程度かけて検討を深める」と答弁しました。
知事の背中を後押しした1万3086人の県民の皆さんに感謝したいと思います。
「親が亡くなったらどうなるか不安でいっぱい。経済的にも親の年齢的にも余裕はない。できるだけ多くの当事者が助成対象としてほしい」との当事者や家族の皆さんの思いに答えるためにも、一年と言わず一日も早く実現させてほしいものです。
 本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。
本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。
今回の私の登壇機会は、10月2日からの一問一答による質問になります。
10月2日の13時から答弁時間も含めて35分間ですので、多くの質問はできないかと思いますが、現在作成中です。
決まれば、質問項目などを、皆さんにお知らせしたいと思いますので、議場やWeb上での傍聴をよろしくお願いします。



昨年5月の震度6強の珠洲市を中心とした地震、元旦の震度7の能登半島地震、そし今回の豪雨被害と、なぜこれだけ試練を与えるのだと心が折れかかっている方がたくさんおられます。
8月、9月に入ってようやく避難所から仮設住宅に入居した方も多く、まさに「これから、少しずつ」復興に向けて一歩を踏み出していこうとする矢先の今回の豪雨被害です。
奥能登を襲った記録的豪雨によって、23日時点で、死者は7人、安否の分からない人は行方不明者を含めて計6人、輪島、珠洲、能登3市町の5千戸で断水しています。
能登では元日の地震で広範囲が長期間断水し、やっと解消したばかりだったというのに、また断水です。
集落の孤立は前日から半減したものの依然3市町の56カ所で続いており、県などが復旧を急いでいるといいます。
「心は折れても生きるしかない」との思いの方々に、頑張れではなくて、「支援し続けているよ」との思いと行動を届けていくしかありません。
高知でも南海トラフ地震の後に、集中豪雨や台風襲撃など複合災害のリスクは今まで以上に高まっています。
能登の皆さんの気持ちを自分事として捉えていきましょう。



今朝の高知新聞でも記事になっていた昨日の平和運動センター記念講演「ぼくが遺骨を掘る人(ガマフヤー)になったわけ」は、大変貴重なお話ばかりでした。
沖縄のガマ(自然の洞窟)などで遺骨収集を続けるガマフヤー(ガマを掘る人)の具志堅隆松さんは、09年に那覇市中心部に近い真嘉比地区での遺骨等の収集品を示しながら、静かな口調で話されていましたが、その遺品や遺骨が何を私たちに教えているかとなると力も入られました。
政府・首相は「戦没者の御霊に哀悼の意を捧げる」と言いながら、やっていることは、戦没者の遺骨を海に投げ捨て、戦没者にさせられた敵国の基地づくりに利用することなのかと怒りが湧くいうことを我が事にする必要があります。
「戦時中は、戦死した家族が人前で泣くことすらできなかったし、モノが言えなかった。今、我々はまだモノが言える。」「日本に戦争をさせないことが、全国でやらなければならないこと。何で日本がアメリカのために中国と戦争しなければならないのか。」と、 主権者として、声をあげなければならないとの訴えに、会場からも「そうだ!」の声があがっていました。
また、お話の中で、長崎県の小学生の体験学習として、遺骨収集の現場で体験してもらったことを紹介し、遺骨を目の当たりにして事実を確認した証言者になれるということも、非常に大事な平和学習の一環だと考えさせられました。
掘り出した遺骨を遺族のもとに戻す、遺族が無理でも縁故者のもとにとの思いで、DNA鑑定を求め続けながら掘り続ける具志堅さんの姿を描いた映画「骨を掘る男」上映会が、県下で開催されます。
当面の予定は、9月29日(日)高知市自由民権記念館13時30分、16時、18時30分、 10月6日(日)南国市後免町防災コミュニティセンター14時、17時です。
ぜひ、ご来場ください。

 復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。
復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。
大雨特別警報が発令された輪島、珠洲両市の雨量は観測史上最大を記録し、各地で道路が土砂崩れで寸断され、県災害対策本部会議によると、床上、床下の浸水は多数で、珠洲市4地区、能登町2地区が孤立したり、停電、断水の地区もあるそうです。
多くの皆さんが、奥能登の皆さんに、何故こんなにも試練を与えるのかとの思いを強くしています。
さらにつらいのは、仮設住宅が浸水し、仮設住宅から避難しなければならない避難者の皆さんがおられるということです。
石川県によると、今回の大雨で輪島市と珠洲市の8カ所の仮設住宅が浸水したそうです。
朝日新聞の調べでは、少なくとも輪島市の4カ所のうち3カ所(宅田町の仮設を含む)はハザードマップで洪水による浸水リスクがあると示された場所であり、県や輪島市は、洪水や土砂災害、津波といったハザードリスクを「織り込み済み」として、海沿いや川沿いなどに建設していました。
「リスクを承知の上」とする代わりに、県は、災害の危険があった際は「警戒、避難態勢をしっかりする」としてきたが、そのような対応がされたのか、今後の検証が必要です。
いずれにしても、災害の仮設住宅は、被災地のなかでも残された少ない平地に建てらるため、そこがこれまで人が住んでいなかった、河川氾濫リスクや、土砂災害リスクのある地域に建てられるという問題があり、今回の能登半島でも同じ現象が発生したと言われています。
それでなくても、本県において仮設住宅用地が確保されていない中で、限られた用地や候補地が総合的な自然災害リスクを想定した場所の選定がされているのか、仮設住宅用地の安全性の調査と分析が求められるのではと考えさせられました。
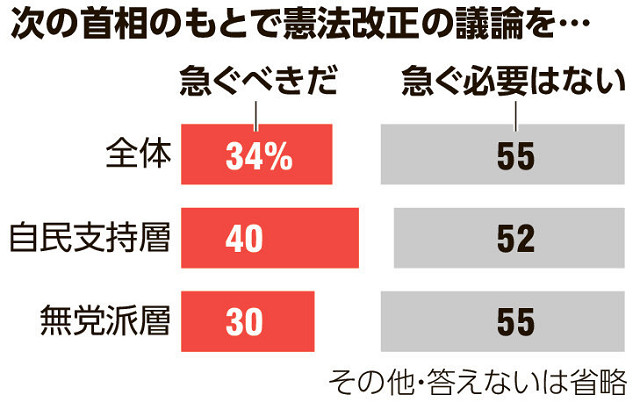 自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。
自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。
9候補の間では、改憲に取り組むスピード感として、賛否を問う国民投票に向け「首相在任中の発議を実現する」と訴えたり、「3年以内に改憲を実現」と打ち出したりする候補がいる一方で、そうした「期限」はあいまいなまま「できるだけ早く」といった言い方の候補もいます。
しかし、この改憲議論をめぐるスピード感を世論はどう見ているのか、9月14、15日に朝日新聞が実施した全国世論調査では、次の首相のもとで、「憲法改正の議論を急ぐべきだと思いますか。急ぐ必要はないと思いますか」という問いに対して、「急ぐべきだ」の34%に対して、「急ぐ必要はない」の方が55%と多い結果となっています。
自民支持層でも、「急ぐ必要はない」が52%と過半数で、「急ぐべきだ」という回答40%を上回っています。
自民党では、改憲をめぐって、退陣を表明した岸田文雄首相が遺言を残すかのように、党内に「論点整理」を急がせていますが、国民の思いとは乖離があることを認識しておかなければなりません。
 県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。
県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。
浜田知事は、提案説明で、「県政運営の基本姿勢」「人口減少対策」「いきいきと仕事ができる高知」「地産外商の取り組み」「イノベーションの取り組み」「いきいきと生活ができる高知」「日本一の健康長寿県づくり」「教育の充実」「安全・安心な高知」などについての考え方を示されました。
能登半島地震や8月の南海トラフ地震臨時情報発表に触れ、これらの教訓を踏まえ、備えを再点検し、強化することの必要性に加えて、県内15の消防本部を一つに統合し、広域化を進める方針に言及しました。
その内容は、以下の通りでした。
「今後、人口減少が進行する中にあっても、高齢化に伴う救急需要の増大や、大規模災害などへの対応に必要となる消防力を将来にわたって確保していかなければなりません。そのためには、現在15の消防本部に分立している常備消防組織を一本化することで、人事管理や通信指令業務などの間接部門をスリム化し、そこから生じた余力を現場要員の配置に振り向けることが最も有効な手法だと考えます。本県では、このような考え方に立ち、昨年度から各消防本部との間で消防の広域化に関する協議を進めており、概ね共通の理解に達しています。今後は、県において、広域化を担う新たな組織の設置に向けた基本構想を年度内に策定した上で、市町村や消防本部を交えてさらに具体的な協議を進めます。」
しかし、現在15の消防本部に分立している常備消防組織を一本化することについて、「概ね共通の理解に達している」と本当に言えるのか、私自身は疑問を抱いています。
9月26、27日、10月1日に一般質問、2、3日に一問一答形式の一般質問が行われますが、私は2日に、一問一答式による質問を行うこととなっていますが、持ち時間が答弁も含めて35分間となっていますので、多くの質問ができないかとは思いますが、近づきましたら、その内容などについてお知らせしていきますので、傍聴して頂ければ幸いです。
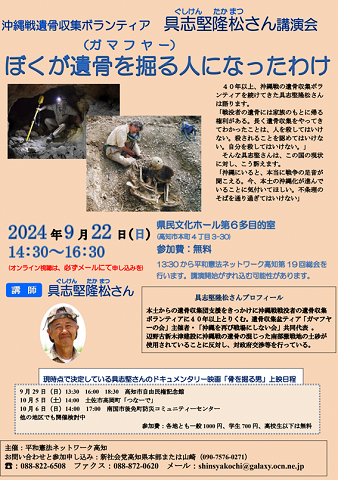
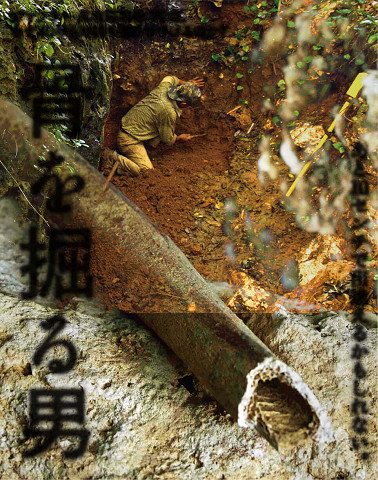 今日から、県議会9月定例会が開会します。
今日から、県議会9月定例会が開会します。
10月3日に質問予定の私にとって、その前段で欠かせないいくつかの取り組みがあって、バタバタしています。
特に、皆さんにもぜひ聞いていただきたいお話と、ご覧になって頂きたい映画があります。
まず、40年以上、沖縄戦の遺骨収集ボランティアを続けてきた具志堅隆松さんのお話です。
「戦没者の遺骨には家族のもとに帰る権利がある。長く遺骨収集をやってきてわかったことは、人を殺してはいけない。殺されることを認めてはいけない。自分を殺してはいけない。」という具志堅さんは、この国の現状に対し、さらに次のように訴えます。
「沖縄にいると、本当に戦争の足音が聞こえる。今、本土の沖縄化が進んでいることに気付いてほしい。不条理のそばを通り過ぎてはいけない。」と。
そんな訴えに9月22日(日)14時30分~県民文化ホール4階多目的室で耳を傾けて欲しいと思います。
そして、その具志堅さんの姿を描いたドキュメンタリー映画「骨を掘る男」の上映会を自由民権記念館で開催します。
上映時間は、13:30~(開場:13:00)、16:00~(開場:15:30)、18:30~(開場:18:00)となっていますので、ぜひご覧ください。
講演会は無料ですが、映画は参加費1000円です。
問合せは、平和運動センターまで(TEL. 088-875-7274/E-mail. heiwa-st@ninus.ocn.ne.jp)
| 9月18日「自民党の旧統一教会との新たな組織的関係発覚」 |
 自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。
自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。
そんな最中、昨日朝日新聞は、旧統一教会との「組織的な関係」を否定してきた自民党の説明に疑義を突き付ける、新たな疑惑を明らかにするような写真と記事を報じました。
自民党が政権復帰した翌13年の参院選の公示直前に、当時の安倍首相が教団トップの会長らと、自民党本部の総裁応接室で面談していたことを写真とともに報じたもので、教団側による自民党の比例区候補の選挙支援を確認する場だったとされています。
岸田首相が「退陣」を表明した記者会見で、「旧統一教会をめぐる問題や派閥の政治資金パーティーをめぐる政治とカネの問題など、国民の政治不信を招く事態が相次いで生じた。」と述べたが、裏金と並んで国民の政治不信を招いた原因に挙げた「旧統一教会」問題も、実態解明は不十分なままでした。
今回の新たな疑惑の解明こそは、新総裁の責務であり、そのことに向き合うことなしに、自民党政権への信頼回復はありえません。
昨日の那覇市で演説会に臨んだ総裁選候補の中で、教団問題に触れた者は一人もいなかったというが、安倍氏が首相の立場にあった2013年の参院選直前に旧統一教会の会長らと総裁応接室で面談していた事実が明らかになった以上、次の総裁候補者は、この問題とどう向き合うのかを示さない限り、さらに国民の信頼を失うことになるのではないでしょうか。
| 9月16日「敬老の日に考える『支え・支えられる』側」 |
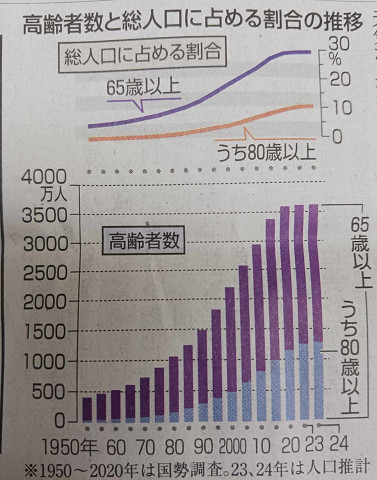
 今日は、「敬老の日」です。
今日は、「敬老の日」です。
総務省が推計した65歳以上の高齢者は3625万人で、総人口に占める割合は29.3%にのぼり、人口10万以上の国・地域としては世界最高とのことです。
年齢を重ねても働き続ける人は増え、今や65~69歳では半数を超え、就業者の7人に1人は65歳以上だとされています。
人手不足が顕在化する中で、高齢者の活躍無しに社会を維持できない状況となっています。
今のご時世、一定の年齢以上なら一律に「支えられる側」とはなりませんが、誰でもいつか必ず「支えられる側」になるし、その時のセーフティーネット、つまり「支える力」や「支えるしくみ」を強くすることは、避けて通れなくなっています。
しかも、高齢になっても、それまでと同じような働きや活躍を求めるのは無理で、その人にあった多様な働き方や役割の選択肢があるような社会が求められることになると思います。
また、高知県では、2021年度の県民世論調査で、4割が「医療や介護が必要になっても自宅で生活したい」と希望されている中で、高齢者が住み慣れた地域で暮らしながら医療や介護などのサービスを一体的に受けられる仕組みは、けして十分とはいえません。
加えて、高知新聞で連載されていた「ヘルパー消滅、高知の介護危機」にあるような実態が、今後も続けば「介護難民」が生じて、「支える側」の脆弱性が浮き彫りとなることが懸念されます。
そのような中で、「医療や介護が必要になっても自宅で生活したい」方が、多ければ多いほど、やがて来る南海トラフ地震で誰一人取り残さない地域の「支える」仕組みも強化しておかなければならないことも考えさせられます。
昨日は、奇数月の第3日曜日ということで、小倉町町内会とアルファスティツ知寄Ⅱ防災会共催の恒例の「おしゃべりカフェ」が開催されました。
お湯を入れて出来上がりを待つ間に、地域包括支援センターの職員さんから、地域ぐるみの支えあいについてお話を頂いた後に、ドライカレーや五目御飯やひじきご飯の防災非常食をおいしくランチとして頂きました。
平時からの、語らいの場としての「おしゃべりカフェ」で顔見知りの関係や地域の支えあいの関係を築き、いざという時には津波避難ビルに避難したり迎え入れたりできる関係が築かれることも、「支える」地域力づくりにもつながっていると考えさせられた敬老の日の前日でした。
| 9月15日「国民の信頼回復を図る本気度が見えない自民党総裁選」 |
 岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。
岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。
しかし、総裁選だからのリップサービスかのように、今まではどれだけ求められてもやらなかったことを「私がなったら」と言わんばかりに口にしている総裁選で、国民の信頼が回復できるのだろうか。
裏金問題への対応では、党が幹部らに渡す政策活動費の廃止や、政治資金収支報告書への不記載相当額の国庫への返納などを主張する候補者がいる一方、中途半端に終わった実態解明には、全員が後ろ向きです。
企業・団体献金や政治資金パーティーは現状のまま放置するのか、「カネをかけない政治」を実現するには何が必要か本気度は伺えません。
派閥の裏金事件を受けて「政治とカネ」の問題などについて、新首相が野党との国会論戦を通じて有権者に説明する機会が、衆院選前にあるかどうかが焦点になっている中で、それをやろうとしたら党内での混乱が生じかねないし、国民の信頼も回復できない。
そんな議論もしないまま、直ちに解散するという「時期」も争点化しています。
自民党の都合による解散総選挙で振り回される国民不在の政治にさらに不信感は高まってい行くことになると思わざるをえません。
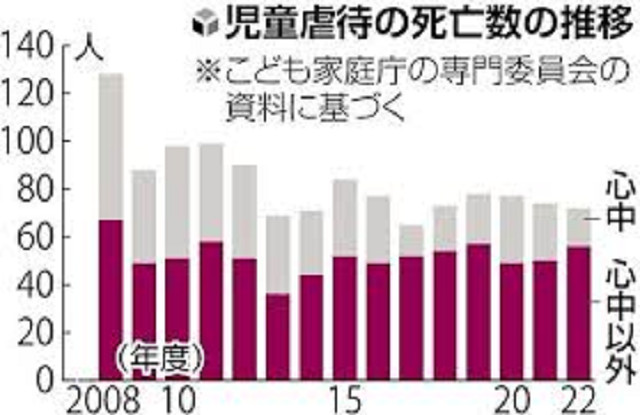
 こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。
こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。
前年度から2人減ったものの、近年は横ばいが続いており、同庁の担当者は「本来はゼロであるべき虐待死が72人いることは非常に大きい課題だ」と話されています。
無理心中16人を除いた虐待死は、56人で死亡時の年齢別でみると、0歳の25人(44.6%)が最も多く、2歳が9人(16.1%)、1歳が5人(8.9%)で続いており、3歳未満だけで全体の約7割を占めています。
死因となった虐待の類型別では、多かったのはネグレクト(育児放棄)24人(42.9%)、身体的虐待17人(30.4%)で、主たる加害者は実母23人、実母と実父7人、実父6人だったとのことです。
専門委員会は11~21年度の虐待死事例について、児童相談所などの対応過程を分析し、短期間で転居を繰り返す世帯は、自治体間で十分な引き継ぎが行われず、状況が悪化するケースがあったとして、早期に情報共有する必要性を訴えられています。
また、国は虐待を防ぐため、望まぬ妊娠や貧困など産前からサポートが必要とされる「特定妊婦」の支援に取り組むが、出生日に亡くなる子どもの数は、年度によって増減はあるものの著しい減少には至っておらず、養育者の心理的・精神的問題(複数回答)としては「養育能力の低さ」(15人)、「育児不安」(11人)が挙げられています。
朝日新聞によれば、「人吉こころのホスピタル」(熊本県人吉市)の興野康也医師は、孤立出産の末に、実子を殺害したり遺棄したりしたとして罪に問われた女性たちの精神鑑定や支援をしてくる中で、女性たちは日常生活や社会生活への適応能力が平均よりやや低い「境界知能」の状態にあるなど精神面での課題があったり、家族や行政などにつながれず孤立したりしていたことを指摘されています。
助けを求めることもできず、また助けを求めたとしてもその声が届くべきところに届かなかったりして、孤立を深める母親たちが多く想定されます。
あらためて、孤立を深めがちな妊産婦さんへの産前から産後、自立までを一貫して支えるきめ細かな取り組みが求められています。
| 9月11日「原発事故避難計画を見直さない30キロ圏自治体」 |
 今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。
今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。
原発事故に備えた避難ルートの寸断が相次いだ元日の能登半島地震を見るにつけ、避難計画の見直しを真剣に考えているかと思いきや、各自治体の避難計画の見直しについて「必要」「どちらかと言えば必要」と回答したのは、3割に留まっていると感じました。
能登半島地震は原発廃止への最後の警告だとも言われる中、地震や津波などの自然災害と原発事故が同時に起きる「複合災害」への危機感がもっと高まっているかと思っていたのですが、30キロ圏自治体は、そうでもないように考えさせられました。
原発の30キロ圏の自治体は、原子力規制委員会の「原子力災害対策指針」などに基づき、住民の避難や屋内退避の計画を定め、必要があれば修正することが法律で義務づけられている中、避難計画の基礎となる指針の見直しに規制委が消極的な一方で、一定数の首長が計画見直しの必要性に踏み込んだが、要否を明確にしない「その他」も5割余りに上っています。
避難計画見直しの必要性を認めたのは41自治体(28%)で、政府が再稼働に注力する柏崎刈羽原発(新潟県)、南海トラフ巨大地震の想定震源域にある浜岡原発(静岡県)では、それぞれ5割の自治体が必要性を認めています。
一方、いずれも今年中の再稼働が見込まれる東北電力女川原発(宮城県)は1割余り、中国電力島根原発(島根県)はゼロだったとのことですが、女川原発のある女川町は、「その他」で(能登半島地震を受けての原子力防災上の検証・検討は国及び関係機関にて行われ、見直しが必要な場合はこの結果を踏まえて各級計画に反映されていくこととなる。本町の地域防災計画(原子力災害対策編)は国・県の防災計画とリンクするもので、見直す場合は国・県の計画とともに行うべきものであるため、現時点で単独での計画見直しは行っていない。なお、立地自治体として考える見直し等に係る観点は当然にあり、必要性について考えていない、ということでないことを付言する。)と答え、宮城県も「その他」で、(避難計画は各市町で作成しているため)と答えています。
このような、県と当該自治体の姿勢に、改めて危機感を感じるとともに、福島原発事故や能登半島地震の警告・教訓は、生かされないのかと情けなくさえ感じます。
| 9月10日「現行保険証の廃止扱い自民党総裁選で異議」 |
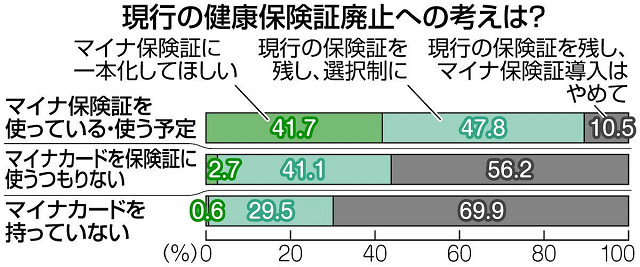 マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。
マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。
以降、現行保険証が新規発行されなくなるが、その後も最長1年間は現行の保険証を利用でき、マイナ保険証を持たない人には当面、代わりに「資格確認書」が交付されることになっています。
マイナ保険証の利用率は7月時点で11.13%と、相変わらずの低調で、現行保険証の存続を求める声が高まっているのに、廃止が強行されようとしています。
そんな中で、自民党総裁選で林芳正官房長官が「まだまだ国民の間にいろんな不安がある。不安を解消するために、見直しを含めて適切に対応していきたい。」と現行保険証の廃止時期を巡って言及し、閣内不一致を露呈することとなりました。
さらに、石破氏も賛同し、舌戦が激化しつつあると言います。
医療の現場では、受付で保険証を渡して診察を待つだけだったものが、マイナ保険証では、カードリーダーで認識させる際に手間がかかり、しかも受診・受付をする場合、初診も再診も関係なく、毎回本人確認が必要となるなど、患者さんに負担をかけています。
また、あるシンポジウムで全国保険医団体連合会副会長の橋本政宏医師は、カードリーダーの読み取りで、トラブルが起きたために、その日の受付をあきらめて帰宅し、急性心筋梗塞のため死亡した事例も紹介されています。
まさに、こういった命に関わる最悪の事態が今後も予想されます。
東京新聞などの地方紙18紙の合同アンケートでは、マイナ保険証を使わない人や、マイナカード自体を持っていない人は、マイナ保険証の導入中止を求める人が多く、マイナ保険証を使う人は、導入中止を望む割合は少なかったとのことです。
ただ、現行の紙の保険証の廃止には否定的な人が多く、47.8%はマイナ保険証と現行の保険証の選択制を望んでいます。
いずれにしても、閣内不一致で推し進めていく現行保険証の廃止は、絶対とどまるべきです。
| 9月9日「誰もが"This Is Me"と言えるように」 |

 昨日の午後は、丸亀市の就労継続支援B型事業所たんぽぽに通う方々の人生について話を聞き、その実体験をもとに苦労や生きづらさをテーマに創作された作品の演劇公演を鑑賞してきました。
昨日の午後は、丸亀市の就労継続支援B型事業所たんぽぽに通う方々の人生について話を聞き、その実体験をもとに苦労や生きづらさをテーマに創作された作品の演劇公演を鑑賞してきました。
香川で好評を博した作品「ダンデライオンズ」が、ミニシアター蛸蔵にて再演されるもので、上演作品は四国学院大学学生と就労継続支援B型事業所のみなさんがつくりあげたストーリーで、出演したのは学生と、障害があり就労支援施設を利用している方たちもおられました。
三人の主人公のそれぞれのこれまでの人生・生き方そして病んでいく過程の背景が、誰にも共通することで、出演者の一人がアフタートークで仰っていた「事業所たんぽぽの利用当事者と話す中で、皆一緒だから大丈夫と言われ、病気になるのは特別ということではない」ということが、この演劇を共同作業として完成させたベースではないかと思いました。
エンディンクで出演者全員の思いがこもった"This Is Me"の圧倒的な迫力素晴らしかったです。
今の4回生も出演した上演は最後かもしれませんが、できる限り各地で公演会が開催されたらと感じたところです。
(舞台の写真撮影は禁じられていましたので、ポスターとパンフレットの写真にさせて頂きました。)

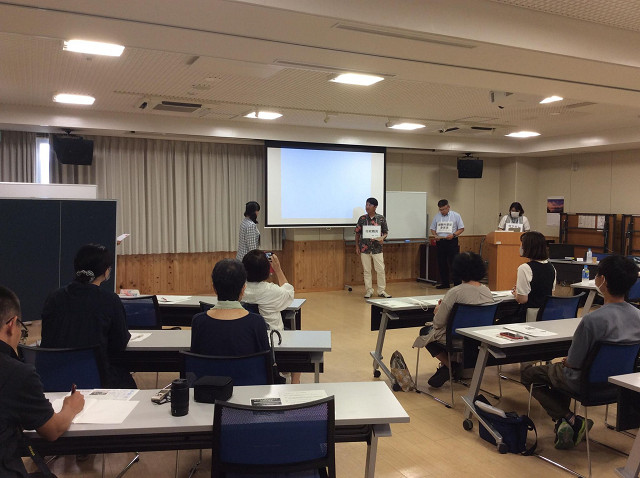


これまで告知してきた下知地区減災連絡会の女性部会発足に向けたキックオフ講演会が、昨日無事開催されました。
講師の西村浩代さんからは「生活者の視点を活かす避難所運営」ということで、 男女共同参画の視点を防災に生かすためのお話を頂きました。
避難所にはいろんな方が、来られる中で、避難所で必要な「もの」や「こと」が、避難者毎によって違うということを理解して対応することの必要性。
過去の事例から、避難所で困ったことについて、具体的な事例をあげて、どう捉えて対応するのかなどを考えさせられました。
多様な困りごとを想像して、多様性に配慮し避難所運営について考えるためにも、多様な生活者の視点で運営にあたることの大切さについて強調して頂きました。
下知地区減災連絡会も12年前の発足当初から、男性中心の運営になりがちな防災組織で、女性枠役員を選任して、女性の視点を大事にするなど工夫をしてきましたが、年度内に女性部会を発足させることで、さらに男女共同参画の避難所運営や防災活動の実践につながればと思います。
今朝の高知新聞でも、記事で具体的に取り上げて頂いていますので、参考にして頂きたいと思います。
| 9月6日「精神に障がいのある方への医療費助成の実現を」 |



昨日は、精神に障害がある人の家族でつくる団体「高知はっさくの会」の皆さんとともに、「精神障がい者保健福祉手帳所持者に対する精神科医療費及び一般医療費への助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)の創設」を求められた「精神障がい者に対する医療費助成制度の創設を求める署名」1万3086筆を県西森子ども・福祉政策部長に手交しました。
会の皆さんのご尽力で、集められた署名に対して部長も「この署名の重みをしっかりと受け止める」と仰っていました。
県内では、今年3月末現在で7659人が精神障がい者保健福祉手帳を持っていて、年々増加傾向にありますが、県内の医療制度については精神障がいのある人への医療費の助成は一部あるものの、長期的な治療で費用ががかさむだけでなく仕事が限られるため収入が減少し生活が困窮してしまうことが課題となっています。
特徴的には、精神障がいをもつ当事者たちは、発症して10~30年も精神科に通い、多量の薬を服用し、また、その障がいゆえに社会参加の機会に十分恵まれないことや生活習慣病など精神疾患以外の病気も発症する人が増加傾向にあり、家計の負担がそれだけ大きくなっています。
収入の柱である障害基礎年金 (ほとんどの場合2級月68,000円 )では、日々の生活維持すらままならず、就労も困難な状況にある当事者が多く、ともすれば病院にかかることさえ控えられている方も少なくないそうです。
当事者とその家族にとって、精神科 (通院・入院)に加えて、精神科以外の一般医療費 (通院・入院)の負担が重なり、それらの医療費の家計負担が重くのしかかっている中で、医療費に対する助成制度の創設は、精神障がいを持つ当事者とその家族にとって最も切実な願いであるのです。
昨日も、参加したメンバーから当事者自身の生きづらさや家族としての悩みなどが個別具体的に部長に訴えられていました。
精神科医療 (通院・入院)費および精神科以外の一般医療 (通院・入院)費に対する助成制度(重度心身障害者医療費助成制度)が一切実施されていない都道府県は、現在高知県を含む6県に留まっています。
県は、6月定例会でも県民の会の岡田議員の質問に答えて、「県内の精神障害のある方の実態や、市町村の意向、また、既に補助金の対象に含めている他県の状況などの情報収集・把握を行っていく」との姿勢を示していましたが、現時点での取り組み状況についても聞かせて頂きました。
部長も、「皆さんからの訴えを聞く中で、改めてご苦労なさっていることが分かった。先行事例としての他県の深堀把握や市町村の意向確認も進めながら合意形成も図っていきたい。」と述べられ、最後には「知事とも話して判断したい」と踏み込んだ考えも示されました。
当事者や家族にとって、経済的にも年齢的にも余裕がないことから、一刻も早い判断を求めて、今後も県の取り組みを注視していきたいと思います。

 9月1日夜のNHKスペシャル「巨大地震“軟弱地盤”新たな脅威」で、活断層の地震として過去最大規模だった能登半島地震における木造や鉄筋コンクリート造の建物が数多く倒壊したことの背景として、科学者は“軟弱地盤”によって揺れが何倍にも増幅された可能性を指摘されていました。
9月1日夜のNHKスペシャル「巨大地震“軟弱地盤”新たな脅威」で、活断層の地震として過去最大規模だった能登半島地震における木造や鉄筋コンクリート造の建物が数多く倒壊したことの背景として、科学者は“軟弱地盤”によって揺れが何倍にも増幅された可能性を指摘されていました。
現地での液状化の被害状況などもそのことを如実に表していたが、番組を見ると改めて、“軟弱地盤”について考えさせられました。
そんな矢先、「30年間沈み続ける関空の島」の毎日新聞の見出し記事で、航空機の騒音対策と24時間運用のため、大阪湾の海上5キロ沖の水深20メートルを埋め立てて造られた開港から30年を迎えた関西国際空港は沈み続けるため、護岸をおおむね20年に1度、かさ上げする必要があるとのことを知りました。
そのことが、2018年の台風の高波による浸水で大きな被害をもたらしたということを考えれば、改めて全国の軟弱地盤の密集地には、土地の成り立ちや災害リスクなどよりも利便性や経済活動を優先した街づくりを容認してきた今に暮らす人々の責任も大きいと思わざるをえません。
首都直下地震や南海トラフ地震という巨大地震がいつ起きても不思議ではなく、気候変動による自然災害のリスクの増大も日々実感する中で、人工島での万博・カジノに奔走している時ではないのではと思わざるをえません。
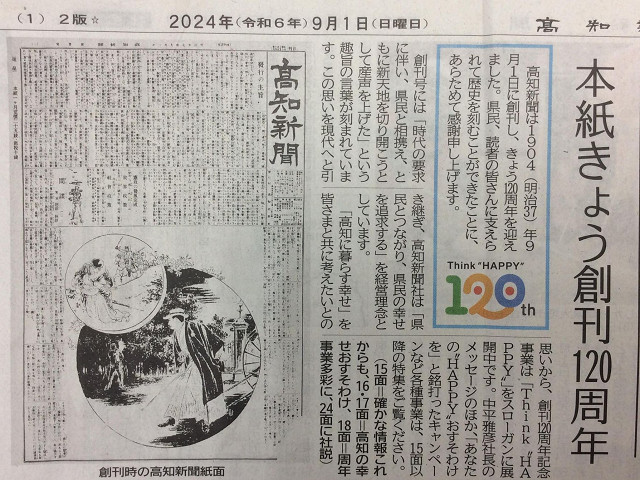 高知新聞は、昨日9月1日、創刊120年を迎えました。
高知新聞は、昨日9月1日、創刊120年を迎えました。
いろいろな特集も組まれていますが、一面の「小社会」は、次のような文章で結ばれています。
―作家の半藤一利さんは晩年、「昭和史をだめにしたのは言論の自由を失ったこと。国民がものを言わなくなった時、国家は何をしでかすか分からない」。肝に銘じたい。本紙はきょうで創刊120年。―
そして、15面の中平社長は「取材に基づき裏付けの取れた事実を伝える新聞は必ずしも刺激的ではなく、むしろ退屈かもしれません。しかし、自分とは異なる意見にも耳を傾け熟考することが、民主主義社会には必要です。」と、「創刊120周年に寄せて」います。
今、求められる貴重な姿勢ではないかと思います。
そして、これらのことを考えながら朝日新聞8月2日付けの「折々のことば」で紹介されていた歌人の永田和宏さんの著書『知の体力』から「みんなが正しいと言いはじめたら、一回はそれを疑ってみること。一度だけでいいから左を見てみること。」との言葉も改めて考えさせられます。
『知の体力』では、この言葉の少し後に、「『一億玉砕』などという言葉が声高に叫ばれ、国民が雪崩を打つように戦争に突き進んでいった歴史は、まだ70年、80年前のことでしかないのである。」と続いています。
新聞の報道姿勢とともに、誰かの強いメッセージに靡かされることのない私たち自身の主体性も問われていることも肝に銘じておかなければなりません。
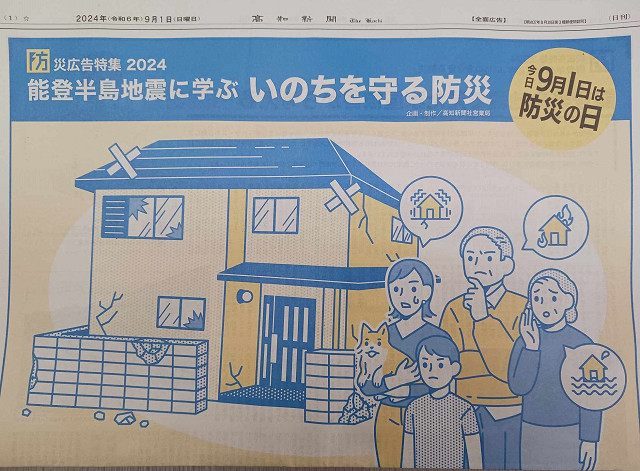 今日9月1日は、101年前の関東大震災にちなんだ「防災の日」です。
今日9月1日は、101年前の関東大震災にちなんだ「防災の日」です。
地震や風水害など自然災害多発列島に住む私たちは、命や暮らしを守るために防災・減災への備えを忘れてはならないことを毎年改めて肝に命ずる日でもあります。
しかも、今年は元旦の能登半島や8月8日の宮崎県沖日向灘などで大きな地震が相次ぎ、日向灘地震の震源地は南海トラフ地震の想定震源域内だったことから、政府は運用開始後初となる「巨大地震注意」の臨時情報を発表しました。
さらに、近年、地震以上に身近な脅威となっている水害は、山形県や秋田県では7月、記録的な大雨で河川氾濫や浸水の被害が発生し、死傷者が出た上に、今現在も台風10号が九州などで暴風雨をもたらし、大きな爪痕を残して迷走し、本日熱帯低気圧になりました。
そのような自然災害に対して、対策として講じられた「南海トラフ地震臨時情報」は周知が不十分だったという指摘を4割の知事が回答しており、高知県知事は「住民の認知度が低かったことは否めない」と回答しています。
また、台風接近について、自治体は早めに避難所を設け、住民に安全確保を促さねばならないし、住民の側も、自宅や周辺の浸水域や水深を予想するハザードマップを確認するなど、自治体による事前情報の丁寧な発信と、住民の命を守ることを最優先にした備えと向き合い方が求められていると思われます。
リスクを引き起こす自然の加害力が凶暴化・常襲化し、お互いを守り・支えあう社会のしくみが脆弱化している中で、平時からの備えにつながる取り組みに着手する契機となる「防災の日」になってもらいたいものです。

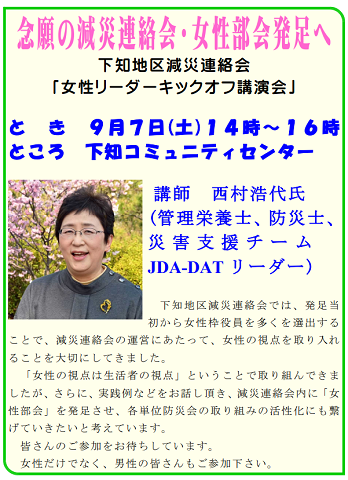 台風10号の通過に伴う下知コミュニティセンターの避難所開設も今朝終了し、市役所の職員さん、センター長とともに最終の確認をさせていただきました。
台風10号の通過に伴う下知コミュニティセンターの避難所開設も今朝終了し、市役所の職員さん、センター長とともに最終の確認をさせていただきました。
ピーク時で8名の避難者で、昨夜は7名が宿泊されていました。
29日16時~31日7時までの開設期間でしたが、また新たな学びもありました。
今回の台風は、高知県にとっては、最悪のコースで大きな被害をもたらすかもしれないと言われ、なおかつ極めてゆっくりとした速度で移動していたため大変心配されましたが、今のところ特に大きな被害はなかったものと思われます。
しかし、通過後明らかになる被害もあろうかと思います。
市内東部を自転車で少し回ってみましたが、結構きつい風が吹くこともありますので、皆さんまだまだお気をつけ下さい。
避難所として二日間過ごした下知コミュニティセンターが、今はいつもの「涼みどころ」として地域の皆さんをお迎えしております。
また、この台風のゆっくりとした速度や定まらないコースのために、週末の多くのイベントや行事が中止にならざるを得なかったところも多くあろうかと思います。
とりわけ、私たち下知地区の二葉町自主防災会を中心にした仁淀川町での広域避難防災キャンプは避難先での受け入れが困難なため中止せざるをえなくなりました。
現地との打合せなど準備に尽力された方々をはじめ、私たち参加予定していたものには残念なことですが、今回の準備が次回の開催に必ずつながるよう取り組んでいきたいものです。
当面は、9月7日(土)14時~16時に、下知コミュニティセンターで予定している下知地区減災連絡会が、女性部会発足に向けた「女性リーダーキックオフ講演会」に多くの皆さんの参加を呼びかける取り組みを進めていきます。
| 8月30日「子どもが追い込まれる前の『逃げる』選択肢」 |
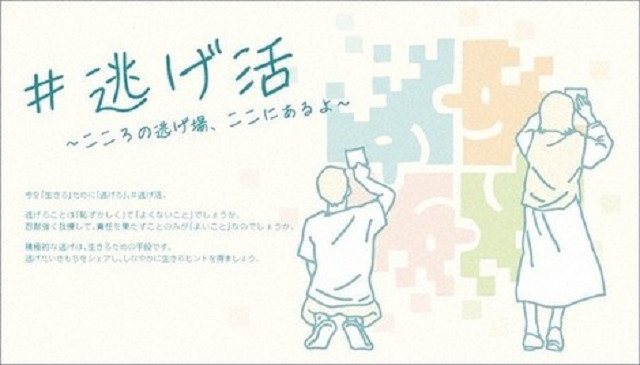 毎年のように、夏休み明けを前にしたこの時期、子ども・若者への自殺防止の呼びかけがいろいろな形で行われているが、今年は長引く台風10号騒動の中で、そんな声かけが届いてないのではないかと心配します。
毎年のように、夏休み明けを前にしたこの時期、子ども・若者への自殺防止の呼びかけがいろいろな形で行われているが、今年は長引く台風10号騒動の中で、そんな声かけが届いてないのではないかと心配します。
特に、今年は、子どもの自殺が増加傾向にあり、小中高生はコロナ下の2022年に過去最多の514人を数え、23年は513人に上り、今年の上半期も249人と、昨年同期を上回っている時期でもあることから深刻であると言えます。
日本財団の22年の若者調査では、約半数が「死にたい」と思ったことがあり、うち4割は準備したり実際に行動に移したりしていたとのことで、10~20代の死因の1位が自殺なのは、主要7カ国では日本だけだと言われています。
その背景には、国のさまざまな意識調査から浮かぶのは、自尊心の低さや、家庭の経済状態も子どもの精神面に影響を与えていたこともあると思われます。
子どもの9人に1人が貧困状態にあるとされ、子育て世帯の収入格差は拡大傾向にあり、学習、習い事、夏休みの体験などを十分にさせてあげられず、子どものやる気の喪失を心配する親は多いと言います。
苦境にある子どもたちのSOSに耳を傾け、支援につなげなければならないが、そのつながりが築けているかというとけしてそうではないかもしれません。
国の指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」は今月、「死にたいほど追い込まれる前に『逃げる』選択肢があるよ」と呼び掛け、「#逃げ活」と題する啓発活動を始めています。
子どもが追い詰められた時、安心して過ごせる場所や寄り添ってくれるおとながいる場所に逃げ込める環境があることや、きっかけや選択肢の提供ができることが求められているのではないでしょうか。




台風10号は今日午前8時ごろ、鹿児島県に上陸しました。
現在、九州をゆっくりした速度で北上中で、高知県内には30日夕方から31日にかけて接近する見込みと言われています。
また、気象庁は29日から30日夜にかけて、県内で線状降水帯が発生する可能性があるとし、うねりを伴う高波や暴風、土砂災害、河川増水などに警戒を呼びかけています。
そのような中で、16時に「高齢者等避難」が発令され、優先開設避難場所23か所が開設されました。
下知コミュニティセンターには、すでにお一人避難されていますが、これから明るいうちにということで、避難者が増えてくるのではないかと思われます。
今回の台風10号には三つの特徴があって、一つ目は、台風から離れた地域でも広範囲で大雨が降る「遠隔大雨」のリスクがあることです。
二つ目は、極めて「遅いスピード」で、「ゆっくり」進んでおり暴風豪雨の時間が長時間に及んでいることです。
そして、三つ目が「最強に近い」(気象庁)とも言われる勢力の強さです。
上陸してから、少し衰えてはいるが、それでも965ヘクトパスカルです。
この三つの特徴が、災害リスクを大きくしていると思われます。
「遅いスピード」での移動ですので、しっかりと備えていきましょう。
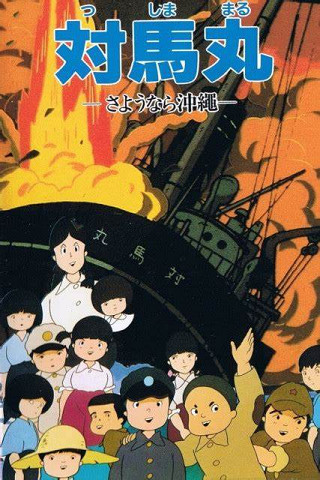
 80年前の8月22日、学童疎開船「対馬丸」が那覇港から長崎に向かう途中、鹿児島県悪石島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しました。
80年前の8月22日、学童疎開船「対馬丸」が那覇港から長崎に向かう途中、鹿児島県悪石島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しました。
乗船していたとされる1788人のうち、判明しているだけで学童784人を含む1484人が亡くなりました。
沖縄県は1944年7月19日、「沖縄県学童集団疎開準備要項」を発令し、学童疎開が始まり、島外への疎開は、沖縄戦に先立つ米軍の空爆が本格化した45年3月ごろまで続き、のべ187隻の民間徴用船が使われ、約8万人が疎開し、不幸なことに、このなかで対馬丸だけが撃沈されたのです。
アニメ映画「対馬丸 さよなら沖縄」というのを当時小学生の息子と一緒に観た時に、涙が止まらなかったことを覚えています。
80年経った今、政府は台湾有事などを想定し、南西諸島の住民が九州・山口の8県に避難する計画づくりを進めています。
沖縄本島の南西に位置する先島諸島の5市町村には11万人と観光客1万人の計12万人が避難する必要があるとして、九州・山口8県の収容可能人数を調べたところ36万人となり、今後は、各県はモデル計画を基に受け入れ計画を調整するとのことが、説明されています。
先島諸島の外に避難する場合、輸送手段が船や航空機に限定される中、どのような計画を策定しようが80年前の対馬丸事件を繰り返す危険性は回避できないように思えてなりません。
今の政府が、対馬丸事件の教訓に学ぶなら、子どもたちをはじめとした国民をそのような危険に晒さないための対策こそが、求められているのではないでしょうか。
| 8月27日「本県には最悪コース大型台風10号に備えて」 |


 大型台風10号は、高知県にとっては最悪のコースを辿りながら、接近しつつあります。
大型台風10号は、高知県にとっては最悪のコースを辿りながら、接近しつつあります。
台風は向きを変え、列島を縦断するように北東へ進む見通しで、気象庁は暴風や土砂災害、浸水、河川増水への厳重な警戒を呼びかけています。
同庁によりますと、西日本を中心に、28日頃にかけて次第に暴雨の影響が強くなる見込みで、九州南部と奄美地方の予想最大瞬間風速は60メートルで、一部の住家が倒壊したり、多くの樹木が倒れたりするような猛烈な風が吹く恐れがあるとのことです。
台風の接近前から大雨災害が発生する恐れがある上、台風自体の進む速度が自転車の速度よりも遅いため影響が長く続く見通しとされています。
しかも、接近するにつれて、中心気圧は980ヘクトパスカルから970、中心付近の最大風速40メートル、最大瞬間風速55メートルへと勢力を増しています。
30~31日にかけて最も高知に接近する中で、長期間に影響が及ぶことも想定されています
。
可能な備えで、被害を最小限にとどめて頂けたらと思います。
県議会でも、予定していた28日からの議会危機管理文化厚生委員会の県外調査も、延期することとなりました。
このコースで接近すれば、避難所開設なども求められてくると思いますので、地域でも避難所運営に協力しながら、避難者の安全確保に努めたいと思います。
そして、私の住むマンションは大規模修繕工事の最中ですので、足場の一部解体とシートの対策を急いでいます。
| 8月22日「『事前復興』『災害ケースマネジメント』について学ぶ」 |
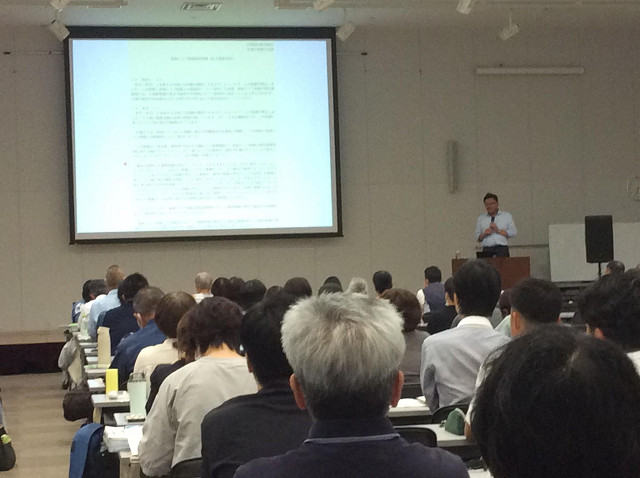
 19日、20日と連続で、この間重点的に取り組んできた二つのテーマで連続しての学びの場に参加してきました。
19日、20日と連続で、この間重点的に取り組んできた二つのテーマで連続しての学びの場に参加してきました。
19日は、高知市防災人づくり塾で高知市事前復興まちづくり計画策定検討委員会会長・牧紀男先生(京都大学防災研究所)による「事前復興のすすめ―南海トラフ地震後の高知の生き残り―」と題したお話で、復興の課題、復興できるための事前の取り組み、なぜ事前復興が進まないのかなどについてお話頂きました。
先生のお話のポイントは、先生の近著「平成災害復興誌―新たなる再建スキームをめざして―」の結びにある「災害前から被災することも踏まえた地域の姿、ありようを描き、その実現のために努力していところが不可欠である。何の備えもなく、良い復興が実現されるということはありえない。」に尽きると思ったところです。
20日は、高知県災害ケースマネジメント研修で、市町村職員や士業会、社協職員の方々約140名(オンライン110名)が参加された中、被災地での被災者支援に尽力されている永野海弁護士(日弁連災害復興支援委員会副委員長)から「過去の大規模災害から生活再建を学ぶ」とのテーマで、能登半島地震での支援活動をはじめ、「罹災証明は市民と自治体の二人三脚作業」「見えにくい被害にこそ寄り添う」「支援制度を使いこなし地域を復興する」「支援制度を活用した住まいの再建を感じる」について、お話頂いたのち被災者生活再建カードを使ったワークショップを行って頂きました。
ワークショップを通じた支援制度を活用した住まいの再建の疑似体験は、被災後の生活再建を自分事にするうえで、有効なものだと感じました。
また、被災前から支援制度を知っておくことが、行政にとっても市民にとっても生活再建の多様な選択肢を活用し、諦めることなく復興に向けて歩み出すことにつながると思いました。
牧先生には、一昨年下知地区減災連絡会の学習の場に来て頂きましたが、今度11月には永野先生にお越しいただくこととなっています。
災害ケースマネジメントの仕組みを事前に学ぶことも事前復興の大きなツールだと思います。
 岸田自民党総裁の突然の再選不出馬表明以降の話題は自民党総裁選、そして解散総選挙の日程などの取りざたに終始しています。
岸田自民党総裁の突然の再選不出馬表明以降の話題は自民党総裁選、そして解散総選挙の日程などの取りざたに終始しています。
総裁選は9月12日告示、27日投開票の日程で行われることが決まったが、自民党はいかに看板の架け替えと映る候補を選ぶのかに腐心しているように思えます。
岸田総裁は、派閥の裏金事件によって政権への信任を失い、再選出馬を断念したことからすれば、選挙戦でまずもって問われるのは政治改革への取り組みであります。
共同通信社が17~19日に実施した全国緊急電話世論調査によると、岸田自民党総裁の退陣が、派閥政治資金パーティー裏金事件からの「信頼回復のきっかけにはならない」との回答が78.0%に上り、内閣支持率は前月の不支持を上回り67.4%に上っています。
総裁選で議論してほしい課題は景気・雇用・物価高対策が最多の50.9%で、2位以下は年金・医療・介護36.6%、子育て・少子化25.7%、政治とカネ20.1%が続いています。
裏金事件など続出する「政治とカネ」問題のうみを出し切り、実のある政治改革に踏み込む総裁こそが国民の要請に応えることになるのだろうが、これまでそのことに言及しない方々の総裁選での決意を俄かに信用できるものではないことを国民は知っているのではないでしょうか。
総裁選候補者は、政倫審での質疑実現など裏金事件の全容解明に向けた指導力を競うことと本気度を示すことができない限り、国民の信頼回復には繋がらないことでしょう。
さらに、総裁選数多の候補者の中で、真っ先に立候補表明した小林鷹之議員は、注目が集まるのと比例して旧統一協会との関係がクローズアップされ、改めて自民党と統一教会の関係問題が浮上することになると思います。
官房長官や外相を務めた伊東正義氏は1989年、リクルート事件で退陣する竹下登首相の後継に推され、「本の表紙だけを替えても中身が変わらないと駄目だ」と、固辞しました。
結局、後継首相には宇野宗佑が選ばれ、自民党は直後の参院選で惨敗しました。
今回も、自民党の中身(本質)は変わらず、表紙だけを替えようとさえ見える総裁選になるなら国民の信頼を取り戻すことは無理ということを自民党員たちは分かっているのでしょうか。
| 8月18日「被爆体験、戦争体験を風化させずに、戦争させない決意を」 |
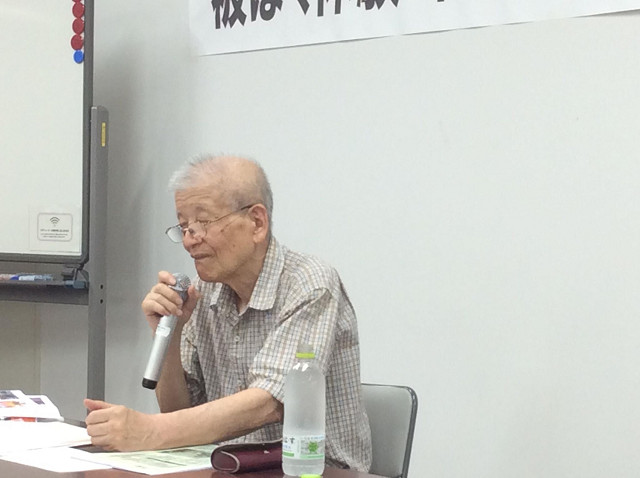



昨日、NPO高知県日中友好協会と高知県日中友好中国帰国者の会では14時~「2024日中友好平和を語る集い」を開催しました。
日中友好協会副会長植野さんの被爆体験と日中友好中国帰国者の会中野会長の残留孤児として国策に翻弄されたお話に参加された50名以上の参加者が耳を傾けました。
植野克彦さんは、広島高等師範学校付属中1年で、農作業に動員されて向かう途上で被爆されています。
路地の日陰で、周りがまっ黄色になったと感じた被爆の瞬間。
恐る恐る眼をあけて「助けてくれ」と大声をあげたこと。
見えてきた青空の中の原子雲、近くにあるある病院を同級生とともに目指して、そこで飲ませてもらったやかんの水、「黒い雨」が冷たく気持ちよく感じた。
昏睡状態で現在の大竹市の小学校の講堂で眼を覚ましたところを母が探し当ててくれた。
治療とも言えないような、血と膿でドロドロになった布巾を洗っては塩水をつけて患部に貼ってもらったこと。
母の故郷の高知に帰って、当時の城東中(追手前高校)に転向してからは、ヒロシマのことは思い出したくなかった。
しかし、「日本でも核武装すべきだ」という大臣が表れて、黙っていられないと80歳を過ぎてから被爆体験を語り始められたそうです。
「これからの人々に永遠にこんな体験をさせたくない。これからもしっかりと伝承して頂きたい。」と結ばれました。
その後の中野ミツヨさんのお話については、7月23日にお聞きした際にも、報告させて頂きましたが、両親が満州へ満蒙開拓団としてわたってから、日本の敗戦後の避難途中で自身が生まれたこと。
そして、養父母に貰われ育てられたが、養父母の離婚で生活が激変したこと。
自身が日本人であることを知りながら、中国での仕事につき、肉親捜しの願いが叶ったが、帰国に至るまでの苦労、そして帰国後の生活で、普通の日本人として生活がしたいとの思いで立ち上がった中国残留孤児国家賠償訴訟、最後に、自らの人生を振り返って思うことについて、語って頂きました。
日本が起こしたあの戦争で残留孤児になった自分たちは失った親や家族と永遠に会えなくなったが、戦争を許さないし悲惨な歴史が二度と来ないようにしたいという残留孤児としての決意ともいえる思いが語られました
。
広島と長崎の原爆被害は、その教訓をしっかり記憶するために、毎年式典が催され教科書にも記載され代々伝承されているが、開拓団も同様に日本国民で多くの犠牲者が出ているのになぜこの歴史は国民に広く知らされないのかと怒りを感じられています。
中国残留孤児にとって、中国は私たちを死の淵から救い育ててくれた命の恩人で、日本国は私たちの母国である。
だからこそ、命の恩人と母国の間で、戦争はさせないためにも、日中友好が世々代々受け継がれていくことを心から願う残留孤児の皆さんの思いを我々が共有し、決意していかなければなりません。
もっともっと若い人たちに聞いてもらいたいお話ばかりでした。



敗戦から79年の15日は、「8.15平和と人権を考える集会」で、映画「戦雲」を鑑賞しながら、会場一杯の参加者の皆さんとともに「戦前の今」について、考えさせられました。
監督は、これまでにも上映会を行ってきた『標的の村』などの三上智恵さんで、沖縄本島をはじめ、南西諸島の島々をめぐり、2015年から8年かけて取材を行ったドキュメンタリー映画でした。
1945年8月15日は常に立ち返るべき原点であり、そこから79年間戦争を拒み、平和を築く国民の意思を再確認する日であったはずです。
しかし、岸田首相は、全国戦没者追悼式の式辞で、安倍元首相や菅前首相と同様、アジアの国々への加害責任には触れませんでした。
そして、この人は、安全保障3文書の閣議決定で「専守防衛」という日本の防衛政策の国是を覆し、防衛費の増額を進め、憲法9条への自衛隊明記に関する論点を整理するよう自民党に指示するなど、戦後日本の柱だった平和主義を蔑ろにし続けて、「戦争する国」づくりを進めて、国民からの不信と批判に耐えきれず、退陣表明をしました。
「新しい戦前」と言われる今、映画「戦雲」に描かれた与那国島、宮古島、石垣島、沖縄本島で行われてきた79年間の戦後は、有事のための開戦準備だったのではないかと思わざるをえません。
このまま沖縄戦を繰り返し、日本全土をアメリカの盾とした有事に突入することに、歯止めをかけることができるのかが、私たちに問われているような思いで、「戦雲」を観たことでした。
機会があれば、この映画を多くの方々に観てもらいたいものです。
そこから、「戦争する国」に抗うことへの一歩が始まるのだと思います。
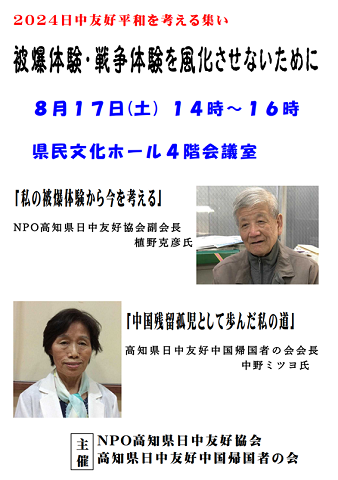 もう一つ、そのような機会になればと思う「2024日中友好平和を語る集い」が本日開催されますので、ご案内します。
もう一つ、そのような機会になればと思う「2024日中友好平和を語る集い」が本日開催されますので、ご案内します。
高知県日中友好協会と高知県日中友好中国帰国者の会では、14時~16時に県民文化ホール4階会議室でを開催します。
日中友好協会副会長植野さんの被爆体験と日中友好中国帰国者の会中野会長の残留孤児として国策に翻弄されたお話をぜひお聞きください。
| 8月16日「臨時情報『巨大地震注意』呼びかけ終了で、さらに備えの継続を」 |


8日午後4時42分頃の宮崎県沖の日向灘を震源とする地震は、最大震度6弱を観測し、震源は宮崎県の東南東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.1でした。
その地震を受けて、気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表し、以降1週間は巨大地震に注意するように呼び掛けられてきました。
特に、今回は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」への対応で各自治体の対応に混乱が生じたり、お盆や夏のイベントで移動や人出の多くなる中での一週間でした。
その間は、今回の「巨大地震注意」では、「巨大地震警戒」と違い事前避難は求められませんでしたが、「日頃からの地震の備えの再確認」に加えて、地震が発生したらすぐに逃げられる準備が求められました。
通常の生活を送りながらも、避難場所・避難経路の確認、家族の皆さんとの安否確認手段の確認、家具の固定ができているかの確認や非常持出品の改めての確認などの備えを、しっかりと行うことが求められました。
とにかく、いつもより備えを確かに、身構えながら、日常生活の継続が求められましたが、南海トラフ地震は今回のように「臨時情報」が出ないまま、突発的に起こる可能性のほうが高いわけでで、「巨大地震注意」の呼びかけが終了しても、防災・減災対応を向上させながら継続していくことが大事になります。
「臨時情報」は、いわゆる避難行動要支援者や耐震性の低い建物に住んでいる人などの被害を大幅に減らすことがポイントですが、それらをチェックしておくことが、突然地震が起きたときにも活かされますので、今回の発令と対応の教訓をチェックし、次の「臨時情報」が発令されたときの対応に活かして頂きたい思います、
令和5年度の高知県民世論調査で、臨時情報の認知度は28%で、多くの住民が情報の意味を十分に理解しないままの発表となりました。
先日、オンラインでお話を伺った愛知県豊橋市の臨時情報啓発については、令和3年に高知とおなじように28%だった臨時情報の認知率を高めるために、行政から住民への一方的な説明会ではなく、大学の有識者を交えて住民と行政が対等な立場で一緒にどうしたらいいかを考える「南海トラフ地震臨時情報勉強会」を、事前避難対象地域のある12小学校区のうち、事前避難対象地域に住家のある9校区を対象に実施したそうです。
専門家の意見や資料など科学的根拠に基づいて伝える、わからないことや不確定な部分がある事も共有する中で、地域特性に合わせた防災訓練の再考や複合災害対応について検討する必要があるなど、住民も行政も相互に気づくことが多くあったとのことでした。
「臨時情報」が出たときの対応は、行政に一律に決めてもらうよりも、受ける側で微調整していくほうが現実的と言われる中で、今回の一週間を踏まえた自助・共助・公助の相互の話し合いで教訓化していく取り組みが求められているのではないでしょうか。
| 8月14日「映画「戦雲」を鑑賞して、沖縄からのメッセージに応える闘いを」 |
 明日、敗戦の日に「8.15平和と人権を考える集会」で、映画「戦雲」が上映されます。
明日、敗戦の日に「8.15平和と人権を考える集会」で、映画「戦雲」が上映されます。
監督は、これまでにも上映会を行ってきた『標的の村』などの三上智恵さんで、沖縄本島をはじめ、南西諸島の島々をめぐり、2015年から8年かけて取材を行ったドキュメンタリーです。
沖縄・南西諸島では、日米両政府主導で戦力配備が進められており、2022年に、台湾有事を想定した軍事演習と文書から、九州と南西諸島を戦場にした防衛計画が明らかとなりました。
一方、過酷な戦争の記憶が残る自然豊かな島では、伝統的な暮らしが営まれています。
メディアが報じることのないまま進められる国防計画の恐ろしさを解き明かしていく内容となっています。
沖縄・南西諸島の今を自分事とし、「特定利用」という名の軍事利用に巻き込まれようとする高知の三港湾の問題と向き合うためにも、ぜひご覧ください。
■上映日 8月15日(木)
■上映時間 18時〜
■会場 高知県民文化ホール 多目的室第6
■主催 戦争への道を許さない女たちの会
■共催 高知県平和運動センター
■チケット協力金 1000円(当日1200円)
| 8月13日「『臨時情報(巨大地震注意)』で備える」 |

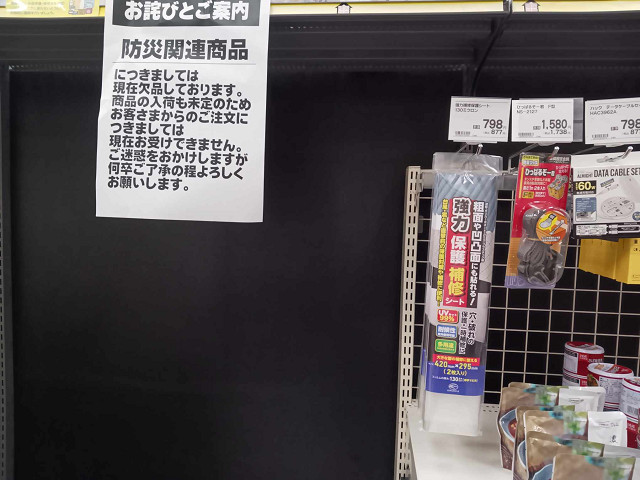 昨日は、東京から帰省した息子とともに、朝から墓掃除・参りのために土佐久礼に行くつもりでしたが、いろいろと話し合って、臨時情報も出ていることだし、もしもの時の対応もあるので、見送ることにしました。
昨日は、東京から帰省した息子とともに、朝から墓掃除・参りのために土佐久礼に行くつもりでしたが、いろいろと話し合って、臨時情報も出ていることだし、もしもの時の対応もあるので、見送ることにしました。
もし、土佐久礼で、被災してもお墓は避難場所の近くですし、地域内の状況はほぼ頭に入っているし、何とかなるとは思うのですが、公共交通機関でしか移動できない私たち家族にとっては、その後が大変です。
そして、マンションの津波避難ビル対応や下知地区のことも気にかかりますので、この一週間は用心にこしたことはありません。
そのかわり、午前中は、マンションの防災ボックスや防災備品のチェックに汗を流しました。
そして、午後には、防災用品を扱う量販店を覗いてきましたが、店員さんは防災用品は店頭に並んだものしかないとおっしゃってました。
慌ててでも、購入しているとすれば、一つの備えのきっかけにはなっているかもしれません。
親子で来ていたお客さんの「お母さん、こうなる前に買うちょかんといかんかったがよ」「確かに、〇〇ちゃんが言いよったね。お母さんが悪い。」との会話を聞くにつけ、いかに、子どもたちの方が防災意識が高いかと痛感しました。
また、この機会に防災食の点検をしたら、今年で期限切れが迫っていたので、これからせっせと食べて、買い替えると仰っている方もいました。
気象庁は昨日、宮崎県で最大震度6弱を観測した地震の後、南海トラフ地震の想定震源域内で観測された震度1以上の地震は、11日の発表から2回増え23回になったと発表しています。
同庁は同地震の「臨時情報(巨大地震注意)」を発表した後、同地震に関連するプレート境界の固着状態に特段の変化は観測されておらず、内閣府の防災担当者によると、このまま地震活動や地殻変動に変化が見られなければ、15日午後5時で同情報の呼び掛けを終了する予定だそうです。
しかし、それで気を緩めるのではなく、キチンとした備えを継続していきましよう。
南海トラフ地震はいつ起きても不思議でないのですから。
| 8月12日「高知の先駆的女性群像~男女平等と権利のために立ち上がった女性たち~の歴史に学ぶ」 |

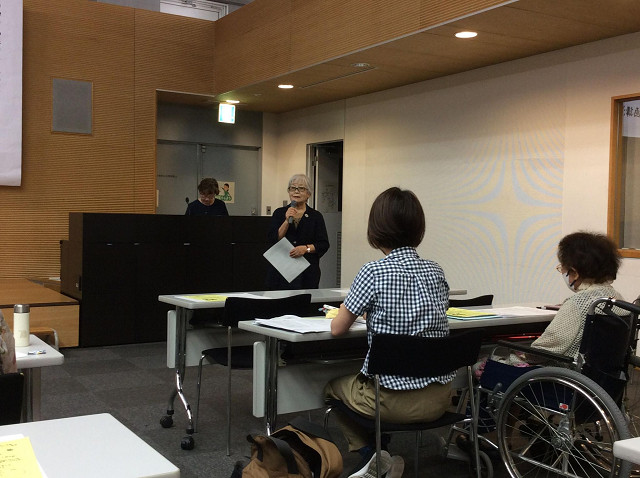
 昨日は、よさこい祭りの喧噪の中を男女共同参画センター「ソーレ」へと自転車で向かい、歴史研究者公文豪氏講演会に参加してきました。
昨日は、よさこい祭りの喧噪の中を男女共同参画センター「ソーレ」へと自転車で向かい、歴史研究者公文豪氏講演会に参加してきました。
今回は南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が、出されている中での開催でしたので、開会前に主催者のこうち男女共同参画ポレールから、もしもの時の対応について説明がされた上での開催となりました。
テーマは「高知の先駆的女性群像~男女平等と権利のために立ち上がった女性たち~」でこれまでの「民権ばあさん楠瀬喜多と女性参政権」、「植木枝盛の女性解放論」に続く公文豪氏から女性の解放や人権獲得にまつわる史実について学ばせて頂きました。
これまでの2回は、日程が重なり、参加できませんでしたが、今回はやっと参加できて2時間近く、貴重なお話を聴かせて頂きました。
今回は、高知の先駆的女性たちが、いかにして立ち上がったか、声をあげたのか。
高知で最初の女性演説をした大原千歳、テーマが男女平等で拍手喝采たったこと。
県議会傍聴の女性第一号となった松鶴楼芸妓・愛吉の演説と「芸妓諸君に告ぐ」の中にある職業に貴賎なし、男女平等、自主独立の傑出した思想。
そして、植木枝盛の女性解放論に感化されて立ち上がった助産師として自立していた富永らく、婦人自らが立ち上がる責務を説いた「婦人の急務」を訴えた吉松ます。
三大事件建白運動に参加した女性たちの中からは、高知の女性が実践的な政治運動に参加し処分された大谷きよえ、女ばかりの大演説会を開催した杉村作、高知県婦人会の結成と論争のリーダーであった傑出した理論家山崎竹、帝国議会と女性の傍聴権獲得の闘いり先頭に立った清水紫琴などの活動の足跡を辿り、男女平等、当たり前の権利獲得に向けてどのように訴え、闘ってきたか聴かせて頂きました。
楠瀬喜多さんが参政権獲得の闘いに立ち上がれたのは、多くの先駆的闘いに立ち上がった女性がいたからこそということも分かりました。
頂いた資料を改めて読み直して、その闘いの教訓に学びたいと思います。
| 8月11日「『巨大地震注意』臨時情報は空振っても、備えを確かなものに」 |
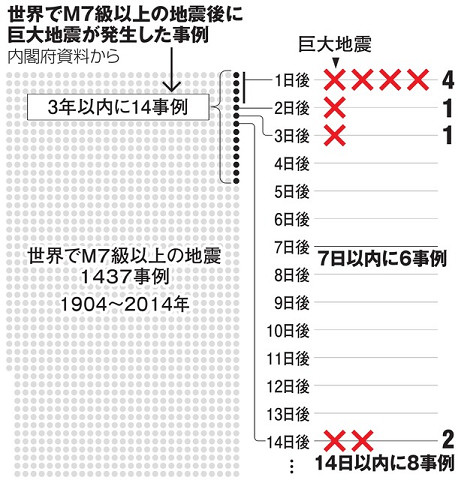 2016年に下知地区減災連絡会で石巻市を訪問した時、同行取材され、下知にもお越しになり、昭和小や下知コミセンで取材頂いた朝日新聞編集委員の佐々木英輔氏が、今朝の朝日新聞に南海トラフ地震臨時情報に関する記事を書かれていました。
2016年に下知地区減災連絡会で石巻市を訪問した時、同行取材され、下知にもお越しになり、昭和小や下知コミセンで取材頂いた朝日新聞編集委員の佐々木英輔氏が、今朝の朝日新聞に南海トラフ地震臨時情報に関する記事を書かれていました。
「巨大地震、起こるのは数百回に1回?なぜ1週間?注意情報の根拠は」の見出しで、南海トラフ地震をめぐって出た「巨大地震注意」の臨時情報で、いつもより数倍起きやすくなっているのに、起こるのは数百回に1回とされていることや、警戒が求められるのは1週間。どのような根拠で決められたのかとの記事です。
記事によりますと、「数百回に1回」のもとになったのは「1437分の6」という数字で、これは、南海トラフではなく、世界で過去に起きた地震の統計にもとづくものだとされています。
マグニチュード(M)7級以上の地震が起きたとき、1週間以内にM8級以上の巨大地震が起きたケースを数えると、1904年から2014年までの1437事例のうち、6事例あったということで、東日本大震災も、このうちの一つでした。
2011年3月9日にM7.3の地震が発生し、2日後にM9.0の巨大地震が起きており、地震は予知できないものの、この時点で巨大地震への警戒が呼びかけられることはありませんでした。
2019年から始まった南海トラフ地震臨時情報は、こうした教訓が背景にあり、予知はできなくても、世界の統計から、起きやすさを類推することはでき、そのことによって「大規模地震の発生可能性が平常時に比べて相対的に高まっている」との表現で、防災対応を呼びかけたものと言えます。
「1437分の6」は、平時の南海トラフと比べると、巨大地震の起きやすさが数倍高まった状態にあたるというが、起きないケースのほうが多いことは否めません。
記事には「南海トラフの震源域では、M7級の地震が15年に1回ほどの頻度で起きていることから、今後も臨時情報の発表が繰り返され、『空振り』が続く可能性のほうが高い。」とあるが、私たちは、それを機会に備えを確認し、気を緩めることなく備えを確かなものにしていくことが求められているのであることと受け止めていく必要があります。
そして、「1週間は注意」との呼びかけについては、内閣府による自治体アンケートで、南海トラフ沿いの534市町村に、避難のストレス、住民感情、自治体業務、経済活動などについて、大きな影響が出始めるまでの期間を尋ね、「社会的な受忍の限度」として最も警戒する期間は1週間が基本とされたとのことであります。
今回は「巨大地震注意」であることから、一週間程度だが、南海トラフでM8級の地震が起こると、「巨大地震警戒」の臨時情報が出ることになると、その時は避難も含めた対応を1週間、さらに1週間は「巨大地震注意」と同様の対応を取ることになりますから、そのことに対応できる備えと覚悟が迫られてくることを改めて共有しておきましょう。
| 8月9日「初の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」」 |
 昨8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市南郷町で最大震度6弱を観測し、震源は宮崎県の東南東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.1でした。
昨8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市南郷町で最大震度6弱を観測し、震源は宮崎県の東南東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.1でした。
この地震を受けて、気象庁は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表し、今後1週間は巨大地震に注意するように呼び掛けています。
特に、今回は初の「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」への対応で各自治体の対応に混乱が生じているようです。
「巨大地震警戒」であれば避難に時間がかかる人には事前避難を求めていますが、今回の「巨大地震注意」では、事前の避難は伴わないで、「日頃からの地震の備えの再確認」に加えて、地震が発生したらすぐに逃げられる準備を求めています。
とにかく、いつもより身構えながら、日常生活を続けてほしいということになります。
皆さん、お盆や夏のイベントで移動や人出の多くなる一週間です。
過度に不安を抱くことはなくとも、くれぐれも正常性バイアスに陥らないように、身構え備えた生活を送りましょう。
なお、昨夜知事からは、それらのことを踏まえて、県民の皆さんには、次のようなメッセージが出されています。
〇「巨大地震注意」の段階で求められている対応といたしましては、発表から1週間から2週間程度は、通常の生活を送りながら、次の地震に向けた備えを再確認していただきたい、という情報です。
○ 具体的には、・避難場所・避難経路の確認・家族の皆さんとの安否確認手段の確認・家具の固定ができているかの確認・非常持出品の改めての確認・緊急情報の取得体制の確認こういった備えを、通常の生活を送りながらも、しっかりと行っていただきたい、というメッセージです。
○ また、今後、大きな揺れを感じたらすぐに避難できるよう準備してください。
○ 具体的には、・非常持出袋をあらかじめ準備しておく・すぐに避難できる態勢で就寝するといった備えをお願いします。
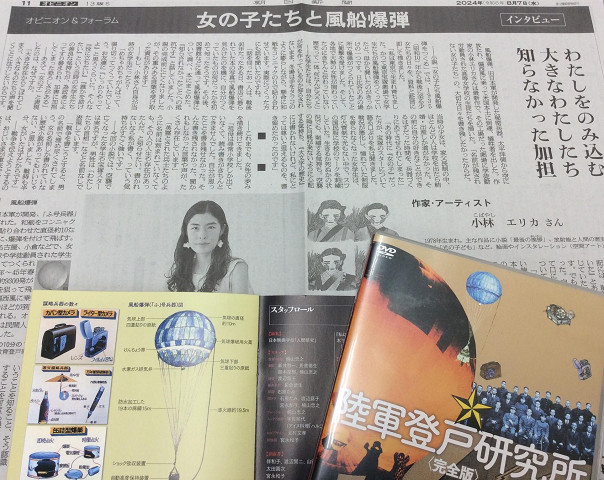 7日付け朝日新聞「オピニオン面」のインタビュー記事の見出しに「風船爆弾」との文字を眼にしました。
7日付け朝日新聞「オピニオン面」のインタビュー記事の見出しに「風船爆弾」との文字を眼にしました。
作家の小林エリカさんは、その工場だった劇場に学徒勤労動員された高等女学校の生徒たちを小説「女の子たち風船爆弾をつくる」で描かれた思いについてのインタビュー記事です。
その記事を読んで、昨年、講談社から高知出身の作家中脇初枝さんが発刊された「伝言」にも、私が亡き母の旧友として紹介する崎山みどりさんたち「女の子たち」が、風船爆弾づくりに勤しむ姿が描かれていたことを思い出しました。
風船爆弾とは、旧日本軍が開発した秘密兵器で、太平洋側から空に放たれ、偏西風に乗って米国本土に到達、犠牲者を出したものです。
そして、風船爆弾などの秘密兵器を研究した映画「陸軍登戸研究所」を2013年6月に高知大学で観せて頂いたことを思い出し、改めて、昨日その映画のDVDを観ました。
映画の中では、陸軍登戸研究所は、陸軍科学研究所の中でも、最も膨大な資金をつぎ込み、「殺人光線、電波兵器、生体実験への道、毒物・爆薬の研究、風船爆弾、生物・化学兵器、ニセ札製造、対支経済謀略」の研究を託された登戸研究所の闇が描かれていました。
新聞の小林さんのインタビュー記事の中にも「生徒が動員された学園に問い合わせて、卒業生への聞き取り調査の資料や、同窓会報などを見せていただきました。風船爆弾についても、陸軍登戸研究所で働いていた方が記録を捨てずに持っており、地元の活動を通じて引き継がれていました」とありますが、陸軍登戸研究所で働き、風船爆弾をつくっていた「女の子たち」が登場します。
また、風船をつくる際の紙には土佐の楮が多く使われていたことにも触れられる中で、改めて他人事ではないことも考えさせられました。
私も、映画を観た2013年当時は、詳しく知りませんでしたが、その際映画について話された監督から「戦争は誰のために続けたのか。図らずも原発ムラと相似する構図」が浮き彫りにされ、事実を知らされずに突き進んでいった戦争と原発推進の背景の相似性や「知らなかった加担」についても、感じさせられる映画であることを教えられました。
| 8月9日「被爆体験、残留孤児の戦争体験と向き合ってください」 |
 昨日広島では、被爆から79年目を迎えました。
昨日広島では、被爆から79年目を迎えました。
世界は、核兵器使用の恐怖と向き合わざるをえない緊張状態が続いています。
そして、沖縄・奄美を中心に始められた「対中戦争態勢」構築は、いま九州を中心に西日本に拡大されています。
陸自・大分分屯地では大型弾薬庫9棟の建設に向けた工事が進み、陸自・湯布院駐屯地には「対艦ミサイル連隊」が今年度中に配備され、宮崎県えびの市の陸自駐屯地や鹿児島県さつま町にも弾薬庫の建設が計画され、熊本の陸自・健軍駐屯地にはすでに「対艦ミサイル連隊」が配備されています。
そして、高知の高知新港・須崎港・宿毛湾港をはじめとした全国の特定利用目的港湾・空港が、軍事目的としての利用につながる懸念はぬぐえません。
そのような中で、「被爆体験・戦争体験を風化させない」ために、高知県日中友好協会と高知県日中友好中国帰国者の会では、8月17日(土)14時~16時に県民文化ホール4階会議室で「2024日中友好平和を語る集い」を開催します。
日中友好協会副会長植野さんの被爆体験と日中友好中国帰国者の会中野会長の残留孤児として国策に翻弄されたお話をぜひお聞きください。
 米国が広島に原爆を投下して、きょうで79年になります。
米国が広島に原爆を投下して、きょうで79年になります。
核を巡る緊張はいま、被爆者の願いに反して、冷戦後で最も高まっていると言えます。
にもかかわらず、核兵器使用の恐怖と向き合わざるをえない、緊張状態が続いています。
その背景には、ウクライナとパレスチナ自治区ガザで続く二つの戦禍があり、核保有国のロシアとイスラエルが核を持たぬ相手に対し、核の脅しを伴って攻撃しており、私たちはそのことからけして目を背けてはなりません。
非人道兵器による脅し合いは国と国民を守る手段にはなり得ないし、国際社会がそう決意した証しが核兵器禁止条約ではないのでしょうか。
日本が果たすべきは、核抑止論を乗り越える行動であり、先制不使用を含む核の役割低減の国際合意を積み上げることあり、その議論を主導することが、今こそ求められています。
松井広島市長は、「平和宣言」で「混迷を極めている世界情勢をただ悲観するのではなく、こうした先人たちと同様に決意し、希望を胸に心を一つにして行動を起こしましょう。そうすれば、核抑止力に依存する為政者に政策転換を促すことができるはずです。必ずできます。」と述べ「日本政府には、各国が立場を超えて建設的な対話を重ね、信頼関係を築くことができるよう強いリーダーシップを発揮していただきたい。さらに、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な取組として、まずは来年3月に開催される核兵器禁止条約の第3回締約国会議にオブザーバー参加し、一刻も早く締約国となっていただきたい。」と迫りました。
また、子ども代表が「平和への誓い」で述べた、「今もなお、世界では戦争が続いています。79年前と同じように、生きたくても生きることができなかった人たち、明日を共に過ごすはずだった人を失った人たちが、この世界のどこかにいるのです。本当にこのままでよいのでしょうか。願うだけでは、平和はおとずれません。色鮮やかな日常を守り、平和をつくっていくのは私たちです。一人一人が相手の話をよく聞くこと。「違い」を「良さ」と捉え、自分の考えを見直すこと。仲間と協力し、一つのことを成し遂げること。私たちにもできる平和への一歩です。さあ、ヒロシマを共に学び、感じましょう。平和記念資料館を見学し、被爆者の言葉に触れてください。そして、家族や友達と平和の尊さや命の重みについて語り合いましょう。」との呼びかけに、どれだけの国民が答えることができるのかが問われています。
放映中のNHK連続テレビ小説「虎に翼」主人公のモデルとなった日本初の女性弁護士、三淵嘉子さんは、戦後は裁判官となり、米国の原爆投下を「国際法違反」と断じた「原爆裁判」にかかわったことは、良く知られています。
判決は、その後の被爆者救済に影響を与えたし、国際社会でも大きな意味を持ちました。
1996年に国際司法裁判所(ICJ)が、核兵器使用は国際人道法に「一般的に反する」とした勧告的意見にも影響を与えたとされているし、この意見を踏まえ、2017年に核兵器禁止条約が採択されたが、日本政府が批准していないことに対して、改めて被災地からの批判は高まるのではないでしょうか。
今日という日を、核兵器廃絶を国際社会に絶え間なく働きかけるという行動を改めて誓う一日にしたいものです。



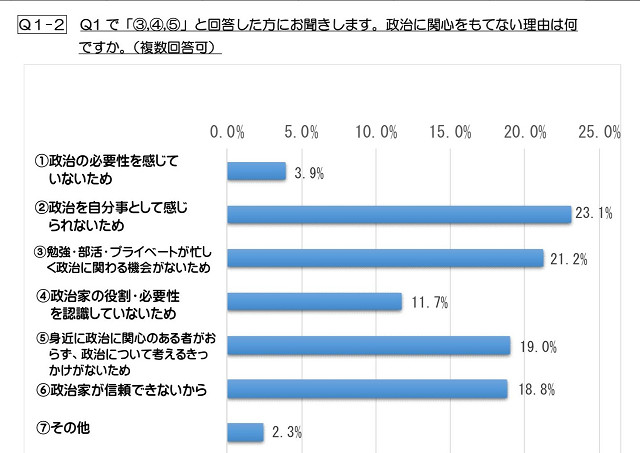
昨日、県明るい選挙推進協議会主催の「若者と議員の座談会」に出席させて頂きました。
この座談会も始まって以来、一回のみの欠席で、多分出席議員の中では最多出席回数になると思われます。
その間には、8年前に選挙権が18歳に引き下げられたことから、高校生の参加が多数になっていましたが、今年は大学生も多少増えていました。
議員側は、議員14名(県議9名、高知市議5名)の予定でしたが、一部欠席もありました。
3人の若者と1グループになって、まずは「どうすれば若者は政治に関心をもつの?」というテーマで意見交換、休憩後グループ替えをして自由テーマで意見交換をしました。
若者の政治への関心・無関心もそれぞれの背景によって違うが、自分の関心のある趣味や学校生活の中で、そのことが政治とつながっていないのか、何らかの形で必ずつながっているので、そこから自分事として捉えることができるようになるのではないかと投げかけさせていただきました。
また、若者からは、政治家を知ることで政治に関心を持つことにはなるので、政治家の方からも直接若者の中に飛び込んでいったり、SNSでの情報発信すべきとのアドバイスがありました。
また、他のグループでは「生徒会で、声をあげても、学校が取り上げてくれず、声をあげても変わらないということが、刷り込まれて、そのことが選挙で投票しても変わらないということで無関心につながるのではないか」ということなども出されていました。
グループ替えの後に取り上げたテーマは「魅力ある高知県にするためにはどうすればいい?(観光・産業振興)」などについて意見交換をしましたが、「観光キャンペーンで打ち出す『極上の田舎』は、若者にとって魅力あるイベントではないし、若者にターゲットをあてたレジャー施設や店舗などにはつながらない」ということをどのように見るかとの意見もあり、観光客は来るけど、若者は出ていくということにもなるのではないか、そこをどうマッチングするのかなど、なかなか面白い意見交換ができました。
また、他にも「介護・医療人材を確保できる給料が確保されるべき。このままでは、高齢社会を支えられなくなる。」という意見に対して「私はアルバイトをしても最低賃金。貯めて何かしようとならない。全部の仕事で給料はあげてもらいたい。」と返されたり、高校生同士の相互討論にもなりました。
若者の関心ある政治課題と議員がしっかりと向き合って行かなければと改めて考えさせられました。
| 8月3日「欠陥機オスプレイはすぐさま撤退・退役を」 |
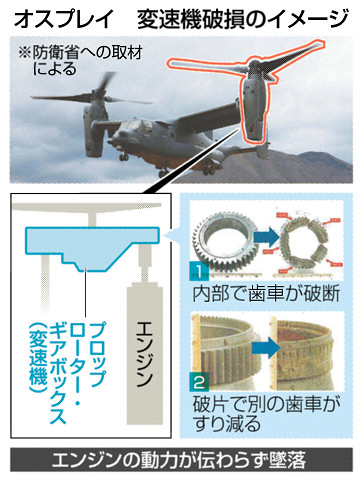
 鹿児島県屋久島沖で昨年11月、垂直離着陸輸送機CV22オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故で、米空軍は昨日事故調査報告書を公表しました。
鹿児島県屋久島沖で昨年11月、垂直離着陸輸送機CV22オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故で、米空軍は昨日事故調査報告書を公表しました。
ギアボックス内の歯車破断と操縦士の判断ミスという2点を原因とした墜落事故だと報告書は結論付けていますが、より深刻な問題は歯車破断であって、過去にもギアボックスの不具合が取り沙汰されており、構造的欠陥が指摘されるゆえんでもあります。
歯車が折れた原因が分からないままでは墜落事故が解明されていないに等しく、同 じような墜落事故が起きる可能性が残されており、本来ならば飛行が許されてはならないはずです。
今回の墜落事故につながった歯車破断の根本原因も特定できていないことも看過できないし、警報の無視は民間航空機では考えられず、乗員間に危機意識が欠落していたなど隊員教育の不徹底、全軍的なオスプレイ安全対策の不備などが指摘されます。
そのようなオスプレイの飛行を容認する日本政府の姿勢も疑問であり、構造的欠陥が明らかなオスプレイという欠陥機は、飛行経路周辺で暮らす住民や乗員の生命を守るためにも、すぐさま撤退、退役しかありません。
昨年12月議会で「自衛官の命を守る観点から、自衛隊へのオスプレイ配備の見直しを求める意見書議案」を提出し、多岐にわたる構造的欠陥を有し、死亡事故が多発してきた中で、まず何よりも運用する自衛官の命を危うくし、世界的にも導入が見送られ、調達コストが膨らんでいることからも、自衛隊へのオスプレイ配備・調達計画の見直す必要があることを求めた賛成討論を行いました。
今回の米軍事故調査報告書を見るにつけ、余計にオスプレイを運用する自衛官の命をはじめ、県民・国民の生命・財産を守るために、陸上自衛隊へのオスプレイ配備を抜本的に見直すよう求めていきたいと思います。
| 8月2日「文書偽装や再稼働詐欺ともいえる原電の敦賀原発は直ちに廃炉を」 |
 7月26日、原子力規制委員会が、日本原子力発電(原電)の敦賀原発2号機は、原子炉建屋の直下に活断層がある恐れが否定できないと結論づけ、再稼働の条件になる新規制基準に適合しないとの判断を示しました。
7月26日、原子力規制委員会が、日本原子力発電(原電)の敦賀原発2号機は、原子炉建屋の直下に活断層がある恐れが否定できないと結論づけ、再稼働の条件になる新規制基準に適合しないとの判断を示しました。
これで、原発の直下で断層が動けば深刻な事態になることから、新規制基準では再稼働は認められないことになり、敦賀原発2号機は事実上廃炉が決定的になったと言えます。
敦賀原発は200mほどの場所に「浦底断層」という活断層が走っており、もともと立地不適と言える場所でしたが、以前は断層評価が甘く、原電は浦底断層を活断層とみていませんでした。
しかし、その後の調査で浦底断層は約4700年前に活動した第一級の活断層であることがわかり、東日本太平洋沖地震の後に、浦底断層の運動に伴い動く可能性がある断層が原子炉直下にも達している可能性があることが明らかになり、改めて再評価を行うことになりました。
一連の審査会合では、原電は過去に国に提出した書類をあたかも最初から活断層ではないと評価してきたかのような文意に書き換えるなど、多数の偽装が見つかり、これでは審査できないと、審査が中断し、その後、規制委は審査を再開させたものの、その後も原電の書類には100箇所以上の間違いが見つかりました。
規制委はデータ管理や審査体制に問題があると、原電の社長を呼び出して資料を出し直すよう求め、その際に山中委員長は「これが最後だ」と述べ、誤りが続けば審査の打ち切りも示唆しました。
まさに、このことからも再稼働を強引に進めたい日本原電による文書偽装が行われていたとしか言わざるをえません。
原電の原発は全て停止しており、発電電力量は12年間ゼロでありながら黒字なのは、東電、関電、中部電、東北電、北陸電の電力5社が「基本料金」として原電に原発の維持管理費用などを支払ってきたからであり、東電などが赤字になっても発電ゼロの原電の黒字が続くという異常事態になっているのです。
大手電力5社は23年度に、944億円を基本料金として支払っており、このまま原電が敦賀2号機を「再稼働申請中」として、基本料金を電力に請求すると、消費者の電気料金が一切の電気を生まない原発のために年間400億円余りを原電に支払うことになり、「再稼働詐欺」とも言われています。
欠陥工事が明るみに出た東海第二と合わせて、毎年900億円を超える電気料金を吸い上げるためだけに存在し維持され続ける原発は、一刻も早く2基とも廃炉にするべきなのです。
この原発は、今後動かすことはできなにもかかわらず、この審査会合の結果を受けて、原電の村松社長は「廃炉は考えていない」として、さらに審査を求める考えを示しているが、規制庁は、これを絶対認めてはなりません。
| 7月31日「『虎に翼』を観ながら、人権問題を我が事として考える視聴者に」 |
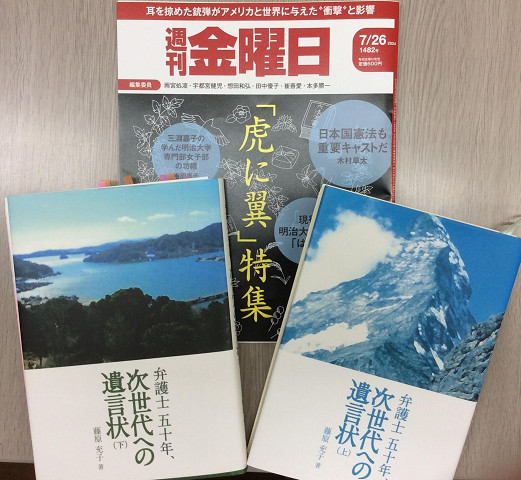 かつて、NHKの朝ドラを見ることは久しくなかったが、「らんまん」を必要に迫られて見始めてから「ブギウギ」と時間のある時には、見てきました。
かつて、NHKの朝ドラを見ることは久しくなかったが、「らんまん」を必要に迫られて見始めてから「ブギウギ」と時間のある時には、見てきました。
そして、今回の「虎に翼」は、自分自身いろいろと考えさせられることも多く、相当入れ込んでいるように思います。
全国で、防災関係を通じてお世話になっている弁護士の方のFBなどを見ても、皆さん関心をもって観られているように思います。
そして、先週手元に届いた「週刊金曜日」は、憲法学者の木村草太さんが、ドラマではどう憲法が描かれているのかを中心に語ったものをはじめとした「虎に翼」特集でした。
「虎に翼」は、女性法律家の先駆者である三淵嘉子さんをモデルとしたオリジナルストーリーで、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性が、困難な時代の道を切り開き、苦境に立たされた人たちを救うために奔走する姿を描いたものです。
とりわけ、木村草太氏は「虎に翼」第1回の冒頭シーンで、主人公の寅子が多摩川の河原で、新聞に掲載された新憲法を食い入るように読み、第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に夢中になっている姿が印象的だったと言われています。
このドラマを観ながら、県内初の女性弁護士でスモン病患者が製薬会社と国を相手取った「高知スモン訴訟」や、中国残留孤児約2200人が国に慰謝料を求めた集団訴訟の「高知訴訟」弁護団を率い、和解や国の責任を認める判決を引き出してこられた藤原充子弁護士(95歳)に、このドラマについて伺ってみたいなと思っていました。
昨日、丁度共に共同代表させて頂いている会議でお会いして、「先生、『虎に翼』は観られていますか」と尋ねたところ「もちろん観てますよ」とのお返事。
「戦災孤児の問題、障害者や在日朝鮮人差別の問題など人権問題のことがしっかりと取り上げられていますね。私は三淵嘉子さんともお会いしたことがありますよ。15歳ぐらい上だったかな。素晴らしい方で、皆さんの憧れでした。」と続けてくださいました。
「私たちの頃でも『女は』と言われて大変な時だったが、三淵さんの頃は、それはそれは大変だったと思いますよ。」とも、言われていました。
週刊金曜日の中で、木村草太氏は「敗戦を経て制定された日本国憲法には、『近代的憲法なら、どこの国でも書いてあること』と、『日本国憲法ならではの先進性を備えたこと』があります。『公権力を、憲法に基づいて運営しよう』という立憲主義や、『人が生まれながらに持つ権利を保障しよう』という人権主義などは、19世紀末には、広がっていました。14条のうち、『法の下に平等』というのは、すでに、広がっていたことですが、個々の属性を示しつつ、『差別されない』と宣言する憲法は、あまり多くありません。」と述べ、単に、「素敵な女性の一代記」というだけでなく、差別問題に焦点を当てるドラマになるのかもしれない、という期待が出たとのことでした。
まさに、ジェンダー平等が叫ばれながらも、ジェンダーギャップ指数は146カ国のうち118位で、選択的夫婦別姓も認められず、人種・民族に対するヘイトや障害者差別、部落差別の解消も図られないままであり、沖縄に対する差別などは国家的に行われていると言わざるをえません。
このドラマによって、第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを視聴者が我が事として捉えられるようになってもらいたいものです。
| 7月30日「最賃は『労働力の再生産を可能にする』生計費であるべき」 |
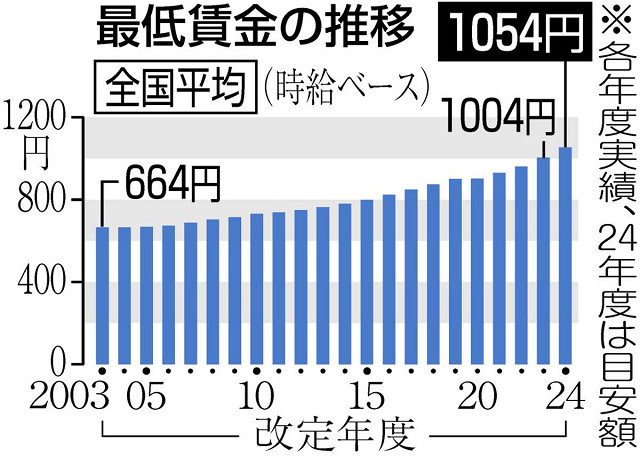
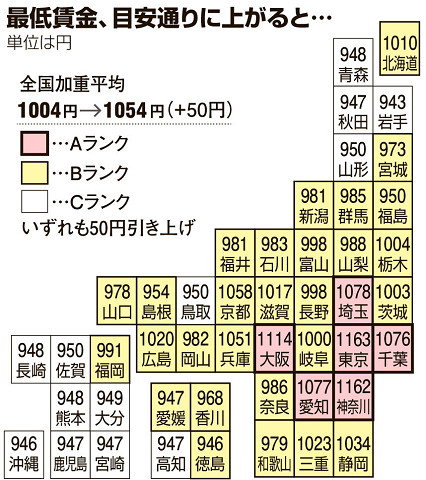 2024年度の最低賃金の全国平均が、現行より50円(約5%増)引き上げて1054円とする目安額を取りまとめられ、上げ幅は23年度の43円を上回り過去最大で、時給額も最高額となりました。
2024年度の最低賃金の全国平均が、現行より50円(約5%増)引き上げて1054円とする目安額を取りまとめられ、上げ幅は23年度の43円を上回り過去最大で、時給額も最高額となりました。
都道府県の区分別の上げ幅には差がつけられていないので、高知は947円が目安となります。
50円の引き上げは、今春闘の賃上げ状況や物価高を考えれば、最賃近くの時給で働く非正規雇用者にとっては当然の額ではあるが、それでもフルタイムで働いて年収は200万円程度にとどまり、厚労省によると、昨年度の最賃引き上げでも暮らし向きが「変わっていない」と答えた労働者は63.4%に上り、最賃の継続的引き上げが必要なことを示しています。
中小零細企業では、原材料や人件費の上昇分を取引価格に転嫁できない状況が指摘される一方で、人手不足感が強まり、業績が改善しない中でも人材確保策を迫られています。
今後、目安額を参考に各都道府県の審議会で議論が始まるが、23年度改定では人材の流出に危機感を持つ24県が目安額を上回る答申をしており、地域の実情に応じた引き上げ額の決定が今年も期待されます。
地域間での労働者獲得競争ではなく、海外との格差拡大も大きくなる中で、最賃が低いままでは、日本で働きたいと思う外国人労働者も少なくなると思われます。
中小・零細企業にとって、50円の賃上げが大変なことは理解できるものの、最低賃金とは労働者に支払うべき金額の最低限であり、労働者の生計費なのであり、使用者側は支払い能力を強調するが、払える金額を労使で話し合う通常の賃金交渉とは性格が異なっているのです。
「ルポ 低賃金」の著者東海林智さんはFacebookで、次のように書かれています。
大幅な引き上げかどうかが議論が分かれるところで、簡単に同意できないが、「企業の支払い能力」ではなく、まずもって、「労働者が人間らしい生活ができる賃金なのか」が重要だ。
この最賃で、労働者がまともに、人間らしく暮らせるのかが最も重要なはずではないか。最賃は「労働力の再生産を可能にする」賃金水準を決めるものだ。
だからこそ、海外の最賃は生計費で決まる。支払い能力がことさら強調されるいびつさはない。労働者が労働力を再生産できないような賃金では、企業活動だってままならないからだ。
シンクタンクの人間が「賃上げにふさわしい生産性の向上が求められる」としたり顔でおっしゃるが、その前に言ってほしいな「大企業は公正な取引をしているのか。利益を貯め込んでいたら経済はまわりませんよ」と。なんなら「吐き出せ。その不当な蓄えを」(カイジ風に)ぐらい、言ってくれよ。
生計費で言ったら、今年の最賃の1054円(加重平均)は、到底足りないねぇ。韓国の最賃は10年でほぼ倍になっているね。25年には1160円だって(現状1103円)。
同じぐらいやろうと思ったら1700円(東京でね)にはなっていないとね。なにより、韓国の最賃は全国一律。日本の現状の最賃は1004円ではなく、893円(岩手)だから。全国一律、1700円って言って良いんじゃないのか。もう、1回言おう。最賃は生計費で決めよう。(抜粋引用終了)
人間らしく暮らせる「労働力の再生産を可能にする」最賃を求めて闘い続けましょう。
| 7月29日「高知大学図書館『崎山ひろみ文庫』に旧満州の歴史を訪ねて」 |
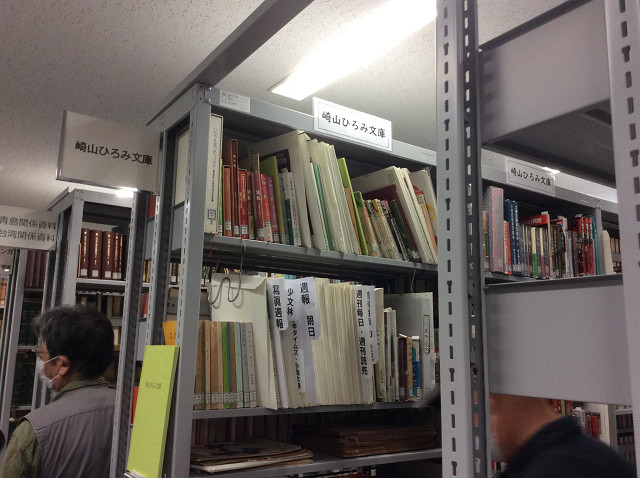
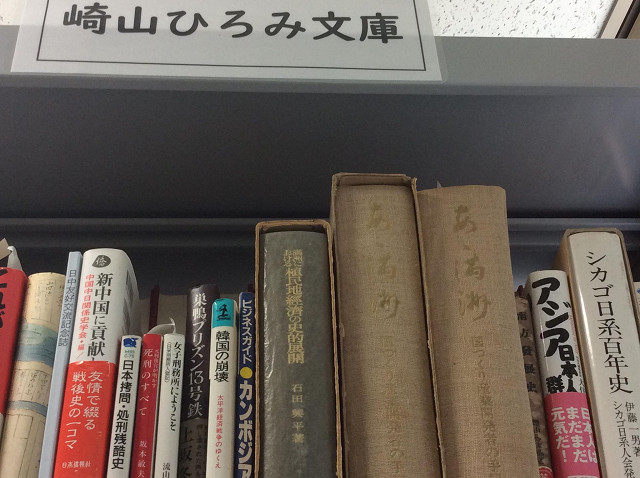
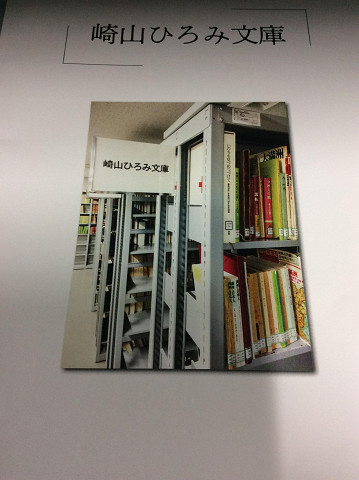
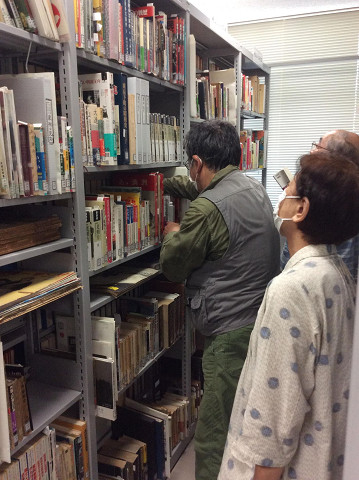
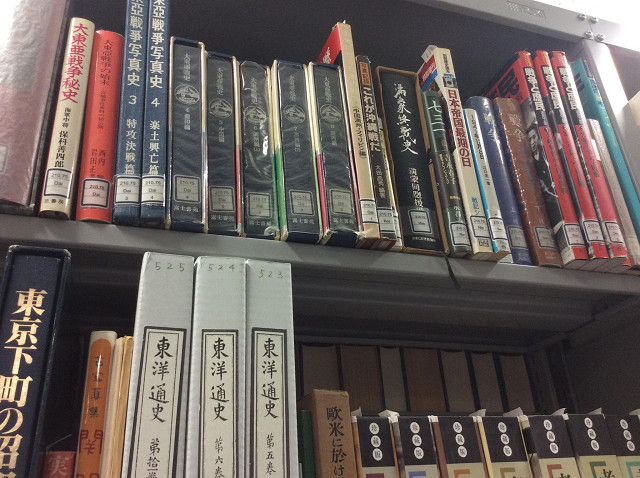
昨日は、ご案内の頂いた第6回満州の歴史を語り継ぐ集いに、所用があって参加することができなかったため、今朝から行われた高知大学図書館内にある「崎山ひろみ文庫」の見学会に伺ってきました。
2年前に亡くなった母は、崎山ひろみさんとは、同じ旧満州からの引き揚げ者ということで、随分と親しくさせて頂いておりました。
これまでも機会があるたびに、満州開拓団のことや戦時中の様々な課題についての学びの場にお声掛けをいただいておりました。
崎山ひろみさんが、戦後長い時間を経て散逸が危惧される「満洲国」関係の資料収集に尽力されており、本来なら県としてその関係資料・年の保管に務めるべきなのですが、資料は歴史民俗資料館に保存し、図書を中心に旧満洲関係の書籍約1300冊を高知大学図書館に寄贈し、「崎山ひろみ文庫」と命名され、広く教育・研究の資料として活用されています。
しかし、ご自宅にも、まだ多くの資料書籍があるとのことで、今後も計画的に保管が進められることが望ましいと思われます。
いずれにしても、これらの書籍、文献に学ぶ学生や県民が、これからの平和の担い手として育つことを願いつつ、文庫を後にしました。
| 7月27日「本県の20歳以下の自殺者は平成以降最多」 |
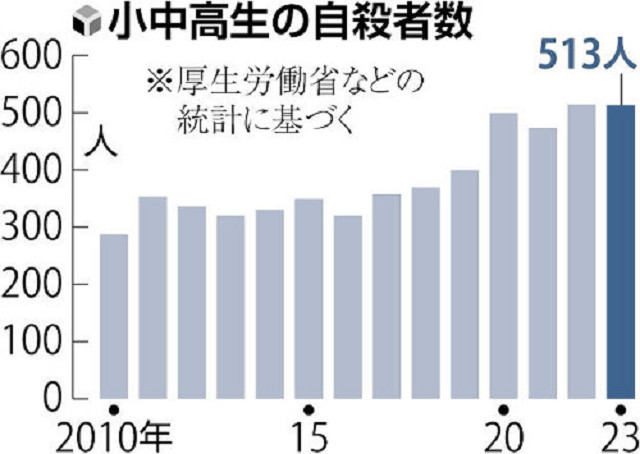 2023年の自殺者数のうち、小中高生の自殺者数は、過去最多だった22年の514人に次ぐ513人で、コロナ禍以降、子どもの自殺者数が高止まりしている状況にあることをこれまでも取り上げてきました。
2023年の自殺者数のうち、小中高生の自殺者数は、過去最多だった22年の514人に次ぐ513人で、コロナ禍以降、子どもの自殺者数が高止まりしている状況にあることをこれまでも取り上げてきました。
厚労省によると、小中高生の原因・動機別の分析では、「学校問題」が最も多く、261件で、「健康問題」が147件、「家庭問題」が116件と続いており、詳しく見ると、学校の問題のうち、「学業不振」が65件、「進路の悩み」が53件、「いじめ以外の学友との不和」が48件となっているとのことでした。
本県では、2023年に県内で自殺した20歳未満は7人で、平成以降で最多となったことが、県や支援機関でつくる自殺対策連絡協議会で23日に報告されています。
県全体の自殺者は前年より10人減って121人で、人口10万人当たりでは18.3人となり、全国で15番目に多くなっています。
2004年に平成で最多の256人になり、10年以降は200人を下回り、17年に最少の109人に減ったが、18年から再び増えておおむね120~130人で推移しているとのことです。
20歳未満はこの20年間、ゼロの年はなく、23年は前年より3人増えて7人に上り、過去10年間の動機では、学校問題36.4%、家庭問題9.1%、健康問題6.1%などで、51.5%は不明となっています。
県は「子どもの自殺が高止まりしている」とし、自殺リスクのある子に応じて学校などに派遣する専門家チームを年内に立ち上げる方針を決め、計画では、学校などが自殺リスクがある子どもを確認すると、同センターに連絡し、派遣された専門家が教員らへの助言や支援態勢の調整を行い、早期の対応を目指す事になります。
自殺対策に取り組むNPO法人「ライフリンク」の清水康之代表は、子どもの自殺についても「非常事態」とし、「子どもの命を守る取り組みを緊急的に進める必要があり、各自治体で学校と行政の連携を強化しなければならない」と指摘されていますが、本県においては、年内にモデル地域を選び、全県に広げる方針としており、報道では精神保健福祉センターの山崎所長は「いろんな機関が関わり、生きづらさを抱える子どもを地域で支える体制をつくりたい」と述べられています。


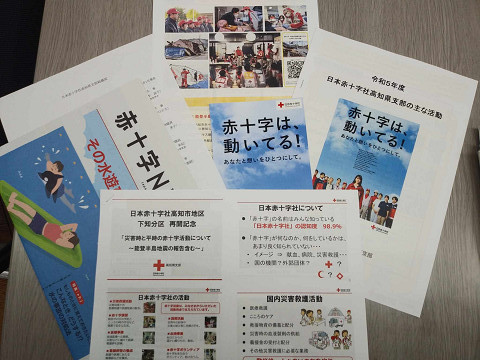
昨夜は、「日本赤十字社高知市地区下知分区再開記念講演会」を開催しました。
下知地区で日赤活動を長らく担って頂いた方のご事情で、活動が少し休止していた「日赤下知分区」の活動を再開することになりました。
休止していた分区の再開ということで、日本赤十字社高知県支部高知市地区吉岡章副地区長、日本赤十字社高知県支部影山真人総務課長が来賓としてお越しいただき、皆本隆明分区長の開会挨拶に続いて、地域共生社会の中での日赤の役割や日赤の組織などについてお話を頂きました。
そして、記念講演としては、日本赤十字社高知県支部中野大智事業推進係長から、「災害時と平時の赤十字活動について~能登半島地震の報告含め~」と題して、講演して頂きました。
お話の中では、「赤十字」の認知度は98.9%と言われましたが、下知地区においては、まだまだでなおかつ「分区」という組織がどのようなものかという質問もあったように、組織は再開したけど活動の再開までは、もうひと頑張りもふた頑張りもしなければなりません。
その活動の実戦部隊でもある奉仕団の再結成までには、もっともっと地域のお力が大事になります。
災害に「も」強くなる下知のもう一つの備えとして、「日赤活動」を再開することは、とても大事なことだとの思いで、これから地域で広げていくことが重要で、日赤活動も下知地区の平時の支えあいと地域防災力の向上につながるものです。
| 7月24日「『選択的夫婦別姓』これでも割れる自民党内」 |
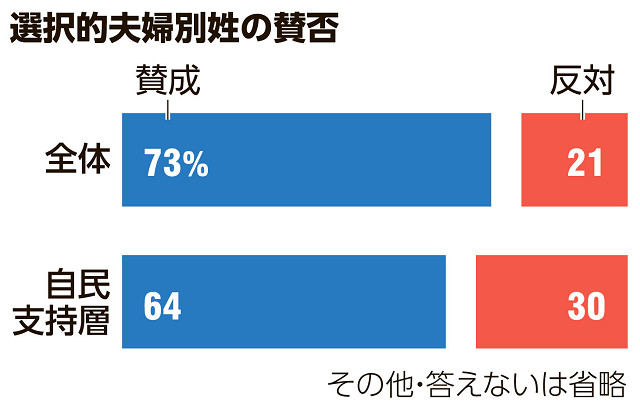 朝日新聞社が20、21日に実施した全国世論調査(電話)で、夫婦が名字を同じにするか別々にするか、法改正して自由に選べるようにする「選択的夫婦別姓」についての設問では、「賛成」が73%で、「反対」の21%を大きく上回ったことが、昨日報じられていました。
朝日新聞社が20、21日に実施した全国世論調査(電話)で、夫婦が名字を同じにするか別々にするか、法改正して自由に選べるようにする「選択的夫婦別姓」についての設問では、「賛成」が73%で、「反対」の21%を大きく上回ったことが、昨日報じられていました。
2021年4月に同様に質問した際には「賛成」67%、「反対」26%で、当時より賛否の差が広がったことも明らかにしています。
自民支持層の中でも、選択的夫婦別姓に「賛成」が64%、「反対」が30%と、「賛成」が「反対」の倍以上になっています。
6月10日には、経団連が、夫婦別姓を認めない今の制度は、女性の活躍が広がる中で企業のビジネス上のリスクになりうるとして、政府に対し「選択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう求める提言が出されていたにも関わらず、自民党は一か月も過ぎた18日に、「選択的夫婦別姓」を巡る党内議論をやっと再開したとのことです。
そして、未だに、「国民的な議論が必要だ」「賛否が分かれるから」と推進派と慎重派が割れる自民党を国民がどのように受け止めていると思っているのでしょうか。
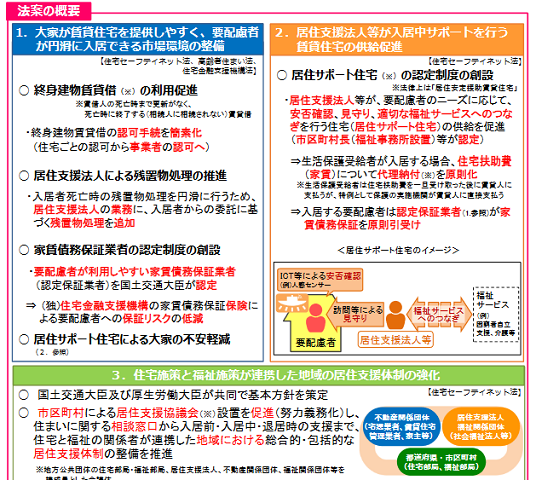 以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げてきましたが、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。
以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げてきましたが、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。
その際に、知事も「安心してつないで頂くように、断らない相談窓口の設置など、市町村の包括的な支援体制の整備や、地域の見守りの仕組みづくりに取り組む。こうした地域レベルでの取組に加えて、県庁でも土木部と子ども・福祉政策部の両部で一層連携を強化して、要配慮者の住まいの確保を推進していく。」との考えを示されていました。
しかし、国段階でも、入居者の希望に合う間取りや家賃の物件が少なく、十分に活用されているとはいえず、新たに法改正によって、「居住サポート住宅」の仕組みが設けられ、安否確認など生活支援サービスを一体で提供する物件をあらかじめ認定することが、来年秋にもスタートすることが想定されているようです。
課題は、高齢者の幅広いニーズに対応できる支援法人をいかに確保するかだが、地域からは担い手不足を懸念する声が上がっているようです。
今回の法改正で、国土交通省だけでなく厚生労働省も所管に加わり、自治体レベルでも縦割りを排し、施策の実効性を高める努力が求められることになるが、本県のように取り組んできたところでも、まだまだ十分な成果があがっておらず、政府と自治体が連携して住まいのセーフティーネットを強化していくことが求められます。


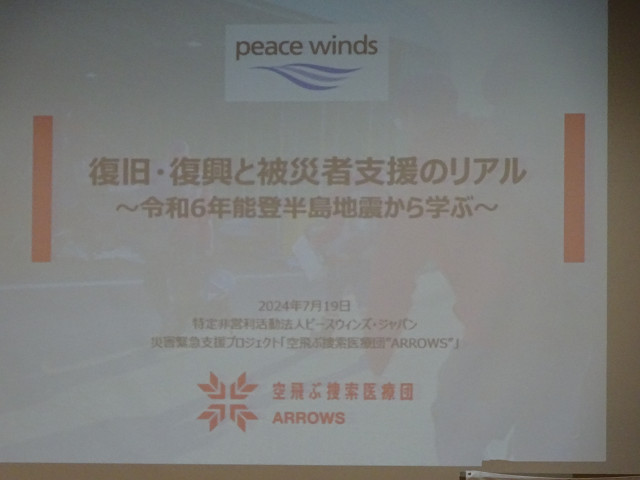
19日夜の高知市防災人づくり塾第4回講師は、日ごろから高知・下知が大変お世話になっているピースウィンズジャパンの国内事業部次長橋本笙子さんでした。
今年に入ってからは、1月1日の能登半島地震以来被災地の珠洲市を拠点にほとんど被災地支援で活動されています。
その橋本さんから「復旧・復興と被災者支援のリアル~令和6年能登半島地震から学ぶ~」と題して、90分のお話そして質疑応答含めた2時間は大変有意義なものでした。
これまでにも全国防災関係人口ミートアップ会議で何度か報告を受けておりましたが、改めて珠洲市の被災状況、そして、支援にはいられた橋本さんをはじめピースウィンズジャパンの皆さんが翌日から現地に入りいかなる支援を行ってきたのか、そして孤立・孤独を防ぎ災害関連死を減らすために今何を取り組んでいるのか。
「仮設住宅への家電支援」「仮設住宅・在宅避難所の見守り」「コミュニティ再建に向けて」「子どもたちの受け入れ」「給水支援」「ペット支援」などに取り組まれている様子をお聞きするにつけ、支援者としての覚悟を突きつけられました。
特に、支援に入られている珠洲市は高齢化率の高い地域で、1/3が後期高齢者でありながら、本来なら介護認定を受けて施設のお世話になっている方が地域の支えで在宅で暮らせるような地域コミュニティが維持されていたのが、被災でズタズタにされる状況になっているとのお話は、改めて平時の地域コミュニティの顔の見える関係の大切さを痛感させられました。
また、公的支援を受けられない準半壊や一部損壊という制度の狭間に追いやられる方々への支援の制度化は急がれなければならないことも重大な課題であることも切迫していることを強調されました。
これまでは、オンラインでの報告ばかりでしたが、久々に直接ご本人から聴かせて頂き、身の引き締まる思いがしました。
| 7月20日「9割が使用する『紙の保険証』を廃止するのか」 |
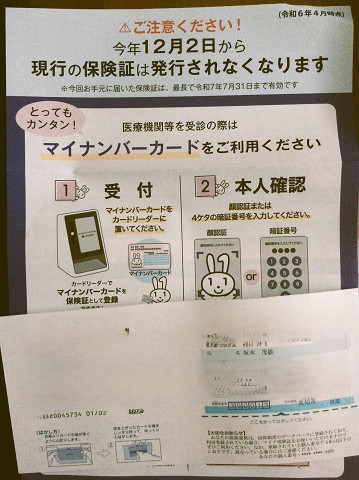
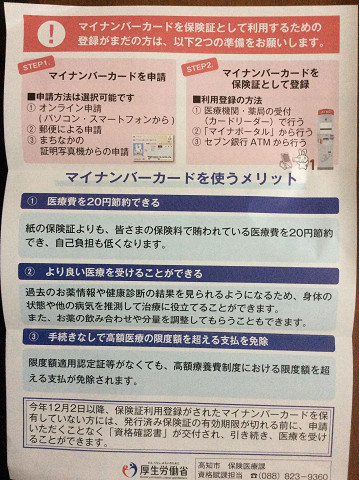

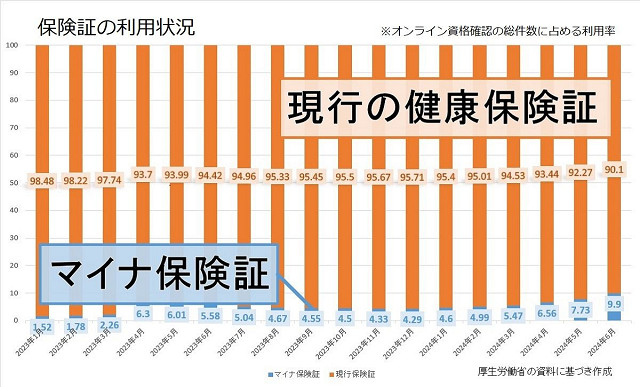
更新の紙の保険証が先日届きました。
同封されていたチラシには、「今年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります」「医療費を20円節約できる」「よりよい医療を受けることができる」「手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除」と書かれています。
そこまでしても、マイナ保険証の6月の利用率は9.9%で、政府は利用者が増えた病院や薬局への支援金を倍増するなどして利用拡大に躍起となっているが、いまだに9割以上が現行の保険証を利用しています。
しかし、医療現場からはマイナ保険証への一本化に不安の声が広がり、10万人超の医師・歯科医師が加入する全国保険医団体連合会の担当者は「既にカードリーダーによるマイナ保険証の認証でトラブルが頻発している」と明かし、同意手続きで何度も画面に触れることにストレスを感じる高齢者が多く、「このままでは12月から医療機関の窓口がパンクする」との危惧もあります。
あの手この手で税金も使い、なりふり構わず、マイナ保険証を推し進める政府のやり方に、憤りを感じる国民は多いと思われます。
6月の利用率について、保険証廃止まで残り5カ月で1割に届いていない現状をみるにつけ、無理矢理底上げしているとしか思えません。
そして、遂に厚生労働省は、介護保険の被保険者証とマイナンバーカードの一体化に向け、本格的な議論を始めたが、これもまた既に交付している介護保険証の取り扱いや、カードを保有していない人への対応が課題で、認知機能障害のある人にはハードルになることも大きな課題となると思われます。
それでも「紙の保険証」は、廃止するのでしょうか。
| 7月19日「能登震災は原発災害に対する『最後の警告』」 |
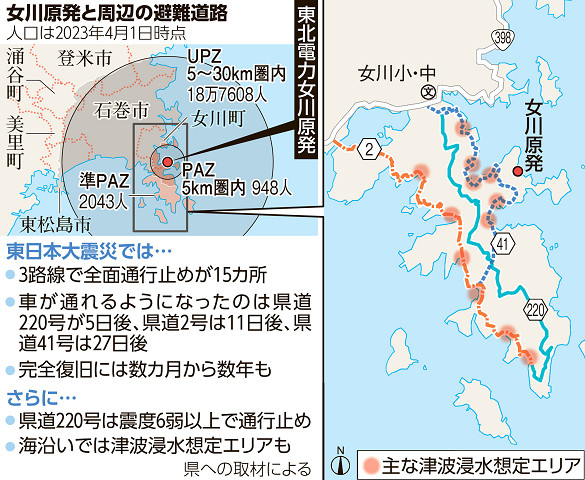
 東北電力が昨日、女川原発(宮城県)2号機の再稼働の時期を11月ごろに延期すると発表したことがマスコミで報じられました。
東北電力が昨日、女川原発(宮城県)2号機の再稼働の時期を11月ごろに延期すると発表したことがマスコミで報じられました。
再稼働の前提となる重大事故発生時の手順を確認する「シーケンス訓練」と、大規模な自然災害などに備えた「大規模損壊訓練」を巡る作業に遅れが出たためで、これまでは9月ごろを目指していましたが、2カ月後ろ倒しになるもので、再稼働時期の延期は3回目ということです。
しかし、何よりも近隣住民にとって、能登半島地震を踏まえた避難計画の不安を抱えたままの再稼働は許されるものではないと思われます。
女川原発は、太平洋に突き出た宮城県北東部のノコギリの歯のようなリアス式海岸が取り囲む約20キロの牡鹿半島の中ほどにあります。
半島から外に抜ける避難経路は計3本の県道で、山間部の1本は震度6弱以上で通行止めとなり、海岸線の2本は県が浸水を予想する複数のエリアを通ることになっており、実際、東日本震災では15カ所が全面通行止めになり、10日間孤立した地域もありました。
1月の能登半島地震では、道路の寸断や海岸部の隆起、家屋の倒壊が相次ぎ、半島の住民の避難や事故時の屋内退避の難しさが露呈しました。
東京電力柏崎刈羽原発の避難計画の検証委員を務めた環境経済研究所の上岡直見代表は「能登半島地震で、少なくとも半島では、当初の計画通り住民は避難できないことが証明された。自治体はその教訓を踏まえて避難計画を見直すべきだ。東北電力はその間、再稼働に踏み切るべきではない」と指摘されています。
能登半島地震の際、北陸電力は「原発は運転停止だったので安全」と発表したそうだが、地元の人は「運転中なら事故が起こりえた」と言うに等しいと感じており、しかも、福島第一原発4号機の核燃料プールの例もあり、停止中なら安全ということは、断じてありません。
原発再稼働の旗振りをした西村前経産相は地元で支持者に「能登の救援に時間がかかったのは、(珠洲に)原発を造らなかったからだ。造っていれば道路も整備していた」と言ったとの報道もあります。
珠洲に原発が造られていたら過酷事故の再現になった可能性もあるのに、そんな認識も想像力もない人々によって原発が推進され、再稼働に踏み出そうとしているのです。
能登震災は原発災害に対する「最後の警告」ということを受け止められる政府、電力会社であって欲しいと思わざるをえません。
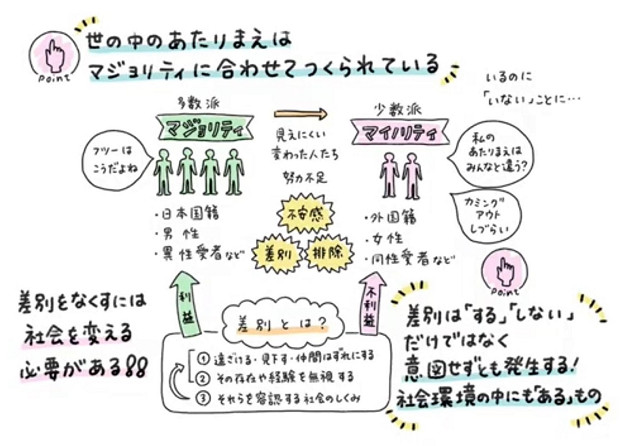 昨日は、「部落差別をなくする運動」強調旬間の高知市記念講演会で内田龍史さん(関西大学社会学部教授)の「部落差別の現在―部落解放への展望」を聴講させて頂きました。
昨日は、「部落差別をなくする運動」強調旬間の高知市記念講演会で内田龍史さん(関西大学社会学部教授)の「部落差別の現在―部落解放への展望」を聴講させて頂きました。
県主催の講演会で聴かせて頂いてから3年ぶりとなります。
最初に、「差別と社会―マジョリティ・マイノリティ関係」について、図にあるような「差別のメカニズム」をもとに、差別と社会についてお話しいただきました。
▼差別も社会現象のひとつであるが、では、人と人との関係によって成立する社会の成立要件は、
一定の規範・ルール・価値観(あたりまえ)が必要であり、それがないと安心して生活ができない。
▼社会にはさまざまなレベルがある。 たとえば、グローバル・国家・県・市町村・地域・企業・インターネット・学校・クラス・家族…
▼しかし、とある社会で通用するルールが、異なる社会では通用しないこともある。例えば、言葉や食べ物。
▼マジョリティ(社会的多数派・支配的集団)の立場からすると、マイノリティ(社会的少数派)の存在は、見ようとしなければ見えないし、見えていたとしても、自分たちとはちがう変わった人たち・変な人たち、という印象を持ちがちである。
▼マジョリティが、自分と同じような知識・経験・感情・価値観を持っていることが「あたりまえ」(社会の常識)だと考えているかぎり、「あたりまえ」ではない、「あたりまえ」のことができないと勝手に判断されるマイノリティの人びとは、理解不能な存在として認識されることになる。
▼社会の常識は、マジョリティの知識・経験・感情・価値観を中心に(マジョリティにとって都合の良いように)作られており、言い換えれば、通常、社会は、当該社会におけるマジョリティを優遇するように、偏って形成されている。
▼世界共通のルールとしての人権の実現については、実現に向けた調整と必要な変更が求められる。
そのような中で、「部落差別とは?」被差別部落に居住する人びと、そこにルーツを持つ人びと、部落と見なされた人びとに対して、日常生活や、結婚・就職などの場面において、不当に①遠ざけ、見下し、仲間はずれにすることによって(権力者や多数派が)利益を得る行為、あるいは②その存在や経験を無視すること、さらには③それらを容認する社会のしくみのことであることを指摘された上で、「部落差別の現在」がどのようになっているか、話されました。
▼「特に大きな現在の課題」として、①部落に対するマイナスイメージがインターネット上で拡散している。②情報化社会が進展するなかで、部落の人・場所などが暴かれている。③部落問題について「知らない」「認識がない」若者たちが全国的に増えている。
▼「インターネット上の部落差別」とは、次のようなイメージを持たし、拡散している。①みんながこわいわけではないのに「過度の一般化」で「こわい」イメージを植え付ける②みんながずるいわけではない「ずるい」イメージを植え付ける
▼自分の信念を肯定するための情報を探し出し、信頼できるものとする「確証バイアス((偏り・偏向)」が作用し、 情報化社会において、バイアスを確証する場が増加するし、否定的な情報の方が注意を向けやすく、記憶に残りやすいという「ネガティブ・バイアス」によって安全・安心・安定を脅かす情報は拡散しやすい。
▼「寝た子を起こすな」論で、差別に直面したり、差別に対する不安があっても、誰にも相談できずに、部落の人びとはだまらされ、だまっていると差別は表面化せず、差別はないように見えてしまう。
まさに、部落差別の現在を知ったうえで、「部落解放に向けて」取り組むべき課題について、話されました。
▼「差別を知って差別をする」「差別を知らないで差別をしない」「差別を知って差別をしない」「差別を知らないで差別をする」層がいる中で、「差別を知って差別をしない」層を育てるために、ワクチン・予防接種としての部落問題学習が必要。
▼差別解消のためには、突破口としての「接触理論」と「接触理論」の実践が必要、それは友だちは差別しない(可能性が高い)ということから言える。
▼差別克服のためには「学習(差別・人権)と経験(であい)が必要」「部落差別が生ずるメカニズムとその不当性を学ぶ」「人権概念について学ぶ」「であい(接触理論)を通じて偏見・差別を解消する」「差別の克服は社会の仕組みを変えること」などを踏まえて、「学びとであい」を重ねていきたいものです。
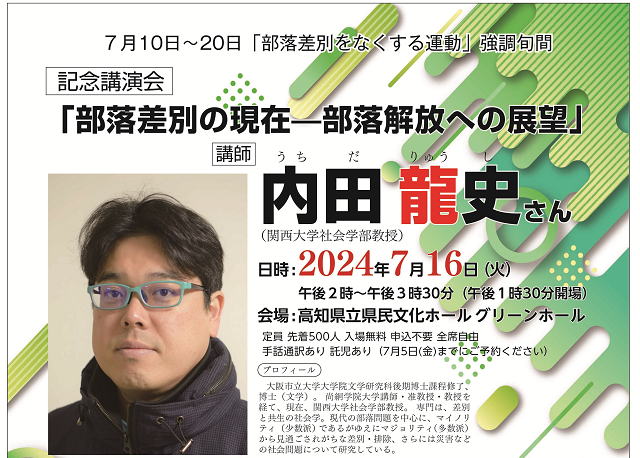 7月16日の今日、私もいよいよ「古希」となりました。
7月16日の今日、私もいよいよ「古希」となりました。
「古希」は、唐の詩人・杜甫が詠んだ詩「人生七十古来稀なり」に由来しています。
古希の「古」は「古来」、「希(まれ)」は「めったにない・珍しい」の意味で、「古来より70歳まで生きる人はまれなこと」という意味だそうですが、杜甫の時代ならそうかもしれませんが、今はまだまだ若造と言われるかも。
日々、学びつつ、地道な取り組みを重ねて行きたいと思います。
今日も、午後から「部落差別をなくする運動」強調旬間の記念講演会で内田龍史さん(関西大学社会学部教授)の「部落差別の現在―部落解放への展望」を聴講してから、春野に向かいます。
雨合羽持参の自転車で、往復し、帰ってきたら夜間の交通安全指導です。
まだまだ、老け込んでおられません。
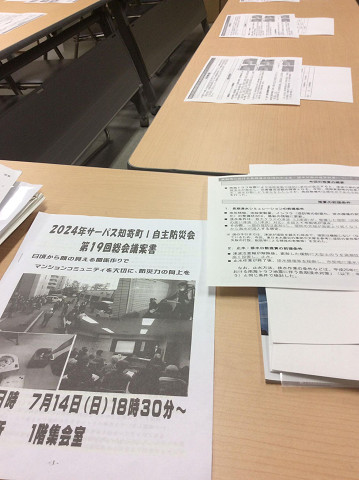
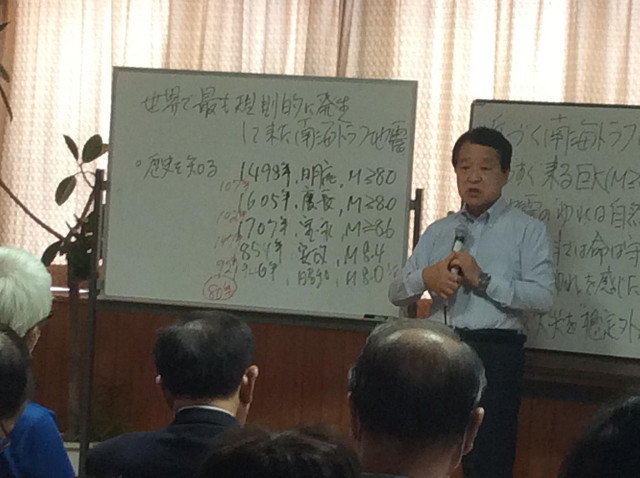


昨夜は、私の住むマンション、サーパス知寄町Ⅰ自主防災会第19回総会を開催しました。
参加者は委任状含めて70.9%の参加率でした。
昨年の事業報告を踏まえて、今年度の「防災避難訓練」の11月24日(日)開催。
防災講演会は、12月15日(日)「災害時の水は」のテーマで開催。
さらに、「災害時の安否確認や情報収集・連絡・伝達システム」「防災マップの改定」「避難行動要支援者対策」についてなどを確認しました。
しかし、何よりも今年の重点事業になりそうなのが、「南海トラフ地震対策・津波避難防災マニュアル」の7年ぶりの改訂です。
中でも、「災害時のトイレ使用マニュアル」の策定、「感染症対策」「在宅避難」の視点と最新の情報を取り入れての改訂に着手することになりますが、難事業になりそうです。
そして、今朝からは、下知地区減災連絡会やえもん部会主催の岡村眞先生の防災講演会とやえもん部会の海老ノ丸、御座、北金田、南金田防災会の避難所開設訓練の準備手伝い、見学、聴講をさせて頂きました。
初めての取り組みを準備されてきた皆さんお疲れさまでした。
100名ほどの参加がある中、準備から片付けまで、皆さんが協力されて手際よくされていましたが、今後も継続する中で、さらに顔の見える関係作りを重ねられることが期待されます。
そのことは、「近づく南海トラフ地震―前回から77年目にやっておくべきこと―」と題して講演された高知大学名誉教授で高知大学防災推進センター授岡村眞客員教も最後に話されていました。
「地震の揺れは自然現象、その揺れを災害にするのは人。地震発生時、広場や畑にいたら人は無傷。人の死は、木造三階建ての一階で発生。怪我をするのは寝室の重いタンス、居間の電化製品。」であることを知ったうえで、備えること。
「1分以上の長い揺れを感じたら、それは海溝型地震 (南海トラフ地震、東北地方太平洋沖地震など)まもなく高い津波が沿岸都市や集落を襲う。揺れが止んだら高いところへ避難。」するために、その場所を確保しておくこと。
「水と食料で命は守れない。それらは地震と津波から助かった人が使うもの。」ということを肝に銘じておくこと。
「1メートルの津波に遭遇した99.8%が死亡 (東北)。津波は車や瓦礫の流れ。」
「この地域では、津波火災を「想定外」にしない。」ことも想定される災害リスクであります。
先生の話は、地盤は高知市内で最悪の弥右衛門地区を選択して住まわれている方に対する戒めのメッセージであったように思います。
だからこそ、先生が指摘した過去の災害の歴史に学び、「2026年」かもしれないX-dayを迎えるための覚悟をし、明日地震が起きてもいいような準備をされることが会長の閉会挨拶に込められていました。
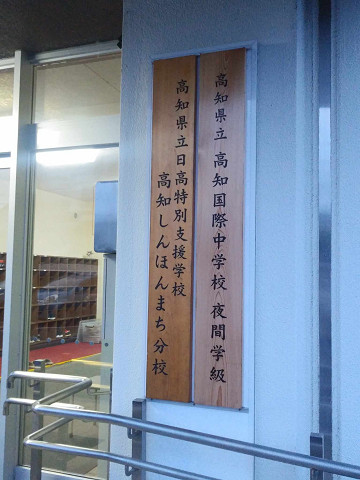
 7月10日に「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」のお誘いで、高知国際中学校夜間学級を訪問させて頂きました。
7月10日に「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」のお誘いで、高知国際中学校夜間学級を訪問させて頂きました。
学級開設以来、3度目になる訪問で、今春一期生4名の卒業を見送る中で、この4年間の「夜間中学」の歩みと生徒たちの「声」に学ばせて頂くことの多い90分間でした。
意見交換させて頂いたお二人ともの真摯な学びの姿勢と意欲に感心させられました。
また、分からないことをすぐ先生に尋ねられる関係性、登校するのに足が重くても後ろから背中を推してくれる人がいて、登校すると分からないことが多くても楽しいと感じられる学習環境が維持されていることが、学びの継続につながっていることも感じさせられました。
異年齢、多様な学生さんがいる中で、授業をとおして、先生も普段目の当たりにしたことのないような生徒たちの気づきが生徒の声にあるとすれば、学生の先生ともっと話せる機会があればとの声に向き合うことも大事なことであることを痛感させられました。
開設の際にも議論になっていたが、入学時期については、昨年検討されて入学時期の一律4月の見直しがされて4月から9月までの途中で、入学の機会も確保できて、今年度は6月入学生が学んでいます。
この3年間で、課題の解決に向けた尽力がされたり、10代の生徒も入学する中で、新たな課題とも向き合う必要性があるなか、一人ひとり個性に満ち溢れた中学生たちの声に寄り添う「学び直しの場」であって欲しいと改めて思ったところです。
そして、教頭先生の「ここには教育の原点がある」と仰っていたことに、もっともっと学び直しをしたいと思われている方々に、ここで学んでもらいたいと思うところです。
そのためにも、一緒に訪問した市議さんからは「学び直しをしたいと思っている人に、この学校の存在を知ってもらえるようなとりくみ」を支援していきたいとの感想もある中で、どのようなアプローチの仕方があるのか、しっかりと考えていきたいものです。
| 7月12日「沖縄県民の人権を守るためにも日米地位協定の抜本的見直しを」 |
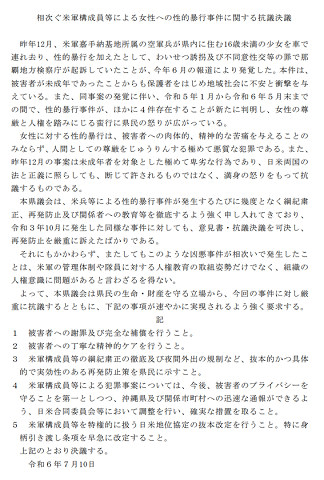
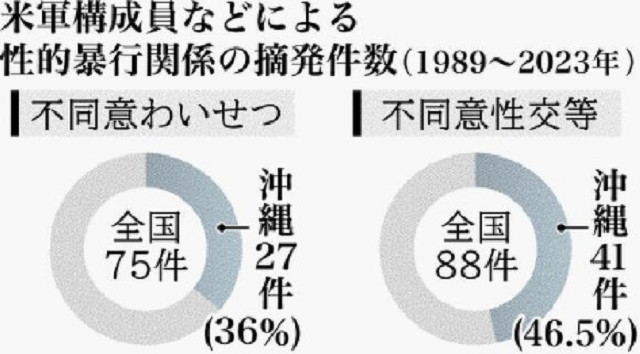 沖縄県内で相次いだ米兵による性暴行事件で、県議会は10日、米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全会一致で可決しました。
沖縄県内で相次いだ米兵による性暴行事件で、県議会は10日、米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全会一致で可決しました。
決議や意見書は、相次ぐ米兵による事件を「被害者への肉体的、精神的な苦痛を与えることのみならず、人間としての尊厳を蹂躙する極めて悪質な犯罪で、組織の人権意識に問題があると言わざるを得ない」と厳しく批判し、「満身の怒りをもって抗議する」と訴え、下記の要求が盛り込まれています。
1 被害者への謝罪及び完全な補償を行うこと。
2 被害者への丁寧な精神的ケアを行うこと。
3 米軍構成員等の綱紀粛正の徹底及び夜間外出の規制など、抜本的かつ具体的で実効性のある再発防止策を県民に示すこと。
4 米軍構成員等による犯罪事案については、今後、被害者のプライバシーを守ることを第一としつつ、沖縄県及び関係市町村への迅速な通報ができるよう、日米合同委員会等において調整を行い、確実な措置を取ること。
5 米軍構成員等を特権的に扱う日米地位協定の抜本改定を行うこと。特に身柄引き渡し条項を早急に改定すること。
沖縄では昨年以降、米軍嘉手納基地所属の空軍兵や在沖海兵隊員らによる性暴行事件が5件起きていたことが6月以降に発覚し、外務省や県警、那覇地検が被害者のプライバシー保護などを理由に情報を県に伝えていなかったことも問題となっています。
全国の米軍専用施設の7割が集中する沖縄では、事件や事故のたびに日米地位協定の障壁があらわになっています。
近年は被害者保護がより重視される中、特に性犯罪事件は公表されないケースが全国でみられているが、米軍関係の事件や事故は、自治体にとって住民の安全に直接関わる情報であり、日米合同委員会は1997年、米側と日本政府、県などの通報経路を整備した際、「在日米軍に係る事件・事故についての情報を日本側関係当局、及び地域社会に対して正確に、かつ直ちに提供することが重要であると認識する」と合意しているだけに、米軍構成員等を特権的に扱う日米地位協定の抜本改定は焦眉の課題であります。
日米地位協定の見直しについても前向きでない政府の姿勢を改めさせる闘いが急がれます。
山本章子琉球大准教授は、「再発防止には、米軍が夜間外出制限や飲酒規制をするしかない。米兵事件は飲酒に起因するものがほとんどだ。東京にいる役人や政治家は『米兵が集まる所に行かなければ事件は起きないのに』とでも思っているのだろう。その考えは、沖縄の実態を何も理解していない。地元住民は、飲食店や公園、アルバイト先で、いやが応でも米兵と接触しながら暮らしている。政府が沖縄に米軍基地を集中させている以上、被害や日米地位協定による不平等な扱いは、政府の責任で改善を求め続けるべきだ。そうした姿勢が見えなければ、沖縄の人たちの怒りや不信はなくならない。」と、再発防止の政府の本気度が見えないと強く非難されています。
| 7月11日「改正されても自民党の裏金体質は変わらない」 |
 6月定例会で、自民党派閥の裏金事件を受けた「政治資金の高い透明性の確保を求める意見書」が自民党・公明党から提出され、25人の賛成多数で可決されました。
6月定例会で、自民党派閥の裏金事件を受けた「政治資金の高い透明性の確保を求める意見書」が自民党・公明党から提出され、25人の賛成多数で可決されました。
一方、私たち県民の会、共産党で提出した「企業団体献金禁止など、政治資金規正法の抜本的な改正を求める意見書」は10人の賛成少数で否決されました。
自民党会派らの意見書は、6月成立の改正政治資金規正法では、その標題にあるように、「政治資金の高い透明性の確保を求める」ことは、改悪法制度のもとで、とても具体化できるものとは思えないことは明らかです。
先日、購入した月刊「世界」8月号には、裏金事件を表舞台に引っ張り出した上脇博之神戸学院大学教授の「改正されても自民党の裏金体質は変わらない」との記事がありました。
まさに的を射た指摘ばかりで、このことを自民党の皆さんは自覚できない限り、政治資金の高い透明性の確保を求めたり、国民の信頼回復はできないことを肝に銘じるべきではないかと思うところです。
上脇氏は「今回の法改正には何ら評価できる点がなく、後退している点さえもあるので、失望しています。」と述べ、「そもそもこの話の出発点は、自民党の各派閥が組織的に裏金を作っていたと言う、動かしようのない事実です。当然、裏金が作れなくなる方策を講じた法改正にならなければならないのに、全くそうなっていない。裏金の元凶である企業・団体献金や、企業・団体によるパーティー券の購入は禁止されず、『合法的な裏金』とも言える政策活動費も存続します。悲しいかな『今後も裏金を作り続けます』と宣言するような内容になってしまいました。」と断じています。
そして、そうなったのは「どうしても裏金をつくりたい"泥棒"に法律をつくらせているのですから、当然の結果なのかもしれません。」と厳しく指摘しています。
それでも、上脇氏の「何より大切なのは、あきらめないことです。主権者のための真の政治改革が成し遂げられるまで、今後も活動は続けていきます。」との決意に、我々も諦めずに闘い続けなければと考えさせられるばかりです。
| 7月10日「医療センターでも、周産期医療体制の負担増に四苦八苦」 |
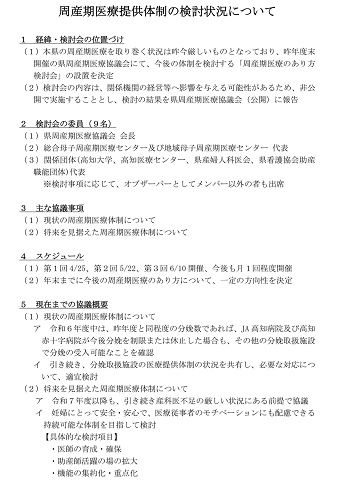
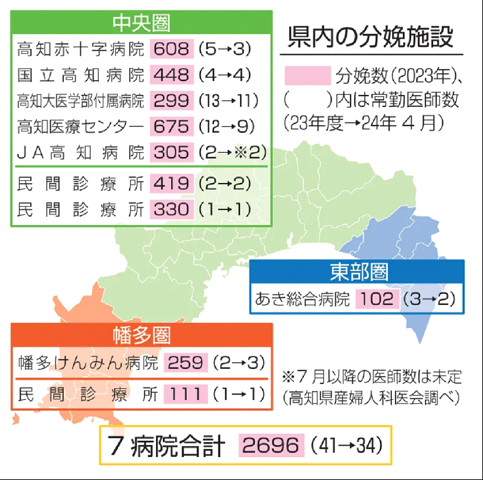 昨日は、県・市病院企業団議会が開催され、企業団議会議員協議会では、経常収支が3億1200万円の黒字となる2023年度の決算見込みが報告されました。
昨日は、県・市病院企業団議会が開催され、企業団議会議員協議会では、経常収支が3億1200万円の黒字となる2023年度の決算見込みが報告されました。
新型コロナの5類移行で関連補助金が前年度から約18億円減少したものの、入院と外来の患者数はいずれも前年度より増加し、高度医療の提供もあって診療単価が過去最高を更新し、医業収益は前年度を12億円上回り、過去最高の202億2800万円を見込み、4年連続の黒字となりました。
ただし、村岡企業長が提案説明で述べたように、過去最高の医業収益に関して「高度で専門的な医療の提供が着実になされた結果」ではあるものの、物価高騰や医師不足を挙げ「今後の経営は大変厳しくなる。経営改善を着実に推進する」ことは、求め続けられそうです。
また、提案説明でも言及された産科医師不足に限らず、医師の地域偏在や診療科偏在による医師確保の困難さが増す中、周産期医療の課題について質疑がされました。
「周産期医療のあり方検討会」の会長となられている林和俊副院長による「以前は月50~60件だったが、今は70~80件。今後は90件ほどになることも想定されている。四つの分娩室をフル稼働しているが、年900件ぐらいが限界だと思う。JA病院が受け入れてきた300件分娩件数は、高知大学病院と医療センターで請け負っていくことになる。」との現状をどう維持していくかが、求められることになります。
助産師、麻酔医との連携を図りながらも体制を維持していくとのことだが、分娩以外に婦人科手術や不妊治療も行っており、両人材も不足している中で、負担は確実に増えており、大変な状況は今後も続きます。
今後は、高知県としての喫緊の課題として、将来を見据えた周産期医療の体制検討について、「医師の育成・確保」「助産師活躍の場の拡大」「機能の集約化・重点化」などを具体的に検討されることが急がれます。
| 7月7日「西日本豪雨災害から学ぶ真備地区の取り組み」 |




2018年7月の西日本豪雨で大きな被害が出た岡山県倉敷市真備町で復興に向けて多様な役割を果たされているお二人が、この時期にはマスコミに多く取り上げられています。
そのお二人とは、川辺復興プロジェクトあるくの槇原聡美さん・鈴華さん親子、看護小規模多機能ホーム「ぶどうの家」の管理者津田由紀子さんで、昨年12月に下知地区の皆さんで訪問し、多くのことを学ばせて頂きました。
昨日の朝日新聞には、槙原さんたちが取り組んでいる毎年1回の効率的な避難の呼びかけにつなげるため、たすきを玄関先に掲げ、避難したことを知らせる訓練を実施し、今年6月の訓練では4回目で初めて参加率が上昇に転じ、「近くを散歩して地域を知ることも立派な防災活動。簡単なことを少しずつ継続する大切さを知ってほしい」との訴えが記事になっていました。
また、今朝の朝日新聞岡山地域版では、真備町では治水対策などハード面での大型事業が3月に完了し、安心感は増したが、住民自らによるソフト面での強化も必要だと津田さんは感じ、被災した民家を地域の交流施設に生まれ変わらせた「土師(はじ)邸」を活用し、「いざというとき、知らない人に声をかけられても動きにくい。普段から顔の見える関係づくりが欠かせない」と、被災を教訓に、地域ぐるみで人と人をつなぐ場所に育てていることが記事になっています。
私たちが、昨年の訪問で学んだのは、槇原さんのお話では、「あるく」の活動の柱になっている「帰りたくなる川辺、帰って良かったと思える川辺」を目指して、「安心して暮らせる街川辺」を取り組む中で、地域力や防災力を向上させることになっている日頃のまちづくりが、住民に「住みやすい街」として受け入れられているのではないかとのことでした。
そして、津田さんからは、「日頃から顔の見える関係を作っていないと避難ができない。例えばタイムラインをつくることは、避難計画ができたということだけでなくて、そのことを通じて顔なじみになる」ことで、「福祉の事業所は、利用者・家族とのつながりはあるが、地域とのつながりは弱く、つながりで、避難を促す声かけの仕方も違ってくる。何よりも、助けてと言い合える関係を作ることが大事。」で、そんな関係作りが「誰もが住みやすい街になり、そんな街が防災にも強い街である」ということにも共通していると考えさせられました。
様々な被害の顔が見える被災地から復興に向けて尽力された方から学ばせて頂くことは、貴重なことばかりです。

 昨日、県議会6月定例会は、2024年度一般会計補正予算など執行部提出の13議案と追加提出の人事議案2件を全会一致で可決、承認、同意するなどして閉会しました。
昨日、県議会6月定例会は、2024年度一般会計補正予算など執行部提出の13議案と追加提出の人事議案2件を全会一致で可決、承認、同意するなどして閉会しました。
補正予算では、教育活動の充実へクラウドファンディングを活用する「ふるさと母校応援制度」関連4551万円を削除する修正案が提出されましたが、少数否決のうえ、高知市と共同で運営する動物愛護センターの整備に向けた基本設計等4095万円を含む8646万円の一般会計補正予算が全会一致で可決されました。
請願議案のグリーン市民ネットワーク高知の皆さんから提出された「地震がくる前に伊方原発3号機の運転停止を求める請願」議案は、私から賛成討論をさせて頂きましたが、県民の会・共産党会派以外の反対多数で不採択とされました。
また、議員提出の意見書議案は、自民党派閥の裏金事件を受けた「政治資金の高い透明性の確保を求める意見書」に対して、私たち県民の会では共産党会派とともに、政党や政治家の資金管理団体への企業団体献金の禁止、政策活動費の即刻廃止、政治資金パーティーの全面禁止を求めた「企業団体献金禁止など、政治資金規正法の抜本的な改正を求める意見書」を提出しましたが、賛成少数で否決されました。
一方、自民会派が提出した意見書は、政策活動費の公開や監査が付則で検討項目となり、国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費の改革も課題だと指摘しながら、改悪政治資金規制法の順守や付則事項の早期実現などを国に求めるもので、多くの国民が納得していない改悪法に則ったものであり、このことによって国民の昌治に対する信頼回復につながるものではないということで、反対しましたが自公の多数て可決しました。
さらに、本会議でも議論のあった「改定地方自治法における自治体への指示権を乱用行使しないことを求める意見書」と「学校給食費無償化の早期実現を求める意見書」は県民の会、共産党会派で提出しましたが、少数で否決となりました。
今定例会では、2027年春の次期県議選を見据え、人口の減少や偏在を踏まえた定数や選挙区の在り方を検討する「議員定数問題等調査特別委員会」と若者の定着、中山間地域の持続的発展など、部局横断の視点で県施策をチェックする「人口減少対策調査特別委員会」を設置しました。
 熊本県南部の球磨川が氾濫し、流域を中心に67人(災害関連死2人含む)が亡くなり、2人が行方不明となった2020年7月豪雨災害は昨日、発生から4年を迎えました。
熊本県南部の球磨川が氾濫し、流域を中心に67人(災害関連死2人含む)が亡くなり、2人が行方不明となった2020年7月豪雨災害は昨日、発生から4年を迎えました。
球磨川流域は治水対策の工事が進む一方で、今も400人以上が仮住まいを続けられています。
仮設住宅の入居者内訳は建設型が190人(90世帯)、借り上げ型のみなし仮設が85人(45世帯)、公営住宅など137人(82世帯)だそうです。
熊本県は3月の復旧・復興本部会議で、仮設住宅の入居者全員について退去後の住まいの再建にめどが立ったと報告したが、土地区画整理や宅地かさ上げといった公共工事の影響で、再建を果たせる具体的な時期は見通せていないとのことです。
木村知事は「被災者の最後の一人まで、住まいやなりわいの再建を支援する。」と言われたそうだが、被災地には災害の爪痕が深く残り、復興はまだ道半ばの現状です。
自然災害がますます頻発化・凶暴化する中で、我々にできることは備えて、けして人災だった言われないようにすることではないでしょうか。
その際たるものが、原発災害であり、今日6月定例会閉会日に議案となる「地震がくる前に伊方原発3号機の運転停止を求める請願」の紹介議員として、本会議で賛成討論をし、そのことを訴えてきたいと思います。
| 7月2日「能登半島地震から半年、遅すぎる復旧・復興」 |
 能登半島地震が発生して、半年。
能登半島地震が発生して、半年。
余りに遅い、復興の現状を突きつけられています。
昨夜、ZOOM会議で、能登半島の被災地の状況を「音のない被災地・静かな被災地」と表現されている方がいました。
支援者も少なく、復興の槌音が聞こえない被災地から聞こえてくるのは、災害関連死が増えているという報道ばかりです。
地震の死者は281人に上り、52人は避難中のストレスなどが原因の災害関連死で、その申請は、すでに認定された人も含めて200人余りに上り、今後も被災後のストレスや疲れから体調を崩すなどして亡くなる人が増加することが懸念されています。
仮設住宅は、計画の7割が完成したものの、今も2000人以上が避難生活を送る。支援が必要でも避難所へ行かず、壊れた自宅に住み続ける高齢者も含め在宅避難者も多く、支援の手は届いているのだろうかと心配されます。
倒壊建物の解体作業も進んでおらず、公費解体の対象は約2万2千棟と推計されるが、完了したのはわずか4%で、調査・作業の人手不足に加え、半島の先端というアクセスの悪さが原因とされています。
奥能登地域では、100を超える事業所が廃業を決めたとされており、なりわいの再生も喫緊の課題です。
輪島市内には小中あわせて12校ありますが、地震の前と同じように単独で授業を続けているのは中学校1校だけで、残りの学校の多くは校舎などに被害を受けたり避難所として使われたりしているため、被害の少なかった3つの学校に集まっているなど、我慢を強いられている子どもたちの心のケアの重要性は増しています。
「創造的復興」を目標に掲げ、岸田首相は「できることはすべてやる」と述べているが、今までは全てやらなかったのかと言いたくなります。
孤立を防ぐなど、きめ細かな支援と対策の徹底を図りながら、止まったかのような時計の針を前に動かすために、政府・自治体はあらゆる措置を講じる必要があるのではないでしょうか。
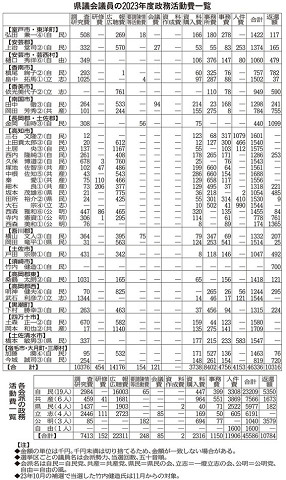 今朝の高知新聞朝刊を5時過ぎに読んで以来、7月1日付け高知新聞5面に、掲載されていた県議会議員の「政務活動費」の記事を見て、私の記載欄に誤りがあるのではないかと思い、もやもやしていたのですが、議会に出向いて確認したところ、誤りであったことが判明してホッとしました。
今朝の高知新聞朝刊を5時過ぎに読んで以来、7月1日付け高知新聞5面に、掲載されていた県議会議員の「政務活動費」の記事を見て、私の記載欄に誤りがあるのではないかと思い、もやもやしていたのですが、議会に出向いて確認したところ、誤りであったことが判明してホッとしました。
毎年7月には、県議会で政務活動費が公表され、高知新聞に記事が出るのですが、政務活動費で事務所費を計上したことないのに、今回は計上されているし、何か所かおかしいなと思って確認したところ、県議会事務局の提供資料に誤りがあったとのことでした。
「資料作成費」0円が36千円、「資料購入費」36千円が218千円、「事務所費」218千円が0円、「事務費」0円が2千円、「人件費」2千円が0円でした。
どのような訂正記事となるか分かりませんが、明日の新聞紙上で、訂正がされることだと思います。
私は、政務活動費の決算だけでなく、活動報告で自らの政務活動を報告することによって県民の皆さんと調査内容を共有することにも意義があると思っています。
内容を昨年は66頁でしたが、今回も結局67頁と多めで、お目通し頂くのは恐縮しますが、ご関心があればこちらからご覧いただけます。
これからも、日頃のこのホームページでの情報共有と政務活動調査報告書での共有で県政の課題理解を深めて頂けるよう努力するとともに、政務活動費を個人、会派ともに有効に活用していきたいと思います。
私個人の昨年1年分の154万円のうち、支出した分を除いて485,336円は返還しています。
| 6月30日「6か月を経た能登から首都直下・南海トラフ地震を見越して」 |
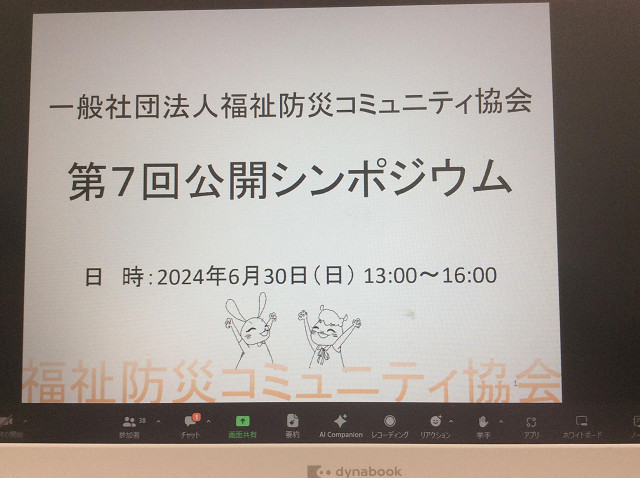
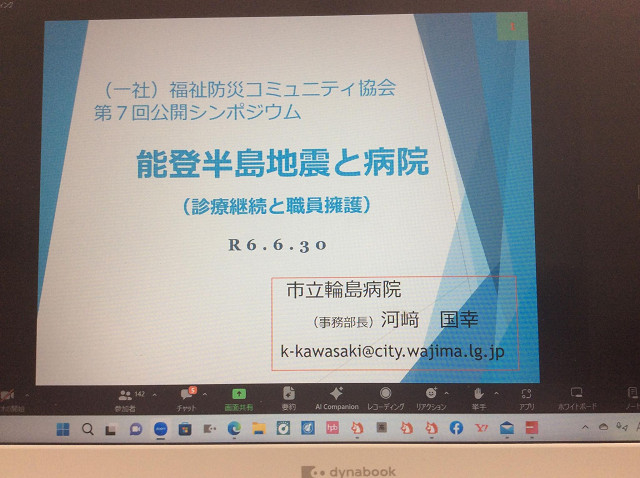

昨日の福祉防災コミュニティ協会第7回公開シンポジウム「災害福祉の現状と課題~能登半島地震から首都直下地震、南海トラフ地震を見越して~」にオンラインで参加しました。
浅野史郎会長(元宮城県知事)の基調講演「障がい者支援とは何か」に始まり、「能登半島地震と病院」について、河崎国幸市立輪島病院事務部長、「能登半島地震と障害福祉事業所」について寺田誠社会福祉法人佛子園施設長、「テルマエノトによる入浴支援」について国崎信江株式会社危機管理教育研究所代表からそれぞれの報告を頂き、跡見学園女子大学の鍵屋一先生から「大都市災害での障がい者支援の課題」の研究発表がされました。
また、三人の報告者をパネリストに「災害福祉をいかに前進させるか」ということでパネルディスカッションが行われました。
なぜ、能登ではこのような厳しい災害になったのかについて「アクセスの悪い地形」「行政・医療福祉事業者間がなかなか一枚岩になれなかった」「発災直後に支援者が入れないという異様な事態。そのことが発信の少なさにもつながり、早い段階で忘れられているという感覚さえあった。」「支援する側からすれば宿泊場所がないという点が大きかった」「メディアなど働き方改革のもと、入る被災地に制約があった。その分情報発信ができなかった。」「警戒心から、大丈夫、大丈夫という声で助けが求められなかった面があったのでは。」「登録ボランティアが入れないという事態が今に続いている」などの特徴が挙げられていました。
そのような中で、次に備えておくこととして「何ともならないトイレ問題、上下水道問題は、何とかしておかなければならない。」「心の問題として、顔見知りの人と災害時に一枚岩になれる繋がりを事前に作っておく」「孤立をどうやって防ぐか」「避難所から仮設という段階で、地域が分断されないように、輪島市では、抽選せず自治会ごとに入居させていたが、今後これが後戻りしないように。仮設住宅の中の集える場が必要。」「シンプルに耐震化。建物だけでなく非構造部材も含めて。」「ハードルが高いかもしれないが地域を越えて逃げるという判断もできるように」「被災地に支援に行ったときに繋がれる事前のつながりが大事」「国・自治体の支援の仕組みをアップデートする」「トイレトレーラーのネットワークをさらに、広げておく」などなど、次に備えるために生かす教訓について提起してくださいました。
備えることの中には、自助・共助でできることもあり、しっかりと積み重ねていきたいものです。
| 6月29日「繰り返される沖縄での米軍犯罪は許されない」 |
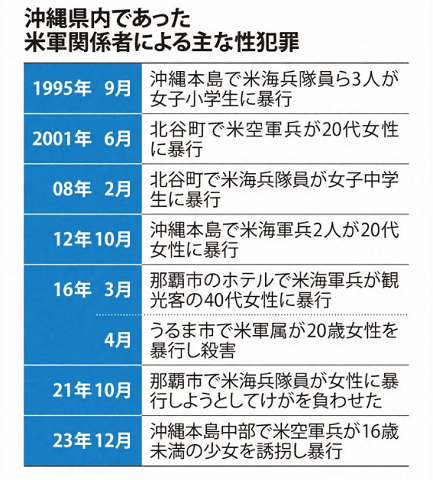
 25日には、昨年12月に米軍嘉手納基地所属の米空軍兵(25)が少女に性的暴行を加えたとして、不同意性交等罪などで起訴されていたことが明らかになっていたが、加えて昨28日、沖縄本島中部で女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、沖縄県警が5月に、在沖縄米海兵隊の男性隊員(21)を不同意性交等致傷容疑で逮捕していたことが判明しました。
25日には、昨年12月に米軍嘉手納基地所属の米空軍兵(25)が少女に性的暴行を加えたとして、不同意性交等罪などで起訴されていたことが明らかになっていたが、加えて昨28日、沖縄本島中部で女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、沖縄県警が5月に、在沖縄米海兵隊の男性隊員(21)を不同意性交等致傷容疑で逮捕していたことが判明しました。
このことは、逮捕時には公表されておらず、、沖縄の米軍関係者による性的暴行事件の相次ぐ発覚に市民の怒りが高まっていますし、我々にとっても許すことのできない事件だと言えます。
沖縄県としては、12月の事件の情報を把握していれば、米国や国に対する申し入れなど、次の被害の発生を未然に防ぐこともできたのではないかと許せない思いが強いと思われます。
日米両政府は1997年、公共の安全に影響を及ぼす可能性のある事件が起きた場合、米側が日本政府や関係自治体に通報する経路を決め、沖縄での事件の場合、米側は中央レベルで在日米大使館を通じて外務省に、地元レベルで防衛省沖縄防衛局に伝え、防衛局が県や市町村に連絡すこととなっていたが、この2事件とも結果的に県への連絡はありませんでした。
外務省のお粗末な対応、そして、県警もこの2事件について米兵の検挙を報道機関に公表せず、県にも伝えなかった理由として「被害者のプライバシーの保護」を理由とした非公表によって、次の犠牲者を作ったことに対する反省が全くなされてないことに、呆れるばかりです。
在日米軍問題に詳しい沖縄国際大の前泊博盛教授は、「米兵による過去の事件が、今になって続々と明らかになるのは異常だ。4月の日米首脳会談や16日に投開票された沖縄県議選への配慮があったのでは、と疑う声が上がってもおかしくはない。県に連絡しなかった外務省の対応も、知事に報告しなかった県警の対応も問題で、本来は米軍が直接、地元に伝えるべきだった。他にも米兵による事件が隠されているのではと疑念を持たざるを得ない状況で、なぜ県に情報が上がってこないのかを検証する必要がある。」と述べられているが、4月の日米首脳会談や16日に投開票された沖縄県議選への配慮があったとしたら、決して許されないことであり、徹底した真実の究明が求められます。
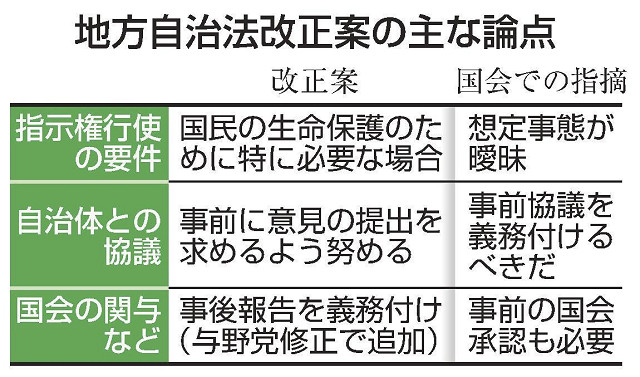

6月定例会本会議質問戦も本日が最終日だが、改定地方自治法の問題点に関する質問が、県民の会の岡田議員をはじめ二人から質問がされ、知事の改定地方自治法に関する見解が示されました。
▼地方自治法の改正は新型コロナ禍の課題を踏まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期す観点から、特例として国の指示権を行使できるようにするもので、その趣旨は理解できるが、一方で拡大解釈で地方自治の本旨や地方分権改革で実現した国と地方の対等な関係を損なうことがあってはならない。指示権の行使は必要最小限の範囲とし、事前に関係する地方公共団体と調整する付帯決議が国会で行われた。国には決議を踏まえて、適切に運用してもらいたい。
▼地方自治法の改正は新型コロナ禍の課題を踏まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期す観点から、国の指示権は特例とされ、地方公共団体と事前調整することや必要最小限度とすることなどの付帯決議がなされています。また、指示権行使の際には、閣議決定を経ることや行使後には、迅速に個別法の規定が整備されるよう国会への事後報告や検証行うといった手続きも講じられている。
こうしたことから国が、指示権を「濫用」する蓋然性は相当程度低いと考える。
▼国は、指示できる事態について、「現時点で具体的に想定し得るものはない」としており、そうした中で、県として個別具体の対応方針をあらかじめ整理することは困難。その上で、仮に本県に指示内容の事前調整があった場合には、本県の実情を踏まえ可能な限り県議会の皆様のご意見もお聞きしながら、私自身が意見を訴えていきたい。
▼国が指示権を行使するにあたっては、その運用が拡大解釈により地方自治の本旨や地方分権改革により実現した国と地方の対等な関係を損なうことがあってはなりません。このため、これまでも全国知事会と連携して国に訴えてきました。その結果、先ほど申し上げた通り、附帯決議や手続き上の措置がなされたほか、国と地方は対等・協力とする地方分権の原則は維持するとされております。このため、今回の法改正をもって、地方の自主性・自立性が危ぶまれるものではないと考えています。
▼国においては、国民の安全に重大な影響及ぼす事態が発生した際にあっても、国と地方との連携が一層強化されるよう、適切に制度を運用していただきたい。
知事の「指示権を濫用行使することなく、適切に制度運用がされ、国と地方は対等・協力とする地方分権の原則は維持するとされ、今回の法改正をもって、地方の自主性・自立性が危ぶまれるものではない」との考えを、議会の総意として国に伝えて行くため、会派として「改定地方自治法における自治体への指示権を濫用行使しないことを求める意見書(案)」を提出することとしました。
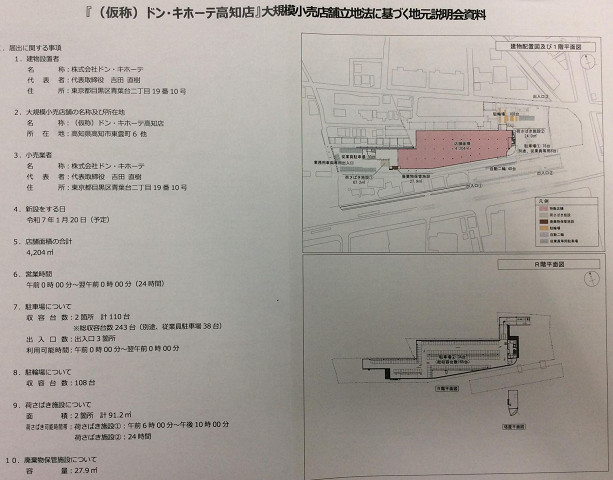
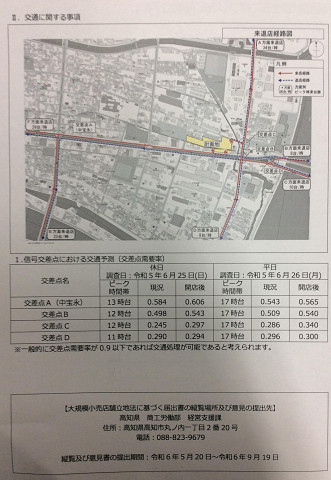


昨夜、「(仮称)ドン・キホーテ高知店の大規模小売店舗立地法に基づく地元説明会」が「ちより街テラス」で開催されました。
昨年11月の事前の地元説明会以上にたくさんの方が参加され、時間制限がされる中ドン・キホーテ側の説明に対して、10人を超す方からの質疑がされました。
昨年の時もそうでしたが、住民の方が最も心配されているのは、今でさえ交通安全面で心配がされている建設予定地の北側の生活道路が、立体駐車場の出退店が集中した場合に、大変な混乱が起きることと、24時間営業に対する営業時間の問題について多くの不安・懸念・要望が出されました。
ドン・キホーテ側は、昨年の11月に行われた地元説明会での意見を踏まえて検討してきたが、電車通りがの南の出入り口を生かしつつ、北出入口を使う、そして北出入口はできるだけ負荷がかからないように使用していくつもりであることや営業時間についても「ご意見を配慮した営業時間の検討」をしているが、12時を過ぎたあたりのところと言う曖昧な表現で、決定はオープンの1ヵ月前に、ホームページで行うとのことでした。
PTA会長からはこの間保護者からいただいたアンケート結果等も手交することが申し出られましたし、北側の生活道に面した出入り口ありきの話はやめてほしい、南側の電車通りからの2カ所で対応すれば良いではないかなどの意見も出されていました。
いずれにしても、交通安全面や防犯上の問題、夜間の静穏維持の問題等々、周辺住民にとっては生活環境が大きく悪化することに対する不安懸念材料は大きく、これらの課題にどうドンキ側が真摯に向き合う姿勢なのかが問われています。
私からも、「昨年11月の地元説明会は、地域住民との良い関係を築くためのものだと言う前提で開かれたが、その姿勢を検討内容に反映されていたのかというのが今回の説明会だったが、今回も多岐にわたって意見・要望が出された。それを踏まえた反映がどのようにされるのかその決意を聞きたい。」
さらには、「営業時間の決定も1ヵ月前にホームページで公表などということではなく、今回出された意見を踏まえてどのような対応をしたのか改めて地元説明会をすべきではないのか」との意見も出させて頂きましたが、「持ち帰って真摯に検討する」あるいは「説明会は今回で終わりです」というような姿勢であり、私としては「地域と良い関係を築きたい」という言葉を俄かに信頼ではないような気持ちにならざるをえませんでした。
これまでのドン・キホーテ立地地域で起きている課題からも、会場やアンケートで出された意見などを事前に解消した上で、そして地域の皆さんが安心して利用できる立地計画とされることをが多くの参加者の願いだと思います。
ドン・キホーテ側は、今回の説明会後も話し合いの窓口を開けているし、オープン後も課題についての話し合いの窓口は開けているとのことですが、形だけでなく、その姿勢が問われているのではないかと思わざるをえない90分間でした。
| 6月24日「沖縄戦の教訓『戦争は民間人を巻き込み、軍隊は住民を守らない』を語り継ぐ」 |


沖縄戦から79年の「慰霊の日」を迎えた昨日、糸満市摩文仁で今年181人が追加刻銘され、沖縄戦に関連する犠牲者は計24万2225人となった沖縄全戦没者追悼式がありました。
玉城知事は平和宣言で、米軍基地の過重な負担が続く県内で急激に自衛隊の配備強化が進むことに、県民の強い不安を代弁し、「今の沖縄の現状は、無念の思いを残して犠牲になられたみ霊を慰めることになっているのでしょうか」と問いかけられました。
沖縄戦の教訓である「戦争は民間人を巻き込み、軍隊は住民を守らない」ということを私たちは語り継がなければなりません。
追悼式の後、岸田首相は記者団の質問に答えて、戦没者の遺骨が混じる可能性のある本島南部の土砂を辺野古新基地建設で使う計画について、「県民感情に配慮して調達先を選定する考え」を示しました。
しかし、南部土砂を新基地建設に使用することは県民や戦没者を冒涜する行為に等しく、本来なら首相ははっきりと不使用を明言しなければなりません。
今回の知事の平和宣言は、「いわゆる、安保3文書により、自衛隊の急激な配備拡張が進められており、悲惨な沖縄戦の記憶と相まって、私たち沖縄県民は、強い不安を抱いています」と政府の防衛政策に対する強い異議申し立てが最大の特徴であると言えます。
集団的自衛権の行使を可能とする憲法の解釈変更、敵基地攻撃を可能とする安全保障3文書の閣議決定によって日本の防衛政策は大転換し、それに続く「特定利用空港・港湾」指定、米軍基地や自衛隊基地周辺を対象とした土地利用規制法、地方に対する国の指示権を拡大する改悪地方自治法なども警戒すべき一連の動きとして、捉えておかなければならないと思います。
今、私たちに求められているのは、麻生副総裁のいう「戦う覚悟」を拒み続け、平和を築く意思と行動であることを我が事として胸に刻まなければなりません。
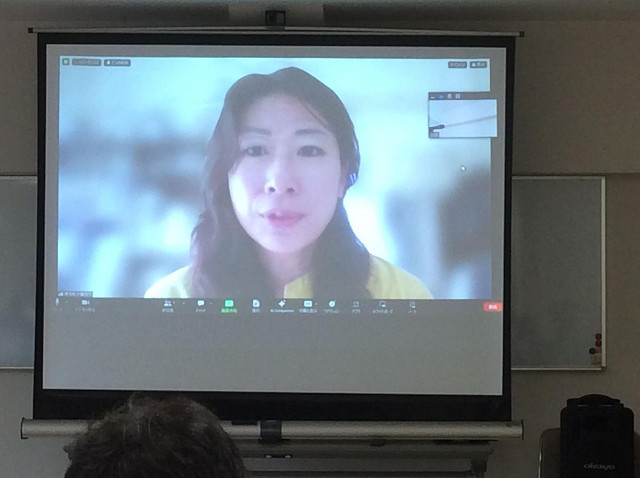
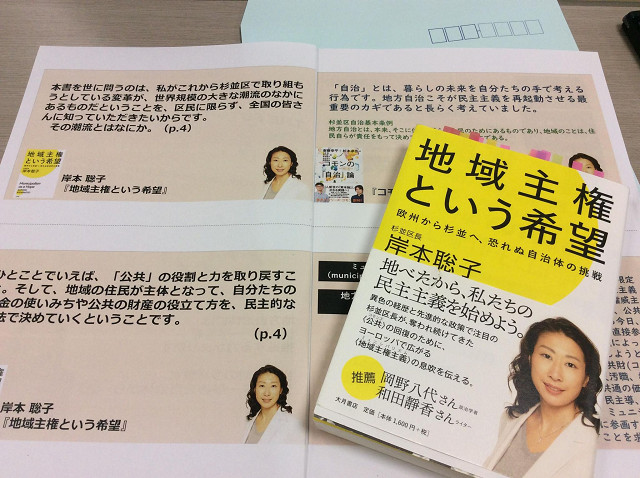

昨日は、高知県自治研究センターのセミナーで、岸本聡子東京都杉並区長から「地域主権で公共の復権を」とのテーマでお話を伺いました。
岸本氏は、本来、みんなのもの(公共)である安全な水、快適な住居、交流の空間である公園や図書館などの運営や管理について、利潤と資本の法則よりも、公益、コモンズ(公共財)が優先されるべきことを訴え、区長としても区政の中で変革に取り組まれています。
「地域主権で公共の復権を」というのは、一言で言えば「『公共』の役割と力を取り戻すこと。そして、地域の住民が主体となって、自分たちの税金の使いみちや公共の財産の役立て方を、民主的な方法で決めていくということです」と言われています。
「地域で住人が直接参加して合理的な未来を検討する実践によって自由や市民権を公的空間で拡大しようとする運動」であるミュニシパリズムの実践。
自治体の公共調達と社会的価値をビルドインしていく「公共の再生」。
区民と行政の信頼を基盤として「対話の区政」「参加型民主主義」を実現することは、「豊かで公正な公共経済と地域のウェルビーイングを作る公共政策と自治」を実現することでもあることを考えさせられながら、全国の自治体で目指されたらと思いました。
その力は「行政を動かせるのは、住民の声が横につながってコレクティブ(集合的)な力になるとき」(岸本氏著「地域主権という希望」)ということを肝に銘じて諦めない住民運動の組織化が、これから求められるのではないでしょうか。


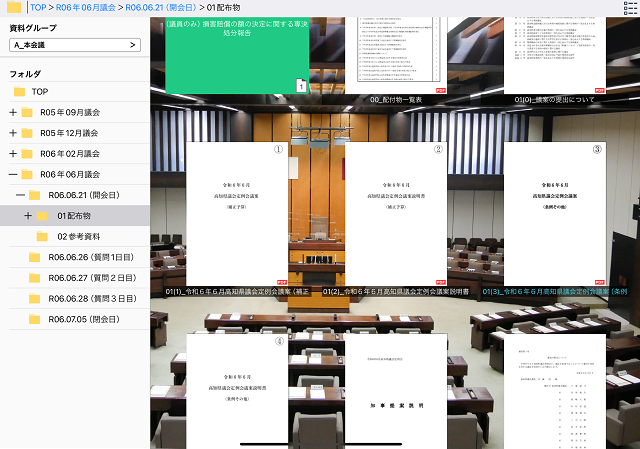
高知県議会6月定例会が21日に開会しました。
今議会から、ペーパーレスということで、議案などは全てiPadで読むことになりますが、まだまだ操作には慣れていないというのが現状です。
執行部の提出議案は、2024年度一般会計補正予算案8645万円など13議案で、26~28日にわたって一般質問が行われますが、中でも人口減少対策や南海トラフ地震対策などが、多く論議されるのではないかと思われます。
今回は、私は質問の機会がありませんが、常任委員会で付託案件や報告事項についてしっかりと論議したいと思います。
さて、浜田知事は提案説明で、11日に能登半島地震の被災地を訪ねたことを振り返り「厳しい現状を目の当たりにし、大規模災害への事前の備えの必要性を再認識した」と強調し、事前復興計画や水道施設の耐震化が必要だとし、南海トラフ地震対策の第6期行動計画(2025~27年度)の策定に向けて「教訓を最大限生かし、対策全般の強化を図る」と訴えました。
その決意がどこまでのものか、提案説明で南海トラフ地震対策で触れた説明をここに紹介しておきたいと思います。
そして、これらの課題が第6期行動計画にしっかりと反映されるのかを注視していかなければと思っています。
能登半島地震の発生から約半年が経過しました。私自身の目で被災状況や復旧・復興の実情を確かめるべく、先日、珠洲市と輪島市を訪問しました。
現地を訪れて最も印象的であったのは、いまだに倒壊家屋のほとんどがそのままの状態で残されており、東日本大震災や熊本地震と比べても処理に時間を要していることです。その要因としては、過疎化が進む半島部という地理的な事情が考えられ、本県の中山間地域においても、南海トラフ地震の発生時には同様の事態が起こり得るものと想定しなければなりません。
こうした厳しい現状を目の当たりにし、今回の訪問の教訓として大規模災害への「事前の備え」の必要性を再認識しました。
第一に、復旧・復興作業に向けた事前の備えです。事前復興計画の策定を通じて、住民の皆さんの「被災後も住み続ける」という意思や地域の再建後の姿をあらかじめ確認しておくことが大変意義深いと考えます。また、倒壊家屋の処理を含めた復旧・復興のプロセスを迅速かつ円滑に進めるため、建物の権利関係の整理や域外からの解体業者の受入態勢づくりといった事前の準備が重要です。加えて、災害廃棄物の仮置き場や応急仮設住宅の候補地をあらかじめ選定しておくことも必要です。
第二に、発災直後の応急活動に向けた事前の備えです。今回の地震では、道路網の寸断や水道施設の損壊などによりライフラインの復旧が遅れた地域で、発災直後の避難所の開設や学校の早期再開が困難となりました。その結果、1.5次避難や2次避難といった予期せぬ広域避難を迫られ、この対応に時間を要したことが、倒壊家屋の処理など復旧・復興に向けた取り組みの遅れにもつながりました。
このため、受援計画の実効性を高めるなど、広域的な対応への備えを強化しておくことが求められます。加えて、断水が続く中でも、災害救護活動などの医療面や、避難所のトイレ対策といった衛生面を含め、衣食住の生活環境を早期に整えることができるよう備えを強化する必要があります。
第三に、災害に強いインフラの整備です。道路の寸断や集落の孤立を回避するためには、強靱な道路ネットワークの構築が何より重要です。また、大規模災害時において、住民生活に不可欠となる上水道を安定的に確保するためにも、水道施設の耐震化を一層加速させなければなりません。
こうした課題を含め、今回の地震の教訓については、これまでに専門家からの意見聴取を終え、現在、被災自治体における対応状況などの調査分析を行っています。今後、国における検証作業の結果も参照した上で、この秋を目途にその成果を取りまとめます。来年度からの次期行動計画の策定に向けては、これらの教訓を最大限生かし、対策全般の強化を図ります。さらに、現在国が進めている南海トラフ地震の被害想定の見直しについては、次期行動計画をバージョンアップする中でしっかりと反映させます。 |
 明日は、理事をさせて頂いている高知県自治研究センターで岸本聡子東京都杉並区長を講師に「地域主権で公共の復権を」と題したセミナーが開催されます。
明日は、理事をさせて頂いている高知県自治研究センターで岸本聡子東京都杉並区長を講師に「地域主権で公共の復権を」と題したセミナーが開催されます。
岸本氏は、本来、みんなのもの(公共)である安全な水、快適な住居、交流の空間である公園や図書館などの運営や管理について、利潤と資本の法則よりも、公益、コモンズ(公共財)を優先させる活動をアムステルダムに本拠を置く政策シンクタンクNGOで続けてこられた方です。
「地域主権」の意義を語ってもらい、みんなのものとしてあるべき「公共」の姿を探ります。
改悪地方自治法についても、ある集会で「コロナ流行の初期、私は海外在住だったが、日本政府がPCR検査の拡充をためらったことに驚いた。一方で、国の要請がなくても独自に検査拡充に乗り出した自治体もあった。正しい答えを見つけるために自治体も一生懸命模索した。自治体は国の指示がなくても動く。むしろ、法改正で自治体が指示待ちの『思考停止』に陥る危険性がある」と指摘されており、触れて頂けるかもしれません。
どうぞ、関心ある方は、ご参加ください。
日時 6月22日(土)13時30分~
場所 自治労高知県本部(高知市鷹匠町2-5-47)
申込 info@kochi-jichiken.jp
| 6月19日「地方自治法改悪で国の指示権拡大・自治体関与強まる」 |
 これまでもその問題点を機会ある毎に指摘し、批判してきた非常時に国が自治体に対応を指示できるようにする地方自治法改悪案が、参院総務委員会で可決され、本会議で成立する見通しとなりました。
これまでもその問題点を機会ある毎に指摘し、批判してきた非常時に国が自治体に対応を指示できるようにする地方自治法改悪案が、参院総務委員会で可決され、本会議で成立する見通しとなりました。
昨日の最後の審議でも、我が徳島・高知選挙区の広田一議員をはじめ多くの議員から、禍根を残すことになる一旦撤回をとの質疑がされていました。
これまで個別の法律に規定がある場合に行使が限られていた指示権を、個別法の根拠がない場合にも広げることが明記されたもので、分権改革に逆行する上、地方の決定権を奪うことにつながり、国の統制が強まる恐れがあるとの懸念が、審議がされればされるほど、広まりつつあったところです。
非常時に国が調整に乗り出す必要性はあるかもしれないが、その場合でも基本は国と自治体が情報共有を密にして解決策を考えるべきで、現行の枠組みでできることであり、それを蔑ろにしてきたのは国の方だったのではないでしょうか。
国の一方的な判断が現場を混乱させかねないことは、コロナ禍の際の安倍政権での唐突な全国一斉の休校要請からも明らかです。
2022年の国家安全保障戦略に基づき、政府は有事に公共施設を使える準備を進めており、今年4月には、本県3港湾や自衛隊の「南西シフト」で防衛力強化が急速に進む沖縄の施設も含まれている16の空港と港を「特定利用空港・港湾」に指定しました。
武力攻撃事態での指示権発動について、政府は「想定していない」というが、改正案に除外規定はなく、現状では空港法や港湾法に基づく自治体との調整が前提だが、この手続きを飛び越え、「おそれがある」段階で強制力の行使が可能となるのではないかとの懸念は強まるばかりです。
さらに、心配されているのは今回の改正で自治体の「指示待ち」が強まることでもあり、2000年の分権改革で国と地方が、「対等・協力」の関係になったにもかかわらず、「上下・主従」に逆戻りする危険性が大きく、地方分権改革の原則に逆行することであります。
自治体が侵略戦争の一翼を担わされた反省に立ったことから、憲法は地方自治について独立の章を設け、制度として保障し、その自主性が「十分に発揮される」ことこそが求められています。
自民党が12年に発表した憲法改正草案には緊急事態での首相の権限として「自治体の長への指示権」が書かれていますが、これまでも指摘してきた「緊急事態条項改憲」を今回の法改正で既成事実化したとも言えます。
付帯決議には、事前に十分に自治体と協議することや他の方法で目的が達成できない時に限ることが盛り込まれてはいますが、政権が恣意的に濫用しないことを監視し続けるとともに、本来の憲法の趣旨にもとづく地方自治法に戻していく闘いを始めなければと思います。
| 6月18日「2001年4月以降、政権担当しながら自民支持率初の10%台」 |

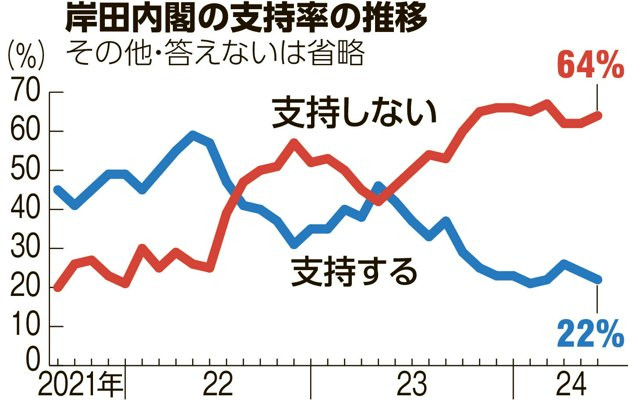
朝日新聞社が15、16日に実施した全国世論調査(電話)で、自民党の政治資金規正法改正案が成立した場合でも、「政治とカネ」の問題の再発防止に「効果はない」とする回答が77%に上っています。
その内訳は、「あまり効果はない」が48%、「全く効果はない」が29%で計77%で、「効果がある」との回答は「大いに」1%と「ある程度」19%をあわせ、20%にとどまったものです。
裏金問題への岸田首相の対応は「評価しない」が83%に上り、「評価する」はわずか10%で、「評価する」割合は5月の12%から、さらに悪化しています。
また、今月から始まった1人あたり4万円の定額減税については「評価する」が35%。「評価しない」が56%と上回り、「評価する」と答えた人でも、そのうち78%が所得の伸びが上回ることを「期待できない」としています。
そのような中で、派閥の裏金問題をきっかけにした不信感は根強く、自民党の支持率は19%と前回5月調査の24%から大きく下がり、岸田内閣の支持率は22%(5月調査は24%)で、内閣発足以降で最低の21%だった2月調査時と同水準でした。
政界では内閣と与党第1党の支持率の合計が50を割り込むと内閣が早晩立ちゆかなくなるという「青木の法則」と言われるものが、かねてから意識されてきたが、もはや50どころか40を割りそうな勢いです。
| 6月16日「『県政かわら版第74号』まもなくお届けします」 |




今朝の新聞折り込みに「県議会だより」があり、その4頁に私の質疑も掲載されているが2問のみに限られています。
もう少し詳細にということで、これも抜粋ではあるが、「県政かわら版」74号で議会報告をさせて頂いています。
今、配布の準備をしていますが、ネット上で一足早く見て頂ければとの思いで、掲載させて頂きます。
こちらからリンクを貼っていますので、関心ある方はどうぞご覧ください
 学校給食法施行から70年となる今年、少子化対策につながる子育て世帯の負担軽減策として学校給食の無償化を求める声が大きい中、公立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化している自治体が、2023年9月時点で、全国の3割にあたる547あったことが文部科学省の調査で分かりました。
学校給食法施行から70年となる今年、少子化対策につながる子育て世帯の負担軽減策として学校給食の無償化を求める声が大きい中、公立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化している自治体が、2023年9月時点で、全国の3割にあたる547あったことが文部科学省の調査で分かりました。
この調査では、児童生徒全員を対象にするか、支援要件を設けるなど一部の児童生徒を対象にして「無償化を実施中」としたのは722自治体で、このうち「小中学校ともに全員が対象」は547自治体(75.8%)で、17年度の76自治体から約7倍に増えました。
また、約150自治体が多子世帯に限定するなど支援要件を設けており、一部の学年に限定して無償化している自治体もあります。
無償化した理由については、652自治体(90.3%)が「保護者の経済的負担の軽減、子育て支援」、66自治体(9.1%)が「少子化対策」(子どもの増加を期待した支援)、37自治体(5.1%)が「定住・転入の促進、地域創生」(人口増を期待した支援)を選んでいます。
一方、722自治体のうち24年度以降に続ける予定はないと答えた自治体も82(11.4%)あり、財源の問題から、時期を限って無償化する自治体もあり、無償化の継続が難しい面も見えています。
今回の調査は、岸田政権の少子化対策「こども未来戦略方針」を受けたもので、今後、実現に向けて課題の整理を行うというが、政権の少子化対策の本気度が問われることになると思います。
| 6月13日「日本のジェンダーギャップ指数は相変わらずの低位停滞」 |

 NHKの朝ドラ「虎に翼」では、日本初の女性弁護士一人であった三淵嘉子さんをモデルとした主人公が、戦後、女性に門戸の開かれた裁判官になり、裁判所長となっていく過程の中で、男女不平等の壁を少しずつ乗り越えていく姿に、励まされている視聴者も多いのではないかと思います
NHKの朝ドラ「虎に翼」では、日本初の女性弁護士一人であった三淵嘉子さんをモデルとした主人公が、戦後、女性に門戸の開かれた裁判官になり、裁判所長となっていく過程の中で、男女不平等の壁を少しずつ乗り越えていく姿に、励まされている視聴者も多いのではないかと思います
世界では、政治の分野での女性進出は進み、世界経済フォーラムは12日、世界の男女格差の状況をまとめた2024年版「ジェンダーギャップ報告書」でも、女性比率の多さなどが評価されて33位となっているメキシコにも女性大統領が誕生したことが報じられたばかりです。
しかし、日本は調査対象となった146カ国のうち118位で、前年の125位からは改善したが、主要7カ国(G7)では、87位のイタリアを下回る相変わらずの最下位でした。
報告書は教育・健康・政治・経済の4分野で、男女平等の度合いを分析し、男女が完全に平等な状態を100%とした場合、世界全体での達成率は68.5%で、日本の達成率は66.3%で前年から1.6ポイント上乗せしたものの、G7では最下位であり、対象国数は異なるが、06年に報告書が始まって以降、日本の順位は下落傾向にあり、ジェンダー平等の取り組みを進める他国に取り残されているのが実情です。
原因は経済と政治の両分野で特に男女格差の解消が進んでいないことで、企業での管理職・役員への女性登用の少なさなどを反映した経済分野の達成率は56.8%、政治分野は11.8%で、衆院議員の女性比率が約10%にとどまるなど、女性の政治参加の遅れが響いているとのことです。
10日、経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、女性の活躍が広がる中で企業のビジネス上のリスクになりうるとして、政府に対し「選択的夫婦別姓」の導入に必要な法律の改正を早期に行うよう求める提言をとりまとめました。
このような動きを政府がどのように受け止めるかも、今後のジェンダー平等の取り組みを左右することになるものと思われます。
| 6月11日「地方自治法『指示権』改悪の強行を許さない」 |
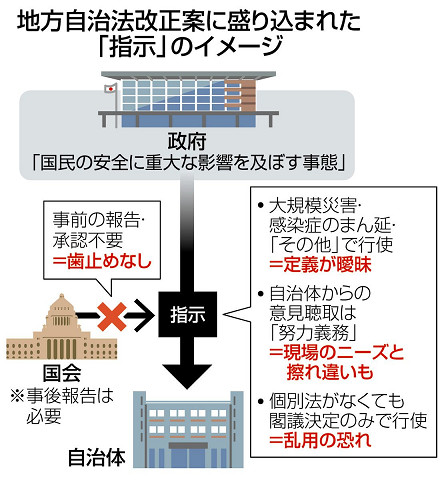 感染症のまん延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるとする特例を盛り込んだ地方自治法改悪案の参院審議が5日から始まっています。
感染症のまん延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるとする特例を盛り込んだ地方自治法改悪案の参院審議が5日から始まっています。
自治体が望んでいるのは、「指示」ではなくて支援であり、特に財政的な支援をコロナ禍でも災害時にでも求めてきたのではないでしょうか。
自治体は、国によって財源さえ担保されれば、指示はなくとも、自治体の実情に合わせた対応ができるはずです。
東京都岸本聡子杉並区長は「コロナ流行の初期、政府がPCR検査の拡充をためらったことに驚くとともに、一方で国の要請がなくても独自に検査拡充に乗り出した自治体もあった。正しい答えを見つけるために自治体も一生懸命模索した。自治体は国の指示がなくても動く。むしろ法改正で自治体が指示待ちの思考停止に陥る危険性がある。」と指摘しています。
また、保阪展人世田谷区長は、「災害対策基本法や新型インフル特措法以外の国の関与が書かれていない分野で、全て大風呂敷で受け止めるとんでもない法制であり、自治体の国への白紙委任法でもある。」と批判しています。
国の「指示権」乱用への歯止めが効かず、何より2000年の地方分権一括法によって「対等・協力」の関係になった「上下・主従」に逆戻りする危険性が大きく、地方分権改革の原則に逆行するものであります。
そんな批判が続く中、裏金議員たちによって、このような悪法を参院で強行採決させないようにしていきたいものです。
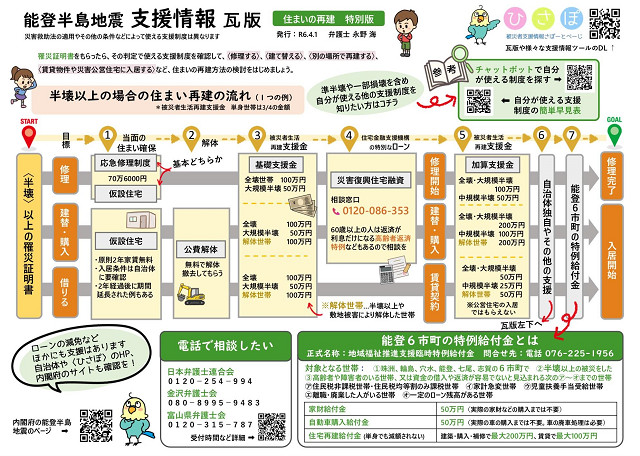
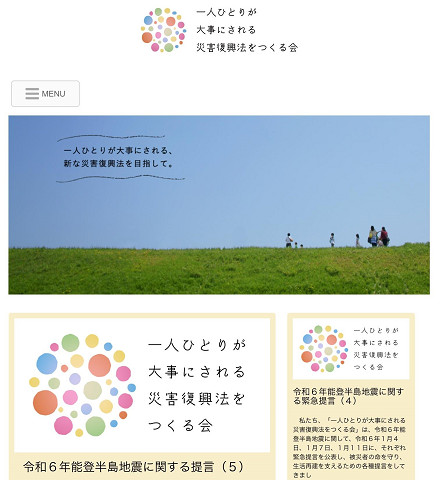
昨日から、高知新聞で「罹災証明という壁 能登が問う高知の今」が連載されています。
罹災証明は義援金や被災者生活再建支援金の支給区分に直結し、融資やさまざまな支援の土台となる重要な書類なのですが、この罹災証明が、住宅がどれくらい壊れたのかということだけを指標とする点については、多くの有識者から疑問視されてきました。
ここでは、記事から気にかかった点だけ、触れておきたいと思います。
支援に向かう自治体職員は、判定のプロでもなく、「行ってみて、やってみての世界ですよ」「人の生活を左右するプレッシャーはある。でも、見たまんまやるしかないっすよ。被災地には研修をしている時間も余裕もないですから」と、コメントしているが、判定をうける被災者は、「家やなくて、もっと人間見てほしいわ」と言われています。
被災者にこのような思いをさせないためにも、 今回の能登半島地震の復旧・復興過程の中で、「家の壊れ方だけでなく、その人が暮らせるのか、暮らせないのかで考えるべきであり、生活の困難さへの理解が欠けています。『制度は被災者のために』という原点に返らないといけません。」と、いつも紹介させて頂く兵庫弁護士会の津久井進弁護士は指摘されます。
また、迅速さについて、独自に判定の迅速化を図る動きとして黒潮町の「一軒一軒ではなく、ドローンを活用して津波被害を受けた地区単位で全壊などを判定できないか研究する」というコメントが紹介されているが、このことも大事なことです。
このことについては、津久井進弁護士らが共同代表をされている「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」は、罹災証明書の申請、認定の方法、発行などについては被災者支援の目的に沿って行われる必要があることについて、提言されています。
提言の中では、罹災証明の申請にあたっては、「被災者の負担となるような資料の提出を求めることのないように注意を促し、申請の際には、壊れた住居の写真などを求めるべきでなく、自己判定方式でない限り、写真の提出を求める必要はないとして、罹災認定の方法も、これまでの大規模災害のように、航空写真やドローンを活用した簡易判定、一定のエリア内の建物はすべて全壊と判定するエリア認定など、考え得る手段をできる限り活用して、手続を進めるべき。」と指摘されています。
まさに、黒潮町の検討は、そのような提言の趣旨に沿って検討されていると思われます。
これから高知県が「罹災証明の壁」を乗り越えていくためには、津久井弁護士らが言われる「制度は被災者のために」という原点に立ち返った現場対応のできる備えが必要なのだと思いながら、明日の「罹災証明という壁 能登が問う高知の今」(下)を待ちたいと思います。

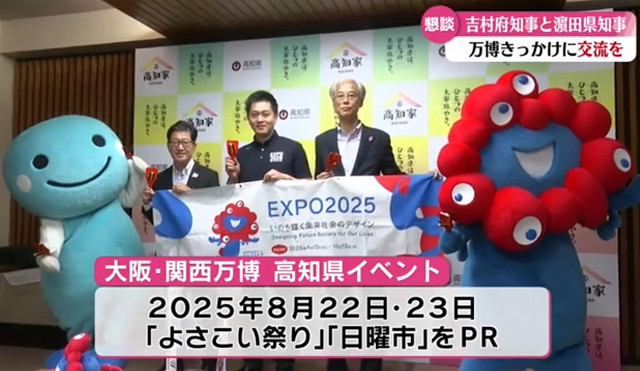 吉村大阪府知事が大阪・関西万博の盛り上げ要請のため、浜田高知県知事を5日に訪ねたことが報じられています。
吉村大阪府知事が大阪・関西万博の盛り上げ要請のため、浜田高知県知事を5日に訪ねたことが報じられています。
その際に、浜田知事は、「7月には高知のアンテナショップも新たに設けることにしているので、万博を機に関西・大阪と高知の交流のパイプを一気に太くしたいのでよろしくお願いしたい。」「一つの世代の象徴になるような一大イベントして、活況を呈してもらいたい。」などとコメントしているが、万博にまつわる懸念や不安は、けして解消されていると言えないのではないでしょうか。
万博会場建設現場で3月28日、地中の廃棄物から出たメタンガスが原因とみられる可燃性ガスに、工事中の火花が引火して爆発する事故が発生したことは、このコーナーで触れたが、日本国際博覧会協会は5月下旬になって、当初は床面としていた損傷が屋根にも及んでいたと発表し、1枚だけ公表していた現場写真についても、複数枚を追加したことが報じられています。
開催まで10カ月余りとなった万博の態勢は万全と言えるのか、情報公開は十分なのか、改めて総点検する必要があると思われます。
万博協会は、心配ないというが、土砂区域からも、爆発の恐れはない濃度ながらメタンガスが検出されており、万が一にも事故を起こさないよう、対策の徹底が急がれます。
そして、不安の声は、とりわけ児童・生徒をもつ家庭や学校関係者の間で強く、大阪府が公費を投じて府内の小中高校生を学校単位で万博に招待する予定がある中、ガス問題にとどまらず、会場への移動手段となる地下鉄やシャトルバスでの混雑、会場内での暑さ対策、そして災害時の避難のあり方など、心配事は多岐にわたっています。
改めて、安全への備えと総点検の上、具体的な対策が求められています。
| 6月3日「政治資金規正法改正『再修正案』では、腐敗は断てない」 |
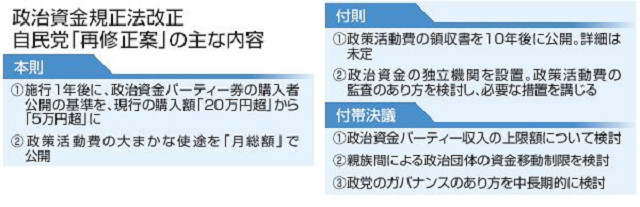 自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案を巡っては、自民党が示した再修正案に公明党と日本維新の会が合意し、今国会で成立を強行させようとしています。
自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案を巡っては、自民党が示した再修正案に公明党と日本維新の会が合意し、今国会で成立を強行させようとしています。
しかし、再修正したところで、企業・団体献金や政策活動費を温存する内容にとどまっており、金権腐敗の根を断ち、政治の信頼を回復できるのかは疑わしい限りです。
再修正案は政治資金パーティー券の購入者名の公開基準を現行の20万円超から5万円超に引き下げ、政策活動費は10年後に領収書や明細書を公開するというもので、裏金に回る余地は残っており、抜け道を封じるにはパーティー券収入の全面公開か、パーティーの禁止こそが不可欠です。
政党が党幹部らに支出する使途の公開義務がなく、不透明なカネの温床となっている政策活動費の使途公開も、なぜ10年なのか、しかも政党交付金に頼っている税金が財源の政策活動費の使い方を10年間も国民に隠す必要はないはずであります。
再修正案では、企業・団体献金の取り扱いに言及していないことも大きな問題です。
抜本改革を避けてきた岸田首相が、内容が不十分な再修正案の成立を強行するなら、裏金事件を反省しない自民党や裏金議員が立法府にとどまり続けることの是非を主権者たる我々国民が判断しなければならないはずです。
今日、質疑を行い明日には、衆院での通過を目指し、5日以降には参院審議に入ろうと企図しているが。こんな中身で一件落着を図る自民党に鉄槌を下さなければなりません。
そして、「首相の英断」と、修正に応じた岸田首相を持ち上げる公明党や「我々の案を自民が丸のみした」と、成果を強調する維新に対して「同じ穴のムジナ」として、批判を強めなければなりません。
| 6月2日「高知で20年前に蒔かれたレスリングの花開く」 |




今日は、レスリングの櫻井つぐみ選手(女子フリー57㌔級)と清岡幸太郎選手(男子フリー65㌔級)のパリオリンピック出場壮行会が開催され、出席していました。
高知県レスリング界の開拓者としてともに3歳からレスリングに取組み、旧県立南高校では、同級生で互いに切磋琢磨を重ねて、今年のパリオリンピックにともに日本を代表して出場が決まるという快挙を成し遂げました。
その間には、本人たちだけにしか分からない苦労があったことだと思います。
二人の活躍に期待する県民が300人を超えて、壮行会会場に詰めかけました。
さまざまな指導者、関係者、県民に感謝しながら、一番輝くメダルを目指して二人が頑張る決意を述べられました。
参加された皆さんは本県にとって90年ぶりのダブルの金メダルです。
それにしても、西高校と統合して国際高校となってしまった南高校からは、もう一人のアスリートがパリ・パラリンピックに出場します。
そうです、リオ、東京と連続して銅メダルを獲得した車椅子ラグビーの池透暢選手も南高校です。
私も、南高校のPTAや進取会役員を長く務めさせて頂きましたが、今日も顔なじみのメンバーや先生方の多くが顔を見せられていました。
今日も早速パブリックビューイング(協議日程はよさこいと同日)の話で大盛り上がりでしたが、高知の夏はオリンピック・レスリングとよさこいで熱く燃えそうです。
皆さんには、ベストの体調で試合に臨んで頂きたいものです。

 この間の危機管理文化厚生委員会出先機関調査で、県東部地域の医療拠点である「あき総合病院」が、何としても存続させたい周産期医療体制の具体化に向けた課題の一つとして、院内助産を目指していることの話を聴かせて頂きました。
この間の危機管理文化厚生委員会出先機関調査で、県東部地域の医療拠点である「あき総合病院」が、何としても存続させたい周産期医療体制の具体化に向けた課題の一つとして、院内助産を目指していることの話を聴かせて頂きました。
そして、東部の周産期医療体制の拠点の継続を図らなければならないと思わされていた矢先、今朝の新聞報道による南国市のJA高知病院が9月末でお産の取り扱いをやめることが報じられていました。
また、看護師を目指し、県内の専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク時の2015年度に800人を超えていた新入生は本年度435人と、9年でほぼ半減したとの報道があった際にも、「幡多けんみん病院」での人材不足の課題と「幡多看護専門学校」での受験者・入学者の定員割れの課題についても聴かせて頂きました。
県内周産期医療をはじめ公的医療体制の危機は、産科医師や助産師をはじめ医療従事者の不足がそのことに拍車をかけていると言わざるをえません。
出産費用は現在、帝王切開や吸引などの「異常分娩」であれば保険適用されるが、正常分娩の場合は適用外で、出産一時金が給付されているが、厚生労働省では妊産婦の経済的負担を低減するため、保険適用について検討されようとしています。
しかし、その保険制度の見直しの際には、人材の確保につながる内容もセットでなければ、出産を受け入れる体制が確保できないのではないかとの懸念も生じることとなります。
いずれにしても「こどもまんなか社会」を築くためには、その周辺の環境を築くための本気度が問われているのではないでしょうか。
 昨日の高知新聞に、看護師を目指し、県内の専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク時の2015年度に800人を超えていた新入生は本年度435人と、9年でほぼ半減したとの報道がありました。
昨日の高知新聞に、看護師を目指し、県内の専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク時の2015年度に800人を超えていた新入生は本年度435人と、9年でほぼ半減したとの報道がありました。
そんな中で、昨日の出先機関調査で訪ねた「幡多けんみん病院」での人材不足の課題と「幡多看護専門学校」での受験者・入学者の定員割れの課題についても聴かせて頂きました。
幡多は、地域内で完結しなければならない医療圏であるだけに、医療人材育成・安定確保は大変重要な課題であることを改めて考えさせられます。
不足してしまってから手を打つのでは、遅すぎるのであり、今から打てる手を打っておくことが重要です。
そのためにも、コロナ禍で顕在化した看護師をはじめとした医療従事者の過酷な労働条件や給与面での処遇改善や、県内でも遠隔地にある幡多看護専門学校では、学生のための寄宿舎の整備か借り上げなども検討してみる必要があるのではないでしょうか。
| 5月29日「憲法改悪先取りの地方自治法改悪は許せない」 |
 非常時に、国が自治体に必要な指示を出せるようにする地方自治法改悪案が、衆院総務委員会で与党や日本維新の会などの賛成で可決されました。
非常時に、国が自治体に必要な指示を出せるようにする地方自治法改悪案が、衆院総務委員会で与党や日本維新の会などの賛成で可決されました。
国会への事後報告を義務づける修正が加えられたが、閣議決定を経れば指示できる仕組みは変わらず、恣意的な運用の恐れも消えていないし、多くの疑問は残されたまま、審議を打ち切りで採決されました。
地方自治の在り方を大きく変えようとし、緊急事態条項改憲を先取りするような改悪法可決に対して、強く抗議せざるをえません。
政府は、大規模災害や感染症などの際に個別の法律で想定しない事態が起きた場合、国民の安全を確保するために必要だと説明するが、武力攻撃事態対処法で想定しない事態も視野にあるかについては、あいまいな答弁を繰り返し、有事の際に一方的に国に従わせることを可能とするような危うい改正も視野にあるのではないかと思われます。
特に、特定利用空港・港湾を全国で指定してきたこととも関連性があるのではないかと思わざるをえません。
有事の際に港湾や空港などを使うには、例えば特定公共施設利用法で自治体が国の要請に意見を申し出る規定があり、可能な限り慎重な手続きを踏むこととされている が、今回の改悪案では、国は国会承認なしに自治体に網羅的に指示ができ、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」の「おそれ」の段階で、自衛隊のための道路開放や攻撃に備えた自治体職員の動員協力にまで道が開けることとなります。
沖縄の基地移設で、埋め立て承認を県が拒否した際、政府は代執行までして工事を強行しており、自治体が思い通りに動かない時、民意を無視してでも国策を推進する意図が背景にあるのではないかと危惧します。
コロナ禍で、突然一斉休校を要請し現場を混乱させたり、熊本地震の際に、屋内避難を政府が指示した避難所の天井が余震で落下し、政府の指示に従っていたら大きな犠牲者が出ていたことも想定されたこともあり、けっして国の考えが常に正しいとは限りません。
地方の声を十分くみ取って審議が進んできたとはいえない中で見えるのは、自治体の現場重視の解決力や実情を軽視する国の姿勢が問われています。
地域の問題は地域で考えるという、地方自治の理念を後退させる悪法は許せません。
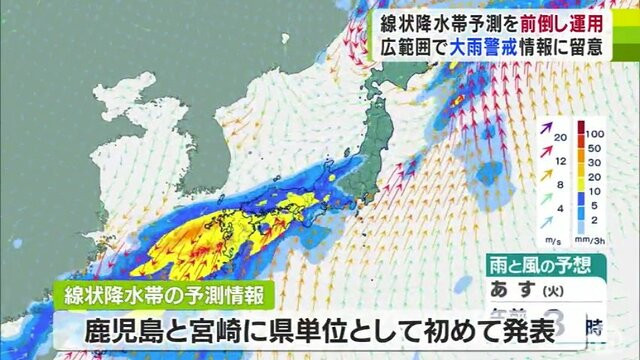
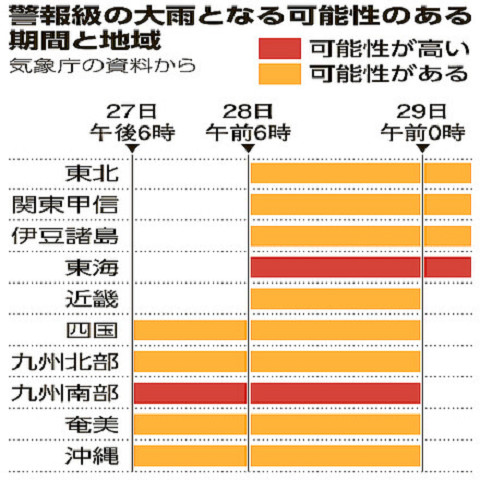 非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が昨夜から28日日中にかけて、宮崎と鹿児島(奄美地方をのぞく)の両県で発生する可能性があると、気象庁が27日午前に発表しました。
非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が昨夜から28日日中にかけて、宮崎と鹿児島(奄美地方をのぞく)の両県で発生する可能性があると、気象庁が27日午前に発表しました。
気象庁は、27日午前11時ごろ、線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけを実施しましたが、同庁は28日から従来の地方単位(全国11ブロック)での予測を県単位(同59ブロック)に狭める運用を始める予定でしたが、発生の可能性が高まったことを受けて運用開始を1日早めたものです。
集中豪雨をもたらす線状降水帯は夜間に発生するケースがあり、明るいうちに避難に活用できるように、気象庁は2022年から半日前予測を始めましたが、予測精度はまだ十分ではなく、的中率は「4分の1程度」とされているが、線状降水帯が発生しなくても大雨となる場合もあり、警戒は必要です。
高知県と徳島県でも、線状降水帯発生の恐れがあるとされており、災害発生も急に高まる可能性があり、今日一日十分注意をしなければなりません。
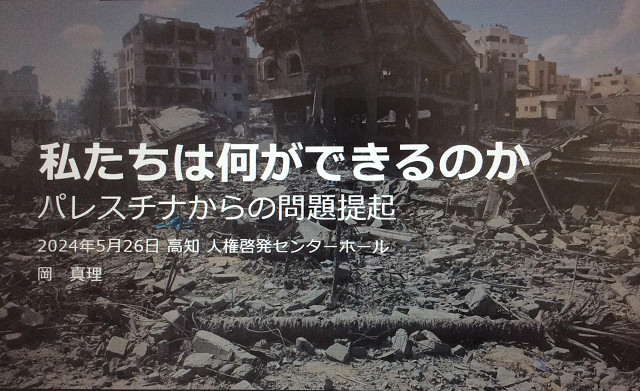
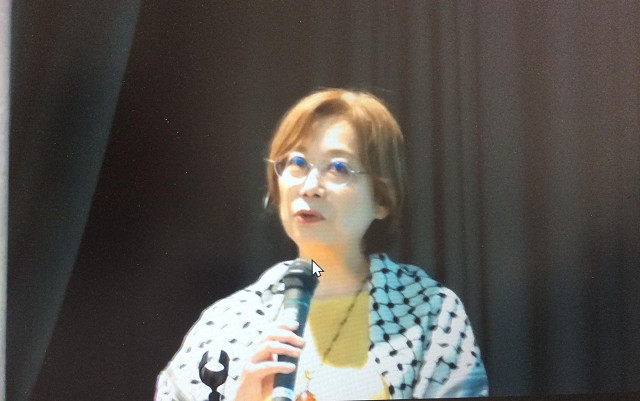
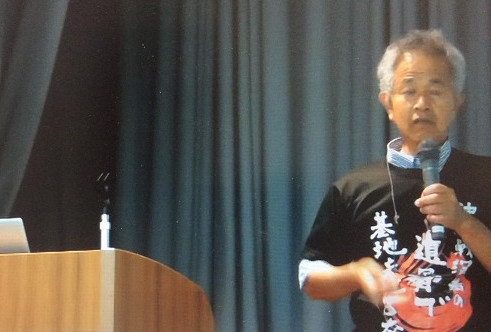
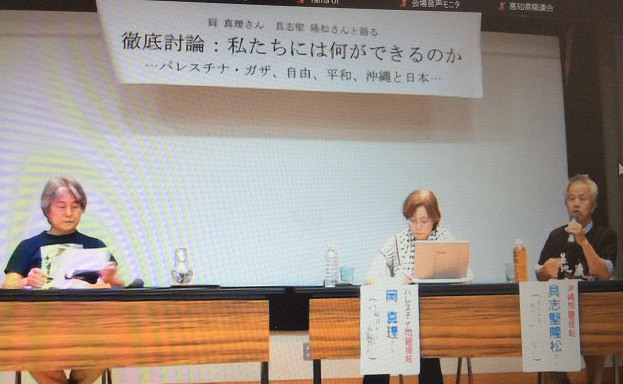
25日、26日と連続してパレスチナ問題に詳しい早稲田大学文学学術院の岡真理教授の「ガザとは何か」、沖縄戦の戦没者の遺骨収集を続ける「ガマフヤーの会」の具志堅隆松代表の「日本を戦場にさせない」ことについてのお話を聴かせて頂きました。
そして、ガザと沖縄に通ずる「構造的暴力」について考える機会を頂きました。
▼具志堅代表は沖縄の洞窟(ガマ)に眠る戦没者の遺骨を掘り、家族の元に返す取り組みを30年以上継続しているが、あろうことかその遺骨が眠る戦地の土砂を米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設のための埋め立てに使おうとしていることは許されない。
▼まさに、このことは人の道に反しているし、遺族と戦友に対する裏切りである。
▼今の政府はアメリカの都合によって作り出された台湾有事によって、日本を中国と争わせようとしている。日本を守るための戦争ではなくて、アメリカを守るための戦争であり、日本を戦場にさせない闘いが今こそ求められている。
▼我々には、戦争を起こさない責任がある。沖縄戦の実態を語る遺骨を埋め立てに使ってなきものにしようとしている。危機感が抗議になり、抗議が行動になることを願っていると訴えられました。
岡真理氏(早稲田大学文学学術院教授)からは、次のようなことに触れて、「ガザで今、何が起きているかを知りながら何もしないことは、加害者に加担することと同じだ」と指摘されました。
▼イスラエルによる電気や水、食料などの封鎖により、230万人のガザの市民生活は崩壊の淵に瀕している中で、ジェノサイドとも言える蛮行を繰り返しており、これを看過してはならない。
▼1948年のイスラエル建国はパレスチナ人に対する民族浄化であり、それから今日まで、イスラエルによる軍事攻撃は繰りかえされてパレスチナ人への暴力は日常的なものになっており、この歴史をふりかえれば、イスラエルはパレスチナ人を非人間化するアパルトヘイト国家だとわかる。
▼イスラエルによる攻撃開始から1か月で死者1万人超、うち子どもが4000人以上で、ウクライナでは2年間で死者10582人のうち子どもは587人を桁違いに上回っており、5月25日現在、死者35903人、負傷者80293人という実態を放置して、日本のメディアは日本人大リーガーの結婚報道などに終始し、爆撃のみならず栄養失調や劣悪な衛生環境が原因で日々、多くの子ども達が死んでいる現実をほとんど報じていない。
▼これはガザの人たちの命など取るに足らないといメタメッセージを発しているようなものである。
▼「民族浄化」「入職者植民地主義」「占領(ガザに生はない)」「封鎖(生きながらの死)」「アパルトヘイト」ということが報道から消し去られることに対して、我々はガザで今何が起きているのかを知り、そのような惨劇が起きている歴史的な背景を知った上で、日本が、そしてわれわれ一人一人が何をすべきかなどについて、考えるべきである。
▼アメリカはイスラエルのジェノサイドの共犯者であり、「日本はアメリカとともにある」などという日本も共犯者である。
▼占領、封鎖、貧困、飢餓、差別などという「構造的暴力」に徹底的に無関心なこの国であってはならない。
▼ 沈黙することはジェノサイドの共犯者になる。そうならないために、即時停戦を訴え、停戦になったら、イスラエルのアパルトヘイト廃絶のために声をあげよう。
ガザや沖縄、全ての不条理に無関心でいると自分の不条理に直面することになるということをしっかり肝に銘じて、我々は声を挙げていきたいものです。
| 5月25日「沖縄・ガザ問題で私たちに何ができるのか」 |
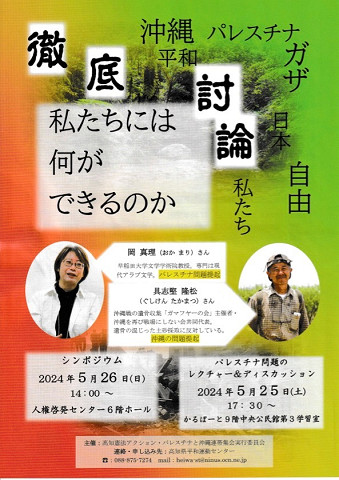 昨年10月7日のハマスによるイスラエルの抵抗以降、ガザにおけるジェノサイドは、もはや「皆殺し」状態をつくりだしています。
昨年10月7日のハマスによるイスラエルの抵抗以降、ガザにおけるジェノサイドは、もはや「皆殺し」状態をつくりだしています。
そして、沖縄では反対の県民世論を無視した総基地化が進められています。
そのような中で、パレスチナ問題が専門の岡真理さんと「亡くなられた方たちを家族のもとに帰したい」「二度と戦争を起こしてはいけない」との思いで、ガマで遺骨を掘る人(ガマフヤー)となり遺骨収集を始めて41年の、ボランティア団体「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さんをお招きした勉強会があります。
今回は、より深く掘り下げるためにということで今日、明日の2日連続で「徹底討論:私たちには何ができるのか~パレスチナ・ガザ、自由、平和沖縄と日本~」という討論会だそうです。
5/25(土)17:30~岡真理さん@かるぽーと9階第3学習室
5/26(日)14:00~岡真理さん・具志堅隆松さん@人権啓発センター
それぞれ参加費は1000円ですが、両日参加頂く方は1500円となります。
ぜひ、ご参加ください。


1966年に静岡県で起きた強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんの裁判をやり直す再審公判が22日、静岡地裁でありました。
検察側は改めて袴田さんが犯人だと主張、死刑を求刑し、弁護側は無罪を主張、結審しました。
判決は9月26日に言い渡されることとなります。
死刑が確定した事件の再審は戦後5件目で、過去の4件でも検察側は死刑を求刑したが無罪となっており、袴田さんも無罪となる公算が大きいと言われています。
裁判の最大の争点で、袴田さんの逮捕から約1年後に見つかった「5点の衣類」について、検察側は「被告の犯行時の着衣だ」と改めて主張したが、「捏造は実行不可能で非現実的だ」と述べるなど、従来の主張を繰り返したにすぎません。
一方の弁護側は、再審公判での審理で「5点の衣類」が捏造であることはよりはっきり確認され、血痕のDNA型鑑定などの結果からも「袴田さんのものでない」と改めて主張しています。
昨日の再審公判で、検察は改めて死刑を求刑しましたが、刑事訴訟法は再審について「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」を新たに発見したときに開くと定めています。
再審はたんなる裁判のやり直しではなく、誤判を受けた人の救済手続きであり、88歳の袴田さんの「人間らしい生活を取り戻すため」、これ以上の先送りは許されません。
そして、東京高裁の「袴田事件」の再審開始を決定以来、「次は狭山だ!」を合言葉に、狭山事件における東京高裁に事実調べを実現させ再審を開始を決意しあってきた運動の集約である5.23狭山中央集会が今日開催されます。
| 5月22日「ドン・キホーテ高知進出に地域の声は届くのか」 |
 ドン・キホーテの高知進出について、今朝の高知新聞で、「来年1月オープン計画 高知県に届け出 24時間営業」との見出しで、出店に関する届け出書を県に提出し、21日告示されたたことが報じられていました。
ドン・キホーテの高知進出について、今朝の高知新聞で、「来年1月オープン計画 高知県に届け出 24時間営業」との見出しで、出店に関する届け出書を県に提出し、21日告示されたたことが報じられていました。
それによると、同市東雲町と知寄町3丁目にまたがる用地に、鉄骨平屋建ての店舗を整備し、名称はドン・キホーテ高知店(仮称)、新設予定日は2025年1月20日で、24時間営業を行う計画となっているとのことです。
下知地区内で、すぐ近隣だけに、地域内の皆さんの関心は高く、昨年11月15日に地域と良好な関係を築くためにということで、事前説明会を開催され、多くの参加者からの質問、要請に対して、当時次のような考え方が示されていました。
「北側出入り口は、西進の入庫、東進の出庫となる。」「西側出入口からは、職員と搬入用に使う4トン車が出入りするが、搬入時間は住民に迷惑がかからないようにしていきたい。」「治安の悪化については、警察と連携しているのでそういう事は無い。」「睡眠時間帯にマイナスの影響を出さないように配慮していく。」「駐車場台数については、他の店舗規模から考えても、これ以上は増えない。」などとの説明があり、狭隘な北側道路からの出入り口はやめてほしいとの意見などが多数ありました。
その後、大規模店舗法に基づいて、3月中に届け出て、2ヶ月以内に説明会をする予定とのことでしたが、届け出自体が4月30日となったことから、説明会は6月下旬位になることが想定されます。
公示された書類を本日県経営支援課に行って、見せて頂いたところ、昨年の説明会で出された意見に対して改善対応をしたようには思えず、6月下旬の説明会では、周辺地域の声をしっかりと反映させていくことが必要になってくると思われます。
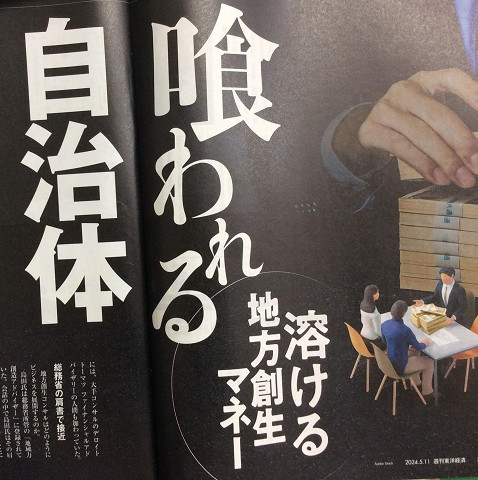 「地方創生が叫ばれて10年。実現できたという自治体はそう多くない。では、政府が流し込んだ膨大な『地方創生マネー』はどこへ溶けていったのか。」ということで、「週刊東洋経済」5月11日号は「喰われる自治体」との特集をしています。
「地方創生が叫ばれて10年。実現できたという自治体はそう多くない。では、政府が流し込んだ膨大な『地方創生マネー』はどこへ溶けていったのか。」ということで、「週刊東洋経済」5月11日号は「喰われる自治体」との特集をしています。
記事の冒頭は「自治体向けのコンサルティングを手がける会社社長が社外で語った音声データがある。『ちっちゃい自治体って(うちが)経営できるんですよ』『財政力指数は0.5以下(の自治体)って、人もいない。ぶっちゃけバカです。そういうとき、うちは第2役場。行政の機能そのものを分捕っている』」とワンテーブルの島田昌幸前社長の音声データの紹介から始まっています。
2014年の増田リポートで、当時の安倍政権が「地方創生」を煽って全国の自治体に地方版総合戦略の策定を要請し、策定費用として各市町村に1000万円ずつ予算措置したが、自治体によっては、その策定をコンサルに丸投げしたことが、当時から問題になっていました。
そして、受注したコンサルの実態が、その後いろいろと明らかにされ、この記事にも出てくる「ワンテーブル」の島田前社長は、「超絶いいマネーロンダリング」と言って行政機能を分捕ってきた結果として、島田氏は昨年5月末に社長を辞任し、総務省もアドバイザーの名簿から同氏を削除しました。
記事にもある「喰われた自治体」と「喰ったコンサル」との事例などについて、検証する中で、お仕着せでない地方創生、真に住民主体のまちづくりをするために「喰われない自治体」を住民と一緒になって築いていくことから始めなければならないかもしれません。
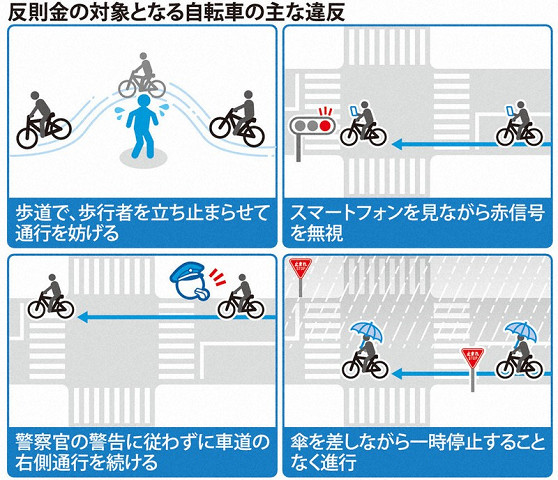
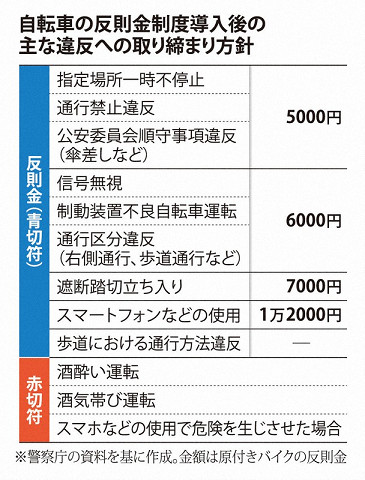 自転車安全利用5則が守れないなど自転車乗りのマナーが悪い傾向が続き、自転車が絡む交通事故も多いことから、自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立してしまいました。
自転車安全利用5則が守れないなど自転車乗りのマナーが悪い傾向が続き、自転車が絡む交通事故も多いことから、自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立してしまいました。
車の違反には、警察官に青切符を切られ、反則金を納めれば刑事罰を科されない仕組みがあるが、そこに対象外だった自転車も加えられ、公布から2年以内の2026年までに施行されることとなります。
自転車で反則金となる取り締まりの対象は16歳以上で、運転免許証の有無は関係なく、反則金は原付きバイクと同程度の5000~1万2000円の見込みで、今後決められるようです。
反則金の対象は113種類だが、自転車に当てはまらないものは除き、信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど事故の原因になりやすい9種類程度になる見通しです。
酒酔い運転や妨害運転(あおり運転)などは、これまで通りに刑事罰を科す赤切符で取り締まり、自転車の酒気帯び運転にも罰則を新たに設け、車と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、自転車の運転中にスマートフォンを使用する「ながら運転」も新たに禁止されます。
私たちも交通安全指導の際に、自転車安全利用5則遵守について啓発してきましたが、自転車は免許が必要ないため、ルールを正しく知らない利用者が多いことを痛感してきました。
警察庁が2023年に実施したアンケートでは、自転車のルールを守らない理由について「ルールをよく知らない」との回答が4割を占めているとのことです。
結局、違反者に対する罰則を厳しくしたとしても、周知されなければ「知らなかった」ですまされる違反運転による事故が減少しないのではないかと懸念されます。
これから、交通安全教育の中で、安全運転のマナー・ルールの周知が互いの命を守ることになることにつながる命の教育として行われることを期待します。

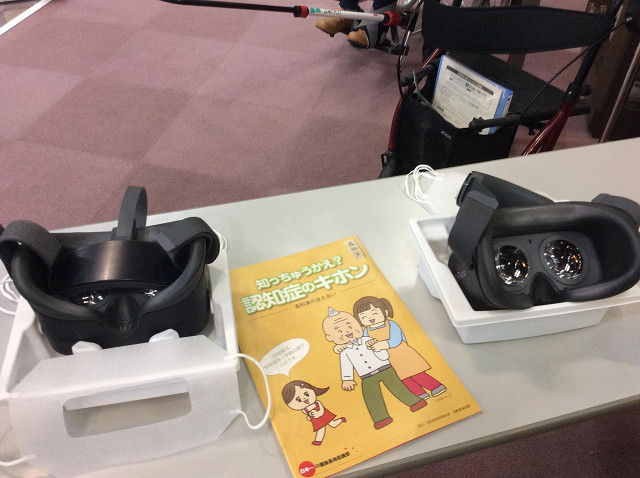

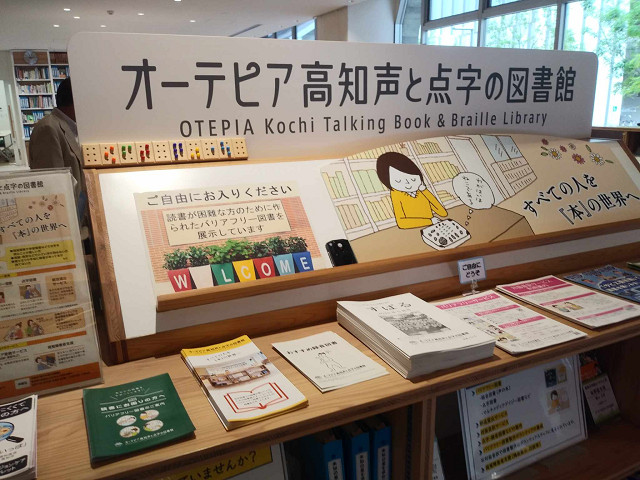

毎年、5月連休明けから、議会常任委員会による出先機関調査が行われます。
今年度は、危機管理文化厚生委員会に所属しており、昨日までに「精神保健福祉センター」「衛生環境研究所」「文学館」「統合制御所」「発電管理事務所」「高知声と点字の図書館」「高知城歴史博物館」「いの町保健福祉課農福連携」事業、就労継続支援B型こうち絆ファーム「TEAMいの」、「消費生活センター」「高知男女共同参画センター」「小動物管理センター」「女性相談支援センター」「高知難病相談支援センター」を訪問し、聞き取り調査、施設視察をさせて頂きました。
昨日は、高知県社会福祉協議会からスタートして、県立大学・工科大学の永国寺キャンパス、県立大学池キャンパス、高知医療センターと調査に伺いました。
それぞれに課題は、多くありますが、「県民誰もが安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現に向け」多様な地域福祉活動支援の取組をされている県社協の報告をしておきます。
取組の柱1「地域における福祉教育の推進」、取組の柱2「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の強化」、取組の柱3「南海トラフ地震等の災害に備えた支援体制づくり」、取組の柱4「あらゆる福祉人材の確保・育成・定着と質の向上」、取組の柱5「高知県社協の組織力・専門力の強化」を軸に、生活困窮者をはじめ多様な生きづらさを抱えた方々、災害時の支援などに取り組まれています。
そのような中で、新たな取組として災害ケースマネジメントの支援体制や孤独・孤立対策推進法にもとづく取組などにも積極的に取り組んで頂きたいことを要望させて頂きました。
県社協は市町村社協と災害時の広域支援に具体的に取り組んでいけるよう進めていることなどについても報告頂きました。
福祉交流プラザ内の福祉機器展示エリアの障害者の自転車競技用の自転車や認知症の疑似体験をさせて頂きました。
VR認知症疑似体験では、レビー小体型認知症の特徴でもある「幻視」体験もできます。私も、母がレビー小体型認知症でよく「〇〇さんが玄関に来ていた」とか話していた時の状態がよく分かりました。
「もっと生活しやすくなる用具はないか」「介護負担を少なくする用具はないか」などお困りの方はぜひ相談されるとよいと思います。(088-844-9271)
今朝からは、須崎市方面に回りますが、後25機関・施設が残っており、30日まで続きます。
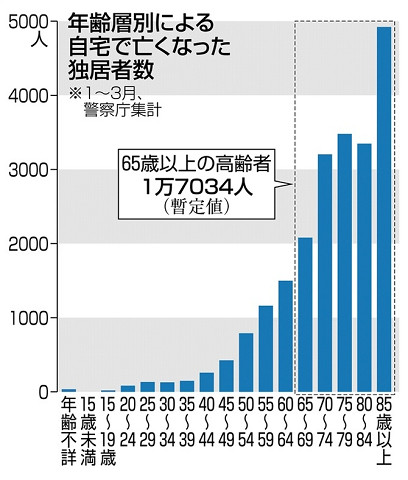 政府は13日、孤独・孤立問題への対策をめぐり、今年1~3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で計2万1716人(暫定値)確認され、うち65歳以上の高齢者が約1万7千人で8割近くを占める現状を明らかにしました。
政府は13日、孤独・孤立問題への対策をめぐり、今年1~3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で計2万1716人(暫定値)確認され、うち65歳以上の高齢者が約1万7千人で8割近くを占める現状を明らかにしました。
年齢が上がるほど死者数は増え、今回の3カ月分のデータを単純に年間ベースに置き換えると、65歳以上の死者数は約6万8千人と推計されます。
内閣府は、「誰にもみとられることなく死亡し、かつ、その遺体が一定期間の経過後に発見されるような死亡の態様」を「孤独死」と定義し、今後も実態把握を進めていく予定だと言います。
今年4月には孤独・孤立対策推進法が施行され、政府は、実態把握に加え、相談体制の整備や居場所の確保などの対策に取り組んでいるが、自治体段階でそのことが具体化されるには、まだ時間がかかりそうです。
「令和5年版高齢社会白書」によれば、令和3年現在、65歳以上の者のいる世帯数は2,580万9千世帯(全世帯の49.7%)にのぼり、夫婦のみの世帯及び単独世帯がそれぞれ約3割を占めていることが指摘されています。
また、1980年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める一人暮らしの割合は男性4.3%、女性11.2%だったのが、2020年には男性15.0%、女性22.1%と増加していることが指摘されました。
様々な実態の中から、なぜ孤独死・孤立死に至ったのか、公的支援・地域社会や人とのつながりがどう途絶えてしまったのか、問題の背景をより正確に理解した上で、さまざまな見守り体制から漏れ落ちる方がいないような仕組みが求められています。
| 5月15日「改悪地方自治法の『指示』が自治体へ服従を強いる恐れ」 |
 沖縄が、戦後27年間の米国の占領・統治を経て本土に復帰した1972年5月15日から52年が経過しました。
沖縄が、戦後27年間の米国の占領・統治を経て本土に復帰した1972年5月15日から52年が経過しました。
しかし、日本にある米軍基地の7割がなお沖縄県に集中するとともに、沖縄県民の意思は蔑ろにされ続け、政府は県の権限を奪う代執行までして、普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事を強行しています。
そんなことが当たり前のように行われるのではないかと懸念される地方自治法の改悪が、今国会で行われようとしています。
恣意的な解釈で物事を強引に進めていくのが安倍政権以降の自民党の特徴であり、その権力の下で、これまでの個別法で規定された指示と違い、一般法である地方自治法で規定される「指示権」は、その対象があらゆる地方行政の業務に広がるので、明らかに恣意的な運用の余地も広がるとの懸念が多くの自治体から出されています。
非常時に、最後は国が指示を出すことになると、自治体は、国からの指示権を待ち、国任せになり、国と自治体の対等の関係は一気に崩されてしまうことになることが、想定されます。
さらに、法改正で「指示待ち」の自治体が増え、岸本聡子杉並区長は、「非常時に自主的に動こうとする自治体が減る一方、自ら動く自治体への評価が厳しくなる恐れがある」と懸念しています。
国の「助言・勧告」や、情報提供を求める「資料提出の要求」には、いずれも法的拘束力はなく、自治体は従わなくても構わないが、「指示」には法的拘束力があり、自治体が従わなければ「違法行為」と判断される可能性があり、国が沖縄に対して行った代執行のようなことが、「想定外」の事態を大義名分にして濫用されるかもしれません。
この悪法が成立すれば、自治体は平時から国の顔色を伺い、「それは違う」と思っても反論しなくなり、ますます国と自治体の「対等な関係」は崩れてしまいます。
地方自治は、国から独立した団体によって運営されるべきだという憲法の趣旨にももとることがされようとしていることを看過してはならないし、こんなことが沖縄には復帰後52年間強いられてきたことを我が事として考えなければなりません。
| 5月14日「6割が不支持の内閣による政治資金規正法改正は8割が評価せず」 |
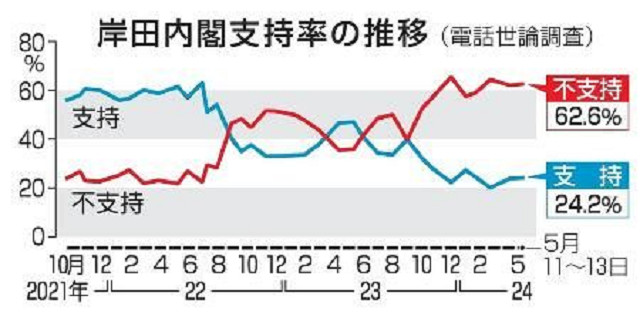
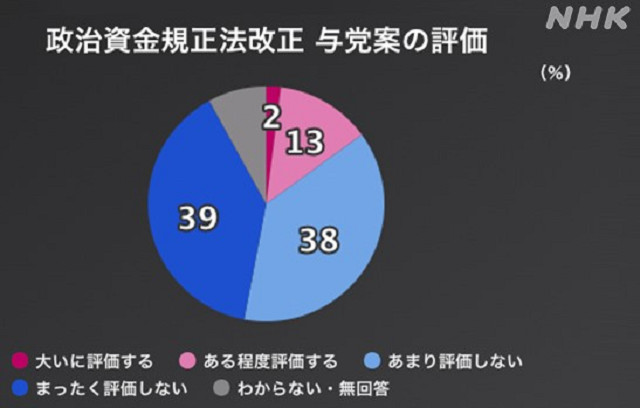 共同通信社が11〜13日に実施した全国電話世論調査で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正の与党案を「評価しない」との回答は79.7%に上り、政党から党幹部らに支出される政策活動費の扱いは「使途を細かく公開」52.0%、「廃止」26.8%と続いています。
共同通信社が11〜13日に実施した全国電話世論調査で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正の与党案を「評価しない」との回答は79.7%に上り、政党から党幹部らに支出される政策活動費の扱いは「使途を細かく公開」52.0%、「廃止」26.8%と続いています。
政治資金パーティーの規制強化策については、「収支報告書への不記載・虚偽記入の厳罰化」42.7%が最多で、「開催禁止」は24.7%、「企業や団体による券購入禁止」は15.9%、「券購入者の公開基準引き下げ」は8.9%と続きました。
また、内閣支持率は24.2%で4月の前回調査比0.4ポイント上昇の横ばいでした。
同じく昨日公表されたNHKの世論調査では、岸田内閣を「支持する」と答えた人は4月の調査より1ポイント上がって24%だったのに対し、「支持しない」と答えた人は3ポイント下がって55%でした。
支持率は、共同通信もNHKもほぼ同率で1/4にも満たない状況が続いています。
政治資金規正法の改正についての評価は、「大いに評価する」が2%、「ある程度評価する」が13%、「あまり評価しない」が38%、「まったく評価しない」が39%で、こちらも「あまり・まったく」をあわせて「評価しない」との回答は77%で、共同通信とほぼ同じく8割近い人が評価していません。
これらの世論と真摯に向き合えば、このような政治資金規正法改正の与党案でお茶を濁して終わりにするようなことはできないはずです。
いずれにしても、自公政権の終わりの始まりとも言える闘いに野党と国民は団結して闘う時を迎えていると言えます。
| 5月12日「成立しても、経済秘密保護法の危険性を批判し続けて」 |
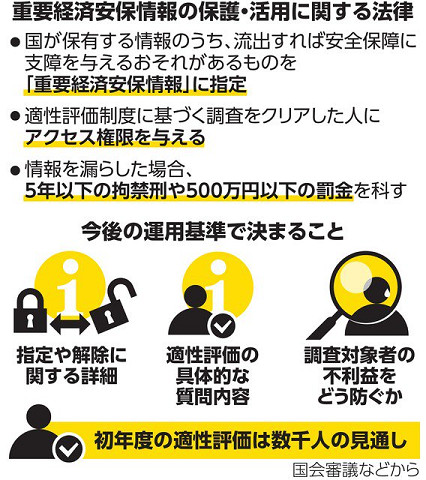 2月末に国会に提案されたいわゆる「経済秘密保護法案」(=重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案)は、私たちの反対の声にもかかわらず、4月8日に衆院本会議で可決され、5月10日参議院で可決成立してしまいました。
2月末に国会に提案されたいわゆる「経済秘密保護法案」(=重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案)は、私たちの反対の声にもかかわらず、4月8日に衆院本会議で可決され、5月10日参議院で可決成立してしまいました。
これは特定秘密保護法を経済と学術の分野に拡大し、軍事研究・軍需生産・武器輸出をすすめるのためのものだとも言われています。
秘密保護法対策弁護団が10日に「経済秘密保護法の成立に強く抗議し、同法と特定秘密保護法の廃止を求める声明」を出し、「法案は、特定秘密保護法を改正手続きによらず拡大するものであること」「秘密指定に関する監督措置が不十分であること」「法案による秘密指定の範囲は限定されていない」「コンフィデンシャル級の秘密指定は欧米では廃止されていて、法案は周回遅れのアナクロだ!」「数十万人の民間技術者・大学研究者が徹底的に身辺調査されプライバシーを侵害される」との理由で、反対してきたことを明らかにしています。
特に、特定秘密保護法の適性評価は主に公務員が対象であったが、経済秘密保護法では広範な民間人が対象となることが想定され、適性評価の調査は、政府委員は、どのような事項について調査しているかも、敵につけ入る隙を与えるので答えられないと答弁しています。
この点は、2013年に特定秘密保護法が成立した後の運用基準では、「評価対象者の思想、信条及び信教並びに適法な政治活動、市民活動及び労働組合の活動について調査してはならない。」と定められていたにもかかわらず、政府委員の頭からは、自らの定めたこの運用基準すら飛んでしまっていることが明らかです。
それで、特定秘密保護法の時と同様に「何が秘密か、それは秘密です」という代物になってしまっています。
戦争への道を開く経済秘密保護法の成立に強く抗議する悪法を止めるための活動は、仮に制定を止められなくとも、反対運動が盛り上がることによって、政府による法の濫用に対する歯止めとなります。
5月5日公表の産経新聞による調査では、主要企業110社から調査回答によると、「セキュリティー・クリアランス(適格性評価)」制度創設に賛成の企業は3割に届かず、プライバシー侵害などの懸念が根強いことが示されています。
5月8日の東京新聞では、福島国際研究教育機構(FREI)と、アメリカの核・原子力研究機関PNNLの協定締結の動きを取り上げ、法案が成立すれば、武器開発・核開発につながる先端技術の研究が秘密のベールで覆われる危険性も指摘しています。
今後予定される運用基準の制定過程で、成立した経済秘密保護法が真の悪法として猛威を振るうことのないよう、継続して粘り強く監視を続けるだけでなく、今回成立した法と特定秘密保護法の両法について、廃止を目指して闘い続けていく必要があります。
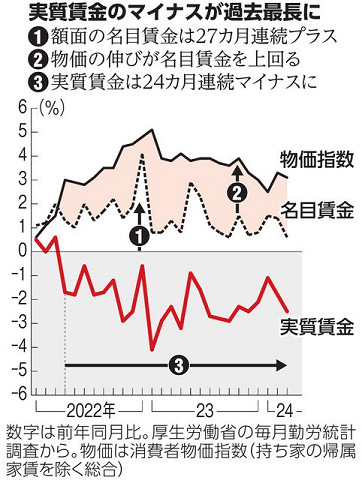
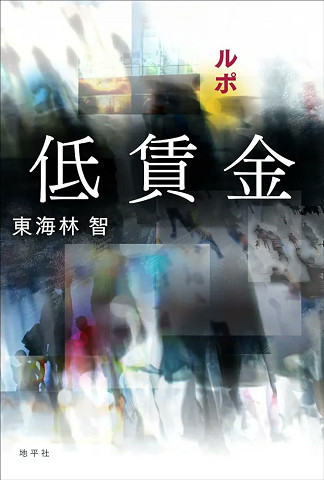 厚生労働省が9日公表した3月分の毎月勤労統計調査(速報)で、物価変動を加味し生活実感により近い実質賃金は、前年同月より2.5%減り、24カ月連続のマイナスとなったことが明らかになりました。
厚生労働省が9日公表した3月分の毎月勤労統計調査(速報)で、物価変動を加味し生活実感により近い実質賃金は、前年同月より2.5%減り、24カ月連続のマイナスとなったことが明らかになりました。
比較可能な1991年以降で、過去最長を記録したこととなります。
労働者が実際に受け取った「名目賃金」にあたる現金給与総額は、0.6%増の30万1193円で、一方、実質賃金の計算に使う3月の消費者物価指数は3.1%上がり、この物価上昇分を差し引いた実質賃金は2.5%減となり、減少幅も今年2月のマイナス1.8%(確定値)から拡大しました。
厳しい人手不足や賃上げ機運の高まりを受けて名目賃金は27カ月連続で前年を上回り、過去最長を更新しているが、その一方で、コロナ禍からの経済の回復やロシアのウクライナ侵攻により、原油や食料などの価格が高騰、歴史的な円安も輸入物価の上昇に拍車をかけ、物価は上がり続け、名目賃金が伸びているものの物価の上昇に追いつかない状況が続いています。
今年の春闘の賃上げ率は33年ぶりの高水準と言われていますが、給与への反映には数カ月の遅れが生じ、実質賃金への影響が出るのは先になる見通しで、非正規労働者の賃上げは一部に過ぎないとも言われています。
今、毎日新聞社会部の東海林智記者の新著「ルポ・低賃金」が明らかにする実態こそから、実感できる賃上げを闘いとる必要があるのではないでしょうか。

 5月1日、水俣市で開催された水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤環境相と患者団体との懇談の場で、発言時間に1団体3分という制限を設けた上で「時間なのでまとめてください」とせかし、発言者の男性のマイクの音を一方的に切った対応に、当事者・患者団体をはじめ多くの国民から批判の声が高まっています。
5月1日、水俣市で開催された水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤環境相と患者団体との懇談の場で、発言時間に1団体3分という制限を設けた上で「時間なのでまとめてください」とせかし、発言者の男性のマイクの音を一方的に切った対応に、当事者・患者団体をはじめ多くの国民から批判の声が高まっています。
伊藤環境相は就任後、水俣を訪れるのは今回が初めてで、訪問を控えた記者会見では、「地域の声を拝聴し、政府としてできる限りのことをしたい」と語り、懇談の冒頭に「みなさまのお話をうかがえる重要な機会だ」と語ったと言います。
その上でのこの対応に対して、患者団体側は「苦しみ続ける被害者たちの言論を封殺する許されざる暴挙」と抗議する文書を伊藤環境相宛てに送付しています。
昨年来、大阪と熊本、新潟の各地裁が水俣病と新潟水俣病に関して示した三つの判決は、今なお多くの被害者が救済から取り残されている現状を突きつけているだけに、このような対応を取る環境省の姿勢が改めて問われています。
岸田政権の「聞く力」の綻びがあちこちに生じているのは、まさに今の自民党政権とそれを支える官僚組織の本質であることが露呈したものだと思わざるをえません。
| 5月6日「『ケアラー』でも、学び続け、働き続けられるために」 |
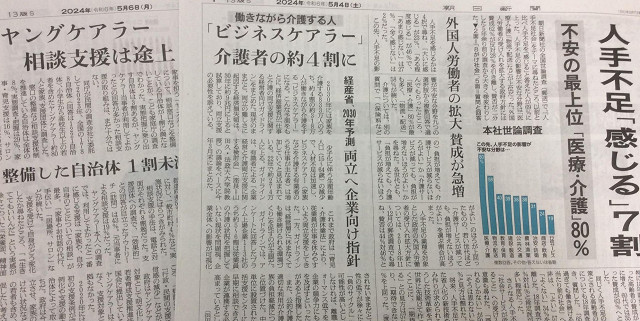
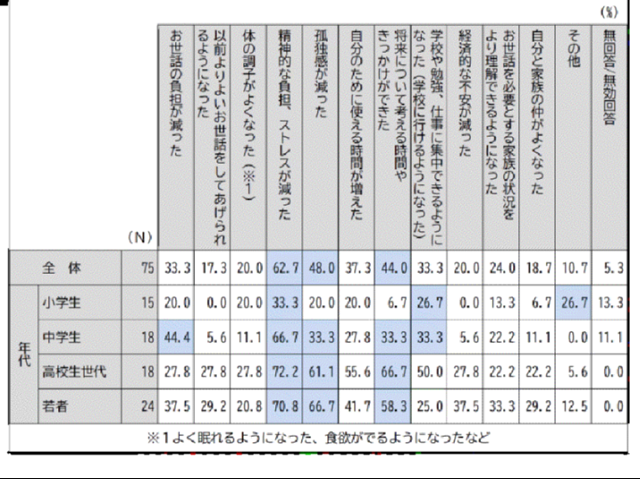
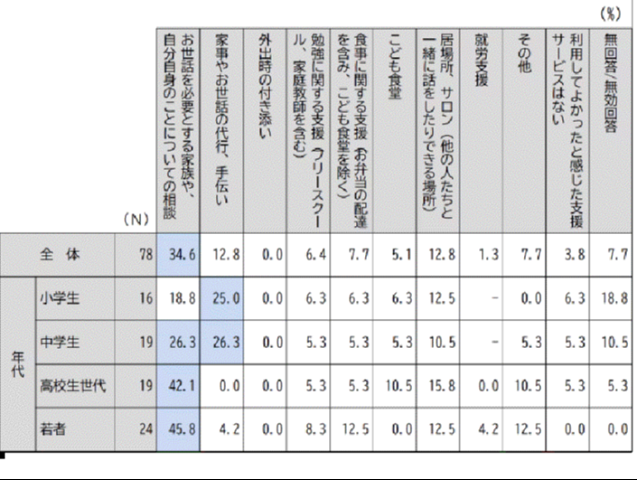
朝日新聞では、4日付一面で「ビジネスケアラー」についてとりあげ、今朝の一面では「ヤングケアラー」について取り上げています。
2030年には家族を介護する833万人のうち、約4割の約318万人が働きながら介護をする「ビジネスケアラー」になるとの予測のもと、経済産業省は「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」をまとめ、現状のままだと、両立の難しさに起因する経済損失額は、30年に約9兆円に上ると試算し、両立支援の必要性を訴えています。
そして、今朝の記事では、大人に代わって家族の世話や家事を担う「ヤングケアラー」について、相談窓口などを整備している自治体が1割に届かず、実態把握に乗り出す自治体は3割あるが、ヤングケアラー当事者が利用してよかったとの回答が多かった相談支援の取り組みは、まだ十分ではないことが、こども家庭庁の調査で明らかになっています。
相談支援体制の推進は、都道府県57%、政令指定市25%に対し、一般市町村4%など、実施状況にばらつきがみられ、相談支援の手法は、電話と対面がそれぞれ8割超で、支援団体への調査で、「効果的」との回答が目立ったアウトリーチ(訪問)は43%。元当事者による相談支援は19%で、ヤングケアラー本人への調査では、利用してよかったと一番に感じる支援は「家族や、自分自身のことについての相談」が最多。「家事やお世話の代行、手伝い」「居場所、サロン」などが続いています。
「ビジネスケアラー」にしても、企業の労働力確保の面だけでなく、家族の介護をしながら生きやすく、働きやすい雇用環境を創出し、「ヤングケアラー」の相談支援体制の充実も含めて、家族の介護によって学びや労働、生きがいが奪われることなく、困ったときは「助けて」といえる家族・地域・社会・職場を築いていけるような環境こそが、求められています。
| 5月5日「50年で半減した子どもたちを大切にする社会を」 |
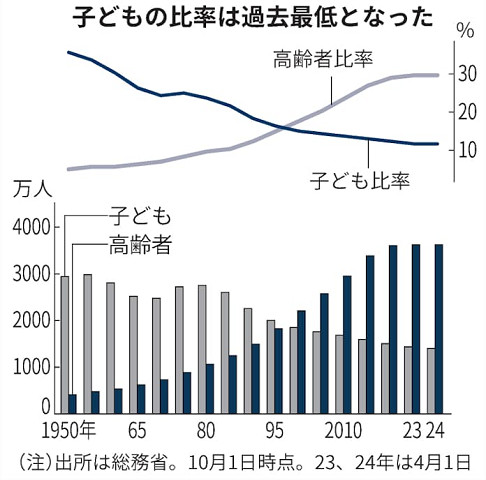
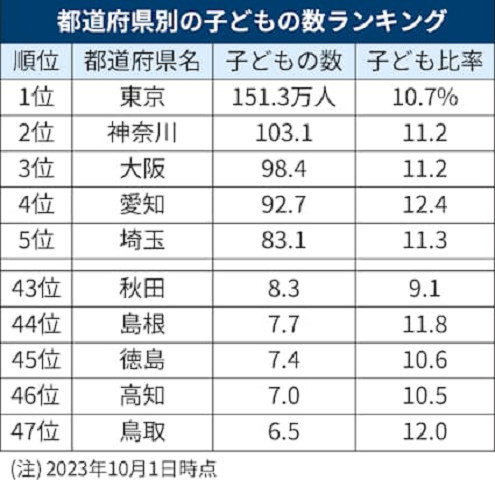 総務省が、人口推計から算出した子どもの数を4日に公表しました。
総務省が、人口推計から算出した子どもの数を4日に公表しました。
15歳未満の男女は4月1日時点で前年より33万人少ない1401万人で、43年連続で減少し、比較可能な1950年以降の最少記録を更新し、総人口に占める比率は0.2ポイント低下の11.3%で過去最低となりました。
1950年に子どもの数は総人口の3分の1を超えていましたが、その割合は75年から50年連続で低下し、過去最低となり、その一方、65歳以上の高齢者の割合は29.2%で最も高くなっています。
都道府県別にみると、2023年10月1日時点で子どもの数は47都道府県すべてで前年より減少し、子どもの割合が最も高かったのは沖縄県の16.1%で、滋賀県の13.0%、佐賀県の12.9%が続き、最も低かったのは秋田県で9.1%で、本県は10.5%で、子どもの数は7万人でした。
子どもの権利尊重をうたった「こども基本法」が施行され1年余りが過ぎましたが、政府が目指す「こどもまんなか社会」実現への取り組みは緒についたばかりです。
昨年12月に策定した「こども大綱」で、子どもが「権利の主体」であると明記し、貧困や虐待を防ぐ対策のほか、学童期・思春期における心のケアや居場所作りなども盛り込まれていますが、これらがいかに実効性を持つようなを施策の具体化が図られるかが、問われています。
| 5月4日「地震が今年特に多いわけではなく、いつ起きても不思議でないとの備えを」 |
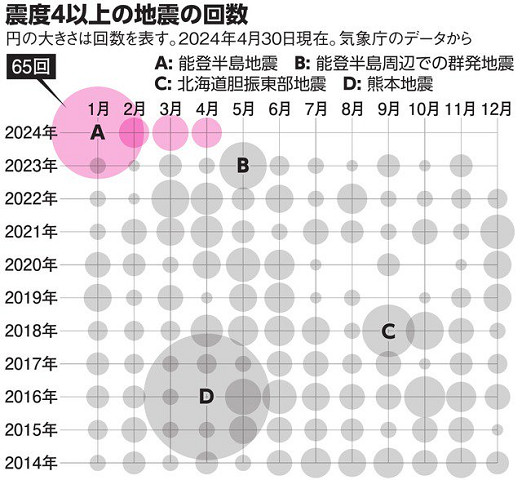 今朝も、最大震度3の余震が南予や高知県西部でおきました。
今朝も、最大震度3の余震が南予や高知県西部でおきました。
1月1日の能登半島地震や4月17日の豊後水道を震源とするマグニチュード6.6の地震で、南予と宿毛市で震度6弱を観測したことによる余震などからも、最近地震多くない?との声が高まっています。
今朝の朝日新聞によると、確かに地震は相次いでいるが、地震学者や気象庁の担当者は「統計的には普通の頻度」と口をそろえているそうです。
気象庁によると、今年1~4月末に、「ほとんどの人が驚く揺れ」とされる震度4以上の地震を全国で89回観測しているが、直近3年の同期間で、震度4以上の地震は2023年は9回、22年は22回、21年は21回とのことです。
これをみると、24年の89回は突出していますが、元日の能登半島地震に関連する66回を除くと、おおむね横ばいになり、政府の平田直地震調査委員会委員長(東大名誉教授)は4月の会見で、「統計を見れば、今が非常に多いということはない」と答えています。
直近10年間(14年5月~24年4月末)をみると、震度4以上の地震は717回で、その前の10年間(04年5月~14年4月末)は831回、さらにその前の10年間(1994年5月~04年4月末)は701回と、おおむね横ばいだが、なぜ多いと感じるのでしょうか
高知に馴染みが深く、地区防災計画でもご指導頂く矢守克也・京大防災研究所教授は「人々が社会現象として地震を体験するようになっているからではないか」との見方を示されています。
SNSが一般化し、ニュースサイトや防災アプリも充実し、「遠地の地震情報に触れる機会が増え、自然現象として体感するだけでなく、社会現象としての地震を経験するようになった」とことから、「最近地震が多い」の実態は、「最近地震に関する話題や投稿が多い」ということなのだと指摘されています。
南海トラフ巨大地震に限らず、大地震はいつどこで起きてもおかしくないとされている中、気象庁の原田智史・地震津波監視課長は「地震が多い気がするとなんとなく怖がるのではなく、日頃の備えを充実させるきっかけにしてほしい」と話されており、我々も肝に銘じておく必要があります。


 日本国憲法は今日、1947年の施行から77年を迎えました。
日本国憲法は今日、1947年の施行から77年を迎えました。
その憲法を9条を中心に変えたくてたまらない人たちがいる中で、世論は平和と人権と民主主義を守るために抗ってきました。
今年のマスコミ調査などによるその動向に、注視したいと思います。
読売新聞社の全国世論調査では、憲法を「改正する方がよい」との回答が63%と、3年連続で6割台、「改正しない方がよい」は35%でした。
毎日新聞の全国世論調査では、岸田首相在任中の憲法改正について「賛成」は27%で、「反対」の52%を下回り、22年4月の調査以来、2年連続で「賛成」が減少する一方、「反対」が増加しています。
共同通信社の世論調査では、岸田首相の任期中の憲法改正の国会議論に関し「急ぐ必要がある」は33%にとどまり、「急ぐ必要はない」の65%と差が開いており、9条改正の必要性は「ある」51%、「ない」46%と賛否が拮抗しています。
朝日新聞では、「戦争放棄や交戦権の否認などを定めた憲法9条」改正の是非は「変えるほうがよい」が32%、「変えないほうがよい」が61%です。
この質問は2013年から毎年の調査で聞いており、「変えるほうがよい」は13年の調査で39%と比較的高かったが、14年以降は30%前後で推移しています。
そのような中で、3日付けの神戸新聞では、「憲法は、戦後復興の険しい道を照らす光となった。人権が危機にさらされる災害時にこそ、その理念を追求し、実践する意義があるはず」と「社説」で述べています。
私たちが、日頃ご指導頂いている兵庫県弁護士会の津久井進さんは、相次ぐ災害の被災地で法律相談に取り組んでこられた中で、復興のさまざまな壁にぶつかり、あるべき法制度を研究するうち「憲法はこの国の復興を目指してつくられた。復興基本法は憲法だ」との考えに至ったと言われています。
津久井弁護士は「災害法制は被災者の生活と幸せを回復するためにある。その理念に沿って運用すれば、これほど悲惨な状況は生じないはず。行政は細かい基準にとらわれ憲法の理解が欠けている」と指摘されていますが、「支援制度の線引きからこぼれる人がいないよう関係機関が連携し、一人一人の困難さに応じて支える災害ケースマネジメント」に取り組む上でも、憲法理念をより具体化していくことこそが求められています。
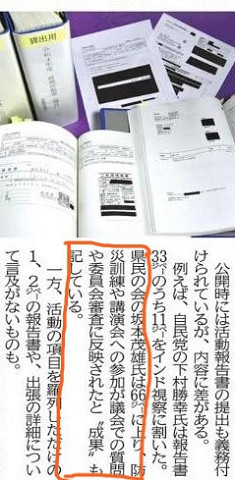
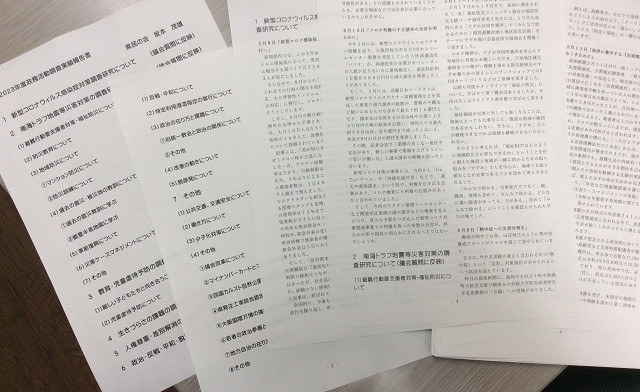 毎年のゴールデンウィークは、政務活動の前年度実績報告まとめに追われる日々を過ごしています。
毎年のゴールデンウィークは、政務活動の前年度実績報告まとめに追われる日々を過ごしています。
昨年も、高知新聞で、政務活動費の公開について、使途への疑問や活動実績報告の濃淡の問題などが取り上げられ、その中で、私の報告書が66頁もあるとのご紹介がありましたが、今年も結局67頁となりました。
時間と関心のある方は、こちらからご覧いただけたらと思います。
今年は、何とかGW前半で、まとめることができましたので、後半は地域活動の中でも最もウエィトの大きい防災・減災活動の昨年度の実績報告と今年度事業計画を作成しなければなりません。
| 5月1日「増え続ける空き家、『住宅過剰社会』放置のままでよいのか」 |
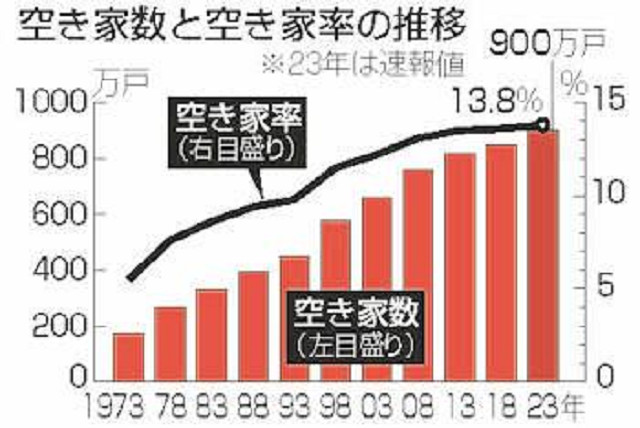
 総務省が昨日発表した2023年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報値)によると、全国の空き家数は900万戸と増え続けている実態が明らかになりました。
総務省が昨日発表した2023年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報値)によると、全国の空き家数は900万戸と増え続けている実態が明らかになりました。
前回18年から51万戸増え、過去最多を更新しており、30年前の1993年(448万戸)から倍増しています。
総住宅数は、世帯数の増加により261万戸増の6502万戸で、このうち空き家が占める割合(空き家率)は13.8%と、いずれも過去最高となっています。
総務省統計局は、過去最多となった要因について「単身高齢者世帯の増加に伴い、亡くなったり施設に移ったりした後、空き家になるケースが増えていると考えられる」としており、今後は団塊の世代の高齢化が進み、空き家は更に増えるとみられています。
空き家のうち、賃貸用や売却用、別荘などに該当せず、使用目的のない物件は前回から37万戸増え385万戸で、空き家全体に占める割合は42.8%と、03年から増え続けています。
中でも、使用目的のない空き家の割合に限ると、高知は鹿児島(13.6%)に次いで、12.9%となっています。
数年前に、高知で講演して頂いた明治大学野澤千絵教授は、新築や中古住宅のリフォームには税制上の優遇措置があるにもかかわらず、家を解体して更地にすると固定資産税が高くなることも空き家の解消が進まない理由にあげており、「家を作るばかりでなく、住まいの『終活』を支援する制度がもっと必要ではないか」と指摘されています。
空き家問題は、野澤教授が著書「老いる家 崩れる街」の中でも指摘されているように「人口減少社会」に「住宅過剰社会」という流れに歯止めがかからない限り、空き家は増加し、資源の無駄遣いや倒壊の危険性増大、防犯上の問題を引き起こすことになり、活用できる不動産でさえ「負動産」になってしまいます。
少子高齢化社会では、誰にでも降りかかってくる明日は我が身の問題であり、今能登半島地震の被災地で進まない公費解体の問題にも通じるだけに、南海トラフ地震対策の視点も取り入れ、さらに県の施策も拡充させていく必要があるのではないかと思います。
| 4月30日「ひきこもり支援は本人目線で寄り添って」 |

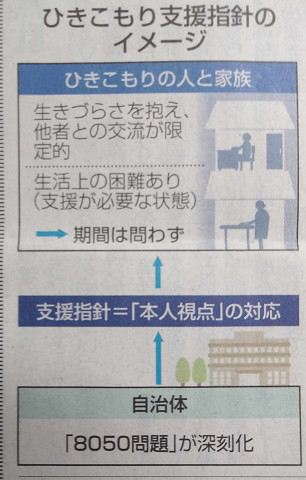 ひきこもりの人や家族の支援のため、厚生労働省が自治体向けに初めて策定する指針の骨子が昨日明らかになりました。
ひきこもりの人や家族の支援のため、厚生労働省が自治体向けに初めて策定する指針の骨子が昨日明らかになりました。
支援の指針では、ひきこもりは生活困窮やいじめ、リストラといった問題から身を守ろうとして、誰にでも起こり得る社会全体の課題だと指摘し、「人としての尊厳」を守り、本人の視点に立った対応を求めるなど、支援のポイントを盛り込み、2024年度中に完成させた上で、全国の相談窓口で活用してもらうとのことです。
最近は、「8050問題」と言われ、長期のひきこもりによって80代の親と50代の子が孤立するなど深刻化し、家族が自治体に相談しても無理解や偏見から窓口をたらい回しにされたりすることもあり、本人や家族の当事者目線で、支援することが求められていました。
指針の名称は「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤」とされ、対象は「何らかの生きづらさを抱え、他者との交流が限定的」「生活上の困難を感じ、支援を必要とする状態」の人や家族としています。
ひきこもり期間は問わず、支援者自身も思うような成果が出ずに悩むことがあり、ケアの対象に加えており、当事者に対して自立を強いるような風潮に対し、「人として尊厳ある存在」と強調し、就労などを一方的に押しつけず「本人の意思を尊重し、自律の力を中心に置いた支援が求められる」とされています。
ひきこもり当事者や御家族、支援者の方々と関り始めて20年近くになりますが、全国ひきこもり KHJ 親の会の故奥山初代代表や高知県支部「やいろちょう」の坂本代表などに教えて頂くことの多かった中、当事者、家族の皆さんのご尽力でここまで来たのかなと思います。
厚労省は今後、相談からの流れ、アウトリーチ(訪問支援)、他機関との連携など具体的なポイントを盛り込み、指針を完成させるとのことですが、当事者や関わる皆さんの目線で寄り添えるきめ細かな相談・支援体制ができることを期待しています。
| 4月29日「戦争を回避することに尽力した時代があった」 |

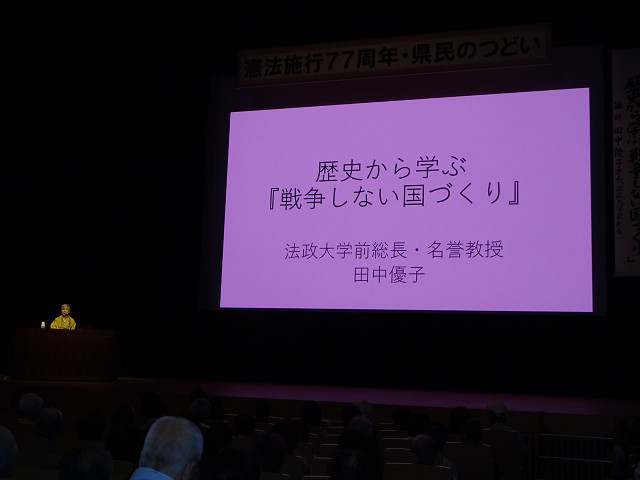 昨日は、午後2時からの憲法講演会で、テレビでもおなじみの田中優子法政大学前総長・名誉教授の「歴史から学ぶ『戦争しない国づくり』」を聴講のため、カルポートに行ってきました。
昨日は、午後2時からの憲法講演会で、テレビでもおなじみの田中優子法政大学前総長・名誉教授の「歴史から学ぶ『戦争しない国づくり』」を聴講のため、カルポートに行ってきました。
会場に300人、サテライト会場・オンラインで200人と合計500人の皆さんが、熱心に耳を傾けました。
「約250年間、内戦も国外との戦争も回避した江戸時代」は、「循環システムの整備により、持続可能性社会を作り上げた時代」であり、「周辺諸国との外交関係、ヨーロッパとの通商関係を樹立し、世界中の情報を得ることで、輸入依存から国産技術へ転換し、大量の職人を輩出し、『ものづくり日本』を創造した時代」であったと述べられました。
「明の国から40年間で10回余り援軍が求められたが、応じたら戦争に巻き込まれるということで、全て断った」ことや万民を救済する「経済」の一例に、納得させられました。
それは、1657年の「明暦の大火」の後に、将軍家綱の補佐役・保科正之が、米倉を開いて庶民に粥を配り、16万両を幕府から拠出して類焼被害にあった人々を助けたり、江戸城消失の再建は執務・住居部分として、戦争のない時代に天守閣は必要ないとして再建せず、玉川上水の江戸への引き込みをより重視したことでした。
まさに、今能登半島地震の災害復興を急ぐためには、万博を中止するとの声に応えない今の政府との違いにも通ずることを指摘されていました。
いろいろと問題はあった江戸時代ではあったかもしれませんが「戦争を回避する」ために、大変な努力を続けられたことに対して、我々の時代は、「いかなる人であっても生きて人生をまっとうする人権」を真ん中においた闘いで、憲法の精神を実現することだと強調されました。
「自民党が改憲せずとも、閣議決定や法律で空洞化させてくるのなら、我々は憲法を変えずに、よりその精神を実現していくことを目指すこと」や「憲法精神を具体化・実現していく上で、共感を広げていくことの大切さ」なども含めて 、貴重なお話が聞けました。
| 4月28日「人権侵害に苦しむ外国人、歴史から学ぶ戦争しない国へ」 |
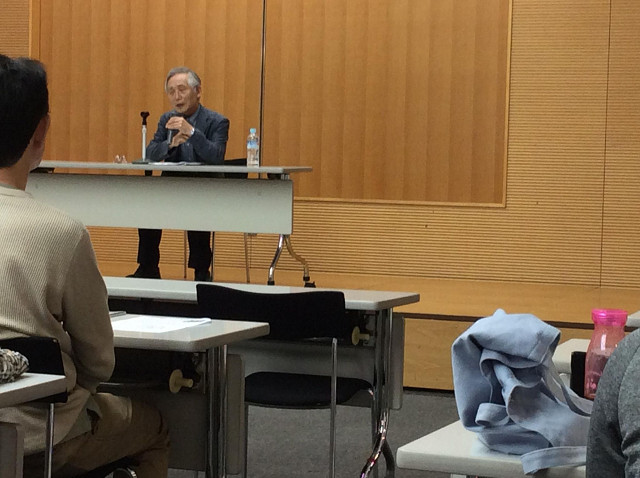
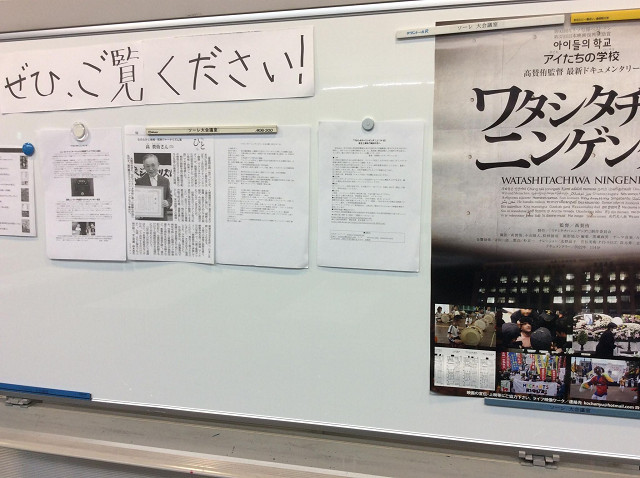
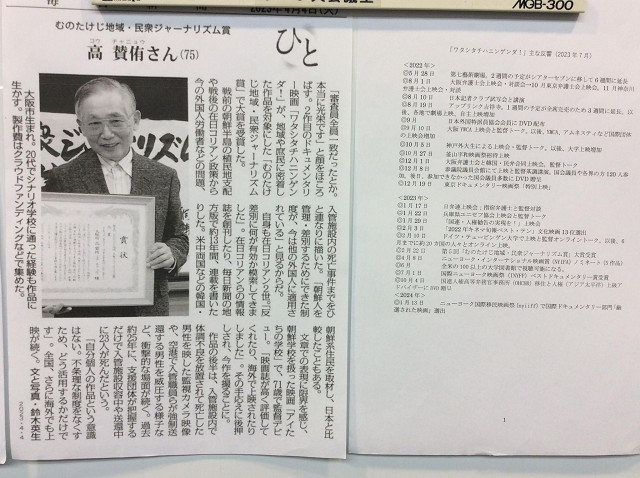 昨日は、ドキュメンタリー映画「ワタシタチハニンゲンダ!」(2022年公開・高賛侑監督)を鑑賞し、高賛侑監督のお話を聞かせて頂きました。
昨日は、ドキュメンタリー映画「ワタシタチハニンゲンダ!」(2022年公開・高賛侑監督)を鑑賞し、高賛侑監督のお話を聞かせて頂きました。
監督が、映像として、描くことが難しかったと言われていましたが、日本政府と在日朝鮮・韓国国籍の方々の歴史に始まって、朝鮮学校の高校授業料無償化対象からの除外、ヘイトスピーチ、難民認定、入管における収容や処遇等の様々な外国人の人権にかかわる問題が多くの当事者、支援者、弁護士等からの取材に基づいて明らかにされていました。
名古屋入管に収容中であったスリランカ国籍の女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件によって大きくクローズアップされた国人の人権保障の実態と日本政府の外国人人権の認識の問題ではあるが、監督に言わせれば、諸外国と比べてその差別性は異常であるとのことでした。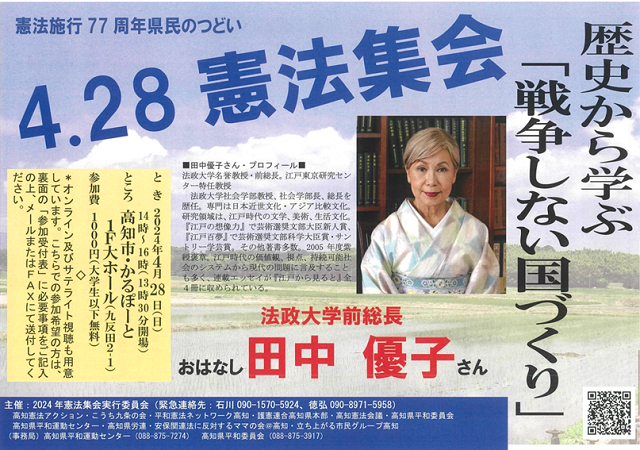
人権侵害に苦しみ、不当な扱いを受けている外国人たちの「私たちは動物ではない。人間だ!」との訴えと、「国家が率先して差別していることを描き、観た人たちに何かをしてもらいたいと思っている」監督の思いを広げていくために、少しでも多くの人たちにこの映画を観てもらいたいものです。
今日は、午後2時からの憲法講演会でテレビでもおなじみの田中優子前法政大学総長の「歴史から学ぶ『戦争しない国づくり』」を聴講のため、カルポートに向かいます。
 4月22日付高知新聞で、連載が始まった「自治のかたち 高知市・地域活動の現場から」では、「町内会って何ですか?会長の苦悩分割?合併?」から始まり、「ごみ当番、広がる外注 町内会未加入者へ募る不満」「やれるもんがやるしか 高齢者見守り、誰が担う」「官製でコミュニティー再生 小学校区で再編、温度差も」と続き、今朝の「世代間の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」で最終回となりました。
4月22日付高知新聞で、連載が始まった「自治のかたち 高知市・地域活動の現場から」では、「町内会って何ですか?会長の苦悩分割?合併?」から始まり、「ごみ当番、広がる外注 町内会未加入者へ募る不満」「やれるもんがやるしか 高齢者見守り、誰が担う」「官製でコミュニティー再生 小学校区で再編、温度差も」と続き、今朝の「世代間の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」で最終回となりました。
まさに、このタイミングは、町内会をはじめとして地域組織、団体の総会時期でもあり、関わっているものにとっては、考えさせられる記事ばかりでした。
私も、連日のように地域の各種団体の総会に出席しているが、同じメンバーが顔を揃えることも多く、昨夜の交通安全会議の総会後に、この記事のことを話題にしたが、最もこの課題に関心を持って頂きたい役員の中でも「若い」とされる層の方は「新聞取ってない」という状況も浮き彫りになりました。
これまで、地域組織・団体をになって頂いた方の高齢化で、その担い手をどのように世代交代していくのか、どこの地域でもご苦労されていることだとは思いますが、最終回の「世代間の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」は、少なからずヒントになるのではと、思ったことでした。
結び目から関わってくれた人たちが、LINEグループでつながり、また次の世代のことを考えながら、可能なきっかけから無理をしない関りを探っていくことが求められているのかもしれません。
地域で「防災」に取り組むために「わがこと」化することの大切さを訴えるが、地域で抱える課題や個人毎の困りごとが、どんな拍子で「わがこと」として直面するかもしれないのですから、平時から「つながる」ことにも、少し関心を持っていただくお隣さんがいたら、「あいさつ」のひと声から「結び目」ができることを期待したいものです。

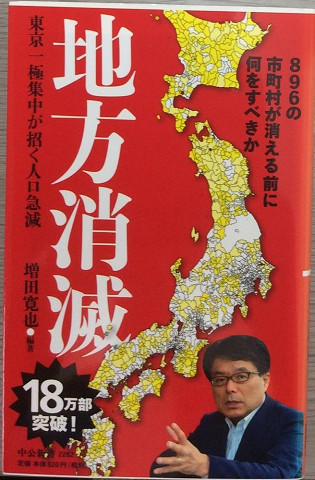 10年前に、増田リポートが出されたとき「896の市町村が消える『地方消滅』」と言われ「消滅可能性自治体」が名指しされました。
10年前に、増田リポートが出されたとき「896の市町村が消える『地方消滅』」と言われ「消滅可能性自治体」が名指しされました。
そして、今回は「744自治体に消滅の可能性」と名指しされました。
前回と比べ、消滅可能性自治体から脱した自治体は239に上り、一方で、新たに該当した自治体は99に上っています。
だとしたら、この10年間で消滅可能性自治体から脱した自治体は、何をして脱したのか、逆に新たに該当した自治体では、手をこまねいていたのか。
これまでの10年を総括しながら、これからの自治体のあり方が議論されることになるとは、思うが、移住促進という人口の「奪い合い」をこれからも、継続するのか。
競って奪い合いをするだけでなく、むしろ、じっくりと地方で少子化対策を中心に、暮らしやすく働きやすく、子育てしやすい地域社会や自治体がつくられていくことで、人口減少に歯止めをかけていくことが、求められているのではないでしょうか。
そして、多少人口が減って「机上の消滅可能性」が高まったとしても、地域住民、移住者、関係人口がいい関係性を築き、地域内での経済循環が促されるような施策に力を入れる中で、国全体の底上げにつなげて行くことになればと思ったりしています。
しかし、むやみな自治体間競争や「選択と集中」による自治体切り捨てなどということだけは、させないようにしていかなければと思います。
| 4月23日「自民党は本気で政治資金規正法を改正できるか」 |

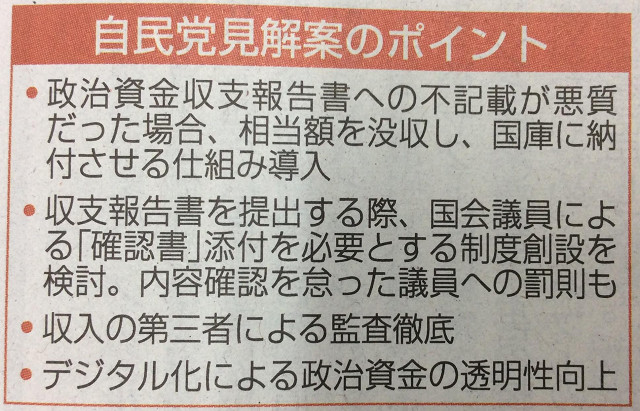 朝日新聞社の直近の全国世論調査(電話)によると、自民党の派閥の裏金問題について、実態が「解明されていない」と答えた人は92%に達し、「解明された」という人は5%でした。
朝日新聞社の直近の全国世論調査(電話)によると、自民党の派閥の裏金問題について、実態が「解明されていない」と答えた人は92%に達し、「解明された」という人は5%でした。
自民党が関係議員に行った処分に「納得できない」は67%にのぼり、「納得できる」は24%、党総裁である岸田首相の処分見送りに「納得できない」は66%、「納得できる」は24%だったことも、含めて関係議員の処分などで、問題の幕引きはできそうにもありません。
そのような中で、自民党自らが迫られていた政治資金規正法改正案の概要では、政治資金収支報告書への虚偽記載などがあった場合、議員本人が罰金刑となる要件を拡大し、悪質な不記載があった場合は不記載額を国庫に納付させることなども盛り込まれるとのことです。
党関係者によると、議員が会計責任者の「選任」か「監督」のいずれかで相当の注意を怠った場合、議員を罰金刑の対象に含めることで罰則を厳しくし、収支報告書を提出する際、議員による「確認書」の添付を義務づける制度も検討しているとのことで、今日にも党政治刷新本部の全体会合を開いてとりまとめられます。
26日に初開催される衆院政治改革特別委員会で各党が法改正に向けた考え方を表明することとなっているが、国民に理解される政治資金規正法の改正案となるのか、注視していきたいと思います。
| 4月22日「これも防災 復活『おしゃべりカフェ』」 |




21日(日)に、コロナ禍で休止していた小倉町東丸池防災会とアルファステイツ知寄II防災会共催の「おしゃべりカフェ」が4年ぶりに再開しました。
当時と同じく20人ほどの参加者が五目チラシとミニソーメンのセットに舌鼓をうちました。
ミニソーメンは市販のものですが、五目チラシは町内会防災会の皆さんで作って下さったものです。
物価高騰ではありますが、価格据え置きの500円ワンコインです。
さらに、今までの食後のインスタントコーヒーが、今回からは、日の出弥生町防災会の助っ人による挽きたてコーヒーでさらに話も弾みました。
この取り組みは、「下知地区防災計画」にある日常から地域コミュニティの活性化を図ることで、災害に「も」強い、災害時に助け合える街にしていくことを目指して、「地域の交流を深める」ために「津波避難ビルに住んでいる人と、津波避難ビルに逃げるかもしれない人が顔見知りになるようにする。」計画の具体化として、スタートしました。
地区防災計画全体で多くのアイデアが出された中から、効果や実現可能性を考えた「下知ベスト10」とし、優先項目として、その中の「地域コミュニティの活性化、近所同士が顔なじみになるようにする。地域コミュニティ活性化のための様々な行事を行い、住民同士が顔見知りになり、いざというときに助け合える関係構築。」の一つです。
今日も、久しぶりの開催ということもあって、約一時間半のランチタイム、コーヒータイム、おしゃべりタイムで賑わいました。
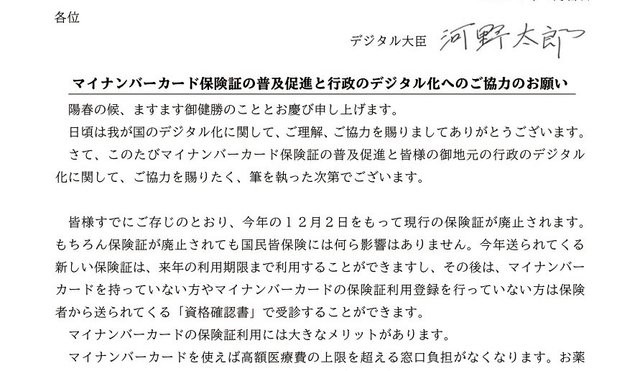
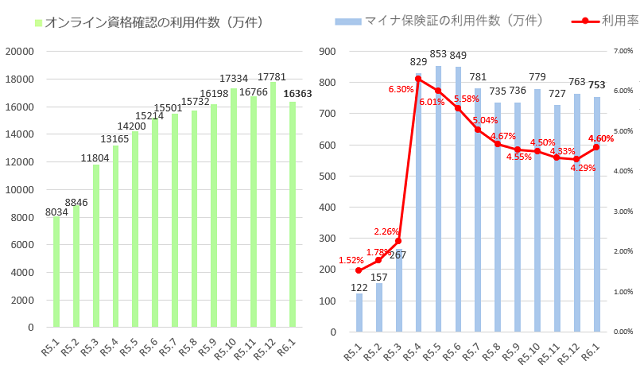
厚生労働省は、「マイナ保険証」の3月の利用率が5.47%だったと発表し、前月(4.99%)からわずかに増えたが依然低迷しており、医療機関に最大20万円を支給して患者への働きかけを促すとしています。
上限は病院が20万円、診療所と薬局は10万円で、今後は利用者数の増加状況に応じて支給額を決め、患者にマイナ保険証の利用を呼びかけることなどを条件としています。
そのような中で、河野デジタル相が自民党所属の国会議員に対し、マイナ保険証を受け付けない医療機関の報告を呼びかける文書を出していたことが判明し、政府のなりふり構わず普及を促進する姿勢が露骨になっています。
河野氏の署名が入った「マイナ保険証の普及促進と行政のデジタル化へのご協力のお願い」と題した文書で、河野氏側が19日までに配布したということです。
河野氏は、政府が医療機関にマイナ保険証の受け付けを義務づけている中、「受付をしていない病院や、患者が受付をしようとしているのに従来の保険証の提示を求める医療機関がある」と指摘し、各議員の地元の医療機関に対し、マイナ保険証の受け付けを働きかけるよう呼びかけています。
さらに、受け付けをしていない医療機関があれば政府の窓口に連絡するよう求め、「必要に応じ、厚労省から医療機関に事実関係の確認などを行う」とも訴えており、いくら、マイナ保険証の利用が政府の思惑通りに進んでいないとはいえ、自民党政治家を利用した医療機関への圧力で利用促進を促すなどというのはいかがなものかと言わざるをえません。
マイナンバーをめぐっては、昨年、健康保険証や公金受取口座とのひもづけの誤りが約1万6千件見つかったほか、今年に入ってもマイナ保険証がカードリーダーで読み取れない事例が報告され、本県などでも、保険医協会は、県内医療機関対象のアンケートで129の医療機関の約6割でマイナ保険証の使用によるトラブルがあったことを公表しています。
マイナ保険証の都道府県別の利用率が初めて公表された際には、最も高い鹿児島県でも8.4%、最も低い沖縄県では2.3%にとどまり、全国平均では4.6%で、それを下回る高知県は、下位から10番目の4.16%でした。
マイナ保険証の利用促進のために、自民党を使った監視通報の仕組みを求める強権さに恐ろしさすら感じます。
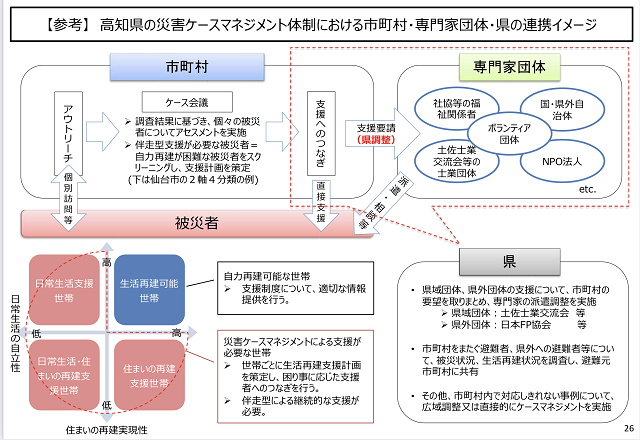
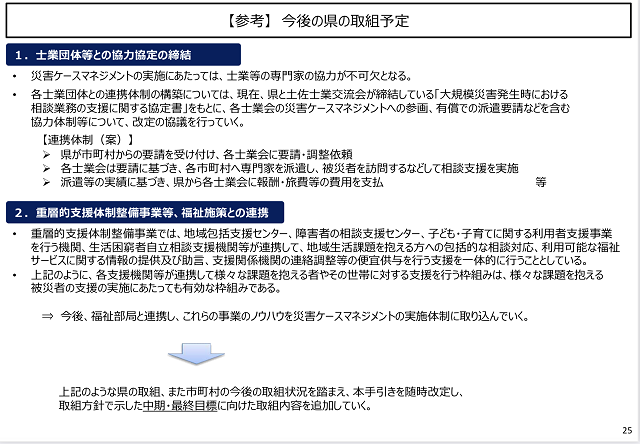 17日の危機管理文化厚生委員会の本庁業務概要調査で、「災害ケースマネジメントの実施体制に係る市町村向け手引き(Ver.1)」の出来上がりについて、質問をしました。
17日の危機管理文化厚生委員会の本庁業務概要調査で、「災害ケースマネジメントの実施体制に係る市町村向け手引き(Ver.1)」の出来上がりについて、質問をしました。
令和2年9月議会で、初めて「災害ケースマネジメント」の導入について取り上げ、南海トラフ地震対策行動計画に盛り込み、取り組んで頂いていた市町村向けの手引きができあがり、17日にホームページにアップされたばかりでした。
17日の質問でも尋ねた平時の重層的支援体制整備事業等、福祉施策との連携についても少し触れて頂いています。
しかし、コンパクト感が強いかなと思っていたら、手引きの中に、「県の取組、また市町村の今後の取組状況を踏まえ、本手引きを随時改定し、取組方針で示した中期・最終目標に向けた取組内容を追加していく。」とありました。
バージョン1であって、随時バージョンアップしていきたいとの考え方を示しています。
私も、これまで以上に「災害ケースマネジメント構想会議」の皆さんにご指導頂き、現場に生かせる手引きとなるよう意見反映もしていきたいものです。
公表された日の深夜に、高知で震度6弱の地震とは、何かこの手引きの持つ意義を余計に感じさせられた気がします。
 四国で6弱を観測したのは、現在の震度階級が導入された1996年10月以降初めてであり、最大6弱の宿毛市をはじめ、県西部を中心に強い揺れに見舞われました。
四国で6弱を観測したのは、現在の震度階級が導入された1996年10月以降初めてであり、最大6弱の宿毛市をはじめ、県西部を中心に強い揺れに見舞われました。
家屋倒壊情報はないものの、土佐清水市の民家の軒先が落下する一部損壊が1件、宿毛市では民家の窓ガラスが割れたり、天井の一部が崩落するなどの被害が相次いで発生しました。
宿毛高校東側では、コンクリート製の橋が崩落し、西町3丁目では水道管が破損し、修復のため周辺の約20世帯が一時断水になったり、給水管破損の相談が市に60件ほど寄せられたとのことです。
しかし、市には給水車がなく、要請を受けた高知市と四万十市、国土交通省土佐国道事務所が派遣して対応しています。
また、梼原町松谷では落石と倒木で町道がふさがれ、5世帯10人が一時孤立しました。
避難所開設は宿毛市のみで10か所最大23人の避難者が身を寄せています。
これが、県内全域に及ぶ震度6強以上の揺れの後に、津波が襲っていたらと思うと、現時点の備えで対応できていたのかと思います。
まだ、被害の全容が判明しているわけではないので、教訓を引き出し、備えにどう反映していくのかは、これからの検討となります。
「直接、巨大地震発生の可能性が高まったとは言えない」としても、いつ起きても不思議でない南海トラフ地震への備えが、迫られていることだけは確かです。
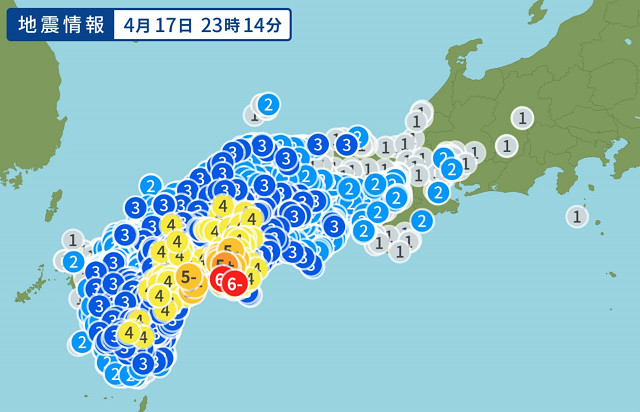
 昨夜、11時14分ごろ、豊後水道を震源とするマグニチュード6.6の地震があり、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度5強から震度1の揺れを観測しました。
昨夜、11時14分ごろ、豊後水道を震源とするマグニチュード6.6の地震があり、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度5強から震度1の揺れを観測しました。
地震による津波がなかっただけでも、皆さん落ち着いた対応ができたようです。
私は、居住しているマンションの大規模修繕工事中で足場に異常などないか周辺を点検して回りましたが、大きな変化はなかったようでした。
それでも、愛媛県と高知県で震度6弱以上の揺れを観測したのは、現在の震度階級が導入された1996年以降初めてのことでしたので、皆さん驚かれたようです。
私も、最大震度を記録した愛媛県愛南町と高知県宿毛市に在住の知人の安否を確認したことでした。
気象庁によると、今回の地震は南海トラフ巨大地震の想定震源域の中で起きたものの、フィリピン海プレートの内部で発生したもので、想定されるプレート境界の地震とはメカニズムが異なるほか、地震の規模が小さいことから、南海トラフ巨大地震の発生の可能性が高まったとは考えていないとしています。
そして、多くの皆さんが心配した伊方原発のある愛媛県伊方町は震度4の揺れを観測しましたが、四国電力では運転中の3号機の出力がおよそ2%低下していることが確認されたものの、運転に影響はないとして、周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないとしています。
地震が頻発するこの国で、原発立地周辺住民がその都度心配を繰り返さなければならないことはいい加減やめにしてもらいたいものです。
震度6弱を観測した宿毛市では電柱が倒れたほか、水道管から水が漏れ出したり。震度4を観測した梼原町では、町内松谷地区では地震による落石や倒木で道路が通行止めとなり、5世帯が孤立状態になっていますが、今朝から本格的な被害状況の把握がされると思いますが、大きな被害が出ないことを願うばかりです。
気象庁は、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6弱程度の地震に注意してほしいとのことですが、皆さん改めて備えのチェックをしておきましょう。
| 4月16日「地元同意なしに再稼働に突き進む東電柏崎刈羽原発」 |
 新潟県柏崎刈羽原発の再稼働に向け、地元・新潟県の同意が得られる見通しが立たない中、東京電力は15日、7号機の原子炉に核燃料を入れる装塡に着手しました。
新潟県柏崎刈羽原発の再稼働に向け、地元・新潟県の同意が得られる見通しが立たない中、東京電力は15日、7号機の原子炉に核燃料を入れる装塡に着手しました。
能登半島地震では避難計画の実効性が問われ、原発から30キロ圏内の自治体からは同意対象の拡大を求める声も出ていますが、課題は置き去りのまま、再稼働への地ならしが進んでいる現状が突きつけられています。
地元の同意がそろう前に燃料を入れるのは異例であり、2013年に新規制基準がつくられて以降に再稼働した他社の12基の原発はすべて、同意後に作業しており、燃料装荷を同意を待たずにやるなんて考えられないとの批判が高まっています。
東電に原発を運転する事業者としての適格性があるのかどうかさえ問われた東電が、それでも作業を急ぐのは、同意後すみやかに動かして経営再建につなげたいだけでなく、早く作業を始めないと、またトラブルが起きるのを恐れているのではとの声も出ています。
「原発を続けるということは、事故が起きる可能性を抱え続けることを意味する。福島第一原発事故では、その影響の大きさを私たちは思い知った。事故をひとたび起こせば取り返しのつかない事態を招くにもかかわらず、原発はなぜこうも優先されるのか。どうして、何のために必要とされているのか。」と青木美希氏は自著「なぜ日本は原発を止められないのか?」の中で、問いかけられています。
地元同意も得られない中で、再稼働に突き進もうとする東京電力に改めて、「原発を運転する適格性はない」と言い続けたいと思います。

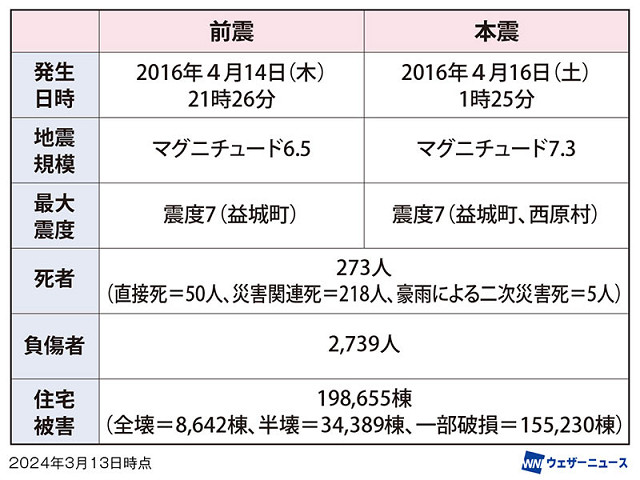

熊本、大分両県で計276人が犠牲となった2016年4月の熊本地震は14日、最初の激震「前震」から8年となりました。
インフラ復旧は大きく前進し、地震の約2カ月後に創設された熊本県の復旧・復興本部会議は今月5日付で廃止されたそうです。
被害の大きかった益城町では4月14日夜の前震、16日未明の「本震」で、観測史上初めて震度7を2回記録しました。
熊本、大分両県で計約4万3千棟の住宅が全半壊し、最大時には計約19万6千人が避難し、両県の犠牲者のうち、約8割に当たる221人が災害関連死だったのも大きな特徴の震災でした。
2021年3月時点の災害関連死の内訳状況は、以下のとおりとなっています。
性別では男性が115人(約53%)、女性が103人(約47%)と、大きな差はなく、年代別では最も多いのが80歳代の75人(34.4%)で、70歳代以上の方は計169人(約78%)でした。
既往症があった方は218人中190人(約87%)と大きな割合を占めていましたが、疾病では「呼吸器系の疾患」が63人(28.9%)と「循環器系の疾患」が60人(27.5%)と多く、「自殺」も19人(8.7%)となっています。
原因区分別では「地震のショック、余震への恐怖による肉体的・精神的負担」が112人(40%)と最も多く、「避難所等生活の肉体的・精神的負担」の81人(28.9%)、「医療機関の機能停止等(転院を含む)による初期治療の遅れ(既往症の悪化及び疾病の発症を含む)」の14人(5%)、「社会福祉施設等の介護機能の低下」の9人(3.2%)が続きました(複数回答のため計280件)などとなっています。
災害関連死が直接死の4倍だった熊本地震から、復興過程で「誰一人取り残さない復興」は、8年が経った今、まさに正念場であり、地震前の住まい、暮らしを再建できず、孤立や苦労を強いられる住民をどう支えるのか。
初期フェーズで災害ケースマネジメントに取り組まれたこともあったが、地域や住民間の復興格差が広がりかねない中、県や市町村がこれからも被災者に長期的に寄り添うとともに、地域社会の見守りも重要になっていることが、平時から求められることになろうと思います。
我々が向き合わざるをえない南海トラフ地震、首都直下地震への警戒に加え、今年3月以降に宮崎県などで震度5弱が相次いで観測されている今、熊本だけでなく、全国で油断することなく備えたいものです。
| 4月12日「緊急事態条項改憲先取りの地方自治法改正に異議あり」 |
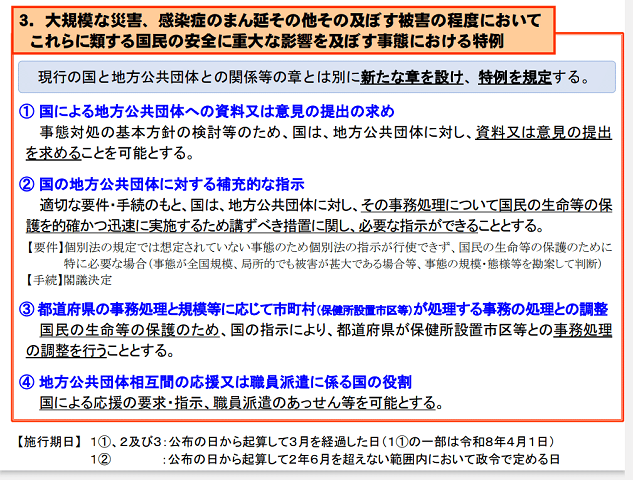 政府は3月1日の閣議で、大規模災害や感染症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要な指示ができる仕組みを盛り込んだ地方自治法改正案を決定しました。
政府は3月1日の閣議で、大規模災害や感染症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要な指示ができる仕組みを盛り込んだ地方自治法改正案を決定しました。
改正案では、事態が全国規模だったり、局所的でも被害が甚大だったりする場合などに指示権の発動を認めるもので、想定外の事態が発生しても、国民の安全確保へ迅速な対応を取れるようにすることが目的とされています。
能登半島地震の対応を受けて、緊急時により迅速にとあたかも言いたげな今回の法改正は、これまで緊急事態条項改憲が進まないなら、地方自治法改悪によって、地方から地ならしをしようとの狙いが見え見えではないかと言いたくなります。
災害時の緊急事態は現行の「災害対策基本法」の第105条にもありますし、第108条の3には、国は緊急事態の時、国民に協力を要求できると書いてあるにも関わらず、後手後手に回っているのは国の災害時対応の不十分さ以外の何物でもありません。
日本弁護士連合会は、3月13日に「地方自治法改正案に反対する会長声明」で、次のように指摘しています。
「大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。そして、2000年地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。」
また、最近は国に対して、物言う姿勢を後退させている全国知事会でも、この法案の閣議決定を受けて「法案上必ずしも明記されていないと考えられる点もあることから、国の補充的な指示が地方自治の本旨に反し安易に行使されることがない旨が確実に担保されるよう、事前に適切な協議・調整を行う運用の明確化などが図られるよう強く求める。」との会長コメントを出しています。
今国会に提出されている、大変問題の多い緊急事態条項改憲先取りの地方自治法改正案は、安易に成立させてはならないものであると思います。

 日本国際博覧会協会は8日、公式ホームページで「みんなで『大阪・関西万博開幕1年前』を盛り上げましょう!」と呼びかけ、公式キャラクター「ミャクミャク」と「くるぞ、万博。」と書かれたイメージ画像をダウンロードしてSNSに投稿するよう訴えかけています。
日本国際博覧会協会は8日、公式ホームページで「みんなで『大阪・関西万博開幕1年前』を盛り上げましょう!」と呼びかけ、公式キャラクター「ミャクミャク」と「くるぞ、万博。」と書かれたイメージ画像をダウンロードしてSNSに投稿するよう訴えかけています。
そして、政府も万博盛り上げに躍起で、機運醸成につぎ込まれる国費は約40億円だと言われています。
そこまでしなければならない大阪・関西万博会場建設現場で3月28日、地中の廃棄物から出たメタンガスが原因とみられる可燃性ガスに、工事中の火花が引火して爆発する事故が発生しました。
現場は、会場西側の「グリーンワールド」工区の屋外イベント広場横のトイレ1階部分で、溶接作業中に発生した火花が、地面と床の隙間にある配管ピット内にたまったガスに引火し、爆発し、1階床が破損したが、けが人はなかったとのことです。
この工区は計155haの会場のうち西側の43haを占めており、広場の他に店舗などが入る営業施設などが建てられる予定で、廃棄物処分場だった所で可燃性ガスが発生しているとのことです。
メタンガスは生ごみなどが廃棄された埋め立て地でも発生することが知られているため、今回事故が起きた現場も以前から危険性が指摘されており、昨年11月の参院予算委員会では、社民党の福島瑞穂議員が「現場でメタンガスが出ている。どういう状況か。火がついたら爆発する」と質問し、自見万博担当相は「関連省令に基づき配管施設を設置し、ガスを大気放散していると聞いている。万博の開催時に危険はないと考えている。」と答弁しています、
工区には約80本のガス抜きをする管が設置されているというが、名古屋大名誉教授竹内恒夫氏(環境政策論)も「ごみが捨てられたことは分かっているのだから、ガスが発生することも分かっているはず。発酵が終わるまで危険性がなくなることはない」と指摘しており、事故現場は会場に不適当でなことは明らかであり、このままの開催には無理があります。
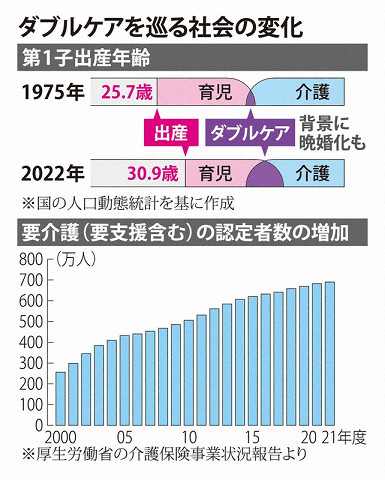 安倍政権は2015年に策定した「女性活躍加速のための重点方針」で、子育てと介護を同時に担うすダブルケア問題を取り上げ、負担軽減の対策を進めると明記しました
安倍政権は2015年に策定した「女性活躍加速のための重点方針」で、子育てと介護を同時に担うすダブルケア問題を取り上げ、負担軽減の対策を進めると明記しました
そして、内閣府は翌年、ダブルケアラーが全国に25万3000人いるとした初の推計値を公表し、16年版の厚生労働白書には「乗り越えなくてはならない課題」と明記されたが、子育てと介護の担当部署が異なる縦割り行政の弊害などを背景に有効な支援が広がっていないと言われています。
「ダブルケア問題の実態について調査を行い、負担軽減の観点から対策の検討を進める」と政府の文書で触れられてから9年が経った今、子育てと介護を同時に担うダブルケアラーの支援法案が、野党から国会に提出されることになり、重い負担や悩みに直面する担い手たちの切実な声が、政府・与党に届くことを願うばかりです。
ジェンダー格差や孤立、社会の無理解など、ダブルケアには多くの問題が潜んでおり、特に深刻な課題として貧困につながる離職の問題があります。
毎日新聞が国の統計を基にした推計29万3700人のダブルケアラーのうち、20万3700人が過去に離職を経験し、この35%は原因に育児や介護だと独自集計で明らかにしています。
ダブルケアによって離職する前に、「ちょっと助けてと言いやすい、優しい社会になってほしい」との思いが実現できる支援法となることが期待されます。
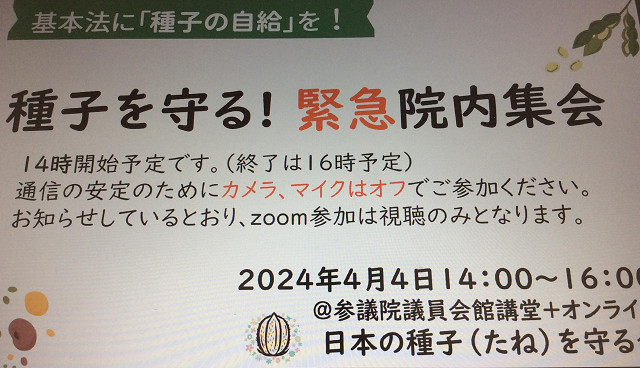


先日、「4・4タネを守る、院内集会」に、ZOOM参加し、現在国会に提出されている「食料・農業・農村基本法」改正案と、食料危機時の対応の枠組みを定めた「食料供給困難事態対策法案」など関連法案の危険性と「みつひかり」不正事件から考える種子の自給など日本の種子問題についての議論を聴かせて頂きました。
私も含めて3月20日現在、47都道府県141自治体の議員252 名が参加している「食料自給の確立を求める自治体議員連盟は3月21日、国会内で基本法に関する政府への要請を行っており、今回も会場参加300人弱、ZOOM参加200人以上の仲間とともに参加していました。
東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授鈴木宣弘先生の「基本法と日本の種子問題」に関しての提起で、農業の憲法とも言える「食料・農業・農村基本法」の25年ぶりの改定で、種の自給どころか食料自給率そのものが入っていなかったことをはじめ、現状の農業・農家の疲弊状況、種が自給できなければ実質自給率9.2%に過ぎない我が国の農業で、これ以上他国に依存することにでもなれば、国民の命を守れないと指摘されました。。
有事には、命令して農業生産を高めさせるといっても、そのようなことはできるはずはなく、また、種子法が改悪されて以降、外国からの種を止められたら野菜の自給率は8%に留まることなどからも種を守ることこそが国防であり、このような状態を放置するのではなく、自分の命の問題として、法改正に種を守ることが入れられるべきだとも言及されました。
そして、何よりも、力点を置くべきは苦しんでいる農家を支えて、今度こそ自給率を向上させ、水田をフル活用し、国内生産を守り、国の責任で買い取り備蓄と援助に回すことこそ食料安全保障であり、「武器は命を奪うもの、食料が命を守るもの。食料を守ることが国防である。」との言葉で締めくくられました。
また、民間の育種技術が向上したことから全国一律に都道府県に種子の供給を義務づける必要がなくなったとして、種子法が廃止された際の錦の御旗であった「みつひかり」の不正事件から考える種子の自給について、岩月浩二弁護士からの報告も頂きました。
種子法廃止の錦の御旗であった「みつひかり」は、三井化学が種子生産・販売事業については、技術的、経済的、人材的要因から本事業を継続することは困難な状況にあり、令和8年以降に向けては別の品種への切り替えを検討して頂きたいと栽培農家に対して撤退予定の旨を昨年暮れに通知しています。
まさに、民間に任せて種子を自給することは不可能であったことが、明らかになっています。
とにかく、「食料・農業・農村基本法」改正案や農業関連法案をこのままで、成立させるわけには、いきません。
抜本的な改正を求めて、国民の皆さんに関心を持っていただくことこそが大事です。
| 4月5日「今年度は危機管理文化厚生委員会で頑張ります」 |
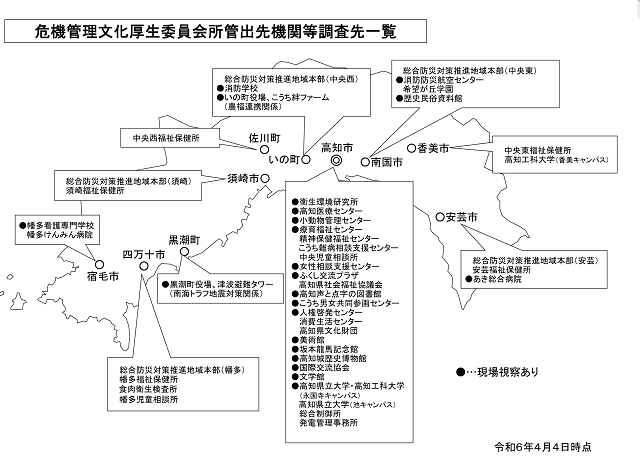
 昨日は、組織委員会ということで、今年度の常任委員会の委員長、副委員長などの選任が行われました。
昨日は、組織委員会ということで、今年度の常任委員会の委員長、副委員長などの選任が行われました。
私は、今年度は危機管理文化厚生委員会に所属し、所管する部局は、危機管理部、健康政策部、子ども・福祉政策部、文化生活部、公営企業局となります。
本県における喫緊の課題である少子化対策や南海トラフ地震対策をはじめとした多様かつ重要な課題について、審議することとなりますが、私にとってはライフワークの南海トラフ地震をはじめとした災害対策と福祉政策をフェーズフリーの取り組みとして、県政の柱にしていけるよう頑張りたいと思っています。
16日から3日間で、本庁業務概要調査を行い、5月には8日から9日間かけて、所管の出先機関を調査させて頂きます。
その際には、またそれぞれの出先機関の抱える課題や成果などについても随時報告させて頂きたいと思います。
なお、私たち「県民の会」会派の各議員の所属委員会は次のとおりとなっています。
橋本敏男議員「産業振興土木委員会」、田所裕介議員「総務委員会」、岡田竜平議員「商工農林水産委員会」で、田所議員は議会運営委員会の副委員長に就きました。
新年度も、県民の会で連携を取りながら、県民の皆さんに寄り添う議会活動を行っていく決意です。
よろしくお願いします。
| 4月4日「被災地の断水で考える水道インフラの事前整備」 |
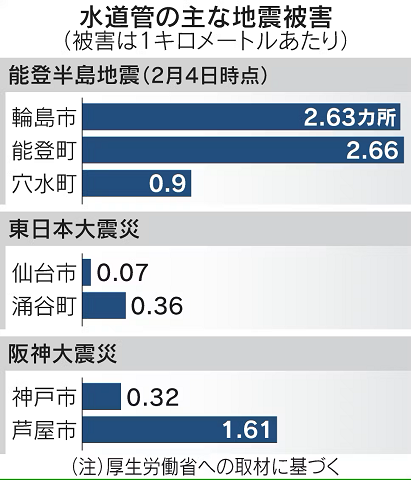
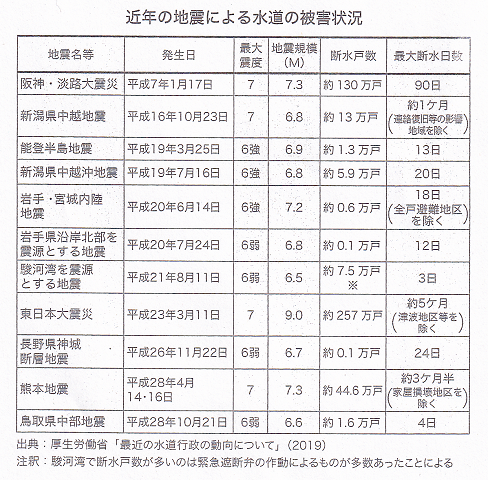 能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。
能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。
元日の震災で、断水は一時、16市町の約11万戸に及び、3月1日時点で7市町の約1万8千戸まで減り、知事は珠洲市も一部地域を除き「3月末までに復旧できる」との見通しを示していました。
しかし、県の今月2日の発表では、残り4市町の約6680戸まで復旧したものの、このうち珠洲市だけで契約戸数の8割超にのぼる約4250戸となっています。
県は、「想像以上に浄水場や配水管の被害が大きかった」と説明しているが、水道管1キロあたりの損傷は、熊本地震の熊本市で0.03カ所、東日本大震災の仙台市で0.07カ所で、能登半島地震では、珠洲市に比べれば復旧が進んでいる隣の輪島市でも2.63カ所に達しています。
水道の復旧のために全国から派遣された自治体職員らは延べ3万人を超えていますが、金沢大の宮島昌克名誉教授(ライフライン地震工学)は「断水が長引くほど地元で事業や生活の再建を望む人が減り、被災地以外に転出する可能性が高まる」と指摘し、「復興の活力を失わないよう全国の自治体による復旧支援に加え、損傷部分を簡単に把握できる新たな技術の導入など、復旧を早める手法も検討すべきだ」と言われています。
そのようなことが、今後の水道インフラ整備に求められる中、安倍政権のもとで2017年に水道法が改悪され、水道の運営権を民間企業に売りやすくしました。
日本は世界一の水道技術と、蛇口から出る水を安全に飲める数少ない国ですが、実は、日本中を走る74万キロの水道管のうち2割が耐用年数超で上水道で300㌔以上、下水道で100㌔以上を、今すぐ直さなければならないと言われています。
「今、能登が直面していることは、全国どこでも起こってもおかしくないのです。水道管の劣化について、政府もマスコミも「財政難」と「人口減」を理由に、できるだけ民間企業に委託するよう、自治体をプッシュしてきましたが、自然災害だらけの日本で、世界一の技術を伝承させず、地方を非常時に弱い民間委託にさせておくのは、自分の首を絞めているようなもの。」と、堤未果氏は著書「国民の違和感は9割正しい」で指摘されています。
改めて、この国の水道インフラの事前再整備こそが事前復興の最重要課題だとも考えさせられます。
 政府は1日、総合的な防衛体制強化の一環で、有事に備え平時から自衛隊や海上保安庁が使用できる「特定利用空港・港湾」の第1弾として、本県の3港をはじめ7道県16施設を選定しました。
政府は1日、総合的な防衛体制強化の一環で、有事に備え平時から自衛隊や海上保安庁が使用できる「特定利用空港・港湾」の第1弾として、本県の3港をはじめ7道県16施設を選定しました。
南西有事などをにらみ、平時でも活用可能にすることで対応能力の向上を図上で、2024年度予算に関連費約370億円を計上しました。
政府は昨年秋ごろから候補として挙げた空港や港湾がある自治体に協力を求めてきたが、その際、「民間の大型のクルーズ船も入れるし、国による災害派遣も効率的に行えるようになる」などと「アメ」をちらつかせるとともに、「軍事」のイメージを拭うため、調整の過程で表現を変更したりもしています。
当初は軍民両用を意味する「デュアルユース」という言葉を使っていたが、自治体からは「攻撃目標にされるのでは」といった指摘があったことから、「民生利用」へと切り替え、枠組みの名称も「特定重要拠点空港・港湾」という仮称を用いていたが、「特定利用空港・港湾」としています。
そのような中でも、沖縄県では、新石垣空港や与那国空港は沖縄県が管理しており、「一番の懸念は日米の共同使用。安易な運用にはクギを刺しておかなければ」との慎重姿勢から、同意せず、特定利用空港に指定されていません。
また、鹿児島県は2空港6港が調整対象に挙がっていたが、「国からの説明を十分にいただけていない段階で、判断する材料が整っていなかった」として指定に同意していません。
さらに、福井、熊本県からも「施設が所在する自治体への説明不足」などを理由に了解が得られませんでした。
このような姿勢で対応してきた県がある中、高知などは県民に十分な説明も行われず、有事の際の国民保護や避難計画なども検討されないままに、拙速に同意しています。
下記のように、予算が配分されていますが、これからもこのような「アメ」に釣られた軍事化が進んでいくのでしょうか。
| 県名 |
空港 |
予算額(億円) |
| 福岡県 |
北九州 |
63 |
| 長崎県 |
長崎 |
19 |
| |
福江 |
2 |
| 宮崎県 |
宮崎 |
27 |
| 沖縄県 |
那覇 |
72 |
| 道県名 |
港湾 |
予算額(億円) |
| 北海道 |
留萌 |
3 |
| |
石狩湾港 |
19 |
| |
釧路 |
26 |
| |
苫小牧 |
24 |
| |
室蘭 |
2 |
| 香川県 |
高松 |
5 |
| 高知県 |
高知 |
18 |
| |
須崎 |
8 |
| |
宿毛湾港 |
2 |
| 福岡県 |
博多 |
17 |
| 沖縄県 |
石垣 |
25 |
(注)福江空港以外の空港は維持管理費39億円を別途計上
| 4月2日「39人の処分で自民裏金プール・キックバック事件の幕引きはさせない」 |
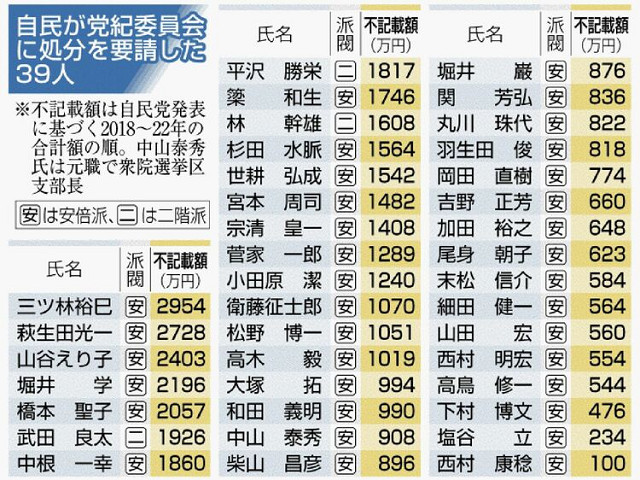 自民党は昨日、派閥の裏金プール・キックバック事件をめぐり、過去5年間の政治資金収支報告書への不記載・不適正記載総額が500万円以上の議員らと、「『派閥』の幹部の立場にありながら適切な対応を取らず大きな政治不信を招いた者」一部の安倍派幹部を含む計39人を処分対象とする一方で、党総裁の岸田首相と二階元幹事長に対する処分を見送ることを決めました。
自民党は昨日、派閥の裏金プール・キックバック事件をめぐり、過去5年間の政治資金収支報告書への不記載・不適正記載総額が500万円以上の議員らと、「『派閥』の幹部の立場にありながら適切な対応を取らず大きな政治不信を招いた者」一部の安倍派幹部を含む計39人を処分対象とする一方で、党総裁の岸田首相と二階元幹事長に対する処分を見送ることを決めました。
「大きな政治不信を招いた者」とされる安倍派座長の塩谷立元文部科学相、下村博文元文科相、西村康稔前経済産業相、同派参院側トップの世耕弘成前党参院幹事長の一部に対し、処分で2番目に重い「離党勧告」とする方向で調整しているとされています。
しかし、首相自身の処分見送りは、自身で責任回避を試みたと映るため、党内外から批判が噴出する可能性が高いし、4日に正式に処分を下し、これで幕引きを図るのであれば、許されるはずはありません。
「1994年政治改革」が、派閥の裏金事件を含め政治とカネ事件の発生を防止できなかったことからも、衆議院の選挙制度を中選挙区制から小選挙区比例代表制にし、税金を原資にした政党助成金導入は明らかな失敗であったことを踏まえた抜本的な政治改革を本気でやらない限り、真の政治改革は果たせませんし、政治の信頼は取り戻せません。
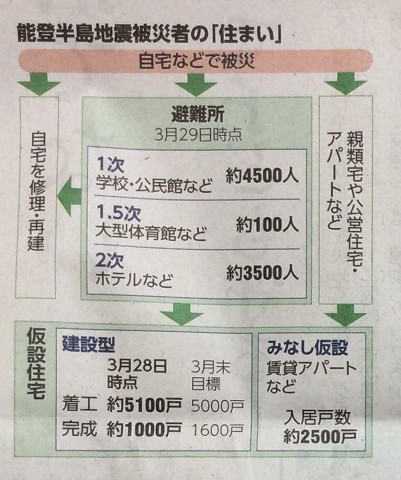 能登半島地震から3か月、月命日の4月1日を迎えました。
能登半島地震から3か月、月命日の4月1日を迎えました。
3月29日の石川県発表では死者244名、内災害関連死が15名にのぼり、75、441棟の住家被害、未だに8千人を超える人が避難生活を続けられています。
石川県では、応急仮設住宅(建設型)のこれまでの入居申請が少なくとも約8300件に上る中3月末の完成戸数は約1600戸で需要に追いつかない状況が続いています。
安定した住まいの確保が困難で、生活再建や復興に向けた過程の中で、元の住まいのあった被災市町村からの人口流出が大きな課題になっています。
私たちが、おたずねしたり、来ていただいたりする中で、東日本大震災の復興から学ばせて頂いた宮城大の阿部晃成・特任助教は3月、輪島市議会の勉強会で「被災者が避難所から2次避難所、みなし仮設とどんどん移動していく。地域への思いを維持するのは難しい」と訴えられたことが、今朝の朝日新聞にも出ていました。
東日本大震災では、地域の仮設住宅にわずかな住民しか入れなかったことが影響し、地域の復興が滞って人口減少が加速した例もあったと記事にはありますが、下知地区で聴かせて頂いた京大防災研の牧先生も仮設住宅が早期に確保できないことが復興の遅れに繋がることを強調されていたことを思い出します。
石川県が3月28日、能登半島地震からの「創造的復興」に向けた計画の骨子案を示した際に、29日付朝日新聞で、石川県災害危機管理アドバイザーを務めてきた神戸大名誉教授の室崎益輝先生は、「被災地の風景はほぼ震災直後のまま。がれきの撤去すら終わっていない。東日本大震災や熊本地震と比べ、遅すぎます。前例のない地震が起き、前例のない被害が出ました。ならば、前例のない対策が必要です。」と述べられ、「骨子案をまとめるのに、これまで被災者の意見はどれほど聞き取ったのでしょうか。これから案を見直し、深めていく作業が必要です。原形がなくなるほど手を入れ、復興への道筋を考えてほしい。そうすれば、描いた絵に向かって後は走り出すだけです。」と結ばれています。
災害前から、このようなことを考えておくだけでも、災害後の復興の着手が早くなるようにとの思いで、粘り強く事前復興について考え、議論し、可視化を図っていきたいものです。
| 3月30日「子どもの自殺を防ぐためにも寄り添えるおとなが身近に」 |
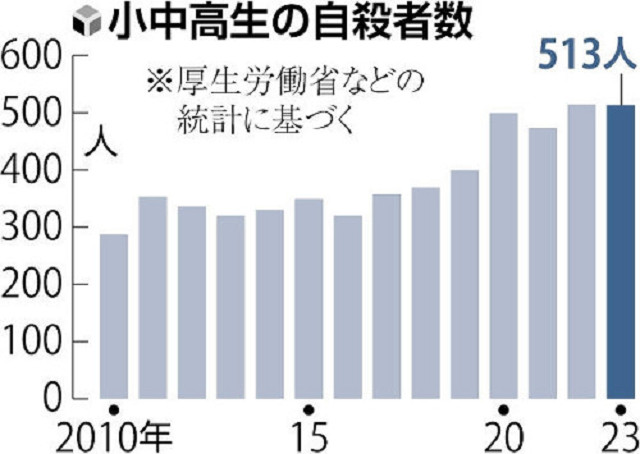
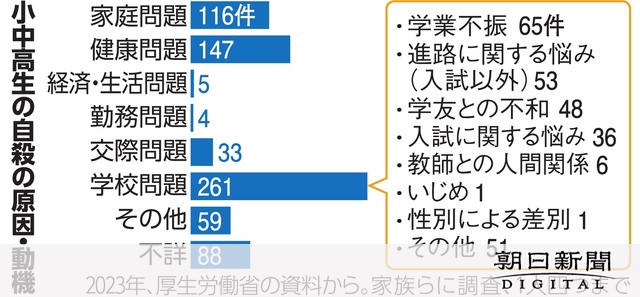 1月28日に、ここで2023年の自殺者数の暫定値を2万1818人、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことを報告させて頂きました。
1月28日に、ここで2023年の自殺者数の暫定値を2万1818人、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことを報告させて頂きました。
昨日、確定値が公表され2万1837人で、前年より44人(0.2%)減少しています。
自殺者の総数は、03年の3万4427人をピークに、19年には2万169人まで減少したものの、コロナ禍以降は再び増加傾向に転じていました。
昨年は、70歳以上で減少幅が大きかった一方で、小中高生の自殺者数は、過去最多だった22年の514人に次ぐ513人で、コロナ禍以降、子どもの自殺者数が高止まりしている状況にあります。
厚労省によると、小中高生の原因・動機別の分析では、「学校問題」が最も多く、261件で、「健康問題」が147件、「家庭問題」が116件と続いており、さらに詳しく見ると、学校の問題のうち、「学業不振」が65件、「進路の悩み」が53件、「いじめ以外の学友との不和」が48件となっています。
ネットで若年層の相談を受け、自殺防止に取り組むNPO法人「OVA」の伊藤次郎代表によると、子どもがほとんどの時間を過ごす家庭と学校では、親も教員も多忙で、時間も気持ちにも余裕がなく、「地域社会から、子どもの居場所となり得る『中間共同体』が失われ、相談できる大人が近くにいない」と話されています。
そして、「積極的な支援をうまく受け取れない子どもも多く、学校の教職員など身近な大人が、変化に気づいて声をかける「ゲートキーパー(門番)」の役割を果たすことが重要」とも指摘されており、今こそ課題や悩みを抱えた子どもたちにしっかりと寄り添える環境を作り出すためにも、おとなのゆとりも必要になっていると言えます。


 昨日、政府は防衛力強化の一環として、有事の際の自衛隊や海上保安庁による使用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に、本県の3港湾をはじめ7道県計16カ所を指定する方針を固めたことが、報じられています。
昨日、政府は防衛力強化の一環として、有事の際の自衛隊や海上保安庁による使用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に、本県の3港湾をはじめ7道県計16カ所を指定する方針を固めたことが、報じられています。
部隊展開や国民保護活動、訓練の拠点を確保するためのもので、2024年度に整備事業を始める初年度の予算は計350億円程度となる見通しとのことです。
政府は22年末に策定した国家安全保障戦略に、台湾有事の懸念を念頭に、国民保護や有事の際の円滑な利用・配備を目的として「有事の際の対応も見据えた空港・港湾の平素からの利活用に関するルール作りを行う」と盛り込んでいるだけに、何よりも中国の海洋進出や台湾有事への懸念が県民に生ずるのは当然です。
それを無視して、災害時に活用できることなどをメリットとして、有事に軍事拠点と見なされ攻撃目標となる危険など整備の必要性とリスクの丁寧な説明のないまま、「指定受け入れ」を判断した浜田県政のやり方に、県民の怒りは高まっています。
そのような状況の中で、港湾管理者の県が合意したことを受け昨日、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」と「高知憲法アクション」主催の抗議集会が県庁前で開かれ、約200人が参加しました。
私も県民の会の同僚議員らとともに参加し、「県民の不安、怒りの声が届いているなら、今からでも合意を撤回すべき」と訴え、県議会6月定例会に、受け入れ撤回を求める請願書の提出を目指す取り組みに協力していくことを確認しあいました。
さすがに、沖縄県などは、国の意図をしっかりと見極めているからこそ、最多の12カ所を候補とされながらも、県管理施設は同意せず、、国管理の那覇空港など2カ所にとどまっています。
そのような動きを高知県でも作っていくためのスタートとする集会となりました。
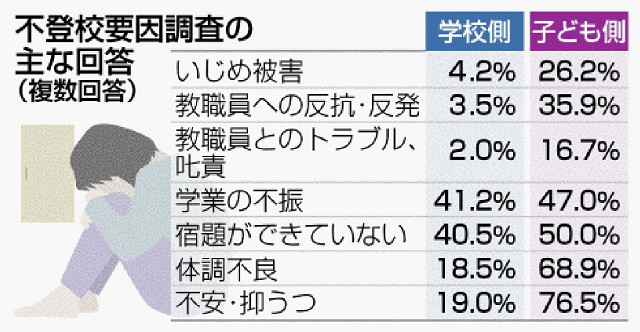 今朝の共同通信の配信記事で、2022年度に不登校を経験した小中高生や担任らに要因を尋ねた調査結果に関する記事がありました。
今朝の共同通信の配信記事で、2022年度に不登校を経験した小中高生や担任らに要因を尋ねた調査結果に関する記事がありました。
要因として、「いじめ被害」「教職員への反発」の項目に該当すると回答した割合が、学校側は子ども側より20ポイント以上低く、認識に大きな差があることが文部科学省の委託調査で分かったとのことです。
この調査では、教員1424人と児童生徒239人に、複数回答で不登校のきっかけを質問したところ「いじめ被害」は子ども側26.2%、学校側は4.2%、「教職員への反抗・反発」「教職員とのトラブル、叱責」は、子ども側がそれぞれ22.0ポイント、32.4ポイント、14.7ポイント高く出ています。
調査報告書は「教員の態度や指導方法が要因の可能性がある」と指摘するとともに、学校が子どもの状況を十分に把握できていない実態が浮かび、重大ないじめを見逃している可能性もあるとのことです。
文科省が学校のみを対象に毎年度実施している「問題行動・不登校調査」では、「無気力・不安」が要因の過半数を占めるなど、実態との隔たりが指摘されており、文科省は今回の結果を受け、問題行動・不登校調査の手法を見直す方針とのことです。
「体調面の不調」は子どもの7割が挙げたのに対し、学校側は2割にとどまっており、報告書は、1人1台配備の学習端末を活用し、心身の変調の早期把握が重要だとしています。
鳴門教育大の阪根健二特命教授(学校教育学)は、「教員がいじめではないと判断したことでも、子どもがいじめだと感じていることは少なくない。今回の調査結果からは、そういった教員の認識の甘さが子どもとの隔たりを生んでいる可能性が見えてくる。確かな数値でこうした乖離を示した意義は大きく、教員が不登校に関して考え直す良いきっかけになるだろう。」と指摘されています。
先生方と子どもたちの間での認識の隔たりを改善するのは、どのような方法が最も良いのか、そしてそれを実践するためには、何よりも先生方が子どもたちとしっかり向き合える環境を作っていくしかないのではないかと考えさせられます。
新年度を迎える中、それぞれの学校で先生方と子どもたちがしっかりと向き合えることのできる環境ができればと思います。

 昨日から、高知新聞で、「明日の足 高知の公共交通を考える」連載第4便が始まりました。
昨日から、高知新聞で、「明日の足 高知の公共交通を考える」連載第4便が始まりました。
そして、県内市町村が、路線バスや鉄道に加え、コミバスや福祉タクシーなどで高齢化する地域の移動手段を確保するのに、いかに苦労しているのか、公共交通維持に向けた自治体の課題と苦悩が描かれようとしています。
そんな矢先の23日に、私も理事をしている高知県自治研究センターの主催で「どうする?どうなる?私たちの公共交通~大切な社会インフラのいまとこれから」のテーマで公共交通について考えるシンポジウムが開催されました。
戸崎先生からは、「コロナ禍が示した公共交通の位置づけ」「高齢社会における公共交通の役割」「公共交通の経営難」「運転手不足への対応、労働力の充実に向けて」「2024年問題」「街づくりと公共交通」「公共交通が活かせるようなまちづくり」「公共交通における今日的評価と社会的認知の向上促進」などの課題について、お話しいただきました。
また、戸崎先生も交えた交通事業者らとのパネルディスカッションでもフロアーとのやりとりも含めてパネラーの皆さんのお話は貴重なものでした。
特に、印象に残った点を下記に記しておきます。
▼公共交通を費用対効果で考えるだけではダメであって、社会的効果を評価しなければならない。そして、交通は社会生活の基盤として、何が成果か見えるようにしなければならない。
▼マイカー中心の道路・交通行政が、今の交通行政の弱体化を招いた。自治体のトップがその気にならなければならない。その熱量によって変わる。
▼公共交通は、高齢化社会を支えるインフラになっているという社会的認知の向上促進が求められている。
▼路面電車という基盤があるメリットを捨てる必要はない。
また、自治研究センターでは、昨年、「高知市における公共交通のクロスセクター効果試算及び利便性向上による利用促進政策」の提言書を高知市に提出し、路線バスと路面電車を乗り換えできるよう、結節点を整備することなどを提案しており、今後さらにこの提言をブラッシュアップすることのアドバイスなども頂きました。
いずれにしても、高知新聞の連載記事も含めて「明日の足 高知の公共交通」を考えていきたいものです。
 「県民の安心・安全を蔑ろにしかねない課題に対して結論を出すには、あまりに拙速でないですか。」
「県民の安心・安全を蔑ろにしかねない課題に対して結論を出すには、あまりに拙速でないですか。」
そんな声が、高まっています。
それを「安保法制反対」の声と一括りにして、十分に声を聴き、理解を求めようとしない姿勢に終始することでよいのでしょうか。
県は、昨日県庁ホームページ「特定利用港湾の指定の受け入れについて」に次のように報告しています。
○県では、高知港・須崎港・宿毛湾港に係る特定利用港湾の指定の受入れについて合意する旨、令和6年3月22日に国へ文書回答を行いました。
○国におけるこの取組みは、国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)に基づき、平素から、必要に応じて自衛隊・海上保安庁が民間の空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これらを「特定利用空港・港湾」とし、その上で、それらの空港・港湾について、あくまで民生利用を主としつつも、自衛隊・海上保安庁の航空機・船舶の円滑な利用にも資するよう、必要な整備や既存事業の促進を図るという内容のものです。
こんな紋切り型の報告で、県民が納得するとでも思っているのでしょうか。
そして、国への回答文書は次の通りです。
「総合的な防衛体制の強化のための公共インフラ整備について(回答)」との表題に続いて、「令和6年3月8日付けで依頼のあったうえのことについて、「高知港・須崎港・宿毛湾港における港湾施設の円滑な利用に関する確認事項」を確認しました。」
ここには、県民の思いは何も感じられません。
県民の思いを切り捨てるような、こんな県の棄民姿勢に県民の気持ちが離れ、県政への諦め感が生ずるのを危惧するばかりです。
| 3月22日「『特定利用港湾』にはリスクを上回るメリットがあるのか」 |



19日に、「特定利用港湾」の候補になっている高知港(新港含む)、須崎港、宿毛湾港がある高知、須崎、宿毛3市と県は、公開で意見交換会(こちらから画像も資料も公開されています)を開催しました。
自衛隊艦船による訓練などを通じた防災面での利点を挙げた一方、県民の不安払拭に向けた丁寧な説明を県に求める中、県港湾・海岸課が特定利用港湾の概要やこれまでの経緯を説明し、3月末までに政府と合意文書を取り交わしたいとの方針を了承しました。
県は、12項目の「県版Q&A案」を提示し、高知新港開港時(1997年)に県議会が全会一致で可決した「港湾の非核平和利用に関する決議」は船舶に非核三原則の順守を求めるもので、自衛隊艦船はこれを順守しているため、「今回の指定同意は決議に反しない」とか「自衛隊艦船の利用実態の変化は年数回の訓練増加程度と微小で、攻撃目標とみなされる可能性を有意に高めるものではない」などとしています。
しかし、これらについても疑問や懸念が解消されるものでなく、Q12に対する回答として示された、「県としては、これまでの国との協議の結果、「特定利用港湾」の指定受け入れに関しては、これに伴って想定されるリスクを上回る、十分なメリットが認められるのではないかとの心証を得ている。」などと言い切れるものでしょうか。
該当3市の首長は、不安を抱いている市民・県民に対する責任がどこまで果たせるのか、また、県としても浜田知事が掲げる目指すべき高知県像の一つとしての「安全・安心な高知」は「南海トラフ地震対策やインフラ整備」によるものだけでなく、平和であることこそが大前提であることが、確認されるべきではないかと思われます。
19日には、県内の平和市民団体や政党などでつくる「郷土の軍事化に反対する県連絡会」が、政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」の受け入れに反対する署名4260筆を浜田知事宛てに提出する場に、県民の会や共産党会派の議員とともに、立ち会わせて頂きました。
そして、夕方の19日行動では、3市と県の意見交換の中で、いずれも「県の意向を尊重する」と表明し、指定を受け入れる県の方針を了承したことに対する抗議の行動が行われました。
県民の声を十分聞かず、理解をえないままの余りに拙速な進め方に、県民の怒りが高まっていますし、「防災のための重要な整備」との大義を優先していますが、災害時に救援活動が行われるのも平和であればこそです。
有事の際の武力攻撃のターゲットにされる可能性を、「防災」という隠れ蓑で覆い隠して強行することがあってはなりません。
寺田寅彦は、「天災と国防」の中で、「今度の風害が『いわゆる非常時』の最後の危機の出現と時を同じゅうしなかったのは実に何よりのしあわせであったと思う。これが戦禍と重なり合って起こったとしたらその結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。」「戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけにはいかない。」と述べられています。
「戦禍」という有事は、「天災」の襲来と違って、「人間の力で避けられる」のである。
そのために、全力を尽くすことこそが、政府・自治体には求められているのではないでしょうか。
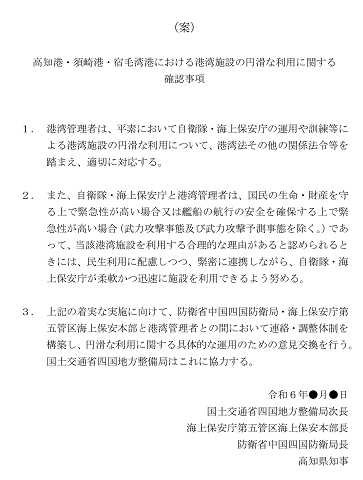
 私たちも、1月15日に平和憲法ネットワーク高知をはじめ、護憲連合高知県本部、高知県平和運動センターの三者で、防衛力の強化のため国が整備・拡充を予定している「特定重要拠点空港・港湾」について、高知県内での整備に反対するよう、県に申し入れていました。
私たちも、1月15日に平和憲法ネットワーク高知をはじめ、護憲連合高知県本部、高知県平和運動センターの三者で、防衛力の強化のため国が整備・拡充を予定している「特定重要拠点空港・港湾」について、高知県内での整備に反対するよう、県に申し入れていました。
しかし、県は、政府が特定利用空港・港湾の考え方を26項目にまとめたQ&Aを公表したことから、浜田知事は県議会の質問戦でQ&Aをなぞる形での答弁に終始し、県民への説明を丁寧に行おうとせず、声を十分に聞くこともせずに3月中に合意を図ろうとしています。
Q&Aでは、「有事の利用を対象としない」「施設の円滑な利用に関する枠組みを設けるが、そのことのみで攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは言えない」「自衛隊は武器・弾薬を含む物資輸送や部隊の展開のため、海上保安庁は火工品や弾薬の積み降ろしのために利用することがある」などと記したものではあるが、これらの文面だけでは読み取れない疑問点は残っています。
11日の県議会産業振興土木委員会委員に資料として配布された「特定利用港湾」確認案(写真)が明らかになりましたが、これまでも本会議で指摘されてきた「重要影響事態」(自衛隊として武力行使はできないが米軍の支援が可能)や「存立危機事態」(自衛隊が集団的自衛権に基づき、日本が攻められていなくても米国などと共に反撃できる事態)が、除かれていないことが確認できます。
知事は、この間「民生利用を主とした平時の訓練の枠組み」と説明してきましたが、確認案では、敵地を攻撃する米軍への武器弾薬の補給や米軍とともに自衛隊部隊が出撃する事態にも用いられることも含んでいるものと思われます。
「郷土の軍事化に反対する県連絡会」では、改めて12日に、県に受け入れに同意しないよう「本県港湾の特定利用拠点化に同意しないこと」「アジア諸国との平和外交を行うことで平和と善隣友好の機運を醸成する」「県民の合意を経ないまま拙速な判断をしないこと」の3点を申し入れています。
明日19日14時から公開で、「特定利用港湾に関する意見交換会」が共済会館で開催されますが、高知港、須崎港、宿毛湾港がある3市は県民の声を踏まえて意見交換をして頂きたいものです。
| 3月17日「地方のけじめこそ求められているのではないか自民党」 |
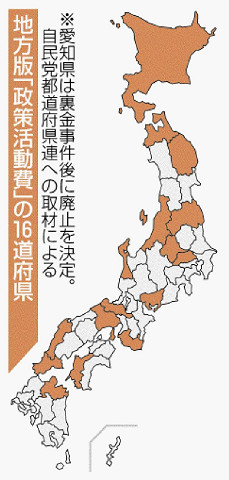 昨日の全国幹事長会議、そし今日は党大会を開催している自民党は、裏金問題を巡って地方組織がけじめを要求しているとのことです。
昨日の全国幹事長会議、そし今日は党大会を開催している自民党は、裏金問題を巡って地方組織がけじめを要求しているとのことです。
しかし、その地方組織においても、政党から政治家個人に支給され、使途を明らかにする必要のない「政策活動費」と同様の制度が16道府県連に設置されていたことが、昨日共同通信の調査で分かったことが報じられています。
派閥パーティー裏金事件を通じて政策活動費の不透明さが問題となり、野党が国会で制度廃止を提案されてもいますが、裏金事件で議員が逮捕された愛知県連は廃止を決めたが、他は廃止や使途の公開に後ろ向きのままで、政治資金のブラックボックス化が地方にも広く定着している現状が浮き彫りとなっています。
31都府県では政策活動費と同様の制度が確認されなかったとのことですが、近畿ブロック青年局の不適切懇親会など、国民からの信頼を失うことばかりが露呈する自民党に政権を担う資格はあるのかとの声が高まっています。
最新の共同通信の世論調査(3月9~10日実施)での政党支持率では、自民党が前回比7ポイント減の24.5%で、立民、維新、共産、国民、「れいわ」などオール野党の支持率を足した数値を比較すると、自民24.5%VS野党36.5%とオール野党が12ポイントもの大差をつけて自民を上回っています。
この支持率をしっかりと定着させる野党の取り組みも求められています。

 7日に一問一答で質問させて頂いた際の質問と答弁のテープ起こしができましたので、仮の議事録としてこちらにリンクを貼っておきますので、関心のおありの方はぜひご一読ください。
7日に一問一答で質問させて頂いた際の質問と答弁のテープ起こしができましたので、仮の議事録としてこちらにリンクを貼っておきますので、関心のおありの方はぜひご一読ください。
今回は、予定していた「孤独・孤立対策」の質問まで足らずで行き届かず、災害対策関連の質問のみで終わっています。
能登半島地震から見えてきた高知でも備えなければならない課題について質す中、少しでも加速化できたらとの思いで質問させて頂きました。
各常任委員会では、付託議案についての採決が全て終わり、来週の18日にはとりまとめの常任委員会を開催し、21日に閉会となります。
今議会では、議案ではありませんが、高知・須崎・宿毛港の「特定利用港湾」指定について、県民に対する十分な説類もなく、十分に声を聞くこともないまま、3月5日に国から示されたQ&Aを鵜呑みにし、知事が3月末には、同意する意向を示していることなど極めて大きい問題も残っています。
| 3月13日「震災直後から見続けてきた『震災遺構』」 |





昨日の天声人語に「震災遺構の力」と題した、当時の門脇小学校の校長先生のお話がありました。
▼13年前のあの日、鈴木洋子さん(73)は小学校の校長だった。両手で机をにぎりしめて揺れに耐えたあとで、児童や教職員と学校裏の山へ。3階建ての校舎は、燃えながら津波に流されてきた家などから延焼し、炎に包まれた。宮城県石巻市の旧門脇(かどのわき)小学校である
▼黒く焦げた校舎はいま、震災遺構になっている。校長室の乾いた泥の上には、流れ着いた赤いランドセルが転がる。4年2組の教室には、焼けて骨組みだけになった椅子が並ぶ。窓の向こうに目をやると震災の傷痕はほとんど見あたらず、復興祈念公園の芝生が海まで続く
▼校舎を残すことに、住民の多くは「見るのがつらい」と反対した。その気持ちを受け止めつつ、鈴木さんは説いた。「地震があったら早く逃げる。校舎そのものが未来の子どもへのメッセージなんです」
▼震災の影響で閉校していなければ、今年度は開校150年を迎えたはずだった。毎朝通ってくる子どもたちの姿はない。だが校舎には新たな使命が吹き込まれた。
私が、初めて門脇小を訪ねたのは、3.11から100日目の県議会の視察でした。
その惨状の背景にあった諦めずに裏山に避難した過程の教訓を語り伝えることの大切さを学んだものでした。
それからも、昭和小学校の先生方を引率して、門脇小学校を訪ね、当時の教頭先生からお話を聞かせて頂き、避難した裏山から校舎のどこから避難したのかも聞かせて頂きました。
そして、一昨年訪ねた時には、震災遺構となった年でしたが、到着したのが閉館した後だったので、入館できず残念でした。
鈴木先生の「地震があったら早く逃げる。校舎そのものが未来の子どもへのメッセージなんです」との言葉を受け止めて、やがて避難することに直面する高知の子どもたちに伝えていきたいものです。
| 3月12日「東日本大震災・能登半島地震の教訓で南海トラフ地震に備えて」 |


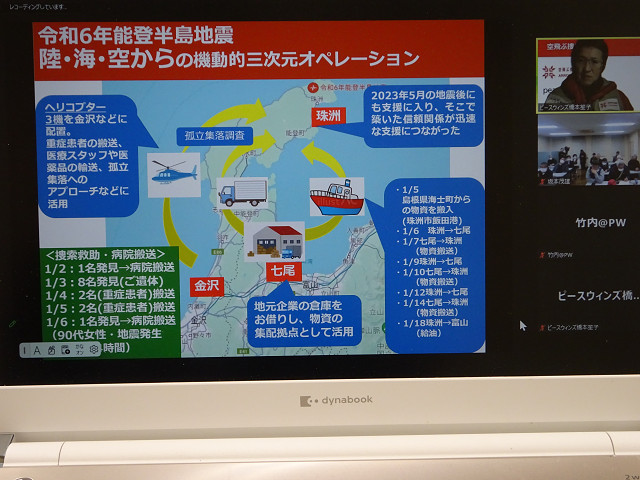
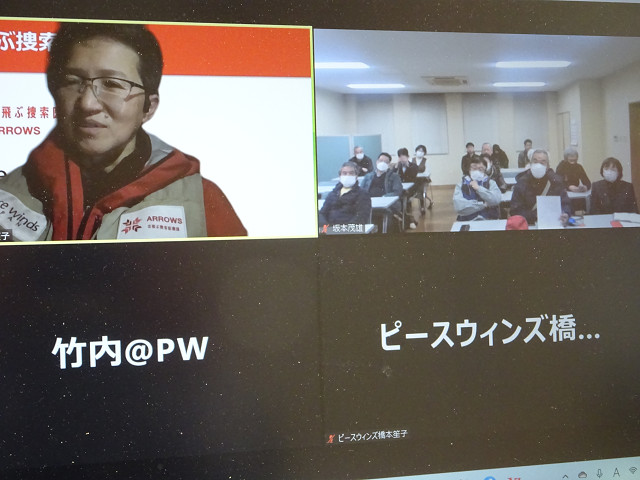
昨日は、東日本大震災の発生から13年となる3月11日で、下知地区減災連絡会では「3.11東日本大震災を忘れない追悼の集いを」青柳公園で開催しました。
10年目を節目に開催し始めて、今年で4回目となりますが、参加者20名余りが黙祷を捧げて、東日本大震災の教訓を南海トラフ地震への備えに生かしていくことを改めて決意しあいました。
例年は、この集いの後に、東日本大震災の被災地とオンラインでつなぎ、被災時と復興の今についてお話し頂いていましたが、今回は元日の能登半島地震の被災地珠洲市で救援・支援活動を継続されているピースウィンズジャパンの橋本笙子さんとつなぎ、お話を頂きました。
橋本さんでさえ「まだまだ備えが足りないぞと頭をガツンと叩かれた思いがした」という過酷な被災地の状況についてお話しいただきました。
珠洲市は昨年の5月の地震に次いでの大地震で、阪神淡路、中越、東日本の被害を合わせた被害を受けたが、さらにその後の被害を大きくした課題として、①限られた交通網②断水③高齢化率52%➃子どもたちの教育を突きつけられています。
東日本大震災から13年経つが、まだまだ被害の中で暮らされていることを思えば、能登でも復興には10年はかかるだろうし、20年かかるかもしれない。
南海トラフ地震と向き合う皆さんは、今来るかもしれないと考えて、準備しなければならない。訓練したことでできることがあった。
誰一人取り残さないよう頑張りましょうとのお話をされました。
参加者からの質問に答えて、避難所での過酷な状況を踏まえて、「非常用トイレ、水、食べ物、電気と通信網の確保」「避難所の寒さ対策として、ダウンジャケットを中に着込んで、暖をとったり、寝袋は良いものを持っておこう」など下知の皆さんへのメッセージを頂きました。
今の下知地区での取り組みをさらに、一段引き上げ、継続させていくことを改めて突きつけられた「被災地とつなぐ会」となりました。
| 3月10日「 道路寸断恐れ109市町村で、避難困難」 |
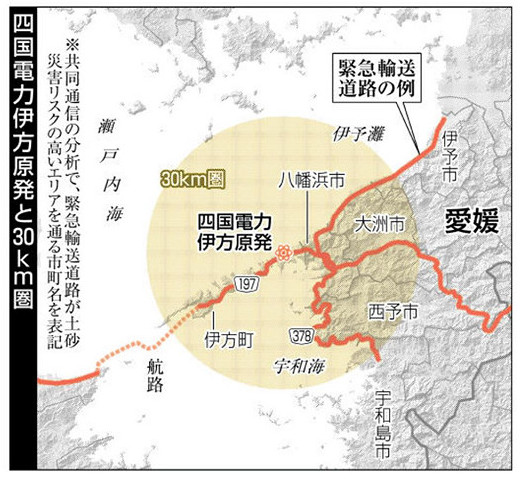
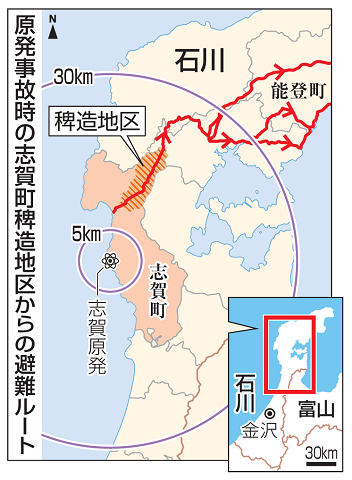 明日13年目の3.11を迎えるにあたり、福島原発事故から未だ復興が果たせない帰還困難区域の課題が浮き彫りになる時期です。
明日13年目の3.11を迎えるにあたり、福島原発事故から未だ復興が果たせない帰還困難区域の課題が浮き彫りになる時期です。
そして、元日の能登半島地震で志賀原発で事故が起きた場合の避難路が寸断されることによる避難すらできない課題も浮き彫りにされています。
昨日の共同通信の配信記事が、建設中を含む国内19原発の30キロ圏にある自治体のうち18道府県計109市町村で、地震など災害時の緊急輸送道路が土砂崩れなどにより寸断される恐れがあることを報じていました。
30キロ圏に含まれる21道府県計138市町村の79%に当たり、原発事故時の避難に支障が出る恐れがあるとされています。
警戒区域は、がけの傾斜などに基づき、地震や豪雨で崖崩れや地滑りが起きるリスクのある場所を都道府県が指定するものですが、避難経路を事前に定める必要がある原発30キロ圏を調べた結果、国道、県道など109市町村で延べ約500本の緊急輸送道路が警戒区域を通っています。
本県は、避難計画の策定義務のある原発から半径30kmの重点区域には入っていないが、万が一の事故に備えて避難計画を策定しているというが、その計画に実効性があるかどうかが問われています。
2012年2月議会で、私は、国際環境NGOグリーンピース・ジャパンが、四国電力伊方原発付近で、原発事故時の放射性物質の拡散範囲を調べるために紙風船を飛ばした結果、南東に85キロ離れた四万十市竹島付近の四万十川河口で、同日午後6時頃に発見連絡があったことから、警戒区域だとか計画避難区域とかいうのは、あまり関係ないと思われる放射能汚染の拡大について、指摘したことがありました。
避難計画の実効性が確保できない中、事故が絶対起きないと言えない以上、原発は人道上からも廃炉にすべきであります。

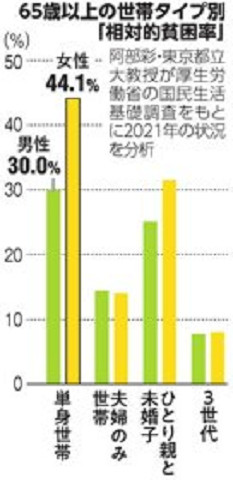 昨日3月8日は、国連が定める「国際女性デー」でした。
昨日3月8日は、国連が定める「国際女性デー」でした。
女性の差別をなくし、地位向上について考え、行動する日として、各地で多様な取り組みがされていました。
女性の就業率は上がっているにもかかわらず、働きにくい環境と、性差を理由に女性の昇進を阻む障壁が未だに存在していることも考えさせられます。
英誌エコノミストは7日までに、先進国を中心とした29カ国を対象に女性の働きやすさを指標化した2023年のランキングを発表し、首位は2年連続アイスランドで、日本は順位を前年から一つ上げたが下から3番目の27位だったことが明らかになっています。
先進国の中でも大きい日本の男女の賃金格差についての朝日新聞の分析では、女性の年収は20代後半から50代まで、正社員に限ってもすべての産業で男性を下回っているとのことです。
政府は女性活躍推進法の省令を改正し、22年7月から301人以上の企業に対し、男女賃金格差の開示を義務づけており、厚労省によると1月19日までに対象1万7370社のうち1万4577社が公表し、正社員女性の平均の賃金水準は、75.2となっているとのことです。
働いている世代においても男女間の賃金格差が継続する中で、さまざまなジェンダー格差が放置された末に、65歳以上の一人暮らしの女性の相対的貧困率が、44.1%にのぼることも分かりました。
貧困問題を研究する阿部彩・東京都立大教授が、厚生労働省の国民生活基礎調査(2021年分)の個票をもとに独自に集計し、1月末に発表したもので、厚労省が同調査で発表している現役世代のひとり親世帯(44.5%)と同じ、深刻な水準だと指摘されています。
20年の国勢調査によると、高齢単身世帯は約672万人で、3分の2の約441万人を女性が占めており、国立社会保障・人口問題研究所は、40年には高齢単身女性は約540万人に達すると推計されており、このままでは、この層の貧困問題がさらに悪化する恐れがあると言われています。
女性が働きづらさ・生きづらさを抱えさせられる社会を、このまま放置するわけにはいきません。
| 3月8日「議会質問は、南海トラフ地震対策だけで持ち時間終了」 |


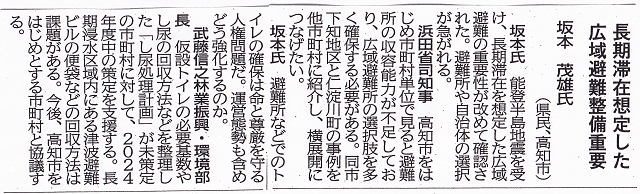
昨日の一問一答による議会質問は、結局最後の「孤独・孤立対策」の質問にまで、行き届かず終わってしまいました。
あれも言いたい、これも言いたい。
答弁を受けたら、また、一言いいたい。
結局時間が足りなくなる。
毎回反省できない私です。
今朝の高知新聞には、「広域避難」と「避難所等のトイレ対策」について簡潔に記載して頂いていますが、テープ起こしができたら、こちらに仮の議事録を掲載しますので、来週になるかと思いますが、今しばらくお待ちください。
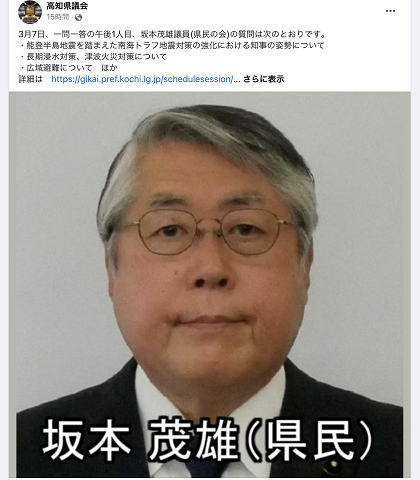 今日で、本会議における一括質問は終わり、明日から一問一答方式による質問戦に入ります。 私は、答弁も含めた40分間の持ち時間で、明日の午後一時から質問を行います。
今日で、本会議における一括質問は終わり、明日から一問一答方式による質問戦に入ります。 私は、答弁も含めた40分間の持ち時間で、明日の午後一時から質問を行います。
お構いない方は、議場またはネット中継で傍聴下されば幸いです。
質問予定項目は以下の通りですが、私の前の議員の質問次第で、重複する場合は省く場合がありますので、ご承知ください。
1 能登半島地震を踏まえた南海トラフ地震対策の強化における知事の姿勢ついて
(1)若い力を防災の担い手にすることについて
(2)「濵田が参りました」における意見交換について
2 長期浸水対策、津波火災対策について
(1)止水・排水対策の再検証が遅れている要因について
(2)結果を公表できる目途について
(3)タナスカ地区における津波火災対策について
(4)中の島地区における津波火災対策について
3 広域避難について
(1)長期滞在期間を想定した広域避難の必要性について
(2)広域避難先との事前交流について
4 避難所における生活環境の整備とトイレ対策について
(1)トイレ確保対策について
(2)津波避難ビルにおける便袋回収について
5 事前復興まちづくり計画の地区別計画具体化について
6 物資の備蓄について
(1)津波避難ビルへの分散備蓄について
(2)集合住宅に対する公助の支援策について
7 災害対応ガバナンスのあり方について
8 福祉避難所について
(1)福祉避難所の開設について
(2)災害関連死対策について
9 最悪の事態を想定した南海トラフ地震対策への決意について
10 孤独・孤立対策について
(1) 窓口機能について
(2) 自立支援を行う団体等への対応について
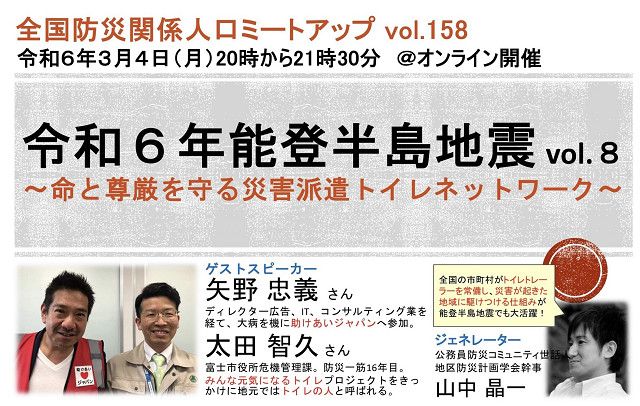
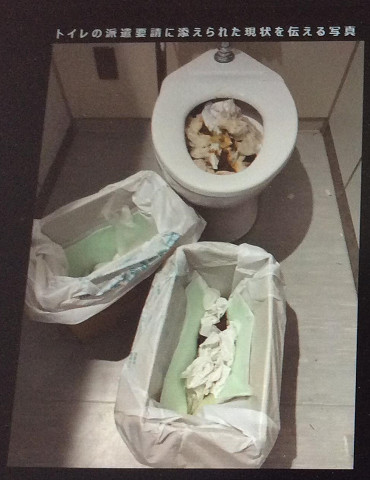 今議会での一問一答による議会質問が明後日に迫ってきました。
今議会での一問一答による議会質問が明後日に迫ってきました。
南海トラフ地震対策で準備していた質問項目も、今回ばかりは多くの議員さんが取り上げられるので、重複した質問を順次省いて、今日の正午までには発言通告書を提出する段階を迎えました。
そんな質問の中の一つで、避難所等におけるトイレ対策について予定しています。
昨夜のオンライン・全国防災関係人口ミートアップで「令和6年能登半島地震vol.8〜命と尊厳を守る災害派遣トイレネットワーク〜」として、上下水道の破損によりトイレが使えない能登半島地震でも全国から集結したトイレトレーラー「災害派遣トイレネットワーク」について、助け合いジャパンの矢野さん、太田さん(富士市役所危機管理課)に話題提供頂き、被災地のトイレ事情と事前の備えについてお話を聞かせて頂きました。
大変深刻な実態、そしてそれをどう変えていくのか、事前の備えとつながりについて貴重なお話を聞かせて頂きました。
質問の際には、そこでの話も紹介させて頂きながら、高知で避難所のトイレ確保対策について、少しでも改善できるような取り組みを求めて行きたいと思います。
| 3月3日「地区防災計画は今後もさらにコミュニティ防災を強化する」 |
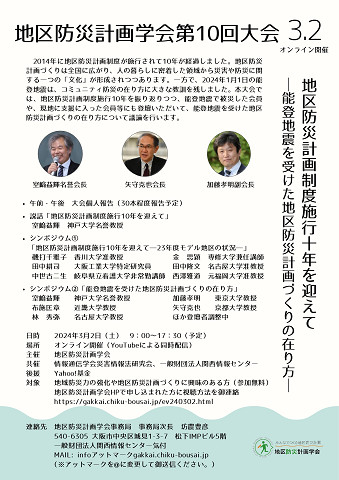
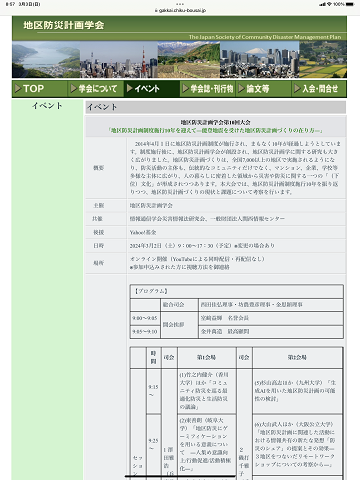
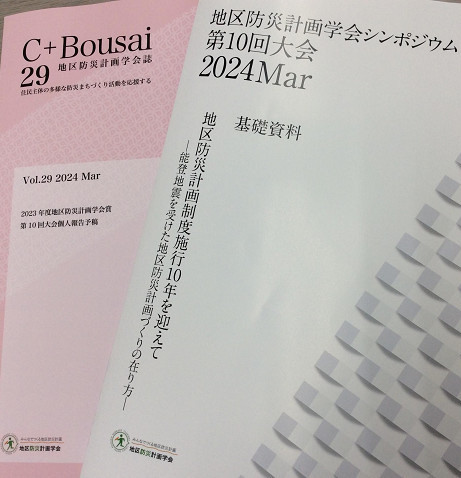
昨日は、地区防災計画学会第10回大会「地区防災計画制度施行10年を迎えて―能登地震を受けた地区防災計画づくりの在り方―」について、終日オンラインで参加していました。
今回は、2014年4月1日に地区防災計画制度が施行され、まもなく10年を迎える中で開催されるものでした。
地区防災計画づくりは、全国7,000以上の地区で実施されるようになり、防災活動の主体も、伝統的なコミュニティだけでなく、マンション、企業、学校等多様な主体に広がり、その成果や教訓に毎年学びあう学会大会となっています。
特に、今回は10年の節目であるとともに、元日の能登半島地震という大災害からの復旧・復興過程の中で迎えた大会でもあり、研究と実践の教訓が能登半島地震の教訓を繋いでいくことにもなるのではないかと思いながら、それぞれの発表を聞かせて頂きました。
先生方から出された「災害の進化は、防災の進化、とりわけコミュニティ防災の進化、地区防災計画の進化を求めている」「地域自立圏の形成」「地区防災計画の目標の一つは、災害直後の急性期を乗り越えること。できれば難なく乗り越えること」「能登半島地震では、孤立という言葉が頻出したが、例え孤立したとしても自立していれば、急性期を乗り越えることは可能」との言葉を改めて考えていきたいものです。
室崎名誉会長は、「言葉だけの防災教育から脱皮が求められている。被害想定をどう受け止めるか、ハザードマップをどう生かすのか。リスクマネジメントをコミュニティに根ざしたものにしなければならない。加えてクライシスマネジメントとしての被害把握や初動対応のあり方も問われた。前例のない被害は、前例のないコミュニティ防災を求めている。コミュニティ防災も、新しい技術を取り入れ、新しい仲間を招きいれ、変わらなければならない。想定外の事態が起きたときには、そこにあるコミュニティを含めた資源を活用して、急場をしのぐしかない。急場をしのぐにも、それなりの準備や計画がいる。いかなる事態にも対応できるようチームワークを磨いておく、想定外の条件を付与する訓練により応用力をつける、といった事前の研鑽や体質改善もいる。能登の経験に学んで、地区防災計画の番外編には「想定外に備える」計画を付け加えておこう。」と学会誌29号の巻頭言で述べられています。
まさに、大会に寄せて述べられたことだと思ったところです。
今から6年前の今日3月3日には第4回地区防災学会大会を高知で受け入れ、県立大永国寺キャンパスでの開催にあたっては、下知地区減災連絡会のメンバーが現地受け入れのスタッフとして汗を流したことを昨日のことのように思い出します。

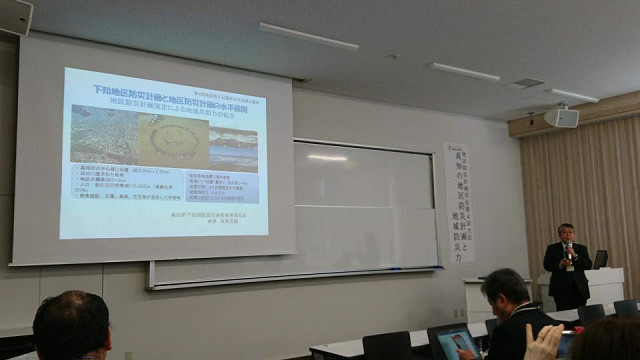
私も「下知地区防災計画と地区防災計画の水平展開ー地区防災計画策定による地域共助力の拡大」のテーマで報告をさせて頂きました。
地区防災計画策定過程の3年間で、何よりも地域の人と人とのつながりコミュニティの大切さを学び、災害に「も」強いまちづくりに向けて、地域の皆さんと力合わせていくことを決意した大会でした。
昨日の大会では、さらにそれをアップデートする「コミユニティ防災」の大切さを学んだことでした。
 自民党派閥による裏金事件を受け、自民党内のドタバタ劇の末に岸田文雄首相が出席する衆院政治倫理審査会が昨日、開かれました。
自民党派閥による裏金事件を受け、自民党内のドタバタ劇の末に岸田文雄首相が出席する衆院政治倫理審査会が昨日、開かれました。
案の定、ただ出席しただけとも言えそうな内容で「確認できていない」の繰り返しで、裏金作りの実態解明は進みませんでした。
ただ、「悪質な場面においては会計責任者のみならず、政治家本人も責任を負う法改正を行うことが重要である」と述べ、今国会中の法改正に意欲を示したとはいうが、果たしてどこまで本気の法改正が行われるかは問題です。
首相に続き、審査会に出席した二階派事務総長の武田良太元総務相は、同派の政治資金収支報告書の不記載を「全く知らなかった」と繰り返すだけでした。
そこで今日安倍派幹部の政倫審登場となるのだが、何と自民党は新年度政府予算案を今日の予算委で採決を強行し、可決すれば衆院本会議に緊急上程して同日中にも参院に送るための強行日程を小野寺委員長(自民党)の職権で決めたというのです。
結局、政倫審開催は、予算強行採決のアリバイ作りであったとしか思えないような国会運営に、腹立たしい限りです。
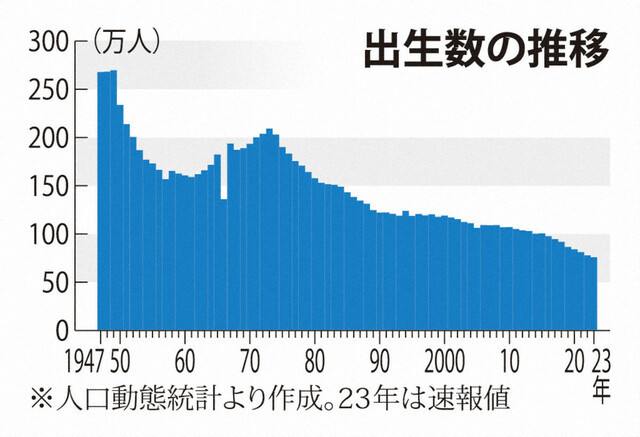 2023年に生まれた子どもの数は、過去最少の75万8631人で8年連続減で、婚姻数は48万9281組で、戦後初めて50万組を割ったことが、厚生労働省が27日に公表した23年の人口動態統計(速報)で明らかになっています。
2023年に生まれた子どもの数は、過去最少の75万8631人で8年連続減で、婚姻数は48万9281組で、戦後初めて50万組を割ったことが、厚生労働省が27日に公表した23年の人口動態統計(速報)で明らかになっています。
出生数は前年に初めて80万人を下回ったが、減少スピードに拍車がかかっており、国立社会保障・人口問題研究所が昨年4月に公表した将来推計人口では、35年に76万人を割って75万5千人になると推計していたが、今回の出生数は、推計より12年も早い結果となりました。
また、23年の婚姻数は、前年比3万542組減で減少率は5.9%、コロナ禍の20年に12.7%と大きく減った婚姻数は、22年に1.1%増となったが、再び減少に転じた形になっています。
少子化に歯止めがかからないのは、コロナ禍で結婚する人が減ったことが一つの要因ではありますが、コロナ禍から「平時」に移りつつある2023年も婚姻数が大きく減ったことで、専門家は出生数も減少傾向が続くとみられています。
お茶の水女子大永瀬伸子教授(労働経済学)は、背景の一つに女性に様々な負担が偏る現状を挙げており、「日本では子育ての負担も、仕事との両立の負担も、離婚した場合の貧困の負担も、女性にくる。若年層が子育ての魅力を感じられる社会の構築が、高齢化がすすむ日本の未来には必須だ」と指摘されています。
また、日本総研の藤波匠上席主任研究員は、児童手当の第3子以降が月3万円に増額されたり、3人以上の子どもがいる世帯は大学授業料などが「無償化」されたりする施策に関して「多子世帯の優遇策は、少子化対策としてミスマッチの印象」であり、「経済的な理由から結婚や出産を控える『第1子にたどりつけない層』へのアプローチが重要だ」と強調されています。
そのような中での、全国最少の子どもの出生数となった高知県で、待ったなしの少子化対策への施策が明日からの2月定例会質問戦で論議されることになります。
| 2月27日「逃げるな自民『政倫審』は全面公開で開催を」 |
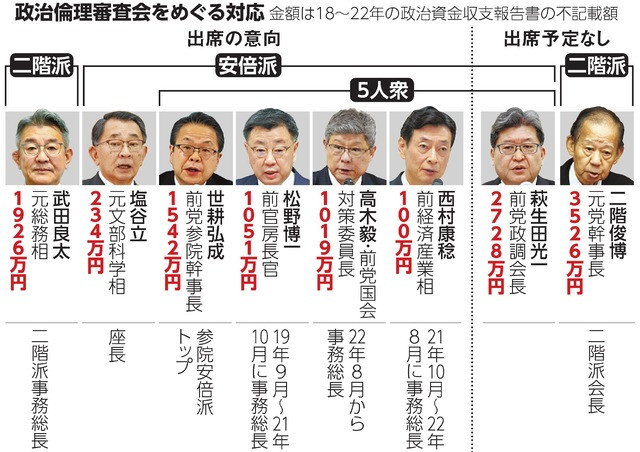 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆院政治倫理審査会(政倫審)の公開の可否を巡って与野党協議が紛糾しています。
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆院政治倫理審査会(政倫審)の公開の可否を巡って与野党協議が紛糾しています。
審査の全面公開を求める野党側に対し、自民は報道関係者への非公開を譲っていません。
政倫審は、公開するか否かの判断が出席者の意思に委ねられるほか、会議録も原則非公開で事実上閲覧できないこととなっています。
まさに、議員が説明責任を果たすべき場としては、制度面の限界が浮き彫りになっているとしか言いようがありません。
自民は、政倫審での審査を申し出た5人の意向として、政倫審に所属しない議員や報道関係者の傍聴を認めない「完全非公開」での審査を主張しており、野党側は「国民に直接説明する審査会であるべきだ」と反発しています。
しかも、政倫審の規程では、会議録が原則非公開とされ、議員以外が閲覧する場合は政倫審での決議が必要になるとされており、これまでも一般閲覧の例は「聞いたことがない」といわれています。
昨日の衆院予算委員会では、立憲民主党の野田元首相から岸田首相自身が政治改革の障害になっているとまで迫られながらも、論点ずらしの曖昧答弁に終始する岸田首相に国民が不信感を募らせるのは当然のことでしょう。
国民の誰もが、「この機会に全面公開のもとで、事実を明らかにし、国民の理解を求めることで、自民党に対する信頼を取り戻せる絶好の機会ではないか」と思うのでしょうが、そう判断しないのは、「全面公開」できない理由があるからだと思わざるをえません。
このまま与野党合意に至らず非開催になったり、「全面非公開」で28、29両日の審査会を強行などすれば、政治不信はさらに高まるものと思われます。
| 2月26日「福祉避難所はいざという時に開設できるよう」 |
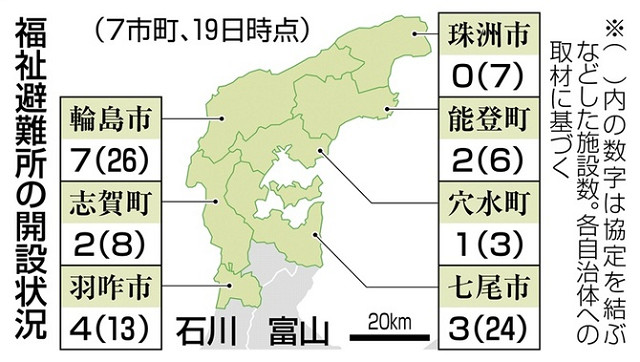 以前にも、高知県における災害時要配慮者が避難可能な福祉避難所は、県全体で必要な17,184人分に対し、指定は令和5年9月末時点で10,500人分にとどまっており、特に高知市では、必要な12,544人分に対し、指定は5,265人分にとどまり、7,279人分が不足している状況にあることを報告しました。
以前にも、高知県における災害時要配慮者が避難可能な福祉避難所は、県全体で必要な17,184人分に対し、指定は令和5年9月末時点で10,500人分にとどまっており、特に高知市では、必要な12,544人分に対し、指定は5,265人分にとどまり、7,279人分が不足している状況にあることを報告しました。
県も、能登半島地震を受け、未指定の施設に対する指定意向調査や理解を深めて頂く周知を図り令和6年度中に改めて、指定促進に向けた市町村の取組を後押ししていくとしています。
福祉避難所として必要な施設確保も当然ですが、能登半島地震では、開設予定の福祉避難所施設の損壊や職員の被災で予定の2割しか開設できなかったことが、報じられています。
石川県内全体の2次避難者は計7千人超に上ったが、大勢をホテルなどに避難させる調整に時間がかかり、支援が必要な高齢者や障害者の対応は後手に回ったと言います。
輪島市で知的障害者向けのグループホームを運営する社会福祉法人は、入所者と家族、職員の約30人で金沢市などへの避難を県に要望したが、約1カ月にわたって行き先が決まらなかったそうです。
まさに、今求められているのは「量の確保」とともに、いざという時に福祉避難所としての機能を維持し開設できる「質の向上」も求められていると言えます。
高知における、その備えも重要な課題です。




本来なら、もっと早く発刊して皆さんのお手元に届けておくべき「県政かわら版」第73号なのですが、先週やっと印刷に発注したところです。
自分の質問日(3月7日登壇予定13時~40分間の持ち時間)までに、皆さんのもとにお届けできるかどうかは、疑わしい限りです。
納品されてから、郵送分の封筒詰めや手配り用の地域ごと区分などを行って、支援いただく皆さんのお手伝いで、なるだけ早い時期にお届けさせて頂きたいと思います。
それまでは、ご関心ある方は、こちらからデータでお読み頂ければ幸いです。
| 2月23日「県議会二月定例会開会 人口減少対策柱に 地震対策強化の議論も期待」 |



県議会2月定例会が21日開会し、2024年度一般会計当初予算案4655億6300万円など85議案を提出しました。
浜田知事は提案説明で、「最重要課題である人口減少の克服に向けて道筋をつけ、未来を切り開いていく、その新しい一歩を踏み出す1年にしたい」と強調し、能登半島地震を踏まえ、住宅耐震化の促進など南海トラフ地震対策を強化する決意も示しました。
知事は、人口減対策のマスタープラン「県元気な未来創造戦略」に基づき、若年人口の増加、婚姻数の増加、出生率向上の取り組みを総合的に進めることで「着実に出生数の増加につなげる」としており、県と市町村が方向性を合わせ、緊密に連携していくために、10億円規模で「人口減少対策総合交付金」を創設し、「地域の実情に応じた取り組みを財政面から強力に支援する」としています。
また、南海トラフ地震対策では、住宅耐震化など建物倒壊対応、火災対策、道路被害や孤立地域への対応、受援態勢の整備、津波からの早期避難意識率の向上、水道管の耐震化や広域避難のあり方などの課題を挙げ、行動計画の見直しや補正予算での対応を含め、必要な対策を早急に講じるとしています。
いつもの議会では、南海トラフ地震対策が本会議で議論されることは少ないですが、今回ばかりは登壇者すべてが取り上げるのではないかと思いますが、期待したいと思います。
私も3月7日の一般質問で一問一答方式で質問しますので、しっかりと質していきたいと思います。(登壇予定13時~40分間の持ち時間)
| 2月22日「万博のデザイナーズトイレはトイレトレーラーに」 |

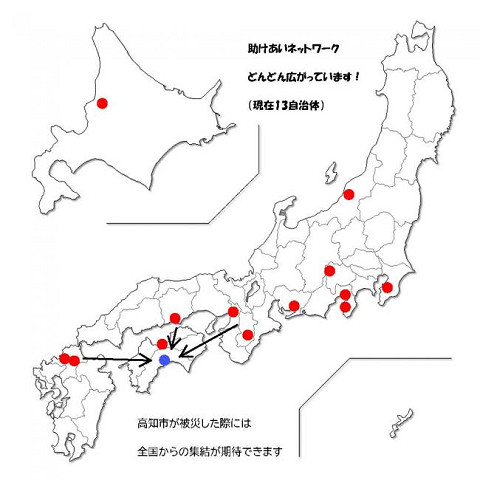 何かと物議を醸してきた大阪関西万博だが、ここにきて350億円もの巨額建設費が投じられた大屋根(リング)に続き、新たに「2億円トイレ」の問題が、浮上しています。
何かと物議を醸してきた大阪関西万博だが、ここにきて350億円もの巨額建設費が投じられた大屋根(リング)に続き、新たに「2億円トイレ」の問題が、浮上しています。
斎藤経済産業相は20日の閣議後会見で、記者から聞かれて、会場内に約40カ所の公衆トイレの設置を計画し、そのうち8カ所は、若手建築家が設計し、デザイン性を考慮して仕様を決めた「デザイナーズトイレ」というものであり、その一部に約2億円で契約を行った施設があると認めたそうです。
日本国際博覧会協会の契約情報によれば、デザイナーズトイレ8カ所のうち3カ所は入札が「取止め・不調」で、落札が決まった5カ所の設置費用は計6億6千万円に上り、うち2カ所が各2億円を占めているとのことです。
斎藤大臣や自見万博相も、50~60台の便器を備えているとして「規模から考えれば必ずしも高額とは言えない」と言い訳をしており、大阪府の吉村知事も「平米単価にすると、一般の公共施設のトイレと値段は大きく変わらないというのが事実」などと主張しているそうです。
しかし、これらのトイレを設置する万博会場は閉幕後に取り壊されるもので、その後のこのトイレの利活用も定かでないと言われています。
能登半島地震を受けて、「大阪国際万博は中止を」の声は、今まで以上に高まっています。
私も、このまま万博が開催されることには強い違和感を覚えているものです。
その中で、このトイレ問題を突きつけられたら、いい加減にせよと言いたくなります。
せめて、この「デザイナーズトイレ」を災害時に役立つ「トイレトレーラー」にして、万博後には、平時には各種イベントで活用し、有事には被災地に一気に派遣する形で大阪府が保管でもすれば、多少なりともの理解は得られるのだろうにと思わざるをえません。
| 2月21日「地震は止められないが、原発は止められる」 |
 1975年の原発誘致決議から2006年まで31年間に及ぶ長い闘いの結果、珠洲原発は断念されていましたが、先人の闘いに感謝するしかありません。
1975年の原発誘致決議から2006年まで31年間に及ぶ長い闘いの結果、珠洲原発は断念されていましたが、先人の闘いに感謝するしかありません。
そして、今回明らかとなったのは、志賀原発の避難計画がいかに絵に描いた餅であったのかということです。
志賀原発から半径30キロ圏内に暮らす約15万人は、今の「志賀町原子力災害避難計画」では、原発北側の住民は重大事故時、山間部を抜けて半島の先端に近い能登町に避難することになっています。
そして、「主たる移動手段は自動車。自家用車で避難できない人はバスを使う。避難ルートは国道、県道など。自衛隊車両や海上交通手段も使う」となっていますが、道路は各所でズタズタ、海路も使えない、避難しようにも動けない地区があちこちにあったのです。
内閣府によると、石川県が30キロ圏外への基本的な避難ルートと位置づけた11路線のうち7路線が崩落や亀裂で寸断し、志賀原発の5~30キロ圏では、一時、輪島市と穴水町の計8地区が孤立状態となっていました。
11路線のひとつでもある国道249号は「斜面の崩壊やトンネル内の崩落など、被災が極めて大規模な箇所がある。本格復旧には数年かかる見込み」と国土交通相も言及しています。
まさに、避難計画の前提がいくつも崩れた中で、もし、地震や津波に原発事故が重なる複合災害になっていれば、大混乱が生じた可能性が高いことは明白です。
もし志賀原発が稼働していて事故を起こしたら、原発周辺の人たちは逃げようにも逃げられませんでした。
この避難計画は原子力規制委員会の審査対象外であり、専門家のチェックも入らない中で、明らかになったのは、地震の際の避難計画に実効性はないということです。
地震は止められませんが、原発は止められます。
| 2月19日「8割超の政権不支持の怒りの声を結集して」 |
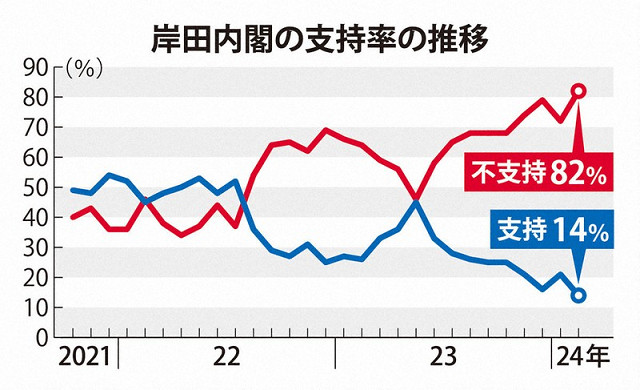 毎日新聞の17、18日実施の世論調査では、岸田内閣の支持率は、1月の前回調査(21%)より7ポイント減の14%で2カ月ぶりに下落し、岸田政権発足以来最低となり、不支持率は前回調査(72%)より10ポイント増の82%となっています。
毎日新聞の17、18日実施の世論調査では、岸田内閣の支持率は、1月の前回調査(21%)より7ポイント減の14%で2カ月ぶりに下落し、岸田政権発足以来最低となり、不支持率は前回調査(72%)より10ポイント増の82%となっています。
調査方法の違いから単純比較はできませんが、内閣支持率14%は、2009年2月の麻生内閣(11%)以来の低い水準で、不支持率が80%を超えるのは、1947年7月以来、初めてのことだそうです。
こんな状態の政権が継続していること自体理解に苦しみます。
調査の中では、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り問題のあった自民議員を国税当局が「調査すべきだ」が93%を占めています。
しかし、派閥からのパーティー券収入還流分などを政治資金収支報告書に記載してこなかった安倍派と二階派の議員・支部長計85人は、自民の党内調査に対し全員が不記載分を政治活動費以外に使ったことはないと答えています。
そのような中で、政党から政治家個人に支給され、受け取った政治家は使い道を明らかにする必要がない「政策活動費」について、「使い道を明らかにすべきだ」と答えた人は90%にのぼっています。
「政治とカネ」の問題に根本から取り組むなら、政治資金規正法の「抜け穴」となっている政策活動費の見直しこそか求められています。
自民党では、政策活動費として2022年に党幹部へ計約14億円を支出しており、最多の茂木幹事長は約9.7億円で、二階元幹事長は在任中の5年間に約50億円を受け取ったとされています。
だが、岸田首相は、公開すれば「党の活動と関わりのある個人のプライバシー、企業・団体の営業秘密を侵害する」と繰り返すばかりで、政策活動費の見直しには後ろ向きの姿勢に終始しています。
政治資金を国民監視の下に置くのが規正法の趣旨であり、政治活動について国民が知る権利よりも、党の利益を優先し、不透明なカネの流れを断ち切る抜本改正に取り組まないのであれば、国民の政治不信は払拭されることはありません。
今後、このようなことを招かないためには、今こそ抜本的な真相究明と政治資金規正法の改正抜きに、この問題を終わらせてはなりません。
| 2月16日「『共働き・共育ち』は安全高知での本気度を」 |
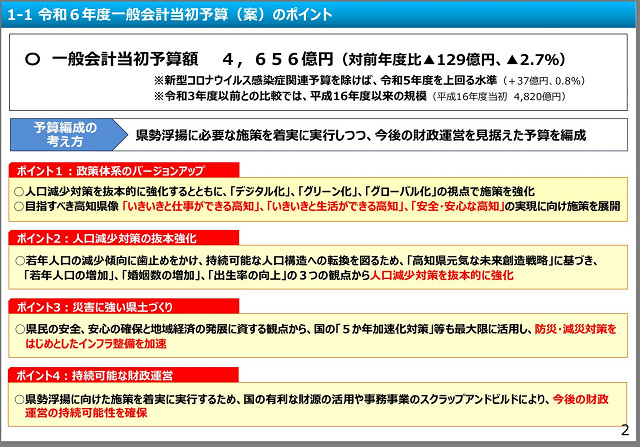
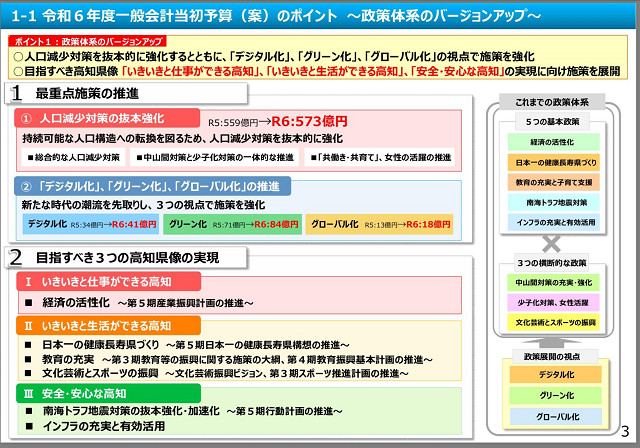



県が昨日、2024年度当初予算案を発表しました。
一般会計で4655億円(前年度比2・7%減)となっていますが、新型コロナウイルス関連費を除くと、浜田県政が19年に発足して以来続いている「積極型予算」は維持されています。
22年の出生数は3721人で、過去最少かつ全国最少だったが、23年は3千人台前半にまで落ち込むと言われる中で、中山間対策を含めた人口減少対策を抜本強化したのが特徴となっています。
特に、新年度予算には、市町村が地域の実情に応じて移住や定住の促進、子育て支援などを進められるよう「人口減少対策総合交付金」10億円を計上しています。
この事業は4年間を想定しており、計40億円規模になる見通しで、4、5年後までに若年人口(34歳以下)の減少傾向に歯止めをかけ、おおむね10年後までに現在の水準まで回復させることを目指すとしています。
人口最少県の鳥取県が「子育て王国とっとり」の取組を2010年に始めて、2022年の人口動態統計(概数)で、「合計特殊出生率」が1.60(前年1.51)となり、全国平均の1.26を大きく上回り、沖縄県、宮崎県に次いで、全国3位(前年10位)となっています。
生まれた赤ちゃんの数(出生数)は、3752人と前年から44人増加し、全国で唯一増加しています。
まさに「子育て王国とっとり」と銘打ち、10年かけて重ねた取り組みの成果が表れ始めています。
高知県では「おおむね10年後までに現在の水準まで回復させることを目指す」と言われているが、今年の「人口減少対策総合交付金」の検証をし続け効果的であれば、規模増額も必要だし、期間の延長も必要であることを指摘しておきたいと思います。
また、高知への移住者を増加させるなら南海トラフ地震をはじめとした自然災害リスクを減少させ、安心して暮らしてもらえる高知でなければなりません。
観光キャンペーンのキャッチフレーズではなく、本当に暮らし続けたい環境を整えた安全な「極上の田舎・高知」で共働き・共育ちを体感できる本気の施策が求められていると思います。
そんなことが、議論される2月定例会も21日から開会となります。
私は、3月7日に一問一答による質問予定となっていますが、近づいてきたら質問内容などをお知らせしたいと思います。
| 2月15日「男女・正規非正規賃金格差の是正も春闘課題」 |
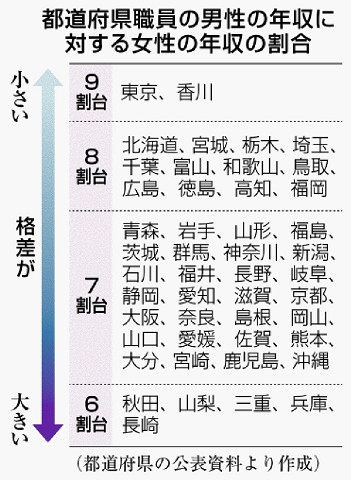 今朝の高知新聞一面に「都道府県職員年収に男女差 22年度男性の7割台過半数」との見出し記事があります。
今朝の高知新聞一面に「都道府県職員年収に男女差 22年度男性の7割台過半数」との見出し記事があります。
都道府県などの自治体と中央省庁は女性活躍推進法に基づき、2023年度から前年度分の男女の賃金差公表が義務付けられており、これをもとに共同通信が、47都道府県が公表した2022年度の職員給与に関する男女格差の資料を集計分析したもので、平均年収は全てで女性が男性を下回り、半数を超える28府県では男性の7割台だったことが明らかになっています。
図のとおり平均年収の差が比較的小さく女性が男性の9割台だったのは香川(93.7%)と東京(90.8%)だけで、83.1%の本県を含む12道県が8割台で、28府県は7割台、残る5県は6割台と格差が大きくなっています。
47都道府県を単純平均した賃金格差は77.6%となっていますが、市町村職員なども含めた自治体職員全体となるとどうなのかも把握する必要があろうかと思います。
また、公務労働に詳しい上林陽治立教大特任教授が地方公務員の賃金差を独自に試算したところ、男性正規一般行政職の平均時給を100%とした場合、女性正規は89%、男女別の資料が公表されていない非正規一般事務職は男女計で43%となっていることからも、この「男女差異公表」だけでは表れない実態があると思われます。
民間企業の賃金の男女差は、従業員301人以上の企業に開示義務があり、厚労省による1万4577社の24年1月時点の状況では、女性の平均年収は男性の69.5%だったとのことです。
いずれにしても、現場の実態を直視しながら、厳然として存在する男女格差、正規非正規格差の是正に向けた課題も春闘の大きな課題であろうと思います。
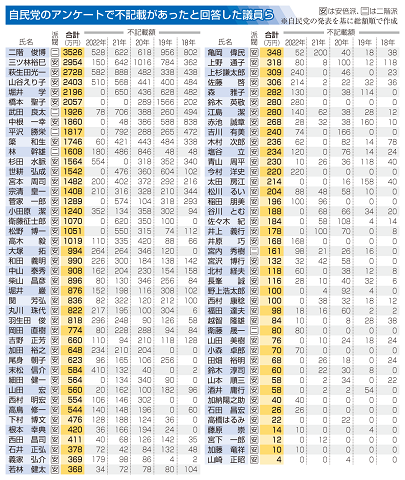
自民党は13日、派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件に関して実施した、党所属国会議員らを対象としたアンケート調査結果を公表しました。
パーティー券収入のキックバックや中抜きに関する政治資金収支報告書への不記載や誤記載があったのは85人で、総額は計5億7949万円に上っているが、新たな不記載の事例はありませんでした。
アンケートの設問は2問のみの調査で、収支報告書への不記載の有無と、ある場合は18~22年の各年の不記載額の記入を求めるのみで、使途などに関する設問はない上に、個人や都道府県連のパーティーなどは含まれておらず、真相解明にはほど遠い状況です。
裏金事件で逮捕・起訴されたりして党を除名されたり、離党したため調査対象外となった議員や元職も含めると議員側の不記載は総額約7.8億円とみられています。
結局、今回の調査に限らず、旧統一教会との関係でも党内調査以降次々と新たな事実が浮上したりして、党内調査の限界が浮き彫りになっています。
裏金が何に使われたのかという使い道も調査すらせず、国民の信頼を取り戻すなど到底無理なことであり、調査の名に値しない「調査結果」などで終わらせることなく、実態を明らかにするための徹底した追及が求められています。
| 2月13日「弱者に集中する『災害関連死』をなくすために」 |

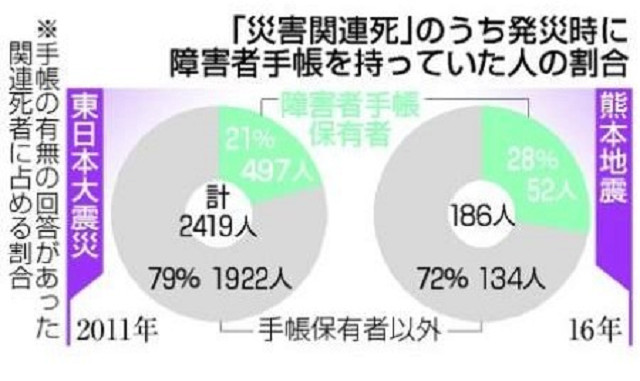 高知新聞2月11日付け一面トップの記事は「災害関連死、2割超が障害者 「救えた命」への対策急務」の見出しで、被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」のうち、発災時に障害者手帳を持っていた人の割合が、2011年の東日本大震災で21%、16年の熊本地震で28%だったことが、自治体への共同通信の調査で分かったと報じられていました。
高知新聞2月11日付け一面トップの記事は「災害関連死、2割超が障害者 「救えた命」への対策急務」の見出しで、被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」のうち、発災時に障害者手帳を持っていた人の割合が、2011年の東日本大震災で21%、16年の熊本地震で28%だったことが、自治体への共同通信の調査で分かったと報じられていました。
国の推計によると、障害者は人口の9%ほどとされ、リスクが際立っていますが、関連死は適切な支援があれば防げると言われます。
能登半島地震の際にも、「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」からは、いち早く「災害関連死が懸念されますが、過去の災害関連死の事例でも、避難生活の肉体的・精神的負担を原因とするものが大きな割合を占めており、早期にその負担を軽減する支援が実施されなければ、救えたはずの命が失われかねません。」として、「早急な広域避難措置を講じること」と「災害ケースマネジメントの実施」を盛り込んだ「令和6年能登半島地震に関する緊急提言」が、発せられています。
能登半島地震の8日時点の死者数241人のうち15人が災害関連死と言われる中で、劣悪な環境の避難生活が続くこれからさらに増えることが心配されます。
南海トラフ地震が想定される高知県においても、障がい者や高齢者など災害時要配慮者が避難可能な福祉避難所は、県全体で必要な17,184人分に対し、指定は令和5年9月末時点で10,500人分にとどまっており、特に高知市では、必要な12,544人分に対し、指定は5,265人分にとどまり、7,279人分が不足している状況にあります。
県も、能登半島地震を受け、未指定の施設に対する指定意向調査や理解を深めて頂く周知を図り令和6年度中に改めて、指定促進に向けた市町村の取組を後押ししていくとしています。
さらに、避難行動要支援者の個別避難計画については、令和元年度末の作成率19%から令和5年9月末時点の65%まで上昇しているものの、引き続き、計画作成を着実に推進するとともに、訓練等による計画の実効性向上を図っていくとしています。
守った命を「つなぐ」ために、要配慮者に集中する「災害関連死」に至らせないために、支援策を強化することが求められています。
| 2月12日「映画『雪道』、『建国記念の日に反対し日本の今と未来を考える集い』に学ぶ」 |



一昨日は、朝の準備から後片付けに追われた昭和小防災オープンデーのため、疲労困憊でしたが、何としても見ておきたかった映画「雪道」の最終回上映を鑑賞するため、自由民権記念館に行きました。
映画「雪道」は2015年、KBS韓国放送公社が制作したものを2017年に映画化された作品だそうで、他の韓国映画と同様、国際的に高い評価を受け、多くの賞を受賞しています。
作品は、日本軍「慰安婦」がテーマで、そのエピソードは元慰安婦の方々の証言が元になっているそうで、当時の創氏改名や日本語教育など日本の植民地支配の様子が描かれていました。
軍の慰安婦とされた主人公のヨンエとジョンプンの強いられてきた生きざまに、改めて、日本軍が侵略先の国々で、いかなる暴虐の限りを尽くしてきたのか突きつけられました。
しかし、それをなかったことにしようとする教育の中で、日本の教科書は改ざんされているのが、今の教科書検定なのではないかということを、昨日の講演会で、学ばされました。
昨日は、「『建国記念の日』に反対し、日本の今と未来を考える集い」に参加し、「子どもと教科書全国ネット21」の鈴木敏夫事務局長による「戦争する国づくりと今~教育と教科書が狙われている」とのテーマで、そのことを実感させられる今の日本の教育と教科書の在り方について、120人の参加者の皆さんとともに、聴講させて頂きました。
| 2月11日「昭和小防災オープンデー『防災』で地域と学校をつなぐ」 |



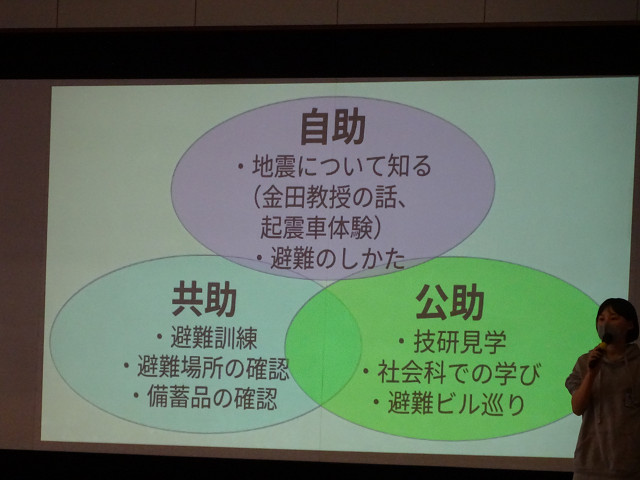




昨日の「昭和小防災オープンデー」では、午前中の「防災体験ブース」は、はしご車救助訓練で屋上から救出するという訓練を中心に、救助工作車、水難救助車などの展示や「プール放水体験」「煙体験」「電気自動車給電デモ」「起震車」なとが運動場で行われました。
4年生以上の体験、お世話いただくPTA役員の皆さんや地域から参加された方などが見学した約2時間でした。
地域からは、近隣の事業所の社長さんや医療機関の事務局の方も参加されるなど、これまでとは違った参加状況には、能登半島地震の教訓からの動機づけがあるものと思われました。
午後の部は、地域住民も保護者や生徒の皆さんとともに、屋上への避難訓練を行しましたが、地域から参加してきた皆さんは、そのまま土足で屋上まで登りましたが、初めて屋上までのぼったという方もおられました。
その後、地域の方は避難した後に過ごす北舎の待機室を見学してもらい、避難後のあり方などについても説明させて頂くと、「知らなかった。」との感想なども漏らされていました。
体育館での5年生の防災学習の発表やいろんなブースでの体験も多様なものがあり、5年生のこの一年間の防災学習の成果を見せて頂きました。
学習テーマを自分事にしながら、発表されていた5年生が今後も継続して、防災を自分事にしながら、成長し続けて、地域の防災訓練などにも参加し、地域防災の担い手になって頂くことを願うばかりです。
さあ、13日には下知地区減災連絡会役員会を開催し、この間の取り組みを総括しながら、次年度につないでいく取り組みの議論をしていくこととなります。
そのためのレジュメ作成にも取り掛からなければなりません。
| 2月9日「昭和小防災オープンデーで地域と学校の防災交流」 |
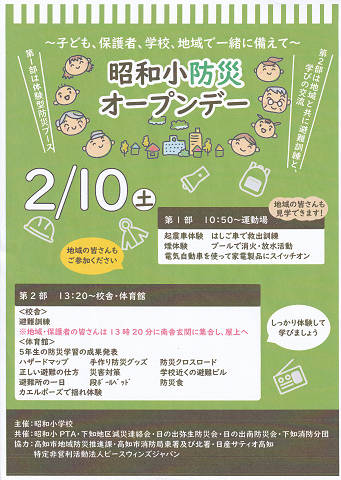 いよいよ明日10日は、「昭和小防災オープンデー」。
いよいよ明日10日は、「昭和小防災オープンデー」。
災害時には、昭和小学校に避難予定の地域住民の皆さんと生徒たちと参観日に出席された保護者の皆さんとともに、防災体験、避難訓練や5年生の防災学習の交流などを行います。
午前中の「防災体験ブース」は、昨年人気を博した「災害救助犬コーナー」が、今年は能登半島地震のために参加できませんが、はしご車救助訓練で屋上から救出するという訓練が子どもさんにとっては関心あるものになるのではないかと思います。
また、その他の防災体験では、「プール放水体験」「煙体験」「電気自動車給電デモ」「起震車」なとが運動場で行われます。
そして、午後の部は、地域住民も保護者や生徒の皆さんとともに、屋上への避難訓練を行った後、体育館で5年生の防災学習の発表やいろんなブースで体験もして頂きます。
学校の備蓄品・災害対策・防災グッズ・段ボールベッド・防災グッズをすごろくで学ぶ・避難所の一日・手作り防災グッズ・防災食・学校近くの避難ビル・防災クロスロード・避難所での生活・救助のしかた・技研REDHILL・防災アプリ・地震の歴史について・ハザードマップ・正しい避難の仕方などに加えて下知減災連絡会と高知市地域防災推進課の皆さんで、ロープワーク教室、段ボールベッドづくり、カエルポーズで揺れ体験なども行います。
毎回、学びの多い防災イベントになっていますので、明日も期待されます。
ご近所の皆さんは、どうぞお越しください。
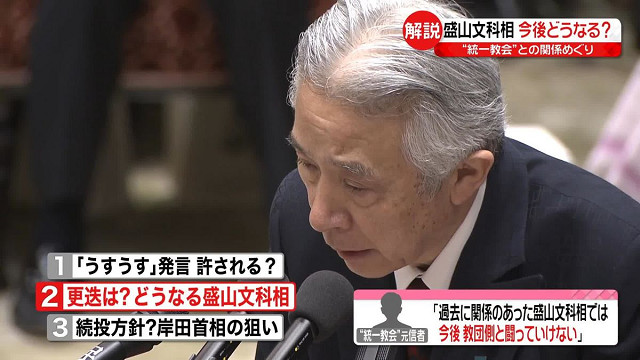
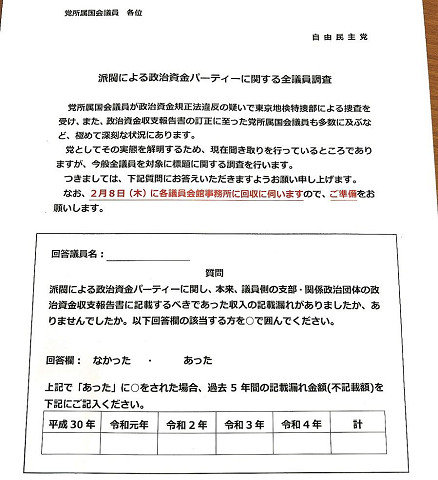 宗教法人を所管する文科相として、旧統一教会の解散命令を請求した盛山大臣は、教団との関係は断ち切られていて当然のはずが、今頃になって2021年の前回衆院選で、教団系団体の世界平和連合から「推薦状」を受け取り、選挙支援を受けていたことが明らかになっています。
宗教法人を所管する文科相として、旧統一教会の解散命令を請求した盛山大臣は、教団との関係は断ち切られていて当然のはずが、今頃になって2021年の前回衆院選で、教団系団体の世界平和連合から「推薦状」を受け取り、選挙支援を受けていたことが明らかになっています。
さらに、国会での質疑を受け、事実上の政策協定にあたる「推薦確認書」も交わしていた疑いもあり、「確認できない」「はっきりした記憶はない」との釈明から、「報道があるまでは正直覚えていなかったが、薄々思い出してきた」と答弁せざるをえなくなりました。
旧統一教会との関係についての22年の自民党の点検に対し、当選後に関連団体の会合で挨拶をしたことだけ申告し、選挙の経緯は伝えておらず、文科相就任時にも明らかにしていませんでした。
教団の解散請求をめぐっては、今月22日、国と教団双方から意見を聞く審問が東京地裁で始まるが、盛山氏が教団への負い目を抱えたままで適切な立証を進められるのか、疑念を抱かざるをえないと国民の不信感は高まっており、岸田首相は、盛山氏を即刻解任すべきです。
結局、このような調査しかしていなかったとなれば、今度の裏金問題の自民党所属議員を対象にしたアンケートなども、全く信頼できないのではとの声が高まるのも当然です。
しかも、このアンケートに至っては、収支報告書への記載漏れの有無と、過去5年の不記載額の記入を求める2問だけで、不記載の経緯も、そのお金の使い道も尋ねていないことから、全員を対象に聴いたというアリバイ作りにすぎないと言われても仕方ありません。
過去にふたをする姿勢に終始する自民党に、自浄作用を求めることは無理です。
今度は、このままで放置させないという有権者の姿勢を示さなければなりません。
| 2月7日「高知の防災がカリブ、大洋州等の島嶼国にも生かされたら」 |



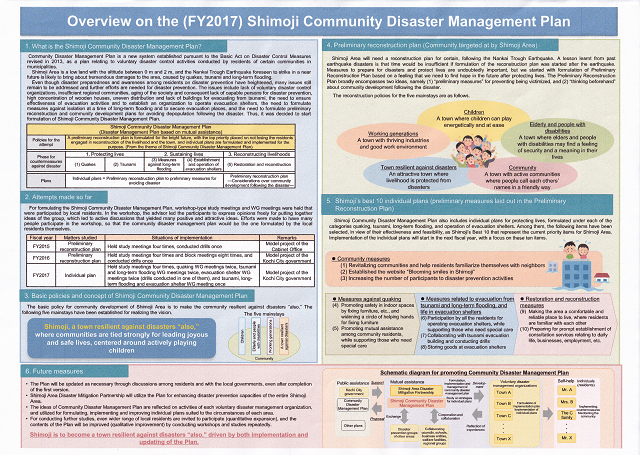
昨日は、JICA課題別研修「島嶼国総合防災コース」の研修生を下知地区で受け入れての研修10時から16時半までの間、下知コミュニティセンターで開催しました。
コロナ禍の時にはオンラインでしたが、4年ぶりの対面開催で、ミクロネシア、トンガ、バヌアツ、サモア、モーリシャスから8名の研修生と2名の高知大生が参加されました。
この研修は、カリブ、大洋州等の島嶼国ではサイクロン起因の高波、土砂災害、洪水、また、地震・津波、火山噴火など日本と同様に多用な災害に悩まされている中で、予・警報とその伝達、コミュニティ防災、防災教育、啓蒙活動など自助・共助の役割、人的ロスを回避するための避難路の整備などの重要性が明らかになっていることから、各国の災害リスクを軽減するには、高知県を中心とした日本の防災の知見を学び、応用することが効果的であるということで取り組まれているものです。
そのような中で、研修構成の一つの「自治体における防災対策及び地域住民の自主防災活動と、自治体による自主防災活動との連携・支援について理解する。」というものの一つとして、下知地区での受け入れが盛り込まれているものと思われます。
それにしても、初めてJICA研修を受け入れたのは2015年でしたから、随分長くなりました。
午前中は、高知市の地域防災推進課職員による「高知市の防災行政」についてのお話で、午後には、下知地区減災連絡会の取り組みとして「地区防災計画とコミュニティ防災」と題して、私の方から報告させて頂き、その後、コミュニティセンターの防災機能についての施設見学をした後、周辺を防災街歩きをしました。
講義では、「下知地区防災計画への着手・検討について」「下知地区防災計画の特徴について①総合防災計画として②「事前復興」で描く街を、今からつくるため③事前復興計画(下知地区のめざす姿)と個別計画(事前復興計画の事前対策)➃量の拡大と質の向上を目指して⑤特徴的な事業計画」そして「地区防災計画の検討過程で明らかとなった「共助」の力と多様な人との繋がり」について、報告させて頂きました。
また、街歩きでは、三重防護の第三ラインの内部護岸を見学してから、多様な津波避難ビル、老朽木造住宅の密集状況など案内して回りました。
研修生からは、午前中の高知市に対するものも含めて下記のような質問が出されていました。
・高知市内各所に避難所はあるのか。
・避難所毎の活動をされていることに、感心する。
・防災倉庫の管理は誰がしているのか。
・住民の参加はどうなのか。その参加を促す工夫はどのようにされているか。
・地区防災計画を具体化することの難しさは。
・地域住民をその気にさせるのは難しいのではないか。
・私たちの国では、避難行動要支援者対策のような制度がなくても、若い人たちが何かあれば高齢者を助けに行くような文化がある
・私の国では、発災直後に初動で動くチームがある。
・個別避難計画については、同意確認書も含めて様式などを教えて欲しいなどのシステムに対する関心も示されていた。
・マンションなどを津波避難ビルに指定する際の合意形成などについて、難しさはないか。
・津波避難ビルの指定要件の中に、階段の広さなどはないのか。
・津波避難ビルを地域住民にどのように周知しているか。
などなどの質問が出され、島嶼国の中でも、関心のある課題や疑問点が共通していたりすることを今回も感じさせられました。
最後に、研修生の代表から、地区防災計画についての感想や避難ビルとして公共だけでなく民間のビルを活用していることは、母国に持ち帰りたいことなどの感想が述べられていましたが、研修を通じて日本での学びを自国の防災対策に対して、どのように適応可能か検討しようとする意欲を感じられ、少しでもお役に立てればと思ったことでした。

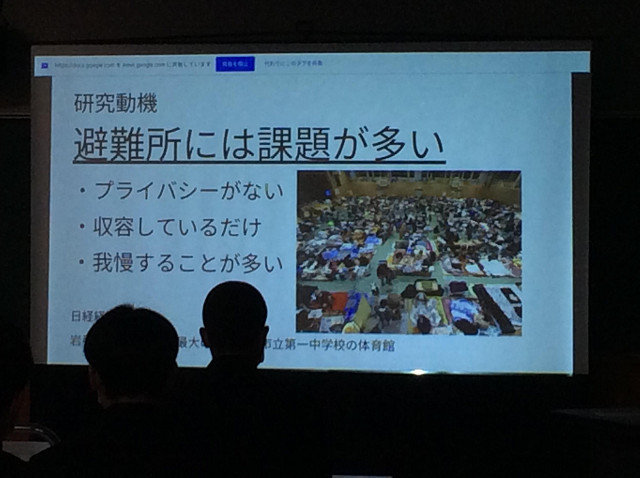

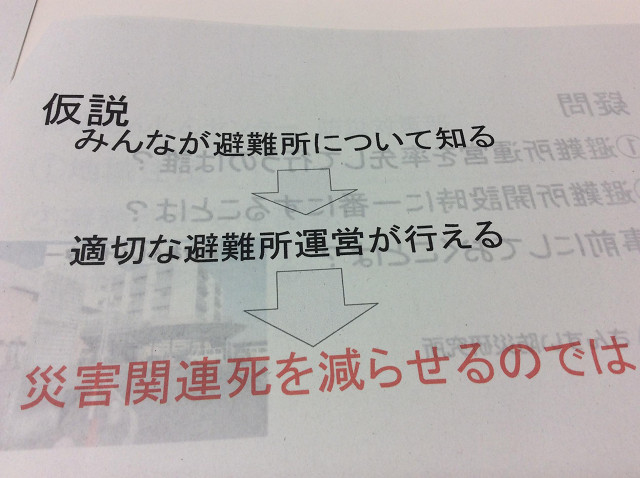
今日は、「県議会議員と高校生との意見交換会」の傍聴ため、県立小津高校に行ってきました。
私たちは、高知市内が選挙区のため、傍聴という形になります。
「県民の会」からは、吾川郡選挙区選出で小津高校OBの岡田竜平議員が意見交換されました。
テーマは「高知県の地域課題解決策についての提案」ということで、学内では約80のテーマで研究されているが、その中から「高知県における公共交通機関の衰退原因とその解決策」と「学校の避難所について」という2つのテーマに絞って、プレゼンがされました。
この意見交換会の目的は、「総合的な探求の時間で、個人またはグループで取り組んだテーマの成果を発表することによって、プレゼンテーション能力の育成や主体的・意欲的に学ぶ生徒を育成する。また、地域に貢献できる人材の育成に向けて、県議会議員と意見交換を行い、多様な見方・考え方に触れることで、現代社会の諸課題について、多面的多角的に考察し、構成に判断できる力や公共的な事柄に、自ら参画しようとする意欲・態度などを育む主権者教育の一層の推進を図るもの」であります。
それぞれに、貴重な研究成果が報告され、議員からも新たな多様な視点の提案もされ、生徒たちも、この研究を通じて、社会に任せきりにするのでなく、それぞれが参画していくことの大切さを学んだとの感想も述べられていました。
| 2月4日「マイナ保険証トラブル継続、利用率8か月連続低下」 |
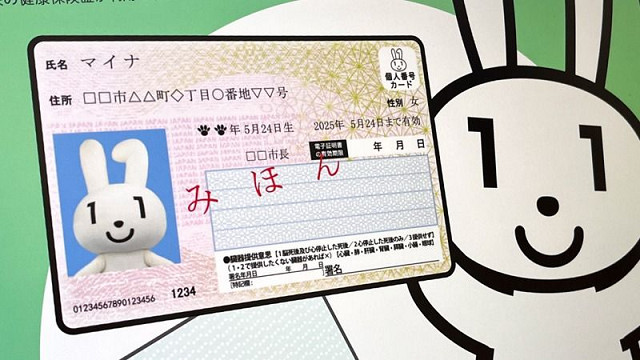 国は健康保険証を12月に廃止し、マイナ保険証に一本化すると決定したが、全国保険医団体連合会は、全国5万5357カ所の医療機関に昨年11月下旬~今年1月上旬、アンケートを実施し、回答を得た8672カ所のうち約6割の5188カ所が、昨年10月1日以降にオンライン資格確認に関するトラブルがあったと公表しました。
国は健康保険証を12月に廃止し、マイナ保険証に一本化すると決定したが、全国保険医団体連合会は、全国5万5357カ所の医療機関に昨年11月下旬~今年1月上旬、アンケートを実施し、回答を得た8672カ所のうち約6割の5188カ所が、昨年10月1日以降にオンライン資格確認に関するトラブルがあったと公表しました。
主なトラブルの内容(複数回答)は、「氏名や住所の文字化け」67%、「カードリーダーのエラー」40%、「被保険者番号がない」25%、「患者の医療費の負担割合が異なって表示される」15%などで、83%の医療機関で、トラブル時に現行の健康保険証で情報を確認し、患者に医療費の全額をいったん請求した事例が、少なくとも753件あったとしています。
また。マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」の利用率が昨年12月は4.29%で、8カ月連続で低下したことが、厚生労働省によって公表されています。
年代別の利用率では、最も高いのは「65~69歳」で、若い世代ほど利用していない実態も明らかになっています。
そのような中で、「マイナ保険証」の国家公務員の昨年11月分の利用率が4.36%だったことがわかっています。
最も低いのは防衛省で2.50%で、マイナ保険証を所管する厚労省は4.88%となっています。
今年12月の現行保険証の廃止に向け、厚生労働省は職員あてにメッセージを発信し、①マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる②よりよい医療が受けられる③手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除されるなどと利用促進を訴えているが、足元の国家公務員の利用もおぼつかない状況となっていることをどのように受け止めているのでしょう。

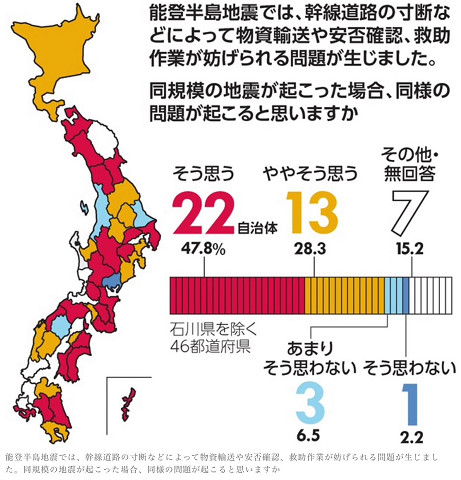

今朝の朝日新聞1~3面にかけて、(検証 能登半島地震)と題して、石川県を除く全国4都道府県知事に対して、「能登半島地震と同規模の地震が起こった場合、同様の問題が起こると思うか」問うたアンケートの結果に対する記事が特集されています。
中でも、7割超の知事が、幹線道路の寸断などで物資輸送や救助活動が妨げられた今回の地震と同様の事態が起こりえると回答したことや、近隣住民で助け合う「共助」の仕組みが困難になっているとの認識は約9割に上ったことが取り上げられています。
能登半島地震での被害のありようは石川県にとどまらず、46都道府県知事が「ひとごとではない」との思いを強くされているようです。
ハードの脆弱性、減り続ける人手、細る地域のつながりなど、全国に共通する「過疎問題」を前に、どのように備えればいいのかが問われていることがアンケート結果に表れています。
特に、今回の地震では、主に高齢化率50%前後の自治体で被害が拡大しており、高齢化や人口減少で地域コミュニティーの担い手が少なくなる中、住民らによる共助の仕組みが困難になっていることに対して「そう思う」と答えたのは18人で、「ややそう思う」は23人とほぼ9割の知事が共助の仕組みが「困難」になっているとの認識を示しています。
事前に、それらの備えを強化することで、過疎地だけでなく都市部も含めた支えあいのしくみができることで、平時にも生活しやすくなるし、被災時に地域の共助力が少しでも高められるのではないかと思います。
これらの課題に、本県ではどのように取り組もうとしているのか、デジタル版には詳細掲載されているので、紹介しておきたいと思います。
そこには、疑問を感じる回答もあるが、明日はわが身との思いで、公助・共助・自助を高めていく本気度を県民挙げて取り組んでいくことが、被災地から学ぶことにもなると思います。
【高知県】能登半島地震・知事アンケート回答全文
能登半島地震と同規模の地震が起きたら
【質問1】1月1日に発生した能登半島地震では、被災者の生存率が落ち込むとされる発災後72時間までに、能登半島の幹線道路の寸断などによって物資輸送や安否確認、救助作業が妨げられる問題が生じました。今回と同規模の地震が貴都道府県内で起こった場合、貴都道府県で同様の問題が起こると思いますか
【回答】そう思う
【質問2】そう回答した理由を教えてください(自由記述)
【回答】急峻な地形や海岸沿いの幹線道路が多いことに加え、未改良区間が多く残っていること、また、高速道路も未整備区間が残っているため。
共助の仕組みが困難になっているか
【質問3】今回の地震では主に高齢化率50%前後の自治体で被害が拡大しました。高齢化や人口減少で自治会や町内会などコミュニティーの担い手が少なくなるなか、災害時の住民による共助の仕組みが困難になっていると思いますか
【回答】そう思う
【質問4】そう回答した理由を教えてください。「そう思う」「ややそう思う」と答えられた場合は、今後どのような対応が必要と考えているかも教えてください(自由記述)
【回答】被害が拡大したことと、高齢化や人口減少などの因果関係は明確になっていないものの、被害を減らすには、地域での共助が重要だと考えています。そのため、本県では、共助の取組の一環として、要配慮者の方々が確実に避難できるよう、市町村と連携して個別避難計画の作成を推進しています。
また、共助の要となる自主防災組織について、高齢化やリーダーの担い手不足により、活動が停滞している中山間地域があります。
このため、現在、本県独自に策定を進めている「中山間再興ビジョン」により、中山間地域に若い力を入れていくことが、地域の支え合いの力を強化することになり、結果的に防災面でも大きな役割を果たすと考えています。
耐震化率の現状と目標は
【質問5】今回の地震では、1981年以降に適用された国の新耐震基準を満たさない古い木造建築が多かったことも被害が拡大した要因との指摘もあります。貴都道府県における新耐震基準での住宅の耐震化率について、①いつまでに何%にすることを目標としているか、②最新の耐震化率はいつ時点で何%か、を教えてください。その上で③都市部と過疎地で耐震化率が大きく異なるなど、自治体間で差がある場合はその理由とあわせて教えてください(自由記述)
【回答】
①令和12年度末までにおおむね完了を目標としています。
②令和4年度末(2023年3月末)88%
③各市町村の耐震化率の推計はしていないが、平成30年の住宅土地統計調査によると、都市部と比べ中山間地域の方が昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の古い住宅が多い傾向があります。このことを踏まえると、中山間地域における耐震化率は低いと思われます。理由としては中山間地域の住宅所有者に高齢者が多いことが理由と考えられます。
避難所運営の備えは
【質問6】今回の地震が貴都道府県内で起こった場合、被災地における円滑な避難所の運営に向けて、食料などの備蓄や簡易トイレ、水道、感染症やプライバシー対策などの備えは十分できていると思いますか
【回答】あまりそう思わない
【質問7】そう回答した理由を教えてください(自由記述)
【回答】
〈目標〉※令和9年度までに完了
食料などについては、国からのプッシュ型支援が4日目以降になることを踏まえ、県と市町村では、令和9年度までを目標に3日分の備蓄に取り組んでいます。
【1日目分】
・市町村が備蓄(避難所避難者数約26万人×1.2倍×1日)
・県は不測の事態に備えて備蓄(避難所避難者数×1日×20%)
【2~3日目分】
・流通備蓄(小売業者・卸売業者との協定締結による)により確保
〈現状〉
【1日目分】
・市町村備蓄
飲料水:64%(603,346/939,930リットル)
食料:149%(1,396,067/934,455食)
簡易・携帯トイレ:177%(2,714,657/1,529,580個)
※その他、ミルク、毛布、生理用品、おむつ、トイレットペーパーを備蓄
・県備蓄
飲料水:100%
食料:100%
【2~3日目分】
・計画上は流通備蓄で対応する方針だが、必要量を担保できていないことが課題
○その他、感染症やプライバシー対策については、新型コロナ感染症対策として、避難所運営マニュアルに反映させるとともに、簡易ベッドやパーティションなど、必要な資機材の整備が完了しています。
過疎地域での地震に備え課題は
【質問8】同規模の地震が貴都道府県内の過疎地域で起こった場合に備え、特に優先度の高い課題はどれになりますか(回答三つまで)
【回答】①水・食料・トイレなど物資の確保②道路や港など交通経路の確保③電気・ガソリンなどエネルギー供給
【質問9】上記の三つの選択肢を選んだ理由を教えてください(自由記述)
【回答】物資や交通経路の確保については、過疎地域は急峻な地形が多いことに加え、道路の未改良区間が多く残っており、道路が寸断すると、救助・救出活動や物資輸送等が速やかに実施できないため。
また、エネルギー供給については、救出・救助活動(車両)や道路啓開(重機)、通信(非常用電源)、医療救護(非常用電源)、寒さ対策(ストーブ)等に燃料が必要なため。
「想定外」の災害と地域防災対策
【質問10】今回の地震では、交通や通信が断絶した上、年末年始で県外から多くの帰省客や観光客が訪れていたこともあり、石川県地域防災計画の想定以上の被害につながったとみられています。最大震度や具体的な被害想定が十分でなかったとの指摘もあります。こうした「想定外」の災害に対し、都道府県や市町村の地域防災計画などを中心とした防災対策の限界を感じますか
【回答】あまりそう感じない
【質問11】そう回答した理由を教えてください。「そう感じる」「ややそう感じる」と答えられた場合は、今後どのような対応が必要と考えているかも教えてください(自由記述)
【回答】本県では、国の被害想定を基に、高知県版の南海トラフ地震による被害想定を策定しています。この被害想定を前提として、人的被害を限りなくゼロに近づける取組の推進や、被害を最小化し早期復興を図るため、地域防災計画の下に「南海トラフ地震対策行動計画」を策定しています。
これまで東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、計画の見直しを行ってきましたが、まだ対策は十分には完了していない状況です。今回の能登半島地震においても、今後、明らかになる課題を踏まえ、取組を見直し、対策の強化及び加速化が必要だと考えます。
【質問12】記の質問に関連し、貴都道府県における現在の地震被害想定はいつ策定されましたか。教えてください(自由記述)
【回答】平成25年5月
政府の防災計画や公的支援に課題は
【質問13】今後の防災・減災に向けて、政府の防災計画や財政も含めた公的支援について課題があると思いますか
【回答】そう思う
【質問14】そう回答した理由と、具体的な課題について教えてください(自由記述)
【回答】今回の能登半島地震を踏まえ、孤立対策として、中山間地域における道路などのインフラ整備について加速化が必要となります。
そのため、国における国土強靱化に必要な予算の拡充や予算・財源を通常予算とは別枠で確保するなどの財政支援が必要です。
なお、見直しが進められている「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に基づき、国の被害想定等の見直しが本年度中に行われるが、それに合わせて都道府県が実施する被害想定の見直しに対しても国の財政支援が必要です。 |

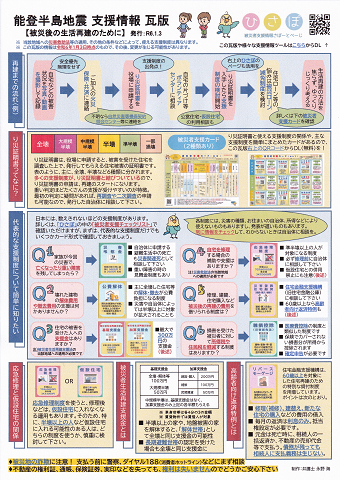 元旦の地震発生以来、辛い日々を過ごされている被災者の皆様にお見舞い申し上げます。
元旦の地震発生以来、辛い日々を過ごされている被災者の皆様にお見舞い申し上げます。
一日も、早い日常を取り戻されることを願うものの、取り戻せないほどに失ったものの大きさを思うと言葉もありません。
あれから一か月が経ち、マグニチュード7.6の能登半島地震は、死者240人(うち災害関連死15人)、住家被害47915棟に及ぶ被害(2月1日時点)を招くこととなりました。
能登半島地震で住民を襲った被害の様相は、震度7の揺れ、極めて短時間で沿岸部を襲った津波、輪島の朝市街が焼け野原となった地震火災、救援・支援を遅らせた道路の寸断や液状化とまさに、想定される地震被害の甚大さ、複合化が被災支援、復旧を遅らせています。
しかし、南海トラフ地震では、さらなる被害として、「津波火災」や「長期浸水」も加わる激甚化・複合化が想定されます。
一か月が経ち、まだまだライフラインの全面復旧に至らず、522か所で合わせて1万4431人となっています。
そのうち、17か所の「広域避難所」などに避難している人は合わせて967人、被災者を一時的に受け入れる「1.5次避難所」に避難している人は3か所で合わせて288人、このほか旅館やホテルなどの「2次避難所」に避難している人は217か所で合わせて4944人となっています。
そのような中で、被災地では、令和6年1月25日に政府の「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」が公表されるなどして、被災者が生活再建に向けて歩んでいく段階に来ているが、被災地の現場に目を向け、一人ひとりの被災者の声に耳を傾けると、今なお生命の危機に瀕している方、取り残されつつある方がいるのも事実です。
震災から一か月、被災地域によって支援格差も生じつつあり、避難先で新たな困りごとに直面している方々もいる中、いつもご指導いただいている津久井進弁護士らが共同代表を務められている「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」では、「制度運用は『迷ったら被災者の利益に』を第一に」、「地域の復興の手順を示したロードマップ(計画書)を事業を行う側の立場でなく、そこで暮らす被災者の生活目線に立って理解できる内容・形式で示すこと」が求められていると提言しています。
これからの復旧・復興過程が、いかに被災者目線で進められるかが問われる正念場だと思います。
そして、私たち高知県では、被災地支援を通じて、自治体職員と地域住民が連携して想像力たくましく、備えることを改めて能登半島地震から学ばなければなりません。
| 1月31日「岸田、麻生に心に滲みこむ言葉は無理か」 |
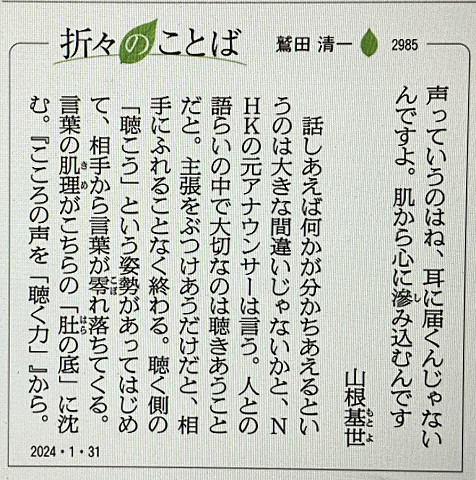

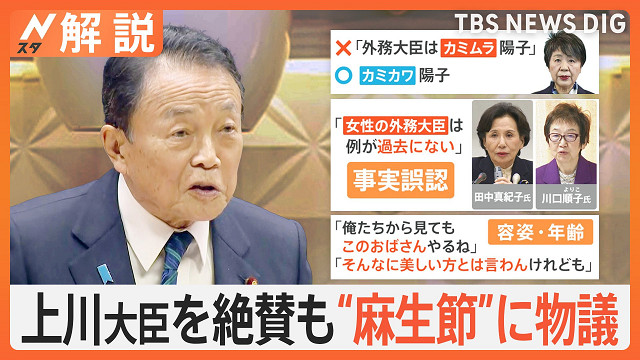
今朝の朝日新聞を読んで、「言葉」ということについて、考えさせられる3つの記事がありました。
1面「折々のことば」の「声っていうのはね、耳に届くんじゃないんですよ。肌から心に滲(し)み込むんです(山根基世)」の言葉。
同じ1面の「天声人語」では岸田首相の施政方針演説の言葉を取り上げています。
そして、12面の社説では「麻生氏の発言 女性進出阻む旧態依然」と題して、毎日のニュースをにぎわしている発言のお粗末さを批判しています。
岸田首相の発言には「丁寧に、真摯に、適切に。岸田文雄首相は、発言に修飾語が多い。きのうの施政方針演説では「しっかり」が気になった。いわく、被災者の生活をしっかり支え、重要政策をしっかり進め、外交のかじ取りをしっかり果たし、賃上げをしっかりおこない、中小企業をしっかり後押しする▼首相としては、決意のほどを伝えたつもりであろう。だが聞く側にとって不安なのは、これらもまた、かけ声倒れに終わるのでは、という点である。」と指摘しています。
そして、最後には「さて通常国会の最大の焦点は、やはり「政治とカネ」であろう。政治家の責任を広く問う連座制を導入する覚悟はあるのか。政策活動費の使い道を公開するつもりはあるのか。おとといの国会で首相は、身内の自民議員から連座制について問われ、こう答えた。「しっかり議論を行っていきたい」▼がくりとひざが折れそうになる。首相に求められているのは本気だ、事実だ、具体策だ。むなしい修飾語ではない。」と結んでいます。
また、言わずと知れた麻生発言は、「外務大臣としての能力と外見とは何の関係もない。言及すること自体が女性への差別と受け取れる、極めて不適切な発言だ。」と断じられ、過去のナチスを引き合いに「あの手口に学んだらどうか」発言など、国際社会ではおよそ容認されない発言もありながら、今回も党内で問題視する動きは見えないことを憂えています。
そして、「背景には、麻生氏が多数の国会議員を従える麻生派トップとして、政権運営に強い影響力を持ってきた派閥政治の構造がある。ゆゆしき発言をしても放任されるとしたら、自民党の自浄能力はおよそ期待できないことになる。党の体質そのものが問われている。」と結ばれています。
自民党の総裁と副総裁の二人の発言に対して、今朝の「折々のことば」で語られている言葉は、同列には語られないかもしれませんが、少しは肝に銘じてほしいと思いながら、自らへの戒めともしたいと思います。
| 1月30日「能登半島地震の今とこれからの課題を南海トラフ地震の備えに活かして」 |
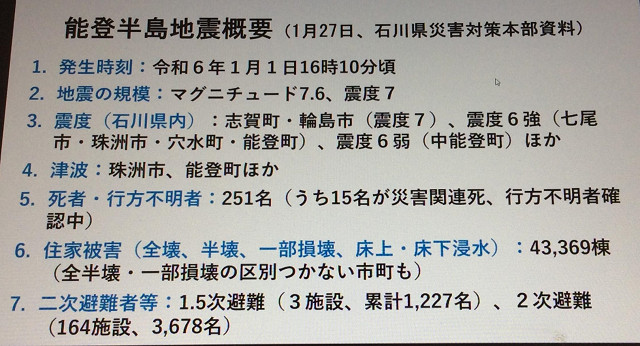
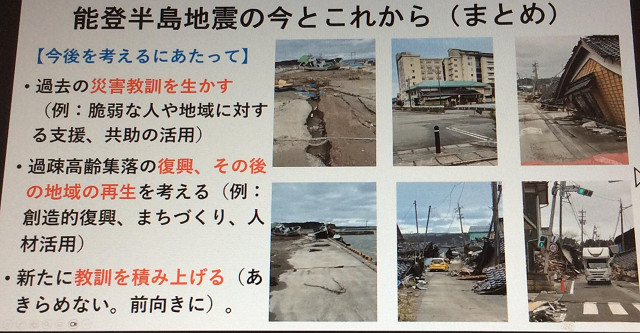 昨夜の毎週月曜20時からの第153回全国防災関係人口ミートアップは「令和6年能登半島地震vol.2〜被災地の今とこれからを考える〜」として、兵庫県立大学の青田良介先生に話題提供いただき、過疎高齢社会の災害対応と生活・生業再建、地域再生など、今とこれからの課題を踏まえて、今後を考える視点を提起頂きました。
昨夜の毎週月曜20時からの第153回全国防災関係人口ミートアップは「令和6年能登半島地震vol.2〜被災地の今とこれからを考える〜」として、兵庫県立大学の青田良介先生に話題提供いただき、過疎高齢社会の災害対応と生活・生業再建、地域再生など、今とこれからの課題を踏まえて、今後を考える視点を提起頂きました。
能登半島地震から一か月この間ずっと、改めて能登半島地震から南海トラフ地震への備えをどのように強化するかということでしたが、昨夜提供いただいた課題は、その視点を整理する意味で参考になりました。
しかし、南海トラフ地震の想定被害は、能登半島地震で起きた被害に加え、長期浸水や津波火災もあり、さらなる「備え」とその被害からの「復旧・復興」への立ち上がり早くするためには、何としても事前に仮設住宅の確保や広域避難場所など、これまで指摘してきた課題の具体化を図っておかなければならないということを痛感させられました。
「能登半島地震の今とこれから」について、次のような課題を踏まえて過去の災害教訓を生かして備えておきたいものです。
1 インフラ(道路・上下水道)による地域の寸断、アクセスの悪さ
→「陸」がダメなら、「空」「海」で補完できないか(人・車・水・物資を運ぶ)
2 災害対応に遅れが見られないか?
→ソフト支援に長けたNPOや専門家等を活用
→平常の行政サービスを他自治体(県内市町村)に任せられないか。
3 大雪が復旧を妨げる
→中越地震や東日本大震災(雪国の被災地)ではどう対処したか>
4 災害関連死が増えそうである
→基本、被災市町村内での避難、再建を目指す。
→二次避難、広域避難、県外仮設・公営住宅等もやむを得ない(移動したで、完了ではない)
→避難するしないに関係なく、寄り添い支援する(→災害ケースマネジメント)
→ソフト支援に長けた専門家、NPO等を活用。
5 これからどうなるのかトンネルの先が見えない
→何もわからないのが問題(= 0点)、満点でなくても数十点がわかる状態に(=希望を見いだす)
→過去の災害事例を参考に、大まかで良いので、道筋を示す(例:3年後、5年後、10年後)。できないことや軌道修正も含め想いを共有する。
6 住まいはどうなるか?
→空き家や住宅の庭に仮設住宅を作る
→関係人口増加にもつながる公営住宅を検討する。
7 生業はどうなるのか
→地域のアイデンティ、再生につながると認識
→公的支援に加え、激励も兼ねた市民・民間支援が不可欠(クラウドファンディング、同業者支援、経営支援、購買活動)
→小規模の新規ビジネスを育てる(成長の目を摘まない)
→介護施設、教育ビジネスも。
| 1月29日「能登半島地震での死亡原因の9割が家屋倒壊」 |
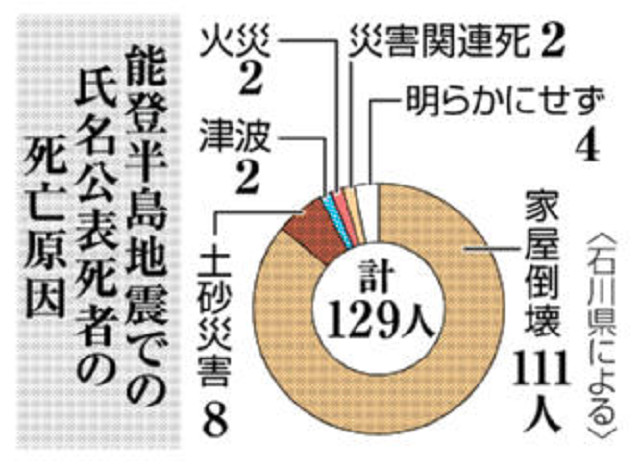 能登半島地震で石川県が27日までに氏名を公表した死者129人のうち、9割近くの111人が家屋倒壊で死亡したことが報じられています。
能登半島地震で石川県が27日までに氏名を公表した死者129人のうち、9割近くの111人が家屋倒壊で死亡したことが報じられています。
被害の大きい地域は、高齢化率が高くて古い木造家屋が多く、経済的な事情も含めて耐震工事が進まなかった背景があるようで、そのことは1月5日のこの欄でもご報告した通りですが、石川県内の住宅被害は一部破損から全壊まで4万3千棟超に上っています。
地震では計236人の死亡が確認されているが、遺族の了解を得た死者の氏名や原因などが公表された129人の中では、家屋倒壊に次いで8人が土砂災害、火災と津波がそれぞれ2人ずつ、別の2人は災害関連死、4人は原因不明とのことです。
年齢別では、60代以上が101人と全体の8割近くで、自宅の所在地は珠洲市や輪島市が大部分を占めています。
2022年時点の65歳以上の高齢化率は輪島市が47.9%、珠洲市が52.8%で、金沢市の27.5%の2倍近く、珠洲市の住宅耐震化率は2018年度末時点で51%に留まっており、輪島市でも耐震化率は、2019年末時点で45.2%に留まっています。
高知県でも、2021年で79.4%で、高知市では2020年で75.1%となっていますが、高齢化の高い地域だとどうなのか、そこまで絞って耐震補強工事を加速化するなどの取り組みが大切になっているように思えます。
特に、津波浸水エリアでは、倒壊した家屋から救助できないままに、津波から避難せざるをえない事態に陥ることも想定されますので、特にこのエリアでの耐震化を加速することが急がれるのではないでしょうか。
改めて、「耐震改修」と「高齢者世帯の防災」を丁寧に取り組むことが、「津波からの避難」にも繋がることを踏まえた取り組みが必要になっています。
| 1月28日「小中高生の自殺者数、過去最高に次ぐ507人」」 |
 2023年の自殺者数は2万1818人(暫定値)で、前年の確定値より63人(0・3%)減したが、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことが明らかになりました。
2023年の自殺者数は2万1818人(暫定値)で、前年の確定値より63人(0・3%)減したが、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことが明らかになりました。
自殺者数は03年の3万4427人をピークに減少し、19年に2万169人になりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行が始まった20年以降は、2万1000人台で高止まりが続いています。
23年の男女別は、男性が1万4854人(前年比108人増)で、13年ぶりに増加に転じた22年から2年連続の増加で、女性は6964人(前年比171人減)と減少しているものの、20歳未満と20代などで増加しています。
小中高生の自殺は507人で、過去最多だった22年の514人に次ぐ水準で高止まりし、深刻な状況が続ています。
内訳は小学生13人、中学生152人、高校生342人で、「学業不振」が最多で「進路に関する悩み」が続くなど、学業や進路の悩みが要因に多い傾向にあります。
すべての子どもが幸せに暮らすことができる社会の実現に向け、実効性のある政策をどう進めていくかが問われている中で、こども基本法に基づき、今後5年間の政策の基本指針となる「こども大綱」が初めて策定されました。
子どもが成長していくにしたがって、学童期・思春期の心のケアの充実や居場所作りなども盛り込まれたというが、生まれながらに人権を持った子どもの多様な人格やその個性が尊重されるよう社会全体で健やかな成長を後押しする必要があります。
にもかかわらず、自らの命を断つ子どもたちが年間500人以上もいることと向き合う社会でなければならないことが問われています。
そして、命の危機に晒される子どもたちへの貧困対策や医療的ケア児や障害児などへの支援が受けられる支える仕組みが、求められているのではないでしょうか。
| 1月26日「起きて欲しくないという思いの『想定外』と向き合う」 |
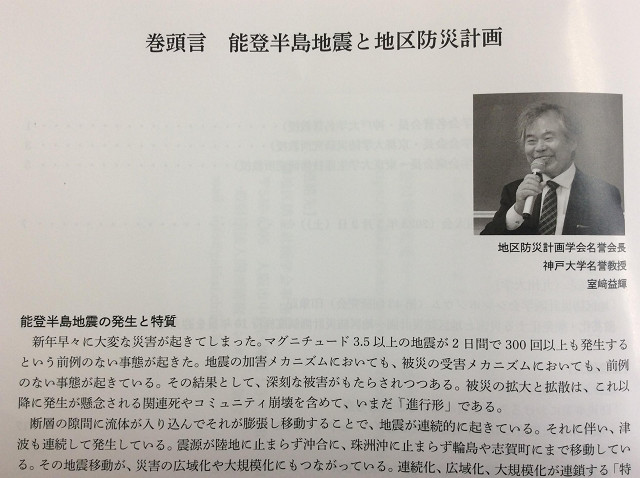 昨日25日時点で、能登半島地震による死者数は236人にのぼり、うち災害関連死が15人となったことが公表されました。
昨日25日時点で、能登半島地震による死者数は236人にのぼり、うち災害関連死が15人となったことが公表されました。
また、住宅や道路、港湾施設など固定資産の損壊による被害額が、石川、富山、新潟の3県で計1・1兆~2・6兆円にのぼるとの推計も発表されています。
ただし、今回の試算は、東日本大震災や熊本地震など過去の事例を参考に、市町村ごとの震度に基づいて機械的に算出したものだそうです。
しかし、このような発災後の数字を見るにつけ、事前の備えで、これらの被害を縮減させることができたのではと思わざるをえません。
昨日、手元に届いた「地区防災計画学会誌」第28号の巻頭言にある室﨑益輝(地区防災計画学会名誉会長)先生の「能登半島地震と地区防災計画」には、「不測の事態に備えるコミュニティ」の見出しで、次のような指摘があります。
「前例のない不測の事態が起きるということを、今回の地震とその被災は改めて教えてくれた。元旦に震災が起きることや、観光地で震災が起きることを前提とした災害対応計画が必要だと、私は主張してきていたが、それが現実のものとなった。「不測ゆえに、無防備になる過ち」を、何倍にも拡大した形で繰り返してしまった。といって、予測できなかったことではない。想像力をたくましくすれば、お正月に大地震が起きることも、過疎地で震度7が起きることも、諸事情で外部支援が全く受けられないことも、火災で密集地が丸焼けになることも、予想できた。起きて欲しくないという思いが、最悪の事態を想定させなかったのだ。そのことが、事前の防備を疎かにさせ、深刻な被害を招いたと言ってよい。ということで、事前防備や事前復興の必要性、さらにはコミュニティ減災や地区防災計画の必要性を、今回の地震で再確認しなければならない。」
そして、今回の能登半島地震の被害の中から想定されて、今後、地区防災計画で取り上げられる課題として、「孤立化に備える地区防災計画」「市街地大火を防ぐ地区防災計画」の見出しで、喚起されています。
「起きて欲しくないという思いが、最悪の事態を想定させず、そのことが、事前の防備を疎かにさせ、深刻な被害を招く」ことにはならないように、想像力をたくましくして、備えなければならないと思ったところです。
| 1月25日「2024年度県予算規模と主要施策の見通し」 |

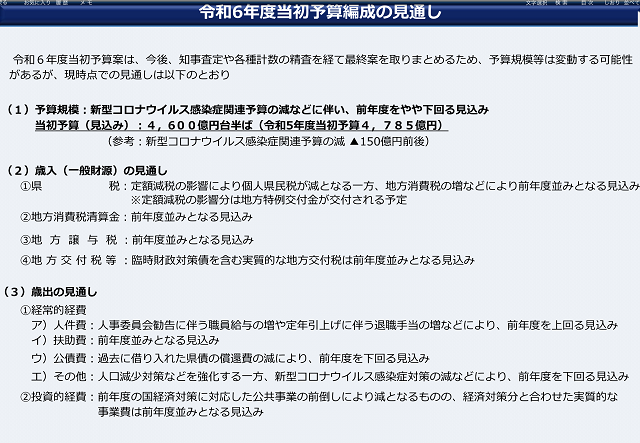
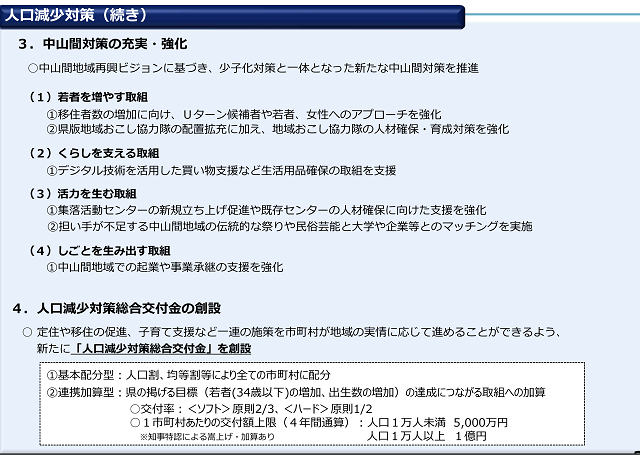
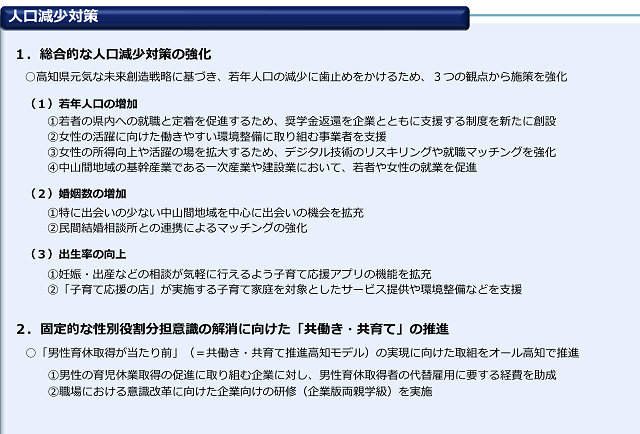
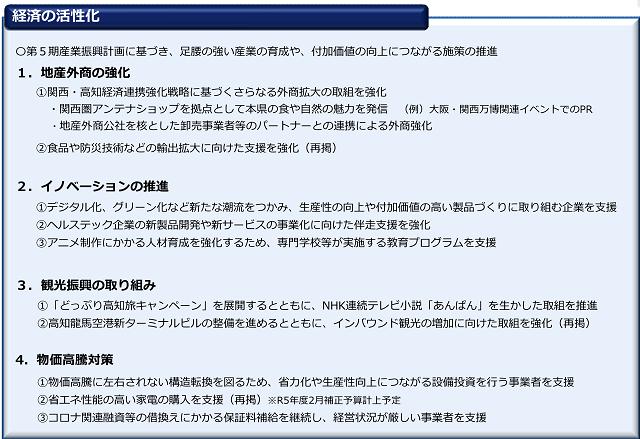
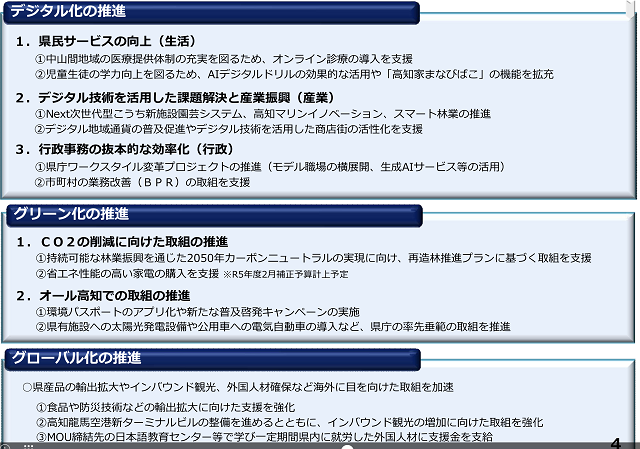
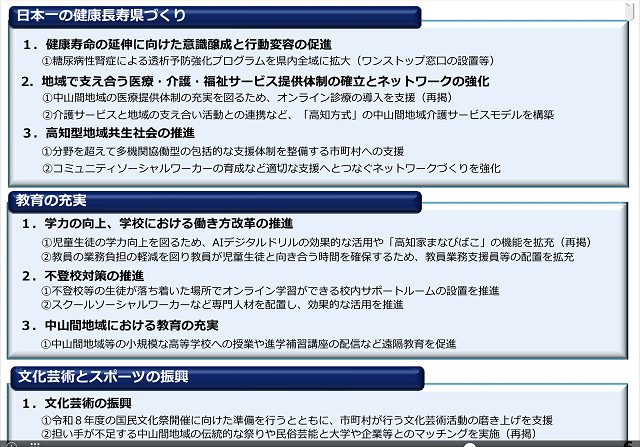
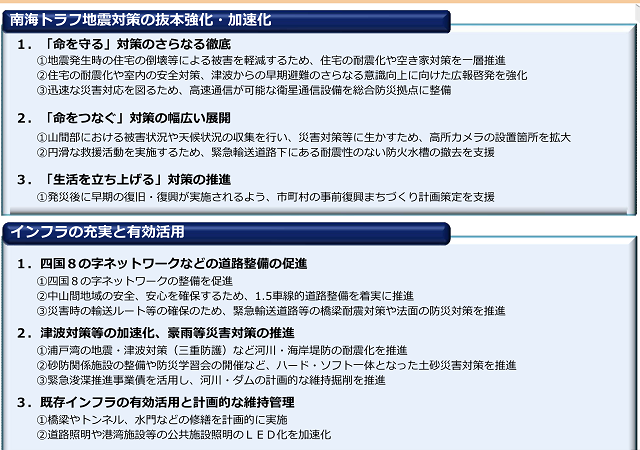
昨日、県議会各会派に対して、県から2024年度一般会計当初予算案の規模が4600億円台半ばとなる見通しが示されました。
昨年度からは、新型コロナウイルス対策関連予算が約150億円減少することなどから、23年度当初(4784億5700万円)を下回る見込みです。
予算案は今日から知事査定に入り、2月中旬に発表されます。
市町村への財政支援として新設される人口減少対策総合交付金をはじめとした人口減少対策や中山間地域再興ビジョン、さらには1月1日の能登半島地震を受けて、強化加速化すべき南海トラフ地震対策など本気度の伺える予算編成となることを注視していきたいと思います。
昨日は、会派説明の後「県民の会」会派で、知事との意見交換も行い次の項目について要望させて頂きました。
1 「高知県人権施策基本方針」の見直しについて
2 南海トラフ地震対策などについて
(1)災害時における「誰一人取り残さない」取り組みの拡充と加速化について
(2)南海トラフ地震対策における長期浸水エリアの諸対策と支援について
3 ビジネスケアラーについて
4 持続可能な林業の推進について
5 漁師の学校(仮称)職業訓練学校の創設について
6 地域での災害復旧を見据えた、地域建設等事業者の維持について
7 教員のメンタルヘルスについて
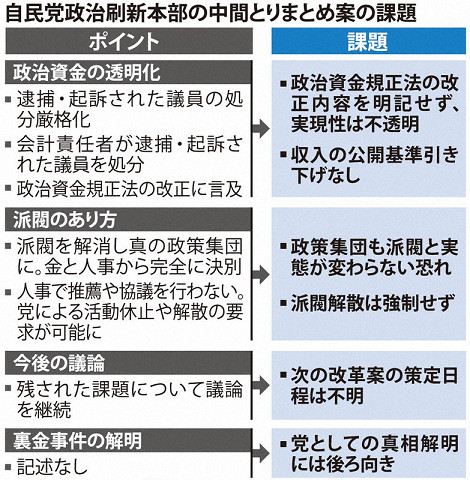
 自民党政治刷新本部は、派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件を受けて、党改革の中間とりまとめ案を昨日事実上了承しました。
自民党政治刷新本部は、派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件を受けて、党改革の中間とりまとめ案を昨日事実上了承しました。
中間とりまとめ案には、派閥の政治資金パーティーの全面禁止や、会計責任者が逮捕・起訴された場合に党として所属議員を処分することなどの改革案は盛り込まれたものの、政治資金規正法などの改正については「各党との真摯な協議を経て、責任体制の確立・厳格化などについて必要な法整備を速やかに行う」との記述にとどまっています。
規正法の改正に関しては、会計責任者が刑罰を受けた場合には議員にも責任が及ぶよう罰則を強化する「連座制」の導入は、とりまとめ案には明記せず、パーティー券の購入者などに関する公開基準の引き下げも現行の「20万円超」から、寄付と同じ「5万円超」に引き下げることについての記述もなく、透明化を推進しようとする姿勢に欠けたものとなっています。
また、派閥は、閣僚人事などで派閥推薦などの働きかけや協議を禁止するとした一方で、派閥の解散は明記せず、法令違反が確認された場合、党が活動休止や解散を求める内容にとどめています。
このままでは、一旦派閥を解散しても、実態は政策集団への衣替えにとどまる可能性があることも懸念されています。
中間とりまとめ案は、今日の総務会で正式了承される見通しだが、まさに明日26日召集の通常国会に間に合わせるための「駆け込み」となった側面は否めません。
名ばかりの改革でお茶を濁すのではなく、裏金問題の全容解明に向けた調査や徹底した原因究明と本気で向き合わない限り、政治の信頼を取り戻すことは無理ではないでしょうか。
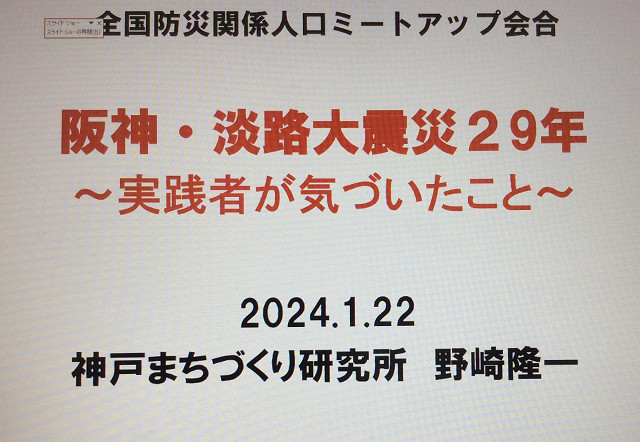
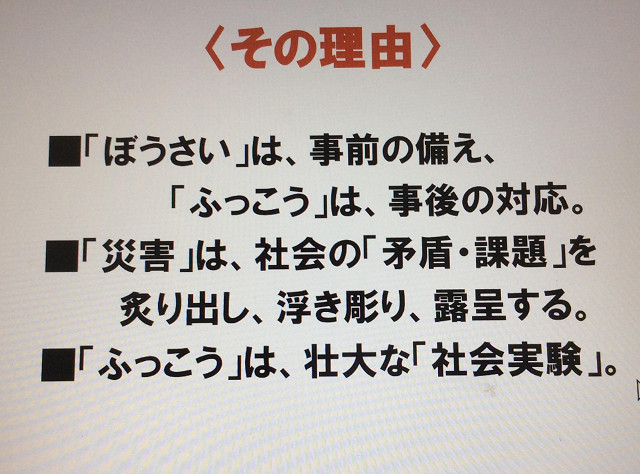
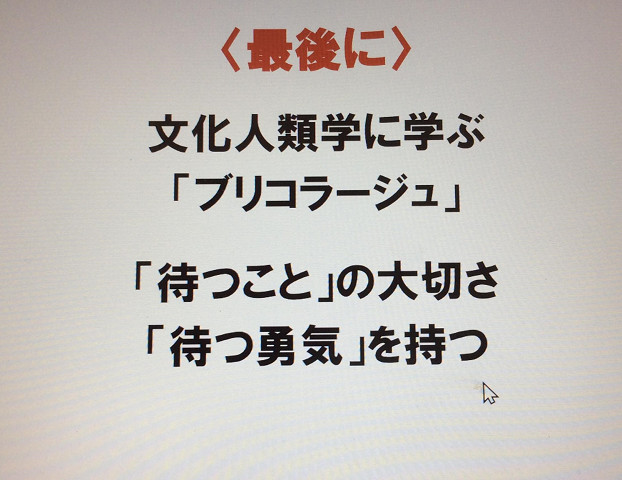
昨夜は、毎週月曜日20時からオンラインで開催されている「全国防災関係人口ミートアップ」で、「阪神淡路大震災29年~実践者が気づいたこと」について、神戸まちづくり研究所の野崎隆一先生からお話をいただきました。
野崎先生は2018年に、下知地区減災連絡会で講演をいただき、その際には「復興まちづくりと日常の地域コミュニティの大切さ~阪神淡路と東日本の経験から~」と題してお話しいただき、その2年後には、私のマンション防災会で「マンション再建における合意形成」について、お話をいただきました。
そして、今回の話を通じて、野崎先生が強調されていた「出発点は『ぼうさい』ではなく『ふっこう』である」という事を改めて考えさせられました。
「災害によって、社会の矛盾や課題をあぶり出し、浮き彫りにして、露呈される現場には、そのすべての課題がある」から、そこに学ぶことが一番大事であり、その課題に備えていくことを通じて、「ぼうさい」に「も」つながるのではないかと思ったところです。
また、「合意形成」の課題も話題になりましたが、マンション防災会でご講演頂いた時に、合意形成の困難さがある中で、復興からの教訓を生かし、合意形成のためには、「正しさは多様」「マナー・ルール・コストが必要」「二者択一にしない全員が目指せるゴール」が必要であるとのお話などを思い出しました。
その場にあるもので作る、対応する方法である「ブリコラージュ」ということの必要性もこれからは大切であり、また、「待つこと」の大切さ、「待つ勇気」を持つことの大切さ、さらには、アリストテレスの対話術で、必要とされる「ロゴス(理屈)」「パトス(情熱)」「エトス(人格)」を兼備した人材育成の有意性などについても考えさせられました。
これから守った命を繋ぎながら、能登で復興に向けて歩んでいく被災者の皆さんにとっても、阪神淡路大震災復興からの29年の市民主体の「ふっこう」の実践の中での「現場」の教訓が生かされることになればと思いながら、聴かせて頂きました。
| 1月22日「中小事業者も、災害前に備えることを学んで取り組んで」 |


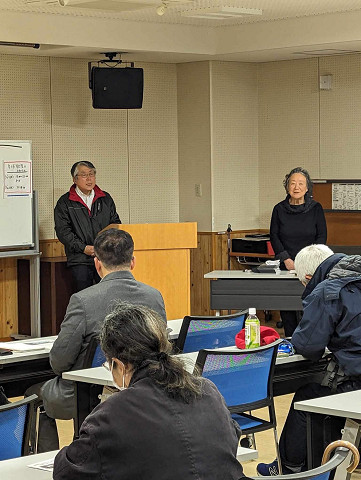
1月20日には、高知市総合防災訓練で、仁淀川町への広域避難訓練を下知地区住民の参加で行いました。
こちらの報告課題などは、後日行わせて頂きます。
今日は、その訓練終了後に下知地区減災連絡会で開催した「東日本大震災に学ぶ~中小企業の防災と復興~」の防災講演会について、報告させて頂きます。
「東日本大震災に学ぶ~中小企業の防災と復興~」のDVDを上映した後、DVDを製作されたソラワン・映像プロデューサーの田中敦子さんのお話で補強いただくとともに、意見交換がなされました。
2019年にもDVD「被災地の水産加工業 あの日から5年」を上映し、お話し頂いたことがきっかけとなり、下知地区の個人事業者などが集まり、グループ補助金などについて学んだり、事前の取り組みとして下知地区減災連絡会に事業所部会を発足させ、中小企業の防災・事前復興の取り組みを強化しようとしてきました。
今回の『被災した経営者から学ぶ① 』映像の主旨は、「東日本大震災で被災した水産加工業の10年間の復興記録映像の中から、他業種の中小企業と共通する「防災」箇所を取り上げ、事例となる画像から、復興過程で何が起きたのかを知ることで災害時の対応を学ぶことが出来る。」もので、ポイントをまとめたハウツーものとなっています。
また、もう一枚のDVD『被災した経営者から学ぶ② 』には、「被災した株式会社「かわむら」の経営者川村賢壽氏へのインタビューから、被災した経営者はどのような心構えで復興に立ち向かったのか、時代の流れを読み現状を打破しようとする姿勢は、他業種の中小企業経営者に共通」するものとして学んで頂こうというものでした。
特に、株式会社「かわむら」の経営者川村賢壽氏の「死に方は選べないが、生き方は選べる」という言葉が参加者には刺さったようでしたが、私は、「生き方の中で、平時の経営と被災時に復興していく備えの決意」を選ぶことこそが、死に方にもつながるのではないかと思ったりもしました。
ここでは、田中さん自身がまとめて頂いたDVD『被災した経営者から学ぶ① 』の内容のポイントを紹介させて頂きますが、最後には「皆様の会社が災害に遭遇した時に役立つと思える事をご紹介しました。実際に取り組める防災事例を知り、今から準備を始めて下さい。」と訴えられています。
これらの事例が水産加工業だけでなく、他業種の中小事業所の備えにも共通していることや今回の能登半島地震で壊滅的被害を受けた水産業の被害の視点としても参考にすることを学んで頂けたらと思います。
▼全員で避難訓練を実行しておく。
▼被災後多くの経営者がとった方法
▼データの管理
▼補助金申請が受理されないと金融機関は融資をしない。
▼グループや組合を作る。
気仙沼鹿折加工組合の設立事例を紹介。組合を作ることで同じスタートラインに立てる。行政との折衝がしやすくなる。その他。
▼補助金申請はいつ受理されたのか? 第3次の補助金申請でやっと受理。
企業負担は金融機関から借り入れ。水産加工業は機械が特注のため補助金も借入金も億単位の高額。
▼驚異的な値上がり
▼顧客離れを防ぐには業務提携
再建には時間が掛かるため様々な業種で顧客離れを防ぐ必要が生じる。共に被災しない地域にあり技術的に信頼が出来る企業を平時に探し、どちらが被災しても業務提携が可能な企業同士の契約を結んでおく。
▼原料の入手先を複数準備。
原料の入手先が共に被災しないエリアにあり、出来れば少量でよいので平時に取引をするなどパイプを作っておくことが大切。
▼工場再建のための建設業者の選択
災害想定地の経営者の方は、建設会社をどこにするかを調べて決めておく。
▼復興には情報入手が不可欠
▼急激な社会の変化
社会風習の変化 ネットによる販売など生活が激変を続けるなか、常に現状と未来を見つめ、自社の方向性を決断。
▼働き手の不足
今や日本中の問題である労働力不足、次世代の育成、海外からの労働力導入については企業グループや組合で独自の取り組みも必要。
▼温暖化など気候変動による影響
この魚がなければダメというのではなく、機械を改良して獲れる魚で新商品を生産するしかない。
▼水産加工業はいま大きな窮地に立たされている。
他業種でも自然環境の変化に大きな影響を受ける場合がある。それをどのように克服すればよいのか、経営者の体力、気力、知力すべてを注いで生き残る方策を見出す。
▼コロナ禍
売り上げは85%減。借金は増えている。戦略を変えないと生き残れない。
▼災害保険
災害保険に入っていたことで、落ち着いて復興に取り組むことが出来た企業があった。いつ来るか分からない自然災害に保険をかけ続けるのは負担だが、何とか備えたい事例です。
 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件は、岸田文雄首相が最近まで会長だった宏池会(岸田派)の元会計責任者も立件対象となることが判明したことから、岸田派は18日、政治資金収支報告書を訂正するとともに、首相は、苦肉の派閥解散案を唐突に打ち出しました。
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件は、岸田文雄首相が最近まで会長だった宏池会(岸田派)の元会計責任者も立件対象となることが判明したことから、岸田派は18日、政治資金収支報告書を訂正するとともに、首相は、苦肉の派閥解散案を唐突に打ち出しました。
首相は、収支報告書の訂正では持たないと見たのか、岸田派幹部と相次ぎ官邸で会談し、派閥の解散を検討していることを伝え、他派閥の解散については、各派の意向に委ねる考えを示しており、他派閥が同調するかは不明で、ある派閥幹部は「岸田派だけ抜け駆けして表明するのはどうなのか。」など党内批判も高まっています。
このような状況にある中で、昨日の時事通信の1月世論調査によると、自民党の政党支持率は前月比3.7ポイント減の14.6%で、野党時代を除き過去最低で、岸田内閣の支持率は前月比1.5ポイント増となったものの18.6%と相変わらず2割を下回っています。
また、この調査では、自民党が派閥を解消すべきだと「思う」が56%で、同党の政治刷新本部に「期待しない」が68%となっています。
自民党では、不祥事を受けてこれまで幾度も派閥が解散し、ほとぼりが冷めると元に戻るという復活劇が繰り返されてきただけに、今回の「派閥解散」を、本当に自民党が抱える政治とカネの問題の根絶につなげることができるかどうかは、不明です。
党内からは、もう岸田政権を支えないとの声も上がっていますが、そのことによって腰砕けになることも想定されますので、派閥をなくしたから終わりでなく、これまで派閥を舞台に何が行われてきたのか、徹底的に解明する責任が問われています。




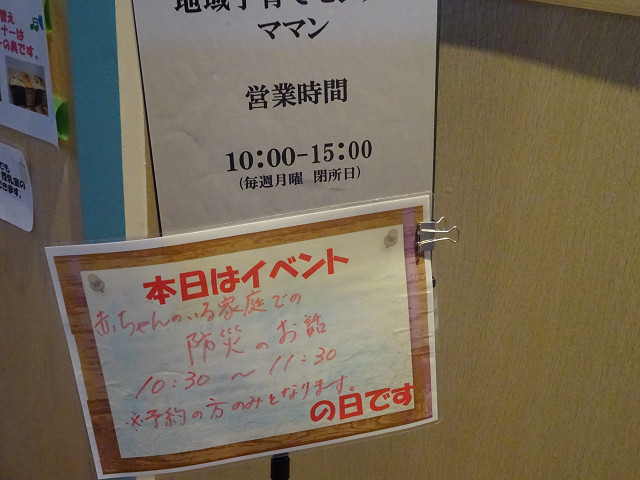
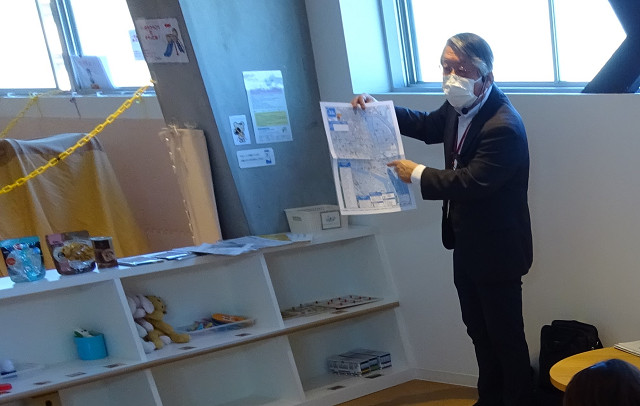
1995年1月17日午前5時46分、兵庫県南部地震は大きな被害と発生当時戦後最多となる死者を出す阪神・淡路大震災を引き起こしました。
6434人の尊い命と生きざまが奪われてから29年、私たちはこの震災の犠牲者の追悼と記憶と教訓を継承するため、下知地区の青柳公園で「1.17追悼の集い」を重ねて10回目となります。
その10回目の追悼は、元旦に発生した能登半島地震の犠牲者への追悼と一日も早い復旧・復興を願う集いにもなりました。
まさに、それは神戸市東遊園地の灯篭でつくった文字が「つなぐ」から「ともに」にかわる必然であったかもしれないと思いつつ、細々ではありますが未災地・高知の追悼の集いで22人が確認しあった5時46分でした。
集いの後には、下知地区内にある子育て支援センター「ママン」で、「赤ちゃんのいる家庭での防災の話」ということで、10組の親子のママさんを対象に防災のお話をさせて頂き「下知地区で赤ちゃんと備える南海トラフ地震」と題して、お話をさせて頂きました。
終わってからも、4人の方から順次相談を頂き、日頃からの備えの大切さをお話させて頂きました。
私は、1.17とか3.11など過去の大震災の日には、よほどのことがない限り、非常食で過ごしています。
今回は、能登半島で厳しい避難生活を送られている方に思いを寄せながらの食事をしています。
今朝の青柳公園で開催された「1.17阪神淡路大震災追悼の集い」の様子が地元テレビ局三社のニュースで報道されています。
こちらにリンクを貼っていますので、ご覧いただければと思います。
テレビ高知
RKC高知放送
さんさんテレビ



昨日、私も共同代表を務める平和憲法ネットワーク高知をはじめ、護憲連合高知県本部、高知県平和運動センターの三者で、防衛力の強化のため国が整備・拡充を予定している「特定重要拠点空港・港湾」について、高知県内での整備に反対するよう、県に申し入れました。
「特定重要拠点空港・港湾」は有事の際に自衛隊や海上保安庁が国民保護などを円滑に行うため、平時に必要な空港や港湾を訓練で利用できるよう国が整備・拡充する方針を示しており、本県では高知港、宿毛湾港、須崎港の3か所が候補にあがっています。
申し入れの際には、「平時の訓練利用としているが結局は有事にも利用されるのではないか」「整備によって攻撃対象になる可能性が高まるのではないか」「アメリカに求められれば米軍の利用も可能になるのではないか」などの懸念を伝え、国からの具体的な説明がなされる際には、これらのことを踏まえて、懸念に対する考え方を明らかにさせることを求めました。
また、年度末までの結論をと言われるが、今後は国から当該市町村長に対して丁寧な説明をしてもらわなければならないし、12月定例会以上の進捗状況にはないことも示されました。
最終的には、県が判断することとなるので、その際には県民には平和と安全への不安を与えることのないように、今後とも求めていくことを申し添えて、申し入れを終えました。
なお、申し入れ書の申し入れ事項の抜粋を下記に掲載しておきます。
「県管理港湾施設の自衛隊利用」に関する反対の申し入れ
私たちは、高知県の港湾の「特定重要拠点」化には反対であり、高知県が同意しないことを求めるものです。その理由は次のとおりです。
一つに、高知県議会では1984年に世界の恒久平和は人類共通の願いであるとして「非核平和高知県宣言」を決議、そして1997年12月には「非核平和高知県宣言に基づき、高知新港の一部開港を控え、県内全ての港において非核三原則を遵守し、県民に親しまれる平和な港としなければならない。当県議会は、ここに改めて高知県の港湾における非核平和利用を決議する」としています。当時の状況として外国艦船の高知県の港湾に入港するさいの非核神戸方式の導入をめぐっての決議でしたが、軍事訓練と平和利用は相いれないものです。
二つに、有事の際には、自衛隊基地はもちろん、自衛隊利用を想定した空港や港湾も攻撃対象になりうるものであり、県民の生命を危険にさらしかねないものです。岸田政権が閣議決定した安保関連3文書において「反撃能力」(敵基地攻撃能力)の保有が明記され、有事の際、相手国のミサイル発射拠点を先制攻撃することになり、逆に「特定重要拠点」も攻撃対象になる危険性が極めて高くなります。知事答弁にあるように、「有事の際の円滑な利用」も想定されていることから、周辺住民の安全が確保できるかはなはだ疑問です。
三つに、「(米軍の利用は考慮外との政府の国会答弁を受けて)米軍の利用につながるものとは現時点で考えていない」との考えですが、昨今の自衛隊と米軍が一体となった合同軍事演習がより強化されている今日、いずれ米軍艦船もふくめた合同使用となることは必至といわざるを得ません。
したがって、国との協議内容等について徹底して情報公開されることを要請するとともに、慎重に検討されることとあわせて県民の安全と安心を守る立場から、国の申し入れについて同意されないよう強く申し入れます。
そして、高知県としてとりわけ中国をはじめとしたアジア諸国との自治体平和外交を積極的に行われ、平和と善隣友好の機運を醸成されるよう要請します。
|
| 1月15日「過去の震災の教訓が生かされるように軌道修正を」 |
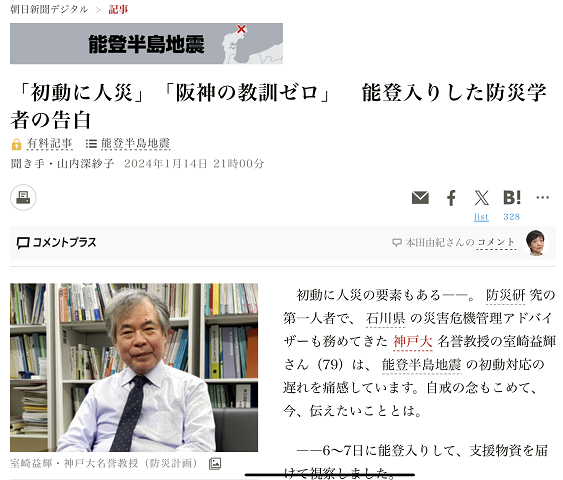
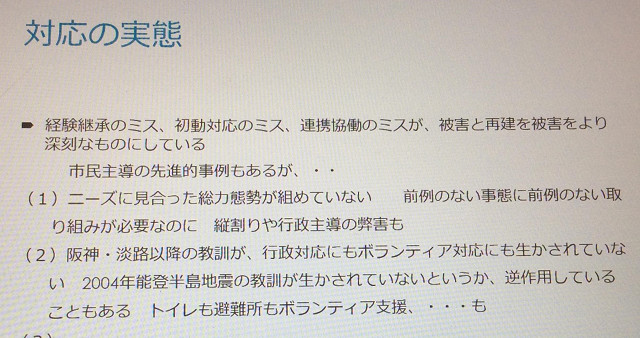
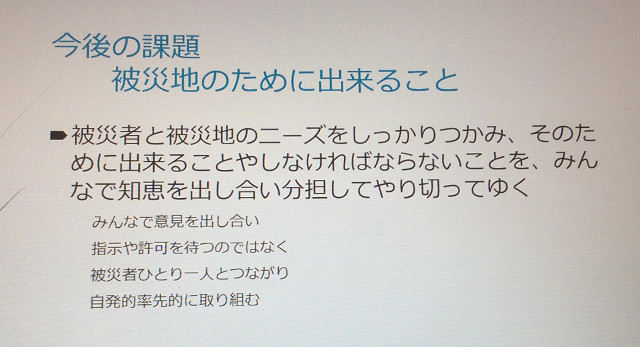
1月8日、被災地から帰られたばかりの神戸大学名誉教授室﨑益輝先生に、毎週月曜日にオンラインで開催されている令和6年最初の全国防災関係人口ミートアップで、「令和6年能登半島地震〜被災地のためにできること〜」として話題提供頂き、200名近い全国の参加者の皆さんで考えさせていただきました。
その時に、お話し頂いた中で、「対応の実態」として、「経験継承のミス、初動対応のミス、連携協働のミスが、被害と再建をより深刻なものにしていること。市民主導の先進的事例もあるが、①ニーズに見合った総力体制が組めていない②阪神淡路以降の教訓が行政対応にもボランティア対応にも生かされていない」ことが指摘されていました。
しかし、そんな中でも「被災者と被災地のニーズをしっかりつかみ、そのためにできることやしなければならないことを、みんなで知恵を出し合い、分担してやり切っていくことが必要であり、それが被災地のために今できることではないか」と仰られていたが、朝日新聞デジタル記事で、改めて繰り返されていました。
取材に答えた室崎先生は、石川県の災害危機管理アドバイザーを務められた自らの責任に自戒もこめて、長年防災と復興支援に関わってきた一人として、誰かが言わなければ、言葉にしなければとの思いで、被災状況の把握が直後にできなかったために、国や県のトップがこの震災を過小評価したことによるマンパワー不足と専門的なノウハウの欠如で、後手後手の対応は「人災の要素すら感じる初動対応の遅れ」だと指摘されています。
初動の際、「一部のボランティアしか入らなかったために、水や食事が手に入らず、暖もとれず、命のぎりぎりのところに被災者が直面した」が、「行くのをためらった状態を作ったことは大きな間違い」ではなかったかと述べられています。
「マンパワー不足と専門的なノウハウの欠如で、後手後手の対応が続いているが、政府は『お金は出す』というリップサービスでなく、関連死を防ぐなどの緊急ニーズに応えられる具体的な対策を提供すべきで、『必要な人材を出す』というサービスに徹するべき」と、今からでも急ぐべきことに言及されています。
「過去の震災では、災害支援や復興計画の専門家が首長につきっきりで的確な助言をしてきたけれど、その態勢もできていない」「被災者の命や生活を守れるかが、かかっている今こそ、教訓がいかされるよう、軌道修正をしなければ」なりません。
ご自身が「悔恨の念にかられ」ながらも、「人と人とが被災者を中心に支え合い、ともに考え、司令塔は、より重い責任を再確認し、基本に立ち返り、柔軟に迅速に的確に動く。私たちが過去の被災地の経験から学び、めざしてきたことを、もう一度確かめ合う必要がある」と結ばれています。
それぞれの重い言葉をしっかりと受け止めながら、私たちができることで、被災者、被災地に寄り添いたいと思います。
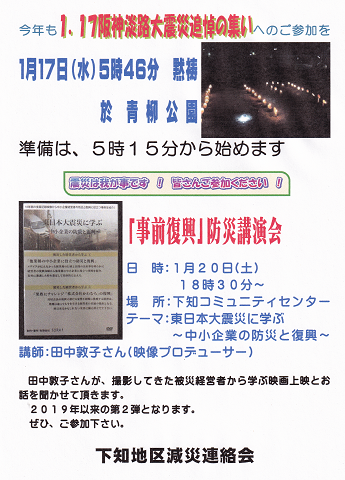

元旦の能登半島地震で被災した皆さんの被災生活の厳しさが連日報道され、胸を痛める方が多いことと思います。
そこには、復旧・復興過程での災害時の教訓がどれだけ生かされているのかと思わざるを得ない場面にも遭遇することがあるのではないでしょうか。
地震をはじめとした自然災害の教訓を学ぶ原点ともなった1.17阪神淡路大震災から29年目を迎えます。
下知地区減災連絡会では、阪神淡路大震災から20年を機に、風化させず多様な自然災害の教訓に学び続けることを確認しあう1.17阪神淡路大震災追悼の集いを細々と継続させてきました。
8人でスタートした集いも、今年が10回目となります。
今では、30人近くの地域の方たちが5時46分に黙祷で追悼しています。
今年も近づいてきましたが、1.1の能登半島地震で犠牲になられた方のための黙祷も合わせて捧げたいと思います。
そして、1月20日(土)には、能登半島地震でも課題になっている「広域避難」の訓練を初めて開催します。
長期浸水エリアからゴムボートで救出された後、広域避難協定を締結している仁淀川町へとバスで避難する予定です。
そして、訓練が終了してからは、18時から下知コミュニティセンターで事前復興防災講演会を開催します。
講師は、ソラワン・映像プロデューサーの田中敦子さんで「東日本大震災に学ぶ~中小企業の防災と復興~」について、記録映画も併映します。
翌、1月21日(日)には、「わくわく昭和交流フェスティバル」に、下知地区減災連絡会のブースで防災啓発を行います。
さらに、2月6日(火)には、JICA研修生を受け入れ、2月10日(土)には昭和小防災オープンデーと矢継ぎ早の防災・減災の取り組みが続きます。
一つ一つの取り組みこそが、被災地を思い、南海トラフ地震への備えを我が事にすることだと思って、準備していきます。
皆さんも、ぜひ、機会を捉えて、お越しください。
| 1月12日「被災者の権利や利益を守るための『特定非常災害』にも指定」 |
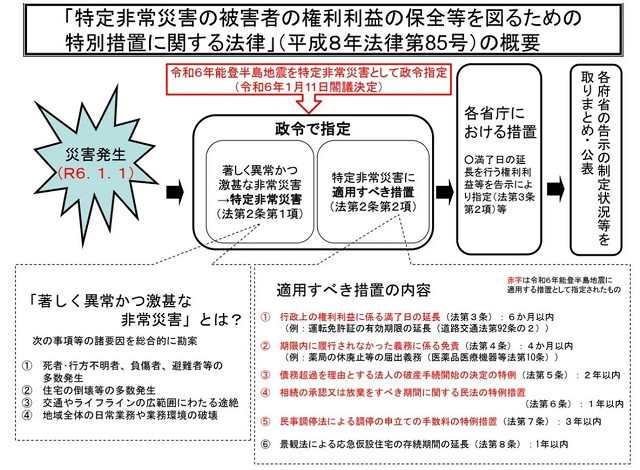 政府が11日、能登半島地震を「激甚災害」に指定し、対象地域を限定しない「本激」の措置を適用することを持ち回り閣議で決定したことが報じられています。
政府が11日、能登半島地震を「激甚災害」に指定し、対象地域を限定しない「本激」の措置を適用することを持ち回り閣議で決定したことが報じられています。
また、「特定非常災害」に指定することも決められました。
このことは、津久井進弁護士らが共同代表をつとめる「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」も1月7日付け「令和6年能登半島地震に関する緊急提言(2)」で「特定非常災害の指定を速やかに」と提言されていました。
「激甚災害」指定によって、自治体が復旧のために行う土木工事や家屋解体などへの国庫補助率を引き上げ、財政負担が軽くなりますので、自治体にとっては激甚法の適用は重要ですが、被災者にとっては、それ以上に「特定非常災害」の指定も重要であります。
この指定によって、法令または先例により、運転免許証の更新期限延長や債務超過となった法人の破産手続きの留保など、被災者の様々な権利保全のほか、被災建物の公費解体の拡充、仮設住宅の期限延長、法テラスによる無料法律相談、災害ケースマネジメントの実施(被災者見守り・相談支援等事業による全面補助)などの可能性が高まり、被災者の権利や利益を守るための措置がとられることになります。
まさに、被災者にとって重要なことについて、高知でも度々講演して下さっています岡本正弁護士が「令和6年能登半島地震が8例目の特定非常災害指定 行政手続や相続放棄の期限延長や半壊住宅の公費解体も」とのタイトルで、ネットニュースで詳細報告して下さっていますので、紹介させて頂きます。
とにかく今不安な状況に置かれている被災者の皆さんに少しでも安心を与えられる情報だと思います。
このような情報が少しでも、被災者の皆さんに届くことを願っています。
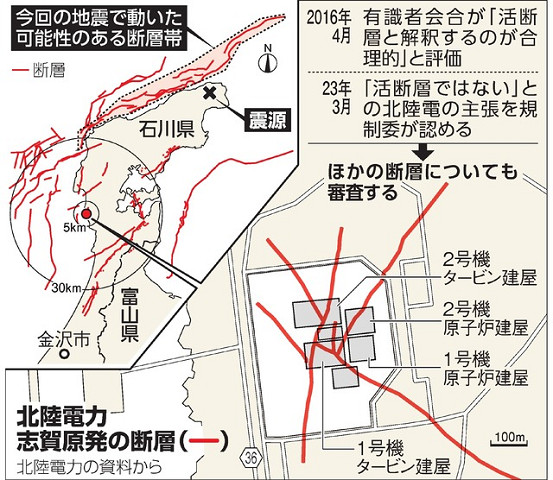 今回の能登半島地震は、揺れ、液状化、津波、火災、土砂災害と被害の全容が明らかになるにつれ、これで、原発災害が重なっていたらと思わざるをえません。
今回の能登半島地震は、揺れ、液状化、津波、火災、土砂災害と被害の全容が明らかになるにつれ、これで、原発災害が重なっていたらと思わざるをえません。
停止中の志賀原発では、3系統5回線の外部電源のうち1系統2回線は停止し、1号機側の起動変圧器では、油漏れに加えて噴霧消火設備の起動及び放圧板が動作したことも確認されるなど原発にとって安全上重大な問題がいくつも起きてます。
これで過酷事故にならなかったのは、稼働していなかったことと、最大の揺れを引き起こした断層から離れていたことが幸いしたに過ぎないのではないかと言われています。
昨日の原子力規制委員会は、今後の原発の審査や安全対策の議論を始め、再稼働に向けて審査中の2号機について、今回の地震の知見を収集するよう原子力規制庁に指示し、「新知見かどうかを確定させるまでに年単位の時間がかかる。審査はそれ以上かかると思う」との見通しを示さざるをえませんでした。
加えて、半島における地理的リスクによる避難困難の実態も明らかになっています。
地震の影響で能登半島では土砂崩れなどで道路が寸断され、通信環境も悪化し、孤立集落が多発するなど、原発事故の際の避難について、半島の地理的リスクが明らかになっています。
原子力防災に詳しい東京大大学院情報学環総合防災情報研究センターの関谷直也教授は「半島は電気や通信、道路の手段を多重化するのが難しい」と指摘しています。
地震は止められないし、対策にも限界があります。
原発災害を最小限に食い止めるには、原発を「止める、冷やす、閉じ込める」対策を、今から実施していくほかないことを改めて痛感させられました。
| 1月10日「災害関連死をこれ以上拡大させないために」 |
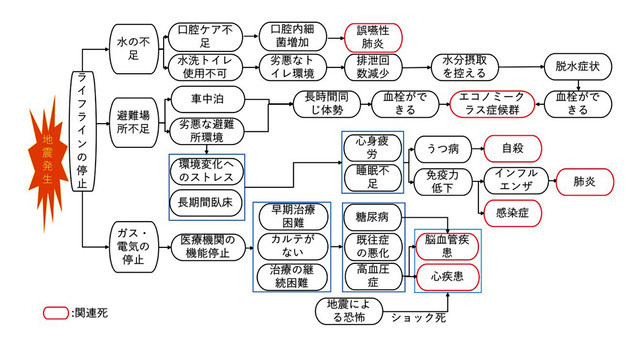 石川県は昨日午後3時時点の集計で、能登半島地震で遂に災害関連死が珠洲市内で6人確認されたと発表しました。
石川県は昨日午後3時時点の集計で、能登半島地震で遂に災害関連死が珠洲市内で6人確認されたと発表しました。
今回の地震で、地震被害による直接死ではない災害関連死の発生が明らかになるのは初めてで、死者は202人にのぼり、安否不明102人となっています。
心配されていたことが、顕在化し始めているということです。
いずれもオンライン参加でしたが、8日に全国防災関係人口ミートアップ会議で室崎益輝先生から、9日には東北大学災害研の「令和6年能登半島地震に関する速報会」での報告を聞くにつけ、今回の地震の規模の大きさと被害の全容が明らかになるにつれその甚大さに驚かざるをえませんでした。
そして、前回「災害関連死を招かないために」と題して、津久井進弁護士の「関連死を防ぐには、インフラなど環境の整った被災地外への避難が不可欠。判断は一刻を争う」、「ぎりぎりまで避難者を我慢させてはいけない。関連死が起きる前に手だてを講じる。それが過去の経験で得た教訓だったはずだ」との新聞コメントを紹介させていただきました。
その言葉を受け止めた自治体の判断が今こそ求められています。
石川県内では、8市7町の避難所404カ所に2万6158人が身を寄せている中で、避難所における水不足、医療人材不足、衛生面などの心配が高まっているだけに、環境の整った避難所に移動するしかありません。
また、関西大学奥村与志弘教授(総合防災・減災学)は、関連死者数は避難者数の増加に伴い、指数関数的に増える特徴があると言い、東日本大震災の時の被災地のような深刻さが続くと、100人以上の関連死の犠牲が出てしまう可能性もあると指摘しています。
さらに、避難所で生活されている方々に加え、自宅や高齢者施設などにも厳しい生活を強いられており、ライフラインが機能しない中、避難所に行くこともできない高齢者が劣悪な環境に置かれている可能性があり、いわゆる「在宅避難」の方々を把握し、支援することが求められます。
私たちが、東日本大震災で学んだことの中に、水不足で口腔ケアがおろそかになって、誤嚥性肺炎のリスクが増大したことなどにも、向き合うことが必要です。
関連死対策では避難所が注目されがちですが、最も多くの関連死が発生しているのは高齢者施設と自宅であり、熊本地震では、関連死の40%が自宅で発生したことからも、しっかりと被災者に目配り、寄り添うマンパワーの確保が急がれます。
そして、せっかく守った命を失う災害関連死をこれ以上拡大させないことを願うばかりです。
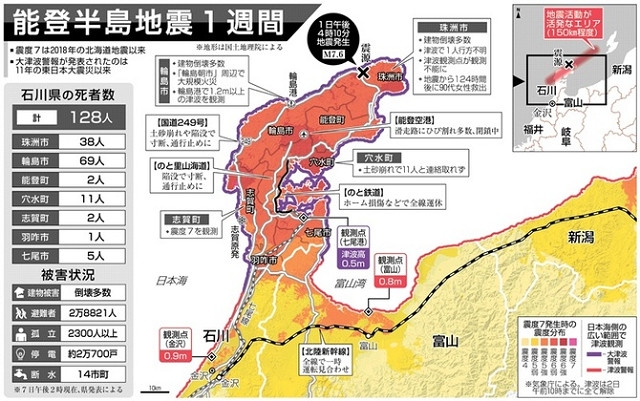
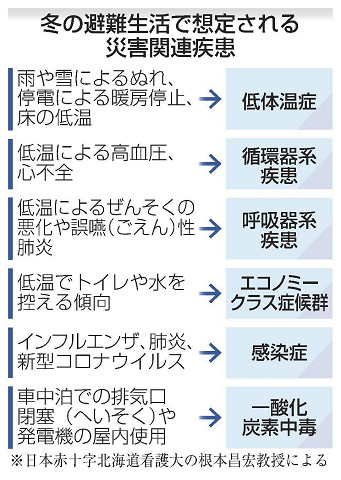
今朝の高知新聞4面には「避難所過酷 命の危機」との見出しで、共同通信の配信記事が掲載されています。
記事には、日頃から高知が下知地区がお世話になっている認定NPO法人「ピースウィンズ・ジャパン」国内事業部次長の橋本笙子さんや多くの災害で支援に取り組んできた元日弁連災害復興支援委員会委員長津久井進弁護士などのコメントが載っていました。
発生から1週間となる能登半島地震で、被災者であふれる厳寒の避難所は、食事や物資も不十分で過酷な状況が続き、命が再び脅かされる事態になっているとのことです。
まさに、被災地は家屋倒壊などによる「直接死」に加え、避難先で亡くなる「災害関連死」にも直面しています。
津久井弁護士は、「関連死を防ぐには、インフラなど環境の整った被災地外への避難が不可欠。判断は一刻を争う」、「ぎりぎりまで避難者を我慢させてはいけない。関連死が起きる前に手だてを講じる。それが過去の経験で得た教訓だったはずだ」と訴えられています。
津久井弁護士が共同代表を務められている「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」は、令和6年能登半島地震に関して緊急提言を出されています。
少し長いですが、下記に紹介させて頂きます。
政府や自治体が判断すれば、もっと迅速な取り組みができるはずです。
せっかく助かった命を、つなげる取り組みが今こそ求められています。
令和6年能登半島地震に関する緊急提言(2) 2024年1月7日
私たち「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」は、令和6年能登半島地震に関して、令和6年1月4日、①一刻も早く広域避難の体制を整備して災害関連死を防ぐとともに、②被災県が中心となって災害ケースマネジメントの実施に向けた連携の場を開設すべきことを提言しました。
広域避難は始動しつつあるものの、救えるはずの命を確実に守るためには、要支援度の高い被災者が取り残されることのないよう、積極的に避難誘導し、速やかに旅館等の避難先に送り届けることが必要です。災害対策基本法の広域避難規定、避難指示の趣旨に準じて、的確かつ強力なオペレーションを実施すべきです。
本日で、震災から7日目を迎えますが、被災地の状況の過酷さは改善されていません。避難所の設置期間を「災害発生の日から7日以内」とするのが災害救助法の一般基準です。これ以上、過酷な避難所生活を強いるべきではありません。
私たちは、一人ひとりの被災者の目線に立って、今、直ちに対応できる事柄を10項目の提言に取りまとめました。ぜひ、検討をお願いいたします。
1 災害対応を最優先にして、部署間の横断的な連携を
元旦の被災で帰省者も多かったこともあり、自治体内で万全な体制が取れなかったことは無理もありません。しかし、始業後も災害対応が最優先になっておらず、あるいは、部署間の横の連携がなくオペレーションが不十分な自治体もあります。全庁的な非常時モードで被災者支援に臨むよう是正されるべきです。
2 防犯対策の徹底により被災者に安心感を
被災者が、地域外に避難するのを躊躇する理由のひとつに、被災家屋が空き巣に遭うのではないかという心配があります。こうした不安を払拭するため、被災地で頻発する便乗詐欺と共に、応援警察官によるパトロール等の防犯対策を強化し、それを内外にアピールすることによって被災者に安心感を与えて下さい。
3 物資と応援人員の空輸の積極活用を
物資輸送は陸路が中心ですが、大渋滞により多大な時間がかかっています。また、物資が被災地に届いても、仕分け・配給の人手が足りず被災者に届いていません。ヘリコプター等の空輸は孤立地に限られていますが、水や食料等の生命に関わる物資や、物資支給に関わる応援人員の運送には、積極的に空輸を活用すべきです。
4 対口支援(たいこうしえん/カウンターパート方式)は官民連携で
特定の被災自治体に特定の自治体が支援する対口支援が行われる見通しです。全国の市民や企業・団体による民間支援やボランティア支援についても、円滑かつ持続可能性が持てるよう、対口支援に合わせたマッチングを進め、被災地における官民連携を強化するのが被災者にとって分かりやすく、合理的です。
5 可能な地域ではボランティア活動の早期推進を
珠洲市や輪島市など石川県の一部地域では、交通寸断によりボランティアの受け入れが困難です。しかし、他県や、石川県内の他地域では民間ボランティアも可能です。これら地域では、速やかにボランティアセンターを開設し、県内外を問わずボランティア活動を早期に進め、被災者のきめ細やかなニーズに応えるべきです。
6 仮設入居は罹災証明書を不要とすべき
仮設住宅の入居にあたり罹災証明書を求めるのが通例ですが、罹災証明書の発行が困難な地域では、広範な被害により地域まるごと生活が困難な状況にあり、余震の危険もあることから、罹災証明を要せず仮設入居を可能とするべきです。
7 罹災証明書の発行は被災者支援の目的に沿って迅速かつ合理的に
被災者生活再建支援法が適用される地域では、一日も早い罹災証明書の発行が必要です。そこで、航空写真等を利用した迅速な住家被害判定手法を最大活用して下さい。民間人も含めた外部の応援職員を大量に派遣し、被災者の申請を待たずに職権発行を行うなど合理的に進めて下さい。被災者支援に資することが主たる目的であることを忘れず、過度な精密性や公平性に決して陥らぬようご注意下さい。
8 被災者の名簿づくりに着手する
被災者支援のベースとして、被災者ごとに被害状況などの情報を整理する必要性があります。生命・財産を守る緊急の必要があるため個人情報保護法上も許容される状況にあります。特に災害ケースマネジメントの実施には、一人ひとりの被災者の個々の情報を、支援を行う官民の共有が必要です。アセスメントシートの調整、情報管理システムの整備と並行して、速やかに名簿づくりに着手すべきです。
9 災害救助法に関する発出通知及び事務連絡の速やかな公表を
避難所、物資提供、仮設住宅、医療提供などは災害救助法に基づいて行われています。その運用について内閣府(防災担当)が通知及び事務連絡を出しています。しかし、その内容は公表されず、混乱を極める被災地の行政機関においてもこれらの内容を把握し切れていないのが実情です。多くの関係者が実情に応じた適切な支援が行えるよう、速やかに通知及び事務連絡を公表して下さい。
10 特定非常災害の指定を速やかに
自治体にとっては激甚法の適用が重要ですが、被災者にとっては、むしろ「特定非常災害」の指定が重要です。法令または先例により、被災者の様々な権利保全のほか、被災建物の公費解体の拡充、仮設住宅の期限延長、法テラスによる無料法律相談、災害ケースマネジメントの実施(被災者見守り・相談支援等事業による全面補助)などの可能性が高まります。政府に速やかな指定を求めます。
以上 2024(令和6)年1月7日
一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会 共同代表 新里宏二、共同代表 天野和彦、共同代表 津久井進 |
| 1月5日「能登半島地震に見る耐震改修の高齢世帯での停滞」 |

 毎日の報道で、能登半島地震の被害の様相が明らかになり、死者84人、安否不明者179人にのぼっていますが、さらに増加するのではと懸念されます。
毎日の報道で、能登半島地震の被害の様相が明らかになり、死者84人、安否不明者179人にのぼっていますが、さらに増加するのではと懸念されます。
そして、能登半島地震では多くの住宅が倒壊した様子が映像で流されていますが、被害が甚大な石川県珠洲市などは県内でも高齢者が多く、費用負担が足かせとなり耐震改修が進んでいなかった実態が背景にあることも今朝の高知新聞などでも報道されています。
耐震化を進める国土交通省は「いつまで住み続けるか分からない住宅に、多額の費用をかけて改修する高齢者は少ない。耐震化が必要な古い住宅ほど対策が手付かずになる悪循環がある」と言っており、解消しなければならない課題のはずです。
「補助金で一部を賄い、対策を促すしかない」とも言うが、それなりに自己負担も必要な耐震改修が進まない中で、東京大広井悠教授(都市防災)は、高齢者が多く、耐震化が進まない地域は全国にあると指摘した上で、「住宅の一部を簡易的に補強し、逃げ込むスペースを確保するような耐震改修に対し、国や自治体が支援を拡充するべきだ」と提言しています。
私たちも、これまで県に対して、一部屋をシェルター的に補強しておけば、地震で家が損傷しても、建物の下敷きにならないスペースを確保し、揺れが収まってから屋外へ逃げるための「一室耐震化」への支援を求めてきました。
しかし、県は二段階に分けて耐震改修を行う場合の一段階目に要する費用を補助する「住宅段階的耐震改修支援事業」ということは認めるものの、「一室耐震化」への補助は認めていません。
全国の自治体では、高齢者等を対象に支援しているところもありますが、今回の能登半島地震の教訓からも全国的に推進する必要もあるのではないでしょうか。
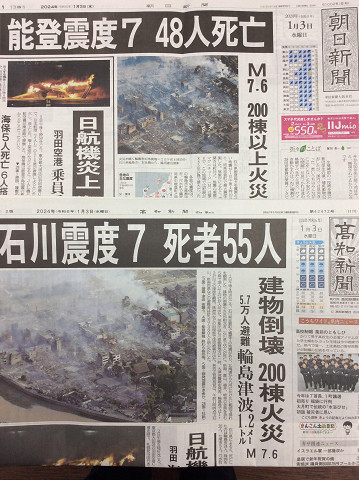 最大震度7を観測した令和6年能登半島地震で、3日には石川県内では、これまでに64人の死亡が確認されましたが、家屋の倒壊現場などで余震の頻発によって救出作業が難航しており、被害の全容はまだまだ明らかになっていません。
最大震度7を観測した令和6年能登半島地震で、3日には石川県内では、これまでに64人の死亡が確認されましたが、家屋の倒壊現場などで余震の頻発によって救出作業が難航しており、被害の全容はまだまだ明らかになっていません。
岸田首相は3日午前の非常災害対策本部会議で、捜索などに当たる自衛隊の態勢増強を表明し、防衛省は要員を1000人から2000人に倍増したとのことです。
死者の内訳は、輪島市31人、珠洲市22人、七尾市5人、穴水町と能登町が各2人などで、県内の355カ所に避難所が開設され、約3万3000人が避難しています。
輪島市では約200棟、約4000平方メートルが延焼し、珠洲市や能登町でも火災が発生したが、おおむね鎮火したとのことです。
北陸電力によると、3日午後3時35分時点で約3万3300戸が停電しており、断水も各地で発生しており、自衛隊などが給水支援を実施しているようです。
石川県は4日朝にかけ、低気圧の影響でやや強い雨が降る所がある見込みで、気象庁は土砂災害に警戒し、突風や落雷に注意するよう呼び掛けているとのことで、避難所での避難生活の厳しさが想定されます。
可能な支援が一日も早く届くことを願っています。
なお、さまざまな災害関連情報を取りまとめたページにリンクを貼っておきますので、必要な方はご活用ください。



穏やかな元旦に、石川県能登地方で夕方震度7を観測する地震が襲い、石川県、福井県、富山県や新潟県などで大きな被害が出ています。
時間が経つにつれて、死亡者数やけが人など犠牲者の数が増加しつつありますが、石川県によると、県内では2日午前8時半現在、避難所336カ所に、3万251人が身を寄せているそうです。
寒い中での避難生活ですが、災害関連死などにつながらないことを願うばかりです。
石川県など日本海側の広い範囲に津波注意報を出して注意を呼びかけられたが、輪島で1メートル20センチ以上の津波が観測された他、金沢でも90センチなど各地で津波が観測されました。
火災の映像で心配された石川県輪島市では、朝市通り周辺で100軒以上が燃えたとみられています。
また、原発銀座と言われる能登地方で震度7の地震に見舞われた志賀原子力発電所は、現在運転停止中の志賀原発1号機では、使用済み燃料貯蔵プールの水が漏れて冷却ポンプが一時止まりましたが、再起動したということです。
さらに、1号機では変圧器から油が漏れたほか、2号機では変圧器の消火設備が起動したが、北陸電力は「火災はなかった」と説明しています。
新潟県柏崎刈羽原発では、異常なしとのことですが、今後の原発の状況にも注視していかなければなりません。
内閣府は令和6年能登半島地震で、新潟、富山、石川、福井の4県が計47市町村に災害救助法の適用を決めたことが明らかにされています。
とにかく早急な救助・救出が急がれます。
| 1月1日「まずは、身近な3.5%の人々とつながる年に」 |
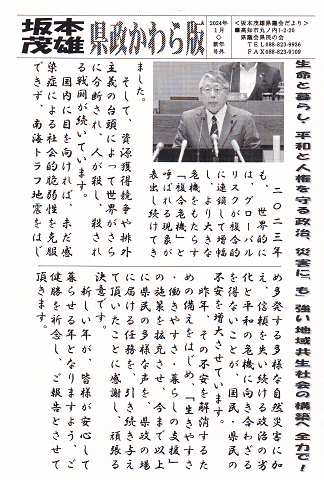

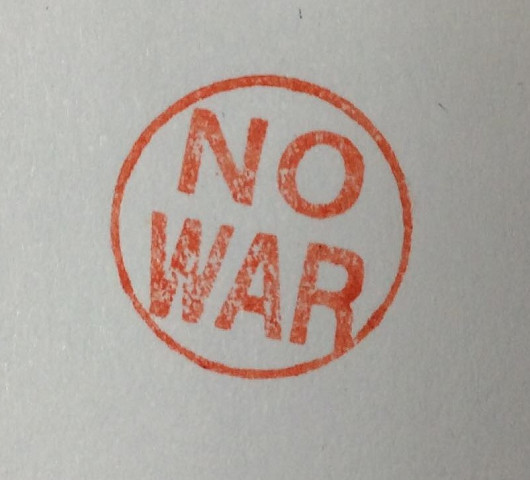
昨年中は、お世話になりました
本年も、よろしくお願いします
安保関連三文書を、一昨年暮れに閣議決定し、この国は新たな戦前に直面する重大な局面を迎えています。
憲法9条に基づく国是とも言うべき専守防衛を全てかなぐり捨てて、この国は敵基地攻撃能力を手にしてきました。
敵基地攻撃能力は、やられる前にやってしまえと言うことであり、これによって岸田政権は日本が公然と戦争ができる国に変えたのであり、断じて許せません。
際限のない軍備拡張路線、軍拡増税を目指す路線は国民生活をもを一層いっそう苦しめることになり、これも許すことができません。
日本は、今やアメリカの従属国になってしまっていますが、今も憲法9条は生きており、アメリカ政府に対し、敢然とした姿勢で日本はアメリカと一緒になって無謀な戦争をしないと言う意思表示をすべきであります。
憲法前文には、「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言しこの憲法を確定する」とあります。
この憲法の精神を一人一人の国民が自覚し、今こそ立ち上がるべき時であるといえます。
ハーバード・ケネディ・スクール教授のエリカ・チェノウェス氏の著書『市民的抵抗 非暴力が社会を変える』には、「3.5%」が動けば社会が変わる可能性があることが、書かれています。
「人口の3.5%を路上での運動に参加させられるほとんどの抵抗運動には実際にはもっと広範な支持基盤があるのだ。3.5%くらい大きな割合の人口が積極的に公に姿を表す抵抗運動のほとんどは、圧倒的な人数の人々の支持を得ている。」
「ある目的を持った行動に出る上で人口の3.5%を取り込むことができるということは、確実に、大多数の人々がその目的を支持しているということだ。かなり大きな規模で抵抗参加者を路上に導き出せることは、おそらく抵抗運動が人々の支持を得ることの原因ではなく結果である。」
少なくとも「3.5%」の人々とつながり、変えることで、社会を、政治を変える一歩を一人一人が踏み出す2024年ではないでしょうか。
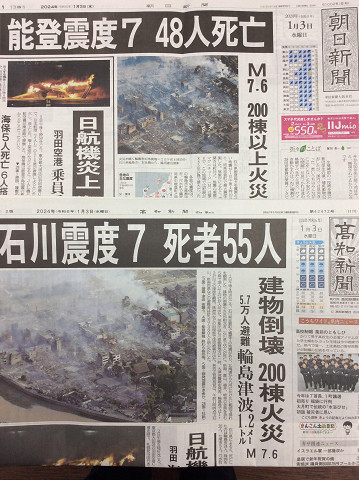
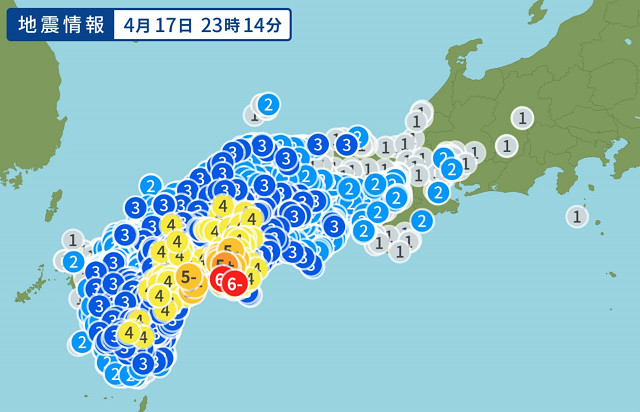

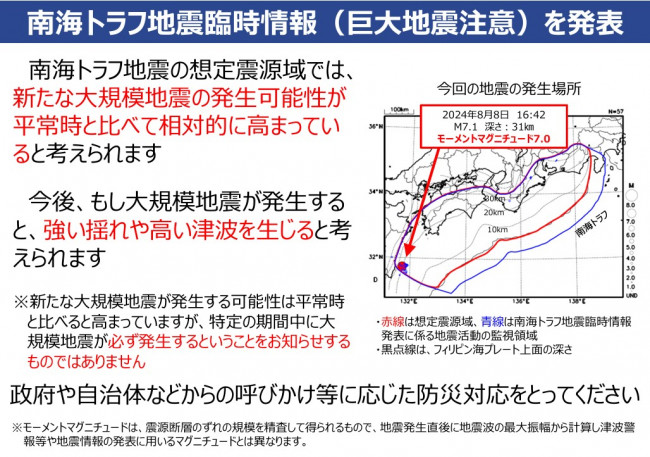
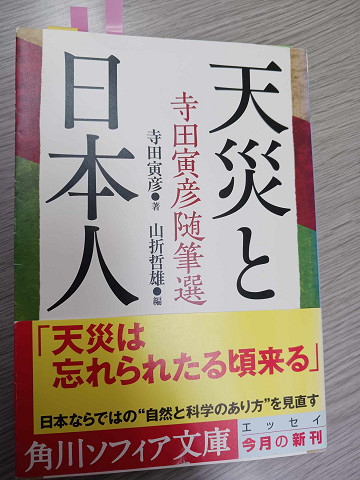 今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。
今朝の朝日新聞社説は「戦争と災害 年の瀬に考える被害と伝承」と題して、1944年12月7日という戦時下に発生した南海トラフを震源とする昭和東南海地震を通じた被害と伝承のあり方について書かれています。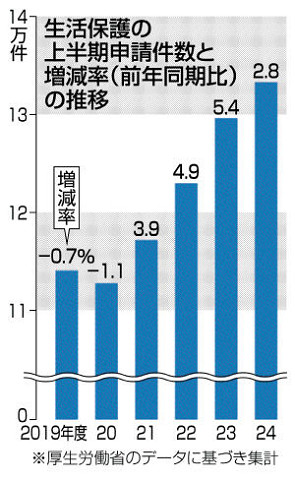 今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。
今朝の高知新聞一面は、物価高を反映し、生活保護申請が増加したことの記事となっています。
 沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。
沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、国が県に代わって工事を承認する代執行に踏み切って、今日28日で1年となります。

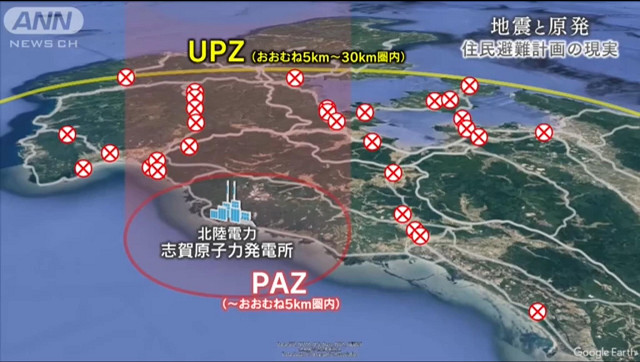

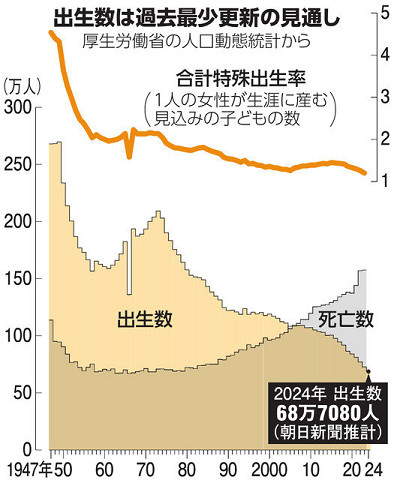 今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。
今朝の朝日新聞一面に「出生数70万人割れ」の見出しがありました。

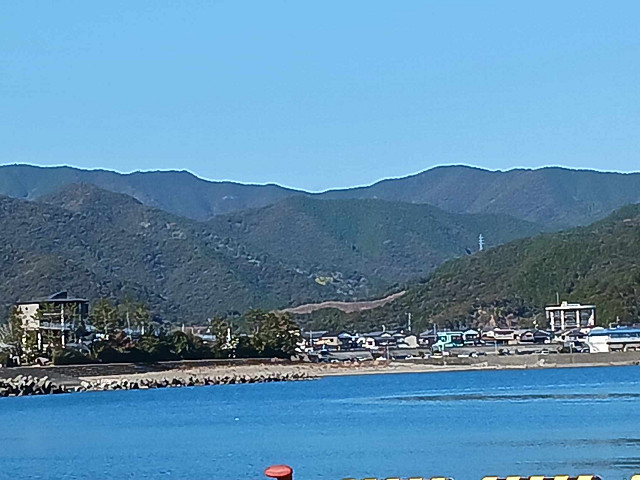


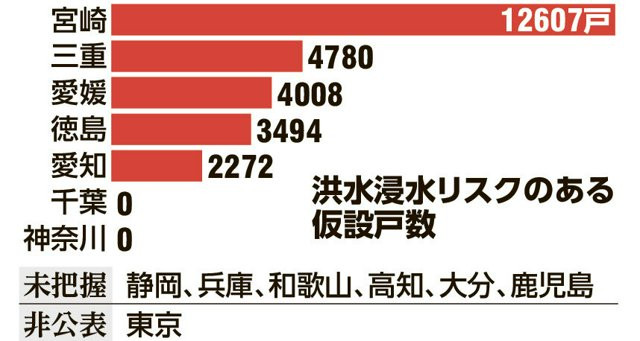 復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。
復興への険しい道のりを歩まれていた能登半島地震の被災地が、9月21日、記録的な豪雨に見舞われ、仮設住宅が浸水し、被災リスクを抱えた土地に仮設住宅を建設せざるをえなかった課題について9月定例会で取りあげたことがありました。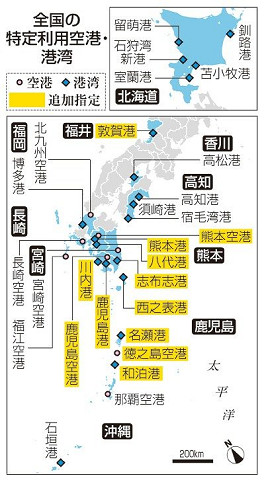 明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。
明日、12月定例会の閉会日となりますが、議案採決などでは請第4号「「特定利用港湾」指定同意の撤回を高知県に求める請願」について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論させて頂く予定です。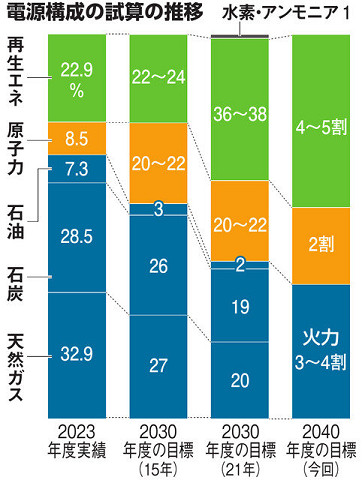
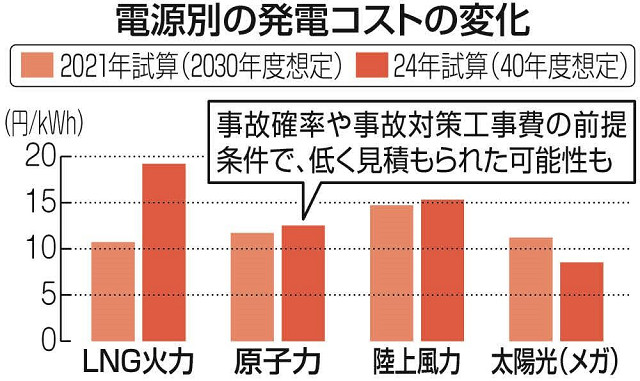 経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。
経済産業省が次期エネルギー基本計画の素案を示したが、福島第一原発の事故後に掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」という方針を削除しており、14年足らずで重大な事故の教訓を投げ捨てるような変更であり、許しがたいものと言えます。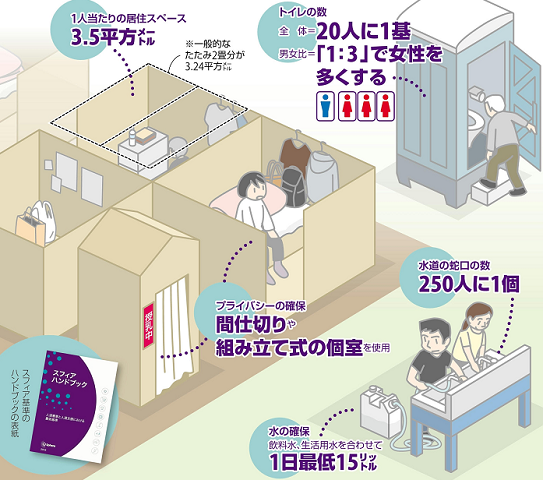
 今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。
今朝の高知新聞の社説では、政府が災害時の避難所運営に関する自治体向け指針を改定し、確保すべきトイレの数や被災者1人当たりの専有面積に国際基準(スフィア基準)を反映させ、避難所環境の抜本的改善に取り組むことが取り上げられていました。
 政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。
政府が防衛力強化のため整備する「特定利用港湾」について、「郷土の軍事化に反対する県連絡会」で取り組んできた県内3港の指定に対する県の同意撤回を求める請願と9989人分の署名を加藤県議会議長に、昨日提出しました。



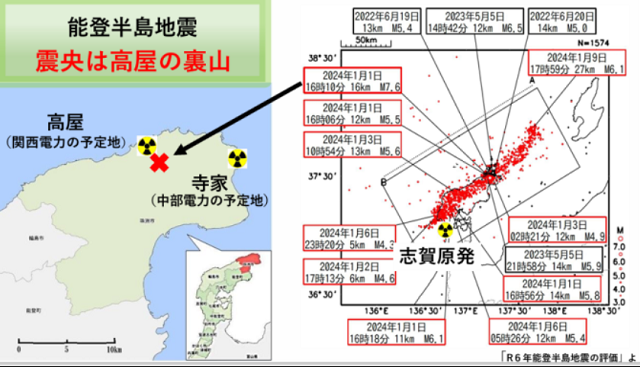 全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。
全国で唯一、県庁所在地に立地し、半径30キロ圏に全国で3番目に多い約45万人を抱え、避難計画の実効性など稼働後も課題が山積している中国電力島根原発2号機が7日、12年11カ月ぶりに再稼働しました。
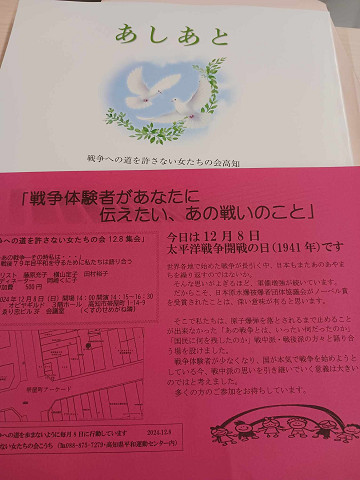

 更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。
更新が滞っていたことから、心配のご連絡なども頂き、ありがとうございました。
 12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授
兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。
12月1日には、地域の総合防災訓練が終わるやいなや、事務所で高知県自治研究センターのセミナー「日本の等身大の姿を見つめる④“行き過ぎた一極集中からの転換”」にオンライン参加し、片山善博(大正大学公共政策学科教授
兼 地域構想研究所長)さんの講演を聞かせて頂きました。





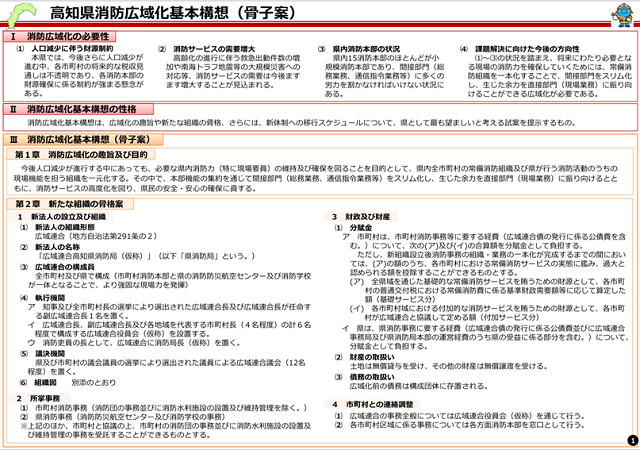
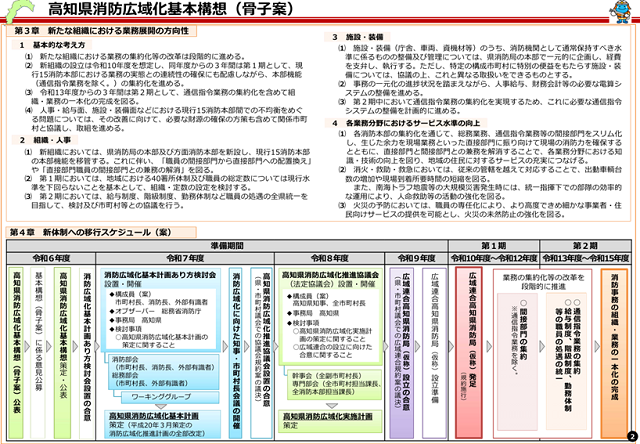
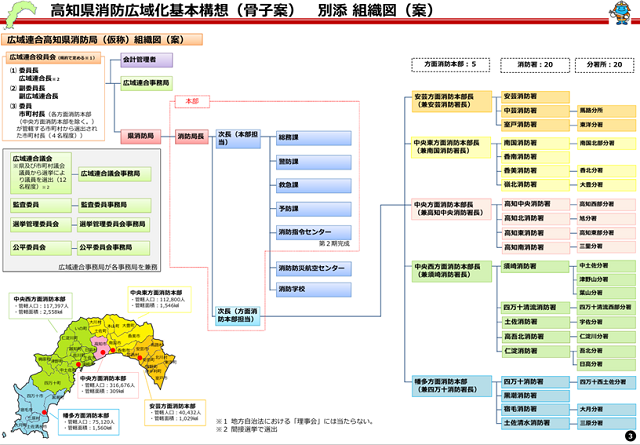

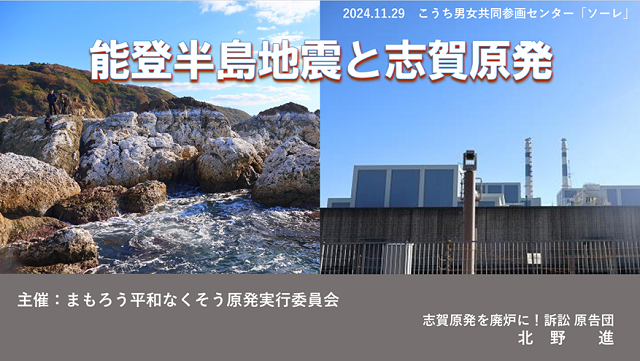 これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。
これまで、中央公園で開催してきた「まもろう平和・なくそう原発ACT10inこうち」が明日11月30日に迫ってきました。
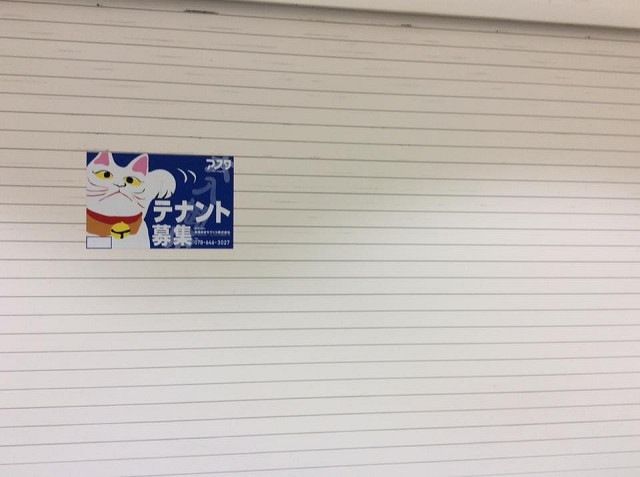



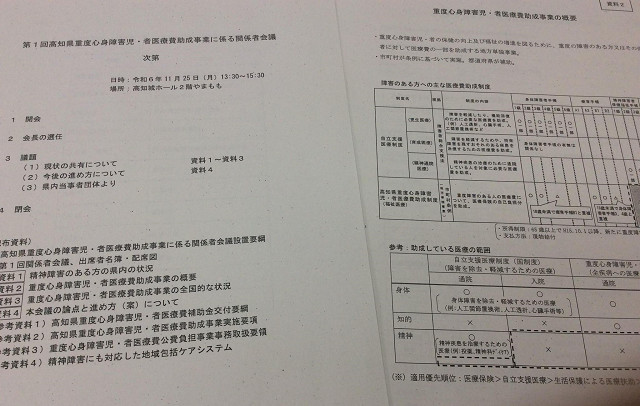 昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。
昨日、「第1回高知県重度心身障害児・者医療費助成事業に係る関係者会議」が開催されましたので、傍聴してきました。





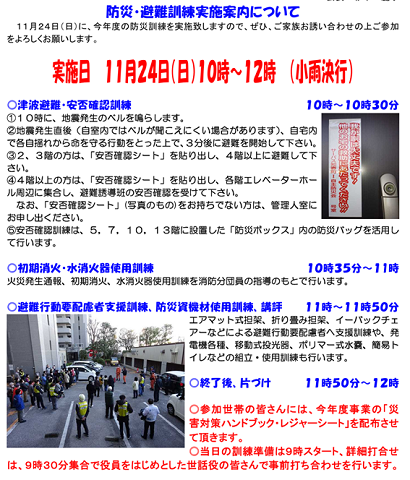 先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。
先週の土曜日もある集会の講師を行い、そのための資料づくりに追われていたが、今週は3日間の県外視察をはさんで、今日の平和運動センターピースセミナーの講師そして明日は、マンション防災会の訓練と準備に追われた日々が続いています。










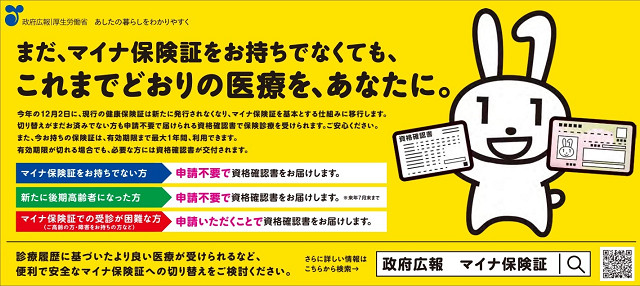 来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。
来月2日から、現行の健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードを使う「マイナ保険証」への移行が進められています。
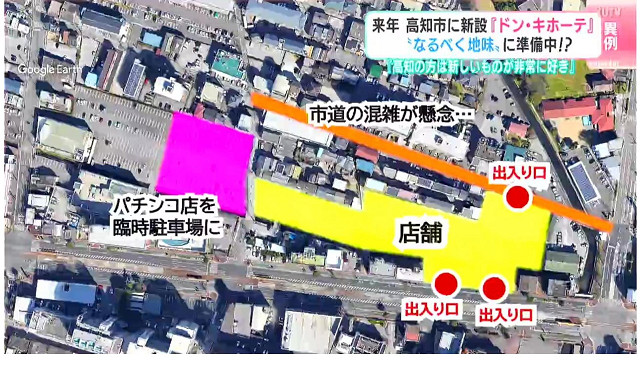

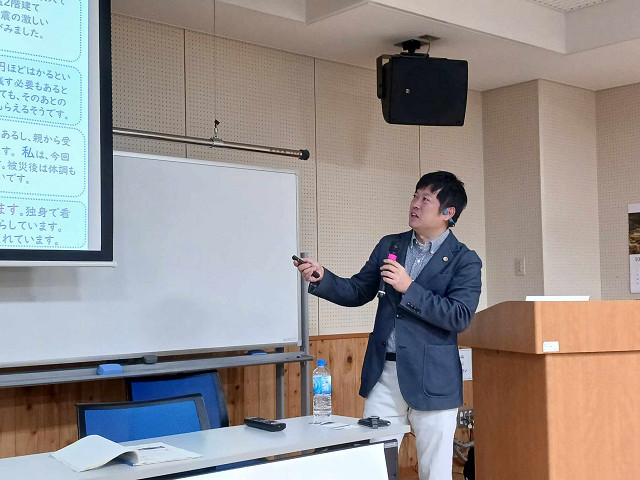
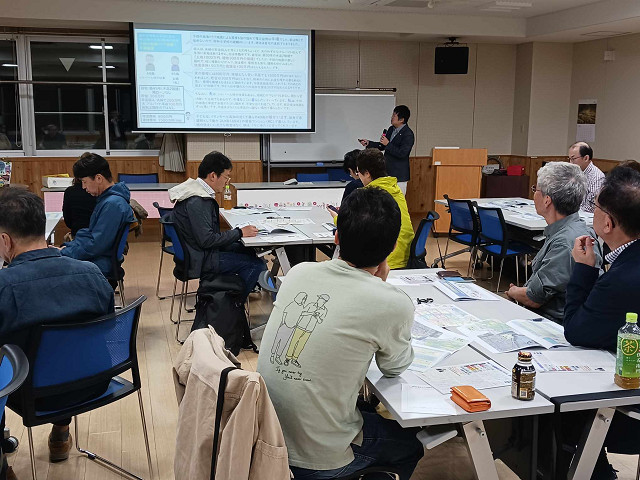
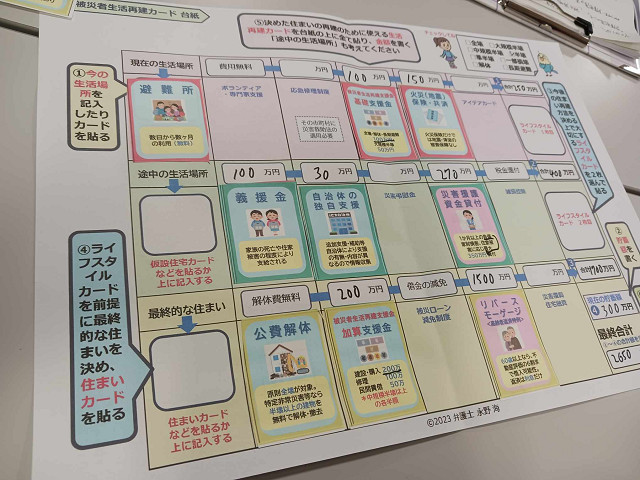
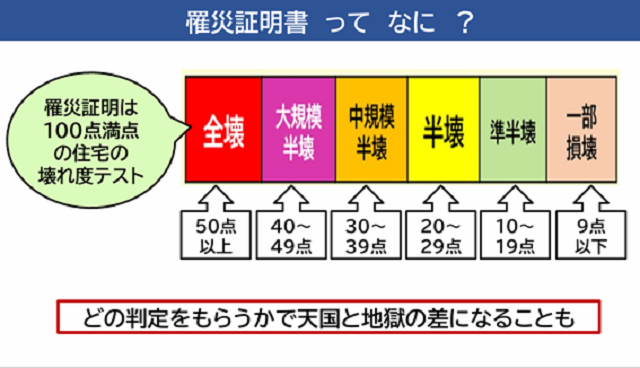
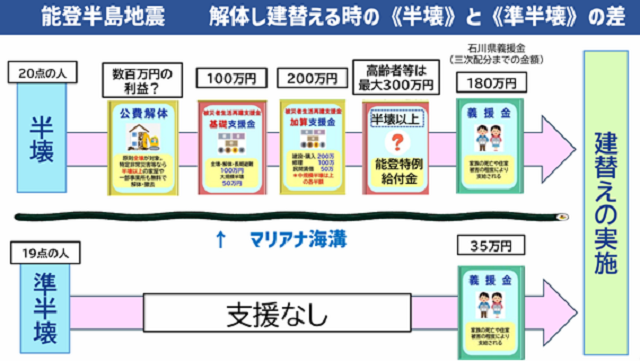
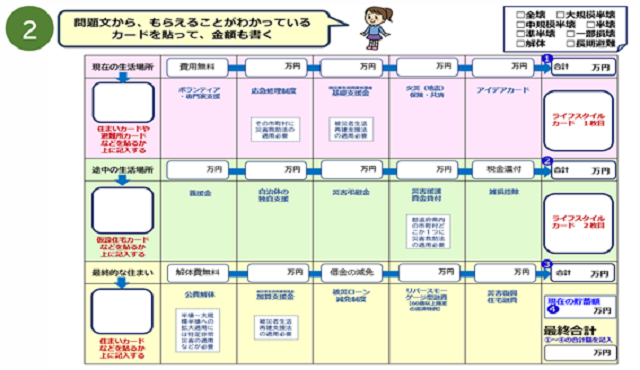
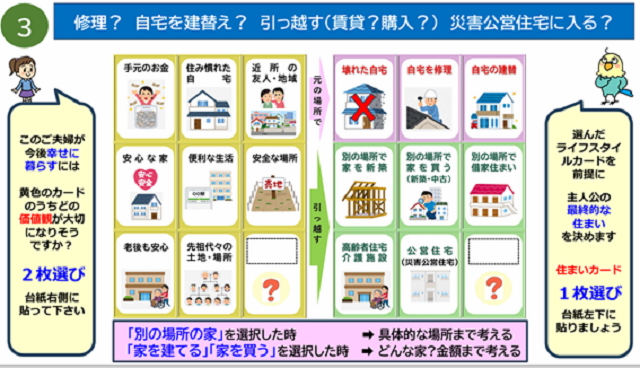

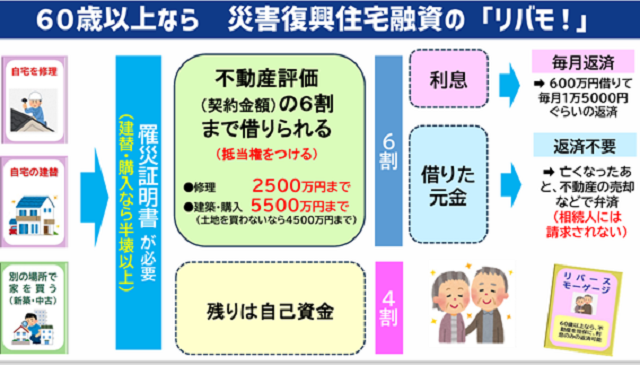
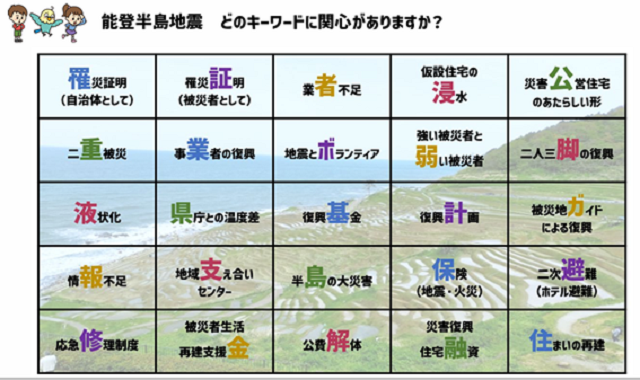

 12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。
12月議会に提出すべく取り組んでいる「「特定利用港湾」の指定受け入れの撤回を求める請願署名」を郷土の軍事化に反対する高知県連絡会で取り組んでいますが、今日は中央公園北口で署名行動を行いました。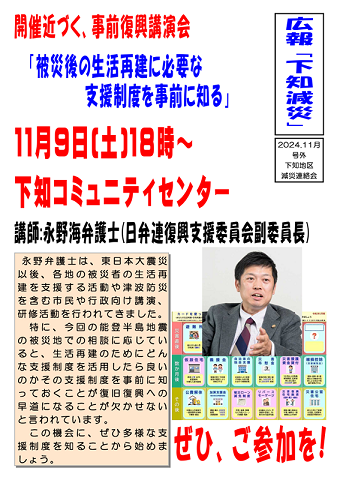 4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。
4日に、輪島市を訪ね、門前総合支所でJOCAの山中弓子さんに、お話を伺った際に、その前日に永野海弁護士が同会場で被災者の説明相談会を開催されていたとのことで、会場一杯の参加者が熱心に相談をされていたとのことでした。 輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。
輪島市役所門前総合支所にあるJOCA(青年海外協力協会)では、門町地区で仮設住宅を訪問し、被災者の支援を行われている「親子支援・災害看護支援*てとめっと」代表の山中弓子さんから、門前地区での仮設住宅や被災者の状況についてお話しを伺いました。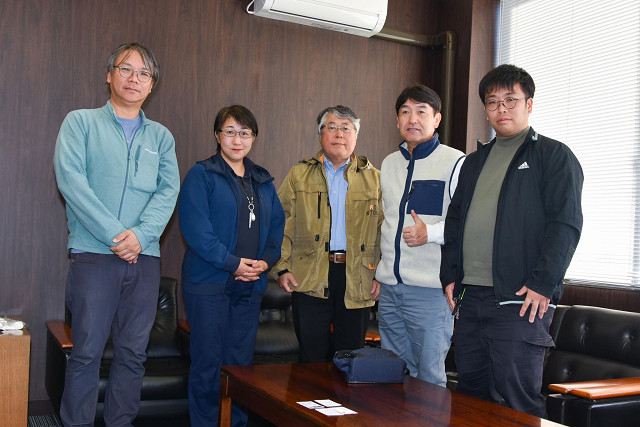





 今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。
今は、砂浜となっている中に波消しブロックが多く見受けられ、港から堤防までがずっと陸上になってしまっており、このような地形変化は「数千年に一度」と言われているとのことでした。



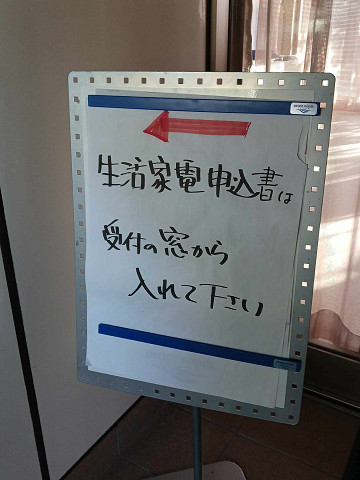 能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。
能登半島地震被災地視察を終えて、報告をしたいのですが、一度には無理なので、まず、3日の珠洲市について報告させて頂きます。
 この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。
この「記憶の街」ワークショップは、槻橋先生のお話をZOOM会議で聞かせて頂いたこともありましたし、京都大学牧紀男先生の事前復興講演会で、兵庫県南あわじ市福良地区の「失われない街」プロジェクトの話として紹介頂いていたので、絶好の機会でした。

 会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。
会場を後にして、営業が再開されている道の駅狼煙で昼食をとった後、岬自然歩道を登って禄剛崎灯台から隆起している海岸線も一望しました。
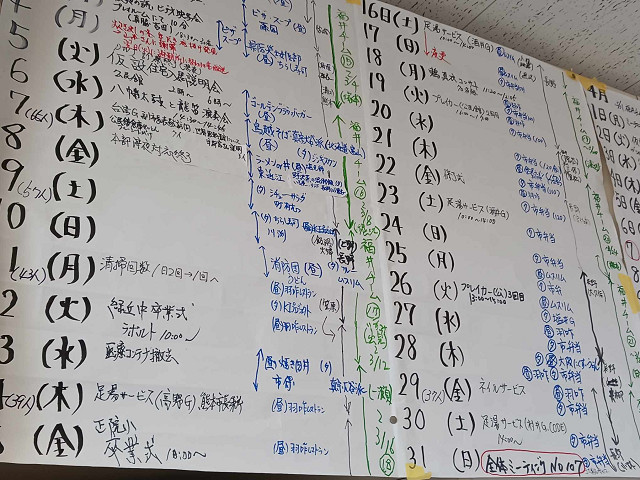
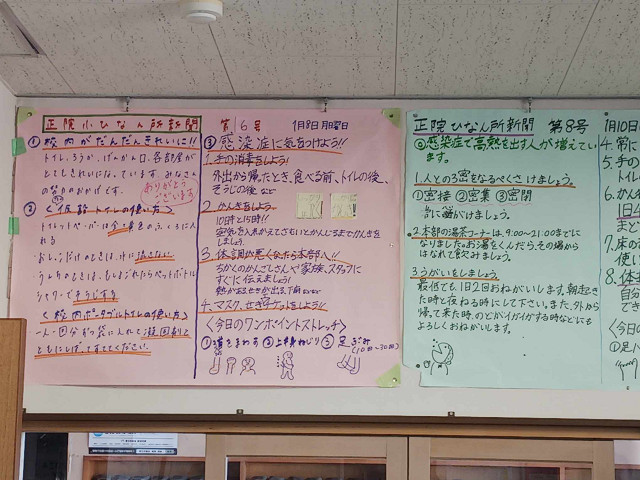
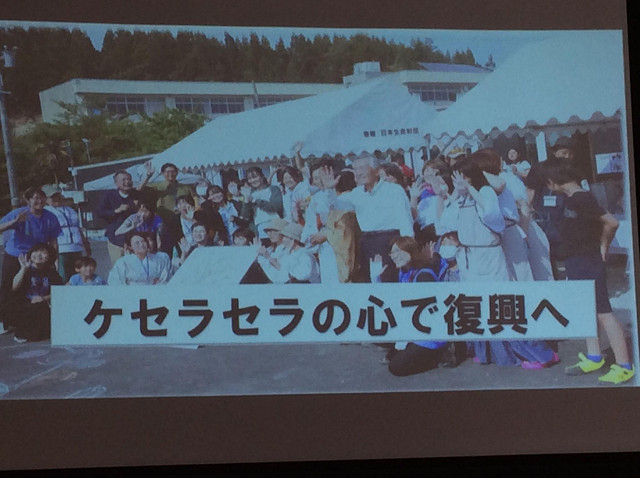
 若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。
若山公民館では、PWJ珠洲事務所の木下さんの案内で9月23日の大水害によって避難されたお二人の方とお話しする機会を頂きました。
 津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。
津波被害の大きかった宝立地区では、液状化によるマンホールなどもそのまま放置されていたり、ほとんど手のついてない沿岸部の復興は見通せない状況です。


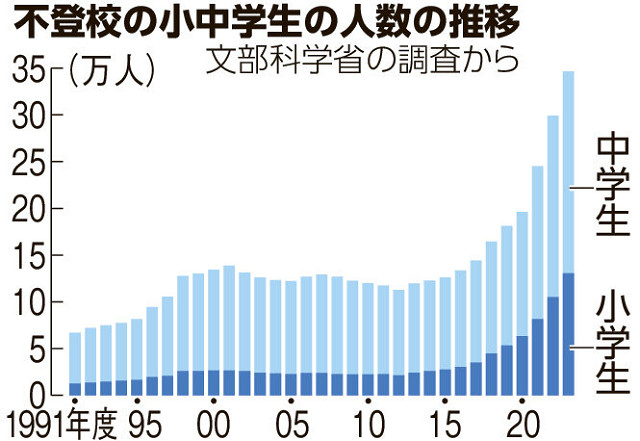 年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。
年30日以上登校せず、「不登校」とされた小中学生が、昨年度は過去最多の34万6482人に上ったことが文部科学省の調査で明らかになりました。
 東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。
東北電力女川原発2号機は、10月29日に再稼働しました。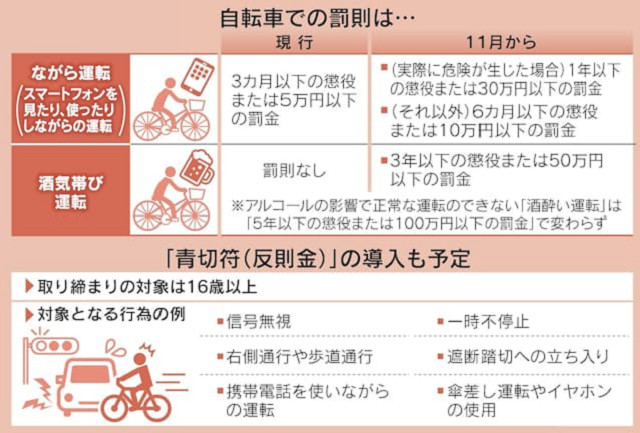 改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。
改正道路交通法が11月1日に施行され、酒気帯び運転が罰則付きの違反となり、スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」の罰則は強化されるなど、自転車の危険な行為が厳罰化されます。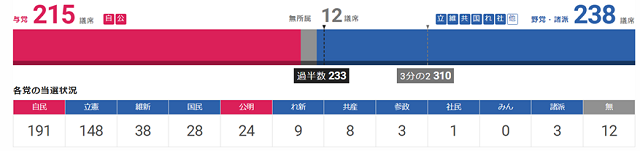 石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。
石破自民党総裁は、首相就任から8日という「戦後最短」の解散に打って出て、衆院選では自らが目標とした自公与党で過半数を割り込みました。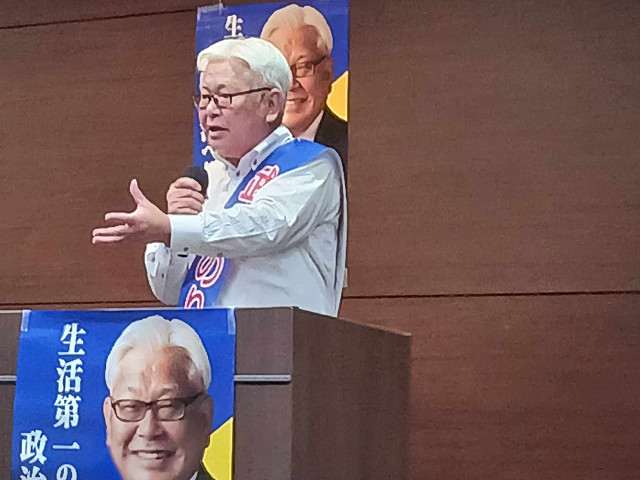
 今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。
今朝の高知新聞に、明日に投票日を迎えた衆院選において、近年50%台に低迷している県内投票率の行方について取り上げた記事がありました。
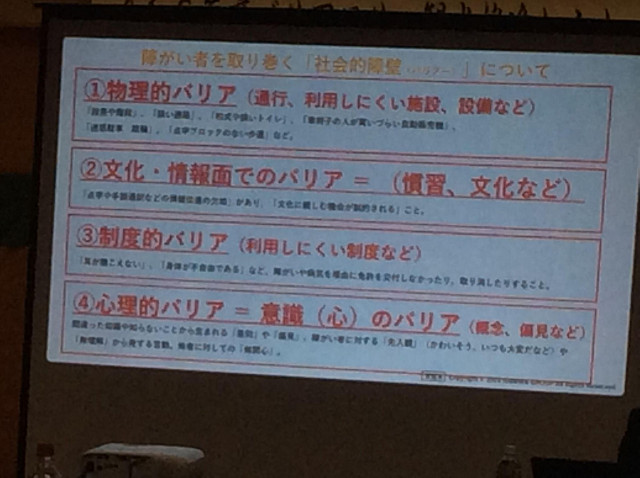


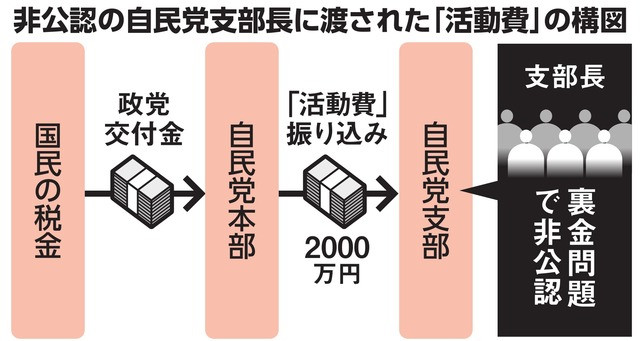 今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。
今朝の新聞報道で、目に入った見出「裏金非公認側に2000万円 自民党本部から支部へ 公認候補と同額」には、驚くばかりです。 衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。
衆院選も終盤という中で、県内若者100人に尋ねた「将来の不安・政治に臨むこと」の一位は、「南海トラフ」で、次いで、「仕事」「結婚」だったと今朝の高知新聞一面の記事にありました。


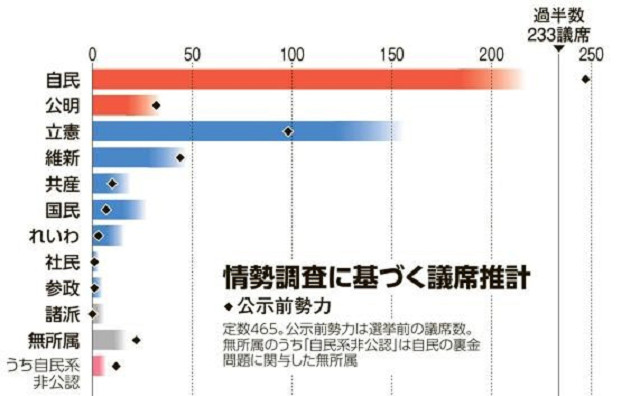
 昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。
昨日は、朝から衆院選高知一区の武内のりお候補の応援のため、候補者カーに同乗し、街頭からのお願いに回りました。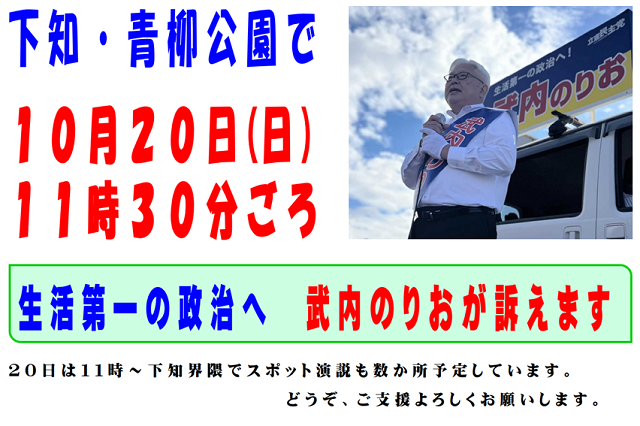 今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。
今回の解散総選挙の引き金となったきっかけは、誰もが「裏金問題」と「旧統一協会問題」が大きいと思われているのではないでしょうか。
 衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。
衆院選公示後の今朝の朝日新聞の一面(天声人語)「まだ覚えていますか」と34面の「私らは枝っこの枝っこ」の記事が、私らに、忘れたらいけないことがあるとのメッセージを突きつけています。
 県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、
県議会9月定例会閉会日に、日本共産党会派と県民の会で提出した「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書議案について、県民の会を代表して、 昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。
昨夕のニュース速報には、驚き・喜びと同時に、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞の持つ意味の大きさを世界の核保有国のリーダーと核兵器禁止条約に署名しない我が国のリーダーがしっかりと受け止めて欲しいと思ったところです。

 58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。
58年前の一家4人殺害事件で死刑が確定していた袴田巌さん(88歳)の再審で、静岡地裁が言い渡した無罪判決に対して、検察側が昨日、控訴しないこと明らかにし、無罪が確定しました。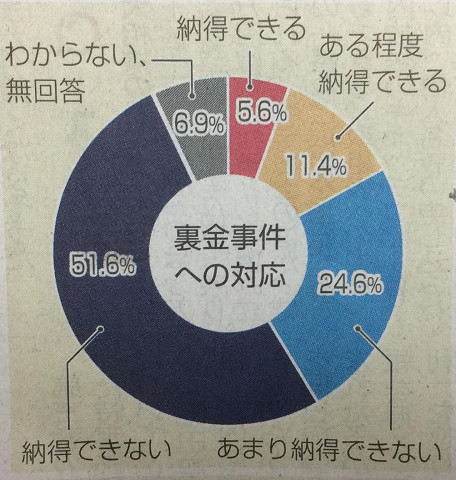
 高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。
高知新聞社県民電話調査などによると、県民の76%が自民党の「裏金対応に納得せず」と回答しています。
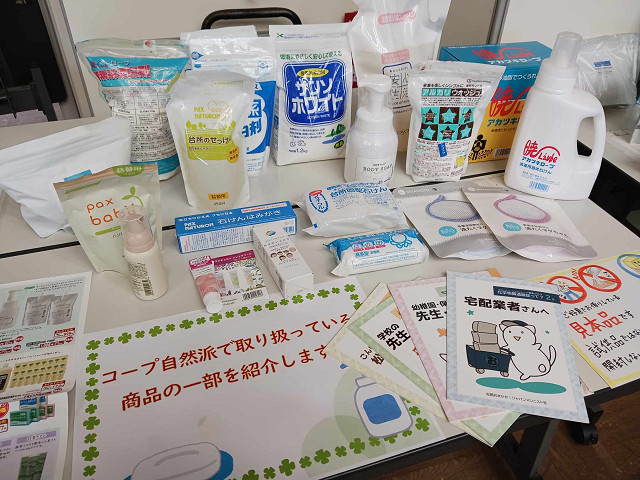

 10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。
10月2日の一問一答による質疑の答弁のテープ起こしができましたので、掲載しておきます。 自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。
自民党総裁選で、最後は、「高市よりましな石破」という選択肢が、解散総選挙を見据えた自民党内で幅を利かせて、石破総裁が誕生し、首相となりました。

 県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。
県議会9月定例会も、一括質問は本日終了し、明日からは一問一答による質問戦が始まります。 9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。
9月26日、静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌さんに静岡地裁の再審公判で「無罪」が言い渡されました。 昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。
昨日の自民党総裁選は、9名の候補者という多数乱立・乱戦の結果、石破氏と高市氏の決選投票で石破氏が5度目の挑戦で自民党総裁となりました。



 本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。
本日から、9月定例会の質問戦が始まりました。






 復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。
復興への厳しい道のりを歩まれている能登半島地震の被災地が昨日、記録的な豪雨に見舞われ、珠洲市で1人が亡くなり、同市と輪島市、能登町でも行方不明者が相次いでいます。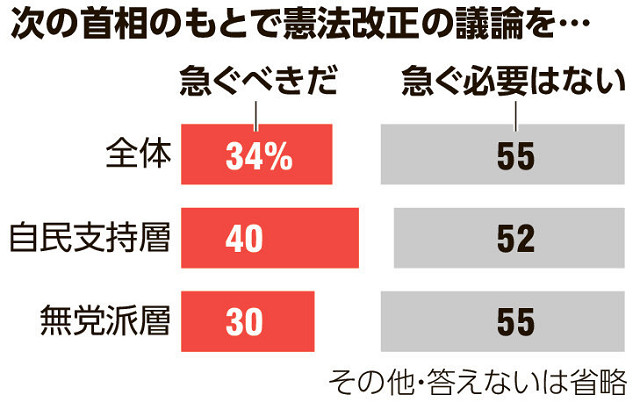 自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。
自民党総裁選では、国民が裏金問題や旧統一教会との組織的関係の真相究明については、言及しないものの、それぞれに支持層でも半数が「急ぐ必要はない」と回答しているのに自衛隊の明記など改憲を打ち出しています。 県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。
県議会9月定例会が昨日開会し、執行部は24年度一般会計補正予算案49億3800万円など50議案を提出ました。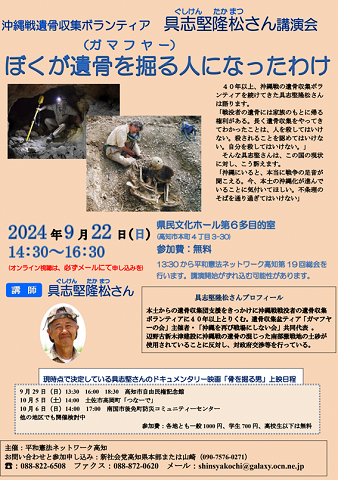
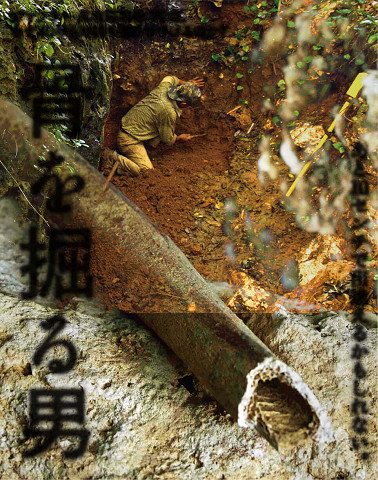 今日から、県議会9月定例会が開会します。
今日から、県議会9月定例会が開会します。 自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。
自民党総裁選挙で裏金問題こそ、真相究明ではないが、今になって「政治改革」などと言って触れられてはいるが、旧統一教会との関係について言及する候補者は誰一人いません。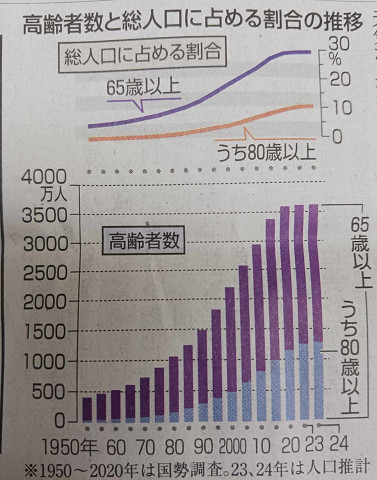
 今日は、「敬老の日」です。
今日は、「敬老の日」です。 岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。
岸田首相が自民党総裁選の不出馬を表明して以降、総裁選は過去最多の9人が立候補する多数乱戦が展開されています。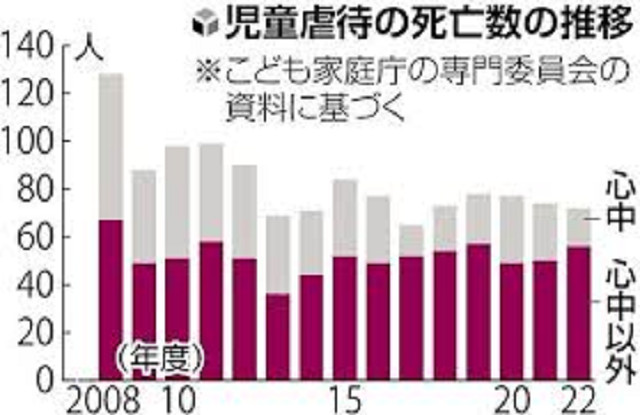
 こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。
こども家庭庁が昨日、2022年度に虐待を受けて亡くなった子どもは72人だったとする検証結果を発表しました。 今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。
今朝の朝日新聞に、全国の16原発30キロ圏の156自治体の首長に行ったアンケート結果が記事になっていました。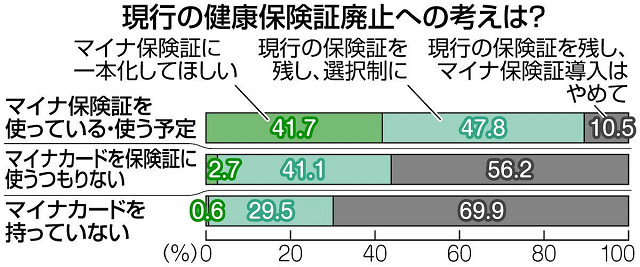 マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。
マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」への本格移行、現行保険証の廃止が12月2日に迫ってきました。
 昨日の午後は、丸亀市の就労継続支援B型事業所たんぽぽに通う方々の人生について話を聞き、その実体験をもとに苦労や生きづらさをテーマに創作された作品の演劇公演を鑑賞してきました。
昨日の午後は、丸亀市の就労継続支援B型事業所たんぽぽに通う方々の人生について話を聞き、その実体験をもとに苦労や生きづらさをテーマに創作された作品の演劇公演を鑑賞してきました。
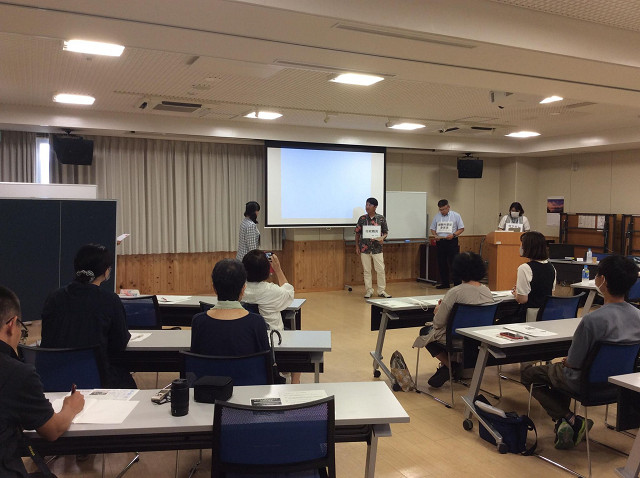




 9月1日夜のNHKスペシャル「巨大地震“軟弱地盤”新たな脅威」で、活断層の地震として過去最大規模だった能登半島地震における木造や鉄筋コンクリート造の建物が数多く倒壊したことの背景として、科学者は“軟弱地盤”によって揺れが何倍にも増幅された可能性を指摘されていました。
9月1日夜のNHKスペシャル「巨大地震“軟弱地盤”新たな脅威」で、活断層の地震として過去最大規模だった能登半島地震における木造や鉄筋コンクリート造の建物が数多く倒壊したことの背景として、科学者は“軟弱地盤”によって揺れが何倍にも増幅された可能性を指摘されていました。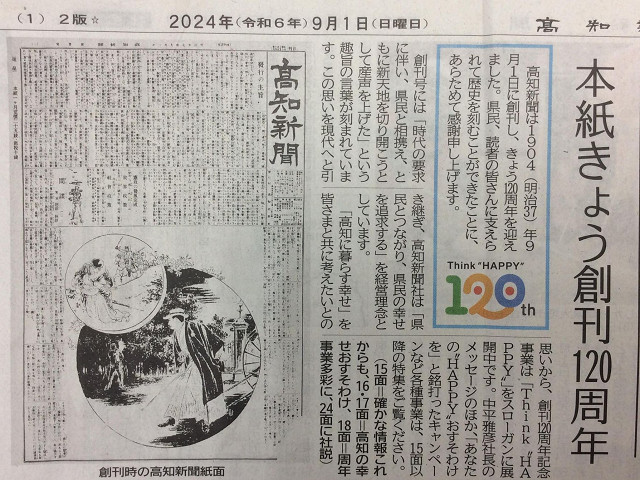 高知新聞は、昨日9月1日、創刊120年を迎えました。
高知新聞は、昨日9月1日、創刊120年を迎えました。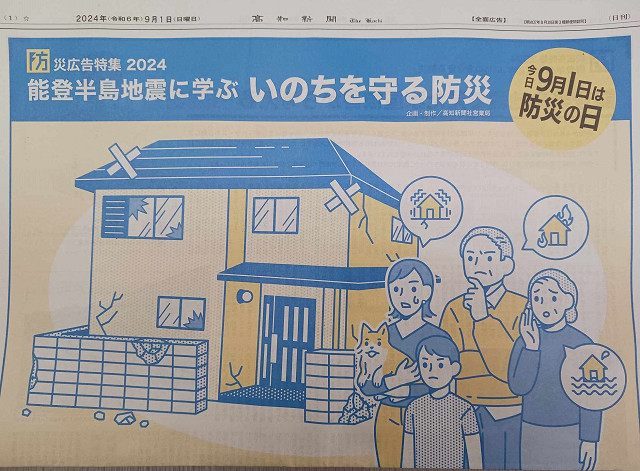 今日9月1日は、101年前の関東大震災にちなんだ「防災の日」です。
今日9月1日は、101年前の関東大震災にちなんだ「防災の日」です。
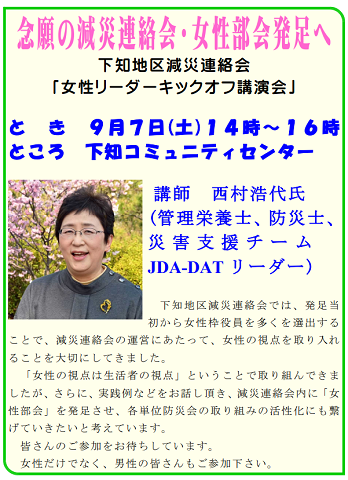 台風10号の通過に伴う下知コミュニティセンターの避難所開設も今朝終了し、市役所の職員さん、センター長とともに最終の確認をさせていただきました。
台風10号の通過に伴う下知コミュニティセンターの避難所開設も今朝終了し、市役所の職員さん、センター長とともに最終の確認をさせていただきました。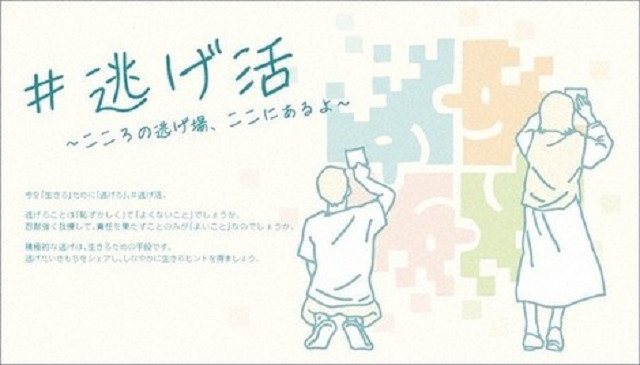 毎年のように、夏休み明けを前にしたこの時期、子ども・若者への自殺防止の呼びかけがいろいろな形で行われているが、今年は長引く台風10号騒動の中で、そんな声かけが届いてないのではないかと心配します。
毎年のように、夏休み明けを前にしたこの時期、子ども・若者への自殺防止の呼びかけがいろいろな形で行われているが、今年は長引く台風10号騒動の中で、そんな声かけが届いてないのではないかと心配します。



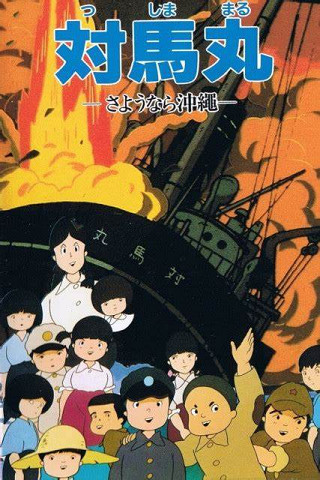
 80年前の8月22日、学童疎開船「対馬丸」が那覇港から長崎に向かう途中、鹿児島県悪石島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しました。
80年前の8月22日、学童疎開船「対馬丸」が那覇港から長崎に向かう途中、鹿児島県悪石島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しました。

 大型台風10号は、高知県にとっては最悪のコースを辿りながら、接近しつつあります。
大型台風10号は、高知県にとっては最悪のコースを辿りながら、接近しつつあります。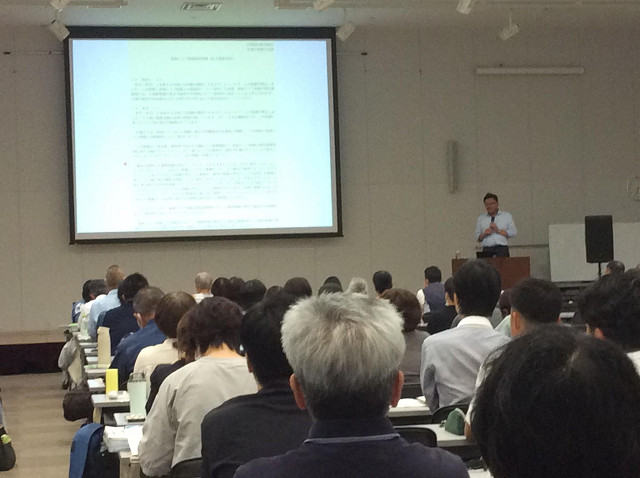
 19日、20日と連続で、この間重点的に取り組んできた二つのテーマで連続しての学びの場に参加してきました。
19日、20日と連続で、この間重点的に取り組んできた二つのテーマで連続しての学びの場に参加してきました。 岸田自民党総裁の突然の再選不出馬表明以降の話題は自民党総裁選、そして解散総選挙の日程などの取りざたに終始しています。
岸田自民党総裁の突然の再選不出馬表明以降の話題は自民党総裁選、そして解散総選挙の日程などの取りざたに終始しています。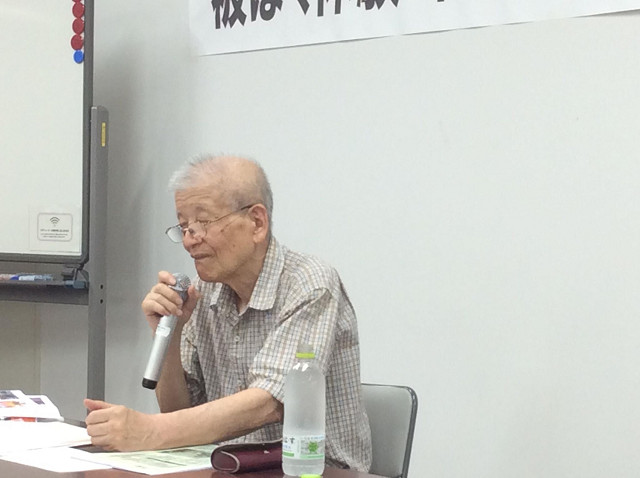






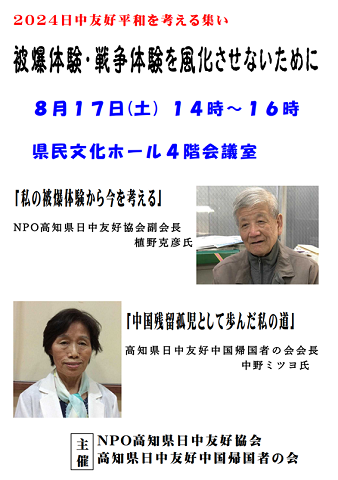 もう一つ、そのような機会になればと思う「2024日中友好平和を語る集い」が本日開催されますので、ご案内します。
もう一つ、そのような機会になればと思う「2024日中友好平和を語る集い」が本日開催されますので、ご案内します。

 明日、敗戦の日に「8.15平和と人権を考える集会」で、映画「戦雲」が上映されます。
明日、敗戦の日に「8.15平和と人権を考える集会」で、映画「戦雲」が上映されます。
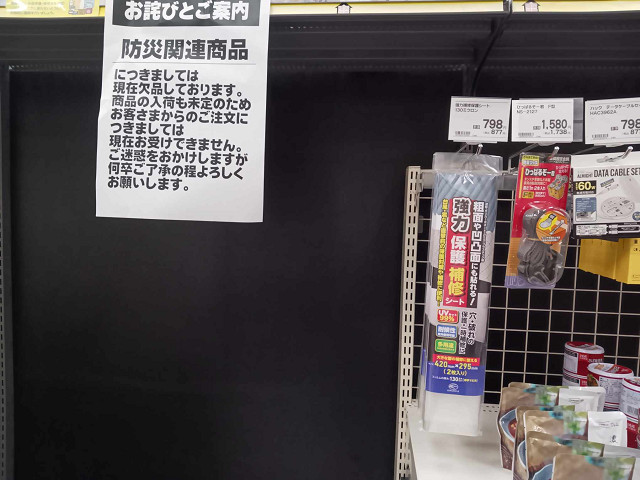 昨日は、東京から帰省した息子とともに、朝から墓掃除・参りのために土佐久礼に行くつもりでしたが、いろいろと話し合って、臨時情報も出ていることだし、もしもの時の対応もあるので、見送ることにしました。
昨日は、東京から帰省した息子とともに、朝から墓掃除・参りのために土佐久礼に行くつもりでしたが、いろいろと話し合って、臨時情報も出ていることだし、もしもの時の対応もあるので、見送ることにしました。
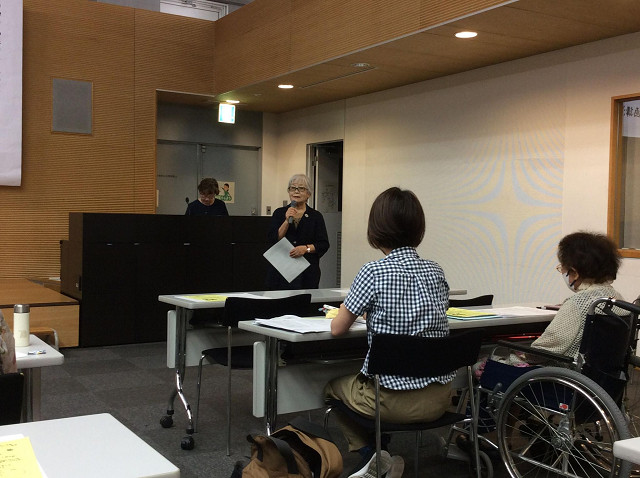
 昨日は、よさこい祭りの喧噪の中を男女共同参画センター「ソーレ」へと自転車で向かい、歴史研究者公文豪氏講演会に参加してきました。
昨日は、よさこい祭りの喧噪の中を男女共同参画センター「ソーレ」へと自転車で向かい、歴史研究者公文豪氏講演会に参加してきました。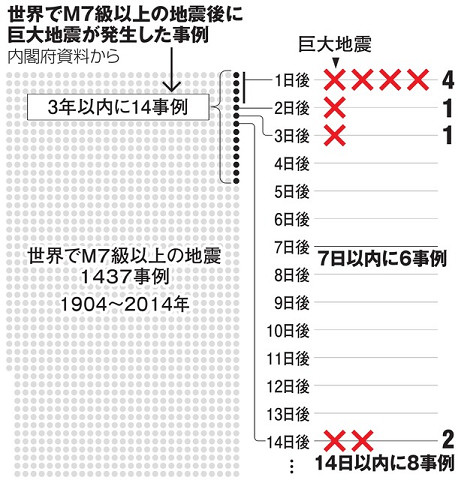 2016年に下知地区減災連絡会で石巻市を訪問した時、同行取材され、下知にもお越しになり、昭和小や下知コミセンで取材頂いた朝日新聞編集委員の佐々木英輔氏が、今朝の朝日新聞に南海トラフ地震臨時情報に関する記事を書かれていました。
2016年に下知地区減災連絡会で石巻市を訪問した時、同行取材され、下知にもお越しになり、昭和小や下知コミセンで取材頂いた朝日新聞編集委員の佐々木英輔氏が、今朝の朝日新聞に南海トラフ地震臨時情報に関する記事を書かれていました。 昨8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市南郷町で最大震度6弱を観測し、震源は宮崎県の東南東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.1でした。
昨8日午後4時42分ごろ、宮崎県沖の日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市南郷町で最大震度6弱を観測し、震源は宮崎県の東南東30キロ付近で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.1でした。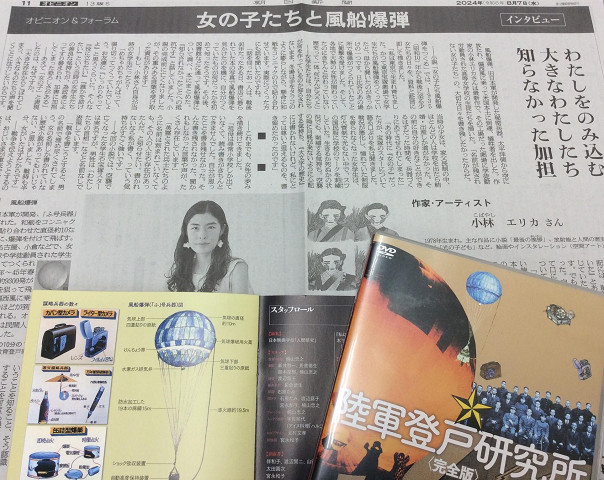 7日付け朝日新聞「オピニオン面」のインタビュー記事の見出しに「風船爆弾」との文字を眼にしました。
7日付け朝日新聞「オピニオン面」のインタビュー記事の見出しに「風船爆弾」との文字を眼にしました。 昨日広島では、被爆から79年目を迎えました。
昨日広島では、被爆から79年目を迎えました。 米国が広島に原爆を投下して、きょうで79年になります。
米国が広島に原爆を投下して、きょうで79年になります。


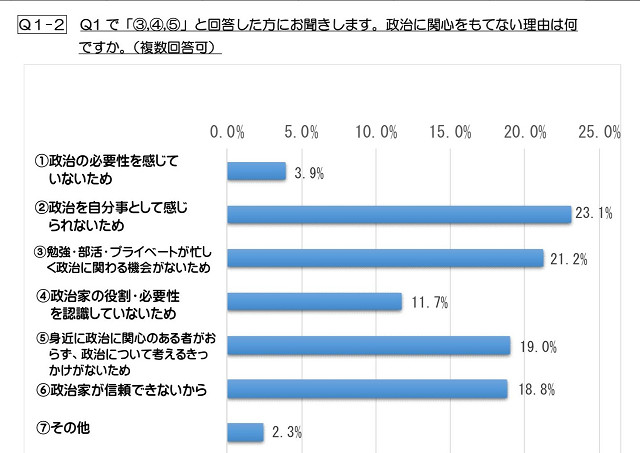
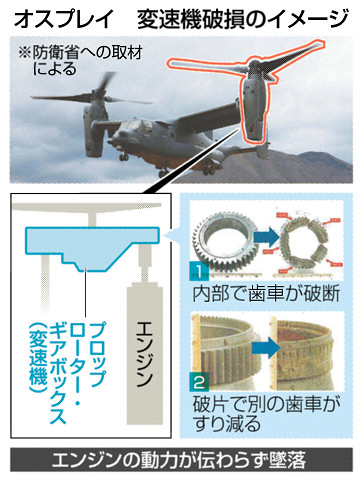
 鹿児島県屋久島沖で昨年11月、垂直離着陸輸送機CV22オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故で、米空軍は昨日事故調査報告書を公表しました。
鹿児島県屋久島沖で昨年11月、垂直離着陸輸送機CV22オスプレイが墜落し、乗員8人全員が死亡した事故で、米空軍は昨日事故調査報告書を公表しました。 7月26日、原子力規制委員会が、日本原子力発電(原電)の敦賀原発2号機は、原子炉建屋の直下に活断層がある恐れが否定できないと結論づけ、再稼働の条件になる新規制基準に適合しないとの判断を示しました。
7月26日、原子力規制委員会が、日本原子力発電(原電)の敦賀原発2号機は、原子炉建屋の直下に活断層がある恐れが否定できないと結論づけ、再稼働の条件になる新規制基準に適合しないとの判断を示しました。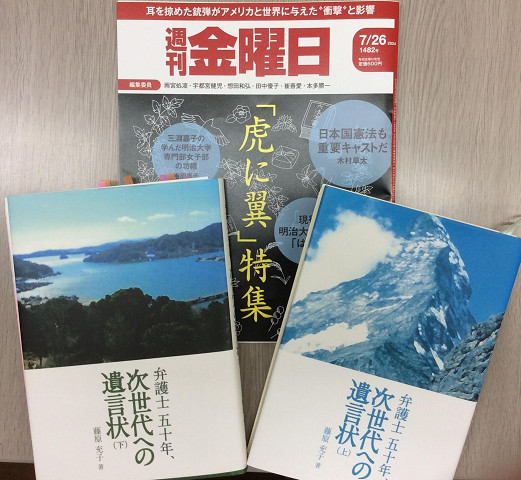 かつて、NHKの朝ドラを見ることは久しくなかったが、「らんまん」を必要に迫られて見始めてから「ブギウギ」と時間のある時には、見てきました。
かつて、NHKの朝ドラを見ることは久しくなかったが、「らんまん」を必要に迫られて見始めてから「ブギウギ」と時間のある時には、見てきました。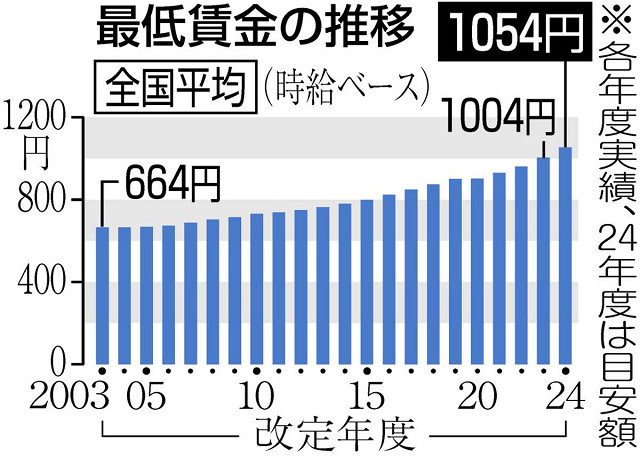
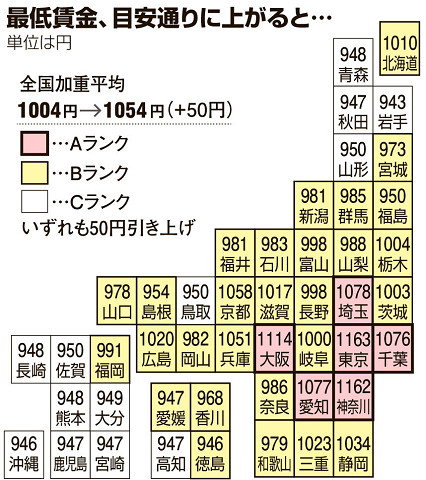 2024年度の最低賃金の全国平均が、現行より50円(約5%増)引き上げて1054円とする目安額を取りまとめられ、上げ幅は23年度の43円を上回り過去最大で、時給額も最高額となりました。
2024年度の最低賃金の全国平均が、現行より50円(約5%増)引き上げて1054円とする目安額を取りまとめられ、上げ幅は23年度の43円を上回り過去最大で、時給額も最高額となりました。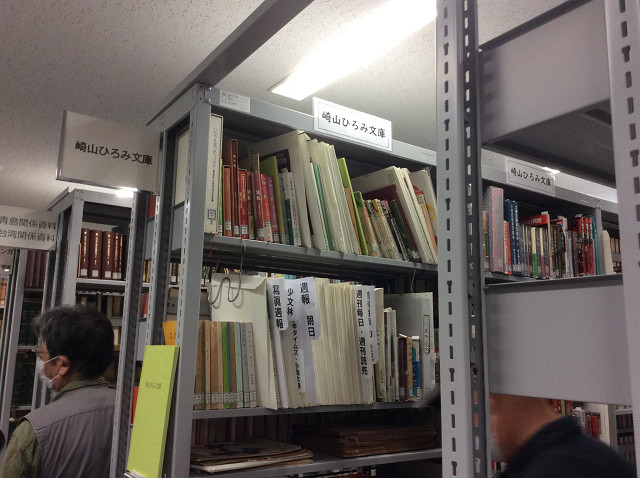
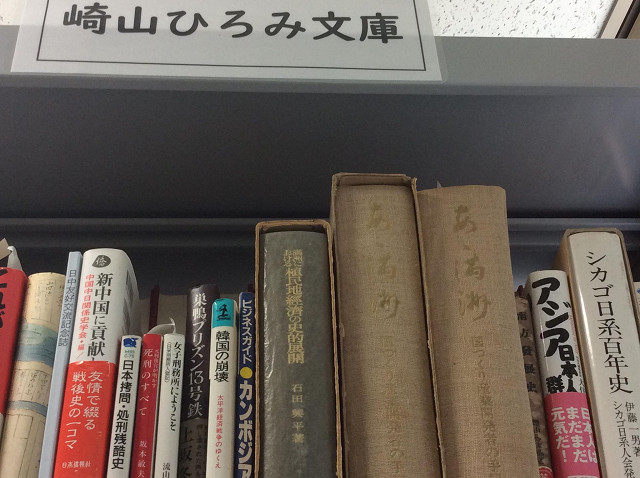
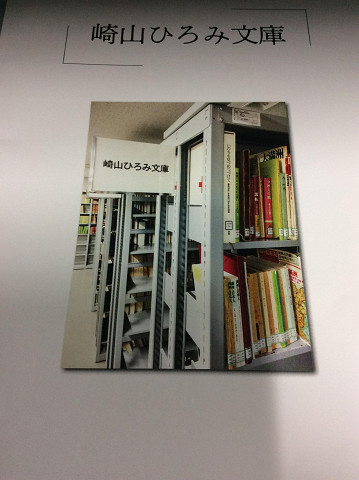
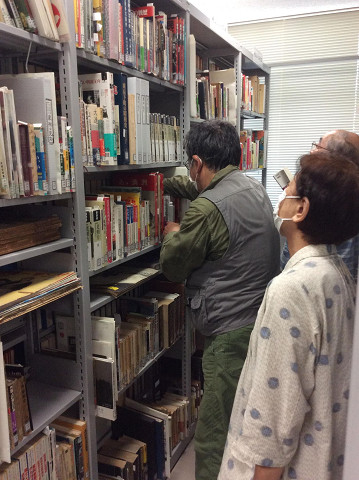
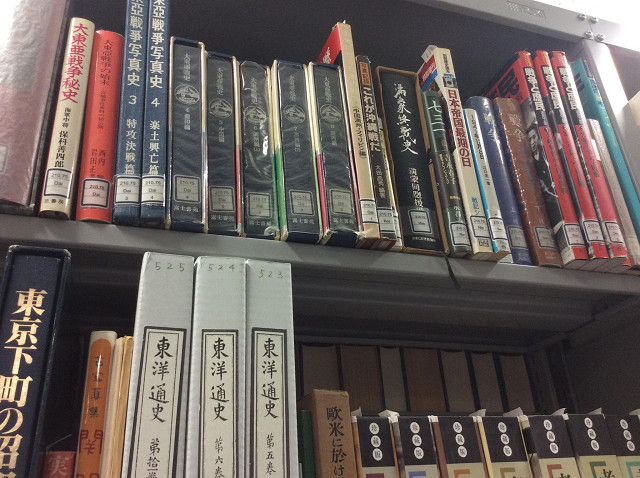
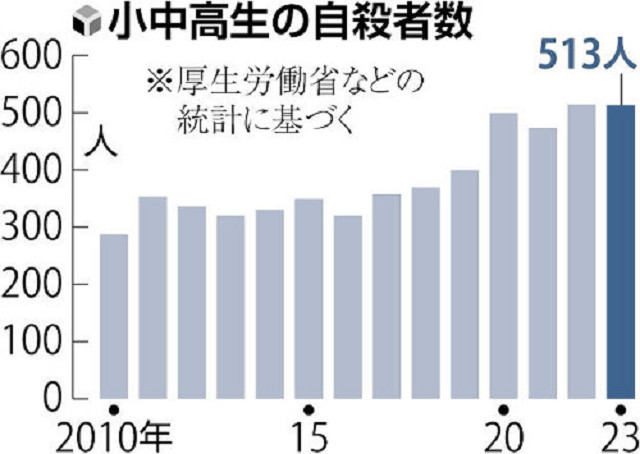 2023年の自殺者数のうち、小中高生の自殺者数は、過去最多だった22年の514人に次ぐ513人で、コロナ禍以降、子どもの自殺者数が高止まりしている状況にあることをこれまでも取り上げてきました。
2023年の自殺者数のうち、小中高生の自殺者数は、過去最多だった22年の514人に次ぐ513人で、コロナ禍以降、子どもの自殺者数が高止まりしている状況にあることをこれまでも取り上げてきました。

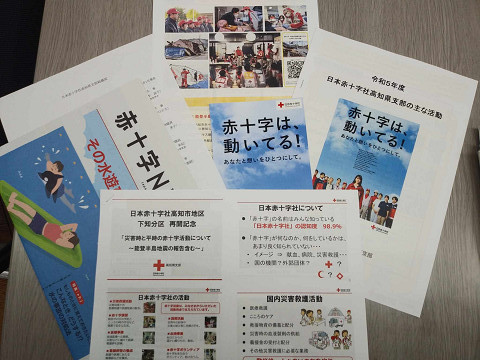
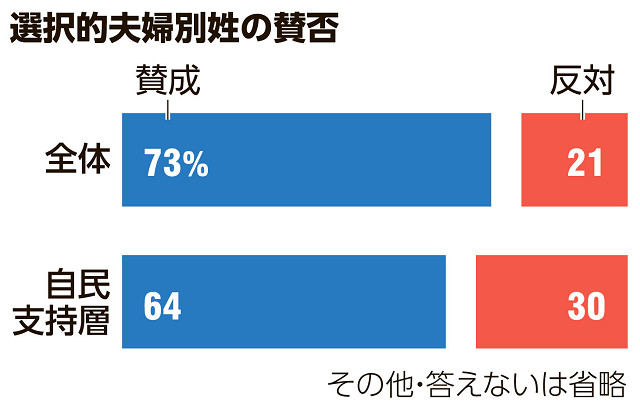 朝日新聞社が20、21日に実施した全国世論調査(電話)で、夫婦が名字を同じにするか別々にするか、法改正して自由に選べるようにする「選択的夫婦別姓」についての設問では、「賛成」が73%で、「反対」の21%を大きく上回ったことが、昨日報じられていました。
朝日新聞社が20、21日に実施した全国世論調査(電話)で、夫婦が名字を同じにするか別々にするか、法改正して自由に選べるようにする「選択的夫婦別姓」についての設問では、「賛成」が73%で、「反対」の21%を大きく上回ったことが、昨日報じられていました。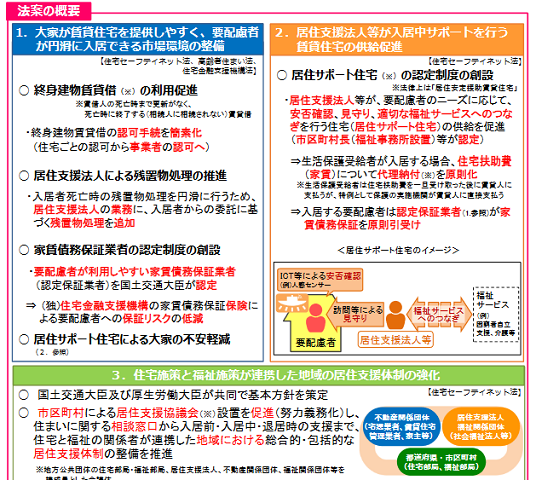 以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げてきましたが、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。
以前から、県内の住宅確保要配慮者の問題に関連して、幾度か県議会質問で取り上げてきましたが、「基本計画にあるようにセーフティーネット住宅の登録戸数のみを成果指標にするのではなく、取組の進め方をさらに具体化し、実効性を示すことが求められている」と指摘し、福祉と住宅をつなぐことを求めてきました。

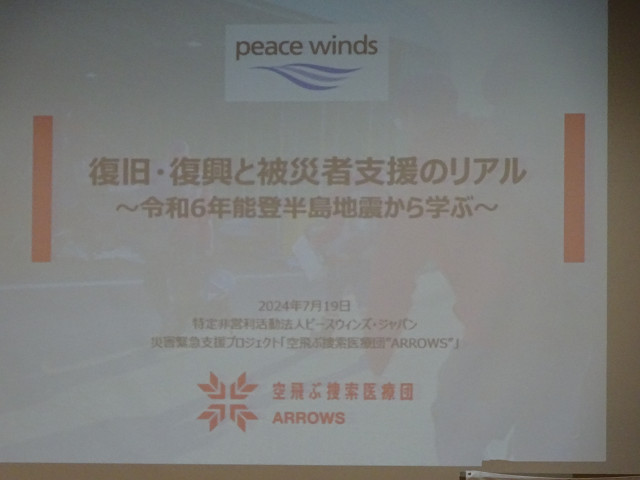
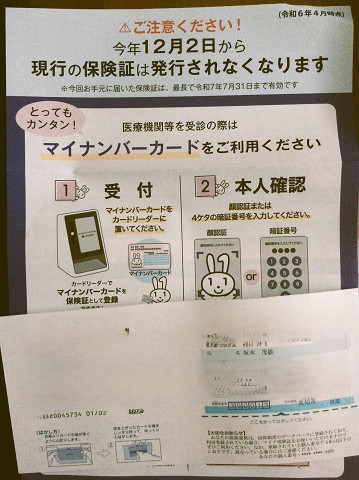
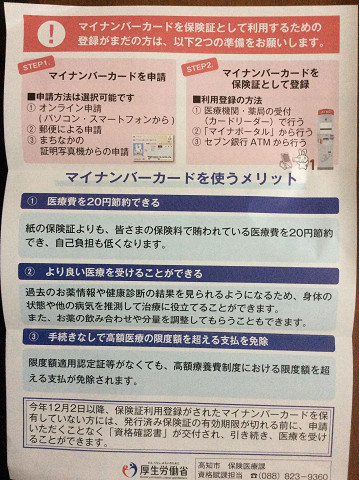

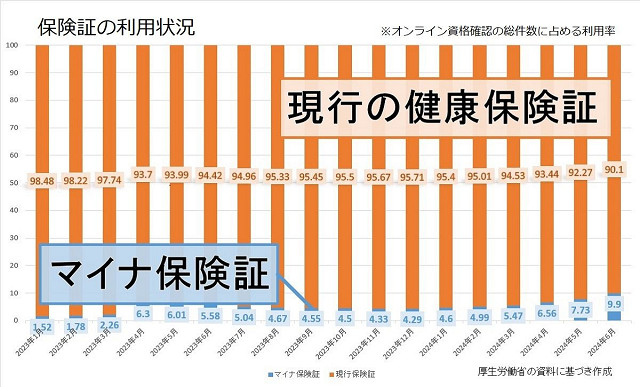
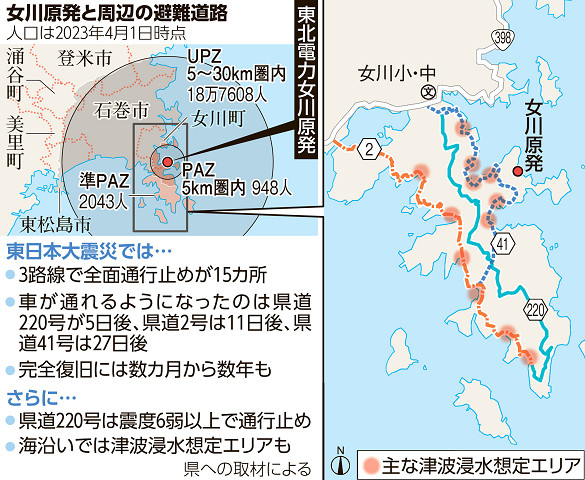
 東北電力が昨日、女川原発(宮城県)2号機の再稼働の時期を11月ごろに延期すると発表したことがマスコミで報じられました。
東北電力が昨日、女川原発(宮城県)2号機の再稼働の時期を11月ごろに延期すると発表したことがマスコミで報じられました。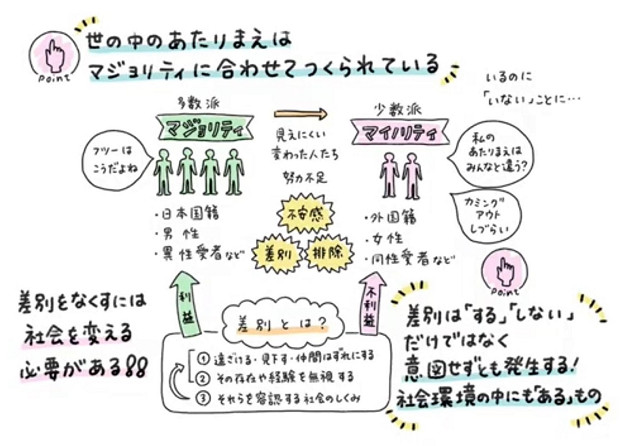 昨日は、「部落差別をなくする運動」強調旬間の高知市記念講演会で内田龍史さん(関西大学社会学部教授)の「部落差別の現在―部落解放への展望」を聴講させて頂きました。
昨日は、「部落差別をなくする運動」強調旬間の高知市記念講演会で内田龍史さん(関西大学社会学部教授)の「部落差別の現在―部落解放への展望」を聴講させて頂きました。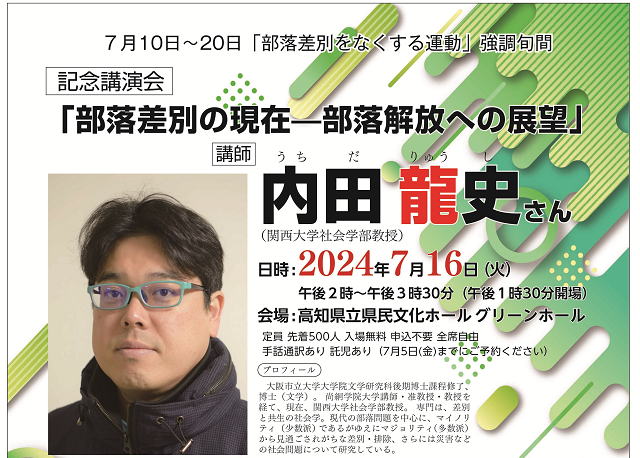 7月16日の今日、私もいよいよ「古希」となりました。
7月16日の今日、私もいよいよ「古希」となりました。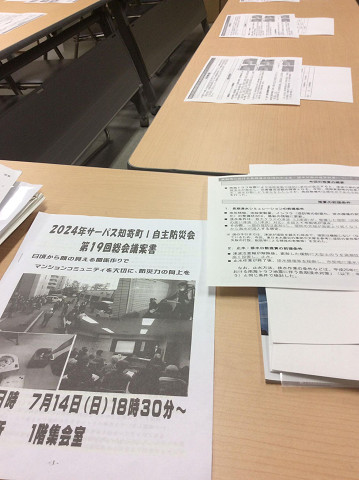
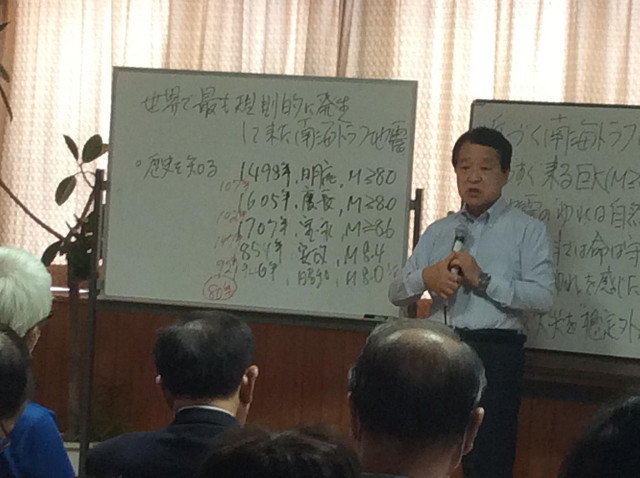


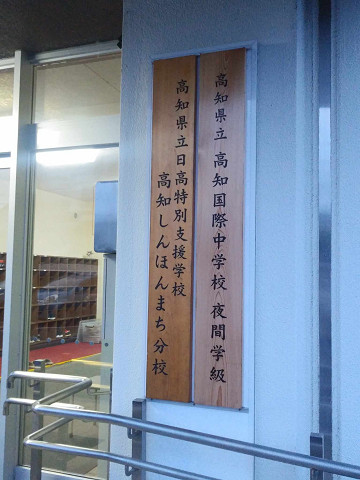
 7月10日に「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」のお誘いで、高知国際中学校夜間学級を訪問させて頂きました。
7月10日に「高知県の夜間中学生の声に学ぶ会」のお誘いで、高知国際中学校夜間学級を訪問させて頂きました。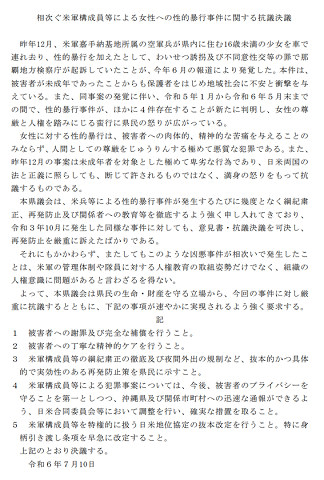
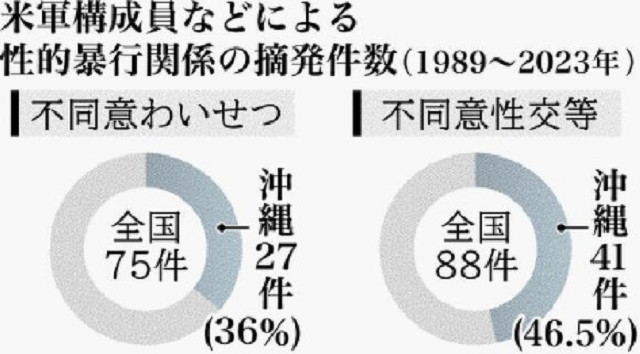 沖縄県内で相次いだ米兵による性暴行事件で、県議会は10日、米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全会一致で可決しました。
沖縄県内で相次いだ米兵による性暴行事件で、県議会は10日、米軍や日本政府に対する抗議決議や意見書を全会一致で可決しました。 6月定例会で、自民党派閥の裏金事件を受けた「政治資金の高い透明性の確保を求める意見書」が自民党・公明党から提出され、25人の賛成多数で可決されました。
6月定例会で、自民党派閥の裏金事件を受けた「政治資金の高い透明性の確保を求める意見書」が自民党・公明党から提出され、25人の賛成多数で可決されました。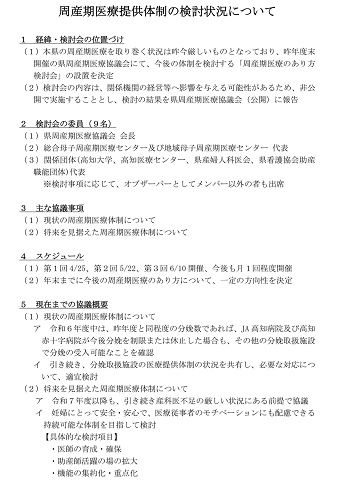
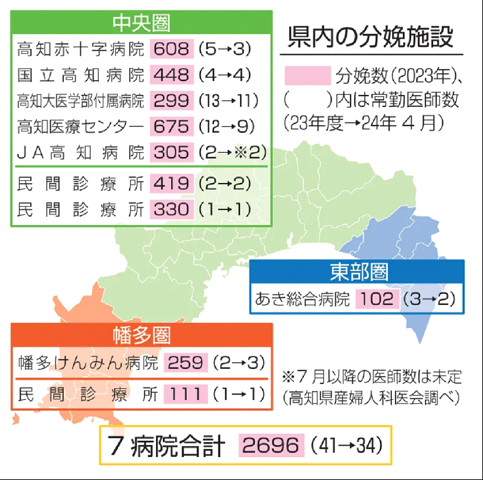 昨日は、県・市病院企業団議会が開催され、企業団議会議員協議会では、経常収支が3億1200万円の黒字となる2023年度の決算見込みが報告されました。
昨日は、県・市病院企業団議会が開催され、企業団議会議員協議会では、経常収支が3億1200万円の黒字となる2023年度の決算見込みが報告されました。




 昨日、県議会6月定例会は、2024年度一般会計補正予算など執行部提出の13議案と追加提出の人事議案2件を全会一致で可決、承認、同意するなどして閉会しました。
昨日、県議会6月定例会は、2024年度一般会計補正予算など執行部提出の13議案と追加提出の人事議案2件を全会一致で可決、承認、同意するなどして閉会しました。 熊本県南部の球磨川が氾濫し、流域を中心に67人(災害関連死2人含む)が亡くなり、2人が行方不明となった2020年7月豪雨災害は昨日、発生から4年を迎えました。
熊本県南部の球磨川が氾濫し、流域を中心に67人(災害関連死2人含む)が亡くなり、2人が行方不明となった2020年7月豪雨災害は昨日、発生から4年を迎えました。 能登半島地震が発生して、半年。
能登半島地震が発生して、半年。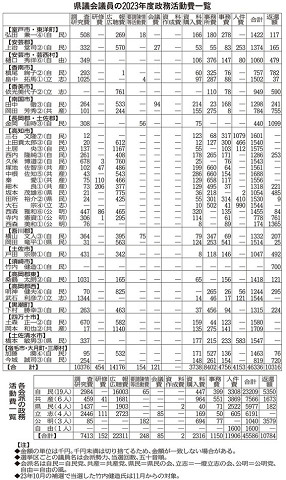 今朝の高知新聞朝刊を5時過ぎに読んで以来、7月1日付け高知新聞5面に、掲載されていた県議会議員の「政務活動費」の記事を見て、私の記載欄に誤りがあるのではないかと思い、もやもやしていたのですが、議会に出向いて確認したところ、誤りであったことが判明してホッとしました。
今朝の高知新聞朝刊を5時過ぎに読んで以来、7月1日付け高知新聞5面に、掲載されていた県議会議員の「政務活動費」の記事を見て、私の記載欄に誤りがあるのではないかと思い、もやもやしていたのですが、議会に出向いて確認したところ、誤りであったことが判明してホッとしました。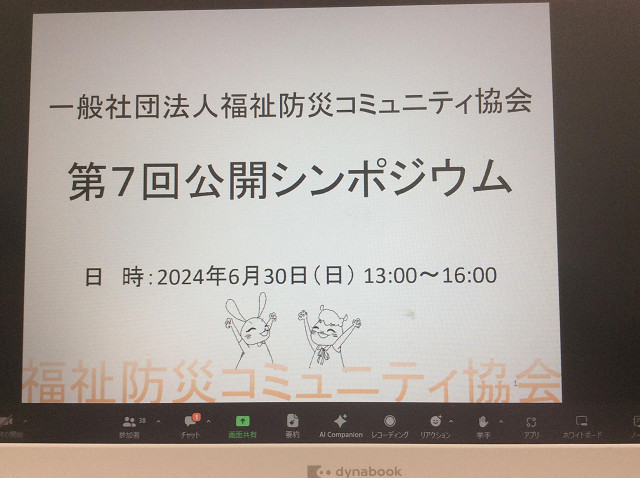
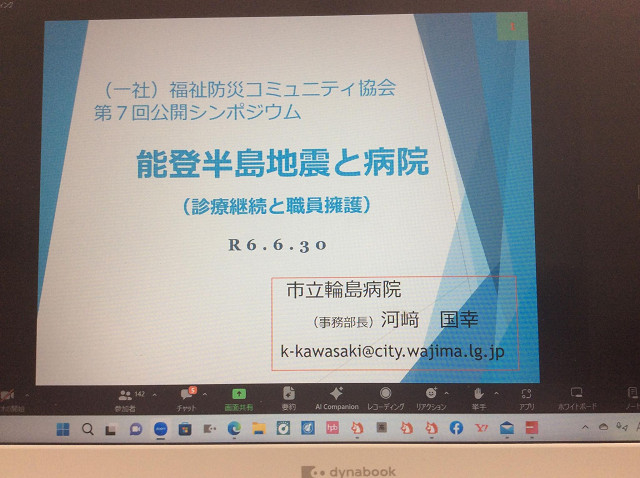

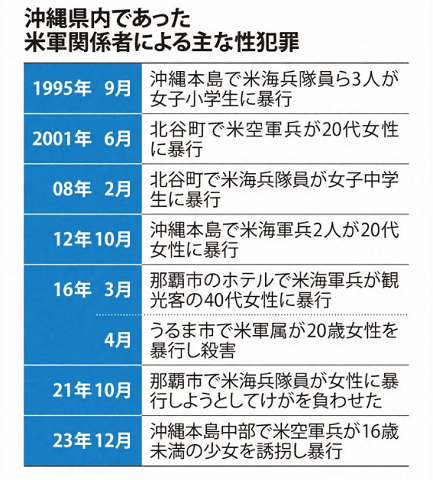
 25日には、昨年12月に米軍嘉手納基地所属の米空軍兵(25)が少女に性的暴行を加えたとして、不同意性交等罪などで起訴されていたことが明らかになっていたが、加えて昨28日、沖縄本島中部で女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、沖縄県警が5月に、在沖縄米海兵隊の男性隊員(21)を不同意性交等致傷容疑で逮捕していたことが判明しました。
25日には、昨年12月に米軍嘉手納基地所属の米空軍兵(25)が少女に性的暴行を加えたとして、不同意性交等罪などで起訴されていたことが明らかになっていたが、加えて昨28日、沖縄本島中部で女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、沖縄県警が5月に、在沖縄米海兵隊の男性隊員(21)を不同意性交等致傷容疑で逮捕していたことが判明しました。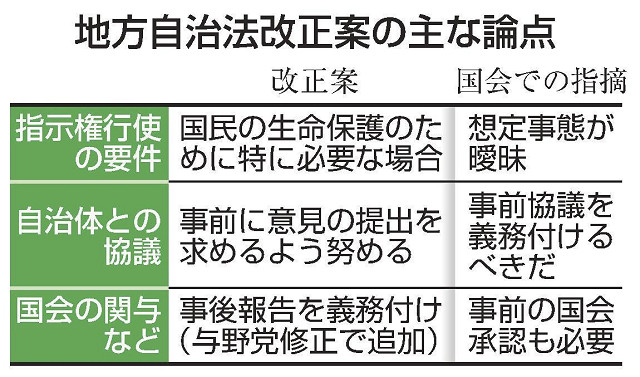

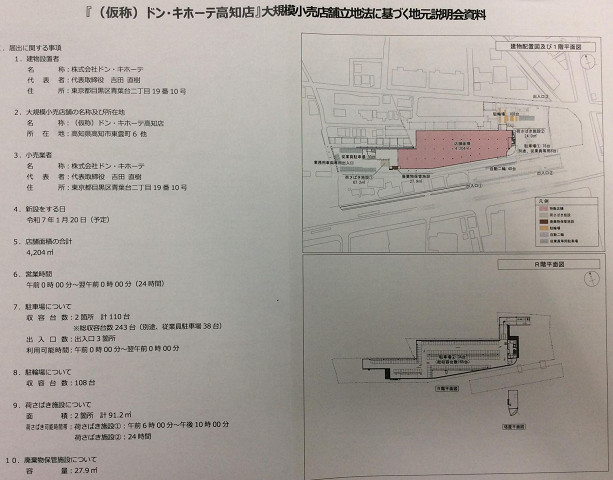
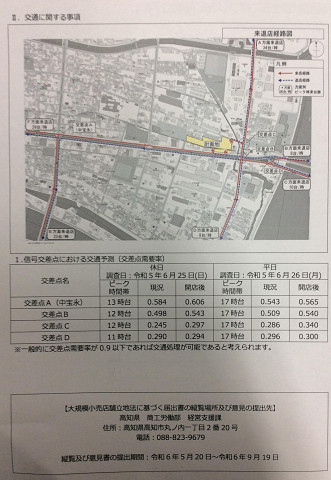




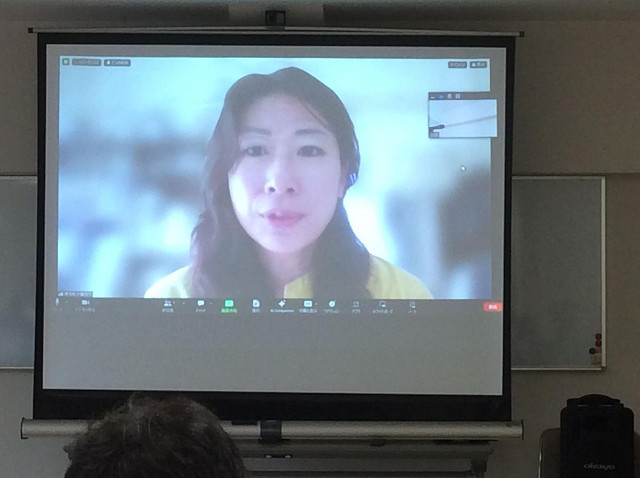
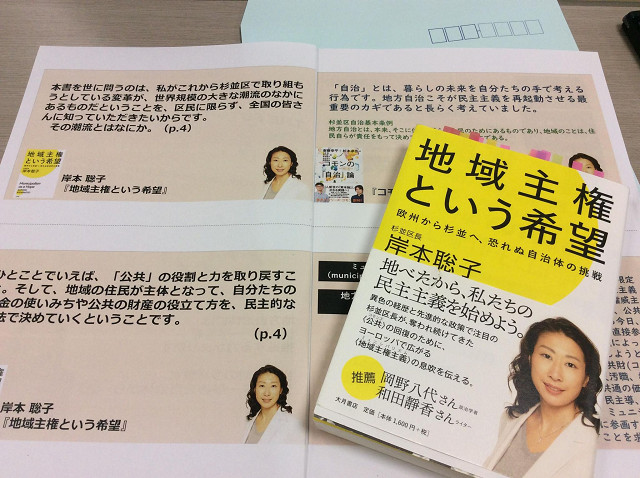



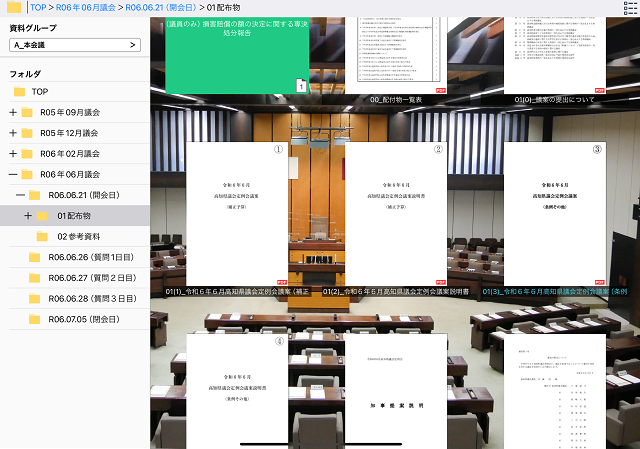
 明日は、理事をさせて頂いている高知県自治研究センターで岸本聡子東京都杉並区長を講師に「地域主権で公共の復権を」と題したセミナーが開催されます。
明日は、理事をさせて頂いている高知県自治研究センターで岸本聡子東京都杉並区長を講師に「地域主権で公共の復権を」と題したセミナーが開催されます。
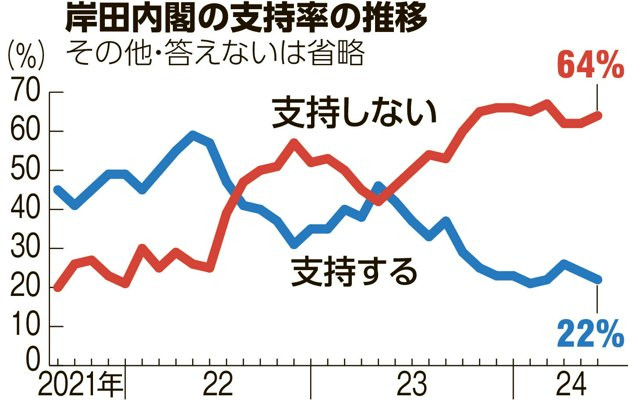




 学校給食法施行から70年となる今年、少子化対策につながる子育て世帯の負担軽減策として学校給食の無償化を求める声が大きい中、公立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化している自治体が、2023年9月時点で、全国の3割にあたる547あったことが文部科学省の調査で分かりました。
学校給食法施行から70年となる今年、少子化対策につながる子育て世帯の負担軽減策として学校給食の無償化を求める声が大きい中、公立小中学校の児童生徒全員の給食費を無償化している自治体が、2023年9月時点で、全国の3割にあたる547あったことが文部科学省の調査で分かりました。
 NHKの朝ドラ「虎に翼」では、日本初の女性弁護士一人であった三淵嘉子さんをモデルとした主人公が、戦後、女性に門戸の開かれた裁判官になり、裁判所長となっていく過程の中で、男女不平等の壁を少しずつ乗り越えていく姿に、励まされている視聴者も多いのではないかと思います
NHKの朝ドラ「虎に翼」では、日本初の女性弁護士一人であった三淵嘉子さんをモデルとした主人公が、戦後、女性に門戸の開かれた裁判官になり、裁判所長となっていく過程の中で、男女不平等の壁を少しずつ乗り越えていく姿に、励まされている視聴者も多いのではないかと思います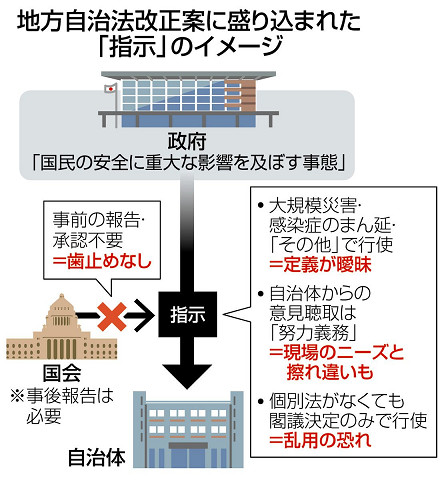 感染症のまん延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるとする特例を盛り込んだ地方自治法改悪案の参院審議が5日から始まっています。
感染症のまん延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるとする特例を盛り込んだ地方自治法改悪案の参院審議が5日から始まっています。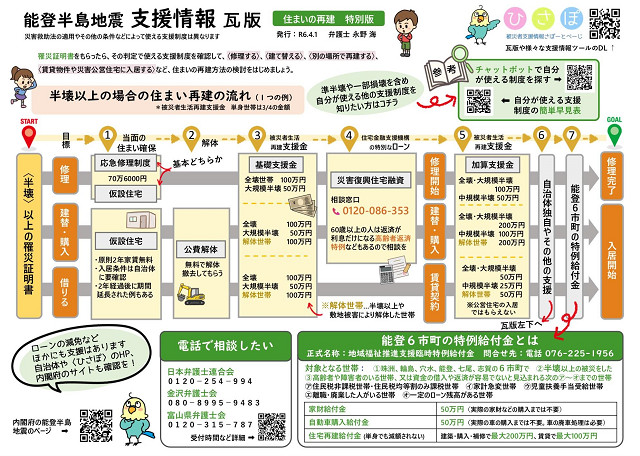
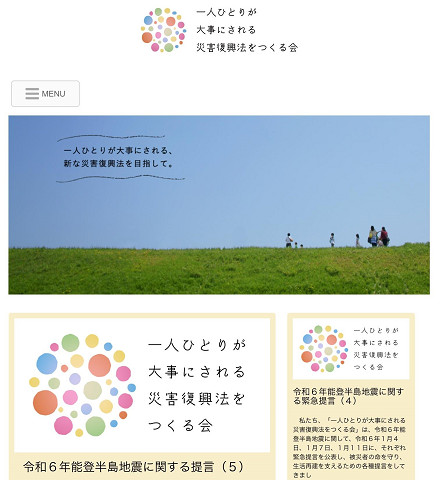

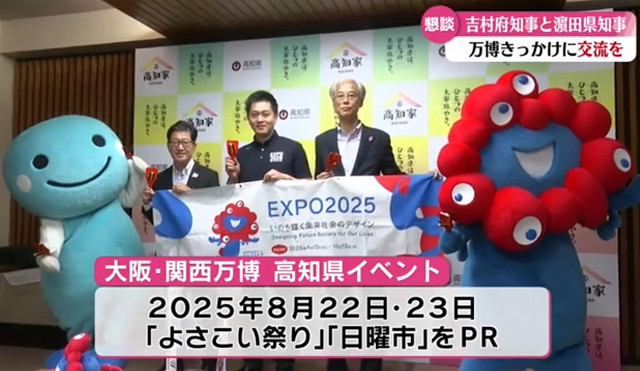 吉村大阪府知事が大阪・関西万博の盛り上げ要請のため、浜田高知県知事を5日に訪ねたことが報じられています。
吉村大阪府知事が大阪・関西万博の盛り上げ要請のため、浜田高知県知事を5日に訪ねたことが報じられています。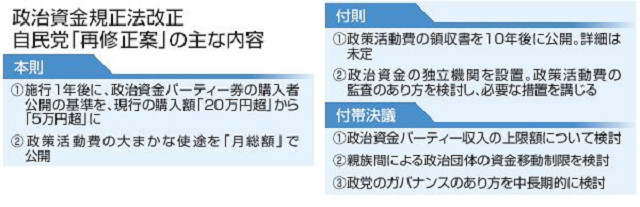 自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案を巡っては、自民党が示した再修正案に公明党と日本維新の会が合意し、今国会で成立を強行させようとしています。
自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案を巡っては、自民党が示した再修正案に公明党と日本維新の会が合意し、今国会で成立を強行させようとしています。




 この間の危機管理文化厚生委員会出先機関調査で、県東部地域の医療拠点である「あき総合病院」が、何としても存続させたい周産期医療体制の具体化に向けた課題の一つとして、院内助産を目指していることの話を聴かせて頂きました。
この間の危機管理文化厚生委員会出先機関調査で、県東部地域の医療拠点である「あき総合病院」が、何としても存続させたい周産期医療体制の具体化に向けた課題の一つとして、院内助産を目指していることの話を聴かせて頂きました。 昨日の高知新聞に、看護師を目指し、県内の専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク時の2015年度に800人を超えていた新入生は本年度435人と、9年でほぼ半減したとの報道がありました。
昨日の高知新聞に、看護師を目指し、県内の専門学校などに入学する生徒が近年、大幅に減少し、ピーク時の2015年度に800人を超えていた新入生は本年度435人と、9年でほぼ半減したとの報道がありました。 非常時に、国が自治体に必要な指示を出せるようにする地方自治法改悪案が、衆院総務委員会で与党や日本維新の会などの賛成で可決されました。
非常時に、国が自治体に必要な指示を出せるようにする地方自治法改悪案が、衆院総務委員会で与党や日本維新の会などの賛成で可決されました。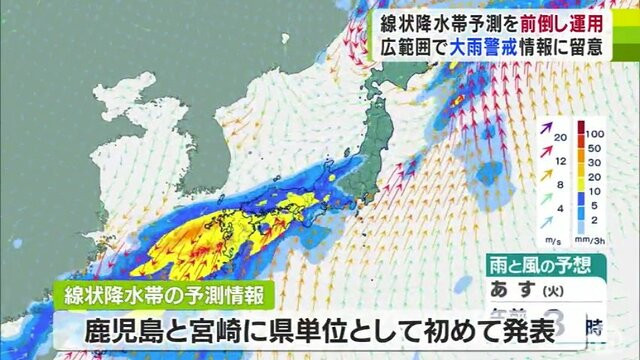
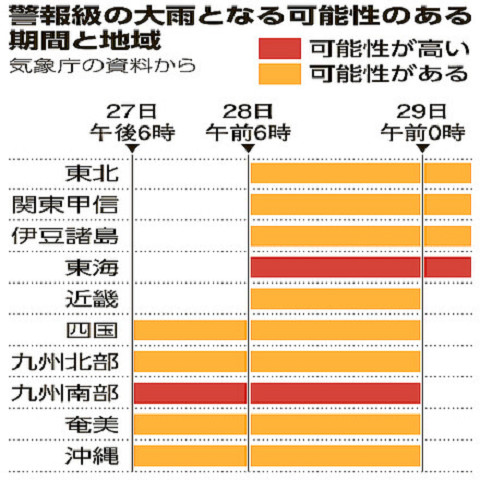 非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が昨夜から28日日中にかけて、宮崎と鹿児島(奄美地方をのぞく)の両県で発生する可能性があると、気象庁が27日午前に発表しました。
非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が昨夜から28日日中にかけて、宮崎と鹿児島(奄美地方をのぞく)の両県で発生する可能性があると、気象庁が27日午前に発表しました。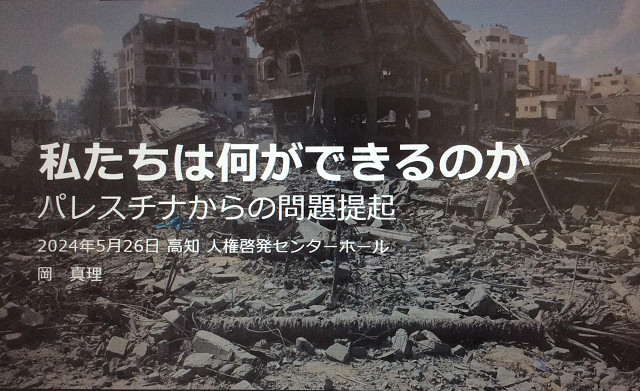
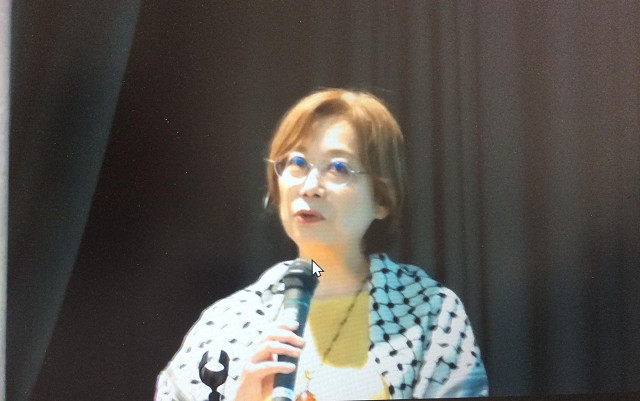
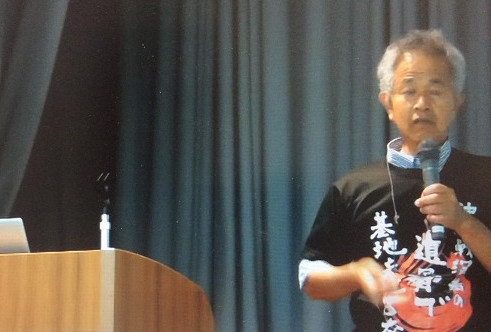
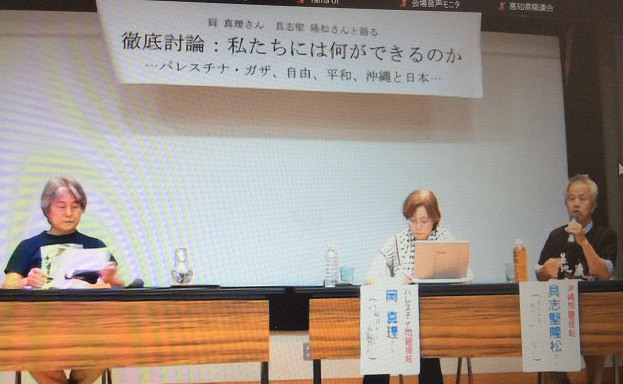
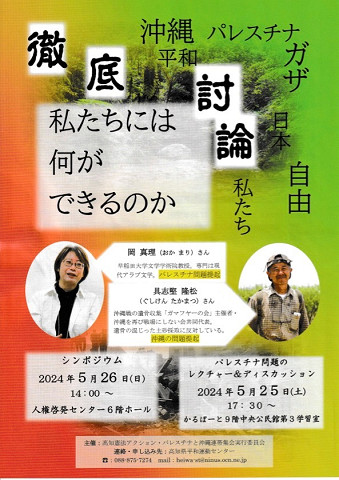 昨年10月7日のハマスによるイスラエルの抵抗以降、ガザにおけるジェノサイドは、もはや「皆殺し」状態をつくりだしています。
昨年10月7日のハマスによるイスラエルの抵抗以降、ガザにおけるジェノサイドは、もはや「皆殺し」状態をつくりだしています。

 ドン・キホーテの高知進出について、今朝の高知新聞で、「来年1月オープン計画 高知県に届け出 24時間営業」との見出しで、出店に関する届け出書を県に提出し、21日告示されたたことが報じられていました。
ドン・キホーテの高知進出について、今朝の高知新聞で、「来年1月オープン計画 高知県に届け出 24時間営業」との見出しで、出店に関する届け出書を県に提出し、21日告示されたたことが報じられていました。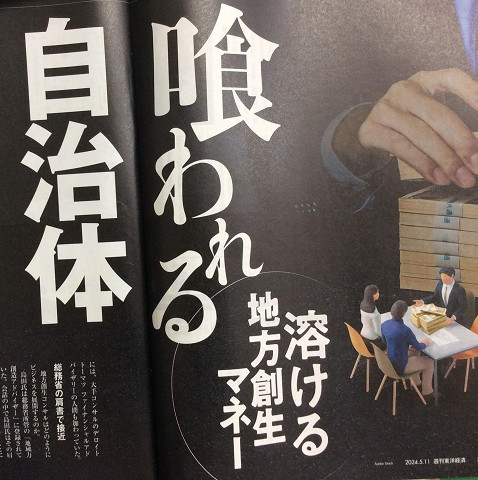 「地方創生が叫ばれて10年。実現できたという自治体はそう多くない。では、政府が流し込んだ膨大な『地方創生マネー』はどこへ溶けていったのか。」ということで、「週刊東洋経済」5月11日号は「喰われる自治体」との特集をしています。
「地方創生が叫ばれて10年。実現できたという自治体はそう多くない。では、政府が流し込んだ膨大な『地方創生マネー』はどこへ溶けていったのか。」ということで、「週刊東洋経済」5月11日号は「喰われる自治体」との特集をしています。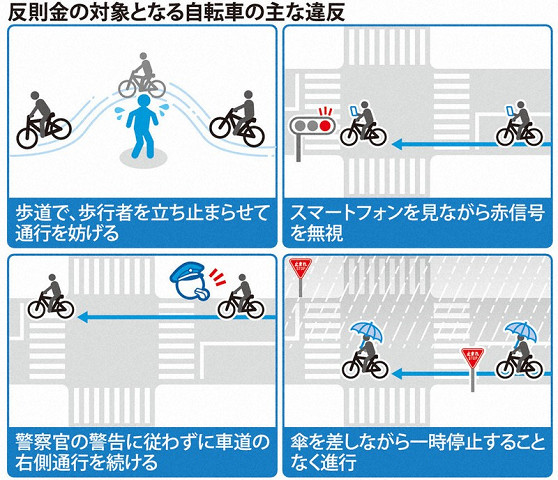
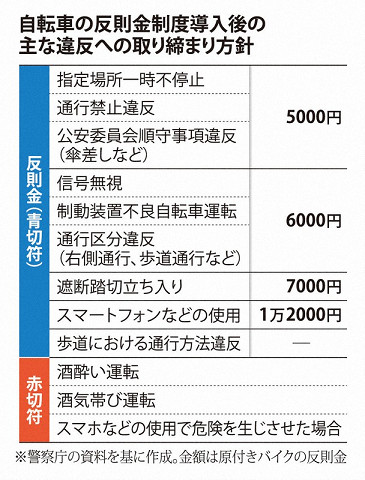 自転車安全利用5則が守れないなど自転車乗りのマナーが悪い傾向が続き、自転車が絡む交通事故も多いことから、自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立してしまいました。
自転車安全利用5則が守れないなど自転車乗りのマナーが悪い傾向が続き、自転車が絡む交通事故も多いことから、自転車の悪質な交通違反に「青切符」を交付し、反則金を納付させることを新たに規定する改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立してしまいました。
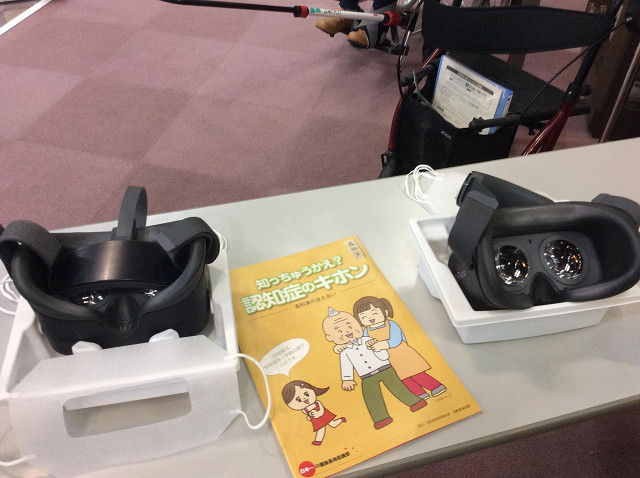

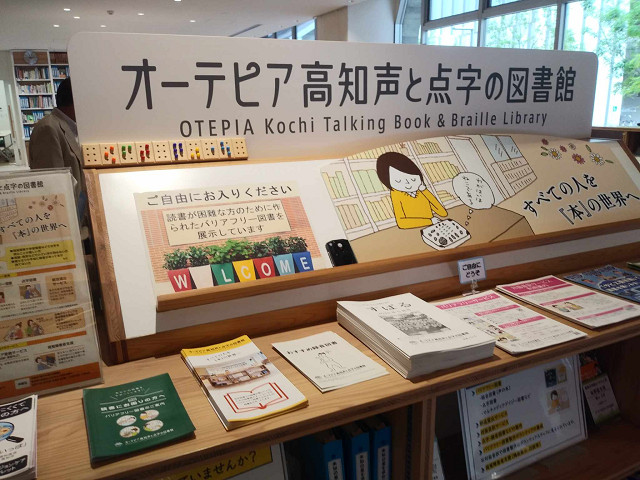

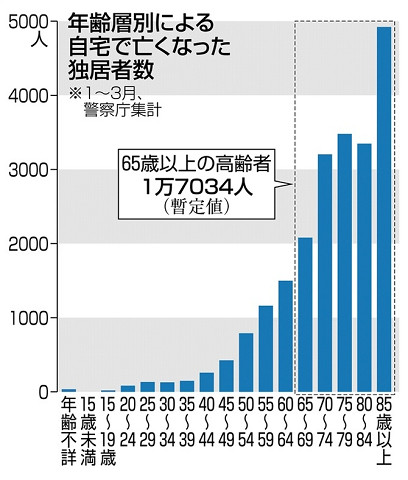 政府は13日、孤独・孤立問題への対策をめぐり、今年1~3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で計2万1716人(暫定値)確認され、うち65歳以上の高齢者が約1万7千人で8割近くを占める現状を明らかにしました。
政府は13日、孤独・孤立問題への対策をめぐり、今年1~3月に自宅で亡くなった一人暮らしの人が全国で計2万1716人(暫定値)確認され、うち65歳以上の高齢者が約1万7千人で8割近くを占める現状を明らかにしました。 沖縄が、戦後27年間の米国の占領・統治を経て本土に復帰した1972年5月15日から52年が経過しました。
沖縄が、戦後27年間の米国の占領・統治を経て本土に復帰した1972年5月15日から52年が経過しました。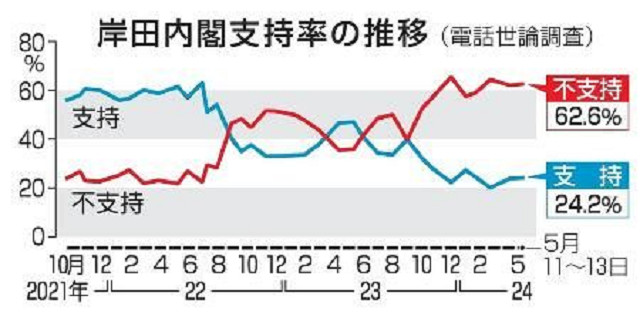
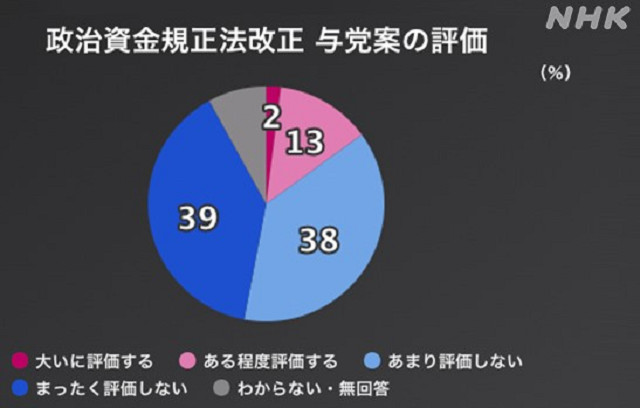 共同通信社が11〜13日に実施した全国電話世論調査で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正の与党案を「評価しない」との回答は79.7%に上り、政党から党幹部らに支出される政策活動費の扱いは「使途を細かく公開」52.0%、「廃止」26.8%と続いています。
共同通信社が11〜13日に実施した全国電話世論調査で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた政治資金規正法改正の与党案を「評価しない」との回答は79.7%に上り、政党から党幹部らに支出される政策活動費の扱いは「使途を細かく公開」52.0%、「廃止」26.8%と続いています。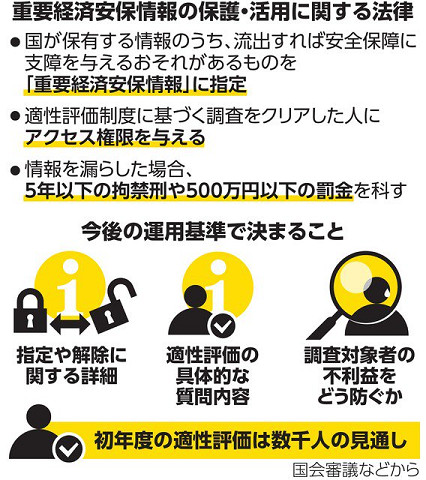 2月末に国会に提案されたいわゆる「経済秘密保護法案」(=重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案)は、私たちの反対の声にもかかわらず、4月8日に衆院本会議で可決され、5月10日参議院で可決成立してしまいました。
2月末に国会に提案されたいわゆる「経済秘密保護法案」(=重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案)は、私たちの反対の声にもかかわらず、4月8日に衆院本会議で可決され、5月10日参議院で可決成立してしまいました。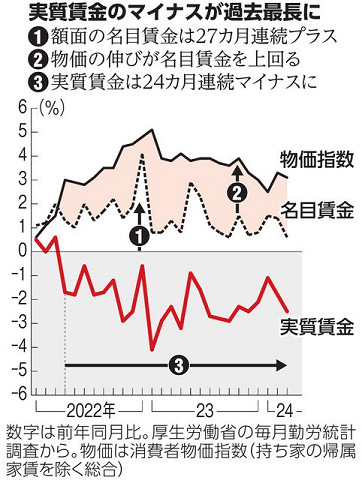
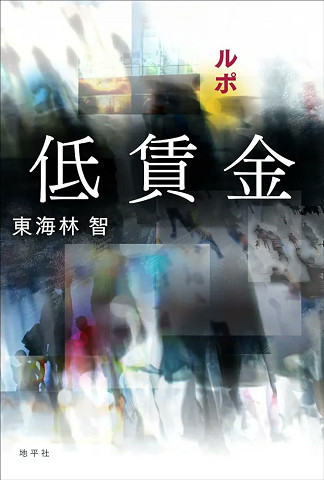 厚生労働省が9日公表した3月分の毎月勤労統計調査(速報)で、物価変動を加味し生活実感により近い実質賃金は、前年同月より2.5%減り、24カ月連続のマイナスとなったことが明らかになりました。
厚生労働省が9日公表した3月分の毎月勤労統計調査(速報)で、物価変動を加味し生活実感により近い実質賃金は、前年同月より2.5%減り、24カ月連続のマイナスとなったことが明らかになりました。
 5月1日、水俣市で開催された水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤環境相と患者団体との懇談の場で、発言時間に1団体3分という制限を設けた上で「時間なのでまとめてください」とせかし、発言者の男性のマイクの音を一方的に切った対応に、当事者・患者団体をはじめ多くの国民から批判の声が高まっています。
5月1日、水俣市で開催された水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤環境相と患者団体との懇談の場で、発言時間に1団体3分という制限を設けた上で「時間なのでまとめてください」とせかし、発言者の男性のマイクの音を一方的に切った対応に、当事者・患者団体をはじめ多くの国民から批判の声が高まっています。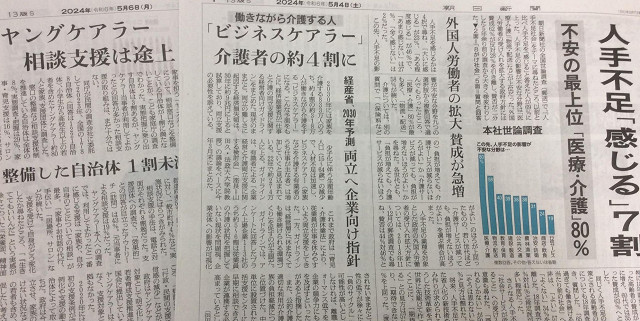
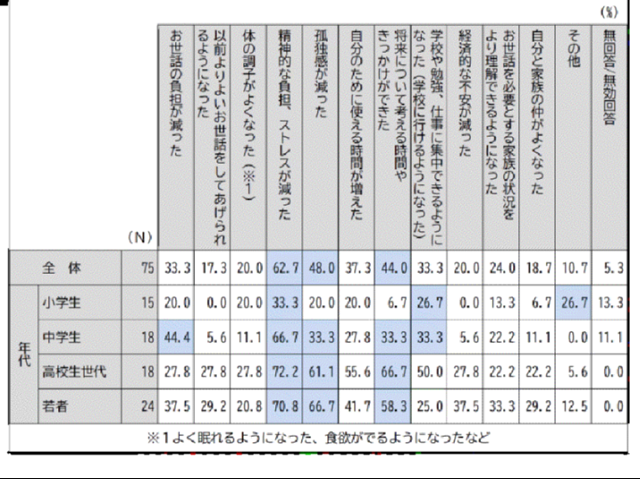
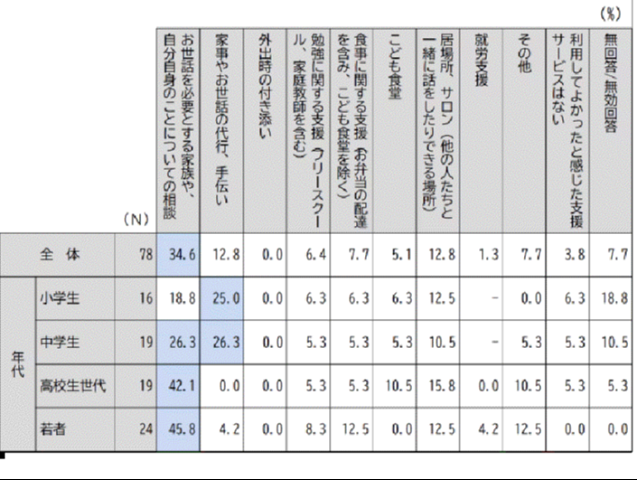
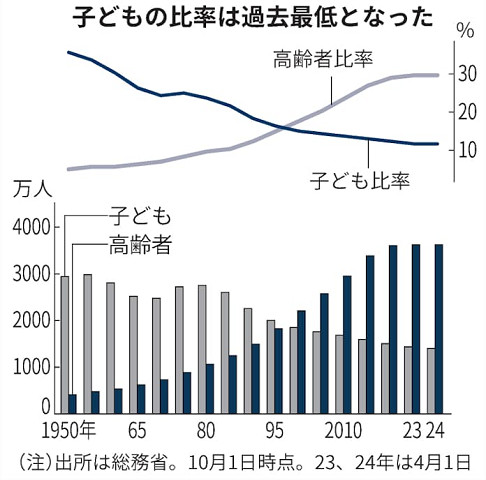
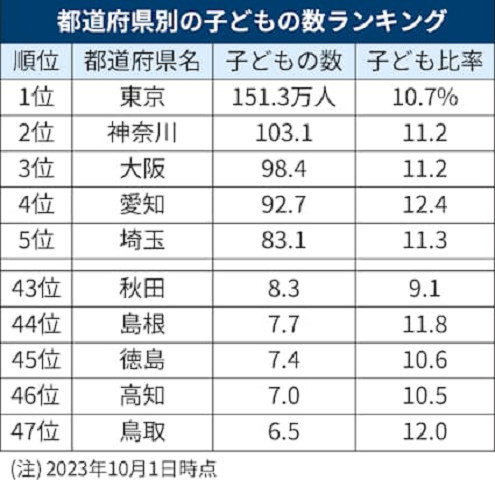 総務省が、人口推計から算出した子どもの数を4日に公表しました。
総務省が、人口推計から算出した子どもの数を4日に公表しました。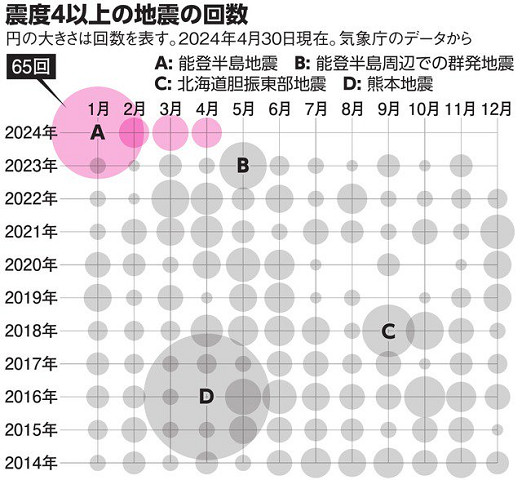 今朝も、最大震度3の余震が南予や高知県西部でおきました。
今朝も、最大震度3の余震が南予や高知県西部でおきました。

 日本国憲法は今日、1947年の施行から77年を迎えました。
日本国憲法は今日、1947年の施行から77年を迎えました。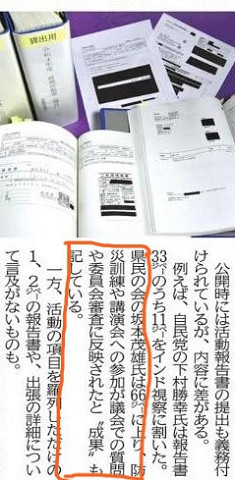
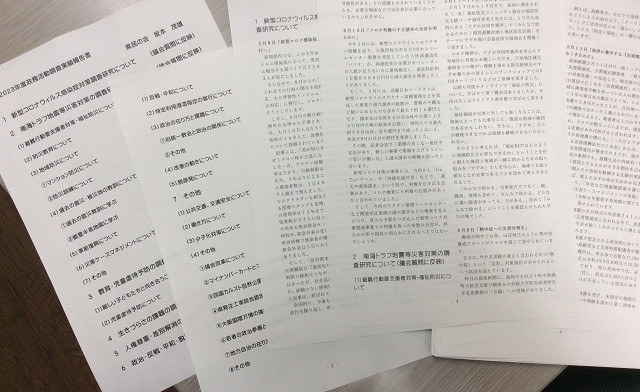 毎年のゴールデンウィークは、政務活動の前年度実績報告まとめに追われる日々を過ごしています。
毎年のゴールデンウィークは、政務活動の前年度実績報告まとめに追われる日々を過ごしています。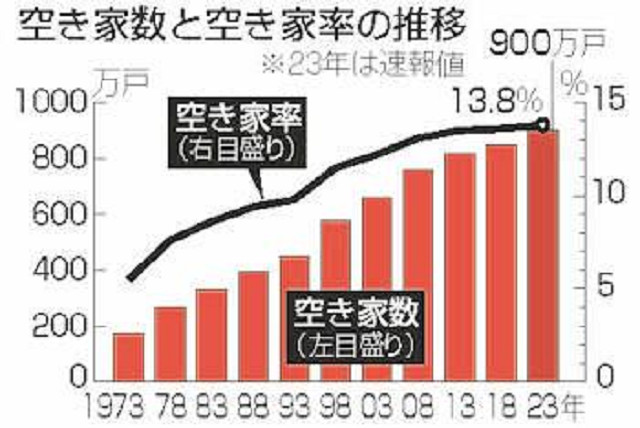
 総務省が昨日発表した2023年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報値)によると、全国の空き家数は900万戸と増え続けている実態が明らかになりました。
総務省が昨日発表した2023年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報値)によると、全国の空き家数は900万戸と増え続けている実態が明らかになりました。
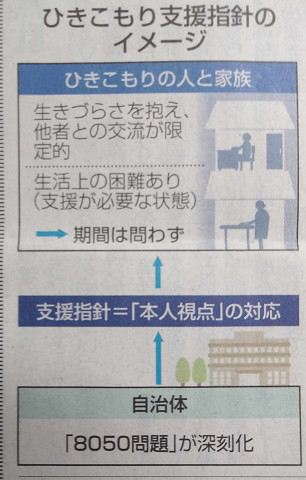 ひきこもりの人や家族の支援のため、厚生労働省が自治体向けに初めて策定する指針の骨子が昨日明らかになりました。
ひきこもりの人や家族の支援のため、厚生労働省が自治体向けに初めて策定する指針の骨子が昨日明らかになりました。
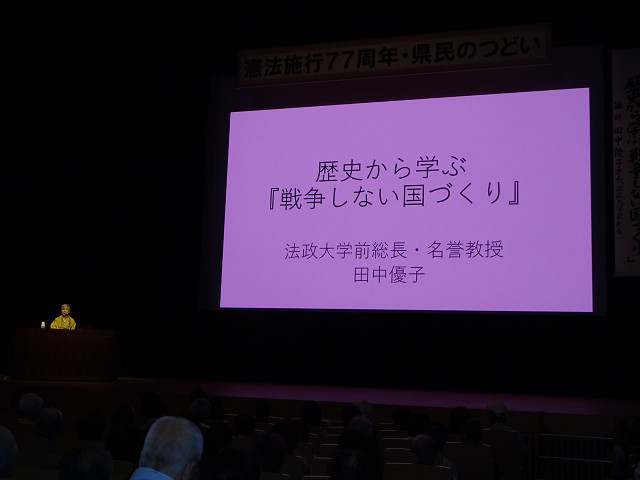 昨日は、午後2時からの憲法講演会で、テレビでもおなじみの田中優子法政大学前総長・名誉教授の「歴史から学ぶ『戦争しない国づくり』」を聴講のため、カルポートに行ってきました。
昨日は、午後2時からの憲法講演会で、テレビでもおなじみの田中優子法政大学前総長・名誉教授の「歴史から学ぶ『戦争しない国づくり』」を聴講のため、カルポートに行ってきました。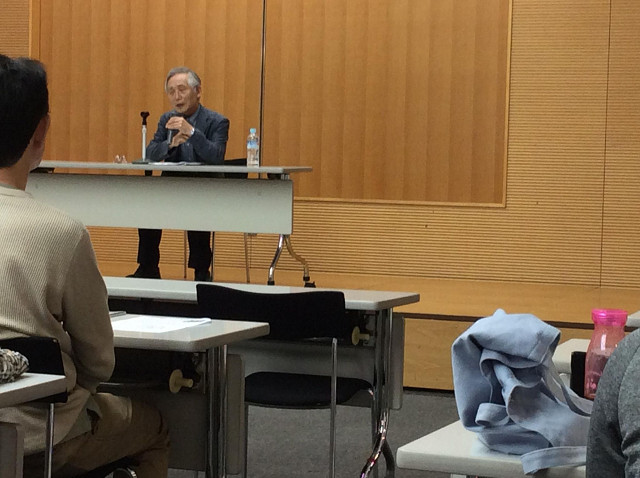
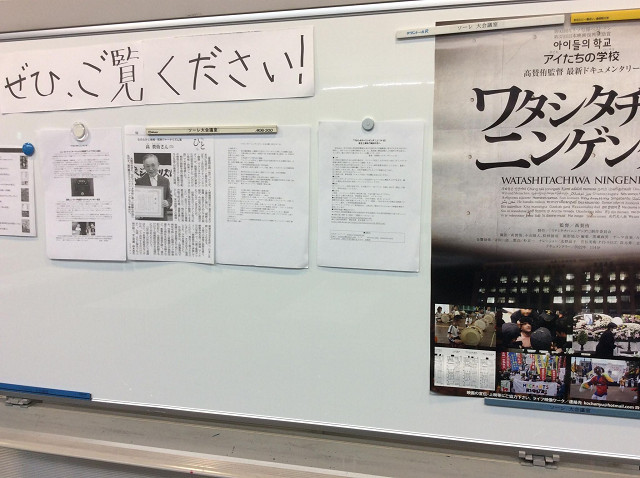
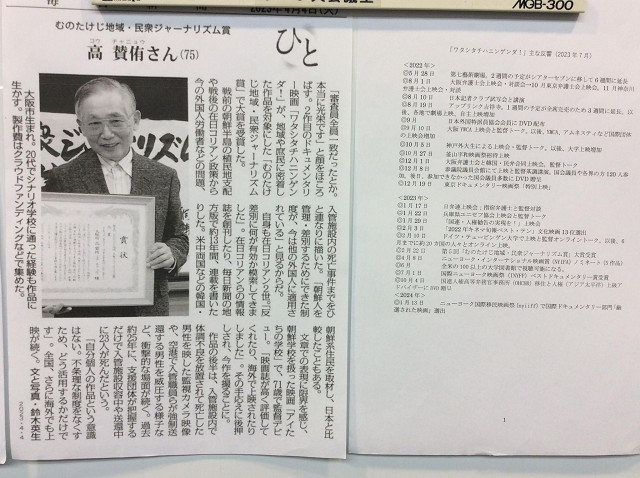 昨日は、ドキュメンタリー映画「ワタシタチハニンゲンダ!」(2022年公開・高賛侑監督)を鑑賞し、高賛侑監督のお話を聞かせて頂きました。
昨日は、ドキュメンタリー映画「ワタシタチハニンゲンダ!」(2022年公開・高賛侑監督)を鑑賞し、高賛侑監督のお話を聞かせて頂きました。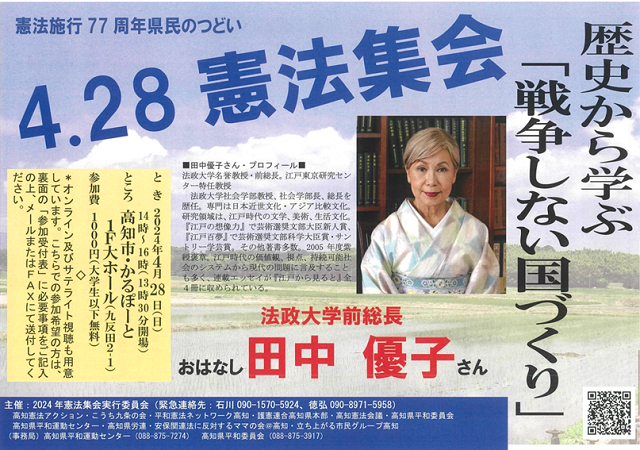
 4月22日付高知新聞で、連載が始まった「自治のかたち 高知市・地域活動の現場から」では、「町内会って何ですか?会長の苦悩分割?合併?」から始まり、「ごみ当番、広がる外注 町内会未加入者へ募る不満」「やれるもんがやるしか 高齢者見守り、誰が担う」「官製でコミュニティー再生 小学校区で再編、温度差も」と続き、今朝の「世代間の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」で最終回となりました。
4月22日付高知新聞で、連載が始まった「自治のかたち 高知市・地域活動の現場から」では、「町内会って何ですか?会長の苦悩分割?合併?」から始まり、「ごみ当番、広がる外注 町内会未加入者へ募る不満」「やれるもんがやるしか 高齢者見守り、誰が担う」「官製でコミュニティー再生 小学校区で再編、温度差も」と続き、今朝の「世代間の結び目探して 探る電子化、子ども見守り」で最終回となりました。
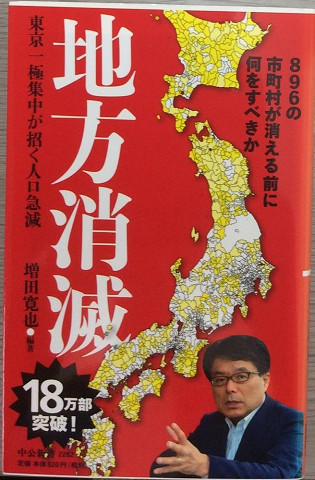 10年前に、増田リポートが出されたとき「896の市町村が消える『地方消滅』」と言われ「消滅可能性自治体」が名指しされました。
10年前に、増田リポートが出されたとき「896の市町村が消える『地方消滅』」と言われ「消滅可能性自治体」が名指しされました。
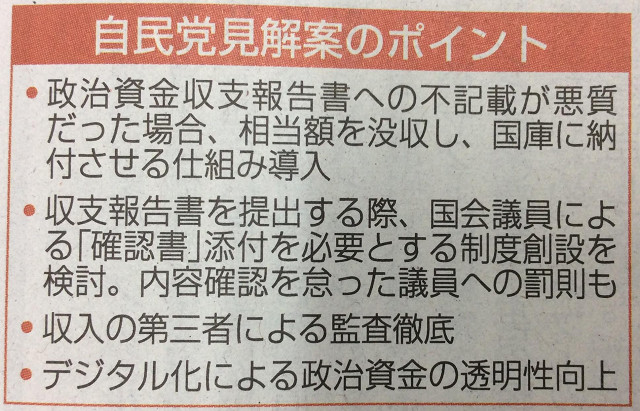 朝日新聞社の直近の全国世論調査(電話)によると、自民党の派閥の裏金問題について、実態が「解明されていない」と答えた人は92%に達し、「解明された」という人は5%でした。
朝日新聞社の直近の全国世論調査(電話)によると、自民党の派閥の裏金問題について、実態が「解明されていない」と答えた人は92%に達し、「解明された」という人は5%でした。



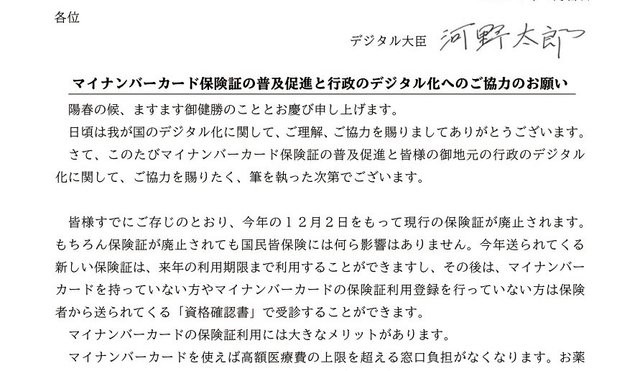
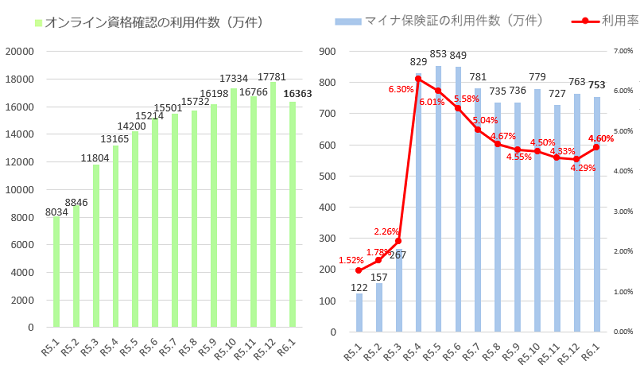
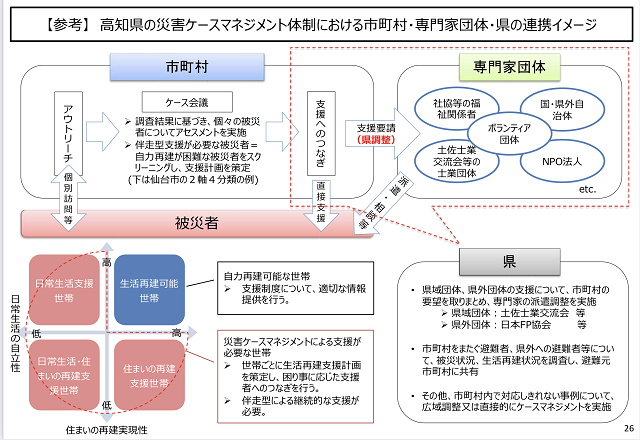
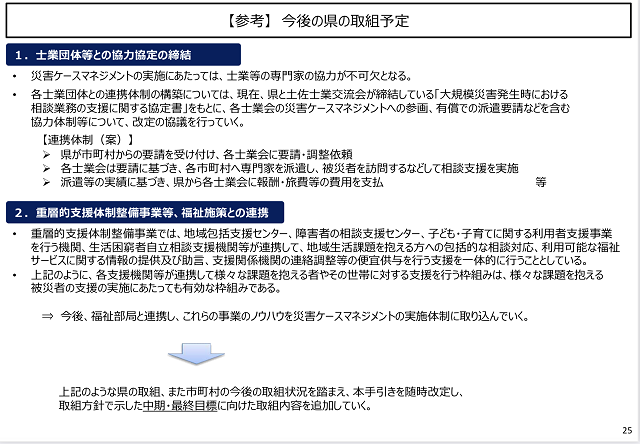 17日の危機管理文化厚生委員会の本庁業務概要調査で、「
17日の危機管理文化厚生委員会の本庁業務概要調査で、「 四国で6弱を観測したのは、現在の震度階級が導入された1996年10月以降初めてであり、最大6弱の宿毛市をはじめ、県西部を中心に強い揺れに見舞われました。
四国で6弱を観測したのは、現在の震度階級が導入された1996年10月以降初めてであり、最大6弱の宿毛市をはじめ、県西部を中心に強い揺れに見舞われました。 新潟県柏崎刈羽原発の再稼働に向け、地元・新潟県の同意が得られる見通しが立たない中、東京電力は15日、7号機の原子炉に核燃料を入れる装塡に着手しました。
新潟県柏崎刈羽原発の再稼働に向け、地元・新潟県の同意が得られる見通しが立たない中、東京電力は15日、7号機の原子炉に核燃料を入れる装塡に着手しました。
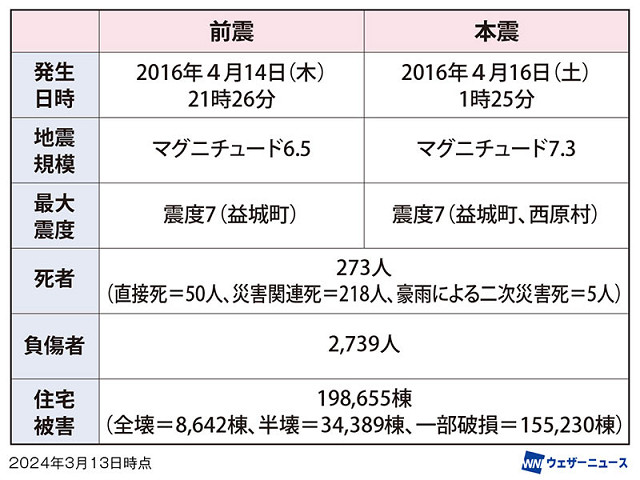

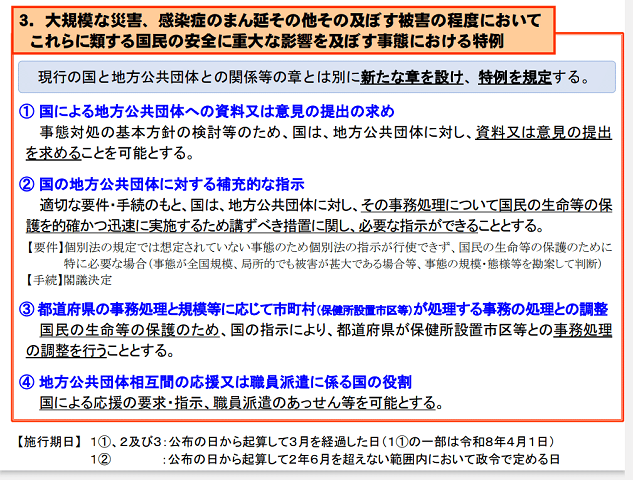 政府は3月1日の閣議で、大規模災害や感染症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要な指示ができる仕組みを盛り込んだ地方自治法改正案を決定しました。
政府は3月1日の閣議で、大規模災害や感染症のまん延といった非常時に国が自治体へ必要な指示ができる仕組みを盛り込んだ地方自治法改正案を決定しました。
 日本国際博覧会協会は8日、公式ホームページで「みんなで『大阪・関西万博開幕1年前』を盛り上げましょう!」と呼びかけ、公式キャラクター「ミャクミャク」と「くるぞ、万博。」と書かれたイメージ画像をダウンロードしてSNSに投稿するよう訴えかけています。
日本国際博覧会協会は8日、公式ホームページで「みんなで『大阪・関西万博開幕1年前』を盛り上げましょう!」と呼びかけ、公式キャラクター「ミャクミャク」と「くるぞ、万博。」と書かれたイメージ画像をダウンロードしてSNSに投稿するよう訴えかけています。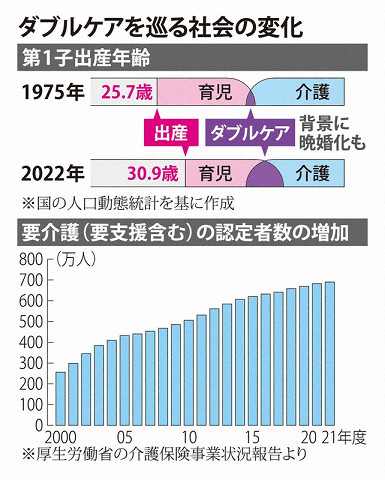 安倍政権は2015年に策定した「女性活躍加速のための重点方針」で、子育てと介護を同時に担うすダブルケア問題を取り上げ、負担軽減の対策を進めると明記しました
安倍政権は2015年に策定した「女性活躍加速のための重点方針」で、子育てと介護を同時に担うすダブルケア問題を取り上げ、負担軽減の対策を進めると明記しました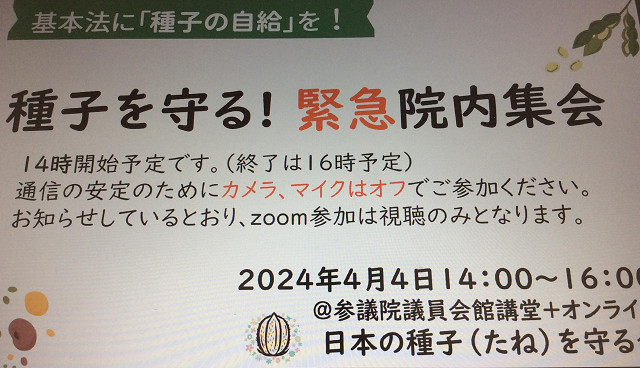


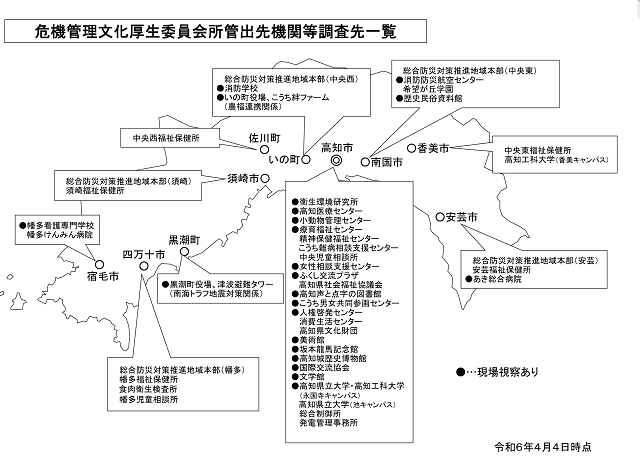
 昨日は、組織委員会ということで、今年度の常任委員会の委員長、副委員長などの選任が行われました。
昨日は、組織委員会ということで、今年度の常任委員会の委員長、副委員長などの選任が行われました。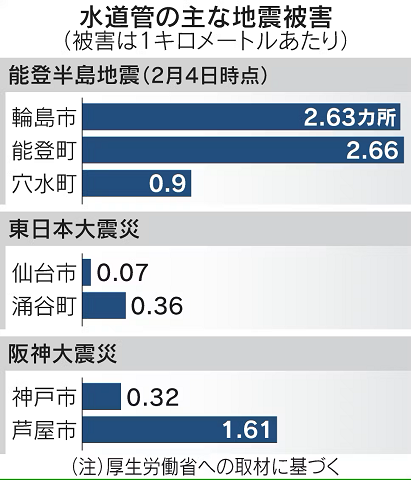
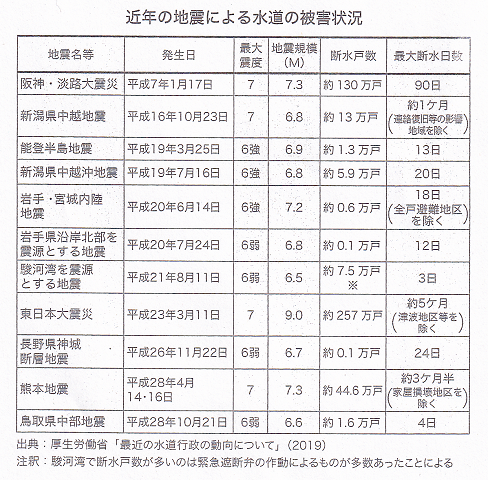 能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。
能登半島地震から3カ月が過ぎ、未だに被災地の断水が継続していることが、報道されています。 政府は1日、総合的な防衛体制強化の一環で、有事に備え平時から自衛隊や海上保安庁が使用できる「特定利用空港・港湾」の第1弾として、本県の3港をはじめ7道県16施設を選定しました。
政府は1日、総合的な防衛体制強化の一環で、有事に備え平時から自衛隊や海上保安庁が使用できる「特定利用空港・港湾」の第1弾として、本県の3港をはじめ7道県16施設を選定しました。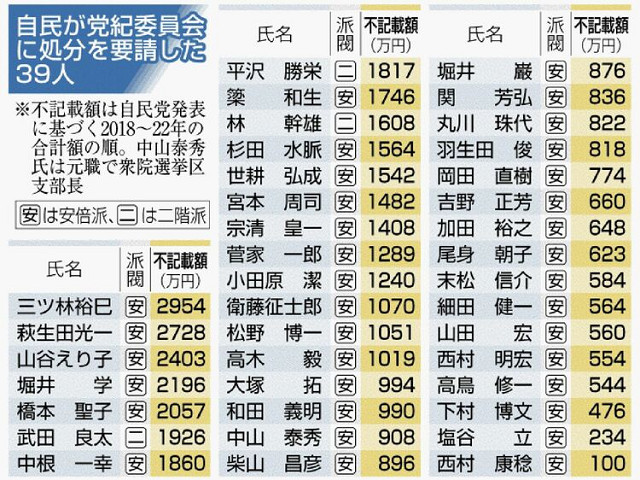 自民党は昨日、派閥の裏金プール・キックバック事件をめぐり、過去5年間の政治資金収支報告書への不記載・不適正記載総額が500万円以上の議員らと、「『派閥』の幹部の立場にありながら適切な対応を取らず大きな政治不信を招いた者」一部の安倍派幹部を含む計39人を処分対象とする一方で、党総裁の岸田首相と二階元幹事長に対する処分を見送ることを決めました。
自民党は昨日、派閥の裏金プール・キックバック事件をめぐり、過去5年間の政治資金収支報告書への不記載・不適正記載総額が500万円以上の議員らと、「『派閥』の幹部の立場にありながら適切な対応を取らず大きな政治不信を招いた者」一部の安倍派幹部を含む計39人を処分対象とする一方で、党総裁の岸田首相と二階元幹事長に対する処分を見送ることを決めました。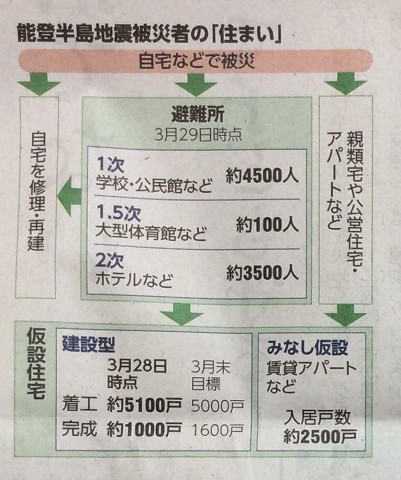 能登半島地震から3か月、月命日の4月1日を迎えました。
能登半島地震から3か月、月命日の4月1日を迎えました。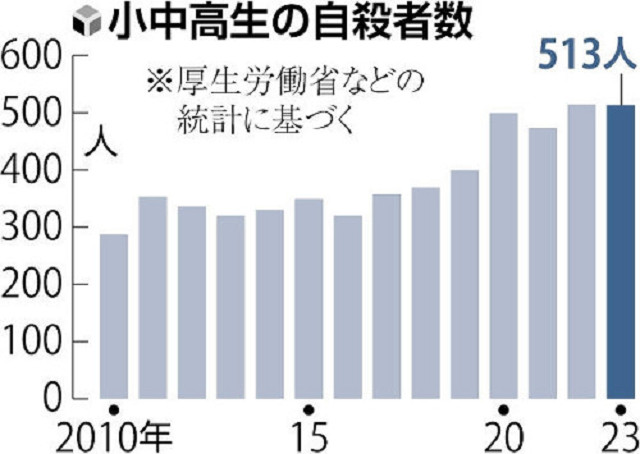
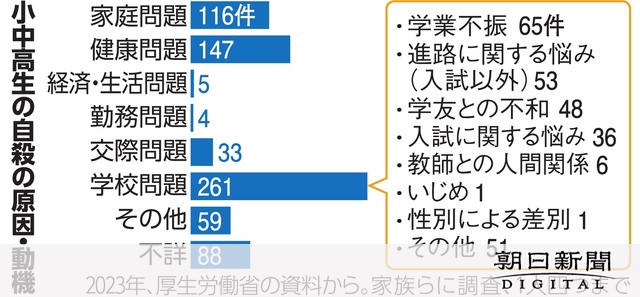 1月28日に、ここで2023年の自殺者数の暫定値を2万1818人、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことを報告させて頂きました。
1月28日に、ここで2023年の自殺者数の暫定値を2万1818人、小中高生は過去最多に次ぐ507人であったことを報告させて頂きました。

 昨日、政府は防衛力強化の一環として、有事の際の自衛隊や海上保安庁による使用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に、本県の3港湾をはじめ7道県計16カ所を指定する方針を固めたことが、報じられています。
昨日、政府は防衛力強化の一環として、有事の際の自衛隊や海上保安庁による使用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に、本県の3港湾をはじめ7道県計16カ所を指定する方針を固めたことが、報じられています。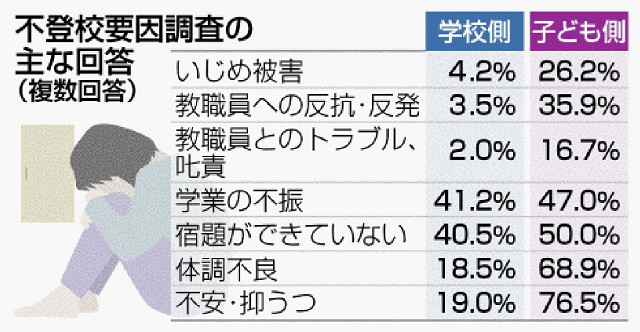 今朝の共同通信の配信記事で、2022年度に不登校を経験した小中高生や担任らに要因を尋ねた調査結果に関する記事がありました。
今朝の共同通信の配信記事で、2022年度に不登校を経験した小中高生や担任らに要因を尋ねた調査結果に関する記事がありました。
 昨日から、高知新聞で、「明日の足 高知の公共交通を考える」連載第4便が始まりました。
昨日から、高知新聞で、「明日の足 高知の公共交通を考える」連載第4便が始まりました。 「県民の安心・安全を蔑ろにしかねない課題に対して結論を出すには、あまりに拙速でないですか。」
「県民の安心・安全を蔑ろにしかねない課題に対して結論を出すには、あまりに拙速でないですか。」


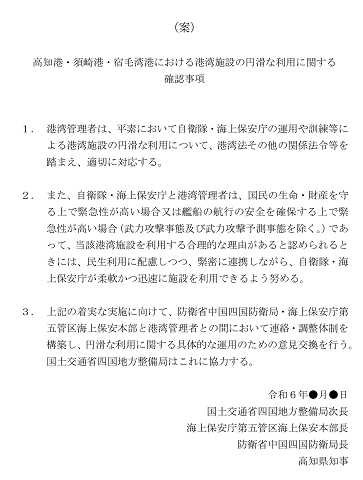
 私たちも、1月15日に平和憲法ネットワーク高知をはじめ、護憲連合高知県本部、高知県平和運動センターの三者で、防衛力の強化のため国が整備・拡充を予定している「特定重要拠点空港・港湾」について、高知県内での整備に反対するよう、県に申し入れていました。
私たちも、1月15日に平和憲法ネットワーク高知をはじめ、護憲連合高知県本部、高知県平和運動センターの三者で、防衛力の強化のため国が整備・拡充を予定している「特定重要拠点空港・港湾」について、高知県内での整備に反対するよう、県に申し入れていました。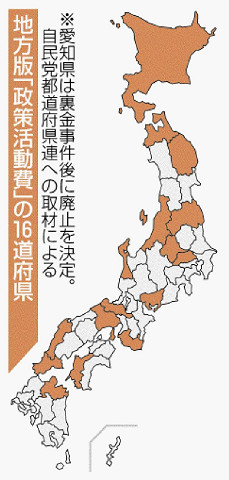 昨日の全国幹事長会議、そし今日は党大会を開催している自民党は、裏金問題を巡って地方組織がけじめを要求しているとのことです。
昨日の全国幹事長会議、そし今日は党大会を開催している自民党は、裏金問題を巡って地方組織がけじめを要求しているとのことです。
 7日に一問一答で質問させて頂いた際の質問と答弁のテープ起こしができましたので、仮の議事録として
7日に一問一答で質問させて頂いた際の質問と答弁のテープ起こしができましたので、仮の議事録として






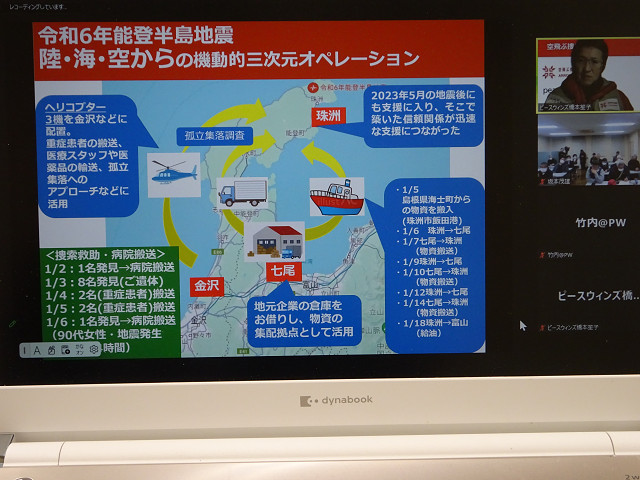
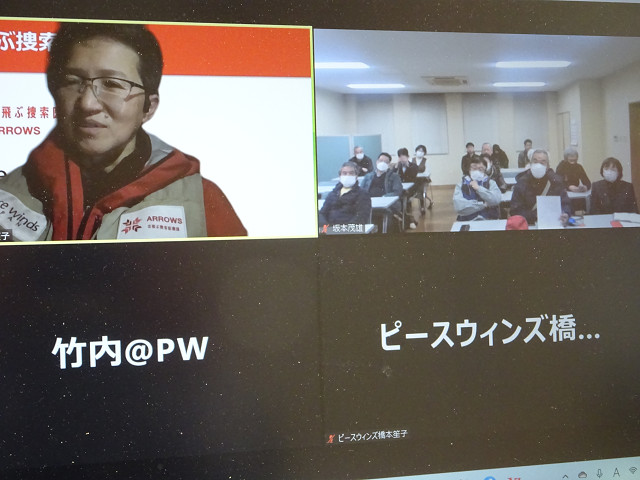
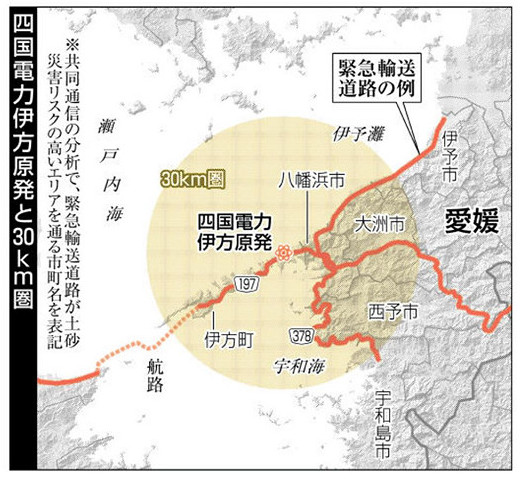
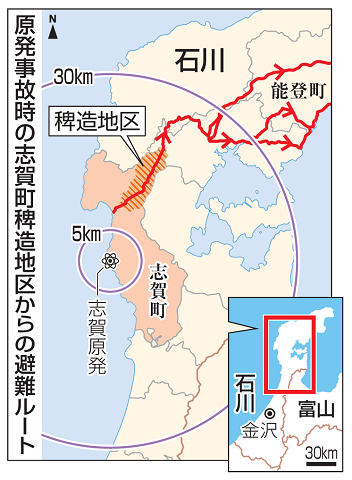 明日13年目の3.11を迎えるにあたり、福島原発事故から未だ復興が果たせない帰還困難区域の課題が浮き彫りになる時期です。
明日13年目の3.11を迎えるにあたり、福島原発事故から未だ復興が果たせない帰還困難区域の課題が浮き彫りになる時期です。
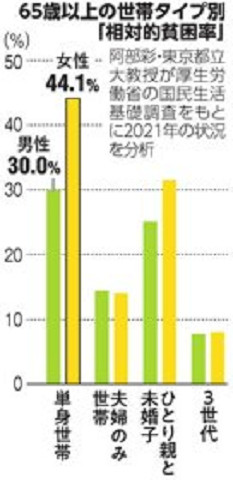 昨日3月8日は、国連が定める「国際女性デー」でした。
昨日3月8日は、国連が定める「国際女性デー」でした。

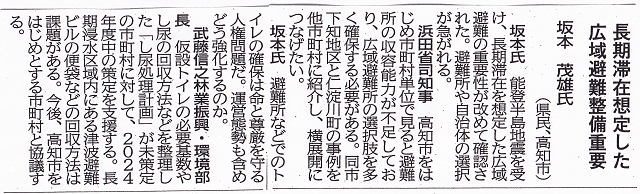
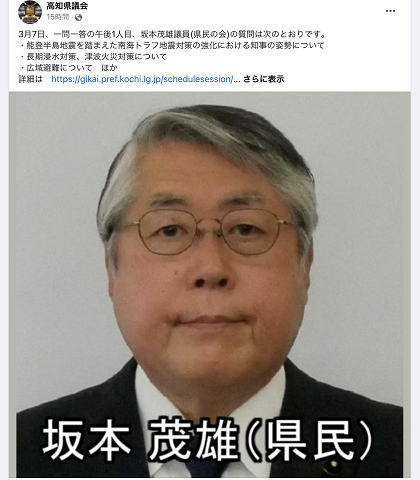 今日で、本会議における一括質問は終わり、明日から一問一答方式による質問戦に入ります。 私は、答弁も含めた40分間の持ち時間で、明日の午後一時から質問を行います。
今日で、本会議における一括質問は終わり、明日から一問一答方式による質問戦に入ります。 私は、答弁も含めた40分間の持ち時間で、明日の午後一時から質問を行います。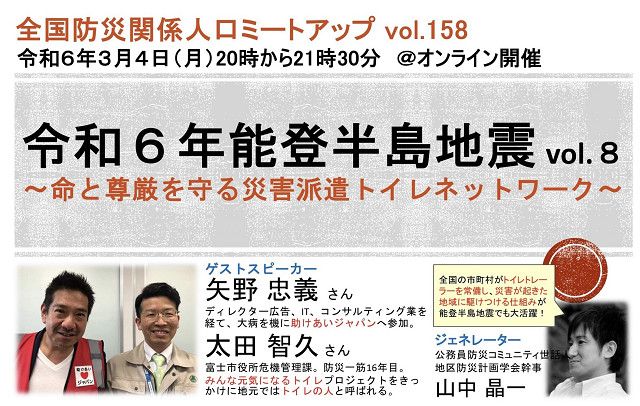
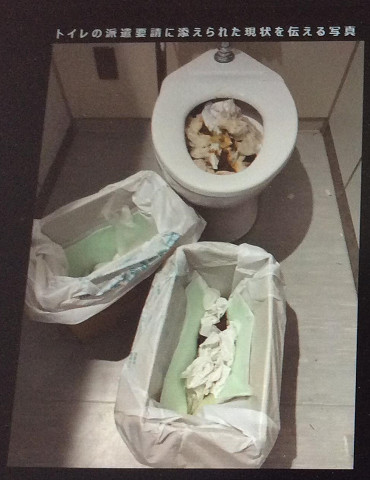 今議会での一問一答による議会質問が明後日に迫ってきました。
今議会での一問一答による議会質問が明後日に迫ってきました。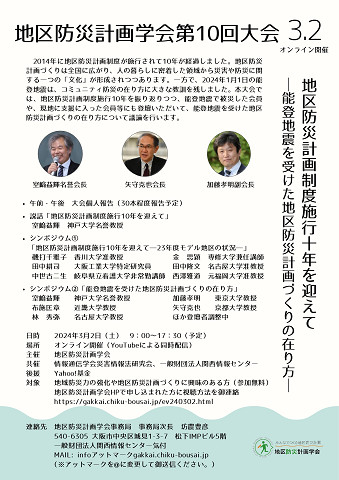
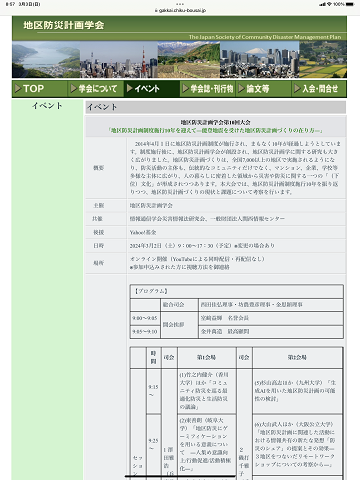
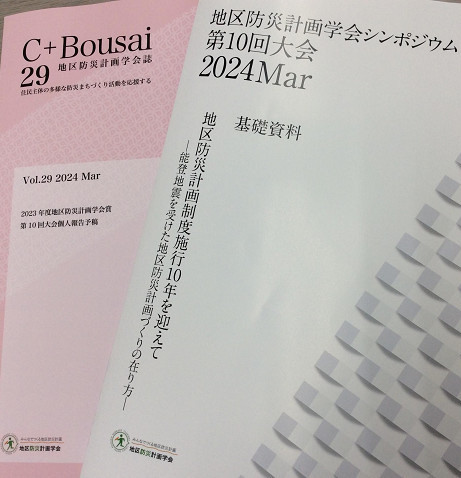

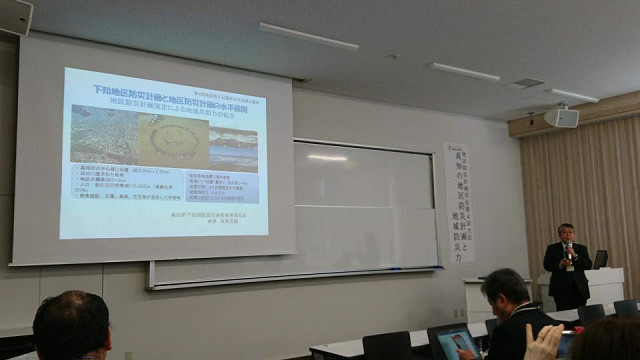
 自民党派閥による裏金事件を受け、自民党内のドタバタ劇の末に岸田文雄首相が出席する衆院政治倫理審査会が昨日、開かれました。
自民党派閥による裏金事件を受け、自民党内のドタバタ劇の末に岸田文雄首相が出席する衆院政治倫理審査会が昨日、開かれました。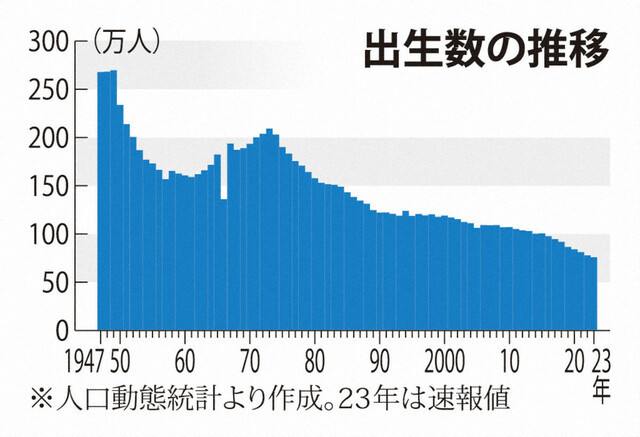 2023年に生まれた子どもの数は、過去最少の75万8631人で8年連続減で、婚姻数は48万9281組で、戦後初めて50万組を割ったことが、厚生労働省が27日に公表した23年の人口動態統計(速報)で明らかになっています。
2023年に生まれた子どもの数は、過去最少の75万8631人で8年連続減で、婚姻数は48万9281組で、戦後初めて50万組を割ったことが、厚生労働省が27日に公表した23年の人口動態統計(速報)で明らかになっています。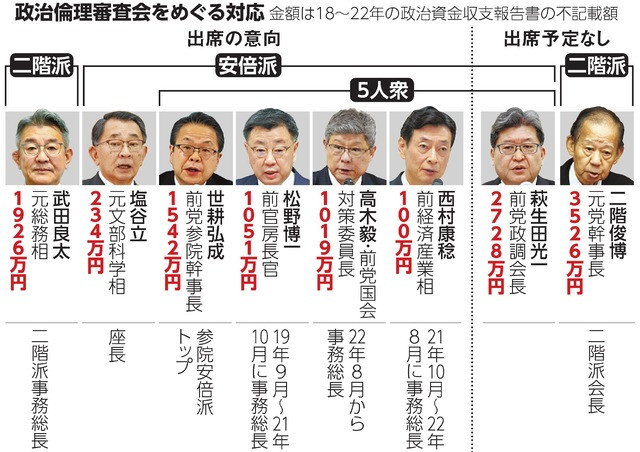 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆院政治倫理審査会(政倫審)の公開の可否を巡って与野党協議が紛糾しています。
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆院政治倫理審査会(政倫審)の公開の可否を巡って与野党協議が紛糾しています。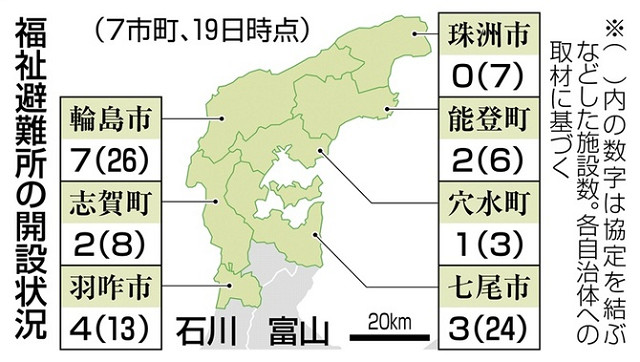 以前にも、高知県における災害時要配慮者が避難可能な福祉避難所は、県全体で必要な17,184人分に対し、指定は令和5年9月末時点で10,500人分にとどまっており、特に高知市では、必要な12,544人分に対し、指定は5,265人分にとどまり、7,279人分が不足している状況にあることを報告しました。
以前にも、高知県における災害時要配慮者が避難可能な福祉避難所は、県全体で必要な17,184人分に対し、指定は令和5年9月末時点で10,500人分にとどまっており、特に高知市では、必要な12,544人分に対し、指定は5,265人分にとどまり、7,279人分が不足している状況にあることを報告しました。







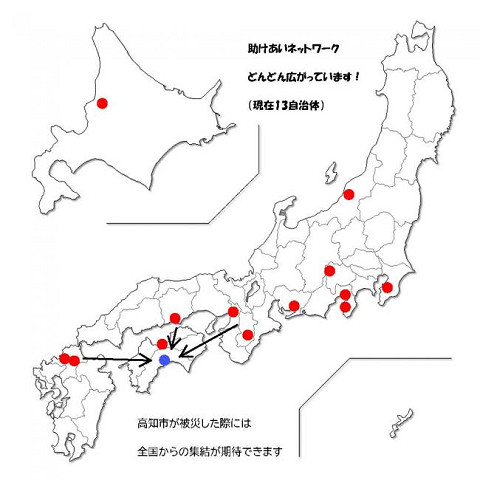 何かと物議を醸してきた大阪関西万博だが、ここにきて350億円もの巨額建設費が投じられた大屋根(リング)に続き、新たに「2億円トイレ」の問題が、浮上しています。
何かと物議を醸してきた大阪関西万博だが、ここにきて350億円もの巨額建設費が投じられた大屋根(リング)に続き、新たに「2億円トイレ」の問題が、浮上しています。 1975年の原発誘致決議から2006年まで31年間に及ぶ長い闘いの結果、珠洲原発は断念されていましたが、先人の闘いに感謝するしかありません。
1975年の原発誘致決議から2006年まで31年間に及ぶ長い闘いの結果、珠洲原発は断念されていましたが、先人の闘いに感謝するしかありません。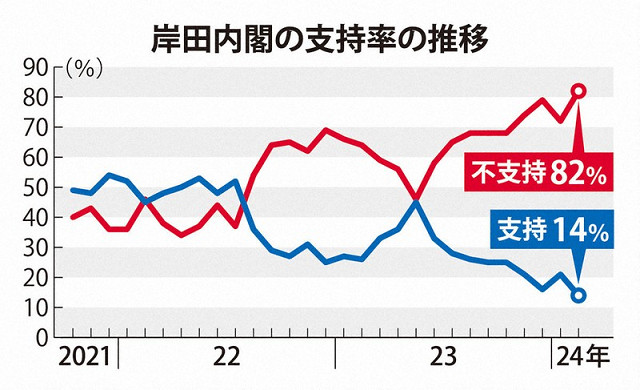 毎日新聞の17、18日実施の世論調査では、岸田内閣の支持率は、1月の前回調査(21%)より7ポイント減の14%で2カ月ぶりに下落し、岸田政権発足以来最低となり、不支持率は前回調査(72%)より10ポイント増の82%となっています。
毎日新聞の17、18日実施の世論調査では、岸田内閣の支持率は、1月の前回調査(21%)より7ポイント減の14%で2カ月ぶりに下落し、岸田政権発足以来最低となり、不支持率は前回調査(72%)より10ポイント増の82%となっています。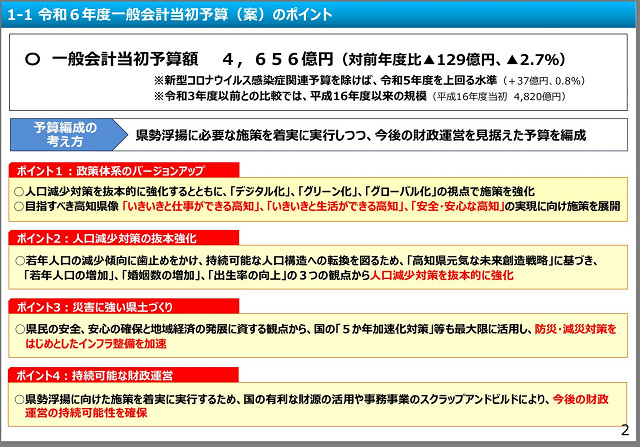
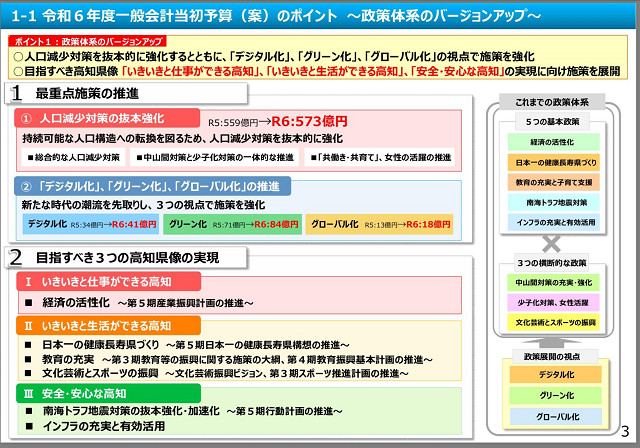



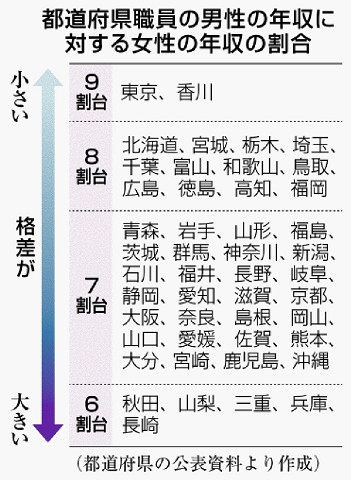 今朝の高知新聞一面に「都道府県職員年収に男女差 22年度男性の7割台過半数」との見出し記事があります。
今朝の高知新聞一面に「都道府県職員年収に男女差 22年度男性の7割台過半数」との見出し記事があります。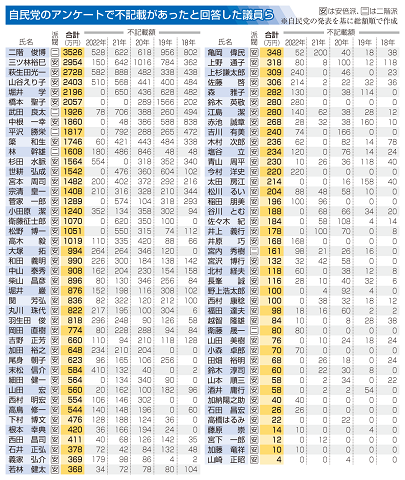

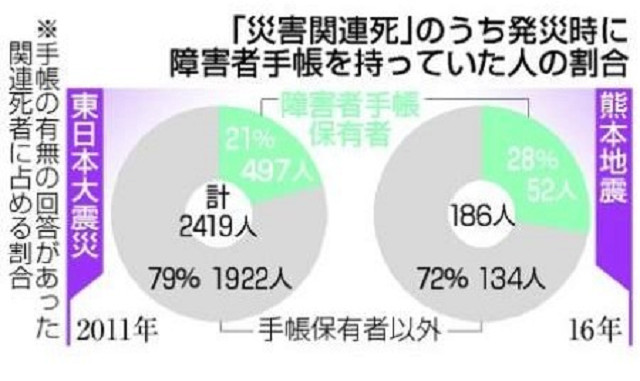 高知新聞2月11日付け一面トップの記事は「災害関連死、2割超が障害者 「救えた命」への対策急務」の見出しで、被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」のうち、発災時に障害者手帳を持っていた人の割合が、2011年の東日本大震災で21%、16年の熊本地震で28%だったことが、自治体への共同通信の調査で分かったと報じられていました。
高知新聞2月11日付け一面トップの記事は「災害関連死、2割超が障害者 「救えた命」への対策急務」の見出しで、被災後の心身の負担が原因で亡くなる「災害関連死」のうち、発災時に障害者手帳を持っていた人の割合が、2011年の東日本大震災で21%、16年の熊本地震で28%だったことが、自治体への共同通信の調査で分かったと報じられていました。





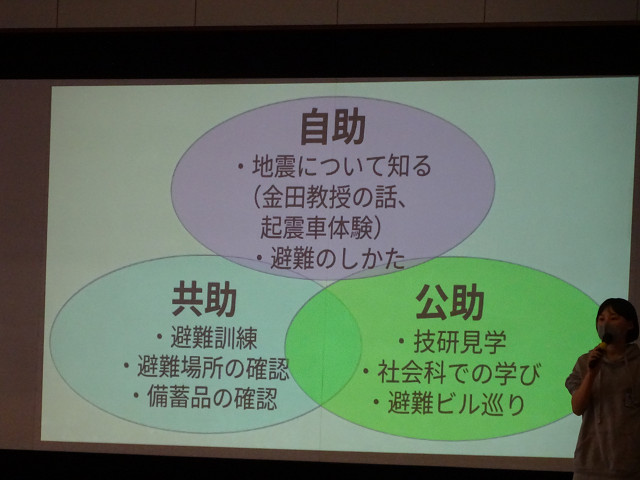




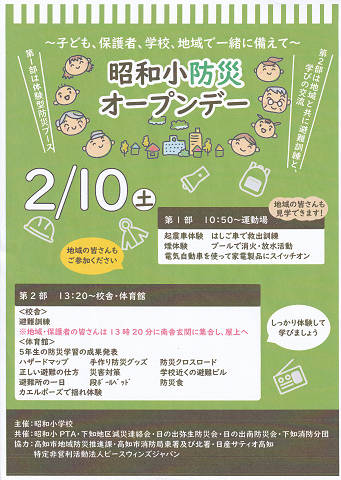 いよいよ明日10日は、「昭和小防災オープンデー」。
いよいよ明日10日は、「昭和小防災オープンデー」。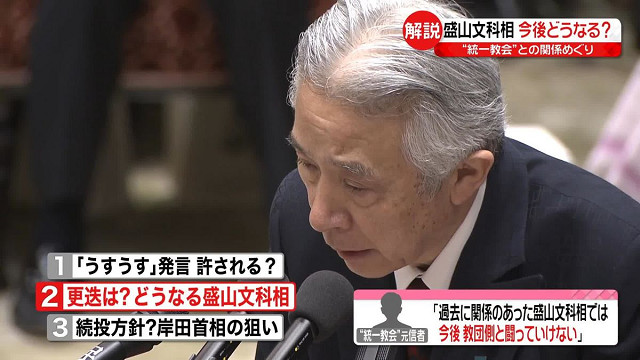
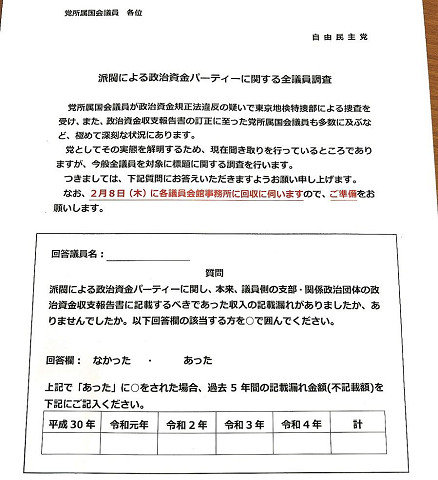 宗教法人を所管する文科相として、旧統一教会の解散命令を請求した盛山大臣は、教団との関係は断ち切られていて当然のはずが、今頃になって2021年の前回衆院選で、教団系団体の世界平和連合から「推薦状」を受け取り、選挙支援を受けていたことが明らかになっています。
宗教法人を所管する文科相として、旧統一教会の解散命令を請求した盛山大臣は、教団との関係は断ち切られていて当然のはずが、今頃になって2021年の前回衆院選で、教団系団体の世界平和連合から「推薦状」を受け取り、選挙支援を受けていたことが明らかになっています。


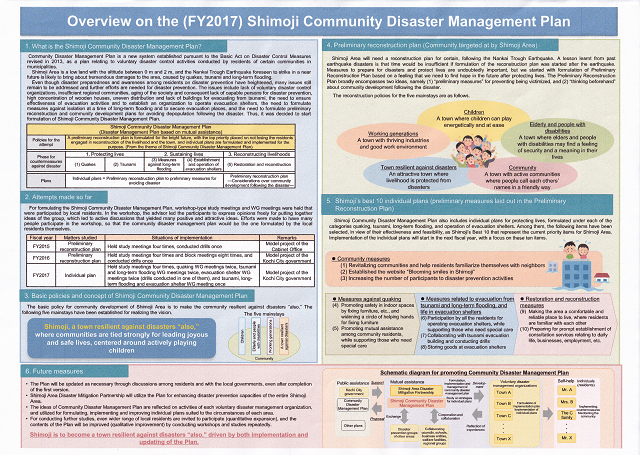

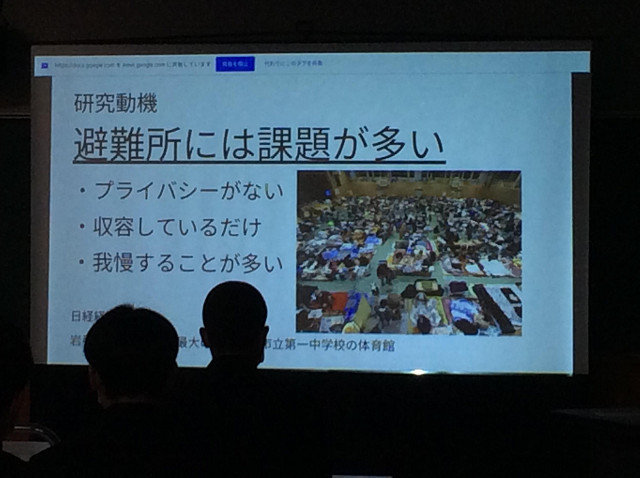

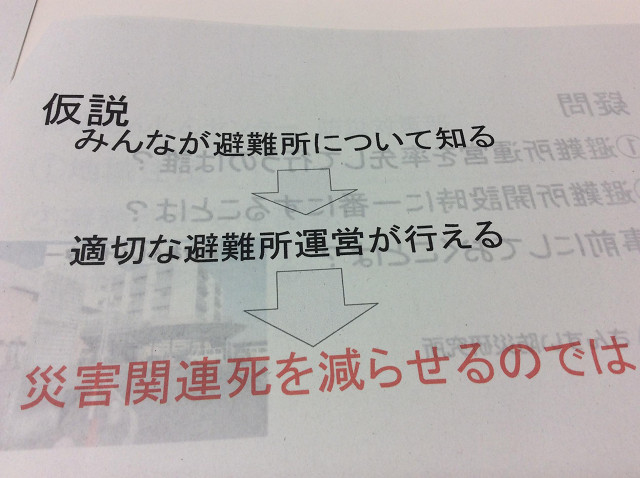
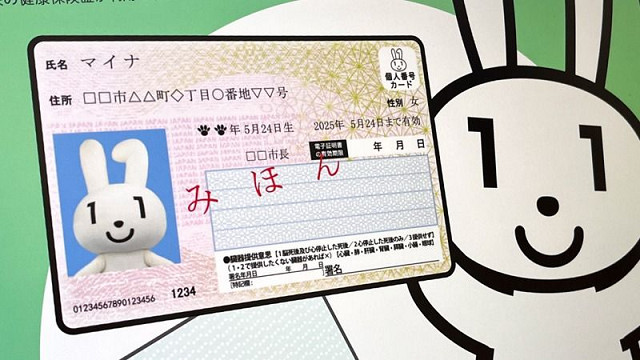 国は健康保険証を12月に廃止し、マイナ保険証に一本化すると決定したが、全国保険医団体連合会は、全国5万5357カ所の医療機関に昨年11月下旬~今年1月上旬、アンケートを実施し、回答を得た8672カ所のうち約6割の5188カ所が、昨年10月1日以降にオンライン資格確認に関するトラブルがあったと公表しました。
国は健康保険証を12月に廃止し、マイナ保険証に一本化すると決定したが、全国保険医団体連合会は、全国5万5357カ所の医療機関に昨年11月下旬~今年1月上旬、アンケートを実施し、回答を得た8672カ所のうち約6割の5188カ所が、昨年10月1日以降にオンライン資格確認に関するトラブルがあったと公表しました。
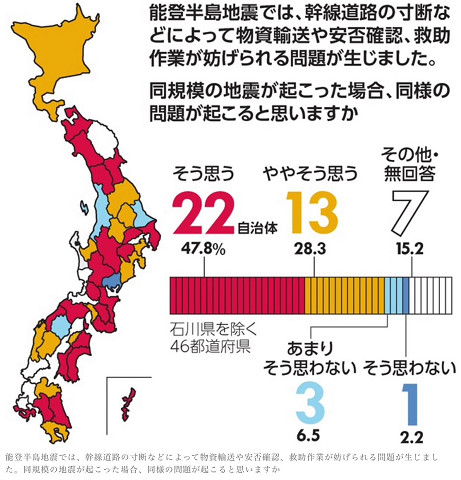


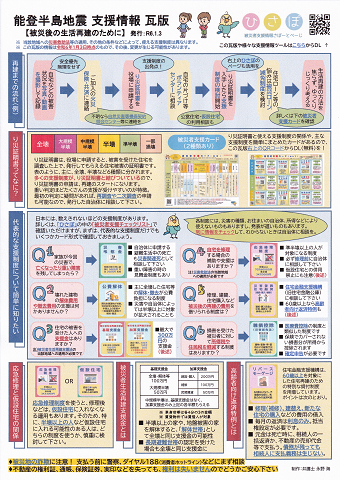 元旦の地震発生以来、辛い日々を過ごされている被災者の皆様にお見舞い申し上げます。
元旦の地震発生以来、辛い日々を過ごされている被災者の皆様にお見舞い申し上げます。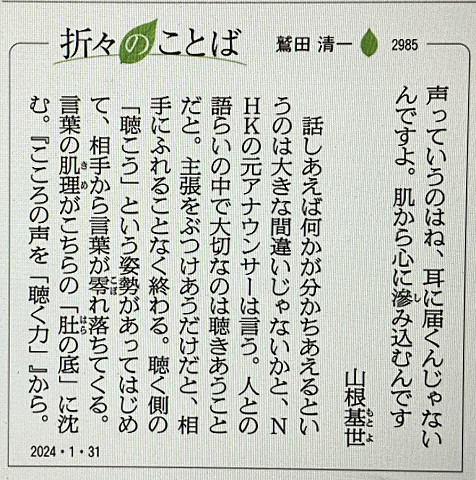

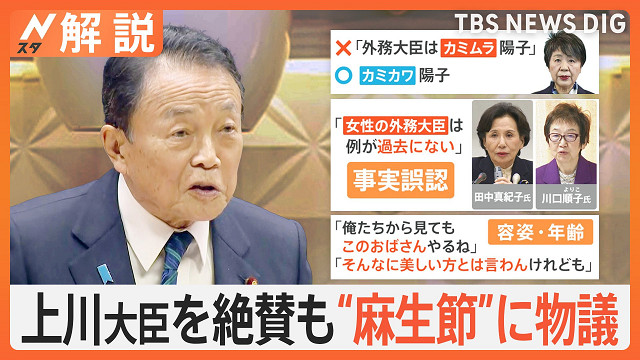
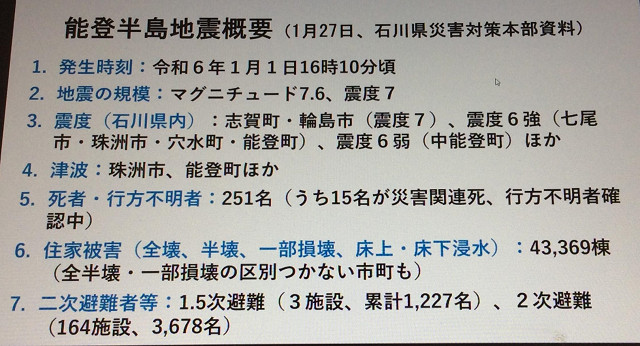
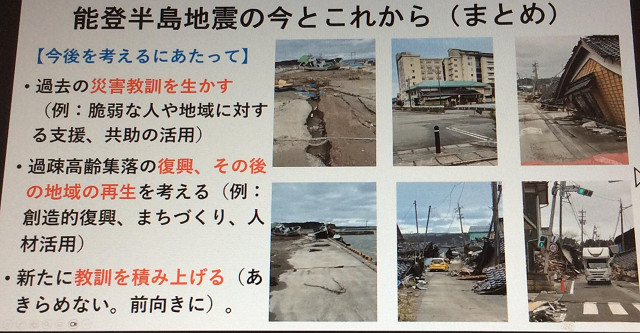 昨夜の毎週月曜20時からの第153回全国防災関係人口ミートアップは「令和6年能登半島地震vol.2〜被災地の今とこれからを考える〜」として、兵庫県立大学の青田良介先生に話題提供いただき、過疎高齢社会の災害対応と生活・生業再建、地域再生など、今とこれからの課題を踏まえて、今後を考える視点を提起頂きました。
昨夜の毎週月曜20時からの第153回全国防災関係人口ミートアップは「令和6年能登半島地震vol.2〜被災地の今とこれからを考える〜」として、兵庫県立大学の青田良介先生に話題提供いただき、過疎高齢社会の災害対応と生活・生業再建、地域再生など、今とこれからの課題を踏まえて、今後を考える視点を提起頂きました。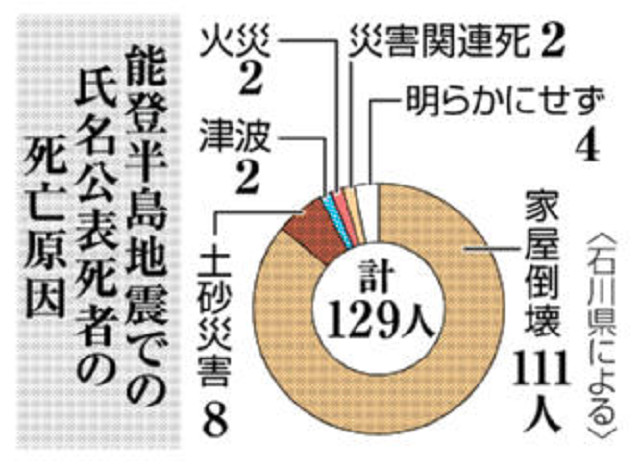

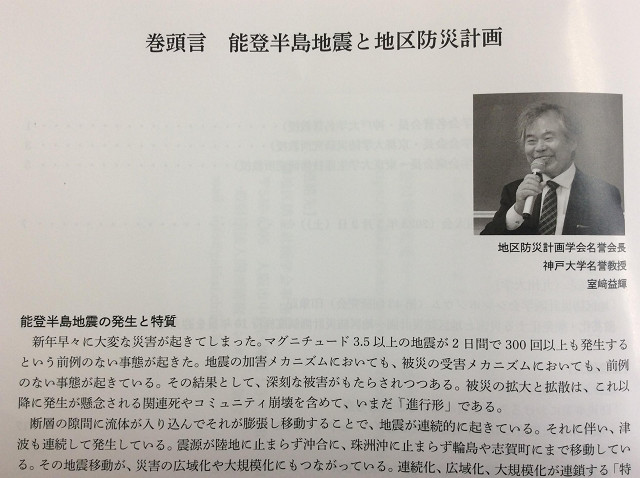 昨日25日時点で、能登半島地震による死者数は236人にのぼり、うち災害関連死が15人となったことが公表されました。
昨日25日時点で、能登半島地震による死者数は236人にのぼり、うち災害関連死が15人となったことが公表されました。
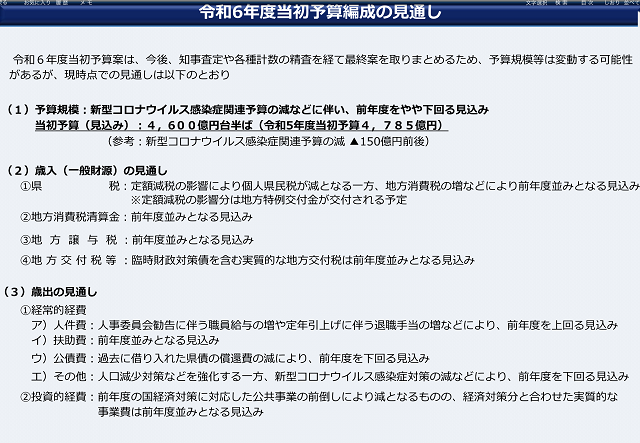
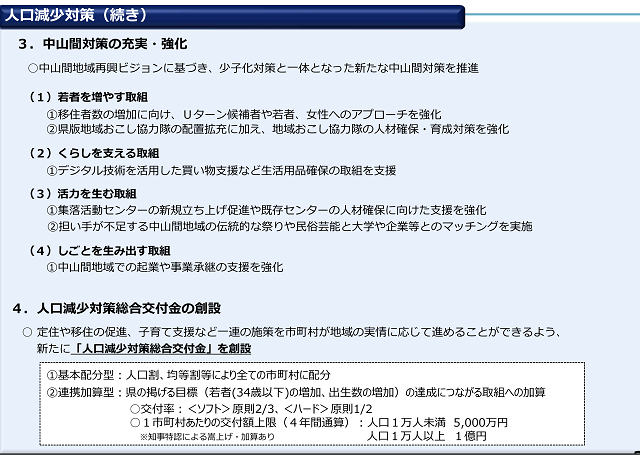
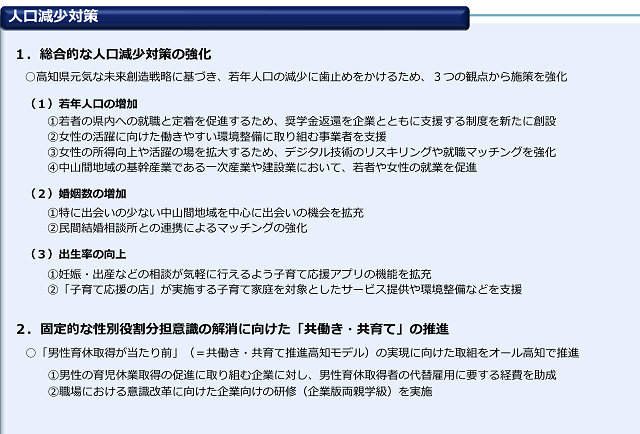
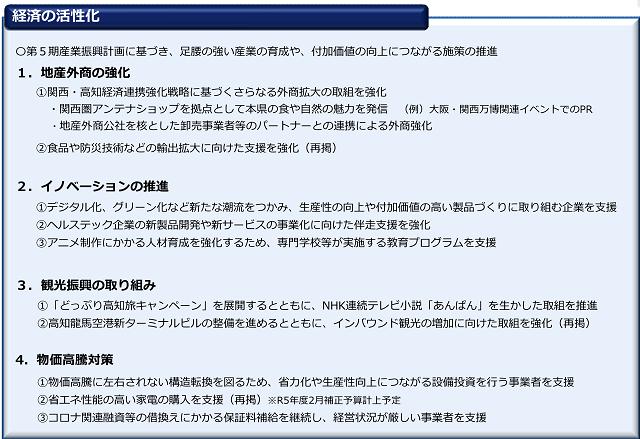
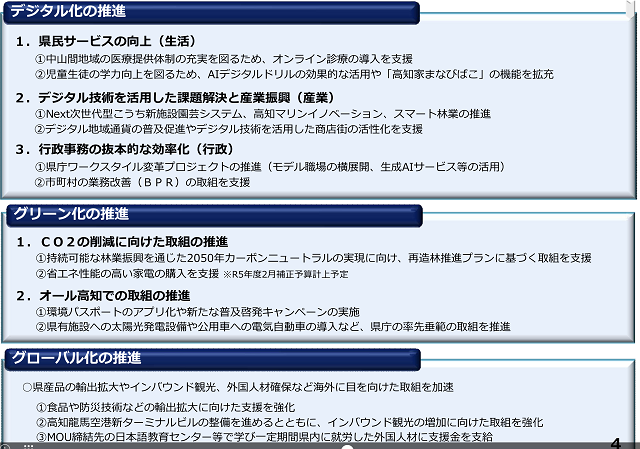
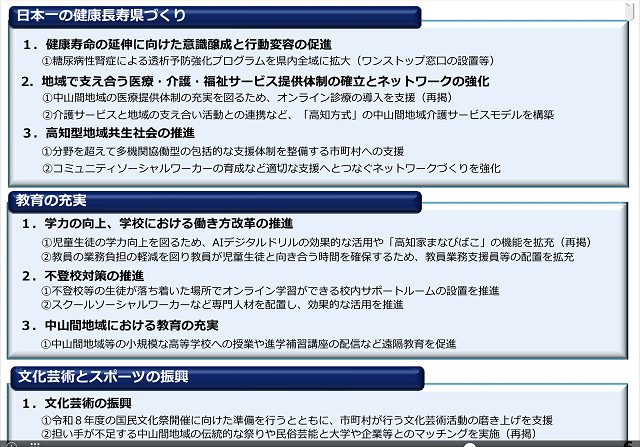
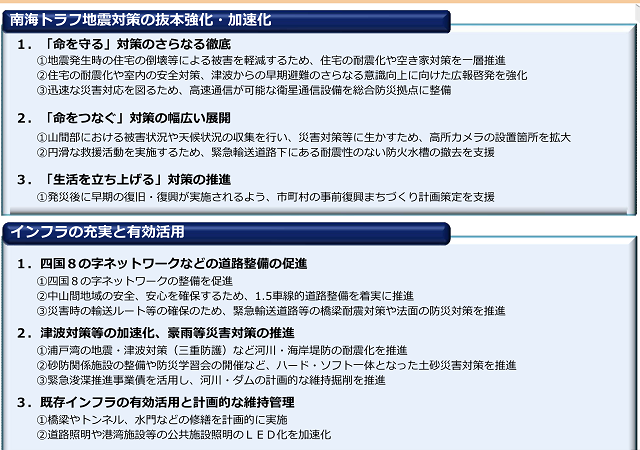
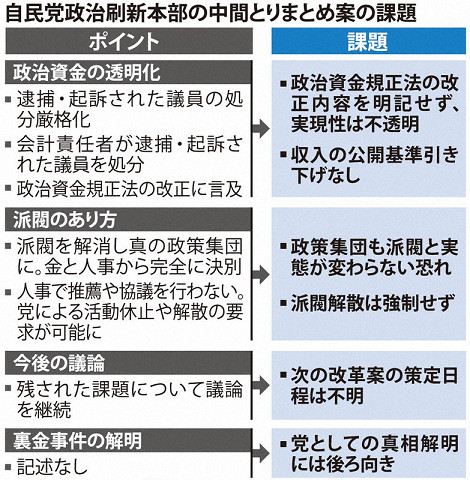
 自民党政治刷新本部は、派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件を受けて、党改革の中間とりまとめ案を昨日事実上了承しました。
自民党政治刷新本部は、派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件を受けて、党改革の中間とりまとめ案を昨日事実上了承しました。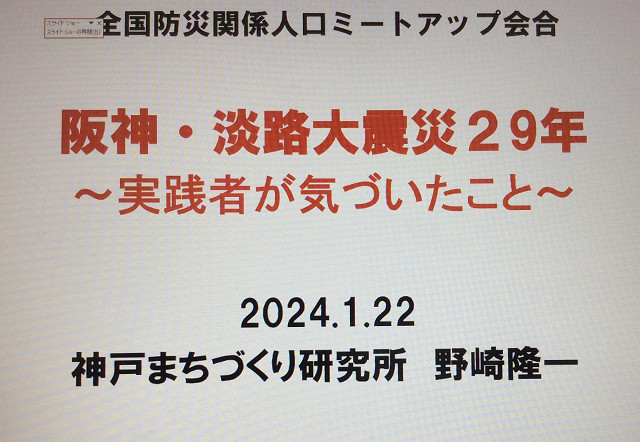
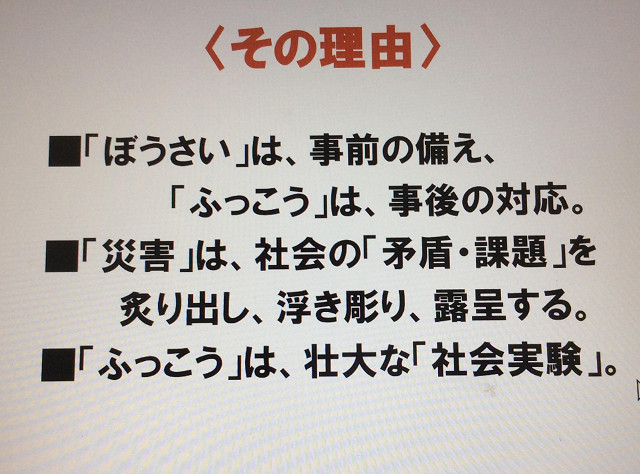
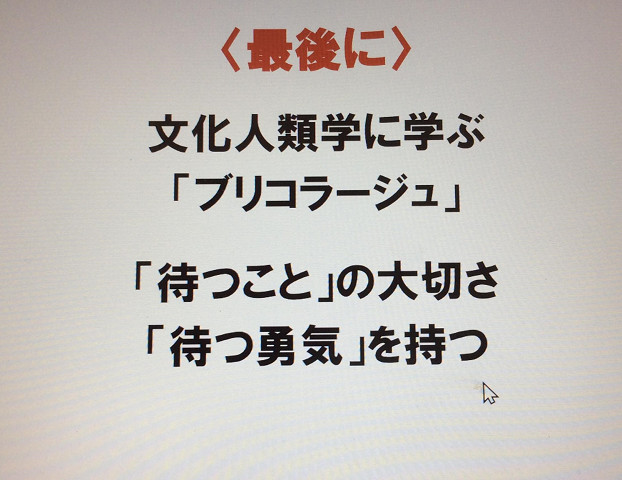


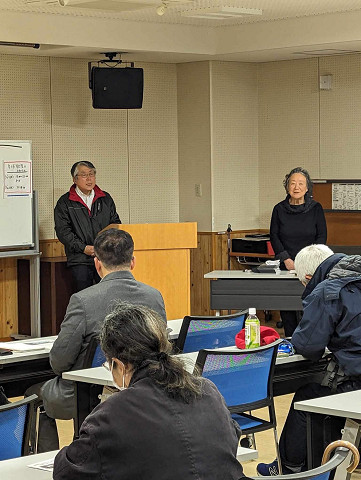
 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件は、岸田文雄首相が最近まで会長だった宏池会(岸田派)の元会計責任者も立件対象となることが判明したことから、岸田派は18日、政治資金収支報告書を訂正するとともに、首相は、苦肉の派閥解散案を唐突に打ち出しました。
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件は、岸田文雄首相が最近まで会長だった宏池会(岸田派)の元会計責任者も立件対象となることが判明したことから、岸田派は18日、政治資金収支報告書を訂正するとともに、首相は、苦肉の派閥解散案を唐突に打ち出しました。



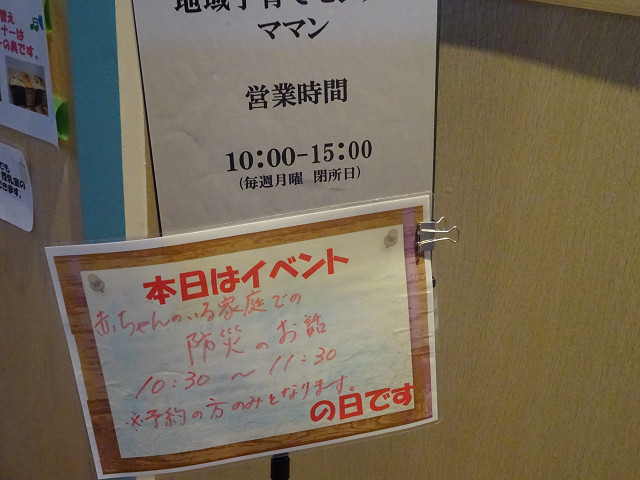
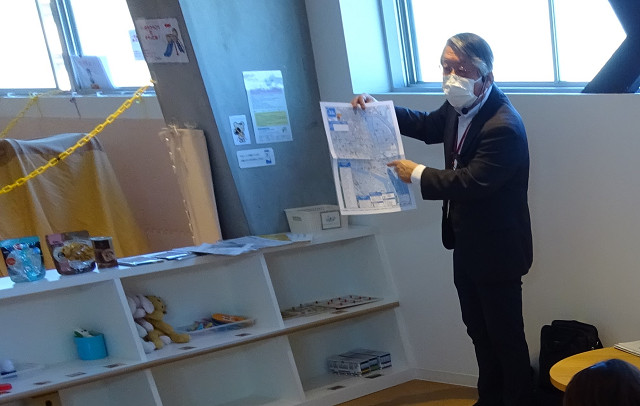



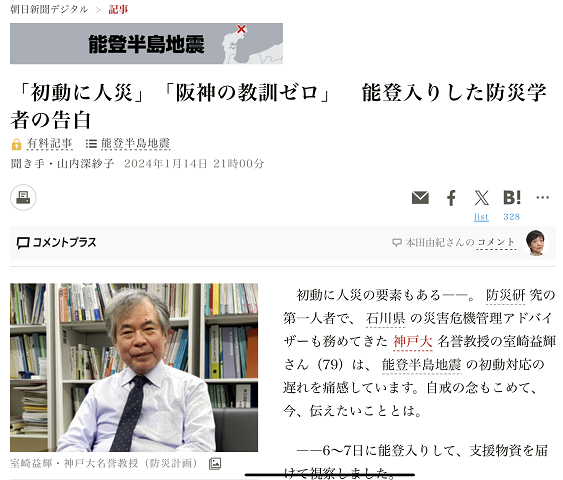
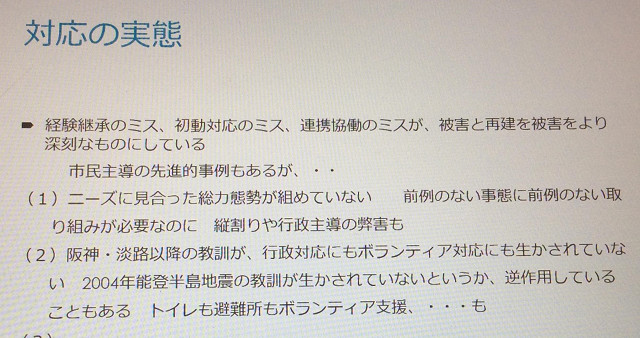
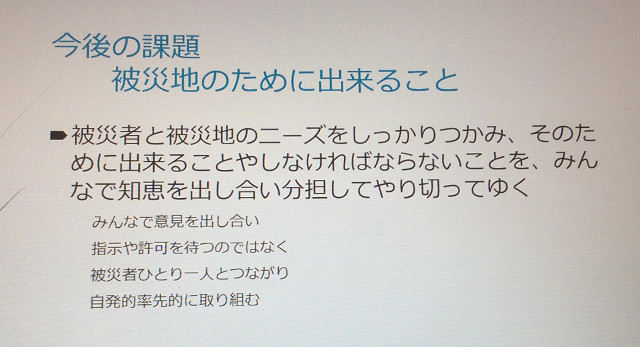
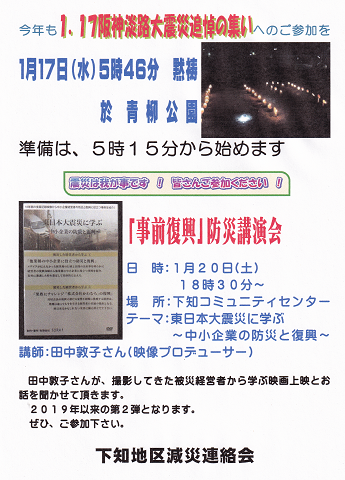

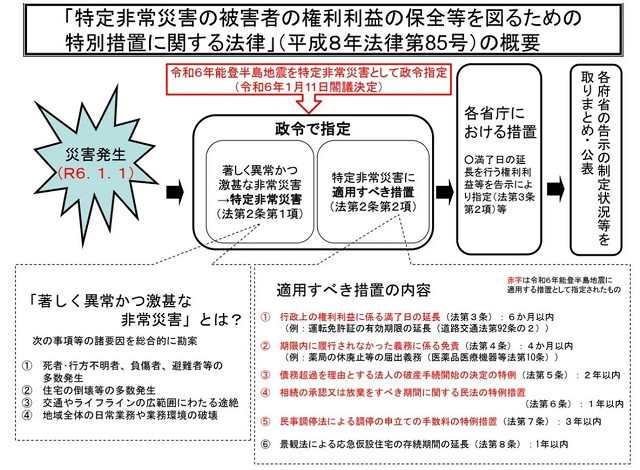 政府が11日、能登半島地震を「激甚災害」に指定し、対象地域を限定しない「本激」の措置を適用することを持ち回り閣議で決定したことが報じられています。
政府が11日、能登半島地震を「激甚災害」に指定し、対象地域を限定しない「本激」の措置を適用することを持ち回り閣議で決定したことが報じられています。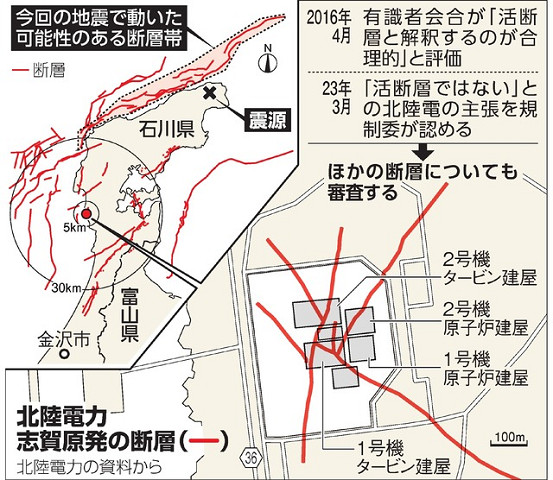 今回の能登半島地震は、揺れ、液状化、津波、火災、土砂災害と被害の全容が明らかになるにつれ、これで、原発災害が重なっていたらと思わざるをえません。
今回の能登半島地震は、揺れ、液状化、津波、火災、土砂災害と被害の全容が明らかになるにつれ、これで、原発災害が重なっていたらと思わざるをえません。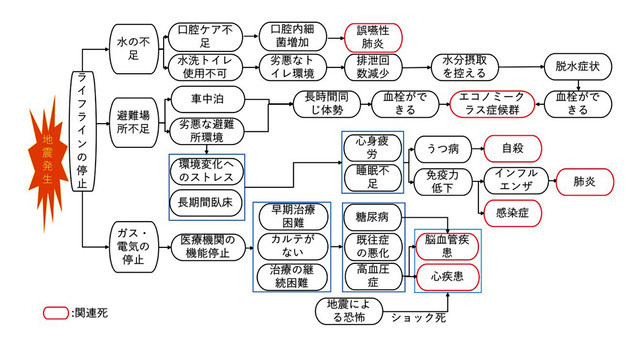 石川県は昨日午後3時時点の集計で、能登半島地震で遂に災害関連死が珠洲市内で6人確認されたと発表しました。
石川県は昨日午後3時時点の集計で、能登半島地震で遂に災害関連死が珠洲市内で6人確認されたと発表しました。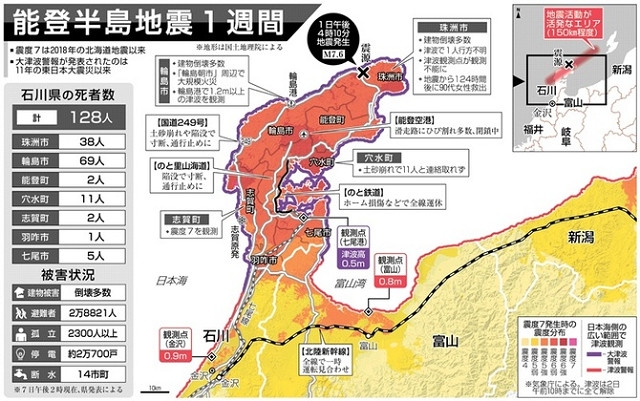
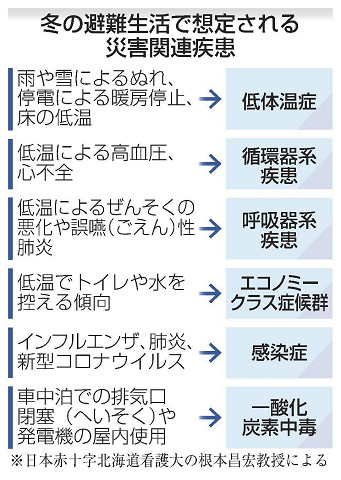

 毎日の報道で、能登半島地震の被害の様相が明らかになり、死者84人、安否不明者179人にのぼっていますが、さらに増加するのではと懸念されます。
毎日の報道で、能登半島地震の被害の様相が明らかになり、死者84人、安否不明者179人にのぼっていますが、さらに増加するのではと懸念されます。